解説記事2023年09月04日 税務マエストロ インボイス制度において事業者が注意すべき事例集(2023年9月4日号・№993)
税務マエストロ
インボイス制度において事業者が注意すべき事例集
#290
税理士 熊王征秀
マエストロの解説
令和5年7月31日、国税庁から「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」なるものが公表された。本番まで残り2か月となったことを受け、制度開始前の「取下げ」と制度開始後の「取消し」手続きの違いや、登録・取消手続などを整理したものであるが、一読しただけでは理解できないようなわかりづらい説明に周知しており、小規模事業者が読んでも、とてもではないが理解できるような代物ではない。直前になってからこのように中途半端な情報が公開されてしまうと、インボイス制度に対する嫌悪感が増すばかりで制度の執行に支障がでることが危惧される。そこで、この「事例集」なるものの緊急解説(加工)を試みることとした次第である。
Ⅰ 「事例集」1頁目の検討(その1)~「登録の取下げ・取消し」
「事例集」の1頁目には次頁のような表が掲載されている。
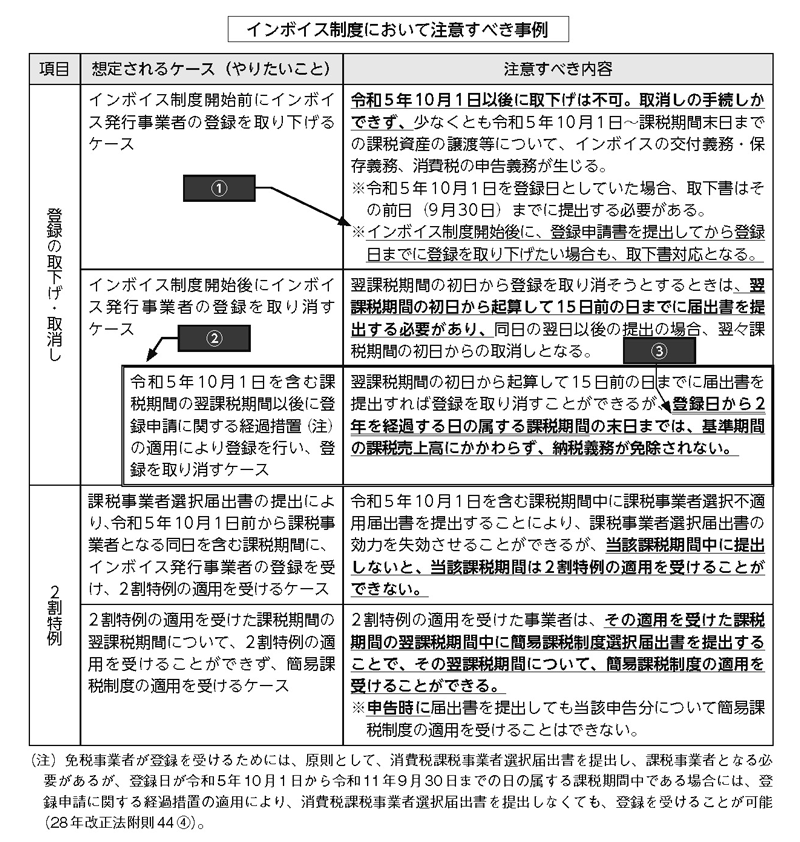
この表について、まずは「項目」の上部「登録の取下げ・取消し」の箇所を検討する。
まずもって違和感を感じるのは、「想定されるケース(やりたいこと)」の「インボイス制度開始前にインボイス発行事業者の登録を取り下げるケース」の箇所(①の箇所)に、※印でインボイス開始後の処理が書かれていることである。
「登録の取下げ・取消し」のボックスは大きく「インボイス制度開始前にインボイス発行事業者の登録を取り下げるケース」と「インボイス制度開始後にインボイス発行事業者の登録を取り消すケース」に区分されているので、インボイス制度開始後の手続きであっても「取下書対応」は「取消し」ではないから「インボイス制度開始前に……」のグループで解説したということなのであろうか……?
また、「インボイス制度開始後にインボイス発行事業者の登録を取り消すケース」の箇所では、さらに中身を細分して「令和5年10月1日を含む課税期間の翌課税期間以後に登録申請に関する経過措置(注)の適用により登録を行い、登録を取り消すケース」とし、令和4年度改正による2年縛りのことをここで説明している(②の箇所)。このような回りくどくわかりづらい日本語を使わずに、「令和5年10月2日以後に開始する課税期間から登録した事業者が登録を取り消すケース」と書いたほうがはるかにわかりやすいのではないか?
ついでに言わせてもらえば、右側の「注意すべき内容」で「……登録日から2年を経過する日の属する課税期間……」と条文の文言をなぞる(③の箇所)一方で、次頁(2頁目)の表の中段では、「登録日から2年経過日の属する課税期間……」と省略形に言い換えている。文体に統一がとれていないのである。これらの問題点については、筆者が可能な限り原文を生かしながら下記のように作り替えてみたので参考にしていただきたい。
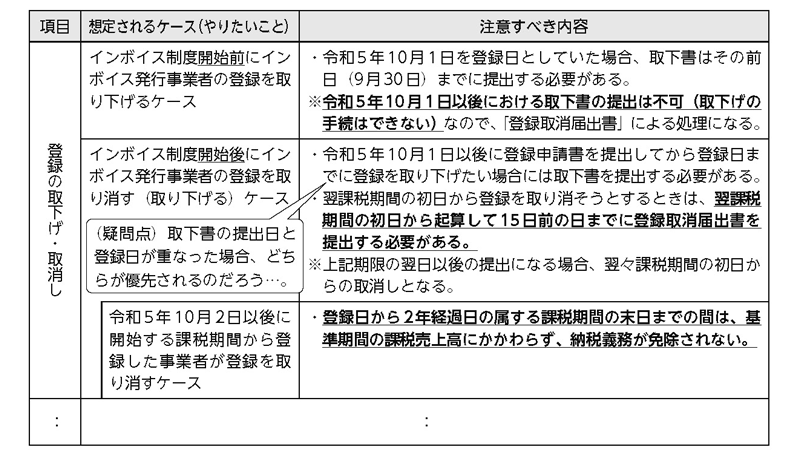
1 取下書と登録取消届出書
登録申請をした後でインボイスの登録をやめたい場合には、取下書又は登録取消届出書を提出する必要がある。手続きをするタイミングにより提出する書類が異なってくるので注意が必要だ。
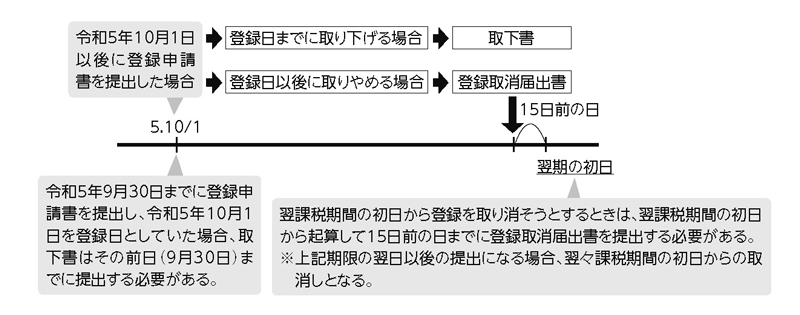
2 令和5年10月2日以後に開始する課税期間から登録した事業者が登録を取り消すケース
令和4年度改正では、課税事業者選択届出書を提出した事業者とのバランスに配慮し、令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間において登録する免税事業者は、令和5年10月2日以後に開始する課税期間について、登録開始日から2年を経過する日の属する課税期間までの間は課税事業者として申告義務を課することとしている(平成28年改正法附則44⑤)。
注意したいのは、令和5年10月1日の属する課税期間において登録する免税事業者は、いわゆる2年縛りの規定がないということである。
したがって、個人事業者(免税事業者)が令和5年10月1日に登録した場合には、令和5年12月17日までに登録取消届出書を提出することにより、令和6年から免税事業者となることができるのに対し、令和6年1月1日に登録した個人事業者(免税事業者)は、登録開始日(令和6年1月1日)から2年を経過する日(令和7年12月31日)の属する課税期間(令和7年)までの間は課税事業者として申告義務があるので、令和6年中に登録取消届出書の提出はできるものの、結果として令和6年と令和7年の2年間は課税事業者として拘束されることとなるのである。
<具体例1>
個人事業者が令和5年12月17日までに登録申請書を提出し、令和6年1月1日から適格請求書発行事業者となった場合には、令和6年12月17日までに登録取消届出書を提出し、令和7年1月1日からインボイスの効力を失効させたとしても、令和7年12月31日までは課税事業者として申告義務がある。
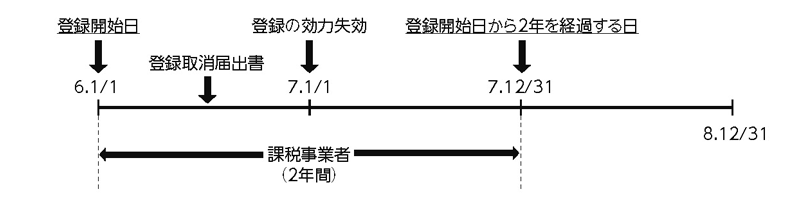
<具体例2>
個人事業者が令和6年1月17日までに登録申請書を提出し、令和6年2月1日から適格請求書発行事業者となった場合には、令和6年12月17日までに登録取消届出書を提出し、令和7年1月1日からインボイスの効力を失効させたとしても、令和8年12月31日までは課税事業者として申告義務がある。
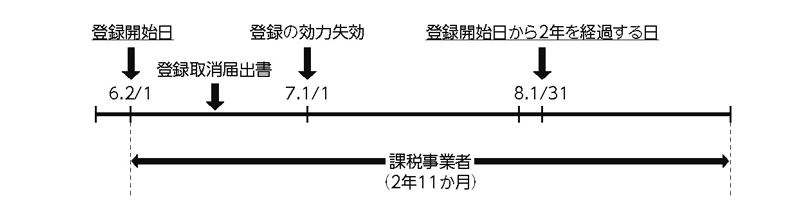
Ⅱ 「事例集」1頁目の検討(その2)~「2割特例」
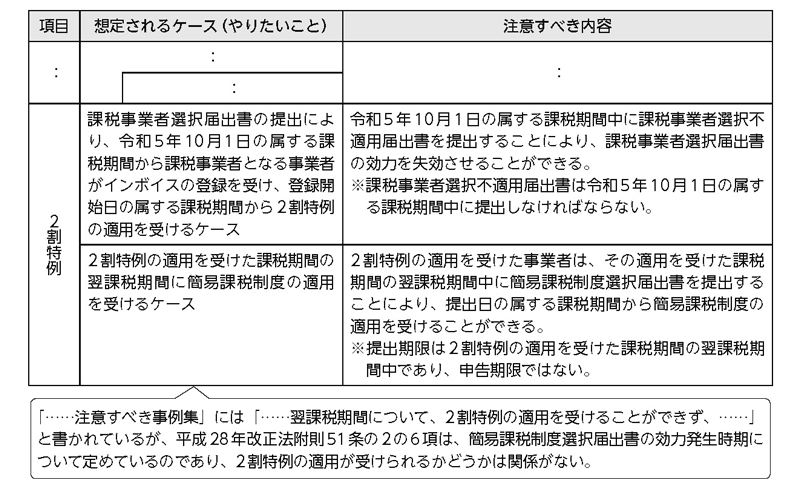
1 課税事業者選択届出書と2割特例の関係
課税事業者選択届出書を提出している事業者がインボイスの登録をしている場合には、次の①と②のいずれの要件も満たす場合について、2割特例の適用が認められる。
① インボイスの登録をしなければ免税事業者となれる課税期間であること
② 「課税事業者選択届出書」を提出しなければ免税事業者となれる課税期間であること
ただし、課税事業者選択届出書の提出により、令和5年10月1日前から引き続き課税事業者となっている事業者は、令和5年10月1日の属する課税期間について2割特例を適用することはできない。
<具体例1>
令和3年中に課税事業者選択届出書を提出した個人事業者が、令和4年分の申告で消費税の還付を受けるケース
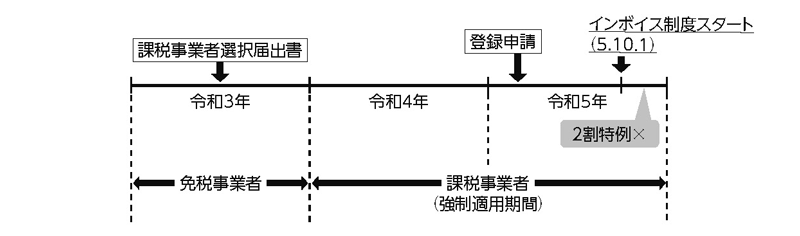
上記の<具体例1>では、課税事業者選択届出書の提出により、令和5年10月1日前から引き続き課税事業者となっている。よって、令和5年分の申告で2割特例の適用を受けることはできない。
なお、課税事業者選択届出書の提出により2割特例の適用が制限されるのは、令和5年10月1日にまたがる課税期間に限定されている。よって、下記<具体例2>のケースでは、令和5年中に調整対象固定資産を取得しない限り、令和6年分の申告で2割特例を適用することができる。
(注)令和5年中に調整対象固定資産を取得した場合には、令和6年と令和7年は2割特例の適用を受けることができない。
<具体例2>
令和4年中に課税事業者選択届出書を提出した個人事業者が、令和5年分の申告で商品の仕入れなどについて消費税の還付を受けるケース
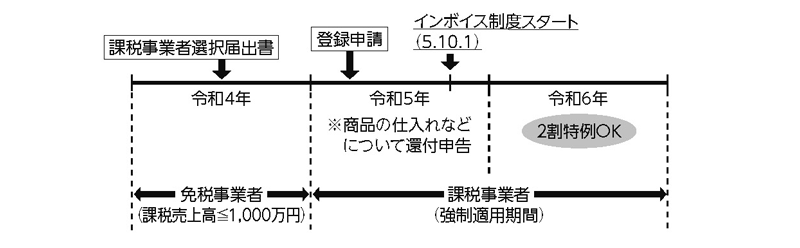
2 課税事業者選択届出書の効力を失効させるケース
課税事業者選択届出書の提出により、令和5年10月1日の属する課税期間から課税事業者となる事業者は、その令和5年10月1日の属する課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出することにより、提出日の属する課税期間(令和5年10月1日の属する課税期間)から課税事業者選択届出書の効力を失効させることができる(平成28年改正法附則51の2⑤)。
<具体例>
令和4年中に課税事業者選択届出書を提出し、令和5年から課税事業者になる個人事業者が、令和5年中に課税事業者選択不適用届出書を提出して課税事業者選択届出書の効力を失効させるケース
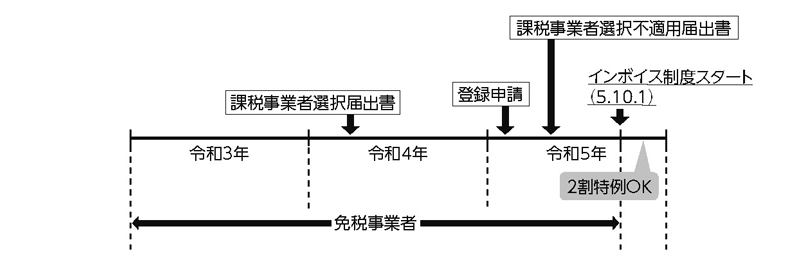
上記の<具体例>では、課税事業者選択届出書の提出により課税事業者となったのは令和5年10月1日の属する課税期間(令和5年)であることから、令和5年中に課税事業者選択不適用届出書を提出することにより課税事業者選択届出書の効力を失効させ、2割特例の適用を受けることができる。
課税事業者選択不適用届出書は、2割特例の適用を受けようとする令和5年中に提出しなければならない。令和5年分の申告期限(令和6年)ではないことに注意する必要がある。
また、この経過措置は、課税事業者選択届出書の提出により、令和5年10月1日の属する課税期間の初日から課税事業者となる事業者だけが適用を受けることができるのであるから、令和5年中に課税事業者選択届出書を提出した個人事業者が、令和6年中に課税事業者選択不適用届出書を提出したとしても、令和6年分については免税事業者になることはできない。
3 簡易課税制度選択届出書と2割特例の関係
2割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、その提出日の属する課税期間から簡易課税により申告することができる。
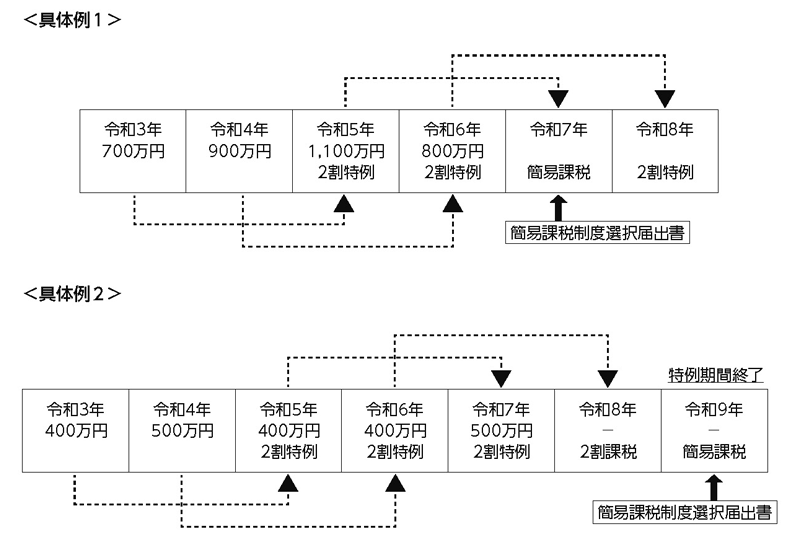
Ⅲ 「事例集」2頁目の検討~「免税事業者に係る登録等の手続・2割特例に係る手続」
「事例集」の2頁目には次頁のような表が掲載されている。
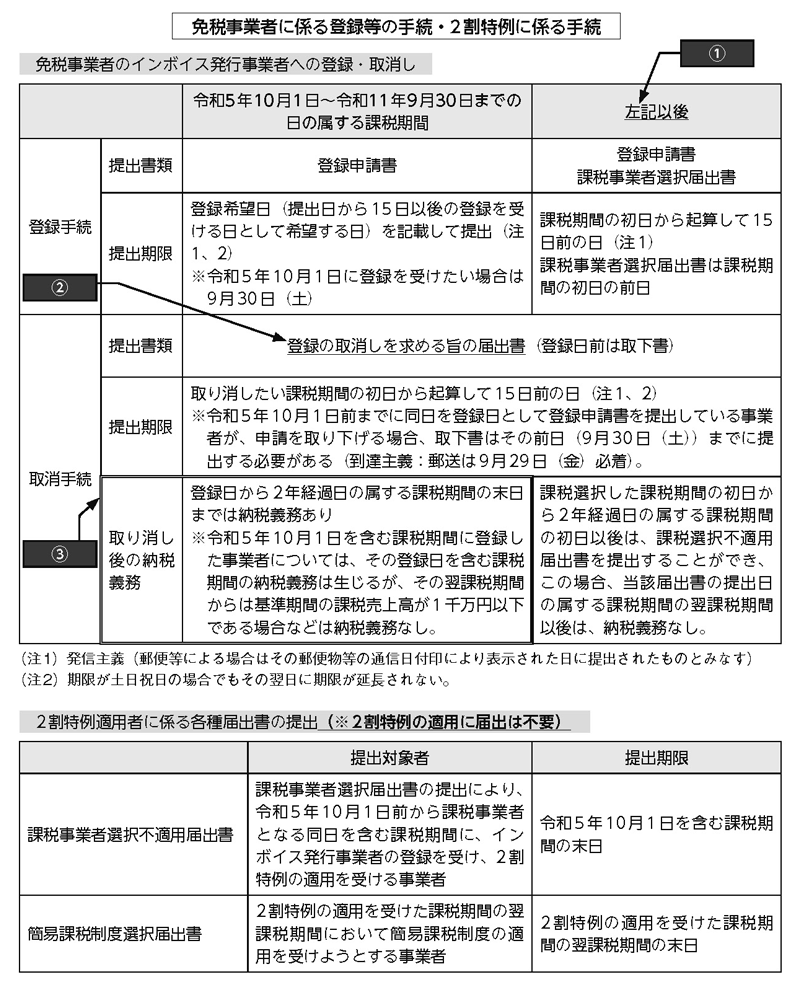
この表の右側の「左記以後」の欄(①の箇所)であるが、これは個人事業者であれば令和12年以後、法人であれば令和11年10月1日以後に開始する事業年度からの取り扱いである。制度開始直前の混乱しているこの時期に、このような何年も先のことを解説する必要があるのだろうか?
また、取消手続の提出書類の欄に「登録の取消しを求める旨の届出書」と書かれている(②の箇所)が、国税庁のインボイスQ&A(消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A)の問14では、「登録取消届出書」と表記している。1頁目の「……登録日から2年を経過する日の属する課税期間……」もそうであるが、わずか数頁の資料であるにもかかわらず、言葉の使い方が統一されていないのである。
さらに2頁目の内容を読んでいくと、1頁目と重複した説明があちらこちらに掲載されており、読んでいて相関関係がよくわからない。例えば③の説明は1頁目と同じことを説明しているはずなのに、言い回しや順番が変えてあるようなのだ。一体何の意味があるのだろう……。
Ⅳ 「事例集」3頁目以降の紹介~おわりにかえて
3頁目はいわゆる15日ルールに関する期間の数え方の解説である。すでに本誌マエストロのNo.978や令和4年度第7回日税連マルチメディア研修でも解説されているところであり、追加で説明する箇所はない。
4~5頁は、1~2頁で解説した登録申請や登録取消手続について図表を用いて説明したものであるが、お世辞にもわかりやすい解説ではない。
6~7頁は2割特例の適用関係を解説したものであるが、筆者が作成したⅡの解説のほうがはるかにわかりやすいと思うので本誌により確認をされたい。
インボイス制度の本番まであと1か月という大事な時期である。本当に必要な情報を、コンパクトに、タイムリーに、要領よく入手することが必要であると強く感じている次第である。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























