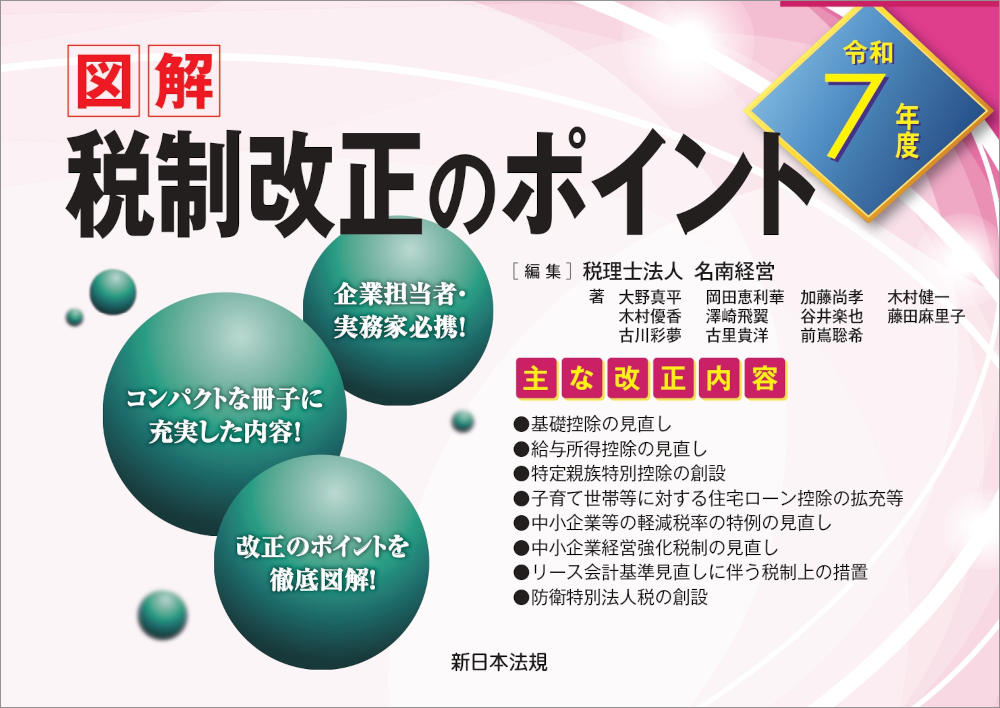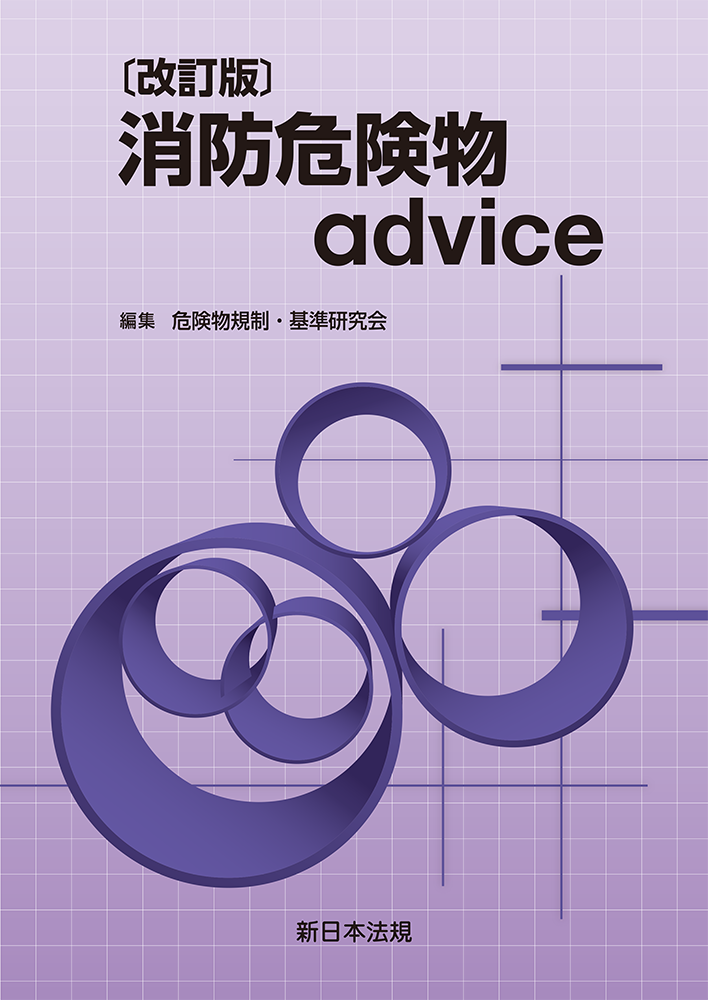解説記事2020年02月10日 ニュース特集 所得税・贈与税の審理ケースQ&A(2020年2月10日号・№822)
ニュース特集
必要経費関係、住宅取得等資金贈与の特例etc.
所得税・贈与税の審理ケースQ&A
東京国税局が作成している「所得税の審理事例」「贈与税の審理上の留意点」が明らかになった。所得税関係では、不動産貸付業が赤字の場合の回収不能家賃の取扱い、低額譲渡により取得した建物の減価償却費の計算、財産債務調書に係る加算税の加重・軽減措置等が取り上げられている。贈与税関係では、住宅取得等資金贈与の特例に係る(特別)住宅資金非課税限度額の適用関係等が記載されている。
所得税
Ⅰ 必要経費
1. 業務的規模の不動産貸付けが赤字の場合において未収家賃が回収不能となったときの不動産所得の金額(更正の請求の可否)
Q
業務的規模による不動産貸付けに係る未収家賃30万円が回収不能となった場合において、その不動産貸付業が赤字のときは、所得税法64条《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》の適用上、「不動産所得の金額の計算上、なかったものとみなされる金額」は、どのように計算されるか。また、この場合、更正の請求をすることができるか。

A
不動産所得の金額の計算上、なかったものとみなされる金額は生じない(更正の請求はできない)。
【解説】
その年分の事業所得の金額を除く各種所得の金額の計算の基礎となる収入金額(不動産所得又は山林所得を生ずべき事業から生じたものを除く)が回収不能となった場合には、次の①ないし③に掲げる金額のうち最も低い金額は、当該各種所得の金額の計算上、なかったものとみなされる(所法64①、所令180②、所基通64-2の2)。
① 回収不能となった収入金額(以下「回収不能額」という)
② 回収不能額が生じる直前において確定している総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、短期譲渡所得の金額、長期譲渡所得の金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
③ 回収不能額に係る②に掲げる金額の計算の基礎とされる各種所得の金額
そうすると、本事例においては、①30万円、②800万円、③0円※となるから、不動産所得の金額の計算上、なかったものとみなされる金額は生じない。
※ 一般に、所得税法において単に「所得の金額」といった場合には、赤字の金額は含まないと解されており、赤字の金額については、「所得の金額の計算上生じた損失の金額」との表現が採られている。
(補足)
不動産所得が黒字であり、「不動産所得の金額の計算上、なかったものとみなされる金額」がある場合において、所得税法64条に規定する収入金額の回収不能の事実が生じたことを理由とした更正の請求の特例(所法152)による更正の請求は、当該事実が生じた日の翌日から2月以内に限ってすることができることに留意する。
2. 低額譲渡により取得した建物の減価償却費の計算
Q
Xは、平成31年1月に父から賃貸用アパートを譲渡され、引き続き賃貸の用に供している。当該アパートの取得価額等は以下のとおりである。
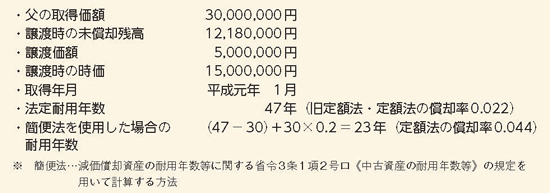
このとき、Xの令和元年分の不動産所得における当該アパートの減価償却費はいくらになるか。
A
660,000円
【解説】
贈与、相続(限定承認に係るものを除く)若しくは遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く)、又は、時価の2分の1未満の対価で、かつ、取得費及び譲渡費用の合計額未満の対価による譲受け(以下「低額譲受け」といい、贈与、相続及び遺贈と併せて、以下、「相続等」という)により取得した減価償却資産の取得価額は、当該減価償却資産を取得した者(=前所有者)が引き続き所有していたものとみなした場合における当該減価償却資産の取得価額に相当する金額となる(所法59、60、所令126②、169)。
この場合において、減価償却資産の耐用年数、経過年数及び未償却残高をどのように算定するかについて直接の規定はないが、減価償却の意義、所得税法60条1項及び所得税法施行令126条2項の趣旨等を考慮すると、所得税法施行令126条2項は、相続等により取得した減価償却資産については、前所有者の取得価額のみならず、耐用年数、経過年数及び未償却残高についても、前所有者から取得者に引き継がれることを予定しているものと解するのが相当である(大阪高裁平成26年10月30日判決)。
なお、簡便法の使用については、簡便法は、中古資産を取得した時点における取得価額を当該取得後における使用可能期間等に償却費として配分するために設けられた規定であると解するのが相当であるが、相続等により取得した減価償却資産については、取得者は前所有者の新品としての取得価額を引き継ぐことになり、この取得価額に対して法定耐用年数が適用されるのであって、相続等による取得の時点で取得価額が発生することはないから、簡便法を適用する余地はない。
本件は、譲渡価額500万円が譲渡時の時価1,500万円の2分の1未満であり、かつ、未償却残高1,218万円未満であることから、低額譲受けに当たる。よって、Xの減価償却費の計算においては、前所有者である父の取得価額、耐用年数、経過年数及び未償却残高を引き継ぐことになる。一方、償却方法については、当該アパートを取得したのは平成19年4月以降であることから、定額法により計算する。
以上により、Xの令和元年分の不動産所得における当該アパートの減価償却費の金額の計算は以下のとおりとなる。
30,000,000円×0.022×12/12=660,000円
(補足)
Xの父の譲渡損はないものとみなされる(所法59②)。
なお、Xについては、譲渡時の時価と譲渡価額との差額1,000万円について、贈与税が課される場合がある(相法7)。
Ⅱ 財産債務調書
3. 財産債務調書に係る加算税の加重・軽減措置(「修正申告の基因となる財産」の意義)
Q
納税者は、平成30年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書並びに平成30年12月31日分財産債務調書を平成31年3月14日に提出した。当該財産債務調書には、不動産所得の基因となる貸付不動産(以下「本件貸付不動産」という)の記載はあったが、不動産所得を生ずべき業務の用に供している車両(以下「本件車両」という)の記載はなかった。
その後、調査により、本件車両の減価償却費について計算誤りが把握され、平成30年分の所得税及び復興特別所得税の修正申告書(以下「本件修正申告書」という)が提出された。
本件修正申告書に係る過少申告加算税について、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「国送法」という)6条の3に基づく加算税の軽減措置の適用はあるか。
A
本件修正申告書に係る過少申告加算税については、軽減措置が適用される。
【解説】
「財産の貸付けによる所得」を含む一定の「財産に関して生ずる所得」に対する所得税に関し修正申告があり、過少申告加算税が課される場合において、提出期限内に提出された財産債務調書に「当該修正申告の基因となる財産」について所定の記載があるときは、当該過少申告加算税について軽減措置が適用される(国送法6の3①、国送令12の3、国送規12の3①三)。
本件修正申告書が、本件車両の減価償却費の計算誤りを要因とするものであることを踏まえると、本件車両は、「当該修正申告の基因となる財産」に該当するとも考えられる。
しかし、「当該修正申告」とは、「財産に関して生ずる所得」に対する所得税に関する修正申告をいうところ、本件修正申告書は、「財産(=本件車両)に関して生ずる所得」に関するものであるということはできない。すなわち、本件修正申告書は、「財産(=本件貸付不動産)に関して生ずる所得」(具体的には「本件貸付不動産の貸付けによる所得」)に関するものであり、「当該修正申告の基因となる財産」は、本件貸付不動産が該当する。
したがって、納税者が提出した財産債務調書には本件貸付不動産が記載されていることから、本件修正申告書に係る過少申告加算税については、軽減措置が適用される。
Ⅲ 申告・その他
4. 公益社団法人に財産を遺贈した場合の取扱い
Q
個人X(民法上の法定相続人が存在しない)が平成30年中に死亡し、Xは遺言により財産を全て公益社団法人Yに包括遺贈した。遺贈された財産は、すべてYの主たる目的である業務に関連して利用される。
このとき、①Xに係る平成30年分準確定申告書の提出義務者は誰で、②法定申告期限はいつか。また、③Xは準確定申告書において当該遺贈した財産に係る寄附金控除の適用を受けることは可能か。
なお、Yは遺言執行者により平成31年1月10日に包括受遺者である旨通知を受けている。
A
① 準確定申告書の提出義務は包括受遺者である公益社団法人Yが負う。
② 法定申告期限は令和元年5月10日となる。
③ 一定の要件を満たす場合には、遺贈した財産に係る寄附金控除の適用を受けることが可能である。
【解説】
所得税法2条2項の規定により「相続人」には包括受遺者も含まれることから、公益社団法人Yは「相続人」に該当する。したがって、Yは準確定申告書の提出義務者となり、その法定申告期限は相続等の開始があったことを知った日(平成31年1月10日)の翌日から四月を経過した日の前日となる(所法125、相基通27-4)。
また、寄附金控除(所法78)の対象となるのは「居住者が各年において特定寄附金を支出した場合」であるところ、大正5年11月8日大審院判決により、遺贈の目的とされる財産は遺贈者の死
亡により相続人を経ることなく直接受遺者に移転すると示されていることから、本件においては、Xが死亡した時点である平成30年中にYに財産が移転したと考えられる。
したがって、その他の手続要件等を満たすのであれば、当該財産について寄附金控除を適用することが可能である。
(補足)
遺贈時に財産に係る含み益が存在していた場合、みなし譲渡課税(所法59)の対象となり、準確定申告において計算する必要がある(一定の要件を満たせば、みなし譲渡課税の非課税の特例が適用される(措法40))ため留意する。
5. 確定申告書の撤回ができる期限
Q
所得税法121条《確定所得申告を要しない場合》の適用を受ける者が、誤って第3期分の税額を記載した申告書を提出した場合において、当該申告書を撤回したい旨の書面による申出をしたときは、当該申出の日に当該申告書の撤回があったものとして取り扱っている(所基通121-2)ところであるが、当該撤回はいつまですることができるか。
A
法定申告期限から5年間と解される。
【解説】
所得税基本通達121-2《確定所得申告を要しない者から提出された確定申告書の撤回》では、「当該第3期分の税額に係る過誤納金については、その撤回の日に更正の請求に基づく更正があったものとして国税通則法58条1項《還付加算金》の規定を適用するものとする」とされているところ、確定所得申告を要しない者から提出された第3期分の税額が記載された申告書は、所得税法120条の規定により提出されたものとして取り扱われる(所基通121-1)ことから、当該申告書について更正をすることができる期間は、法定申告期限から5年間となる。また、上記申告書を提出することができる期間は、法定申告期限から5年間となる。
これらのことを踏まえると、所得税基本通達121-1における申告書の撤回をすることができる期間について、異なる取扱いをする理由はなく、当該申告に係る撤回の期限は法定申告期限から5年間と解するのが相当である。
贈与税
1. 住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合に(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算上取得対価の額等から控除する金額について
Q
Xは、平成31年3月に父から現金1,700万円の贈与を受け、同年4月に居住用マンション(4,000万円)を購入した。令和元年分の贈与税について、下記のような申告をした場合、租税特別措置法41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》1項(以下「住宅ローン控除」という)の適用において、住宅ローン控除額の計算上、取得対価の額等から控除する金額はいくらか。
なお、「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」(措置法70条の2)、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」(措置法70条の3)の各特例の適用要件はすべて満たしているものとする。
(1)①「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」を受ける金額:700万円
②「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」を受け、住宅取得等資金として特別控除する金額:1,000万円
(2)①「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」を受ける金額:700万円
②相続税法21条の9《相続時精算課税の選択》の規定の適用を受ける金額:1,000万円
(3)①「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」を受ける金額:700万円
②「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」を受け、住宅取得等資金として特別控除する金額:600万円(その他400万円は現金贈与)
A
(1)1,700万円(①及び②の合計額)
(2) 700万円(①の金額)
(3)1,300万円(①及び②のうち600万円との合計額)
【理由】
1 住宅ローン控除額の計算上、取得対価の額等から控除する金額
措置法施行令26条《住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除》5項では、住宅ローン控除額の計算上「……個人の住宅借入金等(略)の金額の合計額が、……住宅の取得等(略)に係る対価の額又は費用の額」を超える場合には、住宅ローン控除額の適用については、住宅借入金等の金額の合計額は、当該対価の額又は費用の額に達するまでの金額とすると規定している。
そして、上記「住宅の取得等」に関し、住宅取得等資金(措置法70条の2第2項5号及び同法70条の3第3項5号に規定する住宅取得等資金)の贈与を受けた場合には、措置法70条の2第1項又は相続税法21条の12第1項の規定の適用を受けた部分の金額に限り、その金額を取得対価の額等から控除することとしている(措令26⑤かっこ書)。
2 当てはめ
(1)「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」の適用を受けた700万円及び「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」の適用を受けた1,000万円については、住宅取得等資金に該当する。
したがって、住宅ローン控除額の計算上、取得対価の額等から控除する金額は1,700万円となる。
(2)「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」の適用を受けた700万円については、住宅取得等資金に該当する。一方、相続時精算課税制度を適用する1,000万円については、「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」の適用及び「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」を適用した住宅取得等資金には該当しない。
したがって、住宅ローン控除額の計算上、取得対価の額等から控除する金額は700万円となる。
(3)「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」の適用を受けた700万円については、住宅取得等資金に該当する。一方、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」の適用を受ける1,000万円のうち、住宅取得等資金として特別控除する金額が600万円である場合には、その金額に限り、取得対価の額等から控除することとされている。
したがって、住宅ローン控除額の計算上、取得対価の額等から控除する金額は700万円及び600万円を合計した1,300万円となる。
2. 住宅取得等資金贈与の特例に係る住宅資金非課税限度額及び特別住宅資金非課税限度額の双方の適用について
Q
次の事実関係において、Xは、次の各贈与について、措置法70条の2《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の特例》1項に規定する特例(以下「住宅取得等資金贈与の特例」という)を適用する場合、非課税限度額はいくらとなるか。
なお、住宅取得等資金贈与の特例の適用要件はすべて満たしているものとする。
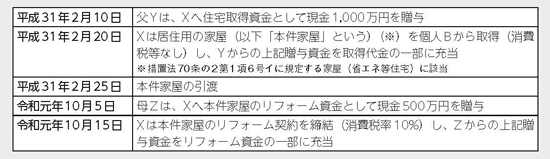
A
4,200万円となる。
【理由】
1 住宅取得等資金贈与の特例の概要
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間にその直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等(以下「新築等」という)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」という)を取得した場合において、一定の要件に該当するときは、その贈与により取得をした住宅取得等資金のうち、住宅資金非課税限度額までの金額又は特別住宅資金非課税限度額までの金額については、贈与税の課税価格に算入しない(措法70の2①)。
2 住宅資金非課税限度額及び特別住宅資金非課税限度額
受贈者が住宅取得等資金を充てて新築等をした家屋の区分に応じて定める(1)及び(2)の各表の金額をいう(措法70の2②六七)。
なお、平成31年4月1日以後に住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結して住宅取得等資金贈与の特例の適用を受ける場合の非課税限度額は、下記(1)及び(2)の表のうちいずれか多い金額となる(措法70の2①かっこ書)。
(1)住宅資金非課税限度額
受贈者が住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋(住宅用の家屋の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合を除く。)の区分に応じて定める下記の表の金額をいい(措法70の2②六)、既に住宅取得等資金贈与の特例の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、当該金額を控除した残額をいう(措法70の2①かっこ書)。

(2)特別住宅資金非課税限度額
受贈者が住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋(住宅用の家屋の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合に限る。)の区分に応じて定める下記の表の金額をいい(措法70の2②七)、平成31年3月31日までに上記(1)の新築等に係る契約を締結して住宅取得等資金贈与の特例の適用を受けた場合を除き、既に同特例の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、当該金額を控除した残額をいう(措法70の2①かっこ書)。

3 当てはめ
本事例の場合、Xは、同一年中において、YとZからそれぞれ住宅取得等資金の贈与を受けているところ、本件家屋の対価の額又は費用の額については、消費税等が含まれていないから、上記2(1)より、取得資金のうち住宅資金非課税限度額の1,200万円までの金額は、贈与税の課税価格に算入しない。
また、リフォーム代金については、その消費税率が10%であるから、上記2(2)より、当該代金のうち特別住宅資金非課税限度額の3,000万円までの金額は、贈与税の課税価格に算入しない。そして、本事例では、平成31年2月20日に本件家屋の取得に係る契約を締結して住宅取得等資金贈与の特例を受けることとなるから、上記2(2)のとおり、既に同特例を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額、すなわち本件家屋の取得資金を特別住宅資金非課税限度額から控除する必要はない。さらに、上記2なお書のとおり、同(1)及び(2)の表のうちいずれか多い金額までとする必要もない。
したがって、Xは、住宅資金非課税限度額及び特別住宅資金非課税限度額の双方を適用することができるから、同人の非課税限度額は4,200万円となる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.