解説記事2024年09月09日 ニュース特集 令和7年度における各省庁の税制改正要望は?(2024年9月9日号・№1042)
ニュース特集
適用期限の延長など、小幅な改正要望にとどまる
令和7年度における各省庁の税制改正要望は?
各省庁等の令和7年度税制改正要望が出揃った。令和6年度における賃上げ促進税制の拡充などの大きな見直し項目は少なく、例年以上に小幅な改正要望にとどまった印象だ。また、事業承継税制の役員要件の見直しや、私的年金制度改革など、閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2024」などに盛り込まれた税制措置も各省庁等から改めて要望が行われている。本特集では、各省庁等の主な税制改正要望を紹介する。
産業用地整備促進税制の創設を求める
経済産業省の令和6年度税制改正要望では、実現した戦略分野国内生産促進税制やイノベーション拠点税制の創設、賃上げ促進税制の拡充など、大型の税制措置が相次いだが、令和7年度税制改正要望では一転して既存の租税特別措置の拡充や延長が主となっており、税制措置の創設は産業用地整備促進税制の1つにとどまっている。すでにお伝えしているが、同税制は、自治体が民間事業者を活用して産業用地を整備する事業において、地権者が土地等を譲渡した際、地権者の譲渡所得への所得控除を行うというもの(本誌1035号参照)。地権者交渉の円滑化や産業用地の迅速な供給により、地域経済に波及効果をもたらす国内投資を後押しするとしている。
国内投資関係では、令和7年3月31日で期限切れとなる中小企業経営強化税制の2年間延長と拡充を求めている。特に売上高が100億円を超える中小企業への上乗せ措置を求めている。また、地域未来投資促進税制についても2年間の適用期限延長を求めたほか、地方公共団体が戦略的かつ重点的に支援を行う産業分野を「重点促進分野(仮称)」とし、同分野に対する新たな枠を設けるほか、地域経済牽引事業計画の期間内(最大5年以内)に行った設備投資について、税制の適用を可能にするよう求めている。
再投資期間を「同一年内」から「複数年」に
エンジェル税制については、令和5年度税制改正において、スタートアップへの再投資に係る非課税措置が創設されている。保有株式を売却し、自己資金による起業やプレシード・シード期のスタートアップへの再投資を行う際、再投資した分の譲渡益には課税を行わないというものである。
この点、非課税措置を適用するには、株式譲渡益の発生した年に投資を行う必要があるが、実際には元手となる所得が発生してから十分な再投資までに1年以上要しているエンジェル投資家が多いほか、一度起業した会社を売却してから次の起業まで複数年を要している連続起業家も多く、「同一年内」に投資し、非課税措置の適用を受けることは難しいとの指摘がある。このため、再投資期間の要件を「同一年内」から「複数年」に延長するよう求めている。
中小企業関係では、事業承継税制の役員就任要件(実際の承継時に、後継者が役員に就任して3年以上経過している必要)の見直しを求めている(本誌1031号、1038号参照)(図表1参照)。現行の法人版事業承継税制の特例措置を適用する場合には、2024年12月末までに後継者が役員に就任している必要があるが、コロナや物価高騰等の急激な経営環境の変化により事業承継の具体的な検討が進んでいない中小企業等が多いとしている。
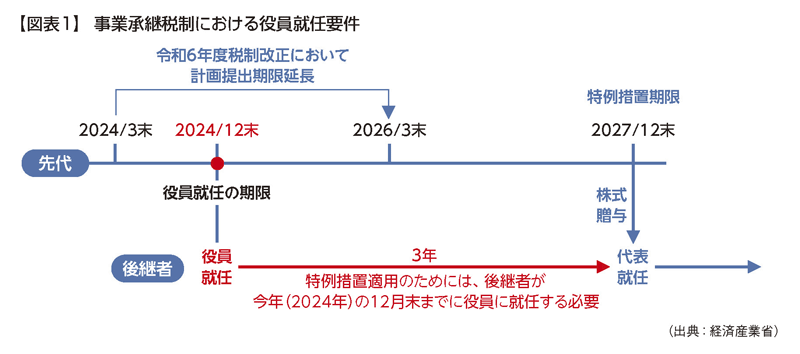
また、中小企業者等の法人税率の特例(15%)の2年間延長のほか、中小企業投資促進税制、中小企業防災・減災投資促進税制、生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置についても、適用期限の2年間延長を求めている。
DX投資促進税制は適用期限で廃止へ
そのほか、DX(デジタルトランスフォーメーション)投資促進税制及び5G導入促進税制については、適用期限をもって廃止することとされている。
会計基準改正でリースはすべて資産及び負債に計上、経産省は税制措置を求める
企業会計基準委員会(ASBJ)は9月3日、改正リース会計基準等を正式決定した。近日中にも公表される。改正リース会計基準等は、国際的な会計基準との整合性の観点から、ファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、すべて資産及び負債に計上することになった。このため、経済産業省では、改正リース会計基準等による変更に伴う企業の負担が可能な限り生じないよう税制上の措置を講じるよう求めている。
なお、改正リース会計基準等については、2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することとされている(早期適用可)。
子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充措置の実施を
金融庁の令和7年度税制改正要望では、昨年に引き続き、換金性の高い上場株式については、物納の特例を措置することを求めた。物納は、「延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること」等の要件があり、税務署長の許可を得る必要があるため、利用実績が限定的であることから、上場株式等については、同要件を撤廃することを求めた。併せて相続財産となった上場株式等の相続税評価方法の見直しも求めている。相続財産となった上場株式等については、相続時の時価と、相続時以前3か月間の各月における終値平均額のうち、最も低い価額で評価されることになるが、上場株式等は相続時から納付期限までの10か月間の価格変動リスクが大きいため、相続後の株価の下落に備えて売却するといったケースが見受けられるとしている。
また、令和6年度税制改正大綱で検討事項とされた金融所得課税の一体化(金融商品に係る損益通算の範囲をデリバティブ取引及び預貯金等にまで拡大)を求めている。
国際金融センターを実現するための税制上の措置としては、昨年に引き続きファンドを介したクロスボーダー投資について、租税条約を適用することができるよう所要の措置を講じることを求めている。日本が締結している租税条約では、二国間の投資を促進する観点から、クロスボーダー投資について、源泉地国での源泉徴収を減免する措置が盛り込まれているが、原則としてファンドレベルではなく、受益者である投資家レベルで租税条約の申請手続きをすることとされているため、実務上申請手続きをすることは困難であるとしている。
令和6年度税制改正大綱では、子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充として、新生命保険料に係る一般枠(遺族保障)について、23歳未満の扶養親族を有する場合には、現行の4万円の適用限度額に対して2万円の上乗せ措置を講ずる旨が示されたが、その内容で令和7年度において措置すべきとした。
無税積立率の割増措置の延長を
火災保険等に係る異常危険準備金制度については、令和7年3月31日までの時限措置となっている「火災・風水害」及び「動産総合・建設工事・貨物」の区分に係る無税積立率の割増措置を延長するほか、高額化する保険金支払いを踏まえた残高を確保する観点から各保険区分の取崩単位を一本化するとともに、取崩基準損害率を55%(現行50%)に引き上げることや、「火災・風水害」の区分の無税積立率(現行10%)及び洗替保証率(現行30%)について引き上げることを求めた(図表2参照)。
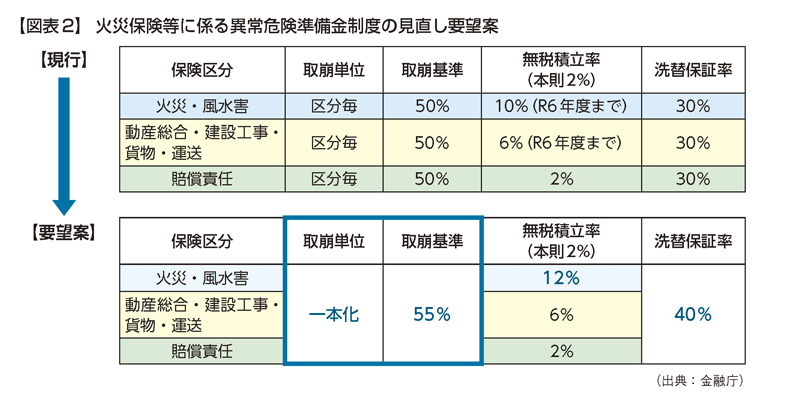
そのほか、NISAについては、利便性向上として、郵送で行っている口座開設10年後の所在地確認のデジタル化や、金融機関変更時の即日買付の実現を求めた。現行では、口座開設の申し込みから買付けが可能になるまで1~2週間を要するが、その間に買付意欲を失うケースがあるとしている。また、つみたて投資枠におけるETFについては、インデックス連動商品のみが対象となっているが、東証の規則改正により、2023年6月以降、インデックスへの連動を必要としないアクティブETFの上場が可能になっているため、これを対象にするよう求めている。
iDeCoの拠出限度額の引上げ求める
厚生労働省では、令和5年4月より社会保障審議会企業年金・個人年金部会で私的年金制度の改革に関する議論が行われており、特にiDeCo(個人型確定拠出年金)については、「経済財政運営と改革の基本方針2024」(令和6年6月21日閣議決定)や「新しい資本主義のグランドデザイン」(令和6年6月21日閣議決定)では、拠出限度額及び受給開始年齢について2024年中に結論を得る、拠出限度額の引上げ等について大胆な改革を検討し結論を得るなどとされている。このため、私的年金制度の改正にあたっては税制上の措置を講じるよう求めた。また、公的年金制度については、前述の「経済財政運営と改革の基本方針2024」において、「公的年金については、働き方に中立的な年金制度の構築等を目指して、今夏の財政検証の結果を踏まえ、2024年末までに制度改正についての道筋を付ける」とされていることから、社会保障審議会年金部会の結果等を踏まえ、税制上の所要の措置を講じる必要があるとしている。
そのほかでは、医療提供体制の確保のため、①医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度(取得価格の15%)、②地域医療構想の実現のための病床再編等の促進に向けた特別償却制度(取得価格の8%)、③高額な医療用機器に係る特別償却制度(取得価格の12%)について、適用期限を2年延長することを求めている。
老朽化マンション再生で非課税措置
国土交通省では、与党の令和6年度税制改正大綱に盛り込まれた子育て世帯等に対する住宅ローン減税等の拡充を令和7年度においても同様に措置すべきとしたほか、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する特例措置を令和9年3月31日まで2年間延長することを求めている(本誌1041号参照)。
また、今後、高経年マンションが急激に増加する見込みとなっているが、老朽化マンションの再生においては、費用負担の問題が区分所有者間の合意形成の最大の阻害要因となっていることから、国土交通省では、マンション建替円滑化法において新設される予定の「マンション取壊し敷地売却事業」(仮称)及び「マンション更新(一棟リノベーション)事業」(仮称)を円滑に進めるため、収益事業以外の所得の非課税措置や資産譲渡等の時期、仕入税額控除及び申告期限の特例を講じることを求めている。
企業版ふるさと納税、税の軽減効果を維持し5年延長
内閣府では、令和6年度までの措置となっている地方創生応援税制、いわゆる企業版ふるさと納税制度について、税の軽減効果(寄附額の最大9割)を維持した上で、税額控除の特例措置を令和11年度まで、5年間延長するよう求めた。令和2年度税制改正で適用期限の延長や税の軽減効果を拡充したことにより、令和元年度では33.8億円だった寄附額が令和5年度では470.0億円にのぼっているとしている。
公益信託法は令和8年4月施行予定
また、公益信託制度については、令和6年5月、「公益信託ニ関スル法律」(大正11年法律第62号)を全部改正した「公益信託に関する法律」(令和6年法律第30号)が公布され、令和8年4月より施行される予定となっている。公益信託の税制優遇に関しては、新しい公益信託法において認可基準等を法定し、公益法人と共通の枠組みで認可・監督する制度としたことを踏まえ、令和6年度税制改正において、これまで信託財産として受け入れる財産を金銭に限る等、一定の要件を満たしたもののみが優遇を受けていた税制を見直し、新しい公益信託法によって認可を受けた全ての公益信託が公益法人並みの税制優遇を受ける制度となった。また、公益法人等に金銭以外の財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税措置の「一般特例」について、公益信託もその対象に追加された。
今回、公益信託制度が公益法人と共通の枠組みで認可・監督される制度であることを踏まえ、譲渡所得等非課税の「承認特例」の対象として追加されることを要望するとともに、公益信託制度に整合的な「一般特例」及び「特定買換資産の特例」の適用その他新公益信託法の施行に向けた所要の措置をすること等を求めている。
特定公益増進法人への寄附を拡充
文部科学省では、法人から特定公益増進法人等に対して寄附する場合に損金算入が認められる範囲である特別損金算入限度額を拡充(所得の10%)するとともに、寄附額が特別損金算入限度額を超過した場合でも、翌年度以降5年間、限度額超過分を繰り越して損金算入することを可能とするよう求めている。
相続登記の登録免許税免除を3年延長
法務省では、既存の相続登記の促進のための登録免許税の特例措置の適用期限を3年間延長するよう求めている。具体的には、①個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。②の場合において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときに、当該個人を当該土地の登記名義人とするために受ける登記に係る登録免許税の免除、②個人が、土地について所有権の保存の登記又は相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地の当該登記に係る登録免許税の課税標準となる価額が100万円以下であるときにおけるその登録免許税の免除である。
そのほか、公正取引委員会では、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律において導入された課徴金制度によって納付した課徴金及びその延滞金について、損金・必要経費に算入しないこととするよう求めている。
なお、各省庁等における令和7年度税制改正要望のうち、適用期限の延長を求めている項目は以下の通りである。
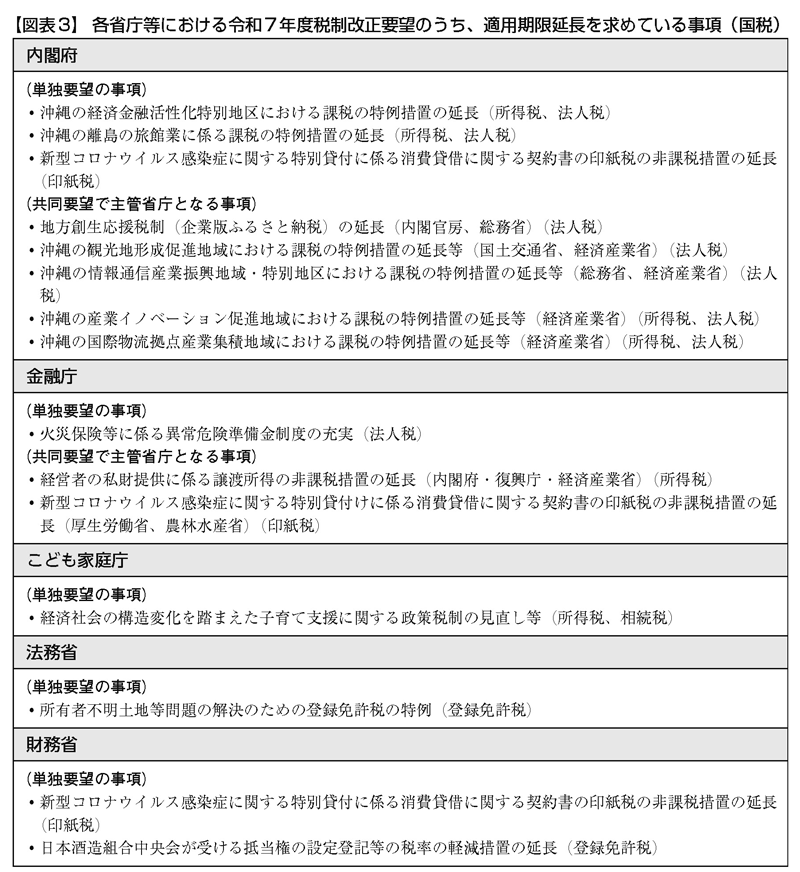
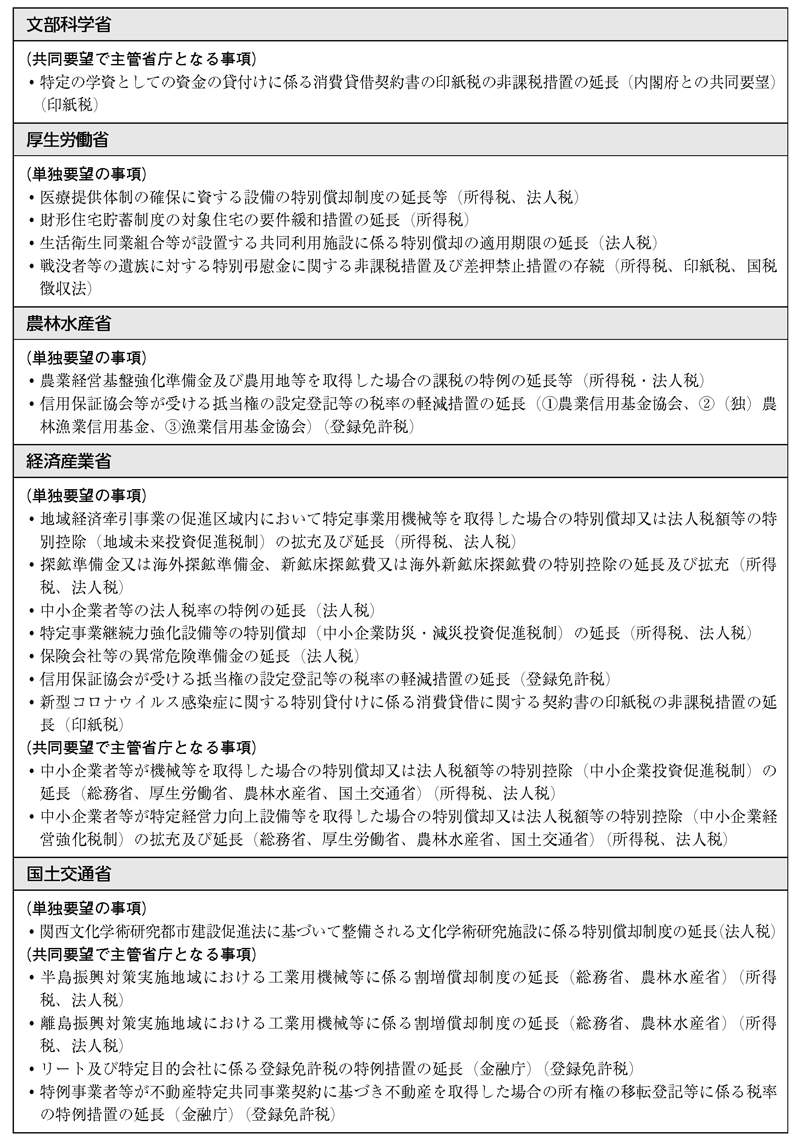
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
情報がありません
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

















