解説記事2024年12月02日 SCOPE ストックオプション付与決議に「募集事項の決定決議」を追記(2024年12月2日号・№1053)
国税庁、令和6年度改正を踏まえQ&Aを改訂
ストックオプション付与決議に「募集事項の決定決議」を追記
令和6年度税制改正では、ストックオプション税制の大幅な拡充が行われている。改正後のストックオプション税制は、令和6年分以後の所得税について適用されるが、令和6年12月31日までの間に契約変更をすれば、改正後のストックオプション税制を適用することができる。今回の改正を踏まえ、国税庁は11月13日付けで「ストックオプションに対する課税(Q&A)」を改訂した。例えば、上場前の権利行使ができないとしていたものを可能にするなど、税制適格ストックオプションに係る要件と何ら関係のない事項に関する契約の変更であれば、税制適格ストックオプションとして取り扱うことができるとしている。
また、本誌が問題提起していた「ストックオプションの付与決議の日」については、会社法238条2項に定める募集事項の決定決議という旨が追記されている。
適格要件と関係のない契約変更なら税制適格を失わず
令和6年度税制改正では、ストックオプション税制の大幅な拡充が行われている。1,200万円とされている年間の権利行使価額については、会社の設立年数により、最大で3倍の「3,600万円」に引き上げられている。改正後のストックオプション税制は、令和6年分以後の所得税について適用されるが、令和6年3月31日以前に締結された契約について、令和6年4月1日から同年12月31日までの間に、①年間の権利行使価額の限度額、②発行会社自身による株式管理スキームに関する契約の変更をし、改正後税制に規定するそれぞれの要件を定めた場合には、令和6年度税制改正後のストックオプション税制の適用を受けることができる(本誌1014号参照)。ただし、令和6年12月31日までに契約を変更しなければならず、来年以降は、税制適格要件について当初契約の範囲を超える契約変更はできない。
なお、今回の改訂Q&Aでは、税制適格ストックオプションに係る要件と何ら関係のない事項に関する契約の変更や、変更後の契約に従って権利を行使したとしても当初の契約に反した権利の行使とならない場合における契約の変更であれば、契約の変更後も、その権利行使は当初の契約に従って行われるものと同様と認められるとし、税制適格ストックオプションとして取り扱って差し支えない旨が明記されることになった(改訂Q&A問10)。例えば、上場前の権利行使を禁止していたものを上場前であっても権利行使可能とする変更や、権利行使を行わなければならない期間について、当初契約の範囲内の別の期間とする変更であれば税制適格要件は失わない。ただし、当初の契約の行使期間である「3~8年」を「2~10年」に変更する場合など、当初の契約の範囲を超える場合には税制適格ストックオプションとして認められないので留意したい。
上場の場合は金融商品取引業者に管理を移管
また、令和6年度税制改正では、現行の証券会社等への株式保管委託要件に加え、発行会社による株式の管理も可能となった(図参照)。株券を発行していないことの多いスタートアップ企業の場合、株式保管委託要件を満たすために株券を発行しなければならず(さらに上場した場合には株券不発行となる)、事務負担やコストの面で大きな弊害となっていたからだ。
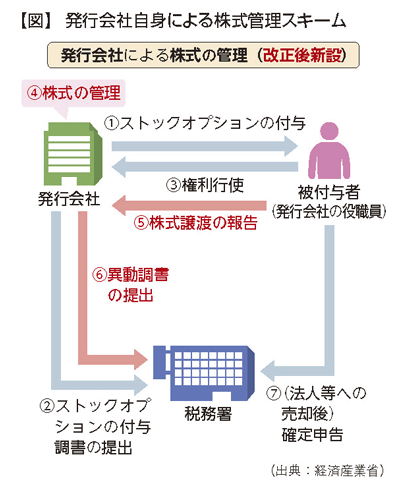
改訂Q&Aでは、前述したとおり、経過措置により改正後の要件を適用することができる旨を明らかにするとともに、発行会社における管理の対象となる株式については、譲渡制限株式に限られることから、株式の発行会社が上場する場合には、当該株式について、金融商品取引業者等による管理の方法に移行する必要があるとしている(改訂Q&A問11)。
移行にあたっては、実務上は上場承認前に①発行会社が金融商品取引業者等と契約を締結し、上場までの間に、②発行会社が金融商品取引業者等に必要な情報を連携するとともに、③特定株式等を保有する株主が金融商品取引業者等に専用口座を開設する必要がある。なお、上場に際して、①~③の手続きを経て、発行会社自身による特定株式等の管理から金融商品取引業者等による特定株式等の管理に、管理主体が不在の期間なく適切に移行する場合、当該移行は「返還又は移転」(措置法29条の2第4項)に該当しないものとして取り扱われるとしている。
割当決議に対する疑問の声に応える
そのほか、改訂Q&Aでは、「付与決議の日」の明確化が行われている。改訂前は、「付与決議の日とは、ストックオプションの割当てに関する決議の日をいいます。」とだけ記載されていたものである。本誌では、税制適格ストックオプションについて定めた租税特別措置法29条の2の規定によれば、付与決議とは、割当決議ではなく、新株予約権の募集事項決定のための決議を指すのではないかとの企業や専門家の疑問の声を伝え、問題提起を行っていた(本誌982号40頁参照)。
この点、今回の改訂Q&Aでは、「割当てに関する決議」とは、会社法243条2項(募集新株予約権の割当て)の決議をいうが、募集新株予約権の総数の引受けを行う契約を締結する場合には、実質的に対象者に新株予約権が与えられることとなる会社法238条2項(募集事項の決定)の決議とする旨が追記されている(改訂Q&A問6、問12)。今回の改訂により、実務上の懸念が払拭されることになりそうだ。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
情報がありません
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

















