解説記事2020年09月28日 実務解説 法人版事業承継税制と遺留分侵害額の請求(2)(2020年9月28日号・№851)
実務解説
法人版事業承継税制と遺留分侵害額の請求(2)
税理士 竹内陽一
公認会計士・税理士 有田賢臣
令和2年7月に国税庁より、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例措置等に関する質疑応答事例について」(資産課税課情報第14号)(以下、「第14号」)、「相続税及び贈与税等に関する質疑応答事例(民法(相続法)改正関係)について」(資産課税課情報第17号)(以下、「第17号」)が公表され、事業承継税制の適用を受けた後継者が、代償分割する場合や遺留分侵害額請求を受けた場合の取扱いが示されている。
3つの質疑応答事例(①代償分割があった場合、②遺贈に対して遺留分侵害額請求があった場合、③贈与に対して遺留分侵害額請求があった場合)について検討すると共に、前回(本誌No.801(2019年9月2日号))の解説の誤りについて整理する。
Ⅰ 代償分割があった場合
(問)子Aは、被相続人の全財産である土地(相続税評価額:2,000万円)とX株式会社の株式(相続税評価額:1億2,000万円)を相続し、X株式会社の株式について「相続税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることとしている。ところで、子Aは、もう一人の相続人である子Bに対し代償財産として7,000万円を現金で支払っているが、この場合の相続税の課税価格の計算において、代償財産として支払った7,000万円はいずれの財産の価額から控除すればよいか。
(注)各財産の代償分割の時における価額は上記の相続税評価額と同額である。
(解説)
代償分割が行われた場合、代償財産を交付した者(子A)の相続税の課税価格は、「相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額から交付をした代償財産の価額を控除した金額」とされている(相基通11の2−9)。
子Aは、土地と自社株式(納税猶予適用財産)を相続しているので、代償財産の価額をいずれの相続財産から控除するかにより、相続税額と納税猶予額が異なってくる。
質疑応答事例では、控除の方法として①納税猶予適用財産から優先控除する方法、②納税猶予適用財産以外の財産から優先控除する方法、③各財産から按分控除する方法のいずれかが考えられるとした上で、③の方法が合理的と考えられるものの控除方法が法令に定められていない以上、①②の方法によっても差し支えないとしている。
表1のとおり、子Aにとって、納税額がゼロとなる②の方法がもっとも有利と言えるが、納税猶予額=将来のリスクと考えれば①の方法を選択することも考えられる。また、当然のことだが、いずれの方法を選択しても子Bの納税額には影響を及ぼさない。
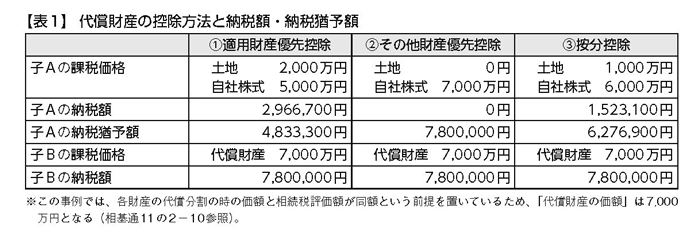
さて、相続税の納税猶予を受けるためには、相続開始の日から8ヶ月を経過する日までの間に、本社が所在する都道府県庁へ認定申請する必要がある。認定申請書には「納税猶予の適用を受けようとする議決権の数」を記載し、遺産分割協議書の写しを添付しなければならない。後継者以外にも相続人がいる場合には、生前贈与や遺贈により後継者に自社株式を確実に承継しておかないと、相続税の納税猶予が受けられない可能性がある。遺留分侵害額請求まで考慮すれば、先代経営者が亡くなる5年以上前に生前贈与をして贈与税の納税猶予を受けておくべきであろう。
なお、この事例のように、相続開始の日から8ヶ月を経過する日までの間に、遺産分割協議が成立した場合には、承継した自社株式の一部についてのみ納税猶予を受けることもできる。納税猶予の適用対象としなかった自社株式をX社(発行会社)に譲渡することで代償分割財産(現金)を調達することが可能となる。この金庫株譲渡については、みなし配当特例(措法9の7)や取得費加算特例(措法39)が適用できる。②の方法を選択すれば、例えば、相続した自社株式120株(相続税評価額:1億2,000万円)のうち70株について納税猶予を受けた場合でも、納税額と納税猶予額は変わらない(表2参照)。
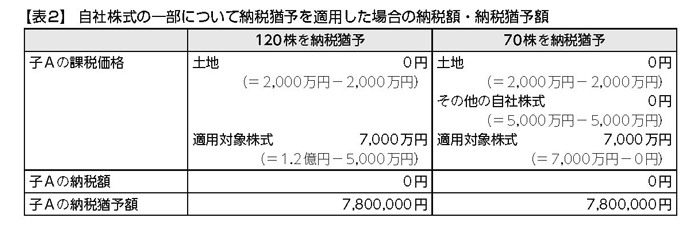
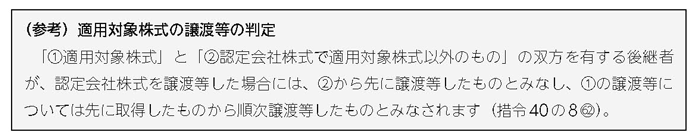
Ⅱ 遺贈に対して遺留分侵害額請求があった場合
(問)「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例措置」(措置法70の7の6)の適用を受ける非上場株式等に係る遺贈が遺留分を侵害するものとして遺留分侵害額の支払の請求が行われた場合においてその金額が確定したときは、納税猶予の対象となる非上場株式等の数に異動は生じるのか。
また、猶予税額の計算はどのように行うのか。
(解説)
(1)納税猶予の対象となる非上場株式等の数について
遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したことにより、相続税の課税価格及び税額が過大となったときは、当該事由が生じたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び税額につき更正の請求をすることができる(相法32①三)。
ただし、自社株式(納税猶予適用財産)の遺贈に対して遺留分侵害額請求が行われ、支払うべき金銭の額が確定した場合でも、当該更正の請求により納税猶予の適用対象株式数を変更することができないことが質疑応答事例により明らかにされた。当初申告により意思表示をした適用対象株式数を後日変更することはできず、株価の計算ミス等により修正申告をする場合においても適用対象株式数を変更することはできない(第14号の問1−5参照)。
(2)納税猶予額の計算について
遺贈に対して遺留分侵害額請求があった場合、受遺者(遺留分義務者)の相続税の課税価格は、代償分割が行われた場合(相基通11の2−9)に準じて、「相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額から遺留分侵害額に相当する価額を控除した金額」とする(第17号の事例2−1参照)。
この場合における「遺留分侵害額に相当する価額」については、代償分割が行われた場合(相基通11の2−10)に準じて、相続開始時の時価に基づいて計算された遺留分侵害額を相続税の課税価格ベースに置き直した額とする。
「遺留分侵害額に相当する価額」の控除方法については、代償分割の質疑応答事例と異なり、前期の3つの控除方法に関する記述はなく、当該非上場株式等の遺贈が遺留分を侵害するものとする遺留分侵害額請求が行われたことを前提としているため、納税猶予額の計算の基礎となる「非上場株式等の価額」は、当該非上場株式等の相続税評価額から「遺留分侵害額に相当する価額」を控除した価額に基づき計算することになるとしている。納税猶予適用財産の遺贈が遺留分を侵害していることから①の方法(納税猶予適用財産から優先控除する方法)によったものと推定できなくもないが、遺留分は遺産等全体に係る割合であることや具体的な控除方法が法令に定められていない以上、②③の方法を含めた別の合理的な方法によることもできると考える。
例えば、遺贈を受けた自社株式200株(相続税評価額:2億円※)のうち170株だけ納税猶予を受けた場合であれば、納税猶予を受けなかった自社株式30株の相続税評価額(3,000万円相当※)から遺留分侵害額に相当する価額(3,000万円※)を控除することは合理的であろう。※(4)の計算例の金額を用いている。
(3)当初申告時における留意点
後継者に自社株式を遺贈することにより相続税の納税猶予を受けることが可能となる一方で、経営承継期間(遺贈の場合は、相続税の申告期限から5年間となる)中に納税猶予適用財産である自社株式を1株でも譲渡した場合には納税猶予額の全額が期限確定してしまう。したがって、経営承継期間を経過していない場合には、遺留分債務を支払うために、自社株式(納税猶予適用財産)を譲渡することはできない。
遺留分侵害額請求が想定される場合には、予め遺贈を受けた自社株式の一部についてのみ納税猶予の適用を受けるなどの対応も考えられる。納税猶予の適用対象としなかった自社株式の金庫株譲渡について、みなし配当特例(措法9の7)や取得費加算特例(措法39)を適用することが可能だ。
(4)相続税の更正の請求書(課税価格、税額等の明細)の記載例
次の計算例(第17号の事例2−4(参考1)参照)に基づいて、相続税の更正の請求書の記載例を示す。
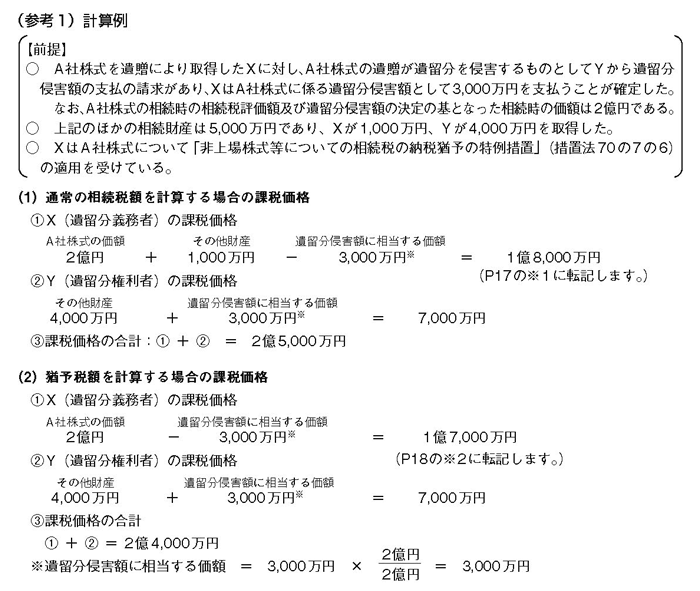
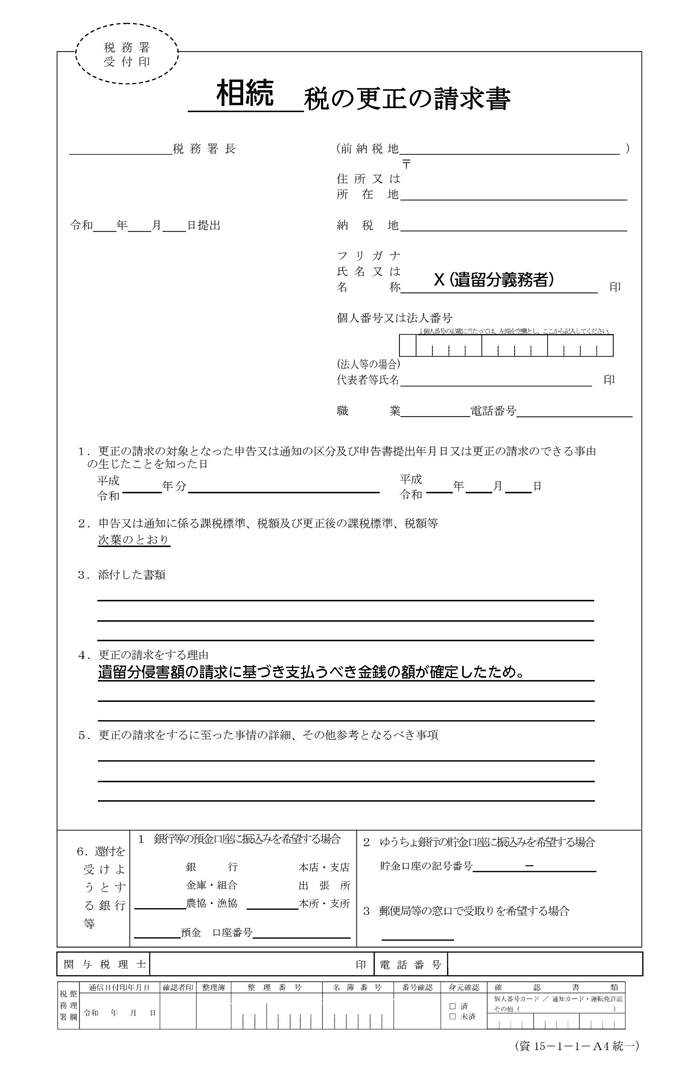
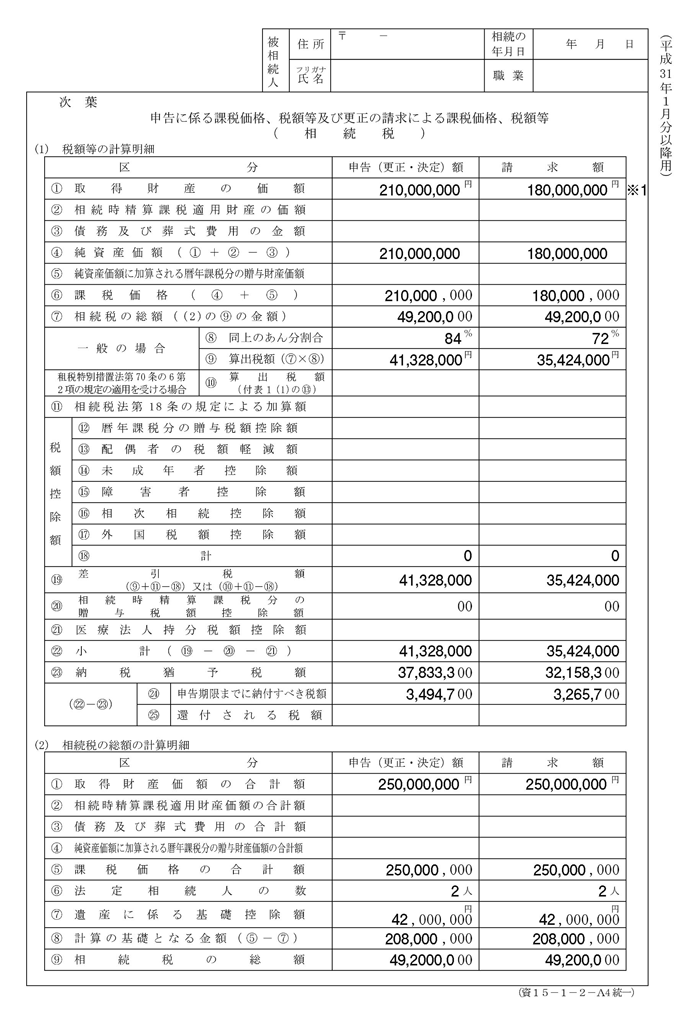
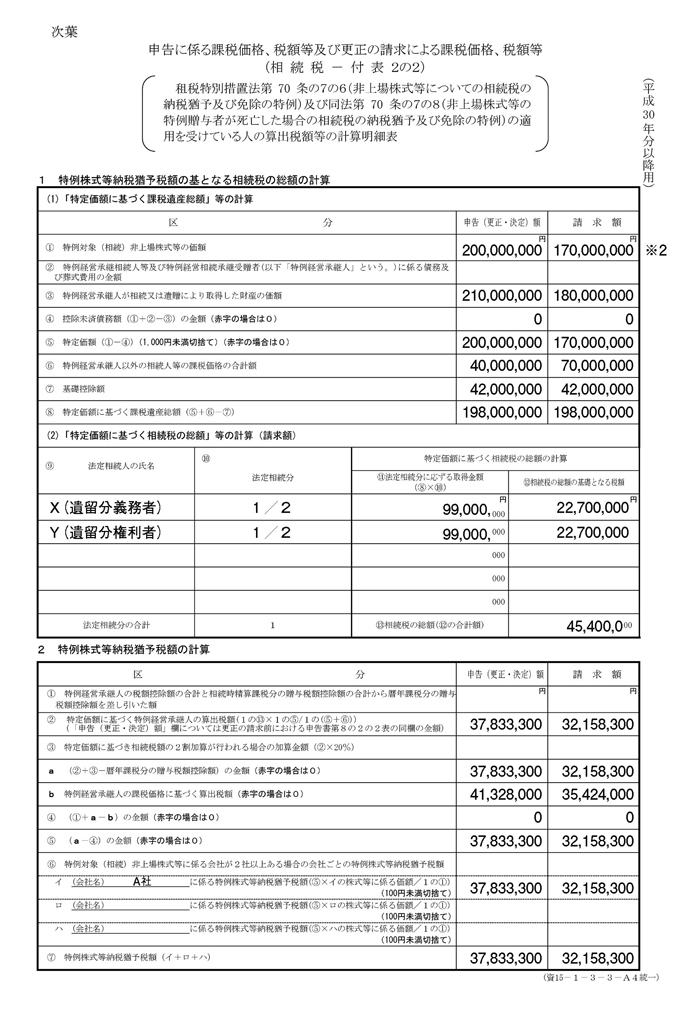
Ⅲ 贈与に対して遺留分侵害額請求があった場合
(問)子Xは、母から贈与により取得をしたB社株式について「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例措置」(措置法70の7の5)の適用を受けていたが、このたび母が死亡したところ、子Yから当該贈与が遺留分を侵害するものとして遺留分侵害額の支払の請求を受けた。
その後、遺留分侵害額が確定したが、この場合、措置法第70条の7の7の規定により母から相続により取得したものとみなされる非上場株式等の数に異動は生じるのか。
また、贈与税の猶予税額及び子Xが当該非上場株式等について「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例措置」(措置法70の7の8)の適用を受ける場合の相続税の猶予税額は、どのようになるのか。
(解説)
(1)相続により取得したものとみなされる非上場株式等の数について
自社株式(納税猶予適用財産)の贈与に対して遺留分侵害額請求が行われ、支払うべき金銭の額が確定した場合でも、当該贈与の贈与者から相続により取得したとみなされる自社株式の数に異動が生じないことが質疑応答事例により明らかにされた。
前回(本誌No.801)の解説では、(C)贈与税の更正の請求から始めて、その後に相続税の更正の請求を行う方法と(D)相続税の更正の請求のみ行う方法で場合分けをし、(C)の方法による場合には、相続により取得したものとみなされる非上場株式等の数に異動が生じると説明した。納税猶予額の計算の基礎となる「非上場株式等の価額」が「遺留分侵害額に相当する価額」だけ減少する一方で、当該非上場株式等の株価は調整されないことから、贈与税の納税猶予に係る適用対象株式数が減少し、その結果、相続により取得したものとみなされる株式数が減少すると考えていた。みなし相続規定(措法70の7の3①・70の7の7①)では、「後継者が贈与者から相続により適用対象株式(猶予中贈与税額に対応する部分に限る。)を取得したものとみなす。」とされており、この文言を猶予中贈与税額の減少に伴い適用対象株式数も減少すると解釈していたからだ。具体的には、当初申告で提出した相続税申告書「第8の2の2表の付表2」を前掲のように書き換えた上で、参考資料として更正の請求書に添付するような実務を想像していた。
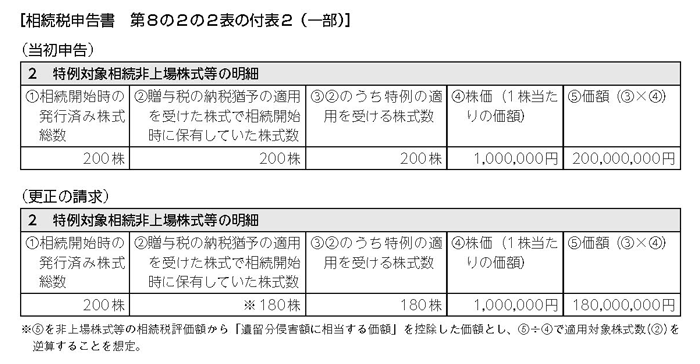
当初申告で提出した相続税申告書の「第8の2の2表の付表2」にて意思表示をした適用対象株式数200株を変更することはできず、「第8の2の2表の付表2」を再提出するような実務は存在しないこと。そして、みなし相続規定(措法70の7の3①・70の7の7①)における「適用対象株式(猶予中贈与税額に対応する部分に限る。)」とは、当初申告で提出した贈与税申告書の「特例株式等納税猶予税額の計算書」にて意思表示をした適用対象株式数(の内、納税猶予が継続している分)という意味でしかないことが明らかとなった。
(2)贈与税の納税猶予額について
贈与に対して遺留分侵害額請求があった場合、受贈者(遺留分義務者)の贈与税の課税価格は、「贈与により取得した現物の財産の価額から遺留分侵害額に相当する価額を控除した金額」とする(第17号の事例2−3参照)。
この場合における「遺留分侵害額に相当する価額」については、相続開始時の時価に基づいて計算された遺留分侵害額を贈与税の課税価格ベースに置き直した額とする。
なお、贈与税の納税猶予額の計算の基礎となる「非上場株式等の価額」は、当該非上場株式等の相続税評価額から「遺留分侵害額に相当する価額」を控除した価額に基づき計算することになる。
(3)相続税の納税猶予額について
贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予に切り替えた場合には、その贈与税の納税猶予額の計算の基礎となる「非上場株式等の価額」に基づいて相続税額及び納税猶予額を計算する(措法70の7の7①)。
自社株式(納税猶予適用財産)の贈与に対して遺留分侵害額請求があった場合には、上記(2)と同様の方法で当該「非上場株式等の価額」を計算する。受贈者(遺留分義務者)の相続税の課税価格から控除される「遺留分侵害額に相当する価額」は贈与税の課税価格ベースに置き直した金額であるのに対し、遺留分権利者の相続税の課税価格に算入される「遺留分侵害額に相当する価額」は相続税の課税価格ベースに置き直した金額となることに注意を要する(第17号の事例2−5(参考2)参照)。
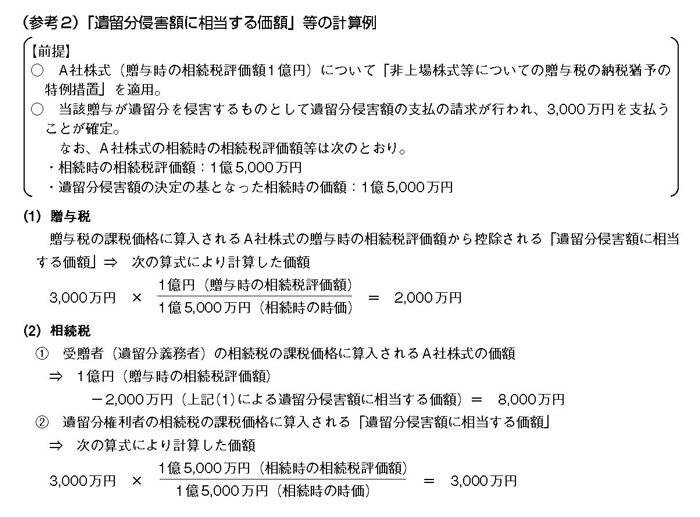
(4)更正の請求について
自社株式(納税猶予適用財産)の贈与に対して遺留分侵害額請求があった場合において、受贈者(遺留分義務者)が相続税の更正の請求をするときは、贈与税についても併せて更正の請求をする必要がある。
ただし、納税猶予されていた贈与税は、贈与者の死亡により免除されていることから贈与税の更正の請求を省略しても差し支えないとされている。なお、納税猶予の期限が確定した贈与税がある場合など、贈与税の還付を受けられるケースにおいては、贈与税の更正の請求が必要となる。
(5)納税猶予適用対象財産である自社株式の譲渡について
経営承継期間(贈与の場合は、贈与税の申告期限から5年間となる)を経過していれば、遺留分債務を支払うために、自社株式(納税猶予適用財産)を譲渡しても、その譲渡した部分に対応する納税猶予額のみが期限確定するだけである。
先程の計算例の金額を用いると、相続税の更正の請求により納税猶予税額が37,833,300円から32,158,300円に減少している。XがA社株式の25%を5,000万円で金庫株譲渡したとすると、更正請求後の納税猶予税額32,158,300円×25%=8,039,500円(100円未満切り捨て。措令40の8の5⑱で準用する措令40の8 )が期限確定する。みなし配当特例と取得費加算特例を適用して譲渡所得税が1,000万円になったと仮定すると、Xの手元の残る金額は、5,000万円−遺留分債務3,000万円−期限確定した相続税8,039,500円−譲渡所得税1,000万円=1,960,500円となる(期限確定に伴う利子税は考慮していない)。
)が期限確定する。みなし配当特例と取得費加算特例を適用して譲渡所得税が1,000万円になったと仮定すると、Xの手元の残る金額は、5,000万円−遺留分債務3,000万円−期限確定した相続税8,039,500円−譲渡所得税1,000万円=1,960,500円となる(期限確定に伴う利子税は考慮していない)。
遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定した時点で経営承継期間を経過していない場合でも、みなし配当特例の適用期限(相続税の申告期限から3年間)までに経営承継期間を経過するのであれば、とりあえず、銀行や自社から資金を借り入れて遺留分債務を支払い、経営承継期間が経過してから自社株式を譲渡して、借入金を返済することも考えられる。
なお、遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したことに伴う相続税の更正の請求と、期限確定の届出は全く別の手続きである(納税猶予の期限が到来しても相続税の修正申告書の対象になるものではなく、その提出は必要ない。)。前回の経営報告基準日の翌日から今回の経営報告基準日までの間に、納税猶予の期限が到来した猶予中税額がある場合には、その明細を記載の上、納税猶予の継続届出書に添付して提出することになる(次頁の「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予の継続届出書(特例措置)」5参照)。
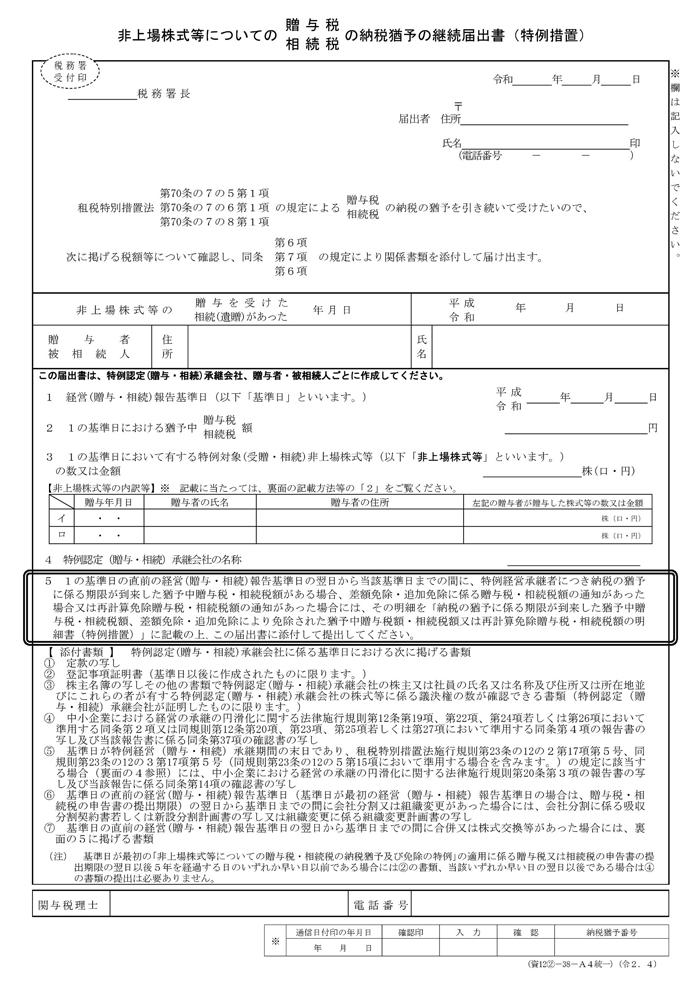
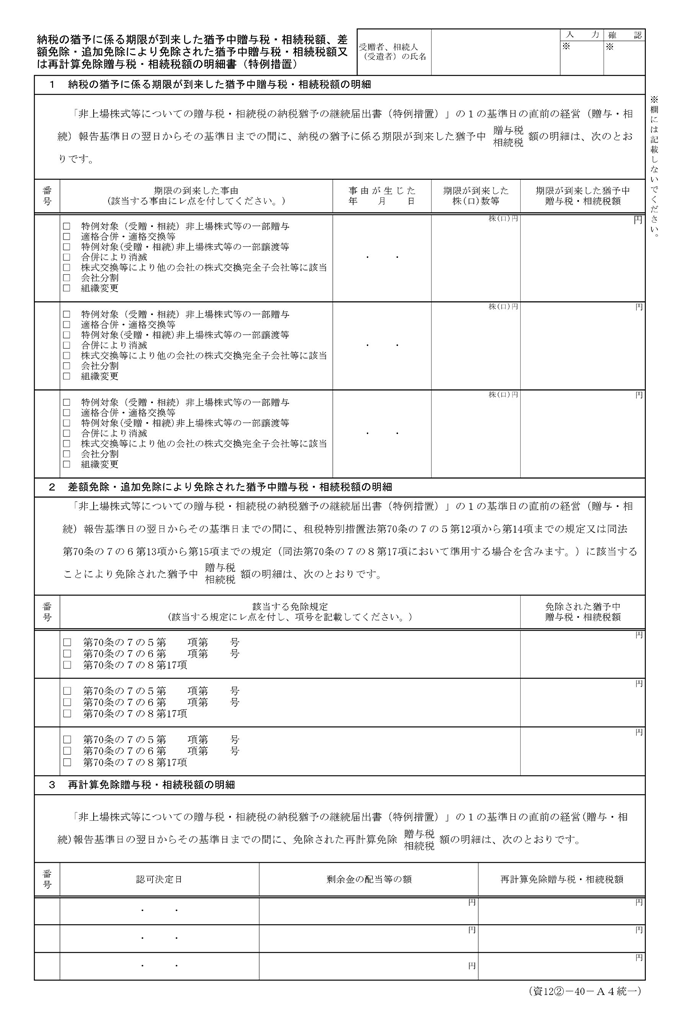
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























