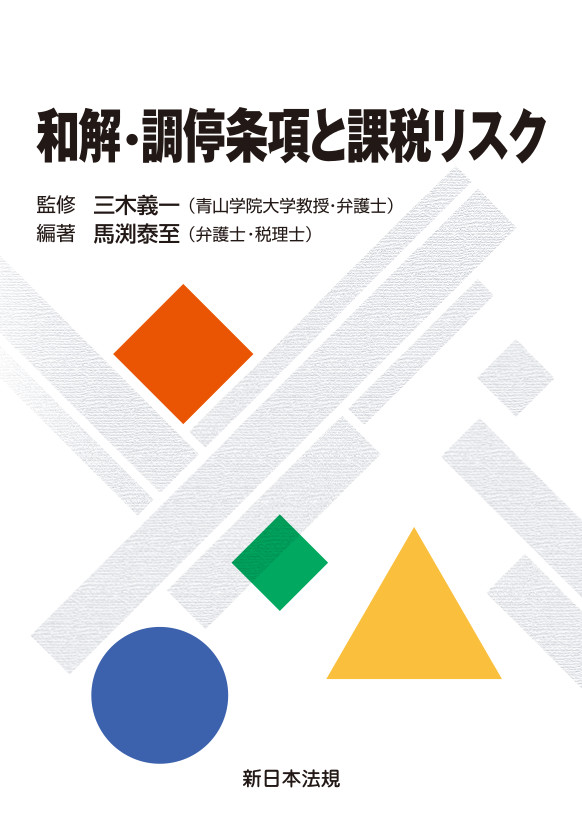民事2013年10月03日 「課税リスク」への配慮のすすめ 執筆者:馬渕泰至
「取得時効を援用すると、援用時に一時所得が発生する」
「相続において限定承認をすると、譲渡所得(税)が発生する可能性がある」
「残業代を『解決金』名目で支払うとしても、源泉徴収は必要」
「債務免除を受けると、債務免除益に法人税や贈与税が課税される」
「消費税の非課税事業者と和解する場合、消費税を考慮すべきか」
「離婚に伴う財産分与において、不動産を譲渡すると、多額の譲渡所得が発生することがある」
「法人に不動産を遺贈したら、時価の譲渡とみなされ、相続人に高額の譲渡所得税が課税される」
「遺産分割協議をやり直すと、新たな取引として課税される」
上記は、和解や調停をはじめとする法律行為が課税関係に影響を及ぼす顕著なケースを列挙したものです。
私たち弁護士は、紛争の処理を生業としていますが、そのほとんどの紛争を和解や調停によって解決しています。
言うまでもないことですが、和解や調停は、相互に権利を譲歩して成立させるものであり、成立時において、新たな権利の得喪が生じます。そして、新たな権利の得喪には、常に課税の問題が付いて回ります。
この点、実際に課税の問題が顕在化するのは、確定申告時あるいは申告後の税務調査の段階ですので、私たち弁護士は、事後的な課税関係を関知しないことが多いでしょう。しかし、ひょっとしたら、私たち弁護士が関わった和解・調停条項に関し、私たちの知らないところで、クライアントが苦しんでいるかもしれません。
私たち弁護士は、紛争案件を受任する際、「課税リスクの検討については委任業務の範囲外」とすることが多いのですが、クライアントは、課税リスクも考慮した紛争の処理を望んでいるでしょうし、紛争を処理したものの、思いの他、高額の税金を持っていかれたというのでは、本当にクライアントのニーズに応えられたのか疑問の残るところです。
専門家に対する損害賠償請求訴訟が増加している昨今、課税リスクの見落としが弁護過誤と評価される日が来るかもしれません。
そこまでは至らずとも、課税リスクを意識して弁護士業務を行うことは、過当競争となってきた弁護士業界において、競争優位を保つことができるのではないでしょうか。
(2013年9月執筆)
人気記事
人気商品
関連商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -