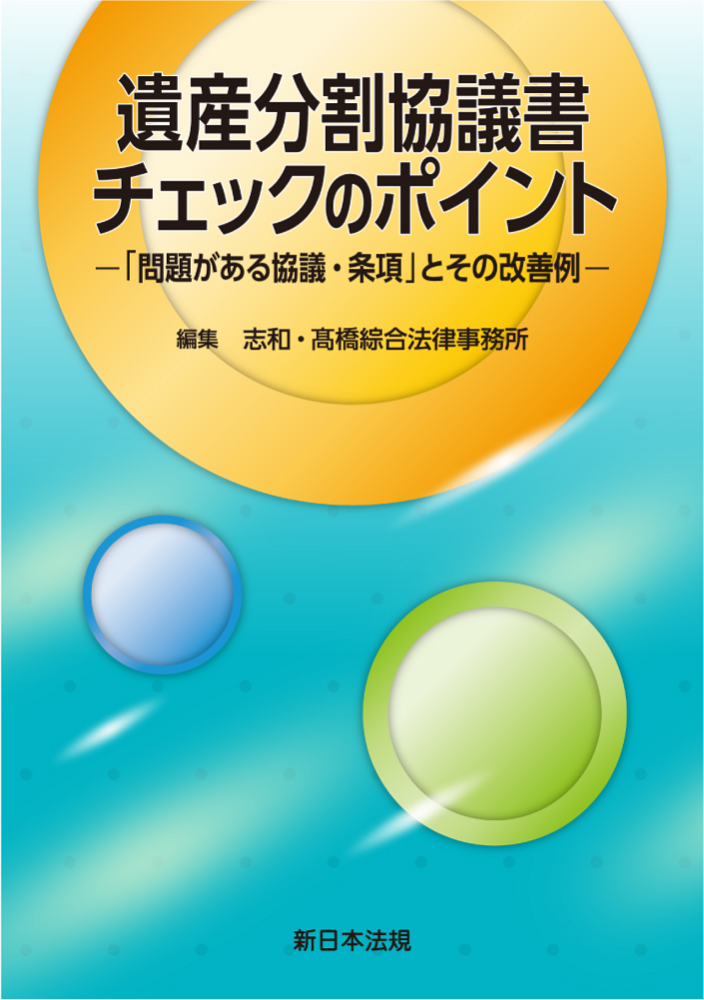一般2025年04月09日 受刑者と職員「交換日記」 悩みや決意、受け止め返事 北海道・月形、更生願い 提供:共同通信社

北海道月形町の月形刑務所は昨年4月、全受刑者と職員の間で「交換日記」を始めた。背景には、一人一人の特性に応じた処遇で再犯防止や更生につなげようとする国の方針がある。悩みや出所後の決意を記す受刑者と、受け止める職員の双方に、気付きや変化をもたらしている。
「悪友との関係を改めるしかない」。薬物を使って交通事故を起こした受刑者の50代男性は、濃くはっきりとした字で冊子に書いた。
外国生まれ。ぜんそくで学校を休みがちで、18歳ごろ来日した。日本語の習得に苦労し、入所後も刑務官から小学生レベルの日本語読解を学んだ。今は算数を勉強中だ。
日記では、出所後に薬物依存者の自助グループに参加し「自分を変える」と記入した。返却された冊子には赤ペンでこう書かれていた。「頼れる仲間と出会えることを願っています」
月形刑務所は累犯者が多く、男性も刑務所への入所は初めてではない。居室でじっくり考えて言葉をつづる半日ほどの時間は、重ねた罪とも向き合っている。取材に言葉を区切りながら語った。「あのときやってさえいなきゃ。苦しい、しんどい面もあるし、自分が悪いんだから、今後しないために(日記を書くのは)良い機会かな」
日記は「3箇月ノート」と呼ばれ、3カ月に1度のペースで記す。「1年を振り返ってみて再犯防止に関する意識はどう変わったか」など、職員が指定したテーマに答える形だ。自由に思いを記せる欄もある。
刑務所では規律や秩序の維持が最優先され、受刑者への抑圧的な対応が問題となることも。更生に向けた働きかけも職員側からの一方的な指導が中心で、紙上で交流する取り組みは珍しい。
きっかけは刑法改正だ。今年6月施行され、受刑者を「懲らしめる」意味合いが強かった懲役刑と禁錮刑が、立ち直りを重視する「拘禁刑」に一本化される。刑務所も転換を迫られる中、限られた職員数でできるアイデアとして取り入れた。ほぼ白紙の冊子もあるが、400人以上の受刑者の多くが何らかを記述する。
返事するのは、再犯防止教育を受け持つ「教育専門官」の職員4人だ。「こちらの言葉を(受刑者は)うざったいと思うのでは」。50代の男性職員は当初、そんな懸念を抱いていたが、冊子をめくり考えを改めた。「まだ薬に走りそうな考えがある」「もうこの中には帰ってきたくない」…。職員は記される率直な思いに日々向き合う。
開始から1年。一部とは、本来の交換日記のようにお互いの文章を踏まえたやりとりもある。「一緒に出所後のことを考え、応援する存在」。職員はそんな役割を果たせたらと考えている。
拘禁刑
現行刑法が刑の種類として定める死刑、懲役、禁錮、罰金などのうち、懲役と禁錮を一本化した新たな刑罰。懲役受刑者に科されてきた刑務作業が義務ではなくなり、薬物依存者や高齢者などそれぞれの特性に応じ、作業や指導を柔軟に組み合わせられるようになる。社会復帰や再犯防止につなげる狙いで、6月1日施行の改正刑法で導入され、同日以降に起きた事件・事故で有罪になると適用される。
(2025/04/09)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.