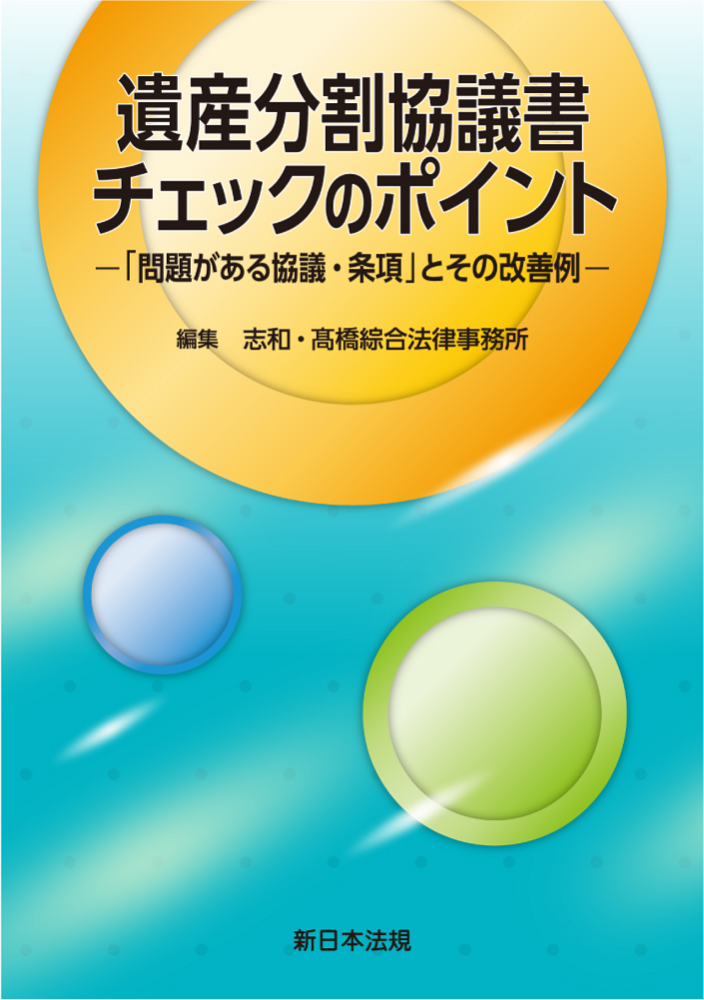民事2025年04月22日 取り違え、実親捜し命令 67年前都立産院、東京地裁 「出自知る権利」憲法保障 提供:共同通信社

東京都立墨田産院(閉院)で1958年4月の出生直後、他の新生児と取り違えられた江蔵智(えぐら・さとし)さん(67)が都を相手取り「生みの親」を調査することなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁(平井直也(ひらい・なおや)裁判長)は21日、「親子関係の根幹に関わる問題で、経過時間や生物学上の親の生存を問わず、出自を知る法的利益は失われない」とし、戸籍などを基に実親について調査するよう命じた。
「出自を知る権利」は憲法13条が保障する法的利益だと判断した。弁護団によると、こうした判断は初めて。
記者会見で江蔵さんは「求めていた内容を裁判所で認めてもらった」と評価。実親も育ての親同様に高齢になっていると思われるとし「都には一日も早く調査してほしい」と述べ、控訴しないよう求めた。
都側は、取り違え当事者かもしれないとの告知を望まない人の権利を侵害する恐れがあると主張したが、判決は「相手方も出自を知る法的権利がある。真実を知ることで、生物学上の親やきょうだいらとの交流が可能になり得る側面がある」などと指摘。分娩(ぶんべん)助産契約に基づき、都には調査を尽くす義務が存続しているとした。
その上で、江蔵さんが生まれた58年4月に作成された「戸籍受付帳」を基に、取り違えられた可能性がある男性を選定し、江蔵さんの母親との親子関係を確認するためDNA型鑑定への協力を依頼するよう都に命じた。鑑定は同意が得られた場合とし、江蔵さんや母親との連絡を希望するかどうか意思を確認するとした。
判決によると、江蔵さんは出生後間もなく産院職員により誤って引き渡され、育てられた。母親の血液型検査がきっかけとなり、2004年、鑑定で両親と血縁関係がないと判明した。取り違えを巡っては、江蔵さん側が04年、都に損害賠償を求め提訴。東京高裁が06年、取り違えを認め「重大な過失で人生を狂わされた」として、都に2千万円の支払いを命じた判決が確定している。
都庁で記者団の取材に応じた小池百合子都知事は「判決の詳細を把握していない。中身を精査したい」と述べた。
判決要旨
他の新生児と取り違えられた男性について、東京都に実親の調査をするよう命じた東京地裁判決の要旨は次の通り。
【訴えの適法性】
調査の対象者が、自分が当事者かもしれないとの疑問が生じ、動揺や不安を受けたり、現在の家族関係に不利益な影響が生じたりする恐れは否定できない。しかし、男性は生物学上の親を知る法的利益があり、見つけるためには取り違えた相手を捜し、個別に接触して確認する以外に方法は見当たらない。
取り違えの相手方も、客観的には出自を知る法的利益があり、必ずしも真実を知らないままにしておいてもらいたかったという意向が示されるとは限らない。真実を知ることで、生物学上の親やきょうだいらとの交流が可能になり得る側面もある。対象者が調査に協力しないなどという選択もできるため、現在の生活関係を優先したいという意向の人への配慮がされている。
調査対象者が取り違えの相手方だった場合に生じる影響を考慮しても、調査請求が不適法とはいえない。
【都の調査義務】
子が生物学上の親とのつながりを確認、構築することが子の人格的生存に重要であり、仮にそれができなくても自身に重要な根源的・歴史的事実である出自に関する情報を知ること自体も、憲法13条が保障する個人の人格的生存に重要なこととして法的利益として位置付けられている。
分娩(ぶんべん)助産契約では、子が親に確実に引き渡されることは親子の関係性の根幹に関わる問題で、医療機関の新生児の取り違えは決してあってはならず、万が一起きた場合には、できる限りの対応を取るべき義務があると解することが合理的だ。
取り違えから長時間経過していても、生物学上の親を見つけるための合理的な方法による調査を尽くすべき義務は存続し、この調査義務は分娩助産契約の当事者間の合理的な意思に合致する。
男性が求める調査は、都が現時点で実施が合理的に可能な方法および範囲であるから、分娩助産契約に基づき調査すべき義務を具体化したものとして認めることが相当だ。
調査では、男性が生まれた1958年4月に作成された「戸籍受付帳」を基に、取り違えられた可能性がある人を選び、男性の母親との親子関係を確認するためDNA型鑑定への協力を依頼する。鑑定は同意が得られた場合で、男性や母親との連絡を希望するかどうか意思を確認する。
【不法行為・債務不履行責任】
この判決より前の段階では都に調査義務の怠りがあったとは認められず、不法行為や債務不履行に基づく損害賠償請求は理由がない。
「一日でも早く会いたい」 法廷で目を閉じ願った原告
「神に願うような気持ちだった。一日でも早く会いたい」。東京都立墨田産院で取り違えられた江蔵智(えぐら・さとし)さん(67)は21日、東京地裁の法廷でじっと目を閉じながら判決を聞いた。実親の手がかりを得られる内容を求めた訴えを認める主文の朗読に続き、裁判長が都に調査を命じる理由を説明。代理人弁護士は江蔵さんの肩を優しくたたき、うなずき合った。
1958年に出生し、取り違えられたとは思わず育った江蔵さん。46歳の時、家族で受けたDNA型鑑定で「あなたの体にはお父さん、お母さんの血は一滴も流れていない」と告げられた。
裁判の傍ら、自ら墨田区役所で情報を集めた。同じ頃に生まれた約70~80人を訪ね歩いたが、時は流れるばかり。さまざまな思いから「自分を失い、体調が悪くなった時期もあった」と語る。
DNA型鑑定から20年以上が過ぎ、判決後の記者会見では「親子関係がないと分かった時から、実親の顔が見たい、会いたいと思っていたのは変わらない」と振り返った。92歳になった「育ての母」は認知症が進むが「一目でいい、遠くからでもいいから顔を見たい」との実子への思いをまとめた陳述書を裁判所に提出したという。
判決が確定し、調査が進めば実親に会える可能性が高まる。江蔵さんは「どんな言葉が出てくるか…。会って、相手の目を見てみないと」と言葉を詰まらせ、さらにこう言った。「僕の願いも、母の願いもかなえたい。時間がない」
新生児取り違え訴訟の経過
1958年4月10~14日 東京都立墨田産院(閉院)で江蔵智さんが他の新生児と取り違えられる
97年 江蔵さんの母親が受けた血液型検査で、親子間ではあり得ない組み合わせと判明
2004年 DNA型鑑定により、江蔵さんと両親の間に親子関係がないことが判明。江蔵さんと両親が東京地裁に損害賠償請求訴訟を提起
05年5月 東京地裁は賠償請求権が消滅する「除斥期間」の経過を理由に江蔵さん側の請求を棄却
06年10月 東京高裁が正しい新生児を引き渡す債務の不履行があったと認め、都に計2千万円の賠償を命じる判決
21年11月 江蔵さんが実親の調査義務があることの確認などを求め東京地裁に提訴
25年4月21日 東京地裁が都に実親の調査を命じる判決
憲法13条
全ての国民が個人として尊重され、幸せを追求する「幸福追求権」を保障するとした規定。憲法の三大原則の一つ「基本的人権の尊重」の基礎を構成する。自己決定権やプライバシーの権利といった、憲法の条文に明記されない「新しい人権」を導く根拠となってきた。過去には、最高裁が2023年、戸籍上の性別を変えるのに生殖能力を失わせる手術を事実上求める性同一性障害特例法の規定を、この条文に基づいて違憲・無効とした。
(2025/04/22)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.