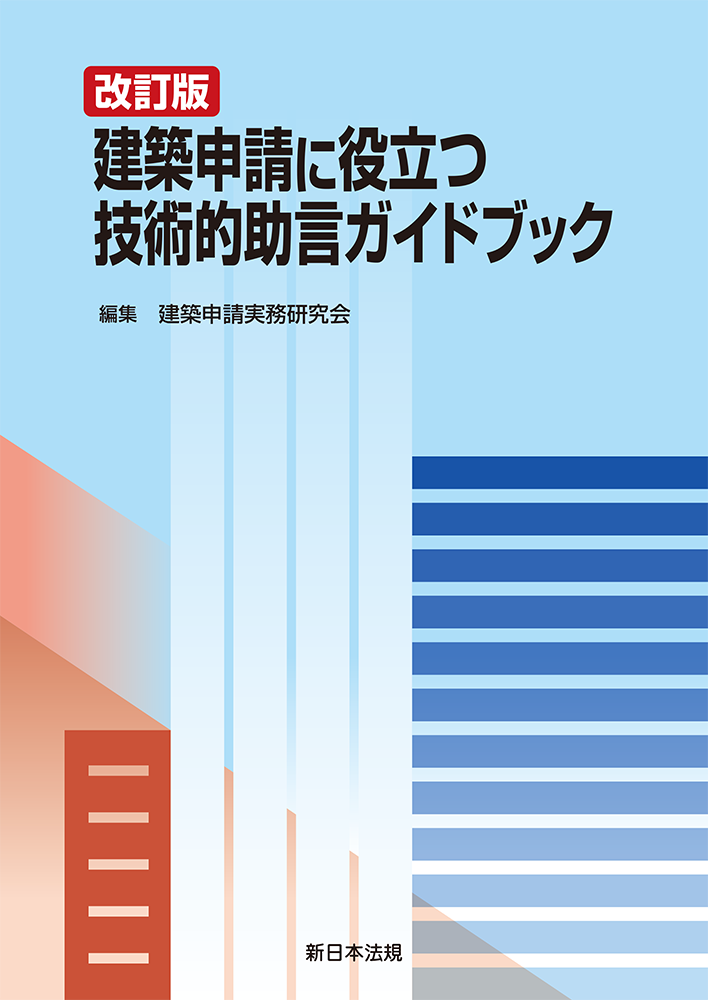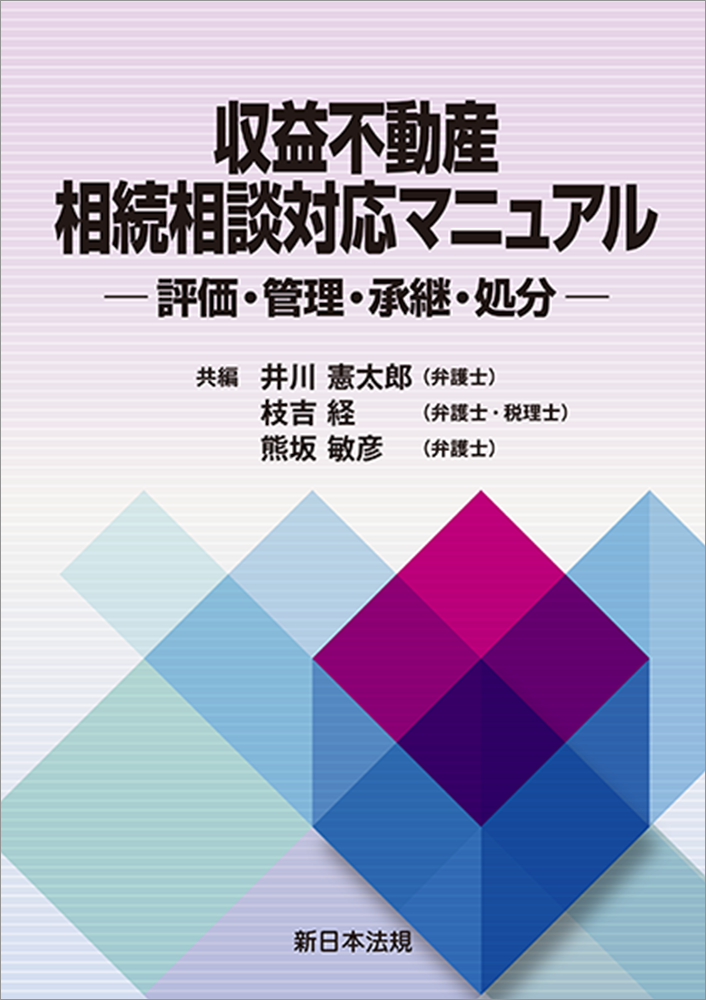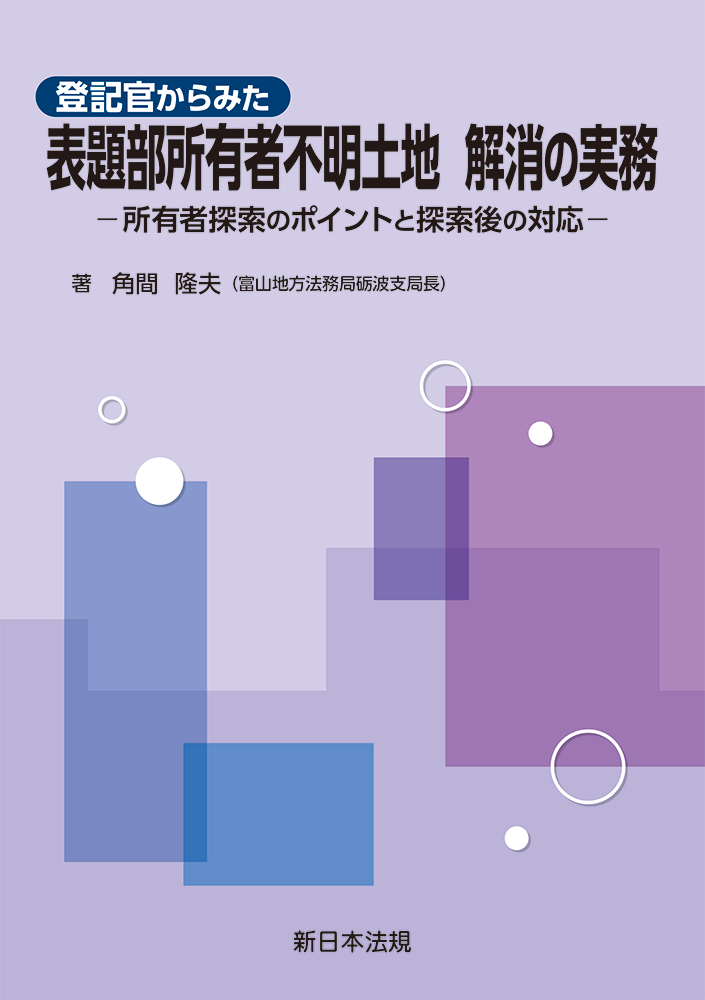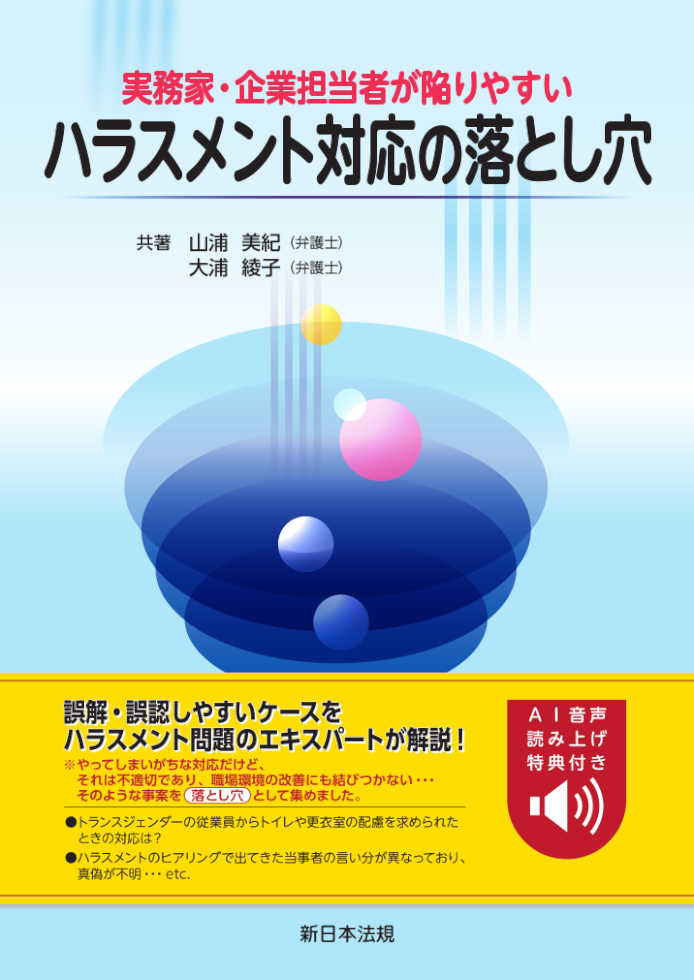民事2025年09月22日 スポーツ界のハラスメント「理解ずれ解消を」 出雲の女子サッカーチームでは外国人選手がセクハラ訴え、「スラングの認識だった」と監督 提供:共同通信社

スポーツに関わる人々の人権を尊重し、暴力や虐待から守る取り組みとして「セーフスポーツ」という考えが広がっている。そんな中、現場で起きているのは、選手や指導者の間で、守るべき規律や規範の「理解のずれ」が生じる事態だ。
女子サッカー2部リーグに所属する「ディオッサ出雲FC」(島根県出雲市)では、所属していたブラジル人選手2人が昨年11月、日本人監督からセクハラを受けたと記者会見で公表した。
しかし、監督は、セクハラとされたポルトガル語の発言は「『やっちゃった、くそ』等の意味と認識していた」「スラングとして口にした」などと主張したとされ、日本サッカー協会(JFA)は今年4月に、「(監督に)懲罰を科さない」と決定した。
調査に入り、「懲罰相当」とJFAに報告した日本女子サッカーリーグの事実認定や見解はまた異なり、「ずれ」が際だった形だ。
現状を「過渡期」とみる専門家が大切だと語るのは、「同じ目標に向かうこと」だ。価値観のずれを解消し、取るべき行動を照らし合わせるのには、どうすればいいのだろうか。(共同通信=木原望衣)
▽被害訴え記者会見
「私たちはいじめの奴隷になるために来たのではない」
2024年11月、ディオッサの選手だったラウラ・スペナザットさん(27)とフェへ・タイスさん(25)はハラスメントを訴え、監督の解任を求めて開いた記者会見でこう語った。
選手の代理人弁護士によると、2人は2022年8月からチームに所属していた。ミスをした際に男性の監督らからポルトガル語で「性器」などを意味するののしり言葉を投げかけられたという。また、入団時に練習や試合で通訳を同行させる契約を結んだが、実際は週1回しか付かず指示が理解できないなどの支障が出た。2人は2024年7月にうつ状態と診断され、8月にチームを離脱した。
同じ日、チームの運営法人も記者会見を開き、監督らの発言については「弁護士と事実関係を調査している」とし、監督は一時活動を自粛した。
▽リーグが調査
被害を訴えた会見から約2週間後の2024年11月下旬、日本女子サッカーリーグの担当者が島根県出雲市を訪れ、ラウラさんとフェへさん、練習で付き添っていた通訳に聞き取り調査をした。
同じ日、チーム側は通訳の同行が限られていたとの訴えに対し、対応に不適切な点があったと金銭賠償に向けて調整すると発表した。監督の一時活動自粛については、解除の申し出を受け入れたとし、監督は再び指揮を執ることになった。
翌12月、契約期間満了に伴い、2人はチームに復帰することなく退団した。
▽JFAの判断
日本サッカー協会(JFA)が監督に懲罰を科さない決定をしたと明らかになったのは今年5月だ。チームが、記者会見し、明らかにした。
選手2人の代理人弁護士が公表したJFAの決定書によると、問題を調査した日本女子サッカーリーグは、当事者や関係者の証言などから監督から2人への暴言や性的発言があったと認定。「チームの監督という指導的地位にありながら、あえて外国人選手の母国語で暴言・性的発言を行ったことは、きわめて悪質な態様であり、理由の如何を問わず、決して許されない」とし、懲罰に相当し得るとJFAに報告した。
一方、決定書は「練習後に(監督自身が)シュートを外した場合など、自分がうまくいかなかったときに『やっちゃった』というような意味合いで使ったことがある」「(ポルトガル語を使った意図は)ブラジル人はシュートを外したらこう叫んだりするよねというような意味で、コミュニケーションをとるために使った」と監督が述べたと記載。
JFAは、監督が「性器」などを意味する言葉を発したこと自体は「不適切」で、ブラジル人に対する侮辱との誤解を与えかねないという意味でも「不適切」と認定した。しかし、女子サッカーリーグの事実認定は録音や映像などの客観的な証拠に基づくものではなく、選手2人に向けられた言葉と認定するには足りないと判断した。
チームの会見に同席した監督の代理人弁護士は、不適切な発言があったことは認める一方で「スラングの認識だった。2人に向けた言葉ではない」と重ねて主張。チーム側は「ハラスメントは存在しない」と強調した一方で、監督に不適切な発言があったとして厳重注意をした。今後、選手やスタッフにコンプライアンスの研修などを検討している。
「他の人には、私たちと同じ思いをしてほしくない」。ラウラさんとフェへさんは6月、精神的被害を受けたなどとして、チームと監督に計340万円を求めて松江地裁出雲支部に提訴した。
現在、2人はともに、海外のリーグで活動している。提訴についての記者会見にオンラインで参加したラウラさんは「大好きなサッカーができなくなると思った。法律が適用されてほしい」と語った。
▽過去最多を更新する相談
日本のスポーツ界は、2023年に暴力行為根絶宣言を採択した。競技団体が相談窓口を設置するほか、日本スポーツ協会などは「NO!スポハラ(スポーツ・ハラスメント)と銘打ったキャンペーンを展開している。
協会の調査によると、2024年度の協会の窓口への相談件数は、536件で過去最多を更新した。近年は、不適切行為かどうかを判断するのがより難しい「暴言」や「ハラスメント」に関する相談が多く寄せられる傾向があるという。
▽理解を合わせるために
スポーツとジェンダーに詳しい中京大学の來田享子教授によると、国際オリンピック委員会(IOC)は2016年の統一声明で「セーフスポーツ」を打ち出し、2024年の更新では「身体的・心理的に安全なスポーツ環境」と定義し、予防措置、教育啓発とケアを「セーフガーディング」として強化している。
來田教授は今回のディオッサのケースについて、こう語る。
「(選手の)国の文化や歴史を理解せず、指導者が発言すべきではない。(選手が守られる)スポーツ環境を適切でない状態にしたという意味では、十分に注意をされるべきだ」
スポーツの現場において成長に必要なことを考える中で、選手や指導者などで人権に関する規律規範の理解のずれが生じる場合がある。
來田教授は「現場は、関係者の価値観のずれを解消し、目標を同じように理解する過渡期にある。組織が人権ポリシーや倫理的な行動の指針などを作り、同じ価値観にもとづき、関係者が協力していく体制づくりが大切だ」と強調した。
(2025/09/22)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
関連商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -