解説記事2007年09月03日 【会計基準等解説】 実務対応報告第23号「信託の会計処理に関する実務上の取扱い」について(2007年9月3日号・№225)
実務対応報告第23号
「信託の会計処理に関する実務上の取扱い」について
企業会計基準委員会 専門研究員 吉田健太郎
はじめに
平成18年12月15日に公布された新信託法では、委託者が自ら受託者となる信託(いわゆる自己信託)などの新たな制度が導入された。新信託法では、信託は財産の管理又は処分の制度であるというこれまでの特徴を残しつつ、受託者の義務や受益者の権利行使に関する規定の整備や、信託の多様な利用形態に対応するための整備がなされている。これらに対応するため、企業会計基準委員会(以下「ASBJ」という)では、これまでの信託の基本的な会計処理を整理するとともに、新信託法による新たな類型の信託等について必要と考えられる会計処理を検討し、平成19年8月2日に実務対応報告第23号「信託の会計処理に関する実務上の取扱い」(脚注1)(以下、「本実務対応報告」という)を公表した。本稿では本実務対応報告の概要を紹介するが、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめお断りしておく。
Ⅰ.これまでの信託の基本的な会計処理の整理
1.会計基準と信託の分類 これまで信託に関する包括的な会計基準等はないものの、その会計処理は必要に応じて、いくつかの会計基準等において示されている(図表1参照)。
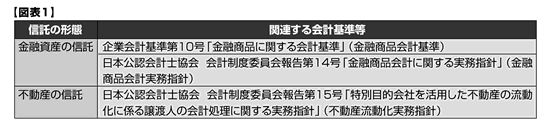
また、信託はこれまで、委託者が信託行為によって受託者に財産権の移転を行い、当該受託者が一定の目的(信託目的)に従って、受益者のためにその財産(信託財産)の管理又は処分の拘束を加えるところに成立する法律関係とされており、これは新信託法においても基本的に変わるところはない。
委託者が当初の受益者になる自益信託(脚注2)においては、実務上委託者が信託行為によって信託財産とする財産の種類により、「金銭の信託」と「金銭以外の信託」に分類されることが多い。さらに、これらはそれぞれ委託者兼当初受益者が「単数である場合」と「複数である場合」に分類されることが多い。このため本実務対応報告では、信託を4つに分類し、委託者及び受益者の基本的な会計処理を整理している(図表2参照)。
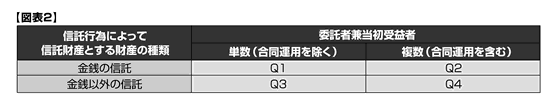
2.信託の委託者及び受益者の基本的な会計処理 (1)委託者兼当初受益者が単数である金銭の信託の場合(Q1) 委託者兼当初受益者は、信託設定時に信託財産となる金銭を金銭の信託であることを示す適切な科目に振り替える。また、当該信託は一般に運用を目的とするものと考えられているため、この場合の信託財産である金融資産及び金融負債については、金融商品会計基準及び金融商品会計実務指針により付すべき評価額を合計した額をもって貸借対照表価額とし、その評価差額は当期の損益として処理することとなる。
(2)委託者兼当初受益者が複数である金銭の信託の場合(Q2)
・基本的な会計処理 委託者兼当初受益者は、信託設定時に信託財産となる金銭を有価証券又は合同運用の金銭の信託であることを示す適切な科目に振り替える。
また、当該信託の受益者は有価証券として又は有価証券に準じて会計処理を行うこととなる。ただし、預金と同様の性格を有する合同運用の金銭の信託(投資信託を含む。)は金融商品実務指針に従い、取得原価をもって貸借対照表価額とするとされている。
・受益者が複数である金銭の信託と子会社及び関連会社の範囲についての考え方 これまで委託者兼当初受益者が複数である金銭の信託については、個別財務諸表上、受益者は信託財産を持分に応じて直接保有する会計処理を行わず、有価証券として又は有価証券に準じて会計処理を行っている。一方、このような金銭の信託については一般に多数の受益者を想定しているため、連結財務諸表上、子会社や関連会社に該当するかどうかを判定する必然性は乏しかったものと考えられる。
信託は財産管理の制度としての特徴も有しており、通常「会社に準ずる事業体」に該当するとは言えないが、受益者が複数である金銭の信託の中には、連結財務諸表上、財産管理のための仕組みとみるよりむしろ子会社及び関連会社とみる方が適切な会計処理ができる場合がある。また、新信託法においては、受益者集会の制度など受益者が2人以上ある信託における受益者の意思決定の方法が明示された。このため、受益者が複数である金銭の信託については、当該受益者の連結財務諸表上、子会社及び関連会社に該当する場合があり得ると考えられる。
・受益者が複数である金銭の信託が子会社及び関連会社と判定される場合 前記の考え方を踏まえ、本実務対応報告では、受益者が2人以上ある信託における次の受益者は、「連結財務諸表原則」及び「連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取扱い」(以下、「子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い」という)に従い、原則として当該信託を子会社として取り扱うことが適切であるとしている。
(a)すべての受益者の一致によって受益者の意思決定がされる信託(新信託法第105条第1項)においては、自己以外のすべての受益者が緊密な者又は同意している者であり、かつ子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い一3(2)の②から⑤までのいずれかの要件に該当する受益者
(b)信託行為に受益者集会における多数決による旨の定めがある信託(新信託法第105条第2項)においては、子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い一3で示す「他の会社等の議決権」を「信託における受益者の議決権」と読み替えて、子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い一3の会社に該当することとなる受益者
(c)信託行為に別段の定めがあり、その定めるところによって受益者の意思決定が行われる信託(新信託法第105条第1項ただし書き)では、その定めにより受益者の意思決定を行うことができることとなる受益者(なお、自己だけでは受益者の意思決定を行うことができないが、緊密な者又は同意している者とを合わせれば受益者の意思決定を行うことができることとなる場合には、子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い一3(2)の②から⑤までのいずれかの要件に該当する受益者)
また、子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い二2で示す「他の会社等の議決権」を「信託における受益者の議決権」と読み替えて、子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い二2の会社に該当することとなる受益者は、当該信託を関連会社として取り扱うこととなるとしている。
なお、当該信託の受益権が売買目的であって、金融商品会計基準や特別の法令の定めに適切に従った結果、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額を当期の損益として処理することとなる場合には、事業投資である子会社や関連会社への投資には該当しないことに留意する必要がある。
(3)委託者兼当初受益者が単数である金銭以外の信託の場合(Q3)
・信託設定時の会計処理 金融資産(金銭債権や有価証券など)の信託や不動産の信託など、委託者兼当初受益者が単数である金銭以外の信託において、受益者は信託財産を直接保有する場合と同様の会計処理を行うものとされているため、信託設定時に委託者兼当初受益者において損益は計上されない。
・委託者兼当初受益者による受益権の売却時の会計処理 前記のように受益者は、信託財産を直接保有する場合と同様の会計処理を行うことから、受益権が売却された場合、信託財産を直接保有していたものとみて消滅の認識(又は売却処理)の要否を判断することとなる。
・委託者兼当初受益者による期末時の会計処理 金銭以外の信託の受益者は、信託財産を直接保有する場合と同様に会計処理することとなるため、原則として、総額法(信託財産のうち持分割合に相当する部分を受益者の貸借対照表における資産及び負債として計上し、損益計算書についても同様に持分割合に応じて処理する方法)によることとなる。
ただし次の場合には、各受益者が当該信託財産を直接保有するものとみなして会計処理を行うことは困難であることから、受益者の個別財務諸表上、受益権を当該信託に対する有価証券とみなして評価する。また、この場合には、連結財務諸表上当該信託を子会社又は関連会社として取り扱うかどうかについては、本実務対応報告のQ2のA3に準じることとなる(脚注3)。
(a)受益権が優先劣後等のように質的に異なるものに分割されており、かつ譲渡等により受益者が複数となる場合
(b)受益権の譲渡等により受益者が多数(多数になると想定されるものも含む。)となる場合
・他から受益権を譲り受けた受益者の会計処理 原則として、他から受益権を譲り受けた場合についても受益者は、信託財産を直接保有する場合と同様の会計処理を行う。ただし、当該信託に係る受益権が質的に異なるものに分割されている場合や受益者が多数となる場合、各受益者は信託財産を直接保有するものとみなして会計処理を行うことは困難であることから、受益権を当該信託に対する有価証券とみなして処理することとなる。
(4)委託者兼当初受益者が複数である金銭以外の信託の場合(Q4)
・信託設定時の会計処理 この場合も他の信託の設定時と同様に、原則として当該信託の設定により損益は生じない。ただし当該信託の設定は、共同で現物出資により会社を設立することに類似するものであるため、現物出資による会社の設立における移転元の企業の会計処理に準じて、当該委託者兼当初受益者が当該信託に対して支配することも重要な影響を及ぼすこともない場合には、その個別財務諸表上、原則として移転損益を認識することが適当と考えられるとされている。
・受益権の売却時及び期末時の会計処理 例えば、各委託者兼当初受益者が共有していた財産を信託し、その財産に対応する受益権を受け取る場合のように、委託者兼当初受益者が複数であってもそれぞれにおける経済的効果が信託前と実質的に異ならない場合には、信託財産から生ずる経済的効果を受益者に直接的に帰属するように会計処理することが可能である。このため当該受益権の売却時には、受益者が信託財産を直接保有するものとみて消滅の認識(又は売却処理)の要否を判断することとなり、また、期末時には原則として総額法によることとなる。
それ以外の場合には、各受益者が当該信託財産を直接保有するものとみなして会計処理を行うことは困難であることから、受益者の個別財務諸表上、受益権を信託に対する有価証券の保有とみなして評価し、売却する場合には有価証券の売却とみなして売却処理の要否を判断することとなる。また、連結財務諸表上当該信託を子会社又は関連会社として取り扱うかどうかについては、本実務対応報告のQ2のA3に準じることとなる。
Ⅱ.新信託法による新たな類型の信託における委託者及び受益者の会計処理
1.新信託法による新たな類型の信託 本実務対応報告では、これまでの信託の基本的な会計処理を踏まえて、新信託法による新たな類型の信託について必要と考えられる会計処理を示している。(図表3参照)。
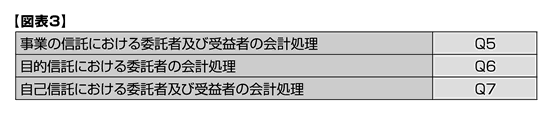
新信託法においては、信託行為において信託契約や遺言による方法に加えていわゆる信託宣言が定められ、委託者が自ら受託者となる信託(自己信託)が可能となった。このような設定方法の多様化のほか、要件又は効果の多様化のための新形態が認められている。新信託法では委託者の債務を当初から引き受け可能であることが明示されたため、積極財産と消極財産から構成される事業自体の信託(事業の信託)を行うのと同様の状態を作り出すことが可能になる。また、公益信託以外にも受益者の定めのない信託(目的信託)が認められた。さらに新信託法では、受託者が信託に関して負担する債務について信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う限定責任信託や、受益権が私法上の有価証券とされる受益証券を発行する受益証券発行信託を設けている。
2.事業の信託における委託者及び受益者の会計処理(Q5) 新信託法では、信託行為の定めがあり、信託前に生じた委託者に対する債権に係る債務の引受けがされたときには、その債務が信託財産責任負担債務の範囲に含まれることが明示され、金銭その他の財産の信託と同時に負債の引受けを組み合わせることにより、これらから構成される事業自体の信託(事業の信託)を行うのと同様の状態を作り出すことができると言われている。その会計処理については、基本的にこれまでの信託と相違はないと考えられる。
このような事業の信託は金銭以外の信託にあたるため、本実務対応報告では、委託者兼当初受益者が単数である場合Q3のAに準じて処理し、委託者兼当初受益者が複数である場合にはQ4のAに準じて処理することとなるとされている。
なお、事業の信託に関連して、本実務対応報告では、金銭の信託において事業を譲り受ける場合であっても事業の信託が設定された場合と整合的になるように、個別財務諸表上、いわゆる総額法によることが適当と考えられるとされている。また、事業の信託であるかどうかにかかわらず、受益者が信託財産を直接保有する場合と同様の会計処理を行うときには、当該受益者と当該信託との取引は内部取引として消去される。
3.受益者の定めのない信託(目的信託)における委託者の会計処理(Q6) これまで、公益信託を除き受益者の定めのない信託は認められていなかったが、新信託法では、信託契約による方法又は遺言による方法によって受益者の定めのない信託(目的信託)をすることができるものとされた。目的信託は、委託者がいつでも信託を終了できるなど通常の信託とは異なるため、原則として委託者の財産として処理することが適当と考えられるが、信託契約の内容等からみて委託者に信託財産の経済的効果が帰属しないことが明らかであると認められる場合には、もはや委託者の財産ではないものとして処理するとされている。
4.自己信託における委託者及び受益者の会計処理(Q7) 新信託法においては、委託者が自ら信託財産の管理等をすべき旨の意思表示を書面等によってする方法による自己信託が定められた。自己信託は、委託者が受託者となるという点に特徴があるが、その会計処理は基本的には他者に信託した通常の信託と相違はないと考えられる。したがって本実務対応報告では、自己信託が自益信託として行われる場合には、委託者兼受託者である自らのみが当初受益者となるため、金銭の信託のときにはQ1のAに準じて、金銭以外の信託のときにはQ3のAに準じて会計処理を行うものとされている。
なお本実務対応報告では、追加情報として自己信託の信託財産および受益権の注記を行うことが適当であるとされている。
Ⅲ.受託者の会計処理(Q8)
新信託法において、信託の会計は一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとするとされており、今後もこれまでと同様に、明らかに不合理であると認められる場合を除き、信託行為の定め等に基づいて行うことが考えられるが、新信託法に基づく限定責任信託や受益者が多数となる信託の会計処理は原則として、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準じて行うこととなる。
Ⅳ.適用時期等
本実務対応報告は原則として、新信託法の施行日(脚注4)以後にその効力が生じた信託及びそれより前に効力が生じた信託が信託の変更により新信託法の規定を受ける信託(信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条)について適用することが想定されている。
(よしだ・けんたろう)
脚注
1 本実務対応報告の全文については、ASBJのホームページを参照のこと。なお、ASBJは、平成19年3月29日に実務対応報告公開草案第26号「信託の会計処理に関する実務上の取扱い(案)」を公表し、平成19年5月7日まで広くコメントの募集を行った後、寄せられたコメントを検討し公開草案の修正を行った上で、本実務対応報告を公表している。
2 本実務対応報告においては、自益信託を前提としており、受益者の金銭拠出を伴う場合を除き、委託者以外の第三者が当初受益者となる他益信託は対象としていないとしている。
3 なお、当該信託が、子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い三で示す特別目的会社にあたることから子会社には該当しないものと推定されている場合には、企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」に基づき、開示対象特別目的会社の開示が必要となる。
4 新信託法は、平成19年8月3日に公布された「信託法の施行期日を定める政令」(政令第231号)により平成19年9月30日から施行され、自己信託については、新信託法の施行日から起算して1年を経過する日までの間は適用しない(信託法附則第2項)とされている。
「信託の会計処理に関する実務上の取扱い」について
企業会計基準委員会 専門研究員 吉田健太郎
はじめに
平成18年12月15日に公布された新信託法では、委託者が自ら受託者となる信託(いわゆる自己信託)などの新たな制度が導入された。新信託法では、信託は財産の管理又は処分の制度であるというこれまでの特徴を残しつつ、受託者の義務や受益者の権利行使に関する規定の整備や、信託の多様な利用形態に対応するための整備がなされている。これらに対応するため、企業会計基準委員会(以下「ASBJ」という)では、これまでの信託の基本的な会計処理を整理するとともに、新信託法による新たな類型の信託等について必要と考えられる会計処理を検討し、平成19年8月2日に実務対応報告第23号「信託の会計処理に関する実務上の取扱い」(脚注1)(以下、「本実務対応報告」という)を公表した。本稿では本実務対応報告の概要を紹介するが、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめお断りしておく。
Ⅰ.これまでの信託の基本的な会計処理の整理
1.会計基準と信託の分類 これまで信託に関する包括的な会計基準等はないものの、その会計処理は必要に応じて、いくつかの会計基準等において示されている(図表1参照)。
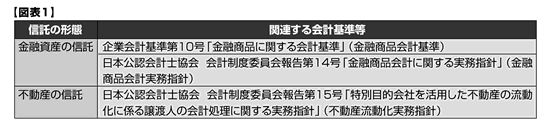
また、信託はこれまで、委託者が信託行為によって受託者に財産権の移転を行い、当該受託者が一定の目的(信託目的)に従って、受益者のためにその財産(信託財産)の管理又は処分の拘束を加えるところに成立する法律関係とされており、これは新信託法においても基本的に変わるところはない。
委託者が当初の受益者になる自益信託(脚注2)においては、実務上委託者が信託行為によって信託財産とする財産の種類により、「金銭の信託」と「金銭以外の信託」に分類されることが多い。さらに、これらはそれぞれ委託者兼当初受益者が「単数である場合」と「複数である場合」に分類されることが多い。このため本実務対応報告では、信託を4つに分類し、委託者及び受益者の基本的な会計処理を整理している(図表2参照)。
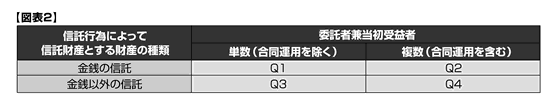
2.信託の委託者及び受益者の基本的な会計処理 (1)委託者兼当初受益者が単数である金銭の信託の場合(Q1) 委託者兼当初受益者は、信託設定時に信託財産となる金銭を金銭の信託であることを示す適切な科目に振り替える。また、当該信託は一般に運用を目的とするものと考えられているため、この場合の信託財産である金融資産及び金融負債については、金融商品会計基準及び金融商品会計実務指針により付すべき評価額を合計した額をもって貸借対照表価額とし、その評価差額は当期の損益として処理することとなる。
(2)委託者兼当初受益者が複数である金銭の信託の場合(Q2)
・基本的な会計処理 委託者兼当初受益者は、信託設定時に信託財産となる金銭を有価証券又は合同運用の金銭の信託であることを示す適切な科目に振り替える。
また、当該信託の受益者は有価証券として又は有価証券に準じて会計処理を行うこととなる。ただし、預金と同様の性格を有する合同運用の金銭の信託(投資信託を含む。)は金融商品実務指針に従い、取得原価をもって貸借対照表価額とするとされている。
・受益者が複数である金銭の信託と子会社及び関連会社の範囲についての考え方 これまで委託者兼当初受益者が複数である金銭の信託については、個別財務諸表上、受益者は信託財産を持分に応じて直接保有する会計処理を行わず、有価証券として又は有価証券に準じて会計処理を行っている。一方、このような金銭の信託については一般に多数の受益者を想定しているため、連結財務諸表上、子会社や関連会社に該当するかどうかを判定する必然性は乏しかったものと考えられる。
信託は財産管理の制度としての特徴も有しており、通常「会社に準ずる事業体」に該当するとは言えないが、受益者が複数である金銭の信託の中には、連結財務諸表上、財産管理のための仕組みとみるよりむしろ子会社及び関連会社とみる方が適切な会計処理ができる場合がある。また、新信託法においては、受益者集会の制度など受益者が2人以上ある信託における受益者の意思決定の方法が明示された。このため、受益者が複数である金銭の信託については、当該受益者の連結財務諸表上、子会社及び関連会社に該当する場合があり得ると考えられる。
・受益者が複数である金銭の信託が子会社及び関連会社と判定される場合 前記の考え方を踏まえ、本実務対応報告では、受益者が2人以上ある信託における次の受益者は、「連結財務諸表原則」及び「連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取扱い」(以下、「子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い」という)に従い、原則として当該信託を子会社として取り扱うことが適切であるとしている。
(a)すべての受益者の一致によって受益者の意思決定がされる信託(新信託法第105条第1項)においては、自己以外のすべての受益者が緊密な者又は同意している者であり、かつ子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い一3(2)の②から⑤までのいずれかの要件に該当する受益者
(b)信託行為に受益者集会における多数決による旨の定めがある信託(新信託法第105条第2項)においては、子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い一3で示す「他の会社等の議決権」を「信託における受益者の議決権」と読み替えて、子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い一3の会社に該当することとなる受益者
(c)信託行為に別段の定めがあり、その定めるところによって受益者の意思決定が行われる信託(新信託法第105条第1項ただし書き)では、その定めにより受益者の意思決定を行うことができることとなる受益者(なお、自己だけでは受益者の意思決定を行うことができないが、緊密な者又は同意している者とを合わせれば受益者の意思決定を行うことができることとなる場合には、子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い一3(2)の②から⑤までのいずれかの要件に該当する受益者)
また、子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い二2で示す「他の会社等の議決権」を「信託における受益者の議決権」と読み替えて、子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い二2の会社に該当することとなる受益者は、当該信託を関連会社として取り扱うこととなるとしている。
なお、当該信託の受益権が売買目的であって、金融商品会計基準や特別の法令の定めに適切に従った結果、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額を当期の損益として処理することとなる場合には、事業投資である子会社や関連会社への投資には該当しないことに留意する必要がある。
(3)委託者兼当初受益者が単数である金銭以外の信託の場合(Q3)
・信託設定時の会計処理 金融資産(金銭債権や有価証券など)の信託や不動産の信託など、委託者兼当初受益者が単数である金銭以外の信託において、受益者は信託財産を直接保有する場合と同様の会計処理を行うものとされているため、信託設定時に委託者兼当初受益者において損益は計上されない。
・委託者兼当初受益者による受益権の売却時の会計処理 前記のように受益者は、信託財産を直接保有する場合と同様の会計処理を行うことから、受益権が売却された場合、信託財産を直接保有していたものとみて消滅の認識(又は売却処理)の要否を判断することとなる。
・委託者兼当初受益者による期末時の会計処理 金銭以外の信託の受益者は、信託財産を直接保有する場合と同様に会計処理することとなるため、原則として、総額法(信託財産のうち持分割合に相当する部分を受益者の貸借対照表における資産及び負債として計上し、損益計算書についても同様に持分割合に応じて処理する方法)によることとなる。
ただし次の場合には、各受益者が当該信託財産を直接保有するものとみなして会計処理を行うことは困難であることから、受益者の個別財務諸表上、受益権を当該信託に対する有価証券とみなして評価する。また、この場合には、連結財務諸表上当該信託を子会社又は関連会社として取り扱うかどうかについては、本実務対応報告のQ2のA3に準じることとなる(脚注3)。
(a)受益権が優先劣後等のように質的に異なるものに分割されており、かつ譲渡等により受益者が複数となる場合
(b)受益権の譲渡等により受益者が多数(多数になると想定されるものも含む。)となる場合
・他から受益権を譲り受けた受益者の会計処理 原則として、他から受益権を譲り受けた場合についても受益者は、信託財産を直接保有する場合と同様の会計処理を行う。ただし、当該信託に係る受益権が質的に異なるものに分割されている場合や受益者が多数となる場合、各受益者は信託財産を直接保有するものとみなして会計処理を行うことは困難であることから、受益権を当該信託に対する有価証券とみなして処理することとなる。
(4)委託者兼当初受益者が複数である金銭以外の信託の場合(Q4)
・信託設定時の会計処理 この場合も他の信託の設定時と同様に、原則として当該信託の設定により損益は生じない。ただし当該信託の設定は、共同で現物出資により会社を設立することに類似するものであるため、現物出資による会社の設立における移転元の企業の会計処理に準じて、当該委託者兼当初受益者が当該信託に対して支配することも重要な影響を及ぼすこともない場合には、その個別財務諸表上、原則として移転損益を認識することが適当と考えられるとされている。
・受益権の売却時及び期末時の会計処理 例えば、各委託者兼当初受益者が共有していた財産を信託し、その財産に対応する受益権を受け取る場合のように、委託者兼当初受益者が複数であってもそれぞれにおける経済的効果が信託前と実質的に異ならない場合には、信託財産から生ずる経済的効果を受益者に直接的に帰属するように会計処理することが可能である。このため当該受益権の売却時には、受益者が信託財産を直接保有するものとみて消滅の認識(又は売却処理)の要否を判断することとなり、また、期末時には原則として総額法によることとなる。
それ以外の場合には、各受益者が当該信託財産を直接保有するものとみなして会計処理を行うことは困難であることから、受益者の個別財務諸表上、受益権を信託に対する有価証券の保有とみなして評価し、売却する場合には有価証券の売却とみなして売却処理の要否を判断することとなる。また、連結財務諸表上当該信託を子会社又は関連会社として取り扱うかどうかについては、本実務対応報告のQ2のA3に準じることとなる。
Ⅱ.新信託法による新たな類型の信託における委託者及び受益者の会計処理
1.新信託法による新たな類型の信託 本実務対応報告では、これまでの信託の基本的な会計処理を踏まえて、新信託法による新たな類型の信託について必要と考えられる会計処理を示している。(図表3参照)。
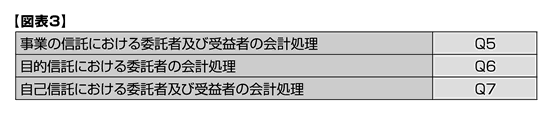
新信託法においては、信託行為において信託契約や遺言による方法に加えていわゆる信託宣言が定められ、委託者が自ら受託者となる信託(自己信託)が可能となった。このような設定方法の多様化のほか、要件又は効果の多様化のための新形態が認められている。新信託法では委託者の債務を当初から引き受け可能であることが明示されたため、積極財産と消極財産から構成される事業自体の信託(事業の信託)を行うのと同様の状態を作り出すことが可能になる。また、公益信託以外にも受益者の定めのない信託(目的信託)が認められた。さらに新信託法では、受託者が信託に関して負担する債務について信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う限定責任信託や、受益権が私法上の有価証券とされる受益証券を発行する受益証券発行信託を設けている。
2.事業の信託における委託者及び受益者の会計処理(Q5) 新信託法では、信託行為の定めがあり、信託前に生じた委託者に対する債権に係る債務の引受けがされたときには、その債務が信託財産責任負担債務の範囲に含まれることが明示され、金銭その他の財産の信託と同時に負債の引受けを組み合わせることにより、これらから構成される事業自体の信託(事業の信託)を行うのと同様の状態を作り出すことができると言われている。その会計処理については、基本的にこれまでの信託と相違はないと考えられる。
このような事業の信託は金銭以外の信託にあたるため、本実務対応報告では、委託者兼当初受益者が単数である場合Q3のAに準じて処理し、委託者兼当初受益者が複数である場合にはQ4のAに準じて処理することとなるとされている。
なお、事業の信託に関連して、本実務対応報告では、金銭の信託において事業を譲り受ける場合であっても事業の信託が設定された場合と整合的になるように、個別財務諸表上、いわゆる総額法によることが適当と考えられるとされている。また、事業の信託であるかどうかにかかわらず、受益者が信託財産を直接保有する場合と同様の会計処理を行うときには、当該受益者と当該信託との取引は内部取引として消去される。
3.受益者の定めのない信託(目的信託)における委託者の会計処理(Q6) これまで、公益信託を除き受益者の定めのない信託は認められていなかったが、新信託法では、信託契約による方法又は遺言による方法によって受益者の定めのない信託(目的信託)をすることができるものとされた。目的信託は、委託者がいつでも信託を終了できるなど通常の信託とは異なるため、原則として委託者の財産として処理することが適当と考えられるが、信託契約の内容等からみて委託者に信託財産の経済的効果が帰属しないことが明らかであると認められる場合には、もはや委託者の財産ではないものとして処理するとされている。
4.自己信託における委託者及び受益者の会計処理(Q7) 新信託法においては、委託者が自ら信託財産の管理等をすべき旨の意思表示を書面等によってする方法による自己信託が定められた。自己信託は、委託者が受託者となるという点に特徴があるが、その会計処理は基本的には他者に信託した通常の信託と相違はないと考えられる。したがって本実務対応報告では、自己信託が自益信託として行われる場合には、委託者兼受託者である自らのみが当初受益者となるため、金銭の信託のときにはQ1のAに準じて、金銭以外の信託のときにはQ3のAに準じて会計処理を行うものとされている。
なお本実務対応報告では、追加情報として自己信託の信託財産および受益権の注記を行うことが適当であるとされている。
Ⅲ.受託者の会計処理(Q8)
新信託法において、信託の会計は一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとするとされており、今後もこれまでと同様に、明らかに不合理であると認められる場合を除き、信託行為の定め等に基づいて行うことが考えられるが、新信託法に基づく限定責任信託や受益者が多数となる信託の会計処理は原則として、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準じて行うこととなる。
Ⅳ.適用時期等
本実務対応報告は原則として、新信託法の施行日(脚注4)以後にその効力が生じた信託及びそれより前に効力が生じた信託が信託の変更により新信託法の規定を受ける信託(信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条)について適用することが想定されている。
(よしだ・けんたろう)
脚注
1 本実務対応報告の全文については、ASBJのホームページを参照のこと。なお、ASBJは、平成19年3月29日に実務対応報告公開草案第26号「信託の会計処理に関する実務上の取扱い(案)」を公表し、平成19年5月7日まで広くコメントの募集を行った後、寄せられたコメントを検討し公開草案の修正を行った上で、本実務対応報告を公表している。
2 本実務対応報告においては、自益信託を前提としており、受益者の金銭拠出を伴う場合を除き、委託者以外の第三者が当初受益者となる他益信託は対象としていないとしている。
3 なお、当該信託が、子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い三で示す特別目的会社にあたることから子会社には該当しないものと推定されている場合には、企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」に基づき、開示対象特別目的会社の開示が必要となる。
4 新信託法は、平成19年8月3日に公布された「信託法の施行期日を定める政令」(政令第231号)により平成19年9月30日から施行され、自己信託については、新信託法の施行日から起算して1年を経過する日までの間は適用しない(信託法附則第2項)とされている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























