解説記事2012年05月14日 【新会計基準解説】 「中小企業の会計に関する基本要領」について(2012年5月14日号・№450)
新会計基準解説
「中小企業の会計に関する基本要領」について
中小企業庁事業環境部財務課 吉田政弘
平成24年3月27日、「中小企業の会計に関する検討会(以下、「検討会」という。)」から最終報告書が公表され、1年1ヶ月強に渡って検討された、中小企業の実態に即した新たな中小企業の会計処理のあり方を示すものである「中小企業の会計に関する基本要領」(以下、「中小会計要領」又は「本要領」という。)の策定及び普及・活用策の検討について一定の区切りを迎えた。
「中小会計要領」の策定主体である「検討会」において、中小企業庁と金融庁が共同事務局として参画しているが、本稿は事務局のうちの中小企業庁としての観点から「中小会計要領」策定の背景、概要、今後の普及・活用策について概説するものであり、また、本稿中意見にわたる部分は、筆者の個人的見解であることをあらかじめお断りしておく。
Ⅰ「中小会計要領」の策定の背景
近年、経済のグローバル化が進展したことにより、財務諸表の国際的な比較可能性を向上させる必要性が指摘され、様々な国において、自国の会計基準を「国際会計基準審議会(IASB)」が設定する「国際財務報告基準(IFRS)」に収斂(コンバージェンス)させる、若しくはIFRSを適用(アドプション)する動きや、IFRS適用のあり方についての議論が展開されている。
我が国においても平成17年からIASBと企業会計基準委員会(ASBJ)との間でコンバージェンス・プロジェクトが実施されており、現在でも金融庁の企業会計審議会においてIFRS適用のあり方について検討されているところである。
世界的にIFRSへのコンバージェンスが議論される一方で、必ずしも国際競争に晒されていない自国内の非上場企業の会計基準についても様々な国で議論が行われている。
我が国にも419万社の企業が存在しており、内99%以上が中小企業である。中小企業は雇用及び製造業における付加価値額の大部分を担っており、我が国及び地域経済の基盤をなす重要な存在である。
これまで、中小企業に適用される会計基準(又はルール)については、その一つとして「中小企業の会計に関する指針」(以下、「中小指針」という。)が設定されていた。中小指針は平成14年6月に中小企業庁が公表した「中小企業の会計に関する研究会報告書」、平成14年12月に日本税理士会連合会が公表した「中小会社会計基準」、及び平成15年6月に日本公認会計士協会が公表した「中小会社のあり方に関する研究報告」を統合し、平成17年8月に、主として会計参与が置かれた企業を念頭に中小企業が会社法上の計算書類を作成する際の会計処理を示したものとして、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の4団体が作成主体となり、金融庁、法務省、中小企業庁がオブザーバーとして参画する形で作成されたものである。
中小指針は、中小企業の実態及びコストベネフィットを考慮し、上場企業等の金融商品取引法適用会社が適用する企業会計基準を簡素化して作成されているものである。しかし「企業の規模に関係なく、取引の経済実態が同じなら会計処理も同じになるべき」とする考え方が採用されていることから、上場企業等に適用される企業会計基準においてIFRSへのコンバージェンスが行われる度に、中小指針についても累次の改訂がなされており、中小企業は間接的にIFRSへのコンバージェンスの影響を受けている状況であった。
その後、我が国に会計基準の国際化の動きがある一方で、中小企業への影響を回避又は最小限に留める必要があるとの意見を踏まえ、平成22年2月に中小企業庁において「中小企業の会計に関する研究会」(以下、「研究会」という。)、同年3月に企業会計基準委員会等の民間団体により「非上場会社の会計基準に関する懇談会」(以下、「懇談会」という。)が設置され、それぞれ非上場企業、特にその大部分を占める中小企業の会計の実態、特性、慣行等から中小企業の今後の会計基準の在り方に至るまで検討が行われた。結果的に、平成22年8月に懇談会、同年9月に研究会の報告書が取りまとめられ、両報告書において、中小企業の会計基準として新たに中小企業の会計処理のあり方を示すものを取りまとめるべきである等の方向性が示された。
今般中小会計要領を策定した「検討会」は、これらの両報告書に示された方向性を受け、平成23年2月に設置され、検討が重ねられてきたものである。
Ⅱ 中小会計要領の概要
中小会計要領の取りまとめにおいては、「研究会」及び「懇談会」の両報告書の内容を踏まえ、中小企業の実態に配慮するという視点で議論が重ねられてきた。中小企業は、多種多様な業種・業態の事業活動を行っており、その規模や経済取引等の実態は個々の企業で異なり、大企業と比べて生産性、収益性等のばらつきが大きいなど、総じて、大企業とは異なる属性を有している。特に中小企業の会計のあり方を検討するにあたって考慮すべきと考えられる、多くの中小企業が該当する属性は、以下の通りである。
① 資金調達の方法として、新株発行や起債といったように資本市場で資金調達を行うことはほとんどなく地域金融機関やメガバンクなどの金融機関からの借り入れが中心。
② 中小企業では、所有と経営が一致しており、いわゆる同族会社に該当する場合がほとんどである。また、通常、株式には譲渡制限が付されており、株式が第三者に自由に流通することは想定されていない。利害関係者は限られており、計算書類等の開示先は、主として、取引金融機関、主要取引先、既存株主等に限られる(図表1参照)。
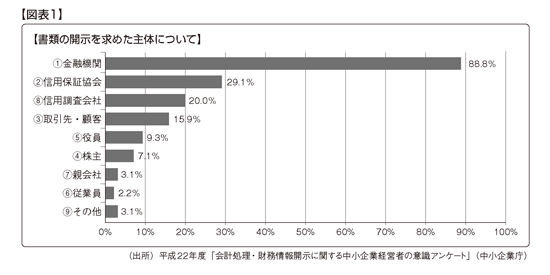 ③ 多くの中小企業では、税務申告が計算書類等作成の目的の大きな割合を占め、法人税法で定める処理を意識した会計が行われている。
③ 多くの中小企業では、税務申告が計算書類等作成の目的の大きな割合を占め、法人税法で定める処理を意識した会計が行われている。
④ 経理担当者の人数が少なく、高度な会計処理に対応できる十分な能力や経理体制を持ち合わせていない(図表2参照)。
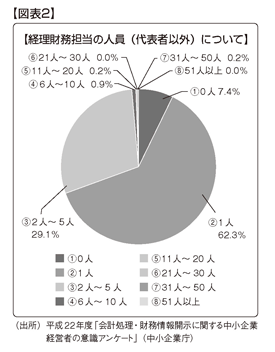
これらの実態に可能な限り配慮した新たな会計処理のあり方を取りまとめ、かつ取りまとめられたものについて幅広く中小企業の自発的な利活用を促す必要があることから、中小会計要領は検討メンバーや検討のアプローチ等にも配慮され、検討が行われてきた。
まず、中小企業関係者の総意として取りまとめられるという手続きを可能な限り担保する観点から、中小会計要領の策定主体である「検討会」及び実務的な検討を行った「中小企業の会計に関する検討会ワーキンググループ」(以下、「WG」という。)のメンバーは中小企業関係者が主体となって構成されている。具体的には、中小企業会計のユーザーである中小企業自身や中小企業団体、中小企業の会計実務を熟知する税理士や公認会計士等の会計専門家及びその団体、多くの中小企業にとって主な利害関係者である金融機関、専門的な見地を有する企業会計基準設定団体や学識経験者といった中小企業の関係者が中心となっており、関係官庁は事務局(中小企業庁、金融庁)、オブザーバー(法務省)として参加する体制となっている。
また、検討のアプローチも、上場企業等が準拠する企業会計基準をベースに、それを簡素化するアプローチ(トップダウン・アプローチ)ではなく、対象とする中小企業の属性を勘案し、取得原価主義や企業会計原則等を踏まえつつ、中小企業が実務で行っている会計慣行を積み上げ方式で策定するアプローチ(ボトムアップ・アプローチ)が採用された。
このように検討し策定された中小会計要領は総論、各論、様式集で構成されており、それぞれについて検討の過程における議論を踏まえつつ、概観していきたい。
1 総 論 総論の項目建ては以下の通りである。
1.目的
2.本要領の利用が想定される会社
3.企業会計基準、中小指針の利用
4.複数ある会計処理の取扱い
5.各論で示していない会計処理等の取扱い
6.国際会計基準との関係
7.本要領の改訂
8.記帳の重要性
9.本要領の利用上の留意事項
「1.目的」においては、中小会計要領が、中小企業の多様な実態に配慮し、その成長に資するために策定されたものであることが明示されており、以下の考えに立って作成されたものであることを示している。
・中小企業の経営者が活用しようと思えるよう、理解しやすく、自社の経営状況の把握に役立つ会計
・中小企業の利害関係者(金融機関、取引先、株主等)への情報提供に資する会計
・中小企業の実務における会計慣行を十分考慮し、会計と税制の調和を図った上で、会社計算規則に準拠した会計
・計算書類等の作成負担は最小限に留め、中小企業に過重な負担を課さない会計
これらの考え方は後述の各論の検討においても常に根底にある考え方として持ち出され、これに沿った形で結論が導かれていたと考えられる。後の各論を概観する際に紹介させていただきたい。
「2.本要領の利用が想定される会社」では、中小会計要領の想定対象として、金融商品取引法の規制の適用対象会社と会社法上の会計監査人設置会社を除く株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社又は合同会社と記載されている。ここまでの記載は平成17年に策定された中小指針の適用対象の記載と同様であるが、中小会計要領では、中小指針での記載を引用した形で「(注)中小指針では、「とりわけ、会計参与設置会社が計算書類を作成する際には、本指針に拠ることが適当である。」とされている。」という注書きが設けられている。検討の過程において、中小会計要領と中小指針の想定対象について、一定の区分を設けるべきという意見があったが、結論として、中小企業は中小会計要領でも、中小指針でも、どちらでも参照することが可能であり(図表3参照)、中小企業が自社の実態に応じて中小会計要領や中小指針を適用し、計算書類の信頼性を向上させ、会計の活用を通じて経営力の強化が図られることが期待されている。
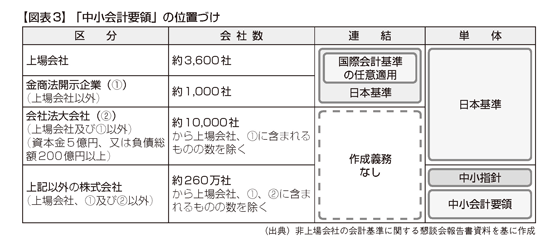
「6.国際会計基準との関係」、「7.本要領の改訂」は、中小会計要領を安定的に継続利用可能なものとする観点から設けられている項目であり、国際会計基準の影響を受けないものとし、また、改訂は中小企業の会計慣行の状況等を勘案し、必要と判断される場合にのみ行うこととされている。これは中小企業に過剰な負担を課さないという考え方から必要な項目と考えられる。
その他、総論において注目すべき点は、企業会計原則の一般原則のうち、「継続性の原則」及び「正規の簿記の原則」の趣旨について特に重視した内容となっていることである。「重要性の原則」と並べて上記以外の他の一般原則については「9.本要領の利用上の留意事項」に列挙されているが、「継続性の原則」の趣旨は「4.複数ある会計処理方法の取扱い」の部分に、「正規の簿記の原則」の趣旨は「8.記帳の重要性」の部分に特出された形で言及されている。これはこの2つの原則が、自社の経営状況を把握する観点からも、利害関係者への情報提供に資する観点からも、中小企業にとって特に重要と考えられるという考えから構成が検討されたものであり、中小企業の属性を勘案して検討された中小会計要領の特徴の一つと言える。
2 各 論 各論の項目建ては以下の通りである。
1.収益、費用の基本的な会計処理
2.資産、負債の基本的な会計処理
3.金銭債権及び金銭債務
4.貸倒損失、貸倒引当金
5.有価証券
6.棚卸資産
7.経過勘定
8.固定資産
9.繰延資産
10.リース取引
11.引当金
12.外貨建取引等
13.純資産
14.注記
各論については、中小会計要領の特徴をより分かりやすく説明する観点から、総論「1.目的」に挙げられている中小会計要領の作成における4つの考え方に沿って概観していきたい。
(1)中小企業の経営者が自社の経営状況を把握し活用できる会計 「1.収益、費用の基本的な会計処理」、「2.資産、負債の基本的な会計処理」の項目では、会計の基本的な原則を分かりやすく解説し、会計の基本的な知識習得が可能な内容となっている。収益の「実現主義」、費用の「発生主義」、費用収益対応の原則、総額主義の原則、「取得原価主義」等の基本的な考え方に言及しており、また、会計用語としての「取得価額」と「取得原価」の違い等も解説されている。
(2)利害関係者への情報提供に資する会計 「3.金銭債権及び金銭債務」の項目では、計算書類を見ただけでは必ずしも把握できない、受取手形割引額及び受取手形裏書譲渡額について必ず注記することとされている。これらの情報は金融機関が企業の受取債権に係る経営指標について分析する際や不渡り手形の買い戻しリスクの評価等を行う上で必要な情報であり、利害関係者側から注記を求める声が多かったことから必ず注記することとされたものである。これにより中小企業と利害関係者である金融機関との信頼関係の構築が図られることが期待されている。
また、「8.固定資産」における減価償却や「11.引当金」の計上については、会計上適切に費用処理すべきとされている項目であるが、税制における損金算入の考え方と異なる部分があり、中小企業会計の実務においてよく問題となる項目である。しかし、中小会計要領は信頼性の高い計算書類を作成し、利害関係者への情報提供に資する観点から、中小企業の実務慣行への配慮を示しつつ、会計上の適切な費用処理(減価償却)や負債計上(賞与引当金、退職給付引当金)等の処理を求めている。
(3)中小企業の実務会計慣行を十分考慮し、可能な限り税制との調和を図った実行しやすい会計 「4.貸倒引当金、貸倒損失」の項目では、回収不能のおそれのある債権以外の一般債権についての貸倒引当金額の見積もり方法として、法人税法上の中小企業に認められている法定繰入率が利用できることが明確化されている。
また、「5.有価証券」の項目においては、有価証券の分類を法人税法上の分類と同様に「売買目的有価証券」と「売買目的以外の有価証券」の二分類とし、売買目的以外の有価証券については取得原価で計上し、著しく価値が下落した場合を除いて保有途中での時価評価を必ずしも求めていない。
さらに、「6.棚卸資産」の項目においては、中小企業が法人税法上認められている「最終仕入原価法」で棚卸資産を評価していることが多い実態を踏まえ、上場企業等の企業会計基準では重要性のないものを除いて認められていない「最終仕入原価法」について、中小会計要領では他の棚卸資産の評価方法とともに中小企業が利用できることを明確にしている。
このように、法人税法上の処理や考え方に可能な限り配慮し、中小企業にとって実行しやすい会計となっている。
(4)中小企業に過剰な負担を課さない会計 中小会計要領は、全体的に、原則として取得原価主義によって資産計上し、明らかに価値の下落が判断できるものについてだけ時価評価を求め評価損の計上を求めるという考え方を取っている。また、中小企業の会計の実態として、利用が多くないと考えられる「税効果会計」や「組織再編の会計」等の項目については規定しておらず、基本的な14項目の会計に限定している。
3 様式集 様式集については、会社計算規則により作成が求められている貸借対照表、損益計算書等について、多くの中小企業の実務において実際に使用され、必要と考えられる項目を検討し、中小企業にとって利用可能なものとなるように配慮がなされている。
Ⅲ 中小会計要領の普及・活用策
これまで見てきた通り、中小会計要領は中小企業の実態に配慮し、実行しやすい会計処理を示している。しかし、中小会計要領はあくまでも会計処理のあり方を示すものであり、これが策定されたからといって、自動的に中小企業の経営力・資金調達力の向上が図られるわけではなく、中小企業に中小会計要領が普及し、中小企業がそれを活用できるようになることが極めて重要である。
この考え方から、「検討会」及び「WG」では、平成23年2月1日に中小会計要領を公表した後も、引き続き「WG」で中小会計要領の普及・活用策が議論され、平成23年3月27日に公表された「検討会」報告書において中小会計要領の普及・活用策(以下、「普及・活用策」という。)が取りまとめられている。
「普及・活用策」は、冒頭に「中小企業の会計に関する検討会は、中小会計要領が定着することで、中小企業の経営者が正確な財務情報に基づき経営状況を把握して経営改善等を図り、また、自社の経営状況を金融機関等の利害関係者に情報提供できるようになることは、中小企業が存続・発展していくために極めて重要であると考える。」と記載されており、この観点から、中小会計要領の普及・活用に向け、政府(中小企業庁・金融庁等)、中小企業関係者、金融機関関係者、会計専門家等(以下「各機関・団体」という。)が一丸となって推進すべき具体的取組が取りまとめられている。
「普及・活用策」は、中小企業が中小会計要領を知り、理解し、自社の計算書類作成に利用し、それにより得た財務情報を活用するところまでをトータルでサポートできる体制を整えるべく、以下の4部構成となっている。
① 中小企業の経営者が中小会計要領を利用して計算書類を作成することの重要性を認識し、関心を持つような環境を整備するための取組をまとめた「広報・普及」編
② 中小企業が中小会計要領の内容について、詳しく学習・理解できる学習機会の提供や、中小企業指導・支援を行う人材の育成を行うための取組をまとめた、中小企業向け、会計専門家・指導員向け「セミナー・研修」編
③ 会計専門家や中小企業関係者の支援体制を整備するための取組をまとめた「中小会計要領に従った計算書類等の作成支援」編
④ 中小企業による中小会計要領の活用を支援するための取組をまとめた「中小会計要領の活用」編
上記「普及・活用策」の中では、共同事務局である中小企業庁や金融庁の取組も発表されており、中小企業が自発的に中小会計要領を活用し、自社の財務経営力や資金調達力の向上が図られること、また中小会計要領の策定メンバーとして参画している金融機関にも、中小企業に対して中小会計要領の活用を促していくことで、中小企業の経営力や資金調達力の強化等を支援していくことなどが期待されている。
「検討会」では平成24年度から平成26年度の3年間を中小会計要領の集中広報・普及期間と定めており、各機関・団体が同じ方向を向いて有機的に連携し、各々の普及・活用策に取り組むこととなっている。また、その取組の達成状況の把握、改善点の検討のため、平成24年度中に初回のフォローアップ会合が開催され、その後も定期的にフォローアップ会合が開催されることとなっている。
今回の「検討会」及び「WG」における中小会計要領の策定、及び普及・活用策の検討は、近年の中小企業施策の考え方にも合致している。
平成22年6月に閣議決定された「中小企業憲章」では、「中小企業の実態に即した会計制度を整え、経営状況の明確化、経営者自身による事業の説明能力の向上、資金調達力の強化を促す」と言及されている。
また、平成23年12月の中小企業政策審議会企業力強化部会中間とりまとめでは、中小企業に会計の定着を図り、会計の活用を通じて、中小企業の経営力向上、資金調達力の向上を促進することが重要であり、そのためには中小企業の実態に即した会計ルールの整備をすべきとされている。
中小会計要領は、これらで指摘されている会計制度、会計ルールに該当するものであり、このような観点からも、中小会計要領が着実にインフラとして中小企業に定着し、中小企業の活性化を図る土台となっていくよう、官民一体となって中小会計要領の普及・活用が図られることを期待する。
最後に、中小企業庁でも普及の一環として、リーフレットやパンフレットを作成しているので、ぜひご活用いただきたい。
(詳細は中小企業庁のHP(http://www.chusho.meti.go.jp/)を参照)
「中小企業の会計に関する基本要領」について
中小企業庁事業環境部財務課 吉田政弘
平成24年3月27日、「中小企業の会計に関する検討会(以下、「検討会」という。)」から最終報告書が公表され、1年1ヶ月強に渡って検討された、中小企業の実態に即した新たな中小企業の会計処理のあり方を示すものである「中小企業の会計に関する基本要領」(以下、「中小会計要領」又は「本要領」という。)の策定及び普及・活用策の検討について一定の区切りを迎えた。
「中小会計要領」の策定主体である「検討会」において、中小企業庁と金融庁が共同事務局として参画しているが、本稿は事務局のうちの中小企業庁としての観点から「中小会計要領」策定の背景、概要、今後の普及・活用策について概説するものであり、また、本稿中意見にわたる部分は、筆者の個人的見解であることをあらかじめお断りしておく。
Ⅰ「中小会計要領」の策定の背景
近年、経済のグローバル化が進展したことにより、財務諸表の国際的な比較可能性を向上させる必要性が指摘され、様々な国において、自国の会計基準を「国際会計基準審議会(IASB)」が設定する「国際財務報告基準(IFRS)」に収斂(コンバージェンス)させる、若しくはIFRSを適用(アドプション)する動きや、IFRS適用のあり方についての議論が展開されている。
我が国においても平成17年からIASBと企業会計基準委員会(ASBJ)との間でコンバージェンス・プロジェクトが実施されており、現在でも金融庁の企業会計審議会においてIFRS適用のあり方について検討されているところである。
世界的にIFRSへのコンバージェンスが議論される一方で、必ずしも国際競争に晒されていない自国内の非上場企業の会計基準についても様々な国で議論が行われている。
我が国にも419万社の企業が存在しており、内99%以上が中小企業である。中小企業は雇用及び製造業における付加価値額の大部分を担っており、我が国及び地域経済の基盤をなす重要な存在である。
これまで、中小企業に適用される会計基準(又はルール)については、その一つとして「中小企業の会計に関する指針」(以下、「中小指針」という。)が設定されていた。中小指針は平成14年6月に中小企業庁が公表した「中小企業の会計に関する研究会報告書」、平成14年12月に日本税理士会連合会が公表した「中小会社会計基準」、及び平成15年6月に日本公認会計士協会が公表した「中小会社のあり方に関する研究報告」を統合し、平成17年8月に、主として会計参与が置かれた企業を念頭に中小企業が会社法上の計算書類を作成する際の会計処理を示したものとして、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の4団体が作成主体となり、金融庁、法務省、中小企業庁がオブザーバーとして参画する形で作成されたものである。
中小指針は、中小企業の実態及びコストベネフィットを考慮し、上場企業等の金融商品取引法適用会社が適用する企業会計基準を簡素化して作成されているものである。しかし「企業の規模に関係なく、取引の経済実態が同じなら会計処理も同じになるべき」とする考え方が採用されていることから、上場企業等に適用される企業会計基準においてIFRSへのコンバージェンスが行われる度に、中小指針についても累次の改訂がなされており、中小企業は間接的にIFRSへのコンバージェンスの影響を受けている状況であった。
その後、我が国に会計基準の国際化の動きがある一方で、中小企業への影響を回避又は最小限に留める必要があるとの意見を踏まえ、平成22年2月に中小企業庁において「中小企業の会計に関する研究会」(以下、「研究会」という。)、同年3月に企業会計基準委員会等の民間団体により「非上場会社の会計基準に関する懇談会」(以下、「懇談会」という。)が設置され、それぞれ非上場企業、特にその大部分を占める中小企業の会計の実態、特性、慣行等から中小企業の今後の会計基準の在り方に至るまで検討が行われた。結果的に、平成22年8月に懇談会、同年9月に研究会の報告書が取りまとめられ、両報告書において、中小企業の会計基準として新たに中小企業の会計処理のあり方を示すものを取りまとめるべきである等の方向性が示された。
今般中小会計要領を策定した「検討会」は、これらの両報告書に示された方向性を受け、平成23年2月に設置され、検討が重ねられてきたものである。
Ⅱ 中小会計要領の概要
中小会計要領の取りまとめにおいては、「研究会」及び「懇談会」の両報告書の内容を踏まえ、中小企業の実態に配慮するという視点で議論が重ねられてきた。中小企業は、多種多様な業種・業態の事業活動を行っており、その規模や経済取引等の実態は個々の企業で異なり、大企業と比べて生産性、収益性等のばらつきが大きいなど、総じて、大企業とは異なる属性を有している。特に中小企業の会計のあり方を検討するにあたって考慮すべきと考えられる、多くの中小企業が該当する属性は、以下の通りである。
① 資金調達の方法として、新株発行や起債といったように資本市場で資金調達を行うことはほとんどなく地域金融機関やメガバンクなどの金融機関からの借り入れが中心。
② 中小企業では、所有と経営が一致しており、いわゆる同族会社に該当する場合がほとんどである。また、通常、株式には譲渡制限が付されており、株式が第三者に自由に流通することは想定されていない。利害関係者は限られており、計算書類等の開示先は、主として、取引金融機関、主要取引先、既存株主等に限られる(図表1参照)。
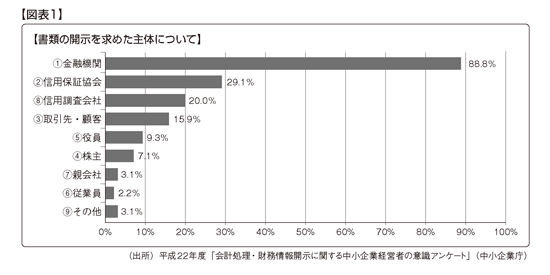 ③ 多くの中小企業では、税務申告が計算書類等作成の目的の大きな割合を占め、法人税法で定める処理を意識した会計が行われている。
③ 多くの中小企業では、税務申告が計算書類等作成の目的の大きな割合を占め、法人税法で定める処理を意識した会計が行われている。④ 経理担当者の人数が少なく、高度な会計処理に対応できる十分な能力や経理体制を持ち合わせていない(図表2参照)。
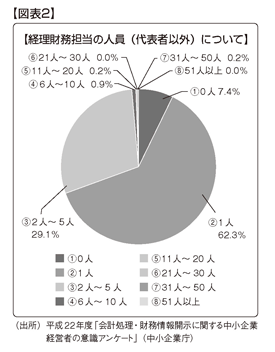
これらの実態に可能な限り配慮した新たな会計処理のあり方を取りまとめ、かつ取りまとめられたものについて幅広く中小企業の自発的な利活用を促す必要があることから、中小会計要領は検討メンバーや検討のアプローチ等にも配慮され、検討が行われてきた。
まず、中小企業関係者の総意として取りまとめられるという手続きを可能な限り担保する観点から、中小会計要領の策定主体である「検討会」及び実務的な検討を行った「中小企業の会計に関する検討会ワーキンググループ」(以下、「WG」という。)のメンバーは中小企業関係者が主体となって構成されている。具体的には、中小企業会計のユーザーである中小企業自身や中小企業団体、中小企業の会計実務を熟知する税理士や公認会計士等の会計専門家及びその団体、多くの中小企業にとって主な利害関係者である金融機関、専門的な見地を有する企業会計基準設定団体や学識経験者といった中小企業の関係者が中心となっており、関係官庁は事務局(中小企業庁、金融庁)、オブザーバー(法務省)として参加する体制となっている。
また、検討のアプローチも、上場企業等が準拠する企業会計基準をベースに、それを簡素化するアプローチ(トップダウン・アプローチ)ではなく、対象とする中小企業の属性を勘案し、取得原価主義や企業会計原則等を踏まえつつ、中小企業が実務で行っている会計慣行を積み上げ方式で策定するアプローチ(ボトムアップ・アプローチ)が採用された。
このように検討し策定された中小会計要領は総論、各論、様式集で構成されており、それぞれについて検討の過程における議論を踏まえつつ、概観していきたい。
1 総 論 総論の項目建ては以下の通りである。
1.目的
2.本要領の利用が想定される会社
3.企業会計基準、中小指針の利用
4.複数ある会計処理の取扱い
5.各論で示していない会計処理等の取扱い
6.国際会計基準との関係
7.本要領の改訂
8.記帳の重要性
9.本要領の利用上の留意事項
「1.目的」においては、中小会計要領が、中小企業の多様な実態に配慮し、その成長に資するために策定されたものであることが明示されており、以下の考えに立って作成されたものであることを示している。
・中小企業の経営者が活用しようと思えるよう、理解しやすく、自社の経営状況の把握に役立つ会計
・中小企業の利害関係者(金融機関、取引先、株主等)への情報提供に資する会計
・中小企業の実務における会計慣行を十分考慮し、会計と税制の調和を図った上で、会社計算規則に準拠した会計
・計算書類等の作成負担は最小限に留め、中小企業に過重な負担を課さない会計
これらの考え方は後述の各論の検討においても常に根底にある考え方として持ち出され、これに沿った形で結論が導かれていたと考えられる。後の各論を概観する際に紹介させていただきたい。
「2.本要領の利用が想定される会社」では、中小会計要領の想定対象として、金融商品取引法の規制の適用対象会社と会社法上の会計監査人設置会社を除く株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社又は合同会社と記載されている。ここまでの記載は平成17年に策定された中小指針の適用対象の記載と同様であるが、中小会計要領では、中小指針での記載を引用した形で「(注)中小指針では、「とりわけ、会計参与設置会社が計算書類を作成する際には、本指針に拠ることが適当である。」とされている。」という注書きが設けられている。検討の過程において、中小会計要領と中小指針の想定対象について、一定の区分を設けるべきという意見があったが、結論として、中小企業は中小会計要領でも、中小指針でも、どちらでも参照することが可能であり(図表3参照)、中小企業が自社の実態に応じて中小会計要領や中小指針を適用し、計算書類の信頼性を向上させ、会計の活用を通じて経営力の強化が図られることが期待されている。
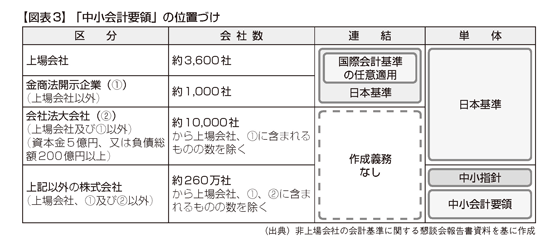
「6.国際会計基準との関係」、「7.本要領の改訂」は、中小会計要領を安定的に継続利用可能なものとする観点から設けられている項目であり、国際会計基準の影響を受けないものとし、また、改訂は中小企業の会計慣行の状況等を勘案し、必要と判断される場合にのみ行うこととされている。これは中小企業に過剰な負担を課さないという考え方から必要な項目と考えられる。
その他、総論において注目すべき点は、企業会計原則の一般原則のうち、「継続性の原則」及び「正規の簿記の原則」の趣旨について特に重視した内容となっていることである。「重要性の原則」と並べて上記以外の他の一般原則については「9.本要領の利用上の留意事項」に列挙されているが、「継続性の原則」の趣旨は「4.複数ある会計処理方法の取扱い」の部分に、「正規の簿記の原則」の趣旨は「8.記帳の重要性」の部分に特出された形で言及されている。これはこの2つの原則が、自社の経営状況を把握する観点からも、利害関係者への情報提供に資する観点からも、中小企業にとって特に重要と考えられるという考えから構成が検討されたものであり、中小企業の属性を勘案して検討された中小会計要領の特徴の一つと言える。
2 各 論 各論の項目建ては以下の通りである。
1.収益、費用の基本的な会計処理
2.資産、負債の基本的な会計処理
3.金銭債権及び金銭債務
4.貸倒損失、貸倒引当金
5.有価証券
6.棚卸資産
7.経過勘定
8.固定資産
9.繰延資産
10.リース取引
11.引当金
12.外貨建取引等
13.純資産
14.注記
各論については、中小会計要領の特徴をより分かりやすく説明する観点から、総論「1.目的」に挙げられている中小会計要領の作成における4つの考え方に沿って概観していきたい。
(1)中小企業の経営者が自社の経営状況を把握し活用できる会計 「1.収益、費用の基本的な会計処理」、「2.資産、負債の基本的な会計処理」の項目では、会計の基本的な原則を分かりやすく解説し、会計の基本的な知識習得が可能な内容となっている。収益の「実現主義」、費用の「発生主義」、費用収益対応の原則、総額主義の原則、「取得原価主義」等の基本的な考え方に言及しており、また、会計用語としての「取得価額」と「取得原価」の違い等も解説されている。
(2)利害関係者への情報提供に資する会計 「3.金銭債権及び金銭債務」の項目では、計算書類を見ただけでは必ずしも把握できない、受取手形割引額及び受取手形裏書譲渡額について必ず注記することとされている。これらの情報は金融機関が企業の受取債権に係る経営指標について分析する際や不渡り手形の買い戻しリスクの評価等を行う上で必要な情報であり、利害関係者側から注記を求める声が多かったことから必ず注記することとされたものである。これにより中小企業と利害関係者である金融機関との信頼関係の構築が図られることが期待されている。
また、「8.固定資産」における減価償却や「11.引当金」の計上については、会計上適切に費用処理すべきとされている項目であるが、税制における損金算入の考え方と異なる部分があり、中小企業会計の実務においてよく問題となる項目である。しかし、中小会計要領は信頼性の高い計算書類を作成し、利害関係者への情報提供に資する観点から、中小企業の実務慣行への配慮を示しつつ、会計上の適切な費用処理(減価償却)や負債計上(賞与引当金、退職給付引当金)等の処理を求めている。
(3)中小企業の実務会計慣行を十分考慮し、可能な限り税制との調和を図った実行しやすい会計 「4.貸倒引当金、貸倒損失」の項目では、回収不能のおそれのある債権以外の一般債権についての貸倒引当金額の見積もり方法として、法人税法上の中小企業に認められている法定繰入率が利用できることが明確化されている。
また、「5.有価証券」の項目においては、有価証券の分類を法人税法上の分類と同様に「売買目的有価証券」と「売買目的以外の有価証券」の二分類とし、売買目的以外の有価証券については取得原価で計上し、著しく価値が下落した場合を除いて保有途中での時価評価を必ずしも求めていない。
さらに、「6.棚卸資産」の項目においては、中小企業が法人税法上認められている「最終仕入原価法」で棚卸資産を評価していることが多い実態を踏まえ、上場企業等の企業会計基準では重要性のないものを除いて認められていない「最終仕入原価法」について、中小会計要領では他の棚卸資産の評価方法とともに中小企業が利用できることを明確にしている。
このように、法人税法上の処理や考え方に可能な限り配慮し、中小企業にとって実行しやすい会計となっている。
(4)中小企業に過剰な負担を課さない会計 中小会計要領は、全体的に、原則として取得原価主義によって資産計上し、明らかに価値の下落が判断できるものについてだけ時価評価を求め評価損の計上を求めるという考え方を取っている。また、中小企業の会計の実態として、利用が多くないと考えられる「税効果会計」や「組織再編の会計」等の項目については規定しておらず、基本的な14項目の会計に限定している。
3 様式集 様式集については、会社計算規則により作成が求められている貸借対照表、損益計算書等について、多くの中小企業の実務において実際に使用され、必要と考えられる項目を検討し、中小企業にとって利用可能なものとなるように配慮がなされている。
Ⅲ 中小会計要領の普及・活用策
これまで見てきた通り、中小会計要領は中小企業の実態に配慮し、実行しやすい会計処理を示している。しかし、中小会計要領はあくまでも会計処理のあり方を示すものであり、これが策定されたからといって、自動的に中小企業の経営力・資金調達力の向上が図られるわけではなく、中小企業に中小会計要領が普及し、中小企業がそれを活用できるようになることが極めて重要である。
この考え方から、「検討会」及び「WG」では、平成23年2月1日に中小会計要領を公表した後も、引き続き「WG」で中小会計要領の普及・活用策が議論され、平成23年3月27日に公表された「検討会」報告書において中小会計要領の普及・活用策(以下、「普及・活用策」という。)が取りまとめられている。
「普及・活用策」は、冒頭に「中小企業の会計に関する検討会は、中小会計要領が定着することで、中小企業の経営者が正確な財務情報に基づき経営状況を把握して経営改善等を図り、また、自社の経営状況を金融機関等の利害関係者に情報提供できるようになることは、中小企業が存続・発展していくために極めて重要であると考える。」と記載されており、この観点から、中小会計要領の普及・活用に向け、政府(中小企業庁・金融庁等)、中小企業関係者、金融機関関係者、会計専門家等(以下「各機関・団体」という。)が一丸となって推進すべき具体的取組が取りまとめられている。
「普及・活用策」は、中小企業が中小会計要領を知り、理解し、自社の計算書類作成に利用し、それにより得た財務情報を活用するところまでをトータルでサポートできる体制を整えるべく、以下の4部構成となっている。
① 中小企業の経営者が中小会計要領を利用して計算書類を作成することの重要性を認識し、関心を持つような環境を整備するための取組をまとめた「広報・普及」編
② 中小企業が中小会計要領の内容について、詳しく学習・理解できる学習機会の提供や、中小企業指導・支援を行う人材の育成を行うための取組をまとめた、中小企業向け、会計専門家・指導員向け「セミナー・研修」編
③ 会計専門家や中小企業関係者の支援体制を整備するための取組をまとめた「中小会計要領に従った計算書類等の作成支援」編
④ 中小企業による中小会計要領の活用を支援するための取組をまとめた「中小会計要領の活用」編
上記「普及・活用策」の中では、共同事務局である中小企業庁や金融庁の取組も発表されており、中小企業が自発的に中小会計要領を活用し、自社の財務経営力や資金調達力の向上が図られること、また中小会計要領の策定メンバーとして参画している金融機関にも、中小企業に対して中小会計要領の活用を促していくことで、中小企業の経営力や資金調達力の強化等を支援していくことなどが期待されている。
「検討会」では平成24年度から平成26年度の3年間を中小会計要領の集中広報・普及期間と定めており、各機関・団体が同じ方向を向いて有機的に連携し、各々の普及・活用策に取り組むこととなっている。また、その取組の達成状況の把握、改善点の検討のため、平成24年度中に初回のフォローアップ会合が開催され、その後も定期的にフォローアップ会合が開催されることとなっている。
今回の「検討会」及び「WG」における中小会計要領の策定、及び普及・活用策の検討は、近年の中小企業施策の考え方にも合致している。
平成22年6月に閣議決定された「中小企業憲章」では、「中小企業の実態に即した会計制度を整え、経営状況の明確化、経営者自身による事業の説明能力の向上、資金調達力の強化を促す」と言及されている。
また、平成23年12月の中小企業政策審議会企業力強化部会中間とりまとめでは、中小企業に会計の定着を図り、会計の活用を通じて、中小企業の経営力向上、資金調達力の向上を促進することが重要であり、そのためには中小企業の実態に即した会計ルールの整備をすべきとされている。
中小会計要領は、これらで指摘されている会計制度、会計ルールに該当するものであり、このような観点からも、中小会計要領が着実にインフラとして中小企業に定着し、中小企業の活性化を図る土台となっていくよう、官民一体となって中小会計要領の普及・活用が図られることを期待する。
最後に、中小企業庁でも普及の一環として、リーフレットやパンフレットを作成しているので、ぜひご活用いただきたい。
(詳細は中小企業庁のHP(http://www.chusho.meti.go.jp/)を参照)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























