解説記事2019年12月09日 第2特集 譲渡所得事案、特例適用上の注意点(2)(2019年12月9日号・№814)
第2特集
当局作成のQ&Aを掲載
譲渡所得事案、特例適用上の注意点(2)
前回(813号)に続き、税務当局作成の「譲渡所得の審理上の留意点」を紹介する。収用対償地(代替地)を譲渡した場合の1,500万円特別控除、残地買収に伴う借地権に対する収用特例、株式等の譲渡所得における概算取得費での更正の請求などが取り上げられている。
Q5
収用対償地(代替地)を譲渡した場合の1,500万円特別控除の特例等の適用関係
地方公共団体の収用事業による甲所有のA土地(以下「事業用地」という。)の譲渡(譲渡価額9,000万円)に伴い、乙、丙、丁、戊(以下「乙ら」という。)らの所有するBないしEの一団の農地(以下「代替地」という。)が収用の対償に充てられることとなり、甲に譲渡された(譲渡価額の総額1億5,000万円)。
1 本事例における収用対償地の買取りに係る契約方式は、租税特別措置法通達34の2-4《収用対償用地が農地等である場合》に定める一括契約方式である。この場合、乙らの譲渡所得の計算上、代替地の譲渡価額のうち、租税特別措置法第34条の2、《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除》(以下「1,500万円控除の特例」という。)の適用が認められる事業用地の譲渡価額相当額(以下「事業用地価額相当額」という。)はそれぞれいくらになるか。
2 事業用地価額相当額を超える部分(一般譲渡部分)について、租税特別措置法第31条の2《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第1項の適用は可能か。
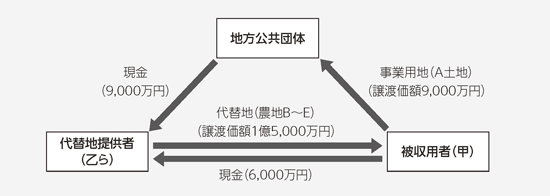
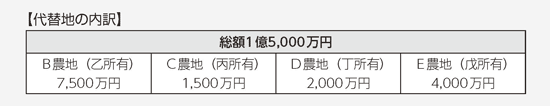
A
1 次のとおり、乙らの事業用地価額相当額は、事業用地の譲渡価額(9,000万円)に、代替地の譲渡価額の総額(1億5,000万円)に占める乙らの譲渡価額の割合を乗じて求める。
乙:9,000万円×(7,500万円/1.5億円)=4,500万円(一般譲渡:3,000万円)
丙:9,000万円×(1,500万円/1.5億円)= 900万円(一般譲渡: 600万円)
丁:9,000万円×(2,000万円/1.5億円)=1,200万円(一般譲渡: 800万円)
戊:9,000万円×(4,000万円/1.5億円)=2,400万円(一般譲渡:1,600万円)
なお、特別控除金額は、それぞれ1,500万円が上限となる。
2 一般譲渡部分については、租税特別措置法第31条の2第1項の規定を適用することはできない。
【理由】
1 収用対償地を譲渡した場合の租税特別措置法34条の2の適用
租税特別措置法第34条の2第2項第2号の規定により1,500万円控除の特例の対象となるのは、租税特別措置法第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》第1項第1号の収用及び同項第2号の買取り等の対償に充てるためのものに限られることから、事業用地価額相当額(9,000万円)を超える部分については、1,500万円控除の特例の適用を受けることはできない。
この点については、租税特別措置法通達34の2-4の(2)(注)および34の2-5《収用対償地の買取りに係る契約方式》(1)(注)に「代替地の譲渡について措置法第34条の2第2項第2号に規定する『当該収用の対償に充てるため買い取られる場合』に該当するのは、当該代替地のうち事業用地の所有者に支払われるべき事業用地の譲渡に係る補償金又は対価に相当する部分に限られる」旨定められている。
したがって、本事例の場合、事業用地の譲渡価額である9,000万円に相当する部分の土地の譲渡のみが1,500万円控除の特例の適用対象となる。
2 代替地提供者各人の事業用地価額相当額について
本事例の場合のように、代替地提供者が複数いる場合の一括契約方式において、代替地提供者各人の事業用地価額相当額をどのように計算すべきかについての規定等は設けられていない。
しかしながら、1,500万円控除の特例の適用対象となるのは、事業用地の譲渡価額(9,000万円)に相当する部分であるから、代替地提供者各人の事業用地価額相当額は、事業用地の譲渡価額(9,000万円)に、代替地の譲渡価額の総額(1億5,000万円)に占める代替地提供者各人の譲渡価額の割合を乗じて求めるのが相当である。
なお、租税特別措置法第34条の2第1項の規定により、特別控除額は、各人毎に1,500万円が上限となる。
3 租税特別措置法34条の2と租税特別措置法31条の2の適用関係
租税特別措置法第31条の2第4項は、個人が、その有する土地等につき、租税特別措置法第34条の2の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、租税特別措置法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当しないものとみなす旨規定している。そうすると、土地等の譲渡に係る対価の一部についてのみ租税特別措置法第34条の2の規定の適用を受けるときであっても、当該土地等の譲渡そのものが租税特別措置法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当しないこととなる。
したがって、本事例においては、一般譲渡部分について租税特別措置法第31条の2第1項の規定を適用することはできない。
Q6
残地買収に伴う借地権に対する「収用等の場合の課税の特例」の適用について
甲は乙に対して、土地を賃貸していたところ、A市の市道拡幅事業施行地内であったことから、その土地の一部について、A市は甲から底地を、乙から借地権をそれぞれ買収した。
甲は、所有地の一部が買い取られたことにより、残地(以下「本件残地」という。)を従来利用していた目的に供することが著しく困難であるとして、土地収用法第76条《残地収用の請求権》第1項の規定に基づく残地収用予定であったところ、A市と甲間で本件残地に係る任意売買契約が締結され、A市が本件残地を取得した。
これに伴い、乙はA市から、本件残地部分の借地権の消滅に係る補償金(以下「本件補償金」という。)を受領したが、本件補償金について「収用等の場合の課税の特例」を適用できるか。
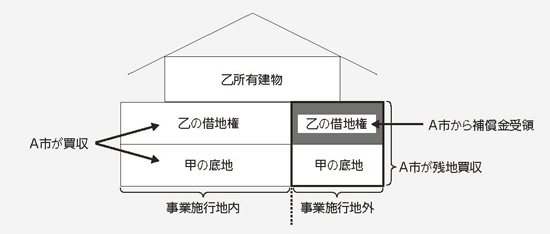
A
乙は、本件補償金について「収用等の場合の課税の特例」を適用できない。
【理由】
租税特別措置法通達33-17《残地買収の対価》は、土地の一部について収用等があったことに伴い、残地が従来利用していた目的に供することが著しく困難となり、その残地について収用の請求をすれば収用されることとなる事情があるため(土地収用法76①)、残地を起業者に買い取られた場合には、その残地の買取りの対価は、当該収用等があった日の属する年分の対価補償金として取り扱うことができる旨定め、「収用等の場合の課税の特例」の適用を認めることとしている。 ところで、残地収用の請求権を有する者は、土地収用法第76条第1項により、土地所有者に限定されているから、土地所有者以外の権利者は、残地収用の請求権を有していないこととなる。
そうすると、乙は借地権者であり、残地収用の請求権を有していないから、本件補償金について「収用等の場合の課税の特例」を適用できないこととなる。
Q7
特定区画整理事業等のために土地等を譲渡した際に受領した建物移転補償金の取扱いについて
甲は、令和元年5月13日、A市施行の土地区画整理事業にあたって、A市に対し、所有する土地及び当該土地の上に存する建物(以下「本件建物」という。)を譲渡(以下「本件譲渡」という。)し、対価補償金2,000万円及び建物移転補償金300万円(以下「本件補償金」という。)を受領し、本件建物を取り壊した。
この場合において、甲は、本件譲渡のうち、土地の譲渡に係る対価補償金2,000万円について、租税特別措置法第34条《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除》第1項(以下「本件特例」という。)を適用する予定であるところ、本件特例の適用のない本件補償金を、譲渡所得として申告することはできるか。
また、本件補償金を譲渡所得として申告することができる場合、本件建物の取壊し費用を本件建物の譲渡所得の計算上、譲渡費用とすることができるか。
なお、本件特例の適用要件は全て満たしているものとする。
A
本件補償金を譲渡所得として申告することができる。
また、本件建物の取壊し費用を譲渡費用とすることができる。
【理由】
原則として、土地等の収用等に伴い、その土地の上に存する建物及び構築物(以下「建物等」という。)を引き家又は移築するために要する費用として交付を受ける補償金(建物移転補償金)は、一時所得の収入金額となるところ、租税特別措置法通達33-14《引き家補償等の名義で交付を受ける補償金》により、その交付を受ける者が実際に建物等を取り壊した場合には、その実態に着目し、当該補償金について、当該建物等の対価補償金として取り扱うことができる旨定められている。 そして、本事例のように、甲が、本件補償金の交付を受け、実際に本件建物を取り壊している場合には、その補償金は建物の対価と考えることができ、この点について、土地等の収用等と取り扱いを異にする理由がないことから、租税特別措置法通達33-14を準用し、本件補償金を対価補償金として取り扱い、譲渡所得として申告することができると解するのが相当である。
また、本件補償金を本件建物の譲渡所得として申告する場合、当該譲渡所得は、本件建物を取り壊したことにより実現したものと考えられる。
したがって、本件建物の取壊し費用は、所得税法第33条《譲渡所得》第3項に規定する譲渡に要した費用に該当するから、本件建物の譲渡所得の計算上、譲渡費用とすることができる。
Q8
株式等の譲渡所得等における概算取得費に係る更正の請求の適用可否
甲は、平成30年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告において、株式等に係る譲渡所得の計算に際し、当該株式等の取得費を実額により計算していた。
その後、甲は、当該株式等の譲渡所得の計算において、取得費を当該株式等の譲渡による収入金額の100分の5に相当する金額(以下「本件概算取得費」という。)に基づき計算した方が実額よりも有利になることから、本件概算取得費により取得費を計算する旨の更正の請求(以下「本件更正の請求」という。)を行った。
この場合、本件更正の請求は認められるか。
A
本件更正の請求は認められる。
【理由】
1 株式等の譲渡所得等に係る概算取得費の適用について
株式等を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上、取得費に算入する金額は、実際の取得に要した金額に基づき計算するところ、当該株式等の譲渡による収入金額の100分の5に相当する金額を譲渡所得の計算上、収入金額から控除する取得費として計算しているときはこれを認めて差し支えないとされている(措通37の10・37の11共-13)。
2 当てはめ
上記1のとおり、納税者が申告において、概算取得費に基づき取得費を計算した方が実額よりも有利になるとして株式等の譲渡所得の計算をしている場合には、概算取得費による当該譲渡所得の計算を認めていることからすれば、株式等の取得費を本件概算取得費とする旨の本件更正の請求を否認する必要性はない。
したがって、本件更正の請求は認められる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















