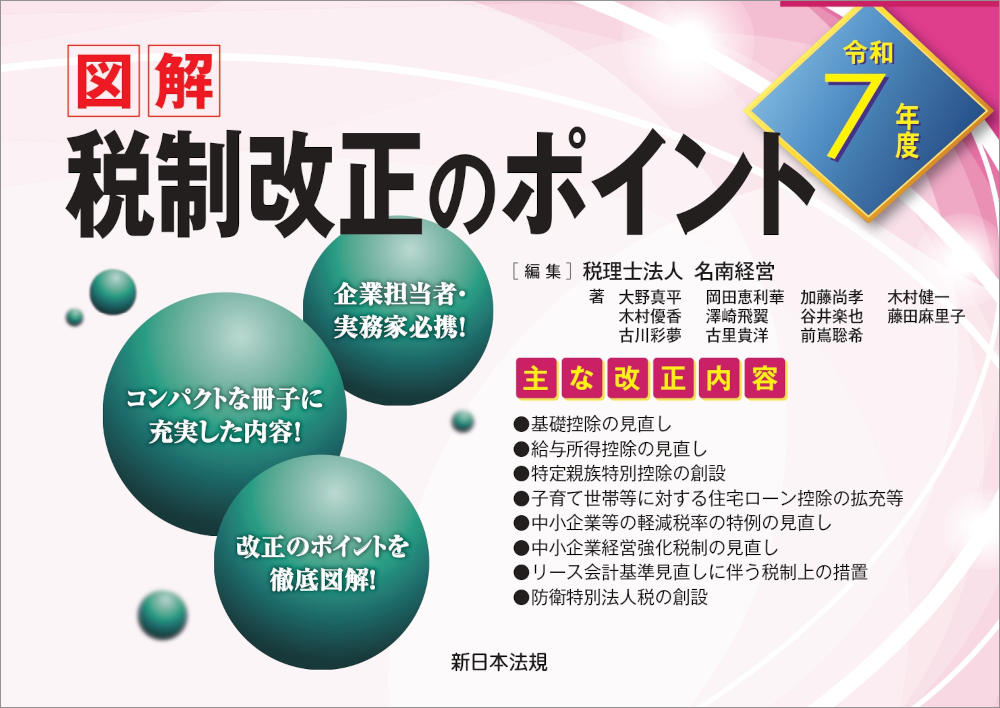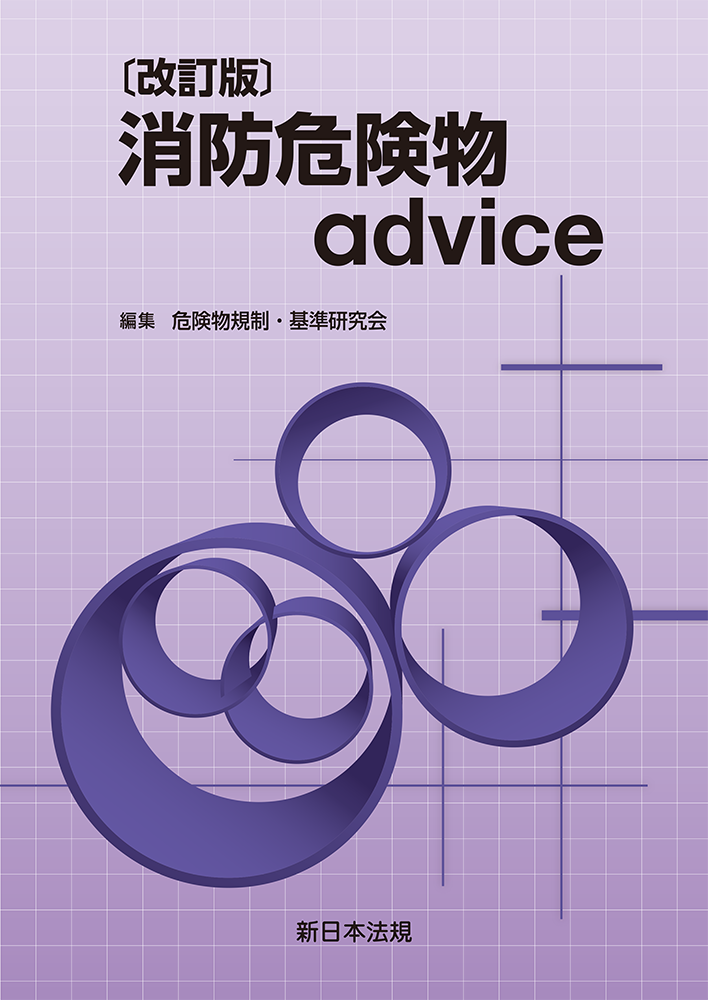解説記事2022年07月11日 ニュース特集 税理士懲戒処分の適法性の判断基準(2022年7月11日号・№938)
ニュース特集
「故意に」「真正の事実に反して」「税務書類の作成」の三要件充足
税理士懲戒処分の適法性の判断基準
税理士法違反行為を巡る調査が平成28年頃から明らかに強化されている。
本特集で取り上げるのは、相続税申告で一部の相続財産を計上せず、業務禁止処分を受けた税理士(原告)の処分取消請求が棄却された事案(令和4年6月3日東京地裁判決)だ。
税理士にとって、相続税申告における相続財産の把握漏れのリスクは大きいだけに、どのような点が懲戒処分につながるのかは関心が高いところだ。本事案で、裁判所が、税理士法45条1項に定める「故意に」「真正の事実に反して」「税務書類の作成をした」という各要件を満たすか否かについてどのような事実認定を行い、判断を下したのかを検証する。
課税当局、平成28年頃から税理士法違反行為に対する調査を強化
税理士法違反行為を巡る課税当局の調査が平成28年頃から明らかに強化されている。
その端緒として、国税庁が平成28年6月に発遣した「『関係各部課及び税務署から税理士管理官への情報提供要領』の制定について(事務運営指針)」が挙げられる。同指針では、平成28事務年度の税理士関係事務運営の新たな特留事項として「課税調査等の結果から税理士法違反行為の疑いがあることを把握した場合には、課税調査担当部署と連絡を密にし、調査の処理方針等について意識共有を図ること」が指示されている(本誌684号)。また、同指針には、平成27年1月に改正された財務省告示「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」の概要も示されている(本誌683号)。
さらに、平成29年6月に発遣された「平成29事務年度における税理士関係事務の運営に当たり特に留意すべき事項について(指示)」においても、国税局や税務署の幹部に対し、課税調査担当者が課税庁者の過程で多額の不正や調査妨害当の事実を把握した場合などには、必ず税理士等の不正関与の有無を確認し、疑いがある場合には速やかに税理士管理官に連絡するよう指示が出されている(本誌715号)。
納税者が提出した原告作成書面は、計算資料ではなく「税務書類」
本事案の概要は図表1のとおり。
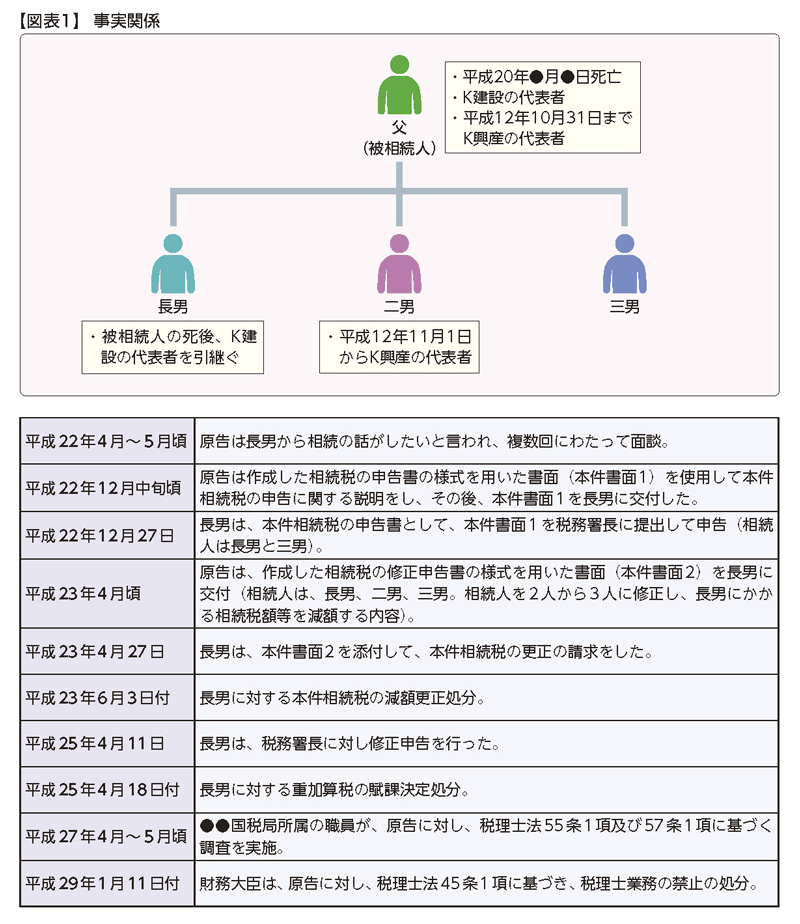
本件は、税理士である原告が、本件長男の相続税の申告に当たり、被相続人の相続財産として計上しなければならないと認識していた財産(K興産に対する出資金及び貸付金並びに米国M社に対する投資証券(M資産)。これらを併せて、以下「本件各財産」)を相続財産として計上せず、本件長男の相続税の課税価格を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成したとして、税理士法45条(脱税相談等をした場合の懲戒)1項に基づき、財務大臣から税理士業務の禁止の処分を受けたことから、当該処分の取消しを求めた事案である。
本事案の争点は図表2のとおり。争点2では、税理士法45条1項に定める各要件、「故意に」「真正の事実に反して」「税務書類を作成したか」をそれぞれ満たしているか、検討が行われた。
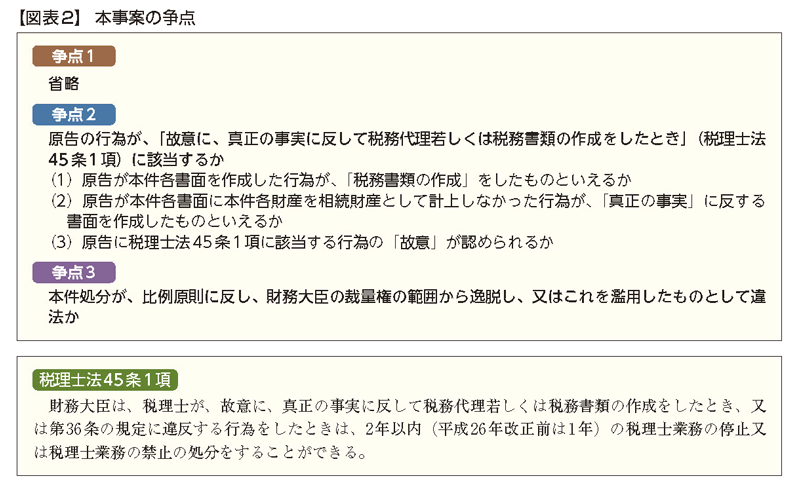
まず、争点2(1)「原告が本件各書面を作成した行為が、『税務書類の作成』をしたものといえるか」について東京地裁は、本件書面1は「国税庁が相続税の申告手続に使用する様式として提供している相続税の申告書と同一の様式で作成され、そのまま税務署長に提出すれば、相続税の申告書としての体を成すものであった」、本件書面2は「本件更正請求に係る請求書と一体となって、国税通則法23条2項に規定された事項が記載された『税務書類』に該当するものである」と指摘した。
原告は、「本件相続税の申告について、長男から税務代理及び税務書類の作成を受任しておらず、本件相続税の申告に関する報酬を受け取ったことは一切なく、原告と長男との間に本件相続税の申告に関する委任関係は存在しないから、原告が本件相続税の申告に関する『税務書類』を作成する前提を欠く」などと主張したが、これに対し東京地裁は、認定事実から、「原告は、長男から、本件相続税の申告に関し、本件相続税の税額等の計算に関する事項についての相談を受けて、これに応じた上で、申告書の作成や修正申告書の作成に協力することを約していたものといえ、遅くとも原告が相続税額試算シートを作成した平成22年12月24日頃の時点において、原告と長男との間に本件相続税の申告に関する委任関係が存在していたと認めるのが相当である。そして、税理士が税理士業務を行うに当たり、必ずしも有償であることは要しないと解されるから、仮に、原告が本件各書面を作成するに当たり、長男から報酬を受け取ったことがないとしても、そのことは上記認定判断を左右するものではない。なお、本件各書面には原告の税理士としての署名押印がないことは、本件各書面の効力に影響を及ぼすものではないから、この点も上記認定判断を左右しない。」との判断を下した。
また、「税額の計算資料として本件書面1を作成したにすぎない旨の原告の供述等はにわかに信用することができず、原告は、長男が本件書面1をそのまま税務署に提出することを想定して、本件書面1をそのまま税務署に提出することができる状態にまで完成させた上で、これを長男に交付したと認めるのが相当である」とも判断している。
東京地裁の判断は、たとえ報酬を受け取っていなかったり、契約書を締結していなかったりしたとしても、税務相談に応じ、税額の計算に必要な書面等を作成したりしていれば、委任関係があると認定される可能性が高いことを示している。また本件では、そのまま税務署に提出できる状態にまで完成された書面が「税務書類」と認定されたことも、裁判所の判断のポイントといえそうだ。
ひとまず判明している相続財産だけを計上、「真正の事実」に反する
次に、争点2(2)「原告が本件各書面に本件各財産を相続財産として計上しなかった行為が、『真正の事実』に反する書面を作成したものといえるか」については、まず、規定の解釈として、原告が「税理士が、客観的な事情により、その存在又はその適正な評価額を把握できない相続財産がある場合に、ひとまず判明している相続財産だけを計上した税務書類を作成する行為は、『真正の事実に反して……税務書類の作成をした』場合に該当しない」と主張したのに対し、東京地裁は、「税理士法45条1項の文言に照らせば、原告が主張するような限定的な解釈を採用することはできない」との考えを示した。
そして、原告が、相続財産として計上しなかった各財産のうち、まずM資産について、「被相続人と二男がジョイント・テナンシーの形態で保有していたものであり、相続されることなく二男に移転した」と原告が主張したのに対し、認定事実から「被相続人は、本件M資産の出資金を全額拠出した上で、本件M資産から生ずる利益を享受していたと認められ、本件M資産は、契約上は二男が共有名義人となっているものの、その実質は被相続人が単独で所有していた財産である」と判断した。
また、K興産の出資金及び貸付金については、K興産の法人税申告書及び貸借対照表の記載等からこれらの資産が存在していた事実を認定した。
原告は、M資産については、「当時は相続人ではなかった二男が所有していると認識しており、上記認識によれば、本件M資産は相続財産として計上してはならない財産であった」、K興産の出資金及び貸付金については、「長男及び二男から必要な資料を得ることができなかった」から「真正の事実」に反する書面を作成したとはいえないなどと主張したが、「税理士の判断如何によって当該書面が『真正の事実』に反する書面であるか否かの判断が左右されるものではない」として、これらの主張は一蹴された。
「真正の事実」に反するか否かに関しては、「ひとまず判明している相続財産だけを計上」「認識がなかった」「把握していなかった」という事実は、裁判所の判断に影響を与えないといえそうだ。
東京地裁「原告は、相続財産であることを未必的に認識」
次に、争点2(3)「原告に『故意』が認められるか」について東京地裁は、「税理士法45条1項に規定する故意があるというためには、真正の事実に反して税務書類の作成をすることについての認識及び認容が必要であり、かつ、それで足りるものと解される。そして、この認識は、未必的なものでも足りると解すべきである。」との解釈を前提に、「税理士が、入手可能な帳簿、書類等の資料を検討し、職業専門家としての知識と経験による合理的な判断に基づき、それが真正の事実であるとの認識に立った上で、税務書類の作成をしたのであれば、結果的にそれが真正の事実に反するものであっても、故意を欠くとの評価を受ける場合があり得るといえるが、原告が主張するように、ひとまず判明している相続財産だけを計上した税務書類を作成しさえすれば、作成された税務書類が真実に反するとの認識があるとしても故意の要件を欠くとの解釈を採用することは困難である」との考えを示した。
そして、原告に本件各財産が真実は相続財産であることの認識があったか否かについては、図表3の認定事実から、「原告は、本件各財産が真実は本件被相続人の相続財産であることを少なくとも未必的には認識しつつ、本件各書面に本件各財産を相続財産として計上しなかったのであるから、税理士法45条1項の故意が認められるというべきである」と結論づけた。
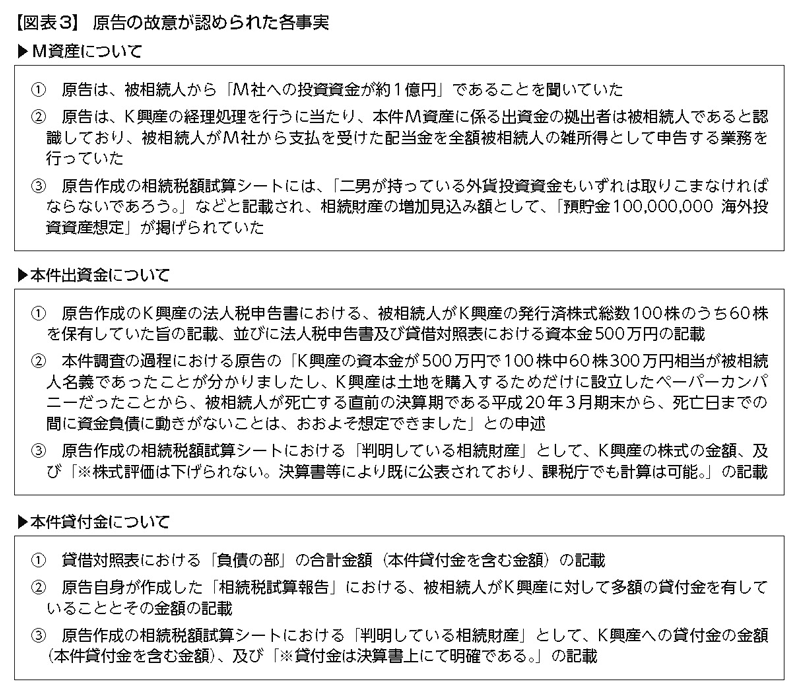
本件では、原告が作成した相続税申告に関係する書類における記載や、原告が行った経理処理、法人税又は所得税申告書作成の過程で把握した事実などから、原告が本件各資産を相続財産として未必的に認識していたことが認定されたといえる。
財務省告示が定める懲戒処分の量定の判断要素・範囲は合理性あり
争点3については、東京地裁は「税理士に対する懲戒処分の量定の判断要素及び範囲については、財務省告示が定められているところ、当該告示は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務書類の作成をしたときの税理士に対する懲戒処分の量定は、税理士の責任を問い得る不正所得金額等に応じて、6月以上1年以内(平成26年改正前)の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止とするとの考え方を基本としつつ、①行為の性質、態様、効果等、②税理士の行為の前後の態度、③懲戒処分の処分歴、④選択する処分が他の税理士及び社会に与える影響、⑤その他個別事情を総合的に勘案し、決定するものとする旨を定めており」「当該告示の考え方は合理性を有する」との考えを示した。
その上で、これらの各要素について検討を行った結果、「原告の責任を問い得る不正所得金額等は極めて多額であり、原告の行為の性質・態様は悪質であって、その効果も重大であることに加え、他の税理士及び社会に与える影響も勘案すれば、原告に対しては厳重な処分が選択されるべきである。そうすると、原告には懲戒処分歴がないという事情その他本件に現れた諸般の事情を考慮したとしても、財務大臣が原告に対して税理士業務の禁止の処分をしたことが、社会観念上著しく妥当性を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものということはできない。」と結論づけた。
なお、検討の過程の中で、「長男から、本件各財産について相続税を負担するのは納得できない旨の発言がされたことを受けて長男の意向に沿う形で、まずは、本件各財産を相続財産として計上せずに本件相続税の当初申告をし、その後、二男が相続人となることが確定した時点で修正申告をするという具体的方法を提案した」事実が認定されている。
相続税申告書自体を作成せず、無償で行ったとしても、納税者の真正の事実に反する相続税申告において、相談に応じ、提案し、税額計算や申告書作成に深くかかわっている事実が認められれば、裁判所は懲戒処分を適法と判断することになりそうだ。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.