解説記事2022年07月18日 ニュース特集 小規模宅地特例を巡る税賠事件で税理士法人が逆転勝訴(2022年7月18日号・№939)
ニュース特集
賃貸借契約締結も相続開始前に賃料の支払いが必須
小規模宅地特例を巡る税賠事件で税理士法人が逆転勝訴
相続税の申告の際に小規模宅地特例を適用しなかったとして税理士法人に損害賠償が請求された事件で、東京高等裁判所(三角比呂裁判長)は令和4年7月7日、税理士法人(控訴人)が敗訴した部分の原審の判決を取り消した(令和2年(ネ)第2973号)。原審の横浜地裁では、本件土地の貸付けについては小規模宅地特例の要件に該当するとして、税理士法人は契約上の注意義務違反があり、債務不履行があったと判断し、合計で約2,120万円の損害賠償請求を認めたが、東京高裁は小規模宅地特例の適用をすることはできないとして、相続人ら(被控訴人ら)の請求をすべて棄却した。本件貸付けについては、賃貸借契約は締結したものの、実際に賃料が支払われる前に被相続人が亡くなっており、小規模宅地特例の要件である「相当の対価を得て継続的に行うもの」に該当するか否かが争われていた。
賃料の支払い前でも貸付けが「相当の対価を得て継続的に行うもの」か
今回紹介する税理士賠償責任事件は、小規模宅地特例の適用の可否を巡るもの。被相続人の相続人ら(被控訴人ら)が、相続税の申告を税理士法人(控訴人)に依頼したが、税理士法人は相続財産の一部の土地について小規模宅地特例の適用の可否を検討せず、その適用を誤った過失があったとして、相続人らが税理士法人に対して債務不履行又は不法行為に基づき合計で約2,120万円にのぼる損害賠償請求を行った。
1回目の賃料支払い前に被相続人が死亡
相続財産の一部の土地には、被相続人の所有する建物があり、本件建物は平成12年8月から被相続人からの使用貸借により、相続人(被控訴人X)の1人がすべての株式を保有する会社Fの社屋として利用されており、本件土地はその敷地として利用されていた。被相続人は、その生前の平成28年10月31日に会社Fに対し、建物について賃貸期間を平成28年11月1日から平成30年10月31日まで(自動更新条項あり)、賃料を月額22万5,000円、駐車場利用料を月額4万円とする約定により賃貸した。この賃貸借契約については、平成28年夏頃に被相続人及び相続人らが被相続人の余命が1年ほどである旨の宣告を医師から受けたことを契機に、相続税対策の一環として相続人が(別の)税理士と相談の上、小規模宅地特例の適用による評価減を受けることを動機の一つとして締結したものであった。賃貸借契約締結後、本件土地については、会社Fの代表取締役である被控訴人Xが相続により所有権を取得した後、相続開始の時から相続税の申告期限まで引き続き保有し、かつ、申告期限まで被控訴人Xの会社Fの敷地として利用されていた。
税理士法人が小規模宅地特例の適用をしなかったことの可否が争われたわけだが、今回の一番のポイントは、貸付けに対する賃料の支払いが行われる前に相続が発生したことにある(図表1参照)。租税特別措置法69条の4第1項の事業には、「事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものを含む」と規定されているが(措令40条の①)、本件貸付けが「相当の対価を得て継続的に行うもの」に当たるかどうかが問題となった。
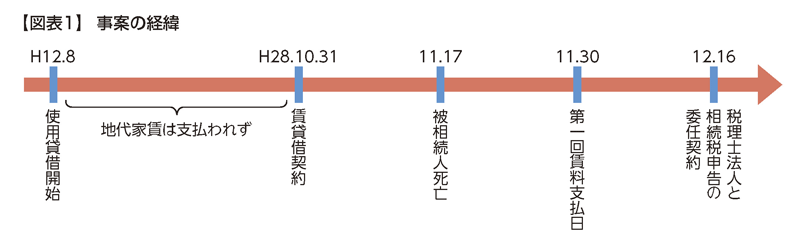
原審、相続開始前の賃料の支払いは必須要件にあらず
原審の横浜地裁は、不動産の貸付け等が準事業に当たるためには相当の対価が定められ、かつ、相当程度の期間継続することを予定した賃貸借契約に基づいて行われていることが必要であるが、相続の開始前に、賃料が支払われたことがあることを必須の要件とするものではないと解するのが相当であるとした。また、本件貸付けにおいては、賃貸借契約上「相当の対価」が定められており、賃貸借契約の契約期間は2年間であるが、自動更新条項が定められていること、賃貸借契約の目的物である本件建物は、賃貸借契約の締結以前から、相続人(原告X)の会社社屋として利用されており、現在でもその利用実態には変化がないと認められること、Xは、本件賃貸借契約締結後、現在に至るまで賃料の支払を続けていると認められること等に鑑みると、本件貸付けは、相当程度の期間継続することを予定した賃貸借契約に基づいて行われているものと認められるとの判断を示した。
特例の検討を行わず契約上の債務不履行あり
その上で、横浜地裁は、税理士法人(被告)は申告時点までに小規模宅地等の特例の適用が可能か否かについて検討していなかったものと認められ、税理士法人には同特例の適用の可否の検討を怠った点で契約上の注意義務違反があり、本件契約上の債務不履行があったと認められると判断し、相続人らの請求をほぼ認容した(令和2年6月11日判決、平成30年(ワ)第3861号)。
税理士法人、死亡直前に「賃貸借契約」に体裁が整えられただけと主張
控訴を行った税理士法人側は、小規模宅地等の特例が適用されるためには、事業又は準事業に該当することが必要であるが、本件土地については、会社Fから被相続人に対しては、平成12年8月から平成28年10月まで、地代家賃は一切支払われておらず、被相続人の死亡直前になり、突如として「賃貸借契約」との体裁が整えられただけであって、被相続人と会社Fとの間では、使用貸借に係る合意しかなかったといえ、事業における営利性・有償性を欠いていると主張。また、補助参加人として参加した損害保険会社は、裁判例などで直接的な先例は確認できないとしたが、平成9年11月19日裁決では、一般論として「相当の対価を得ていたかどうかについては、相続開始の直前において、相当の対価を現実に得ていたかどうかという客観的事実により判断するものと解される」との見解が示されており、現実の賃料授受のない以上「対価を得て」とはいえないのではないかとの疑問が深まるなどと意見を述べている。
一方、相続人らは、税理士法人は契約を締結した以上、相続税額が最も低くなるよう、事実関係及び関係法令を調査した上で、税務代理業務を遂行すべき注意義務を負っていたにもかかわらず、小規模宅地特例による評価減を受けられる土地について評価減の適用可能性を調査せず、しかも、適用を誤って看過したまま申告を行い、相続人らに相続税額として過大な金員を納付させたことは契約の債務不履行に当たるなどと主張した。
東京高裁、特例の適用を検討しなかっただけでは債務不履行とはいえず
東京高裁は、まず、小規模宅地特例の適用の検討をしなかったことをもって当然に債務不履行又は不法行為責任を肯定することはできないとの見解を示し、本件土地につき、相続開始の直前において小規模宅地特例の要件を満たしていることに加え、申告当時における実務(関係法令、通達、先例及びこれらに関する税理士等専門家の議論状況等)を踏まえた通常の税理士の認識・判断を基準にして、税理士である控訴人が、申告当時、要件のいずれもが満たされていると判断して本件土地に小規模宅地等の特例を適用して申告をするべき一般的注意義務(作為義務)を有していることを要するのであり、以上の適用要件該当性及び作為義務の存在という要件をいずれも満たさない限り、控訴人の債務不履行責任及び不法行為責任のいずれも肯定することはできないとした。
小規模宅地特例の適用要件を満たさず
その上で東京高裁は、小規模宅地特例の適用要件である準事業の要件の「対価を得て」に関しては、「文理上、賃料を現実に得ていることを意味すると理解するのが最も無理のない解釈と考えられる」とし、また、「継続的に行うもの」との要件に関しては、「その文理からすれば、不動産の有償貸付けが現実に実施され継続していることを意味すると解するのが自然」であり、本件貸付けのように、相続開始の直前において、いまだ賃料の授受がないばかりでなく、賃料の履行期が一度も到来したこともないという場合は、有償貸付けが現実に実施され継続しているという実体があるものとは言い難く、「継続的に行うもの」に該当すると認めるのは困難と解されるとの判断を示し、小規模宅地特例の適用要件を満たさないとした(図表2参照)。
【図表2】東京高裁と横浜地裁の主な判断
| 東京高裁 | 横浜地裁 |
| 「相当の対価」があるか否か | |
| 小規模宅地等の特例の適用要件は、租税特別措置法69条の4第1項柱書の「事業に準ずるものとして政令で定めるもの」について、同法施行令40条の2第1項により「事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの」と定められているのであり、上記の準事業の要件のうちの「対価を得て」の文理上、賃料を現実に得ていることを意味すると理解するのが最も無理のない解釈と考えられ、また、租税特別措置法上、小規模宅地等の特例の適用要件として、相続開始の直前において少なくとも準事業該当性を要すると定められ、準事業に当たらない無償の使用関係は同特例の適用対象から除かれたことからみれば、本件貸付けのように、相続開始の直前において、いまだ賃料の授受がないばかりでなく、賃料の履行期が一度も到来したことのない場合については、「対価を得て」の要件に該当するものとは認め難いといわざるを得ない。 | 租税特別措置法69条の4第1項及びこれを受けて準事業について定める同法施行令40条の2第1項は、小規模宅地等の特例の適用対象地について、相続の開始の直前に、被相続人等の準事業の用に供されていることを求めているが、それ以上に、当該準事業において、相続の開始の時点で、相当な対価が支払われたことがあることを要するとする規定は設けていない。 また、当該土地が供されている事業が、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為であっても、土地や同土地を敷地とする建物について、一旦、相当程度の期間継続することを予定する賃貸借契約が締結され、これに基づく利用が開始されれば、相続開始の時点で賃貸借契約に基づく賃料が支払われたことがあるか否かにはかかわらず、借主の事業等に関する関係者との社会的な関係等からその処分が制約されることがあり得るから、同特例の趣旨からしても、準事業に当たる要件として、相続開始の時点までに賃料が支払われたことを必要とする理由は考え難い。 |
| 「継続的に行うもの」の要件について | |
| 小規模宅地等の特例の適用要件は、租税特別措置法の規定を受けた同法施行令40条の2第1項が準事業の要件の一つとして「継続的に行うもの」と定められているのであり、その文理からすれば、不動産の有償貸付けが現実に実施され継続していることを意味すると解するのが自然であり、また、租税特別措置法上、小規模宅地等の特例の適用要件として、相続開始の直前において少なくとも準事業該当性を要すると定められ、準事業に当たらない無償の使用期間は同特例の適用対象から除かれたことからみれば、本件貸付けのように、相続開始の直前において、いまだ賃料の授受がないばかりでなく、賃料の履行期が一度も到来したこともないという場合は、有償貸付けが現実に実施され継続しているという実体があるものとは言い難く、「継続的に行うもの」に該当すると認めるのは困難と解される。 | 本件賃貸借契約の契約期間は2年間であるが、自動更新条項が定められていること、本件賃貸借契約の目的物である本件建物は、本件賃貸借契約の締結以前から、会社Fの社屋として利用されており、現在でもその利用実態には変化がないと認められること、Fは、本件賃貸借契約締結後、現在に至るまで賃料の支払を続けていると認められること等に鑑みると、本件貸付けは、相当程度の期間継続することを予定した賃貸借契約に基づいて行われているものと認められる。 |
加えて、東京高裁は、本件土地につき、小規模宅地特例の適用要件をすべて満たすと解したとしても、①租税特別措置法施行令40条の2第1項の「対価を得て」という文言は、少なくとも履行期が到来していることを要する趣旨と理解できる、②平成9年裁決事例では、その判断の前提となる一般論として「相当の対価を得ていたかどうかについては、相続開始の直前において、相当の対価を現実に得ていたかどうかという客観的事実により判断するものと解される」との見解が示されている、③「継続的に行う」については、文言に相続開始までの継続期間についての定めはなく、またその解釈指針を明確に示した通達等は見当たらないものの、小規模宅地特例の対象から排除されている使用貸借との区別の見地からみれば、相続開始直前に使用貸借から賃貸借に切り替えられた場合を無制限に含む趣旨であるとまでは容易に解されないなどとし、直ちに一般的注意義務(作為義務)を肯定することはできないとの判断を示し、被控訴人らの請求を棄却した。
コラム
責任制限条項、消費者契約法10条で無効になるケースも
原審の横浜地裁では、委任契約に盛り込まれた責任制限条項が消費者契約法10条後段(信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効とする)により無効となるかどうかも争点となっていた。責任制限条項とは、受任者である税理士法人が税務申告代理の業務を遂行する上で、過失によって委任者である相続人らに損害を生じさせた場合であっても、相続人らが税理士法人に対して請求できる損害賠償額の上限を相続人らが税理士法人に支払った報酬の額にするというものである。
横浜地裁は、責任制限条項は被告(税理士法人)に対して、報酬の限度では責任を負担させるものとはいえるが、その性質は、事業者に当たる税理士法人として、本来の業務である相続税の申告代理に関して税額等の調査・検討を求められる立場にある被告が、契約の締結時点で、相続について、小規模宅地の特例の適用について検討することもなく、その点に関する見解の相違やその適用の有無による税額の違いの有無・程度等、本件責任制限条項の存在に伴うリスクの有無・程度に関して何らの判断材料を提供することもなく、原告(相続人)に生じた損害(本来納めるべき税額と負担額との差額等)の賠償を求める権利について、その多寡に関わりなく、被告が受領すべき報酬を返還することで消滅させる性質のものであると指摘。責任制限条項は、被告の債務不履行により原告に生ずる損害の額と、被告が放棄する報酬の額との差額が多額に及ぶような場合にも、当該報酬の額を超える損害を被告のみに負担させることとなる点で、信義則に反し、消費者の利益を一方的に害する内容を含むものということができるとし、横浜地裁は、本件責任制限条項は消費者契約法10条後段により無効となり、原告らは、被告に対し、被告の債務不履行によって生じた損害の全部の賠償を求めることができるとの判断を示した。
東京高裁では、小規模宅地特例の適用はできず、相続人らの請求が棄却されたため、責任制限条項の有効性に関する判断は行われていない。
トラブルが発生した際のリスクを回避するため、契約上、責任制限条項を設ける税理士や税理士法人も少なくないだろう。本件では、契約締結時に遺産や報酬の見込み額を示すことはしておらず、責任制限条項についての説明も、税理士ではない事務員がルーティンワークとして同条項を読み上げ、事前に決まっている定型の説明を行うにすぎず、消費者からの個別の質問に回答できる体制とはなっていなかったという。このようなケースでは、消費者契約法10条により責任制限条項が無効となる可能性もあるだけに税理士サイドとしては留意しておくべき点といえそうだ。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























