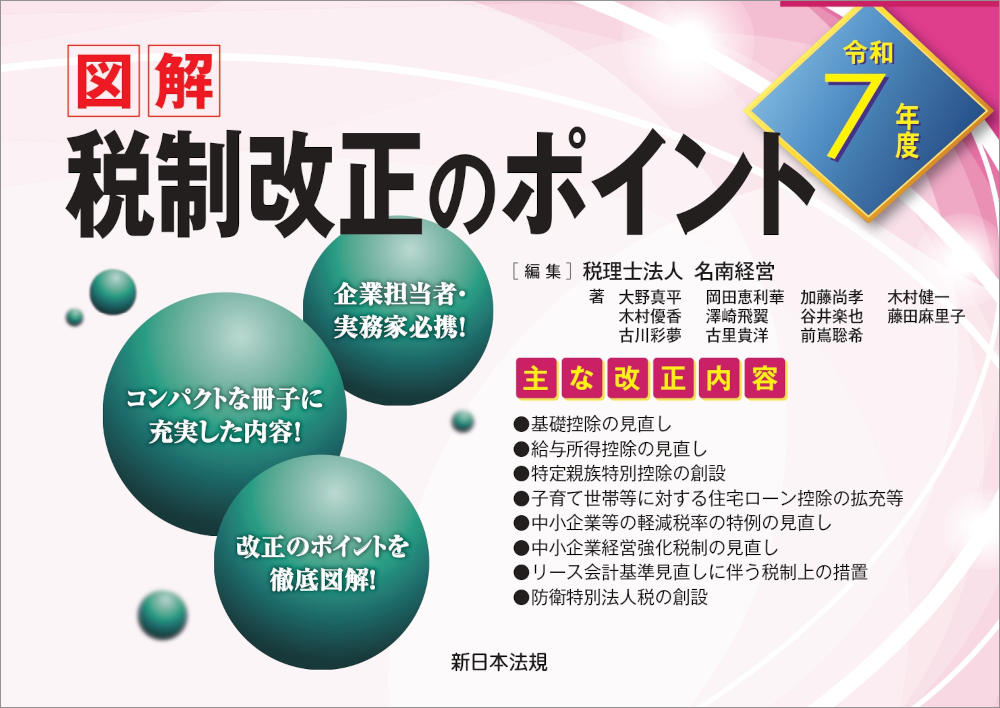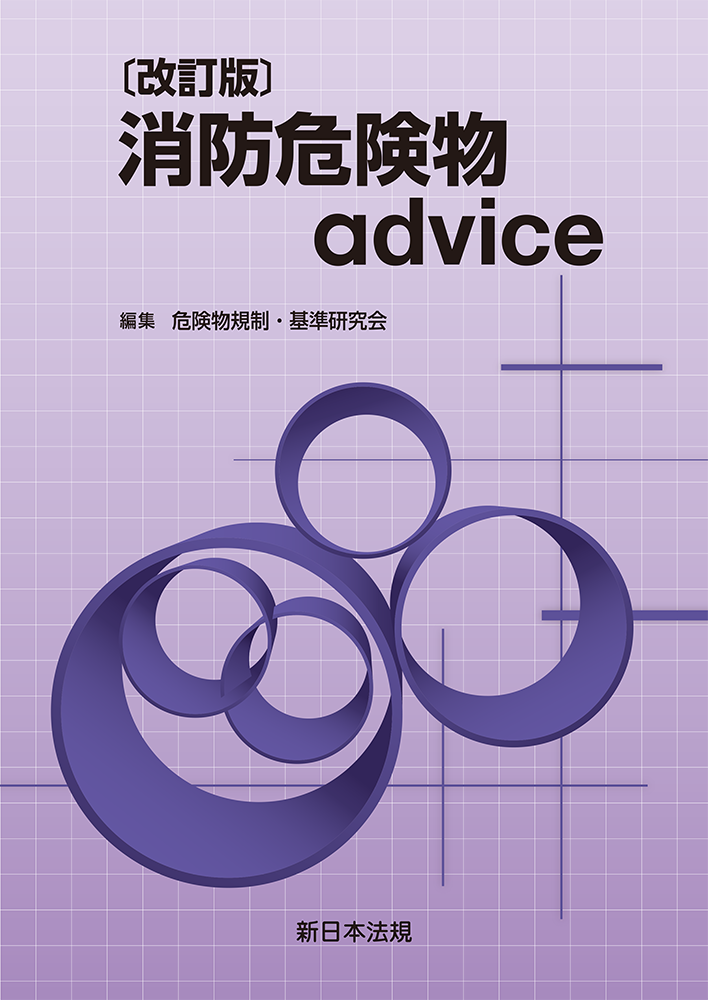解説記事2022年10月10日 未公開判決事例紹介 不服申立てを超えた税務署への働きかけ行為は不適切(2022年10月10日号・№949)
未公開判決事例紹介
不服申立てを超えた税務署への働きかけ行為は不適切
1,800万円請求も最終的な税理士報酬は約5万円
本誌946号4頁で紹介した業務委託報酬請求事件の判決について、一部仮名処理した上で紹介する。
○税理士とクライアントとの業務委託契約の内容が問題となり、税理士が報酬を請求した事件。東京地方裁判所(大濵寿美裁判官)は令和4年3月10日、税理士が不服申立手続を超えて税務署等に働きかける行為は不適切であり、内容を報酬対象業務と評価することはできないとの判断を示した(令和2年(ワ)第19350号)。税理士は還付金の20%相当額である約1,877万円をクライアントに請求したものの、裁判では、報酬は約5万5,000円しか認められなかった。
主 文
1 被告は、原告に対し、5万5000円及びこれに対する令和2年8月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを360分し、その1を被告の、その余を原告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告は、原告に対し、1877万5360円及びこれに対する令和2年8月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は、被告との間で締結した業務委託契約に基づき業務を行ったと主張する原告が、同契約に基づく報酬額あるいは報酬相当額及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和2年8月12日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 争いのない事実等(末尾に証拠を掲げたもの以外は、当事者間に争いがないか、弁論の全趣旨により容易に認められる。)
(1)当事者
原告は、各種税金の申告・申請、税務書類の作成、税務相談、税に関する不服審査手続等、会計及び税務に関する総合的なサービスの提供を取扱業務とする公認会計士・税理士である。
被告は、投資家であり、その投資業務に係る税務申告等を行っていたところ、後記の税務事務問題に関し、原告を紹介された。
(2)被告の納税とその減額更正等
ア 被告は、平成29年初め頃、平成26年分確定申告において、指数先物取引及び指数オプション取引の損失4億5472万4888円の計上を失念したことに気づき(以下、計上漏れ分を「本件損失額」という。)、平成29年3月、平成26年分の所得税及び復興特別所得税に係る更正の請求を行い、その損失が翌年に繰り越されたとして平成27年分の所得税及び復興特別所得税についても更正の請求を行った(甲2の1及び2。以下、平成26年分の更正の請求と平成27年分の更正の請求を併せて「本件更正請求」という。)。また、平成28年分及び平成29年分の確定申告(甲13、甲14)において、本件損失額の計上漏れがあったことを前提に、本件損失額の一部を雑所得の計算上繰越控除して申告した。
N税務署は、平成29年10月24日、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年分については、損失の金額の計算に関する明細書等を添付して確定申告書を提出する必要があるところ(租税特別措置法41条の15第1項及び第3項参照)、被告の平成26年分の確定申告書に本件損失額についての記載はなく、請求損失に係る計算書類の添付もないこと、損失が生じた年の翌年以降の年分については、その年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額、その年の前年以前3年内の各年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額等を併せて提出する申告書に記載しなければならないところ(同法施行令26条の26第4項参照)、平成27年分の確定申告書は平成28年3月に既に提出されており、そこには損失を認める記載がないため、「その後において連続して確定申告書を提出した」要件を満たしていないこと、したがって、被告の平成26年分及び平成27年分の所得税及び復興特別所得税について先物取引に係る繰越控除を適用することはできないことを理由として、本件更正請求について理由がない旨の通知(以下、「本件通知」といい、その書面(甲3の1及び2)を「本件通知書」という。)をした。なお、N税務署は、本件通知書に、不服申立てはこの通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に再調査の請求又は審査請求をすることができる旨記載された書面を添付していたが、被告担当者の不手際により本件通知書が被告に交付されなかったため、被告が本件通知を認識したときには、同通知に関する不服申立期間は経過していた。
また、N税務署は、平成26年分の更正の請求が認められないことを前提に、平成30年3月13日、平成28年分の更正及び加算税の賦課決定(追加納税額は、本税について4177万1900円、加算税について571万5500円)の通知(乙5)を、同年7月6日に平成29年分の更正及び加算税の賦課決定(追加納税額は、本税について3391万3000円、加算税について339万1000円)の通知(甲4)をそれぞれした(以下、平成28年分及び平成29年分の更正・賦課決定を併せて「本件更正・賦課決定」という。)。
イ 被告は、平成30年7月頃、原告を紹介され、前記アの件の善後策を相談した。なお、その結果、原告と被告がいかなる契約を締結したかについては、後記のとおり当事者間に争いがある。
被告は、同月19日、本件更正・賦課決定における本税を納付した上で、原告を代理人として、同年10月初旬、N税務署長に対し、本件通知及び平成29年分の更正・賦課決定に対する再調査請求を申し立てた(以下、この申立てを「本件再調査請求」と、その書面(甲16の1ないし3)を「本件再調査請求書」という。)。
その後の経緯等については後記のとおり当事者間に争いがあるが、N税務署は、平成26年分の損失計上を認め、平成27年分以後もその損失が繰り越されるため、平成26年分ないし平成29年分の所得税及び復興特別所得税の額を更正し、平成28年分については本税を4190万1700円、過少申告加算税を571万5500円減少する旨の、平成29年分については本税を2157万8300円、過少申告加算税を215万8000円減少する旨の、平成30年12月7日付の更正通知書(甲7の1ないし4)を被告に交付した(以下、この更正通知書を「本件更正通知書」と、その内容を「本件変更決定」という。)。なお、本件更正通知書には、このように変更した具体的理由は記載されていない。
2 争点及びこれに関する当事者の主張
(1)争点1(平成30年7月頃、原告と被告の間で、どのような内容の契約が締結されたのか)
【原告の主張】
原告と被告は、平成30年7月11日、本件更正・賦課決定によって被告が追加納税しなければならなくなった額を可能な限り減免させることを業務とし、減免額の20パーセント相当額を報酬額とすることを内容とする業務委託契約(以下「本件業務委託契約」という。)を締結した。
【被告の主張】
本件業務委託契約の締結の事実は否認する。
被告は、平成30年7月頃、原告に対して、本件更正・賦課決定の善後策、具体的には延滞税あるいは過少申告加算税を減免できないかということを相談したにすぎない。
なお、被告は、不服申立期限を徒過しないために、原告に対し、本件再調査請求書の提出を依頼している。ただし、これは、同月頃、被告が代表取締役を務める株式会社◯◯◯◯と原告、被告個人と原告との間でそれぞれ締結した顧問契約の業務内容(所得税等に関する相談対応等)の範囲内の業務である。
(2)争点2(本件変更決定は、原告の業務遂行によるものか)
【原告の主張】
原告は、本件業務委託契約締結後、元国税局職員である税理士などの協力を得た上で、T国税局やN税務署に赴いて税務当局と粘り強く折衝を重ねた。その結果、原告は、平成26年分及び平成27年分の確定申告における先物取引等に係る損失額の記載漏れによって租税特別措置法が定める先物取引等に係る損失額の繰越控除の適用を受けられなくなるとの税務当局の解釈及び運用が誤っていることについて、税務当局を説得し、これまでの実務運用を実質的に覆した。また、本件通知に関しては、行政不服審査法の定める再調査請求の期限が徒過していたため、本件再調査請求自体が却下される可能性が高い状況にあったが、原告は本件では再調査請求が許されるべき正当な理由があるとして、税務当局を説得し、再調査請求を受容させた。原告のこのような活動なくして、税務当局が一度下した処分を自主的に撤回・変更することなどあり得ない。
以上の原告の粘り強い活動の結果、被告は税額について合計9387万6800円もの減免を受けたのであるから、本件変更決定は原告の本件業務委託契約に基づく業務の遂行によるものといえる。
【被告の主張】
被告は原告から税務署に善処を求めることを勧められたが、原告が被告担当者を同行して平成30年7月19日と同月27日にN税務署及びT国税局を訪問して面談した際、N税務署は、東京高等裁判所の同年3月8日判決(以下「参考判決」という。)の存在を指摘し、善処など認められないと述べた。そこで、被告は、とりあえずは追加納税額(本税分)を納付し、後日、自ら税務署に赴いて説明を求めるつもりであった。
被告は、同年12月7日、本件更正通知書を受領した。被告は、N税務署から本件再調査請求の取下げを求められたことから、確認のため、平成31年1月、原告と共に同署担当者と直接面談した。被告は、同署担当者から、減額更正した理由について、税務署が間違っていたので更正した旨、誰が来ても結論は変わらない旨の説明を受けたことから、本件再調査請求を取り下げ、その後、追加納税していた本税分の還付を受けた。
本件更正通知書には減額更正した理由の記載はないが、課税庁は法定申告期限から5年間更正することができることからすると、本件再調査請求により本件を再検討し、参考判決との差異(参考判決の事案では、期限内申告を継続していなかったが、被告は本件更正請求の後、その数字に基づいて平成26年分、平成27年分は連続して、さらにそれを受けて平成28年分、平成29年分と毎年連続して繰越損失額を引き継いだ期限内確定申告をしていること)を検討して、減額更正をしたものと推測される。
以上からすれば、N税務署は自らの間違いに気づき、更正しただけであって、原告の働きかけによって更正したものではないといえる。
(3)争点3(原告の業務遂行にかかる報酬額等)
【原告の主張】
本件変更決定により、平成28年分の所得税等については合計6279万1350円、平成29年分の所得税等については合計3108万5450円減免され、両年度合わせた減免額の合計は9387万6800円となった。本件業務委託契約における報酬額は減免合計額の20パーセントであるから、被告が支払うべき報酬は1877万5360円である。
仮に本件業務委託契約の締結が認定されないとしても、被告は、原告が行った業務の相当報酬額を支払うべきであるから(商法512条)、その額は1000万円を下らない。
被告は、原告の業務遂行により多額の経済的利益を得ておきながら、原告の業務遂行が税法上の解釈や行政手続法的な観点から極めて画期的かつ異例の結果であると正しく評価せず、税務署が間違えたから法に従った対応をしたにすぎないと主張して報酬の支払を拒絶するが、そのようなことは信義則に反して許されない。
【被告の主張】
原告の主張は否認ないし争う。
原告が行ったのは再調査請求書の作成であるが、これは原告との業務委託契約の内容たる受任業務に含まれていないから、別個の契約に基づいて報酬が支払われることになるというべきである。
第3 当裁判所の判断
1 事実認定
前記第2の1、後掲証拠、証拠(甲10、甲15、乙16、乙17、乙20、K供述、原告供述、被告供述)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認定できる。
(1)被告は、平成29年初め頃、平成26年分の確定申告において本件損失額の計上を失念していたことに気づき、経理を手伝っていたK(以下「K」という。)の勧めにより、平成26年分及び平成27年分の確定申告について本件更正請求(甲2の1及び2)をした上、平成28年分と平成29年分について損失繰越調整後の数字を前提とした確定申告(甲13、甲14)をした。
N税務署は、平成29年10月24日付で、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年分については、損失の金額の計算に関する明細書等を添付して確定申告書を提出する必要があるところ、被告の平成26年分の確定申告書に本件損失額についての記載はなく、請求損失に係る計算書類の添付もないこと、損失が生じた年の翌年以降の年分については、その年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額、その年の前年以前3年内の各年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額等を併せて提出する申告書に記載しなければならないところ(同法施行令26条の26第4項参照)、平成27年分の確定申告書は平成28年3月に既に提出されており、そこには損失を認める記載がないため、「その後において連続して確定申告書を提出した」要件を満たしていないことなどの理由から、更正請求を認めない旨の本件通知(甲3の1及び2)をした。
また、N税務署は、平成26年分の更正の請求が認められないことを前提に、平成30年3月13日に平成28年分の更正及び加算税の賦課決定(乙5)を、同年7月6日に平成29年分の更正及び加算税の賦課決定(甲4)をした(両決定を併せて本件更正・賦課決定としている。)。
(2)被告は、Kが本件更正請求を被告に勧めたが更正が認められなかったことに動転して本件通知書を隠匿したため、平成30年7月7日になって本件更正・賦課決定を知った。
被告は、知り合いの税理士に相談したが、実際の対処はKと関係が全くない税理士に相談したいと考え、同月11日、知人から原告の紹介を受けて、原告に対し、本件更正・賦課決定について過少申告加算税や延滞税だけでも減額してほしいとの相談をした。
原告は、これを受けて、同月19日と同月27日、Kとともに、T国税局及びN税務署を訪問したが、T国税局は、申告内容についてはN税務署に相談するようにと述べ、N税務署は、本件通知書に記載のとおりである旨、その点に関しては参考判決がある旨述べた。被告は、T国税局から、不服申立てをするとしても本税が納付されればその後過少申告加算税及び延滞税は発生しないといわれたため、同月19日、追加本税分を納付した。その後、原告は、同年8月下旬にN税務署から参考判例の情報を得て、被告にも連絡するとともに、これを検討して対策を考えることにした(乙8の1、乙10)。
なお、被告は、Kが本件通知書を隠匿したため、Kが行っていた被告に係る経理業務に問題がないかを原告に確認してもらうことにして、同年8月1日付で、原告と被告の経営する株式会社との間及び原告と被告個人との間の、法人税等及び所得税等の税務代理業務等を内容とする業務委託契約を締結した。被告の経営する株式会社と原告との業務委託契約の固定顧問料は月額10万円とされ、被告個人と原告との業務委託契約の固定顧問料は定められなかった。(乙6、乙7)
(3)原告は、平成30年9月頃、被告に元国税局職員である税理士に税務署に交渉に行かせたいと申し出た。被告は、税務署側の感触をうかがう程度にしてほしい、交渉はさせないでほしいと述べた上で、白紙の委任状を作成し、原告に交付した。
その後原告は、他の税理士や元国税局職員である税理士と本件更正・賦課決定についての相談を重ねていた。
(4)原告は、平成30年10月頃、再調査請求人を被告、その代理人を原告とする本件再調査請求書を作成した。本件再調査請求書には、被告が、平成26年度の確定申告において、実際の損失額よりも過少な申告を行い、平成27年度も同様の申告をしたこと、被告は、平成26年、平成27年、平成28年及び平成29年の所得について所得税及び復興特別所得税の確定申告書を継続して提出しており、先物取引に係る損失の金額の計算に関する明細書も各年度において税務署に提出しているのであって、単純な勘違いにより申告書記載金額に誤りが生じたにすぎないこと、本件通知書には、租税特別措置法が定める「その後において連続して確定申告書を提出した」要件を満たさないとの記載があるが、「連続して確定申告書を提出する」という文言の意味を、当初の申告において記載が漏れた部分については、後の自発的修正を一切認めないと読むことはできないこと、本件通知書を第三者が隠匿していたため、被告が本件通知書を実際に確認したのは平成30年7月7日であるから、通知書を受領してから3か月以内の再調査請求といえることを理由として、本件更正請求を認めるよう再調査を依頼する旨の記載、あるいは、本件通知の時期の点の記載を除き、同様の内容を理由として、平成26年度の先物取引に係る損失額の発生実態を確認し、実態に即した損失の繰越しを認めるよう、平成29年分についての再調査を依頼する旨の記載があった。原告が被告に本件再調査請求書を提出することを提案したところ、被告がこれに署名押印したため、原告は同年10月5日に本件再調査請求書をN税務署に提出した。(甲16の1ないし3)
(5)N税務署は、平成26年分及び平成27年分については請求どおりに確定申告を更正する旨の、平成28年分及び平成29年分については平成26年分が更正されたことを前提として所得税及び復興特別所得税の額等の更正及び加算税を変更する旨の平成30年12月7日付の本件更正通知書(甲7の1ないし4)を被告に送付し、被告が納付していた追加本税分を還付すると連絡するとともに、本件再調査請求を取り下げるよう依頼した。なお、本件更正通知書には更正の理由は記載されていなかった。
同月の忘年会において、原告から3000万円の報酬を求められた被告は、原告が元国税局職員である税理士に正規の手続以外の方法を取らせ、そのために金員を使い、その結果本件変更決定がされたのではないか、そのために原告はこのような高額の報酬を請求しているのではないかと考えるに至り、N税務署から説明を受けるまでは追加納税分の還付は受けないことにした。
その後、被告は、原告とKとともにN税務署に赴き、同署の職員から、再度検討した結果、確定申告を連続して申告していなければ損失の繰越しができないという勘違いを前任者がしていたので、更正は認められるとの判断に至ったこと、元国税局職員が来たが、そのことと更正を認めることとの間に関係はないこと、更正を認めるので本件再調査請求を取り下げてほしいことなどを聞いた。被告は、更正請求を認めないとした本件通知は税務署の間違いであることを念押しして確認した後、本件再調査請求を取り下げ、納付していた追加本税分の還付を受けた。
2 争点1(平成30年7月頃、原告と被告の間で、どのような内容の契約が締結されたのか)について
前記1の認定事実によれば、原告と被告は、平成30年7月11日、本件変更・賦課決定を再考してもらうことを内容とする業務委託契約を締結したが、報酬についての合意はしなかったことが認められる。なお、原告と被告は、同年10月頃、上記の業務の具体的内容として、本件再調査請求の手続をとることにしたといえる。
原告は、口頭で、「被告が追加納税しなければならなくなった額を可能な限り減免させること」を業務とし、減免額の20パーセント相当額を報酬額とするとの内容の本件業務委託契約を締結した旨主張し、同旨の陳述あるいは供述する。しかし、業務の内容についていえば、法律に則った手続等のほかに、原告が税務署を説得して納税額を減免させることまで業務内容としていたとの事実を認定することはできない。また、原告は、被告との間で合計月額10万円の顧問契約について契約書(乙6、乙7)を作成しているところ、同じく被告との間で成功報酬を減免額の20パーセントとする契約、すなわち最大で2000万円程度の報酬額となる契約を締結しながらこれについては契約書等の書面を作成していないというのはあまりに不自然であるし、平成30年12月には3000万円を請求しているのであるから、「減免額の20パーセント相当額を業務報酬とする」との合意をしたとの事実を認定することもできない。
他方で、被告は、「平成30年7月頃、原告に本件更正・賦課決定の善後策を相談したにすぎない」、「本件再調査請求を依頼したが、これは平成30年7月頃に別途締結した業務委託契約(乙6、乙7)の対象業務である」と主張し、「今後課税理由について税務署に話を聞くためにとりあえず時効を中断しておく必要があるとの説明があったため、本件再調査請求に係る請求書に署名押印した」旨の陳述あるいは供述する。しかしながら、本件更正・賦課決定の善後策を相談した後、本件更正・賦課決定の善後策の具体化と思われる文言のある本件再調査請求書を示されて、これに署名押印している以上、被告は、平成30年7月頃に原告に依頼した業務内容の具体化として本件再調査請求の手続をとってもらうつもりであったというべきであって、上記の被告の主張は採用できない。
3 争点2(本件変更決定は、原告の業務遂行によるものか)について
前記1の認定事実によれば、原告は、被告との間の業務委託契約に基づく業務の具体化として、不服申立手続である再調査請求に係る請求書を作成し、被告を代理して再調査請求を申し立てたこと、N税務署がこれに基づき再調査をし、誤りを認めて更正したことが認められる。
原告は、それ以外にも、元国税局職員である税理士等の協力を得ながら、税務署等に対して折衝や説得等の働きかけを行い、これによって、税務当局はこれまでの実務運用を実質的に覆し、本来却下される可能性が高い再調査請求を受容させたと主張し、その旨陳述あるいは供述する。確かに、前記1の認定事実によれば、原告が元国税局職員等に依頼するなどして、税務署等への折衝等を行っていたことは認められる。しかしながら、法律上の不服申立手続を超えて税務署等に働きかける行為も、税務署等がそのような働きかけに応じる行為も不適切というべきであり、原告がそのような働きかけを行ったとしても、その内容を報酬対象業務と評価することはできない。そのことは、税理士業務要覧の資料(乙2、乙3)に、不服申立ての代理業務を行った場合、税額の減免額によって報酬が定まるものではない上、そもそも税理士報酬規定では、いわゆる成功報酬的な要素を一切排除している旨の記載があることからも明らかである。
4 争点3(原告の業務遂行にかかる報酬額等)について
前記2及び3のとおり、原告が行った報酬対象業務は本件再調査請求に係る請求書の作成と再調査請求の代理業務であるところ、平成9年11月に作成された税理士業務要覧の資料(乙1ないし乙3)によれば、不服申立ての代理報酬は、審査請求の場合は最高限度額が50万円、不服申立てに関する書類作成報酬の限度額が5万円であり、成功報酬的な要素は一切排除されるため、税額の減免に対する報酬は受けられないこととなっているといえる。
そこで、事案の内容、資料の収集、法令の適用等の調査等の内容を踏まえ(乙1参照)、原告の行った業務の相当報酬額を検討する。本件通知書の内容は、繰越控除の適用を受けるつもりがありながら、資料の存在を失念し、本件損失額を記載せず、これに係る資料を添付せず、翌年以降も失念した状態で確定申告を繰り返したときは、およそ後日の更正を一切認めないという明らかに誤った内容であって、その点を指摘する本件調査請求がなされたときは税務署が更正することになるのは当然といえる。そのことは、本件調査請求書が提出された数か月後にその旨の更正がされ、しかも、N税務署が、被告に対して同署職員の誤りであることを認めるとともに、本件再調査請求を取り下げるよう依頼したことからも裏付けられる。そうすると、本件再調査請求に係る手続の代理業務については5万円、本件再調査請求に係る書類の作成は5000円が相当な報酬というべきである。
第4 よって、原告の請求は、5万5000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和2年8月12日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限りで理由があるからその限りで認容し、その余は理由がないから棄却することとし、訴訟費用について民事訴訟法61条、64条を、仮執行宣言について同法259条1項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第32部
裁判官 大濵寿美
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.