解説記事2025年04月07日 最新判決研究 2段階の適格合併による欠損金の引継ぎと行為計算の否認(2025年4月7日号・№1069)
最新判決研究
2段階の適格合併による欠損金の引継ぎと行為計算の否認
東京地裁令和6年9月27日判決(令和3年(行ウ)第181号)
筑波大学名誉教授・弁護士・税理士 品川芳宣
一、事実
(1)X社(原告)は、ゴルフ場等を運営するP社をトップとするPグループの1社であるが、Pグループ内で行われた2段階の適格合併に係る未処理欠損金額の損金算入の可否が問題とされた。すなわち、Pグループ内で、平成29年に、まず、休眠会社で欠損金額57億8148万円余(以下「本件未処理欠損金額」という。)を有するA社を被合併法人とし、B社を合併法人とする「完全支配関係適格合併」(以下「本件合併1」という。)が行われ、次いで、B社を被合併法人とし、X社を合併法人とする「支配関係適格合併」(以下「本件合併2」といい、本件合併1と合わせて以下「本件各合併」という。)が行われた。そして、X社は、平成29年3月期分法人税につき、本件未処理欠損金を連結欠損金額とみなして確定申告をした。
これに対し、処分行政庁は、本件未処理欠損金額はX社の連結欠損金額とみなすことは認められないとして、法人税法132条の2の規定を適用して更正処分等(以下「本件更正等」という。)をした。X社は、これを不服として、不服申立ての前置を経て、国(被告)に対して、本件更正等を取り消すよう本訴を提起した。
(2)本件の2段階合併の概要(イメージ)は、図のとおりである。
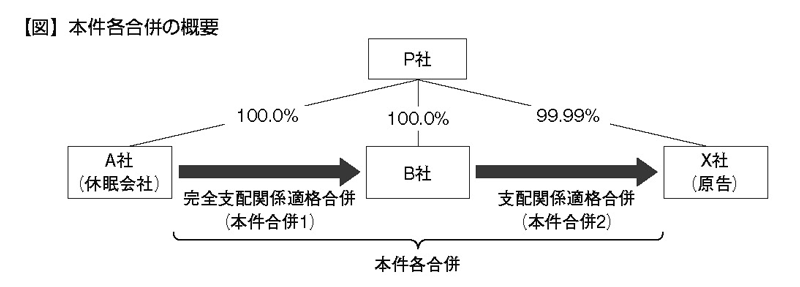
二、争点と当事者の主張
1 争 点
本件の争点は、本件更正等の適法性であり、具体的には、本件各合併が法人税法132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」(不当性要件)に該当するか否かである。
2 国の主張
(1)本件各合併は、A社の繰越欠損金を最終的にX社に引き継がせるための具体的な手順等をPグループ内において繰り返し検討した上で、X社を含む関係法人が、X社に本件未処理欠損金額を引き継がせること以外に事業上の必要性のない本件合併1を同日に差し挟んだ上で、本件合併2を行い、本件各合併を2段階に分けて実行するというあえてう遠な手順や方法をとることにより、本来は組織再編税制上の非適格合併であるX社とB社との合併が適格合併として取り扱われるという形式をあえて作出したもの(適格作り)ということができるものであって、明らかに不自然なものである。
(2)以上のとおり、本件各合併は、①通常は想定されない組織再編成の手順や方法に基づいたり、実態とは乖離した形式を作出したりするなど、不自然なものであり、②税負担の減少以外に合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在しないから、組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図し、組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるものと認められ、「組織再編税制に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるもの」といえるから、不当性要件に該当する。
3 X社の主張
(1)組織再編税制に当たっては、複数の法人を被合併法人とする吸収合併が同日に行われる場合があるが、会社法上3社以上を同時に合併させる場合には、複数の合併を同日に行うものと解されており、そのような3社以上の合併(三社合併)を行うに当たっては、当事者が個々の合併に自由に順位を付することができる。そして、複数の吸収合併を行う際に、互いの吸収合併の効力発生に条件や順位を付けることは、極めて一般的な方法であり、実務上も行われているところである。
(2)前記のとおり、複数の合併に条件や順位を付けることは全く問題なく認められており、複数の実例も存在するところ、Pグループがグループ内において本件各合併を行うに当たり、X社にはC社という外部株主が存在していた。そのため、X社を合併法人とし、A社及びB社を被合併法人とする吸収合併を行う場合には、X社とA社との合併比率及びX社とB社との合併比率をそれぞれ計算した上で、B社に対し、A社とB社の2社分の株式について、X社の株式を割り当てることが必要となるところ、P社の100%子会社(孫会社)であり外部株主が存在しないA社とB社との合併を第一合併として先行させ、同日、第一合併の効力発生を停止条件とする第二合併としてX社とその100%子会社3社及び第一合併後のB社とを合併させれば、B社の1社分の株式についてのみX社の株式を割り当てれば足りることとなる。そのため、ゴルフ事業を営み収益力を有するA社とB社を先に合併させた上で、X社との合併を行うことが適当と考えられた。
(3)以上のとおり、本件各合併は、Pグループのビジネスモデルに基づく正当なビジネス上の行為であり、およそ、組織再編税制に係る各規定を租税回避の手段として濫用するものではない。
したがって、本件各合併は、組織再編税制に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものではなく、不当性要件に該当しない。
三、判決要旨
請求認容。
(1)Pグループにおいては、経営危機に陥るなどしたゴルフ場運営法人を買収して規模を拡大させ、多数のゴルフ場を本部で集中管理し、ゴルフ用品等を一括購入するなどしてスケールメリットを追求するとともに、買収により増え続ける子会社の数を合併により削減することにより、経営の合理化・効率化を追求するというビジネスモデル(本件ビジネスモデル)の下、事業を営んでいる。
なお、ここでいう経営の合理化・効率化とは、単に、一括購入による調達費用の削減や税務申告コストの削減等にとどまらず、経営に係る意思決定や監査の迅速化・合理化・効率化を包含するものである。
Pグループは、本件ビジネスモデルに基づき、本件各合併の10年以上前から、買収によってP社の子会社の数がある程度増える都度、グループ内での吸収合併を繰り返し、最終的にはX社にこれらの会社を吸収合併させることによってゴルフ場の保有機能をX社に集約させつつ、P社の子会社の数を削減するための合併を繰り返していた。このような合併に当たり、ゴルフ場事業を営んでいない法人も合併の対象となったほか、合併に伴って被合併法人から合併法人へ未処理欠損金額が引き継がれない合併も複数あった。
こうして買収と吸収合併が繰り返された結果、平成17年から本件各合併の日(効力発生日)の前年である平成28年までの間に、Pグループでは、合計46の法人を取得又は設立する一方、合計53ものゴルフ場保有子会社等が吸収合併され(他に、他社に売却した法人が1社)、毎年末のグループ内の法人数は、平成18年末の36をピークに、おおむね右肩下がりに減少し、平成28年末の時点では15であった。
また、本件合併1を決議した、A社及びB社における平成28年12月26日付けの各臨時株主総会議事録には、本件合併1の「合併目的」につき、それぞれ、「2社を合併することにより、事務管理費の削減と経営効率の向上を図るため」と記載されている。
そして、本件合併2を決議した、X社、A社、B社、C社及びP社における平成28年12月26日付けの各臨時株主総会議事録には、本件合併2の「合併目的」につき、それぞれ、「B社を合併することにより、事務管理費の削減と経営効率の向上を図るため」と記載されている。
(2)組織再編成においては、実務上、複数の法人を被合併法人とする合併が同日に行われる場合があるが、会社法上、吸収合併は、単一の存続会社と単一の消滅会社との間で行われるものと整理されていることから(会社法2条27号、749条参照)、2社以上の消滅会社と単一の存続会社との間で一体のものとして吸収合併を行う場合であっても、各消滅会社と存続会社との間で各別に吸収合併が行われるものとして整理されることとなり、吸収合併契約も消滅会社ごとに各別のものとして存在することとなる。
そして、このような複数の吸収合併を実質的に一体のものとして行うため、実務上、同日付けで複数の吸収合併を実施する場合には、例えば、第1合併の効力発生を停止条件として第2合併を実行するなど、各吸収合併に順序を付し、その効力発生に条件を付けるという方法が一般に採られている。
(3)組織再編成は、その形態や方法が複雑かつ多様であるため、これを利用する巧妙な租税回避行為が行われやすく、租税回避の手段として濫用されるおそれがあることから、法人税法132条の2は、税負担の公平を維持するため、組織再編成において法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる行為又は計算が行われた場合に、それを正常な行為又は計算に引き直して法人税の更正又は決定を行う権限を税務署長に認めたものと解され、組織再編成に係る租税回避を包括的に防止する規定として設けられたものである。このような同条の趣旨及び目的からすれば、同条にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは、法人の行為又は計算が組織再編税制に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものであることをいうと解すべきであり、その濫用の有無の判断に当たっては、①当該法人の行為又は計算が、通常は想定されない組織再編成の手順や方法に基づいたり、実態とは乖離した形式を作出したりするなど、不自然なものであるかどうか、②税負担の減少以外にそのような行為又は計算を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮した上で、当該行為又は計算が、組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって、組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるもの又は免れるものと認められるか否かという観点から判断するのが相当である。
そして、①適格合併が行われた結果、未処理欠損金額が引き継がれ、租税負担が減少する場合があるというのは、組織再編成税制が予定しているものであること(むしろ、適格合併の場合に譲渡損益の計上を繰り延べて従前の課税関係を継続させることは、組織再編税制の趣旨そのものである。)、②利益を生み出し、これを株主に対して還元することを究極の目的とする株式会社において、一定規模以上の取引をするに当たり、税務上の影響を全く考慮しないことは考え難く、むしろ、かかる考慮をしないで取引を行えば、取締役の責任を追及される事態も生じかねないのであって、株式会社が事業の目的に沿って種々の経済活動を遂行するに当たり、業務の管理・遂行上、財務上又は税務上等の様々な観点から利益を最大化し得る方法を法令の許容する範囲内で自由に選択することができると解されることからすると、行為・計算の不自然性が全く認められない場合や、そのような行為・計算を行うことの合理的な理由となる事業目的等が十分に存在すると認められる場合には、他の事情を考慮するまでもなく、組織再編税制に係る各規定を租税回避の手段として濫用したものということはできず、不当性要件に該当すると判断することは困難である。
(4)平成13年度税制改正により導入された組織再編税制の基本的な考え方は、実態に合った課税を行うという観点から、原則として、移転資産等についてその譲渡損益の計上を求めつつ、組織再編成により資産を移転する前後で経済実態に実質的な変更がない場合には、その譲渡損益の計上を繰り延べて従前の課税関係を継続させるというものであり、この考え方に基づき、組織再編成において、移転資産に対する支配が再編成後も継続していると認められるものについては、経済実態に実質的な変更がないことから、移転資産の譲渡損益の計上を繰り延べることとしたものである。
また、法人税法57条2項等の適用の前提の一つである適格合併については、同法2条12号の8において定義されているところ、適格合併には、大別して、企業グループ内の適格合併((完全支配関係適格合併)及び(支配関係適格合併))と共同事業を営むための適格合併(共同事業適格合併)がある。同条及びこれを受けた法人税法施行令においては、完全支配関係適格合併、支配関係適格合併及び共同事業適格合併のいずれについても、移転資産の対価として株式又は出資以外の資産の交付がされないこと(合併対価要件)が要件とされているところ、これは、株式又は出資以外の資産の交付がされる場合には、その経済実態は通常の売買取引と異なるところがなく、組織再編制の前後で経済実態に実質的な変更がないとはいえないためであると解される。
そして、企業グループ内の適格合併のうち、支配関係があるにすぎない場合(支配関係適格合併)には、上記要件に加えて、従業者引継要件及び事業継続要件が必要とされており、共同事業適格合併については、更に共同事業要件が必要とされているが、完全支配関係適格合併については、同法2条12号の8イの文言上、これら従業者引継要件及び事業継続要件等のいずれについても必要とされていない。
この点に関し、税制調査会法人課税小委員会(小委員会)が平成12年に組織再編税制について議論した際、組織再編成の前後で経済実態に実質的な変更がない場合には、その譲渡損益の計上を繰り延べて従前の課税関係を継続させるという組織再編税制の基本的な考え方を基に、経済実態に実質的な変更がないか否かは、移転資産等に対する支配の継続の有無によって判断することとされた上で、資産の移転等を「個別の資産の売買取引と区別する観点」から、「資産の移転が独立した事業単位で行われること」と「組織再編成後も移転した事業が継続すること」を要件とすることが必要とされつつ、「ただし、完全に一体と考えられる持合割合の極めて高い法人間で行う組織再編成については、これらの要件を緩和することも考えられる。」との見解が示されていた。このように、小委員会において示された組織再編税制の基本的な考え方は、飽くまで、組織再編成の前後で経済実態に実質的な変更がない場合には、その譲渡損益の計上を繰り延べて従前の課税関係を継続させるというものであり、この観点から、移転資産等に対する支配が組織再編成後も継続しているものについて、譲渡損益の計上を繰り延べるというものであって、「資産の移転が独立した事業単位で行われること」と「組織再編成後も移転した事業が継続すること」が必要とされたのは、「個別の資産の売買取引と区別する観点」からにすぎない。
以上によれば、組織再編税制に係る法人税法57条2項等の趣旨及び目的は、組織再編成により資産を移転する前後で経済実態に実質的な変更がない場合には、その譲渡損益の計上を繰り延べて従前の課税関係を継続させるというものであり、経済実態に実質的な変更がないか否かを判断するなどのために、法人税法2条12号の8及びこれを受けた法人税法施行令4条の3等において、適格合併と判断するための具体的な要件が定められているものと認められる。
これらの事情によれば、組織再編税制の立法に当たっては、小委員会の前記の見解も踏まえた上で、前記のような完全子会社の吸収合併の場合も含め、完全支配関係があり対価要件を満たす法人間の合併の場合には、基本的に、合併の前後で経済実態に実質的な変更がなく、個別の資産の売買取引との区別も問題とならないことから、支配関係適格合併及び共同事業適格合併とは異なる、より緩和された適格合併の要件があえて定められ、従業員引継要件及び事業継続要件が必要とされなかったと解するのが相当であって、法令上、上記のような合併の場合に組織再編税制の適用を一律に否定するとの趣旨を読み取ることはできない。
(5)X社がB社らを吸収合併したのは、Pグループの採用する本件ビジネスモデルに基づくものと認められ、特に不自然なものではなく、かつ、合理的な理由となる事業目的が十分に認められる。また、B社をPグループ内の既存法人に吸収合併することに合理的な理由となる事業目的が十分に存在する上、何ら不自然なものではないといえることは、前記のとおりである。
もっとも、本件各合併は、いずれも平成29年に行われたものであるが、B社を合併法人、A社を被合併法人とする本件合併1の効力発生を停止条件として、X社を合併法人、B社らを被合併法人とする本件合併2の効力が発生することとされており、本件未処理欠損金額を有していたA社をX社が直接合併するのではなく、A社を吸収合併した後のB社とX社が合併するという2段階で実施されたものである。
そこで、以下、このようなスキームで実行された本件各合併につき、組織再編税制に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものに当たるか否かを検討する。
株式会社の合併には、取締役会決議や株主総会決議を要し、合併後は商業登記手続等を要することなどから、複数の株式会社を吸収合併しようとする際は、同一の機会にこれを行うのが効率的であると考えられ、実際、複数の法人を被合併法人とする合併が同日に行われる例が見受けられる。しかし、会社法上、吸収合併は、単一の存続会社と単一の消滅会社との間で行われるものと整理されていることから、2社以上の消滅会社と単一の存続会社との間で一体のものとして吸収合併を行う場合であっても、各消滅会社と存続会社との間で各別に吸収合併が行われるものと整理され、吸収合併契約も消滅会社ごとに各別のものとして存在することとなっており、このような複数の吸収合併を実質的に一体のものとして行うため、実務上、同日付けで複数の吸収合併を実施する場合には、例えば、第一合併の効力発生を停止条件として第二合併を実行するなど、各吸収合併に順序を付し、その効力発生に条件を付けるという方法が採られている。このような順序及び条件の付いた合併としては、単一の存続会社が複数の消滅会社を同日に吸収合併するものだけでなく、A社をB社が吸収合併し、その効力発生を停止条件として、同日付けでB社をC社が合併するという、2段階にわたる重層的な合併も行われている。
したがって、本件各合併が2段階で行われたからといって、必ずしも、通常は想定されない手順や方法が採られたということはできない。
しかも、A社とB社には外部株主が存在しないのに対し、X社には外部株主(C社)が存在していたから、①本件各合併のスキームを採れば、C社に対しては、B社の1社分の株式についてのみ、X社の株式を割当て交付すれば足りるのに対し、②仮に本件合併1を経ずに、A社及びB社をそれぞれ被合併法人とし、X社を合併法人とする各合併を実施した場合には、X社とA社との合併比率及びX社とB社との合併比率をそれぞれ計算した上で、C社に対してA社とB社の2社分の株式について、X社の株式を割り当てることが必要となると認められ、この点において、一定の事務の煩雑さがあることは否めない。
(6)以上を総合すると、B社がA社を吸収合併し(本件合併1)、その効力発生を停止条件として、X社がB社らを吸収合併する(本件合併2)という本件各合併について、その各部分を個別にみた場合においても、その全体をみた場合においても、「通常は想定されない組織再編成の手順や方法に基づくもの」でも「実態とは乖離した形式を作出したりするもの」でもなく、何ら不自然なものとはいえないし、かかるスキームを採用して合併を行うことの「合理的な理由となる事業目的その他の事由」が存在することからすると、組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるものとは認められない。
したがって、本件各合併は、組織再編税制に係る法人税法57条2項等の各規定を租税回避の手段として濫用することによって法人税の負担を減少させるものとはいえず、「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」(同法132条の2)に当たるということはできないから、これに該当することを前提に行われた本件更正等は、いずれも違法である。
四、解説
はじめに
本件は、ゴルフ場等の経営・管理等を業とする会社グループ内において、同日に2段階に渡って行われた合併における未処理欠損金の引継ぎとその損金算入に関し、法人税法132条の2の規定(行為計算の否認)を適用した課税処分(本件更正等)が行われ、その適否が争われた事件である。この場合、組織再編成税制そのものが、合併等の組織再編成に関し帳簿価額の引継等による租税負担の軽減(繰延べ)を目的としていることもあって、それぞれの各組織再編成において、「法人税の負担を減少させる結果と認められるもの」をどう判断するかは種々の問題を伴うことになる。
他方、組織再編成は、その段階で損益を計上しないで済むということ等もあって、種々の経営目的に適合することになり、その利用方法も多様化している。そのことは、組織再編成税制を活用する機会が多くなり、法人税法132条の2の規定の適用の可否も問題になることが多くなる。この場合、経営目的に適合した組織再編成においては、法人税法132条の2の規定の適用要件とされる「不自然」又は「不合理」の判断が一層困難になると考えられる。
本件においても、ゴルフ場の経営・管理を目的とする企業グループ内においては、その目的を達成するため、他社の買収や傘下の会社間の合併等は常時行われている中で、本件各合併における未処理欠損金の処理が問題となったものであり、そのこと自体は、経営目的に適った合理的な処理と言える。そのためか、本判決は、その経営目的を評価し、本件更正等を取消し、X社の請求を認容した。このような判決は、一つの事例として理解できるのであるが、組織再編成においては、企業側も巧妙な経営計画の下に租税負担の回避を企図してきているだけに、納得し難いところもある。いずれにしても、法人税法132条の2の規定の適用のあり方が一層難しくなってきているので、以下、それらの問題を整理した上で、本判決の是非を検討することとする。
1 組織再編成税制の趣旨と問題点
(1)平成13年度税制改正において導入された組織再編成税制以前の法人税法(以下「法」という。)においては、個々の法人を納税主体とする完全な単体課税制度が採用されており、かつ、各法人の取引による資産及び負債の移転(移動)は、原則として、それらの価額(時価)によって測定されることになっていた(法法22②参照)。その唯一の例外として、圧縮記帳制度が設けられていた(法法42~51参照)。
また、繰越欠損金の損金算入についても、被合併法人からの引継ぎも認められることはなかった。すなわち、最高裁昭和43年5月2日第一小法廷判決(民集22巻5号1067頁)は、「欠損金額の繰越控除は、それら事業年度の間に経理方法に一貫した同一性が継続維持されることを前提としてはじめて認めるのを妥当とされる性質のものであって、合併会社に被合併会社の経理関係全体がそのまま継続するものとは考えられない合併について、所論の特典の承継は否定せざるをえない。合併会社とは無関係な経営のものに生じた被合併会社の既往の欠損金額を合併によりこれと経営を異にする合併会社に承継利用させる合理的な理由は、通常の場合見いだしがたく、また、被合併会社の欠損金額は、合併会社において受入資産の価額の定め方によって当然調整できるものであるから、普通には欠損金額の引継などを考慮する必要もないのである。」と判示していた。
更に、被合併法人の繰越欠損金の引継問題については、多額な繰越欠損金を有している法人を合併法人とする手法も用いられることもあったが、そのような逆さ合併による事実上の繰越欠損金の引継についても、異常な合併であって実質上存続会社が同一性を保持しているとはいえない租税回避手続であるとして判例上否定されてきた(注1)。
(2)ところが、組織再編税制においては、前述のような課税制度を一変させた。まず、第二編第1章第1節(課税標準及びその計算)に、「第6款 組織再編成に係る所得の金額の計算」を設け、法62条1項に、「内国法人が合併又は分割により合併法人又は分割承継法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該合併又は分割の時の価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。」と定めた。これは、本件改正前の所得金額の計算の考え方を承継し、確認的に定めたものと考えられる。
しかしながら、法が定めた要件を充足した適格合併、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資等(法2・十二の八、十二の十一~十八)については、当該合併等における資産及び負債の移転について、それらの帳簿価額による引継(評価損益の繰延べ)を認めることとした(法62の2~62の6)。
このような組織再編税制の導入について、国税当局の担当者は、企業法制の整備等に対応するとして、次のように説明している(注2)。
「このような状況を踏まえ、税制においても、我が国の経済社会の構造変化に対応した税制を創設すべく、合併、分割、現物出資、事業設立及びみなし配当を中心として、組織再編の全般にわたる抜本的な見直しを行うこととされました。」
また、組織再編税制の基本的考え方について、同担当者は、次のように説明している(注3)。
「平成13年度改正後の新しい組織再編成に係る税制は、実態に合った課税を行うという税制の基本を踏まえ、原則として、組織再編成により移転する資産等についてその譲渡損益の計上を求めつつ、特例として、移転資産等に対する支配が継続している場合には、その譲渡損益の計上を繰り延べて従前の課税関係を継続させる、という基本的な考え方に基づき創られています。」
以上の国税担当者の立法趣旨の説明については、法人税についての所得金額算定の理念の検討よりも、組織再編による経済活動の活発化を図ろうとする経済界の要請を優先せざるを得なかったことが窺える。そのことは、組織再編成税制それ自体、法人の租税負担の最少化の機会を多く与えたことを意味し、本件のような租税回避的事件を惹起することにもなる。
2 被合併法人の繰越欠損金の引継
(1)組織再編成における税制上の措置は、前述のような移転資産等の譲渡損益の繰延べにとどまらず、各種引当金、繰越欠損金の引継等にも及ぶことになる。そこで、前述の国税担当者は、「組織再編成に伴う各種引当金等の取扱いについては、基本的には、移転資産等の譲渡損益に係る取扱いに合わせて、従前の課税関係を継続させることとするか否かを決めるものとされています。」(注4)と説明している。この「各種引当金等」の中に、繰越欠損金が含まれることになるのであるが、むしろ、繰越欠損金の取扱いが最も注目されることとなった。
かくして、法57条は、青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しを定めているところであるが、組織再編税制の導入に伴い次のように改められることになった。
まず、法57条2項は、適格合併等が行われた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人又は分割法人の当該適格合併等の日前10年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額(以下「未処理欠損金額」という。)について、当該合併法人等において生じた欠損金とみなして、法57条1項の規定を適用することとした。
(2)しかし、このような法57条2項の規定のみでは、欠損金の繰越控除が悪用され易いことを慮って、法57条3項は、適格合併等に係る被合併法人等と合併法人等との間に特定資本関係(いずれか一方の法人が発行済株式数の50%超を支配する等の関係をいう。)があり、かつ、当該特定資本関係が当該合併法人等の当該適格合併等に係る合併等事業年度開始の日の5年前の日以後に生じている場合において、当該適格合併等が共同で事業を営むための適格合併等として政令で定めるものに該当しないときは、前項に規定する未処理欠損金額には、当該被合併法人等の次に掲げる欠損金を含まないことにしている。
すなわち、合併法人等の欠損金の繰越控除の対象になるための被合併法人等の未処理欠損金額の範囲については、次の要件を満たす必要がある(法57③、法令112③)。
① 適格合併等に係る被合併法人等の被合併等事業と当該適格合併法人等に係る合併法人等の合併等事業とが相互に関連するものであること(事業の相互関連性要件)。
② 適格合併等に係る被合併法人等の当該適格合併等の前における特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。)である者のいずれかの者(当該被合併法人等が当該適格合併等に係る合併法人等と特定資本関係が生じた日前において当該合併法人等の役員であった者に限る。)と当該合併法人等の当該適格合併等の前における特定役員であるもののいずれかの者とが当該適格合併等の後に当該合併法人等の特定役員となることが見込まれていること(特定役員引継要件)。
3 法132条の2の規定の意義とその解釈
(1)租税法の定める課税要件は、各種の私的経済活動等を基にしており、それらの経済活動等は、第一次的には、私的自治の原則ないし契約自由の原則が支配している私法によって律せられている。かくして、「このような私法上の選択可能性を利用し、私的経済取引プロパーの見地からは合理的理由がないのに、通常用いられない法形式を選択することによって、結果的には意図した経済的目的ないし経済的成果を実現しながら、通常用いられる法形式に対応する課税要件の充足を免れ、もって税負担を減少させあるいは排除すること」(注5)を、一般に、租税回避(行為)と称される。
このような租税回避に対する包括的否認規定として、同族会社等の行為又は計算の否認規定(法132、所法157、相法64)がある。
(2)このような同族会社等の行為又は計算の否認規定については、昭和37年の国税通則法の制定の際、国税通則法制定答申において、当該否認規定の拡充と租税回避に対する一般的否認規定の創設が提言されたことがある(注6)。しかし、当該一般的否認規定は立法化されることはなかったが、当時、国税当局は、同族会社等の行為又は計算の否認規定は確認的規定であると解して、同族会社以外の者に対しても不当な租税回避を否認する課税処分を行い、当該課税処分が下級審段階では支持されたこともある(注7)。
かくして、当該否認規定をめぐって確認的規定説と効力的規定説の対立と論争を惹起したのであるが、当該論争が最高裁判決によって決着がつく前に、法132条の2が創設された。これは、前述の論争について、国自身が、立法によって、確認的規定説を否定し、自己に不利な解決を図ったものと言える。
(3)かくして、法132条の2は、「税務署長は、合併、分割、現物出資若しくは事後設立(〈略〉)又は株式交換若しくは株式移転(以下この条において「合併等」という。)に係る次に掲げる法人の法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には、合併等により移転する資産及び負債の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の増加、……の事由により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。」と定め、「次に掲げる法人」について、「合併等をした一方の法人又は他方の法人」等を掲げている。
以上の法132条の2の規定は、法132条の規定に類似するものであるが、両者の差異は、対象となる法人の範囲、「法人税の負担を不当に減少させる」事由について、法132条の2が、「合併等により移転する資産及び負債に係る利益の額の減少」等に限定していること等である。
(4)ところで、法132条の2に規定する「法人税の負担を不当に減少させる」は、法132条に規定する「法人税の負担を不当に減少させる」と同じ用語であるから、法132条の場合と同義と解される。
この点、従前の法132条の解釈については、当該不当性の判断について、主として、次の説によっていた。
① 非同族会社基準説(非同族会社では通常なしえないような行為・計算、すなわち同族会社なるが故に容易になし得る行為・計算がこれに当たる。)(注8)
② 純経済人説(純経済人の行為として不合理・不自然な行為・計算がこれに当たる。)(注9)
しかしながら、最近の租税回避事件を考慮してみるに、このような各説に当てはめて「法人税の負担を不当に減少させる」か否かを判断することが極めて困難になっていると考えられる。けだし、同族会社であれ、非同族会社であれ、租税が経済取引におけるコストであると解されているようになっているから、いずれも当該コストの削減(回避)を画策することとなり、また、純経済人であるということは、経済取引における税コストを最小にすることを目的とすることに合理性があると考えられるからである(注10)。
そのため、最近の裁判例等では、前記のような2説ではなく、法132条の2の立法趣旨を考慮した上で、当該事案に対応している。例えば、本判決も引用している最高裁平成28年2月29日第一小法廷判決(民集70巻2号242頁)(注11)は、本件と同様に被合併法人の未処理欠損金の引継ぎ(損金算入)を否認した事件について、次のように判示している。
「同条にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは、法人の行為又は計算が組織再編成に関する税制(以下「組織再編税制」という。)に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものであることをいうと解すべきであり、その濫用の有無の判断に当たっては、①当該法人の行為又は計算が、通常は想定されない組織再編成の手順や方法に基づいたり、実態とは乖離した形式を作出したりするなど、不自然なものであるかどうか、②税負担の減少以外にそのような行為又は計算を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮した上で、当該行為又は計算が、組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって、組織再編税制に係る各規定の本体の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるもの又は免れるものと認められるか否かという観点から判断するのが相当である。」
この判決では、「意図したもの」という主観的要件を採用しているが、これに固執すると租税回避と脱税との区分を困難にする。よって、この主観的要件は必要条件ではなく十分条件であると解すべきであろう。
また、法132条を適用した事件に係る判決ではあるが、最近の最高裁判決として、令和4年4月21日第一小法廷判決(民集76巻4号480頁)(注12)は、次のように判示している。
「このような同項(編注:法人税法132条1項)の趣旨及び内容に鑑みると、同項にいう「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは、同族会社等の行為又は計算のうち、経済的かつ実質的な見地において不自然、不合理なもの、すなわち経済的合理性を欠くものであって、法人税の負担を減少させる結果となるものをいうと解するのが相当である。」
4 本件における否認規定適用の可否
(1)本件各合併等が行われた平成20年代は、ゴルフ場経営の選別が激しかった頃であり、経営悪化に苦しむゴルフ場と業績を維持できたゴルフ場とに二分化していた。その頃に、Pグループは、経営危機に陥ったゴルフ場運営法人を買収し、多数のゴルフ場を集中管理し、スケールメリットを追求するとともに、買収した子会社を合併により消滅させることにより、経営の合理化・効率化を追求するというビジネスモデル(本件ビジネスモデル)の下、事業を営んでいた。そこには、当然、税務上のメリットも考慮されていたはずである。このような本件ビジネスモデルは、不況下にあったゴルフ場業界にあっては、リーダー的存在であった。
本件各合併も、本件ビジネスモデルの一環として行われたものであるが、本件合併1と本件合併2が同時に行われ、かつ、X社の本件未処理欠損金額(約57億円)控除前の所得金額が80億円を超える状況にあったため、余りにも税務上のメリットが際立つことになった。そのため、本件更正等が行われることとなり、国も、本訴において、「本件各合併は、通常は想定されない組織再編成の手順や方法に基づくものであり、実態としては、事業の移転・継続を伴わないものである以上、実態とは乖離した適格合併の形式を作出するものであって、明らかに不自然なものである」等を主張している。
(2)これに対し、本判決は、Pグループの経営の実態を具さに認定した上で、「株式会社が事業の目的に沿って種々の経済活動を遂行するに当たり、業務の管理・遂行上、財務上又は税務上等の様々な観点から、利益を最大化し得る方法を法令の許容する範囲内で自由に選択することができると解される」と判示した上で、「本件各合併について、その各部分を個別にみた場合においても、その全体をみた場合においても、「通常は想定されない組織再編成の手順や方法に基づくもの」でも、「実態とは乖離した形式を作出したりするもの」でもなく、何ら不自然なものとはいえないし、かかるスキームを採用して合併を行うことの「合理的な理由となる事業目的その他の事由」が存在することからすると、組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的を逸脱する態様でその適用を受けるものとは認められない。」と結論づけた。
(3)このような判断については、Pグループにおける本件ビジネスモデルがゴルフ場業界において評価されるところ、本件各合併が本件ビジネスモデルの一環として行われたことを重視すれば、特に、その合理性については是認し得るところであろう。しかしながら、本件合併1と本件合併2の関係からのみ考察すれば、実質的には、X社がA社を吸収合併して多額な本件未処理欠損金を引き継ぐことによって税務上のメリットを享受したものであり、X社とA社との間には事業の関係性も継続性も認められないことからすると、法人税法132条の2に定める「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当するものとも考えられる。
ともあれ、法人税法132条の2又は同法132条に定める「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に係る不自然・不合理性の裁判上の判断は、当該裁判官の自由心証によるところ、最近の裁判例では、企業グループ内のビジネスモデルの一環として行われている場合には、当該ビジネスモデルを高く評価し勝ちであるようにも考えられる。
例えば、前掲の最高裁平成28年2月29日判決の事案では、単独で適格合併が行われ、被合併法人の巨額な未処理欠損金額が引き継がれたのであるが、前掲判決は、被合併法人との事業等の継続性がないということで、当該課税処分を維持している。
他方、前掲最高裁令和4年4月21日判決の事案では、音楽事業を国際的に展開するフランス法人の同族会社グループの詳細な経営計画の一環として、同グループ内の内国法人が他のグループ内法人から高利息借入れをした場合に、前掲判決は、前記経営計画を高く評価し、当該高利息借入れにつき行為計算の否認をした課税処分を取り消している。
このような各事例を考察してみると、本判決は前掲最高裁令和4年4月21日判決の影響を受けているようにも考えられる。もっとも、組織再編成税制自体が、前述したように、課税の繰り延べという税負担の軽減を立法趣旨にしているが故に、どのような事実関係があれば、「法人税の負担を不当に減少させる結果となる」と判定し得るかについては、当該事件の当事者に困難な判断を求めることになろう。
なお、本件については、国が控訴しているようであるので控訴審の行方が注目される。
(注1)大阪高裁昭和38年12月10日判決(行裁例集14巻12号2158頁)等参照。
(注2)藤本哲也、朝長英樹「法人税法の改正」「平成13年 改正税法のすべて」(国税庁)132頁。
(注3)前出(注2)134頁。
(注4)前出(注2)134頁。
(注5)金子宏「租税法 第24版」(弘文堂 2021年)133頁。
(注6)税制調査会「国税通則法の制定に関する答申(税制調査会第二次答申)及びその説明」(昭和36年7月)第二の二参照。
(注7)大阪高裁昭和39年9月24日判決(税資38号606頁)等参照。
(注8)東京地裁昭和26年4月23日判決(行裁例集2巻6号841頁)、東京高裁昭和40年5月12日判決(税資49号596頁)等参照。
(注9)東京高裁昭和48年3月14日判決(行裁例集24巻3号115頁)、東京高裁昭和49年10月29日判決(同25巻10号1310頁)等参照。
(注10)品川芳宣「節税と税務否認の分岐点」(ぎょうせい 令和6年)183頁以下、同「租税法学と租税実務 第8回」税務弘報2024年11月号133頁等参照。
(注11)品川芳宣「組織再編成税制における行為計算の否認−ヤフー事件−」本誌2016年6月6日号14頁、同「重要租税判決の実務研究 第四版」(大蔵財務協会 令和5年)940頁等参照。
(注12)前出・品川芳宣「重要租税判決の実務研究 第四版」(大蔵財務協会 令和5年)969頁等参照。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























