解説記事2025年04月14日 巻頭特集 東京高裁令和6年9月26日判決の納税者代理人解説(2025年4月14日号・№1070) ~整備法に基づく移行法人の有価証券の譲渡原価及び減価償却資産の償却費に関して、租税法令の文理に忠実な法解釈を示し、課税処分を取り消した事例~
巻頭特集
東京高裁令和6年9月26日判決の納税者代理人解説
~整備法に基づく移行法人の有価証券の譲渡原価及び減価償却資産の償却費に関して、租税法令の文理に忠実な法解釈を示し、課税処分を取り消した事例~
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 弁護士 加藤新太郎
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 弁護士 仲谷栄一郎
法律事務所Y Cube 弁護士 川添文彬
1. はじめに
(1)本稿の目的
東京高裁令和6年9月26日判決(金融・商事判例1709号8頁。以下「本判決」という。永谷典雄裁判長)は、公益法人制度改革により、特例民法法人(脚注1)が一般財団法人に移行した(脚注2)後の事業年度における、有価証券の帳簿価額(脚注3)及び減価償却資産の取得価額(脚注4)の解釈に関し、理論的にも実務的にも重要な司法判断を下した(以下、整備法に基づく移行後の一般財団法人を「移行法人」という。)。本判決は、東京地裁令和5年2月17日判決(判時2596号21頁。以下「原判決」という。鎌野真敬裁判長)(脚注5)を基本的に維持して課税処分を取り消したものであり、上訴されることなく確定した。本件は、公益法人制度改革の時期に発生した事案であるが、他の類似の状況にも影響する、より一般的な論点を含むものである。
もっとも、本件に関連する公益法人制度改革の趣旨・関連する法令(私法及び租税法)の内容は複雑であるため、本判決及び原判決だけを読んで、本判決の本質、論点及び意義を的確に把握することにはいささか労力を要するかもしれない。そこで、納税者代理人を務めた筆者らにおいて、本判決の理解を容易にすることを目的として、本稿を公表する(脚注6)。なお、紙幅の関係で、全ての論点を満遍なく解説するのではなく、重要部分のみを解説する。
(2)本件のポイント
本件のポイントは、納税者が租税法ではない法律の要請に従って、会計上、資産の評価損を計上などした場合に、それが租税法上も意味を持ち、法人税法(以下、文脈に応じて「法」という。)上の「税務上の帳簿価額」を変更することになるのかという論点にあった。国税当局は、公益法人制度改革に関連してなされた資産の評価損を計上するなどの一定の場面において、法人税法上の「税務上の帳簿価額」が変更されるとの解釈に基づき課税処分を行った。
しかし、これを認めると、会計上の資産の評価損は法人税法上損金算入されないにもかかわらず(法33条1項)、減額した帳簿価額を前提に有価証券の譲渡益(法61条の2第1項)が過大に認識されることになり、不当ではあるまいか。公益法人制度改革に関連してなされた資産の評価損の計上について、この不当と目される結論に法的根拠はあるのだろうか。筆者らが納税者から相談を受けたときに最初に抱いたのはこうした素朴な疑問であった。
そして、筆者らは、その疑問を解消すべく、租税法の規定の内容、趣旨及び文理解釈などを精査した上で、法律に基づく正しい解釈論を、わかりやすく論理的に組み立てたのであるが、裁判所の的確な事案解明的訴訟指揮も加わって、課税処分取消しの判決を得ることができた。
2. 事案の概要
本件の納税者(原告・被控訴人)は、旧民法上の財団法人(脚注7)として設立されたが、公益法人制度改革に伴い特例民法法人(脚注8)となり(整備法42条2項)、平成23年2月3日(以下「本件移行日」という。)に、一般財団法人(脚注9)に移行した(脚注10)(以下「本件移行」という。)。
(1)有価証券
ア 納税者の立場
納税者は、本件移行前、収益事業以外の事業(以下「非収益事業」という。)に属する資産として、有価証券(以下「本件各譲渡有価証券」という。)を保有し、その取得価額をもって帳簿価額としていた。納税者は、移行に当たり、公益目的財産額の算定のために本件各譲渡有価証券を時価評価することが義務付けられたため(脚注11)、本件移行前の最終事業年度の決算整理において、移行前の日付による会計処理として、当該日付における時価に基づいて算出した有価証券の評価損を計上した。その後、納税者は、本件移行後の各事業年度において、本件各譲渡有価証券を順次売却し又は償還を受けた。
納税者は、当該各事業年度の確定申告において、本件各譲渡有価証券の譲渡損益(法61条の2第1項)の計算にあたり、取得時の対価、すなわち上記評価損計上前の帳簿価額(取得価額と同じ)をもって、その譲渡原価(同項2号)とした。
イ 処分行政庁・国の立場
これに対して、処分行政庁は、本件各譲渡有価証券に係る譲渡損益の額の計算に当たっては、施行令131条の6が適用されるとして、上記評価損計上後の会計上の帳簿価額をもってその譲渡原価(同項2号)とすべきであるとして、納税者に対し、平成30年5月30日付けで、更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件各更正処分等」という。)をした。
施行令131条の6 ……公益法人等が普通法人……に該当することとなつた場合のその該当することとなつた時において有する資産及び負債……の帳簿価額は、……その普通法人……に該当することとなつた時においてその帳簿に記載されていた金額とする。
施行令131条の6の意義について、立案担当者は、「公益法人等が普通法人……に移行する場合には、収益事業以外の事業に属していた資産及び負債について、これまでの課税対象外の資産及び負債としての取扱いから課税対象の資産及び負債としての取扱いに変更されますが、当該資産及び負債には会計上の帳簿価額しか付されていなかったため、税務上の帳簿価額として付されるべき金額が明らかではありません。」「移行により課税対象外の資産及び負債が課税対象の資産及び負債となった場合には、移行時の会計上の帳簿価額を税務上の帳簿価額とするというものです。」と解説していた(脚注12)。
また、原審において、国は、公益法人等の非収益事業から生じた所得については法人税が課されない(法7条(現行6条))ため、公益法人等の非収益事業に属する資産には、法人税法第2編及び第3編の規定は適用されないと主張した。従前の課税実務においては、このような暗黙の理解がなされていたようである。その理解を前提にすると、それらの資産には「税務上の帳簿価額」が存在しないため、同資産からの所得に法人税が課されるようになった場合(たとえば、公益法人等が普通法人に移行した場合)には、その時点における同資産の会計上の帳簿価額を税法上の帳簿価額とするしかないことになるのであろう。原審において国は、これを定めたのが施行令131条の6だと主張した(図1参照)。
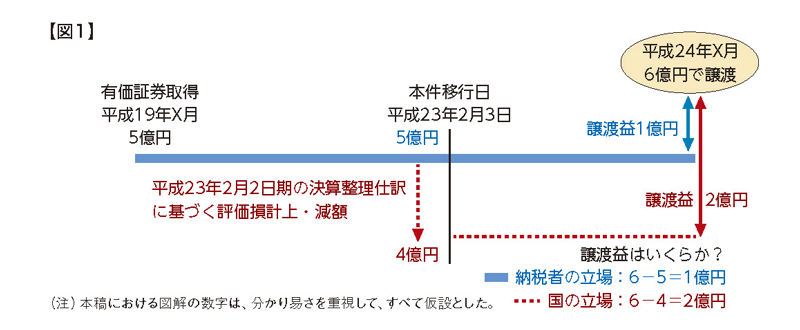
(2)減価償却資産
ア 納税者の立場
納税者は、本件移行前、非収益事業に属する資産として、減価償却資産(以下「本件各移行減価償却資産」という。)を取得・保有し、その取得後、本件各移行減価償却資産について減価償却費を計上していなかったが、本件移行前の最終事業年度(平成23年2月期)の決算整理において、移行前の日付による会計処理として、移行前の減価償却費を一括して計上した。その会計処理を前提として、納税者は、移行後の各事業年度においても(会計上)減価償却費を計上した。
納税者は、移行後の各事業年度における当初の確定申告においては、本件各移行減価償却資産のうち旧定率法が適用されるものの償却限度額(法31条1項)について、上記減価償却費の一括計上後の帳簿価額を基に計算した。その後、納税者は、平成30年5月30日付け本件各更正処分等を受けた後の平成30年12月10日、本件各移行減価償却資産のうち旧定率法が適用されるものの償却限度額について、上記減価償却費の一括計上前の帳簿価額、すなわち取得価額を基に計算すべきであり、かつ、損金算入されなかった当該一括償却費が移行後の事業年度において「損金経理額」(法31条1項及び4項)に含まれるとの考え方に基づき、処分行政庁に対し、平成24年3月期から平成30年3月期までの事業年度について、更正の請求をした。なお、このような更正の請求をしなければ、本件移行前において一括計上した減価償却費を損金の額に算入する機会が永久に失われることになる。
イ 処分行政庁・国の立場
これに対して、処分行政庁は、本件各更正処分等の理由と同様に、施行令131条の6が適用されることを理由として、「移行前の最終事業年度(平成23年2月期)に係る減価償却費の一括計上後の会計上の帳簿価額をもって、当該減価償却資産の帳簿価額とすべき」として、更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「本件各通知処分」といい、本件各更正処分等と総称して「本件各処分」という。)をした(図2参照)。
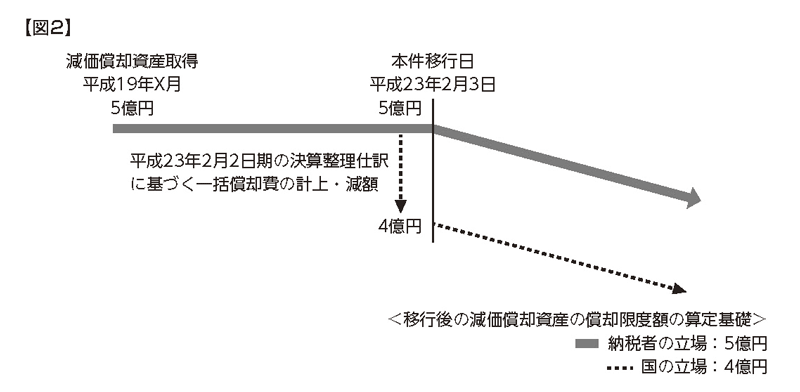
3. 主要な争点
(1)施行令131条の6は「税務上の帳簿価額」を定めたものか
ア 国の主張
国は、移行後の各事業年度における有価証券の譲渡原価(法61条の2第1項2号)及び減価償却資産の償却限度額(法31条1項)が、その「税務上の帳簿価額」に基づき算出され、かつ、本件では移行時に、施行令131条の6の適用により有価証券及び減価償却資産の「税務上の帳簿価額」が決まる旨、並びに、これらの考え方を正当化するための以下のような法令の解釈を主張した。また、東京高裁において国が証拠として提出した財務省主税局税制第三課が作成した令和5年4月17日付け調査回報書(以下「本件調査回報書」という。)にも、国の主張と概ね同様の内容の見解が記載されていた。
<有価証券の譲渡原価(法61条の2第1項2号)>
① 公益法人等が非収益事業に属する資産として有価証券を取得することは、施行令119条の2第1項1号にいう「取得」に該当せず、当該公益法人等が普通法人に移行した後、当該有価証券と同一銘柄の有価証券を追加取得せずに、当該有価証券を譲渡した場合には、同号にいう「その取得の直前の帳簿価額」とは、当該有価証券の譲渡直前の税務上の帳簿価額を意味すると解すべき旨、
② そして、移行日における税務上の帳簿価額は、施行令131条の6に基づき決まる旨。
<減価償却資産の償却限度額(法31条1項)及び損金経理額(同条1項及び4項)>
① 移行法人が移行前に非収益事業に係るものとして保有していた減価償却資産に係る償却限度額を、旧定率法を用いて計算する場合、施行令48条1項1号イ(2)にいう「取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額……の計算上損金の額に算入された金額……を控除した金額)」は、当該事業年度の期首における税務上の帳簿価額に旧定率法の償却率を乗じて償却限度額を計算することを定めた趣旨であると解すべきである旨、
② 納税者が本件移行前に計上した償却費は、「所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額」(法31条4項)に当たらず、「損金経理額」(同項)に含まれない旨。
イ 納税者の主張
これに対して、納税者は、「税務上の帳簿価額」が講学上の概念かつ各場面における具体的な法令の適用の結果として算出される金額にすぎず、法令の根拠なしに「税務上の帳簿価額」なるものが存在することはあり得ないとして、以下のように主張した。代理人として、こうした主張が、法令の文言に忠実な解釈だと考えたからである。
<有価証券の譲渡原価(法61条の2第1項2号)>
① 本件各譲渡有価証券の譲渡原価は、移動平均法(「有価証券をその銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄を同じくする有価証券の取得……をする都度その有価証券のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした有価証券の取得価額……との合計額をこれらの有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。」)の適用により決まる旨(脚注13)、
② 公益法人等が非収益事業に属する資産として有価証券を取得することも「取得」(施行令119条の2第1項1号)に該当する旨、
③ 移動平均法は、一回限りの取得で、複数回の取得をしない有価証券にも適用される旨(一回限りの取得しかない場合、「その有価証券のその取得の直前の帳簿価額」は0円として条文を適用すれば足りる。)、
④ その取得をした「有価証券の取得価額」は、法61条の2第23項(現行24項)の委任を受けた施行令119条1項(本件では1号)(脚注14)により定まる旨。
<減価償却資産の償却限度額(法31条1項)及び損金経理額(同条4項)>
① 本件各移行減価償却資産の償却限度額は、旧定率法を適用する場合の「減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額……を控除した金額)」を基礎として決まる旨(法31条1項・施行令48条1項1号イ(2))、
② 「減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額……を控除した金額)」は、その文言どおり、「減価償却資産の取得価額」(脚注15)から、「既にした償却の額で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額」を控除した金額を意味する旨、
③ 納税者が本件移行前に計上した償却費は、「既にした償却の額で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額」(施行令48条1項1号イ(2))には該当しない旨、
④ 納税者が本件移行前に計上した償却費は、「所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額」(法31条4項)に当たり「損金経理額」(同項)に含まれる旨。
(2)施行令131条の6の委任の根拠規定
ア 国の主張
国税当局は、本件各処分の理由において、施行令131条の6の適用があると述べるだけで、法人税法の委任の根拠規定その他の適用した法令を明らかにしていなかった。
これに対し、納税者は、本件各処分の適法性を基礎づける国の主張する法律構成を明らかにすることを求め、複数回の求釈明申立てを行った。そうしたところ、国は、最終的に、施行令131条の6は、法64条の4第6項のみならず、法65条の委任をも受けたものであり(脚注16)、本件各処分では、法65条の委任を受けた施行令131条の6が適用される旨の法律構成を主張するに至った。
本件調査回報書にも、国の主張と概ね同様の内容の見解が記載されていた。しかし、国が提出した立法時の資料(脚注17)には、施行令131条の6の委任の根拠規定の記載は見当たらなかった。
イ 納税者の主張
(ア)政令委任の限界
国の主張(委任の限界の問題)に対して、納税者は、以下の解釈論上の論拠により、施行令131条の6が法65条の委任を受けたものではない旨を主張した(脚注18)。
① 法65条の文言からして法61条の2が明確に定める有価証券の譲渡原価を重複して政令に委任することは想定されていないこと。
② 施行令131条の6が施行令第2編第1章第1節第3款の4「公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算」に位置し、法65条の法令の位置と対応しないこと。
③ 施行令131条の6が「取得価額」(施行令119条、48条1項1号イ(2))につき定めていないこと。
(イ)法人税法による委任の範囲の逸脱
さらに、納税者は、仮に施行令131条の6が法65条の委任を受けたものだとしても、施行令131条の6は、少なくとも、修正公益目的財産の計算の基礎に含まれる資産に対して適用され、かつ、移行日における調整公益目的財産残額が公益目的財産残額を上回る場合に適用される限度(以下「本適用場面」という。)では、以下の論拠に基づき、同65条の委任の範囲を超えており、無効である旨を主張した。
① 最判令和3年3月11日民集75巻3号418頁(脚注19)において、法の趣旨に反する施行令が無効となる旨の判例法理が形成されていること。
② 国が、第一審の前半から、法61条の2第1項2号及び同法31条1項の趣旨を、二重の所得金額の減少を防止する点(以下「二重の所得減少の防止」という。)ないし課税の公平を維持する点にあると主張していたこと。
③ 関連法令を精査すると、本適用場面において、施行令131条の6を適用しても、二重の所得減少の防止の結果にならず、かえって、現実の利益のないところに課税する結果になること。
(3)二重の所得減少
ア 公益法人税制の概要
本件では、本件移行に関する公益法人税制の適用上、二重の所得減少が発生するかどうかが重要な争点の一つとして前景化した。そこで、二重の所得減少の争点の理解を容易にするため、公益法人税制の概要を解説したうえで、同争点に関する当事者の主張を整理しておく(次頁図3参照)。
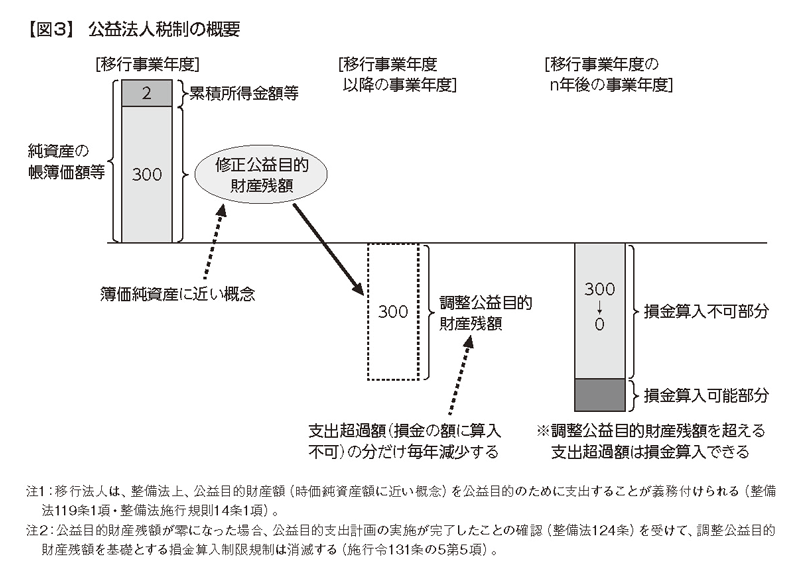
(ア)移行日の属する事業年度における清算的な課税
法人税法上の公益法人等が普通法人に移行する場合、移行日前の非収益事業から生じた所得の金額又は欠損金額の累積額としてそれぞれ政令で定めるところにより計算した金額(累積所得金額又は累積欠損金額。以下、併せて「累積所得金額等」という。)に相当する金額は、移行日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金又は損金の額に算入される(法64条の4第1項)。これにより、移行前の公益法人等としての非収益事業から生じた所得の累積額等につき、清算的な課税がされることとなる(脚注20)。
ただし、特例民法法人である公益法人等が普通法人に移行する場合には、累積所得金額等の算定にあたり、追加の調整が存在する。この場合には、移行日以後に公益の目的のために支出される金額として政令で定める金額(修正公益目的財産残額)は、累積所得金額から控除し、又は累積欠損金額に加算することとされている(法64条の4第3項、施行令131条の5第1項3号)。これは、整備法の規定により公益目的への支出が義務付けられている場合には、その支出される金額については、その使途が公益目的に限定されていることから清算的な課税の対象から除く趣旨であるという(脚注21)。
累積所得金額等の計算過程の詳細は、本稿末尾の別表にまとめたとおりである。
(イ)移行日の属する事業年度以後の各事業年度における課税
特例民法法人である公益法人等から移行した普通法人は、公益目的支出計画に従い、公益目的財産額に相当する金額から、各事業年度末日における公益目的収支差額(脚注22)を減算した額である公益目的財産残額が零になるまで、公益目的支出を続けることとなる(脚注23)。そして、移行日の属する事業年度以後の各事業年度においては、公益目的支出の額(脚注24)が公益目的支出計画に係る公益事業から生ずる実施事業収入の額(脚注25)を超えるときは、その超える部分の金額(支出超過額)は、調整公益目的財産残額(施行令131条の5第7項)を超えない限り、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されない(同条5項)。他方、実施事業収入の額が公益目的支出の額を超えるとき(調整公益目的財産残額がある場合に限る。)は、その超える部分の金額(収入超過額)は、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入されない(同条6項)。このような課税関係は、当該法人が、公益目的財産残額が零となったとして認可行政庁から受ける、公益目的支出計画の実施が完了したことの確認(脚注26)に係る事業年度まで継続される。
なお、当初の調整公益目的財産残額は、修正公益目的財産残額の額と同額である(施行令131条の5第7項)。
イ 国の主張
国は、法61条の2第1項2号及び法31条1項の趣旨を、いずれも、二重の所得減少の防止ないし課税の公平を維持する点にあると主張した。その上で、移行後の各事業年度における有価証券の譲渡原価(法61条の2第1項2号)及び減価償却資産の償却限度額(法31条1項)の算定基礎となる取得価額を移行時の税務上の帳簿価額としなければ、又は、納税者の主張によれば、二重の所得金額の減少が生じる旨を主張した(図4参照)。
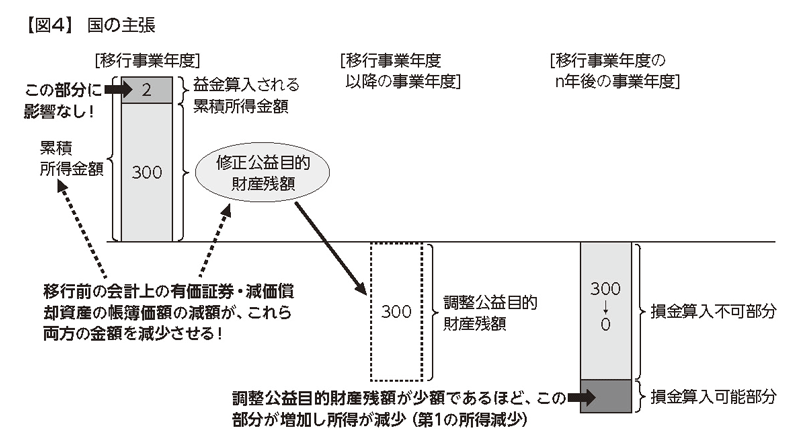
国は、当初は、移行前に移行時資産等の評価損を計上した場合、累積所得金額等が減少する旨(第1の所得減少)を主張していた。しかし、納税者から、関連法令の規定に基づけば、累積所得金額等は減少しない旨の指摘(本稿末尾の別表「累積所得金額等の計算過程の詳細」参照)を受けて、最終的に、①このような場合、調整公益目的財産残額(施行令131条の5第7項)が少額になることにより、移行後の事業年度において損金算入制限額の総額が少なくなり、損金の額に算入できる金額が増える旨(第1の所得減少)、②有価証券の譲渡原価及び減価償却資産の償却限度額の算定基礎となる取得価額に当該評価損の額が含まれないことにより、移行後の事業年度において、有価証券の譲渡損益が減少し又は損金の額に算入できる減価償却費が増える旨(第2の所得減少)を主張するに至った。
ウ 納税者の主張
これに対して、納税者は、少なくとも、当初調整公益目的財産残額が公益目的財産残額(脚注27)を上回る場合(本適用場面)には、国の主張する第1の所得減少は現実的には発生しない旨の反論をした。
これを敷衍すると、①移行法人の移行後の事業年度において、支出超過額につき調整公益目的財産残額を限度とする損金算入制限(施行令131条の5第5項)が適用されるのは、移行法人が整備法124条(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認)の確認に係る事業年度までであるところ(施行令131条の5第5項括弧書)、支出超過額が公益目的財産残額に達した場合(脚注28)には、移行法人は「認可行政庁に公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を求めることができる」(整備法124条)ためその確認を受けることになり、その確認後の事業年度においては、支出超過額につき調整公益目的財産残額を限度とする損金算入制限は適用されない(施行令131条の5第5項括弧書)。また、②公益目的財産残額と調整公益目的財産残額は、いずれも支出超過額の分だけ減少するため、減少額は同額である(脚注29)。したがって、③少なくとも、当初調整公益目的財産残額が公益目的財産残額を上回る限り、調整公益目的財産残額よりも先に公益目的財産残額が零になり公益目的支出計画の実施完了の確認を受けることになるから、当初調整公益目的財産残額が少額になったことにより、移行法人の移行後の事業年度における所得の金額が減少する余地はない。
この納税者の主張する法令の仕組みを図解すると図5のとおりである。
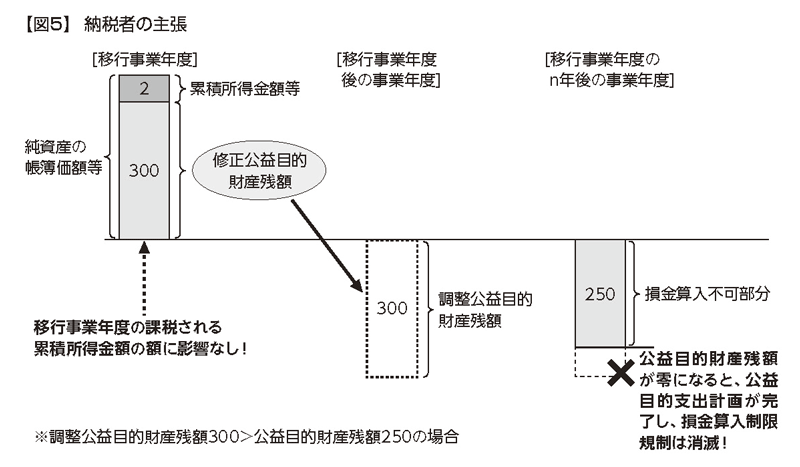
4. 原判決の判示内容
(1)有価証券
原判決は、本件各譲渡有価証券について、次のとおり判示した。
ア 有価証券の譲渡原価~施行令119条の2第1項1号の文理解釈
「租税法律主義の原則に照らすと、租税法規はみだりに規定の文言を離れて解釈すべきものではないというべきである(最高裁昭和43年(行ツ)第90号同48年11月16日第二小法廷判決・民集27巻10号1333頁、最高裁平成19年(行ヒ)第105号同22年3月2日第三小法廷判決・民集64巻2号420頁、最高裁平成26年(行ヒ)第190号同27年7月17日第二小法廷判決・裁判集民事250号29頁参照)。」
「公益法人等が非収益事業に属する資産として同一銘柄の有価証券を1回又は複数回にわたり取得した場合であって、当該公益法人等が普通法人に移行した後、同一銘柄の有価証券を追加取得せずに、当該有価証券を譲渡したときであっても、当該公益法人等による有価証券の取得は施行令119条の2第1項1号にいう『取得』に当たるものと解するのが同号の規定の文言に沿う解釈であって、これに反する被告の主張する解釈を採用すべき文言上の根拠はないというほかない。」
イ 二重の所得金額の減少
「被告の主張する解釈を採用すると、二重の所得減少は生じ得ない一方、調整公益目的財産残額が公益目的財産残額を上回る場合には、所得の金額が一度も評価損の額相当額分減少しない事態が生じ得る。」
「評価損の額相当額は、公平な課税の観点からは、一度に限り所得の金額から控除されるのが相当であり、二重の所得減少が生ずるのも、又は一度も控除されないのも、いずれも望ましくない。」
「二重の所得減少を防ぐために、評価損の額相当額につき、一度も所得の金額を減少させないという事態を招来することは、法律上の根拠なく当然に正当化されるものではない。」
「被告の主張する点は、施行令119条の2第1項1号につき、……文言上の根拠を欠く被告の主張する解釈を採用すべき積極的な根拠とはならない。」
ウ 政令委任の限界
「施行令131条の6は、公益法人等が普通法人に移行した時において有する移行時資産等の帳簿価額は、移行時においてその帳簿に記載されていた金額とすることを定める規定であって、その文言からすると、法61条の2第23項の委任を受けて定められた施行令119条及び119条の2第1項1号の規定の適用を排除し、あるいはその文言を読み替えて、移行法人について同法61条の2第1項2号にいう『一単位当たりの帳簿価額の算出の方法』の特則を定めた規定であると解することは困難である。」
(2)減価償却資産
次に原判決は、本件各移行減価償却資産について、次のとおり判示した。
ア 償却限度額~施行令48条1項1号イ(2)の文理解釈
「施行令48条1項1号イ(2)の文言を見ると、同規定にいう『取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)』とは、施行令54条に基づき計算される取得価額から、既にした償却の額で各事業年度の所得の金額等の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額を意味するものと解するほかなく、移行時資産等減価償却資産についてかかる金額を計算する場合であっても、これと異なる解釈を採用する文言上の根拠は存在しない。したがって、上記の解釈に反し、移行法人の移行後最初の事業年度において、移行時資産等減価償却資産に係る『取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)』とは、施行令131条の6に基づいて計算される移行日における税務上の帳簿価額を意味するものと解釈する文言上の根拠はないというほかない。」
イ 二重の所得金額の減少
「調整公益目的財産残額の減少によって、所得の金額が当該減価償却費相当額分減少するのは、原則として、調整公益目的財産残額が公益目的財産残額を上回らない場合に限られるから、二重の所得減少が生ずるのも、かかる場合に限られることになる。そうすると、……この点は、施行令48条1項1号イ(2)につき、……文言上の根拠を欠く被告の主張する解釈を採用すべき積極的な根拠とはならない。」
ウ 政令委任の限界
「施行令131条の6の文言からすると、法31条6項の委任を受けて定められた施行令48条1項1号イ(2)及び54条の規定の適用を排除し、あるいはその文言を読み替えて、移行法人について同法31条1項にいう償却限度額の計算方法の特則を定めた規定であると解することは困難である。」
エ 損金経理額
「法人税法上、公益法人等は、収益事業から生じた所得以外の所得については法人税を課されていないから、公益法人等が普通法人への移行前に収益事業に属しない減価償却資産について減価償却費を計上した場合であっても、当該減価償却費は、損金に算入されることもないのであって(同法7条)、そうである以上、当該減価償却費の金額は、同法31条4項にいう『所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額』に該当するというべきである。」
(3)国の控訴
原判決が納税者の主張を全面的に認めたため、国は原判決を不服として控訴し、控訴審において、以下の更正の期限に関する主張と公益目的支出額に関する予備的主張を追加した。
① 更正の期限に関する主張
平成24年3月期の更正の請求のうち、純損失の金額以外の課税標準及び税額の更正は、国税通則法70条1項の期間制限によりできないため、更正をすべき理由がない旨の主張。
② 公益目的支出額に関する予備的主張
仮に納税者の主張が正しいとした場合には、有価証券の譲渡損及び減価償却費の増加額が「損益計算書に計上すべき……事業費の額」(整備法119条2項1号・整備法施行規則16条1号)として「公益目的支出の額」ひいては「支出超過額」に含まれるため、当該部分は損金の額に算入できない旨(施行令131条の5第5項)の主張(脚注30)。
5. 本判決の判示内容
これに対して、本判決は、有価証券の譲渡原価を定めた法人税法61条の2第1項2号の立法趣旨・立法経緯のうち、原審において国が明確に主張していなかった部分を更に探究するなどして、次のとおり判示した。
(1)有価証券
ア 有価証券の譲渡原価を定めた法人税法61条の2第1項2号の立法趣旨・立法経緯
「法人税法61条の2第1項2号……が『一単位当たりの帳簿価額』を譲渡原価の計算の基礎としているのは、金融商品に係る会計基準により、企業会計上、時価法が採用され、損益計算書に評価損益と譲渡損益を区別して計上することになったことを踏まえて、法人税法も売買目的有価証券について時価法を採用し、時価評価額をもって期末評価額(帳簿価額)とし、評価損益と譲渡損益を区分して認識させることとしたことから(同法61条の3第1項1号及び2項)、期末における有価証券の帳簿価額が、評価替えにより取得価額と異なる価額(時価評価額)になる状況が生じたことに起因するものである……。一方、売買目的外有価証券については、時価法ではなく原価法が維持されているから(同条1項2号)、法人税法61条の2第1項2号をもって、有価証券一般について、その譲渡原価を時価評価した帳簿価額によるとの立法政策を採用したものであるということはできない。まして、法人税法61条の2第1項2号が、平成18年に制定された整備法上の公益目的財産額の算定を目的とする有価証券の時価評価を念頭においたものでないことは明らかである。」(脚注31)
イ 租税法の解釈手法
「法人税法61条の2第23項は、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類は、政令で定めるとしており、その委任を受けた規定は、施行令119条の2以外には見当たらないから、同規定を離れて、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を解釈することは、租税法律主義の観点から許されないというべきである。すなわち、租税法は、侵害規範であり、法的安定性の要請が強く働くから、その解釈は原則として文理解釈によるべきであり、みだりに拡張解釈や類推解釈を行うことは許されない。規定の文理上その意味を直ちに明らかにすることができない場合、文理解釈を基礎とし、規定の文言や当該法令を含む関係法令全体の用語の意味内容を重視しつつ、事案に応じその文言の通常の意味内容から乖離しない範囲内で、規定の趣旨目的を考慮することは許容されているというべきであるが、施行令119条の2の規定の文言は、不明確とはいえず、同規定が想定していない解釈をして納税者に不利益を負わせることは租税法律主義の観点から許されない。」
「有価証券の取得とは別の目的で時価評価した価額に依拠して、有価証券の一単位当たりの帳簿価額とすることは、同規定の想定するところではないというべきである。」
ウ 政令委任の限界
「施行令131条の6は、……有価証券の譲渡損益の計算について定めた法人税法61条の2の委任を受けたものでないことは明らかであり、同規定を有価証券の譲渡原価の額を算定する根拠とすることもできないというべきである。」
エ 法令の不備
「そもそも、平成18年に公益法人等を普通法人に移行させる法整備が行われた際に、公益法人等が保有していた有価証券を移行後に売却した場合の譲渡損益をどのように算出するかについて検討された形跡は見当たらず、この問題は、法令上の手当がされなかったことによるものと言わざるを得ないが、後付けの無理な法解釈を行ってそのつけを納税者に負わせることはできないというべきである。」(脚注32)
オ 結論
「したがって、移行時に評価替えした帳簿価額……を譲渡原価の額とすることはできず、取得価額……を譲渡原価の額とするのが相当である。」
(2)減価償却資産
ア 償却限度額
「被控訴人の減価償却資産には、施行令48条1項1号イ(2)の『既にした償却の額で各事業年度の所得の金額(中略)の計算上損金の額に算入された金額』があるとはいえないから、当該減価償却資産の取得価額(本件各減価償却資産処理前価額)に基づいて償却限度額を計算すべきである。」
イ 損金経理額
「同項(引用者注:法31条4項)の『当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額』が、償却限度額を超える減価償却費であるため損金の額に算入できなかったものを想定しているとしても、非課税のために損金に算入できなかったものについては、これと区別して損金経理額に含まれないことを明らかにしていると解釈することは同項の文理上困難といわざるを得ない。」
ウ 結論
「そうすると、移行前最終事業年度に一括計上した減価償却費は被控訴人の損金経理額に含まれ、旧定率法の適用に当たっては、本件各減価償却資産処理前価額(引用者注:取得価額)に基づいて償却限度額を計算すべきところ、これによらずに計算した本件各通知処分は違法であ」る。
(3)小括
本判決は、国が控訴審において新たに主張した、更正の期限に関する主張及び公益目的支出額に関する予備的主張を認めたものの、重要部分において原判決の結論を維持し課税処分取消しの判断を下した。
6. 原判決及び本判決の意義
(1)文理解釈
原判決及び本判決は、いずれも、租税法令の文理に忠実な法解釈を示して課税処分を取り消した。文理解釈のあるべき実践例として、事例的意義があると解される。
租税法令の文理解釈についてのリーディングケースは、ホステス源泉徴収事件(最判平成22年3月2日民集64巻2号420頁)である。その調査官解説は、次のとおり述べて、基礎控除制度の趣旨目的を説いている(同事件の多数意見においても、基礎控除制度の趣旨目的が検討されている。)。
① 「租税法の解釈は、原則として文理解釈によるべきであるが、文理解釈によって規定の意味内容を明らかにすることが困難な場合には、当該規定の趣旨目的に照らしてこれを明らかにする必要がある……。」
② 「施行令322条(引用者注:同事件においてその解釈が問題となった、源泉徴収の対象となる支払金額から基礎控除する金額を定めた規定)の『当該支払金額の計算期間の日数』の解釈については、規定の趣旨目的を検討するまでもなく、文理解釈により、当該支払金額の計算規定の全日数を指すという解釈が導かれることになる。」(脚注33)
③ 「文理解釈により規定の意味内容を明らかにすることが可能であっても、その帰結が明らかに不合理である場合には、規定の趣旨目的に照らして合理的な解釈を導き出すことが可能かどうかを検討すべきであるとする見解もあり得ないではない。」(脚注34)
原判決は、上記解説の考え方と同様に、文理解釈を原則としたうえで、その帰結が明らかに不合理かどうか(例えば、二重の所得金額の減少を導くかどうか)、その規定の趣旨目的(例えば、二重の所得減少の防止)に照らして合理的な解釈を導き出すことが可能かを検討したと解される(脚注35)。そして、本判決も、租税法令の解釈にあたり、「規定の文言や当該法令を含む関係法令全体の用語の意味内容を重視しつつ、事案に応じその文言の通常の意味内容から乖離しない範囲内で、規定の趣旨目的を考慮することは許容されている」旨を述べて、原判決の考え方と同旨の解釈手法を採用したものと評価することができる(脚注36)。
(2)税務上の帳簿価額と租税法律主義
原判決及び本判決は、「税務上の帳簿価額」という講学上の概念を基礎とした法令の解釈を行うことなく、法令の文言、趣旨目的、帰結の合理性、法令の委任構造等を丹念に検討して、法令の解釈を行った。租税法律主義の下では、課税は、講学上の概念ではなく、法律に基づきなされなければならないから(憲法84条)、このような司法による法令解釈の態度は正当である。
(3)従前の課税実務上の解釈の否定
前記(2(1)イ)のとおり、従前の課税実務においては、原審で国が主張したように、公益法人等の非収益事業から生じた所得については法人税が課されない(法7条(現行6条))ため、公益法人等の非収益事業に属する資産及び負債について法人税法第2編及び第3編の規定は適用されない旨の考え方が存在していたように思われる。
しかし、裁判所は、このような(ある意味、便宜主義的な)課税実務の考え方に与することなく、法令の文言、趣旨目的、帰結の合理性、法令の委任構造等を丁寧に検討して、施行令119条の2第1項1号及び48条1項1号イ(2)を解釈した。この点について、判タ匿名解説(判タ1514号144頁)は、原判決を、「特例民法法人が一般財団法人に移行する場面における施行令119条の2第1項1号及び48条1項1号イ(2)につき、課税当局が採用してきた解釈を否定する新たな判断を示した」と評する(同号149頁)。これを維持した本判決も、同様に評価すべきものと解される。そして、租税法律主義の下では、課税は、課税実務ではなく、法律に基づきなされなければならないから(憲法84条)、このような司法による法令解釈の態度は至極正当である。
(4)事後に作成した国の内部資料の排斥
国が東京高裁で財務省作成の本件調査回報書を提出したのは、施行令131条の6の立法趣旨が立法時の資料から必ずしも明らかでなかったためであろう。しかし、本件調査回報書は、立法時の資料を含むものではなく、また立案担当者の見解を含むかどうかも明らかではなく、概ね、国の主張する法令解釈と同じ内容が記載されているものにすぎなかった。
納税者代理人は、このような本件調査回報書が、国の一省庁が本件に関して事後的に作成した法令の解釈の主張にすぎず、当事者である国の主張以上の意味を持たないと主張した。
本判決は、「この問題は、法令上の手当がされなかったことによるものと言わざるを得ないが、後付けの無理な法解釈を行ってそのつけを納税者に負わせることはできない」と判示して、本件調査回報書の法解釈を採用しなかった。この点は、安易に行政庁の解釈を追認することなく、司法判断としての見識を示したものとして特筆しておきたい。また、税務訴訟において本件調査回報書と同種の証拠が提出された場合にも実務上参考になるであろう。
7. 本判決の射程
(1)二重の所得金額の減少が生じる場合
本件の納税者は、移行日における調整公益目的財産残額が公益目的財産残額を上回っていたため、移行前に有価証券や減価償却資産の評価損を計上した場合であっても、現実には(極めて特殊な事情がない限り)、二重の所得減少が生じる余地のない事案であった。
しかし、原判決及び本判決の示した有価証券の譲渡原価及び減価償却資産の償却限度額と損金経理額に関する法令解釈は、判決文上、本件の個別の事情に基づく法令解釈ではなく一般論であるため、本件の納税者と同様に、移行日における調整公益目的財産残額が公益目的財産残額を上回っている移行法人のみならず、移行日における調整公益目的財産残額が公益目的財産残額を上回っていない納税者に対しても、妥当すると考えられる(脚注37)。
したがって、整備法上の移行法人一般としては、移行前から保有する有価証券又は減価償却資産について、本判決の解釈に沿わない申告を行っていたとすると、本判決の解釈に従って、今後の確定申告をすること又は更正の請求をすることは検討に値するといえよう。
(2)転用資産の場合
施行令131条の6は、移行時資産等の帳簿価額のみならず、非収益事業に属する資産等を収益事業に属する資産等に転用した場合の当該資産等の帳簿価額を定めている。原判決及び本判決の示した法解釈との関係で、「有価証券又は減価償却資産を転用した場合に、当該有価証券の譲渡原価又は当該減価償却資産の償却限度額がどのように判断されるか」という問題がある。しかし、原判決及び本判決には、この点について何らの判断も示されていない。したがって、この問題は、原判決及び本判決の判断の射程外ということになる。
そこで考えるに、①原判決及び本判決の判示内容の考え方からすれば、転用資産である有価証券の譲渡原価及び減価償却資産の償却限度額の算定にあたっても、施行令131条の6は適用されないと解するのが法令の自然な文理解釈である。また、②転用資産について施行令131条の6を適用しなくても二重の所得減少その他の不合理な帰結は生じないように思われる。そうすると、転用資産である有価証券の譲渡原価及び減価償却資産の償却限度額の算定にあたり、施行令131条の6は適用されないという解釈も十分成り立ち得るであろう。
この問題は、事柄の性質上、仮に上記のような文理上自然な法令解釈が立法者の意図とは異なるとすると、裁判所による法令の解釈に委ねるのではなく、立法により、早期かつ明確に解決されることが望ましいと考える。
8. おわりに~税務訴訟における納税者代理人の役割
令和5年度において終結した税務訴訟において納税者が部分的にでも勝訴した事案は、全体の7.6%(172件のうち13件)であり(脚注38)、一般的に、裁判所において国税当局の見解や課税処分を覆すのは容易ではない。しかし、裁判所は、納税者の主張に理由と説得力があれば、納税者を勝訴させることを躊躇しないはずである。実際にも、近時は、本件を含めて、重要な事件における納税者勝訴の判決が散見される(脚注39)。
本件で納税者が勝訴できた主な理由として、次の点を挙げることが許されよう。
(1)素朴な正義感・公平感に訴えること
本件の事案を把握した際に、筆者らが法令を離れて抱いた素朴な感覚は、国税当局の立場によれば、納税者に現実の利益が生じていないのに所得が過大に認識されて、不正義・不公平ではないかということであった。そのような法令を離れた不正義・不公平の感覚は、弁護士のみならず、裁判官を含む法曹三者が等しく共有しうるものであると思う。
納税者は、上記の素朴な感覚に基づき、国の法解釈によれば納税者に現実の利益が生じていないのに所得が過大に認識されて課税されること及び納税者の法解釈によっても本件では二重の所得減少は生じないことを、法令に即して具体的に指摘した。そのうえで、納税者が、その素朴な正義感・公平感に適う法令の文理に忠実な解釈及び適用を主張したことは、当該法解釈に、より強い説得力をもたらしたように思われる。
なお、法令に不備があり、その内容どおりに法令を適用すると、著しく不正義・不公平をもたらす結果を招くことになると考えられる場合、当該法令を無効とする主張も検討に値しよう。本件でも、納税者は、上記のような素朴な正義感・公平感を軸に、法令の文理に忠実な解釈及び適用を主張するとともに、施行令131条の6は無効である旨の法律構成も主張していた。租税法律主義の下では、素朴な正義感・公平感のみを根拠に課税の適法性を判断することはできないから、納税者代理人としては、先例がない問題であっても、裁判所が採用しうる法律構成を考えて、幅広に主張することも重要であると考える。
(2)不適切な節税行為、租税回避行為がなかったこと
納税者が適切な申告をすることは基本的な事項であるが、このことは本件でも重要であった。また、本件は租税回避事案ではなく、納税者が技巧的な節税の手法を用いたものでもなかった。課税庁からみて何らかの「目に余る」行為があったから課税されたという事案とも思われず、裁判所が納税者に対し悪い印象を抱く事実はみられなかった。本件は、その意味で、税務訴訟案件としてスジの良い事件であったということができる。
(3)訴訟活動の基本を徹底すること
納税者代理人として、先例のない中で、どのように取り組んだか。
第1に、複雑・難解な関連法令を読み解き、租税法律主義、法令の委任構造、法律と政令の違い、課税要件、租税法の解釈手法、判例法理及び立法時の資料の記載等の基本から、説得的な主張を展開できる法律構成を探ることにした。第2に、裁判所に対して、正しい法令の解釈適用を、本稿に掲載したような図解及び法律の条文を用いながら可能な限り分かりやすくかつ説得的に説明することに腐心した。
これらのいずれが功を奏したかは不明であるが、本件各処分の理由として掲げられた施行令131条の6の解釈のみに拘泥しすぎることなく、納税者が現実に利益のないところに課税されたという有利に働く事情を裁判所に採用してもらいやすい法律構成を組み立て主張できたことは勝因といえるように思われる。
なお、翻ってみれば、本件は、①法令上の明確な手当がなされていない問題であったこと及び②関連法令が複雑・難解であったことが、誤った課税処分が行われた主な原因であったとも考えられる。移行法人の有価証券の譲渡原価及び減価償却資産の償却限度額は決め方の問題(脚注40)であり、国の主張も立法論上の選択肢の一つではあり得たのであろう(脚注41)。しかし、納税者代理人としては、立法論は解釈論にはなり得ないことを前提に、法解釈論を説得的に論じることを心掛けた。税務訴訟であっても、特別なことをする必要はなく、基本を丁寧に一つずつ積み重ねる訴訟活動が重要であると考える。
(4)裁判所との相互信頼
税務訴訟を含むおよそ裁判は、人(裁判官)が判断するものであることから、裁判所から信頼されるに足る誠実な納税者(当事者)及び代理人であることは一般的に重要である。また、代理人としては裁判所の訴訟指揮の趣旨を理解して、的確な事案解明的なものであれば、これを信頼して粛々と対応していくことも必要不可欠であろう。
本件では、当事者による節税の意図・節税行為・租税回避行為がなかった案件としてのスジの良さに加え、素朴な正義感・公平感に訴えるとともに、訴訟における基本を積み重ね、裁判所を信頼し提示される疑問に基本的なところから丁寧かつ誠実に回答したことなどの事情が、良い結果に繋がったのではないであろうか。勝訴できたからいうわけではないが、「代理人が裁判所を信頼し、裁判所に信頼される」という相互信頼に基づき真摯に議論の応酬をしていくことこそが、新規性のある(先例のない)ケースにおける司法判断の質を規定するものであるように思う。
本稿が、本判決の理解を容易にするとともに、今後の裁判実務、課税実務及び租税法立案実務の参考になることを祈念して擱筆したい。
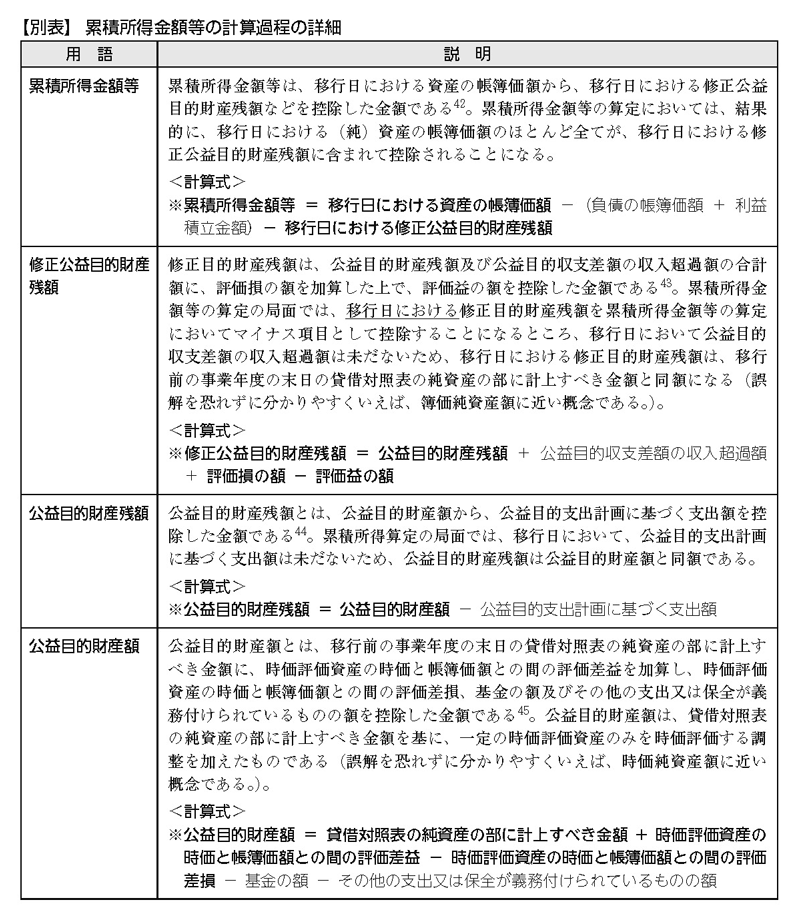
脚注
1 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)42条2項。本件では、平成18年改正(平成20年施行)前の民法(以下「旧民法」という。)の規定に基づく財団法人であった法人。
2 整備法45条に基づく移行。
3 法人税法施行令(以下「施行令」という。)119条の2第1項1号
4 旧定率法を適用する場合の「取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額……を控除した金額)」(施行令48条1項1号イ(2))。
5 原判決の解説として藤原眞由美「判批」税理67巻3号(2024年)132頁、藤間大順「判批」重判解説令和5年度(ジュリ臨時増刊2024年5月20日号)176頁、匿名解説(判時2596号21頁、判タ1514号144頁)、佐藤香織「判批」税経通信79巻3号(2024年)186頁、中村信行「判批」ジュリ1605号(2025年)150頁、本判決の解説として匿名解説(金融・商事判例1709号8頁)(2025年)、大野直也「判批」ジュリ1608号(2025年)10頁がある。
6 本稿における更正の理由、当事者の主張、概念及び判決内容は、筆者らにおいて調整したものであり、原文を逐語的に引用していないこと、並びに、厳密さを犠牲にして分かりやすさを重視した表現を用いた箇所があることにご留意されたい。
7 法人税法上の公益法人等(平成20年法律第23号による改正前の法2条6号・別表第二)。
8 法人税法上の公益法人等(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則10条1項)。
9 法人税法上の普通法人(法2条9号・同条5号ないし7号・別表第二)。
10 整備法45条
11 整備法119条1項、整備法施行規則14条1項1号ロ
12 佐々木浩ほか『平成20年版改正税法のすべて』(大蔵財務協会、2008年)312頁。
13 法61条の2第23項(現行24項)・施行令119条の2第1項1号、法61条の2第1項2号・施行令119条の7第1項
14 施行令119条1項1号は、「内国法人が有価証券の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一 購入した有価証券(省略) その購入の代価(省略)」と定める。
15 法31条6項の委任を受けた施行令54条の適用により決まる取得価額。
16 具体的には、法64条の4第6項の委任を受けた施行令131条の6が、累積所得金額等の計算に用いる移行時資産等の帳簿価額に関して定める部分に適用され、法65条の委任を受けた施行令131条の6が、移行後の各事業年度における所得金額の計算における課税要件の基礎を定める部分に適用される旨の法解釈。
17 前掲注12・佐々木浩ほか280~327頁、佐々木浩「平成20年度の法人税関係(含む政省令事項)の改正について」租税研究第706号29頁、佐々木浩「平成20年度公益法人税制の改正について」租税研究第708号66頁。
18 納税者の立場によっても、施行令131条の6が法人税法64条の4第6項の委任を受けて、累積所得金額等(法人税法64条の4第1項)の算定の局面における資産及び負債の(税務上の)帳簿価額の算定の場面において適用されることは、否定し難いように思われる。そうだとしても、同条6項は、「第一項から第三項(引用者注:法人税法64条の4第1項から3項)までの規定の適用(引用者注:累積所得金額等の算定)に関し必要な事項」(同条6項)を政令に委任するものであり、有価証券の譲渡損益の算定のために施行令131条の6を適用することは、法人税法64条の4第6項の委任の範囲を超えると考えられる。
19 判旨は、「株式対応部分金額の計算方法について定める法人税法施行令23条1項3号の規定のうち、資本の払戻しがされた場合の直前払戻等対応資本金額等の計算方法を定める部分は、利益剰余金及び資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当につき、減少資本剰余金額を超える直前払戻等対応資本金額等が算出される結果となる限度において、法人税法の趣旨に適合するものではなく、同法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効というべきである」というものである。
20 前掲注12・佐々木浩ほか305頁。
21 前掲注12・佐々木浩ほか307頁。
22 整備法施行規則23条2項
23 整備法119条1項、2項、123条、124条
24 整備法119条2項1号
25 整備法119条2項2号
26 整備法124条
27 整備法施行規則23条1項
28 「第百十九条第二項第一号の支出により公益目的財産残額が零となったとき」(整備法124条)。
29 公益目的財産残額につき法施行規則27条の16の4第1項・整備法119条2項2号・整備法施行規則17条、調整公益目的財産残額につき施行令131条の5第7項・同条第5項。
30 前掲注5・大野は、本判決がこの論点につき「法人税法の解釈によってこれらの額が増加するのであれば、それに伴い損益計算書に計上すべき実施事業の事業費の額も増えることになる」と判示して、国の公益目的支出額に関する予備的主張を認めた部分を捉えて、「会計と税務を混同しているようにもみえる。」と評し、疑問を呈する(ジュリ1608号(2025年)11頁)。
31 本判決が施行令119条の3(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に言及していないことに着目し、本判決が同条に言及しなかった理由を探る向きもあるかもしれない(前掲注5・大野11頁参照)。控訴審において、裁判所は、国に対して、公益法人等から普通法人に移行した法人の移行前における有価証券の評価替えについて、施行令119条の3に類似する規定を定めるか否かにつき立法時に議論があったかどうかを確認するよう釈明をした。これに対して、国は、立法時にそのような議論がされていたか否かは明らかではない旨の回答をした。このような訴訟の経緯からすれば、本判決が施行令119条の3について言及しなかったのは、同条を踏まえた検討を怠ったからではなく、本件では同条の適用がないことが明らかであり、同条に言及する特段の必要性がなかったからではないかと推察される。
32 納税者代理人としては、本判決による法令の不備の指摘こそは本件争訟の本質を見事に射抜いたものであると受け止め、あるべき司法判断として特筆したいと考えている。
33 鎌野真敬「判例解説」最高裁判所判例解説民事篇平成22年度(上)136頁~137頁。
34 前掲注33・鎌野137頁。
35 原判決の裁判長は、ホステス源泉徴収事件の担当調査官であった。
36 本判決の匿名解説(金融・商事判例1709号8頁)は、「本判決は、最高裁判例の租税法律主義の原則に照らし、租税法規はみだりに規定の文言を離れて解釈すべきものではないという考え方に則った判断といえよう。」と評する(同号13頁)。
37 原判決の匿名解説(判例タイムズ1514号144頁)は、「本判決の判断の射程」につき、移行日における調整公益目的財産残額が公益目的財産残額を上回っていない納税者に対して、本件において国が主張した解釈を採用することにつき、「なお検討の余地があろう」と留保しつつも、「相当の困難が伴うとも考えられる」旨を指摘する(同号148頁)。
38 国税庁「令和5年度における訴訟の概要」(令和6年6月)。
39 法人税法施行令を無効とした最判令和3年3月11日、同族会社の行為計算否認規定の適用を違法とした最判令和4年4月21日、非上場株式につき通達評価によらない相続税課税を違法とした東京高判令和6年8月28日、東京高判令和6年8月28日と異なる事案において、非上場株式につき通達評価によらない相続税課税を違法とした東京地判令和7年1月17日等。
40 決め方の問題については、佐藤英明『スタンダード所得税法〔第4版〕』(弘文堂、2024年)302頁が、減価償却費に関して、「今年の償却費がいくらかということは、外部との取引の事実に基礎づけられたものではなく、そもそも一定のストーリーにもとづいたフィクションにすぎないから、前提となるものごとの『決め方』によって、それをどうにでも変更できるのである」と論じている。
41 参考になりうる他の税制としてNISA制度がある。同制度の下では、個人が、非課税口座において購入した上場株式等を譲渡した場合には、所得税が課されないものとされ(租税特別措置法37条の14第1項)、譲渡をせずに、同一人の課税口座に移管等による払出しがされた場合、その払出しの対象となる株式につき、その時点の価額により譲渡があったものとみなされ、かつ、その時点の価額により(再度)取得したものとみなして、所得税に関する法令の規定を適用するものとされている(同条4項)。これに対して、法人税法には、公益法人等が普通法人に移行する場合において、移行後に課税対象となる資産の(再)取得擬制を定める規定は存在しない。納税者は、原審において、裁判所が本件の参考になりうる他の税制につき国に釈明し関心を有していることが窺われたことから、このようなNISA制度に係る法令の仕組みと、公益法人等が普通法人への移行時の法令の仕組みの違いを指摘した。
42 法64条の4第1項・施行令131条の4第1項、法64条の4第3項・施行令131条の5第1項3号・同法施行規則27条の16の4
43 施行令131条の5第1項3号・同法施行規則27条の16の4第1項・整備法施行規則23条2項
44 法施行規則27条の16の4第1項・整備法119条2項2号
45 整備法119条1項・整備法施行規則14条1項
加藤新太郎 (かとう しんたろう)
名古屋大学法学部卒業。博士(法学)。弁護士、中央大学法科大学院フェロー。司法研修所教官、東京高裁部総括判事など40年に及ぶ裁判官勤務の後、2015年、アンダーソン・毛利・友常法律事務所(当時)顧問就任。2015−21年、中央大学法科大学院教授(担当科目:民事訴訟法、法曹倫理)。『民事事実認定論』『民事事実認定と技法』(いずれも弘文堂)、『四日目の裁判官』(岩波書店)ほか、著書・論文多数。
仲谷栄一郎 (なかたに えいいちろう)
東京大学法学部卒業。弁護士。アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナー。2007−08年、早稲田大学法学部非常勤講師(担当科目:国際租税法)。『租税条約と国内税法の交錯』(第36回日本公認会計士協会学術賞受賞 共著・商事法務)、『国際取引と海外進出の税務』(共著・税務研究会)ほか、著書・論文多数。
川添文彬 (かわぞえ ふみあき)
一橋大学法科大学院修了、Leiden大学(国際租税法LL.M.)修了。法律事務所Y Cube代表弁護士。早稲田大学法務教育研究センター講師(租税判例研究)。近時の論考等として、佐藤修二=川添文彬=津江紘輝「鼎談 未上場株式のセカンダリー・マーケットに関する金商法改正と株式の相続税時価評価~租税法と金商法の“交差点” 金商法改正で総則6項の適用は増えるか~」週刊T&Amaster1040号(2024)4頁、佐藤修二=木村浩之=川添文彬「鼎談 信託型ストック・オプションに関する国税庁見解の法的検討~国税当局への照会制度の課題の検討を兼ねて(前編)(後編)」週刊T&Amaster991号(2023)4頁、同992号(2023)13頁ほか、多数。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























