解説記事2020年05月18日 税務マエストロ 非上場株式に係るみなし譲渡課税における時価(2)(2020年5月18日号・№834) -令和2年3月24日最高裁判決に敷衍して-
税務マエストロ
非上場株式に係るみなし譲渡課税における時価(2)
-令和2年3月24日最高裁判決に敷衍して-
#247
税理士 梶野研二
略歴
国税庁課税部資産評価企画官付企画専門官、同資産課税課課長補佐、東京地方裁判所裁判所調査官、国税不服審判所本部国税審判官、東京国税局課税第一部資産評価官、玉川税務署長などを経て、平成25年6月税理士登録。現在、相続税を中心に税理士業務を行っている。
○主な著書 「ケース別相続土地の評価減」、「非公開株式評価実務マニュアル」(新日本法規)、「判例・裁決にみる非公開株式評価の実務」(共著)(新日本法規)、「株式・公社債評価の実務」、「土地評価の実務」(共著)(大蔵財務協会)
※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
ta@lotus21.co.jp
3 所得税基本通達59−6について
従来、所得税法第59条第1項における非上場株式の時価については、所得税基本通達23〜35共−9の取扱いに準じて判定されてきたところであるが、同通達に定める「売買実例のあるもの」や「類似会社の株式の価額のあるもの」はわずかであり、ほとんどのケースにおいて「純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」により判定せざるを得ないところ、その具体的な算定方法が明確ではないとの指摘が少なからずあったところである。そこで、先に示されていた法人税の取扱い(脚注7)や個人の株式取引の実態を踏まえて設けられたのが、平成12年の所得税基本通達改正により設けられた59−6である(脚注8)。この通達には、上記2で紹介した事件で争点となった点を含め、分かりにくい点があり(脚注9)、実務において判断に迷うところもある。以下、この通達の適用に関して疑問の生じる点をみていくこととする。
(1)議決権割合の判定を譲渡前で行うのか、譲渡後で行うのか
上記2の事件の争点となったのが、配当還元方式が適用される「同族株主以外の株主等」に該当するかどうかの判定を、譲渡者の譲渡前の議決権割合に基づいて行うのか、それとも譲渡後の取得者の議決権割合に基づいて行うのかという点である。
所得税基本通達59−6(1)は、「財産評価基本通達188の(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかは、株式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること」と定めているものの、財産評価基本通達188の(2)、(3)及び(4)については、特に言及していない。しかしながら、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算して課税するとの譲渡所得課税の趣旨に照らせば、譲渡者の譲渡の時における価額を求めることは当然のことであり、同通達上に読替えの文言がないことをもって、これが否定されることにはならないと考えられる。
(参考)財産評価基本通達
| (同族株主以外の株主等が取得した株式) 188 178≪取引相場のない株式の評価上の区分≫の「同族株主以外の株主等が取得した株式」は、次のいずれかに該当する株式をいい、その株式の価額は、次項の定めによる。 (1)同族株主のいる会社の株式のうち、同族株主以外の株主の取得した株式 この場合における「同族株主」とは、課税時期における評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者(法人税法施行令第4条⦅同族関係者の範囲⦆に規定する特殊の関係のある個人又は法人をいう。以下同じ。)の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の30%以上(その評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が最も多いグループの有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の50%超である会社にあっては、50%超)である場合におけるその株主及びその同族関係者をいう。 (2)中心的な同族株主のいる会社の株主のうち、中心的な同族株主以外の同族株主で、その者の株式取得後の議決権の数がその会社の議決権総数の5%未満であるもの(課税時期において評価会社の役員(社長、理事長並びに法人税法施行令第71条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)である者及び課税時期の翌日から法定申告期限までの間に役員となる者を除く。)の取得した株式 この場合における「中心的な同族株主」とは、課税時期において同族株主の1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族(これらの者の同族関係者である会社のうち、これらの者が有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である会社を含む。)の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である場合におけるその株主をいう。 (3)同族株主のいない会社の株主のうち、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の15%未満である場合におけるその株主の取得した株式 (4)中心的な株主がおり、かつ、同族株主のいない会社の株主のうち、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の15%以上である場合におけるその株主で、その者の株式取得後の議決権の数がその会社の議決権総数の5%未満であるもの((2)の役員である者及び役員となる者を除く。)の取得した株式 この場合における「中心的な株主」とは、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の15%以上である株主グループのうち、いずれかのグループに単独でその会社の議決権総数の10%以上の議決権を有している株主がいる場合におけるその株主をいう。 |
高裁判決のように財産評価基本通達188(2)、(3)及び(4)については譲渡後の取得者の議決権割合で時価の評価方法を判定するとした場合、同族株主の判定は、譲渡者の譲渡前の議決権で判定しながら、中心的な同族株主がいる場合の議決権割合5%未満で、かつ、役員に該当しない同族株主の判定については、取得者の取得後の議決権で判定することとなるが、そのようなねじれた扱いは、到底理解できるものではない。また、従業員などの少数株主が、取得後に15% 以上の議決権割を有することとなる法人株主に譲渡した場合に、原則的評価方法を基にみなし譲渡課税を行うこととなるが、常識的ではない。
なお、所得税基本通達59−6と同様の定めを置く法人税基本通達2−3−4⦅低廉譲渡等の場合の譲渡の時における有償によるその有価証券の譲渡により通常得べき対価の額⦆で準用する同通達4−1−6⦅上場有価証券等以外の株式の価額の特例⦆(脚注10)には、所得税基本通達59−6(1)に相当する条件は明記されていないが、この通達が、法人税法第25条第3項⦅資産評定による評価益の益金不算入⦆の規定を適用する場合において、再生計画認可の決定があった時における当該株式の価額について定めたものであることから、所得税基本通達59−6の(1)に相当する条件を設ける必要がなかったものである。法人が、非上場株式を低額又は無償で譲渡又は取得した場合の寄附金課税又は受贈益課税においては、譲渡法人又は譲受法人のそれぞれの議決権割合により評価方法の判定を行うべきであると考えられる。
いずれにしても、令和2年3月24日の最高裁判決により、財産評価基本通達188の例による場合には、譲渡者の譲渡前の議決権に基づいて、譲渡者が原則的評価方法が適用になる者であるかどうかの判定を行い、譲渡者が原則的評価方法が適用される者であると判定されたならば、原則的評価方法により非上場株式の価額を判定することが明らかとなった。この点については、近いうちに通達改正が行われるものと見込まれる。
(2)いわゆる小会社方式
所得税基本通達59−6の(2)は、「当該株式の価額につき財産評価基本通達179の例により算定する場合(同通達189−3の(1)において同通達179に準じて算定する場合を含む。)において、株式を譲渡又は贈与した個人が当該株式の発行会社にとって同通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。」と定めている。小会社に該当するものとして評価するとは、原則として①純資産価額方式又は選択により②Lの割合を0.5として純資産価額方式と類似業種比準方式の併用方式により評価することを意味している。②の併用方式における類似業種比準方式とは、次の算式により評価会社の類似業種比準価額を求める方式である。
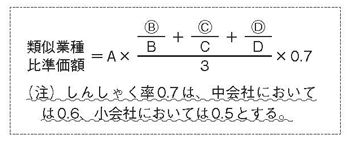
②の方式を選択した場合に、所得税基本通達59−6(2)に定める「「小会社」に該当するものとしてその例による」場合のしんしゃく率について次の二つの考え方があり得る。
(a)類似業種比準方式における算式中の斟酌率は、大会社は0.7、中会社は0.6とする。
(b)類似業種比準方式における算式中の斟酌率は、大会社又は中会社であっても小会社と同じく0.5とする。
(b)の考え方については、いわゆる小会社方式により評価した価額が、次頁の例のように所得税基本通達59−6の(2)の条件がなかったとした場合の価額を下回ってしまう事例が生じることが指摘できる(例参照)。
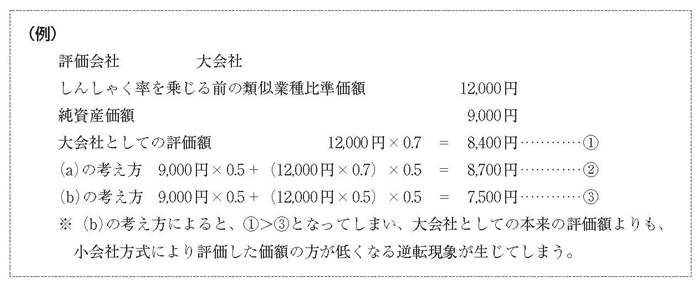
中心的な同族株主については、一般的な同族株主に比して、評価会社に対する支配力は強く、評価会社の有する資産への結びつきも大きいということができる。所得税基本通達59−6が同通達23〜35共−9の「その株式の発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」を受けて設けられた取扱いであることからすれば、評価会社への支配力のより強い中心的な同族株主が譲渡した株式の価額を評価するのに、純資産価額に着目することは、所得税基本通達56−6の上位規定である同通達達23〜35共−9との整合性を有する扱いであるといえる(脚注11)。
一方、類似業種比準価額を算定するうえで、類似業種比準方式の算式におけるしんしゃく率0.7を中会社においては0.6、小会社においては0.5とする趣旨が、評価会社の規模が小さくなるにしたがって、上場会社との類似性が希薄になっていくことから、この格差を適正に反映させるためにしんしゃく率に差異を設けたものであることからすれば、大会社の株式を「小会社」に該当するものとしてその例により評価する場合において、類似業種比準方式の算式中のしんしゃく率まで、小会社に適用される0.5による理由はないといえる。
さらに、(2)は、「財産評価基本通達179の例により算定する場合」について、「同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること」としているのであって、財産評価基本通達179についてのみ言及しており、財産評価基本通達180に定める算式の適用におけるしんしゃく率の読替えまでは行っていないのであるから、文理的にもしんしゃく率を0.7以外とする趣旨は含まれていないと考えられる(脚注12)。
(3)子会社等が有する土地等又は上場株式等
所得税基本通達59−6の(2)は、「当該株式の発行会社が土地(土地の上に存する権利を含む。)又は金融商品取引所に上場されている有価証券を有しているときは、財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については、当該譲渡又は贈与の時における価額によること。」と定めている(脚注13)。
財産評価基本通達では、同通達185本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、評価会社の有する資産の価額は、財産評価基本通達の定めによって評価した価額を基に計算することとされている。財産評価基本通達に定める土地及び土地の上に存する権利(以下「土地等」という。)は路線価方式又は倍率方式により評価することとされているが、これらの評価方式における路線価や評価倍率は、評価の安全性に配慮し、公示価格と同水準の価格の80%程度を目途として定められている(脚注14)。また、同通達は、上場株式、上場されている証券投資信託受益証券及び不動産投資信託の受益証券(以下「上場株式等」という。)については、課税時期の最終価格又は課税時期の属する月以前3か月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうち最も低い価額によって評価することとしている(評基通169(1)、199(注)、213)(脚注15)。
一方、譲渡所得課税における時価の評価においては、1年間の地価変動や一時的な価額の上下に配慮する必要はなく、まさに譲渡又は贈与の時における価額によることが相当であると考えられたため所得税基本通達59−6 の(2)が定められたものと思われる。
ところで、相続税又は贈与税の課税目的で評価会社の株式を純資産価額方式で評価する場合に、その評価会社がさらに非上場会社(以下「子会社等」という。)の株式を有する場合には、その子会社等の株式は財産評価基本通達の定めにより評価することとなり、その子会社等の株式を純資産価額方式で評価する場合において、その子会社等が土地等や上場株式等を有する場合には、それらの資産は、財産評価基本通達の定めによって評価することとなるが、譲渡所得課税目的での評価において当該子会社等が有する土地等や上場株式等の価額は、財産評価基本通達の定めにより評価したいわゆる相続税評価額によるのか、あるいは時価によるのかが問題となる(図表5参照)。
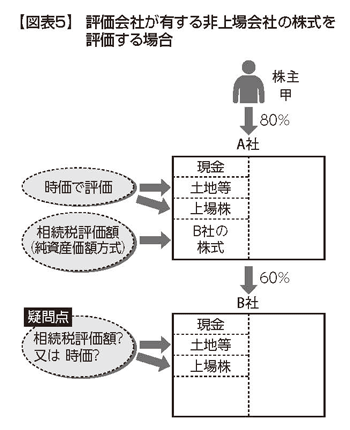
所得税基本通達59−6の(2)の文言上は、子会社等の有する土地等や上場株式等の評価についてまで言及されていないことから、評価会社の有する土地等及び上場株式等についてのみ所得税課税における時価によればよいこととなり(脚注16)、子会社等の有する土地等及び上場株式等については、この取扱いは及ばないものとも解される。
しかしながら、所得税基本通達59−6(2)の趣旨に照らせば、子会社等が有する土地等や株式等についても、財産評価基本通達の定めにより評価した価額ではなく、所得税課税における時価によることとなろう。上記最高裁判決も、所得税基本通達59−6(1)を文理解釈するのではなく、譲渡所得課税の趣旨から判断を下したところであり(脚注17)、同様に所得税課税における時価の観点からすれば、子会社等の株式を評価する場合においても、(2)がそのまま当てはまると考えることが常識的であろう。
なお、評価会社の保有する土地等及び上場株式等についてのみ(2)を適用することとしたとすれば、その趣旨は、実務上の簡便性に配慮したものと考えることもできるが、土地等の評価における路線価及び評価倍率は、上記のとおり公示価格と同水準の80%程度の価額となっていることから、相続税評価額を0.8で割り戻すことにより公示価格ベースの価額を算定する簡便的な方法も広く行われているところであり、地価の極めて高い地域に所在する土地等や値動きの著しい地域にある土地等などを除き、実務上はこのような手法も許容されるところであり、また、上場株式等について、譲渡の日の最終価格とすることは、財産評価基本通達の定めよりも簡便であることに照らせば、このような見方は当を得たものとはいえないであろう。
(4)純資産価額方式における法人税等相当額
財産評価基本通達に定める純資産価額方式においては、1株当たりの純資産価額を、相続税評価額ベースの資産の価額の合計額から負債の金額の合計額を控除し、さらに評価差額に対する法人税等相当額を控除することとされている(評基通185)が、所得税基本通達59−6(4)では、法人税等相当額の控除はしないとしている。
財産評価基本通達185において、1株当たりの純資産価額を計算する場合に、評価差額に対する法人税等相当額を控除するのは、「個人事業主がその事業用資産を直接所有するのとは、その所有形態が異なるため、両者の事業用資産の所有形態を経済的に同一の条件のもとに置きかえたうえで評価の均衡を図る必要があることによるものである」と説明されている(脚注18)。これに対して、所得税課税に係るみなし譲渡所得の算定に伴い、取引相場のない株式の評価における1株当たりの純資産価額を計算するに当たっては、通常の取引においては会社が継続的に事業活動を行うことを前提として取引価額が形成されることから、当該譲渡時において当該会社の正味資産の価額を参酌して算出した価額を算定する趣旨に出たものと解される(脚注19)。
かつて所得税基本通達59−6は設けられておらず、法人税基本通達にもこの点について明確な定めがなかったことから、法人税等相当額の控除の適否を巡っては、見解が分かれることがあったが(脚注20)、平成12年に所得税基本通達59−6が設けられ、法人税基本通達も改正された今日では、所得課税の場面で非上場株式を純資産価額方式で評価する際に、法人税等相当額を控除しないことは、定着した扱いであるといえる。
(5)純然たる第三者間取引
所得税基本通達59−6の取扱いは、通達中の文言にも記載されているとおり原則的な取扱いとして定められており、このことはこの通達が適用されない例外的な場合があることを意味している。国税庁担当者によるこの通達の解説によれば、「純然たる第三者間において種々の経済性を考慮して取引された場合など、所得税基本通達59−6の定めを形式的に当てはめて、低額譲渡かどうかを判定することが相当でない場合」を例外的な場合として掲げている(脚注21)。
しかしながら、純然たる第三者間において種々の経済性を考慮して決定された価額であるかどうかの判定は、容易なことではない。そもそも取引相場のない株式の売買自体が限られた当事者間でしか行われない。親族関係や同族関係にある当事者間の取引がこれに該当しないことは言うまでもないが、これらの関係にない当事者間での取引だからといって、例えば、その株式の発行会社の取引先や取引銀行との間で行われた取引がこの例外的な場合に該当するとは、一般的には、考えにくい。譲渡者は少しでも高く売りたい、譲受者は少しでも安く買いたいという思いがあり、そうした両当事者の間で決定された価額であるから、上記通達の解説に示す例外的な場合に該当するという考え方は、少々短絡的にすぎると思われる。誤解を恐れずにあえて言うならば、取引相場のない株式の売買においては、企業買収などの場面を除けば、純然たる第三者間において経済性を考慮して価額が決定されるケースは極めて限定的なケースと考えるべきではないだろうか(脚注22)。
(6)いわゆる高額譲渡
非上場株式の譲渡に係る課税関係について説明する場合、①時価相当額の対価で譲渡した場合、②時価を下回る対価で譲渡した場合(無償譲渡を含む。)及び③時価を上回る対価で譲渡した場合の3つのパターンに分けて説明することが多い。その説明自体はそれほど難しいものではないが、③の時価を上回る対価で譲渡した場合(以下「高額譲渡」という。)に該当するかどうかの判定は非常に難しい。所得税基本通達59−6の定めによって評価した価額を上回る対価の額による譲渡は高額譲渡に該当するかのような説明も一部にみられるが、このような考え方は必ずしも正しい考え方ではない。
同通達で「例による」としている財産評価基本通達は、相続税等の課税を目的として定められたものである。相続税等が臨時偶発的に生じる税であり、また財産に対する課税であって、課税対象の財産は一般的には譲渡を目的としたものではないなどの相続税等に固有の性質を考慮し、評価の安全性に配慮したものとなっている。類似業種比準方式においては、類似業種の選定、類似業種の株価の選定、1株当たりの利益金額の算定、1株当たりの純資産価額の算定、比準要素を1株当たりの配当金額を含む3要素としていること、しんしゃく割合を設けていることなど評価額を引き下げる仕組みが随所に設けられており、純資産価額方式においては、所得税基本通達59−6において土地等及び上場株式等については相続税評価額ではなく「時価」によることとしているものの他の財産については相続税評価額を用いている。また、これらの方法によっては、株式の価額に影響する評価会社の将来性、技術力、開発力、経営者の能力、従業員の質などの要素は加味されることがない。さらに、少数株主(被支配株主)に至っては、配当還元方式という過去の配当実績のみに着目した評価方法が採られている。
株式の売買において、買主はできる限り低い価額で取得したいと考えるが、売主はできる限り高い価額で譲渡したいと考える。その場合、評価の安全性に配慮された財産評価基本通達に定められた評価方法により評価した価額が当該株式の適正な価額とは考えないであろう。上場株式等とは異なり、一義的な価額を算定することのできない非上場株式であれば、その価額には一定の幅があると考えるべきであり、財産評価基本通達の定めによって評価した価額又は所得税基本通達によってこれを一部修正した方法によって評価した価額は、その幅の最低ラインと考えるべきであり、その上限は、現行の通達では定められていないのである。したがって、高額譲渡に該当するかどうかについては、個々の取引ごとに慎重に検討すべきこととなる。
4 おわりに
所得税において、非上場株式について財産評価基本通達の定めに準じた時価評価をすることとしたことから、税目の差異による取扱いの修正が問題となることはこれまで見てきたとおりである。上記に指摘した点以外にも相続税・贈与税課税を目的として定められた財産評価基本通達を所得税や法人税の課税を目的として使用する場合に問題となる点は、他にもあり得る(脚注23)。上記3で指摘した点を含め、明確化が望まれる。
さらに、財産評価基本通達の定めを利用することとしたことから、財産評価基本通達自体が抱える多くの問題点も同時に抱え込むこととなってしまった(脚注24)。
最近、生活雑貨の企画販売等を行う会社の株式の譲渡を巡って、譲渡者である個人及び法人に対して更正処分が行われたとの報道がされた(脚注25)。報道によれば、1株当たり約8万円の譲渡価額に対し、国税当局はこの会社の株式1株当たりの時価は約84万円であると認定したとのことである。詳細は不明であるが、譲渡前に子会社を吸収合併したことにより、評価会社の資産が大幅に増加した点が問題視されたようである。合併後に課税時期がある場合に類似業種比準方式を適用することができるかどうかについては、個々の事例ごとに判断することとなる旨を解説した文献も存する(脚注26)。通達にはその旨の具体的な記載がないから、いわゆる総則6項が適用される場面ということかもしれないが、具体的な取扱い基準が示されることが望まれる(脚注27)。また、時価評価に関する所得税基本通達及び財産評価基本通達の定めの一層の適正化が期待される。
脚注
7 法人税基本通達9-1-14⦅上場有価証券等以外の株式の価額の特例⦆。なお、この取扱いは株式の譲渡が行われた場合の時価について直接規定したものではなく、資産の評価損の計上を行う場合の「期末の時価」についての取扱いを定めたものである。
8 一色広己ほか共編「所得税基本通達逐条解説(平成29年版)」(大蔵財務協会)716頁。
9 最高裁判所宮崎裕子裁判官は、上記判決における補足意見の中で「所得税法適用のための通達の作成に当たり、相続税法適用のための通達を借用し、しかもその借用を具体的にどのように行うかを必ずしも個別的に明記しないという所得税基本通達59-6で採られている通達作成手法には、内容を分かりにくいものにしているという点において問題があるといわざるを得ない。」と述べている。
10 法人税基本通達4-1-6は、平成17年の通達改正により追加されたものであり、それ以前は、法人税基本通達2-3-4は、同様の規定である法人税基本通達9-1-14⦅上場有価証券等以外の株式の価額の特例⦆を準用していた。
11 「譲渡者が支配的な立場にある中心的な同族株主に該当する場合には、純資産価額を原則とする小会社として判定することによって、できるだけ純資産価額の影響度合を高めて算定しようとしたものと考えられます。」(与良秀雄著「非上場株式の評価と活用の留意点Q&A」(平成30年・税務研究会出版局)253頁)。
12 「判定会社の併用方式に限って小会社とするもので、その併用方式における類似業種比準価額を算定する場合は、本来の会社規模により算定すべきと考えられます。」(与良前掲書253頁。同245頁にも同旨の説明がある。)。
13 なお、財産評価基本通達185かっこ書きにおいて、評価会社が課税時期前3年以内に取得又は新築した土地及び土地の上に存する権利並びに家屋及びその附属設備又は構築物の価額は、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価することとしていることから、これらの資産については、所得税基本通達59-2(2)の定めにかかわらず、時価により評価されることとなる。
14 北村厚編「財産評価基本通達逐条解説(平成30年版)」(大蔵財務協会)52頁及び国税庁報道発表「令和元年分の路線価等について」(国税庁ホームページ)など。
15 「1時点における需給関係による偶発性を排除し、ある程度の期間における取引価格の実勢をも評価の判断要素として考慮し、評価上のしんしゃくを行うことが適切である」との趣旨によるものである(前掲北村編541頁)。
16 与良前掲書249頁では、子会社等の有する土地等及び株式等については、「あくまでも評価通達の例(相続税評価額)によって算定することになります。」と説明されている。
17 宇賀克也裁判官は補足意見の中で、「所得税基本通達59-6は、評価通達の「例により」算定するものと定めているので、相続税と譲渡所得に関する課税の性質の相違に応じた読替えをすることを想定しており、このような読替えをすることは、そもそも、所得税基本通達の文理にも反しているとはいえない」と述べている。
18 北村厚編前掲書655頁。
19 平成27年12月11日東京地裁判決、平成28年9月8日東京高裁判決。
20 昭和62年分の所得税に関する事件で、平成17年11月8日最高裁判決は、通達の制定を意識しつつ「営業活動を順調に行っている会社の株式であっても、法人税額等相当額を控除して算定された1株当たりの純資産価額は、昭和62年当時において、一般には通常の取引における当事者の合理的意思に合致するものとして、所得税基本通達23~35共-9(4)にいう「1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」に当たるというべきである。」と判断している。
21 一色広己ほか共編「所得税基本通達逐条解説(平成29年版)」(大蔵財務協会)718頁。
22 財産評価基本通達に定める評価方法は、相続税等の課税を目的として定められたもので、相続税等に固有の事情から評価の安全性に十分な配慮がされている。所得税基本通達59-6において、一定の読替えを行っているにしても、なお評価の安全性への配慮の部分は多々存することからすれば、同通達により評価した価額は依然として本来の時価よりも低めに評価されるケースが多いと思われる。したがって、純然たる第三者間で種々の経済性を考慮して決定された価額は、通常は、所得税基本通達59-6により評価した価額を上回ることとなるのではないかと思われる。
23 例えば、評価会社に中心的な同族株主が存するときに、同族株主に該当する法人が保有する評価会社の議決権割合が5%未満であるならば、常に特例的評価方法が適用されることとなるのかどうか、原則的評価方法が適用される場合があるとすれば、それはどのような場合なのか疑義がある。財産評価基本通達は相続、遺贈又は贈与により財産を取得した個人に対する税であることから、法人が保有している株式を前提とはしていないためにこのような疑義が生じるものである。
24 例えば、財産評価基本通達における純資産価額方式では、評価会社の退職給付債務については考慮されないが、株式の売買における価額交渉では、退職給付債務についても考慮されるであろう。この点については、関係団体から財産評価基本通達の見直しの要望がされているところである(日本税理士会連合会「令和2年度税制改正に関する建議書(令和元年6月27日)」、日本公認会計士協会「令和2年度税制改正意見・要望書(2019年6月)」など。)。
25 日本経済新聞令和2年4月3日夕刊、同4日夕刊。
26 加藤千尋編「平成31年版 株式・公社債評価の実務」(大蔵財務協会)234頁には、「合併後に課税時期がある場合に類似業種比準方式により取引相場のない株式の評価ができるかどうかは、個々の事例ごとに、直前期末(あるいは直前々期末)における比準3要素について、合理的な数値が得られるかどうかによります」との記述がある。
27 日本公認会計士協会「令和2年度税制改正意見・要望書(2019年6月)」においても、「合併などの組織再編成後における株式等の評価方法として、類似業種比準価額の適用が可能となる要件を明確にすること」を要望している。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















