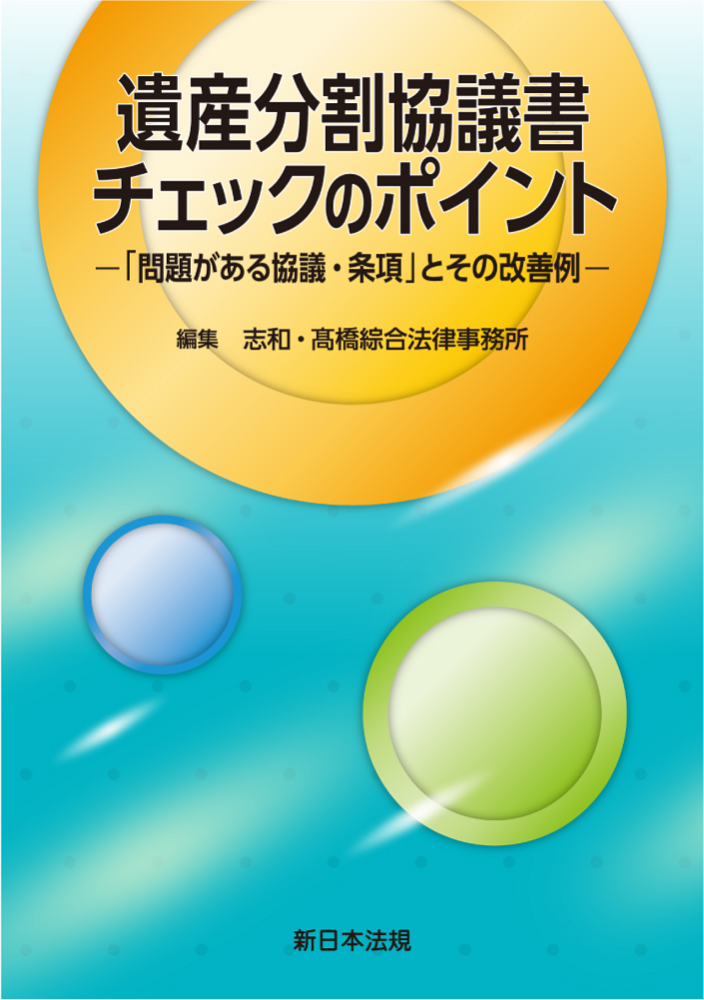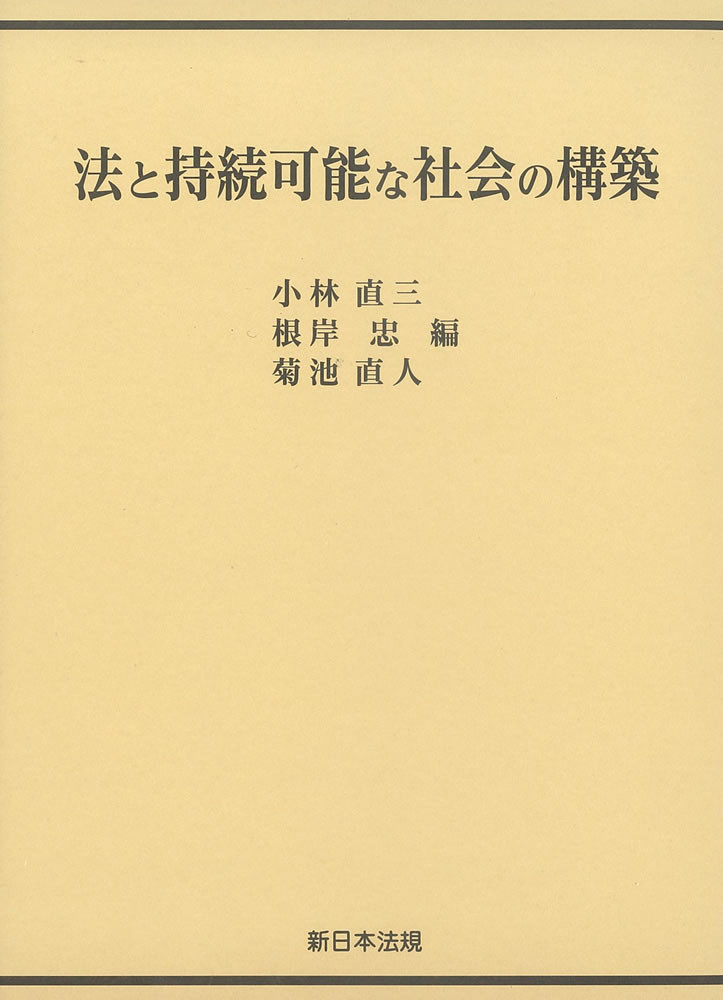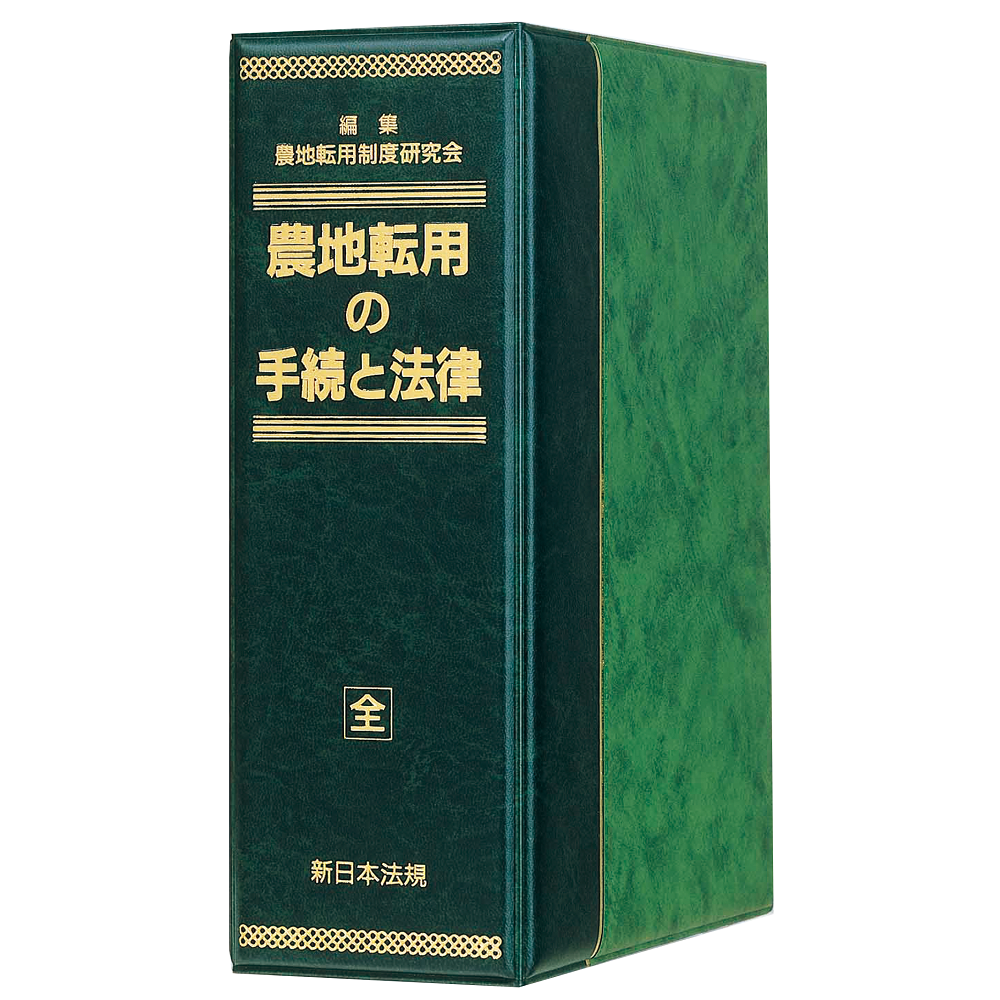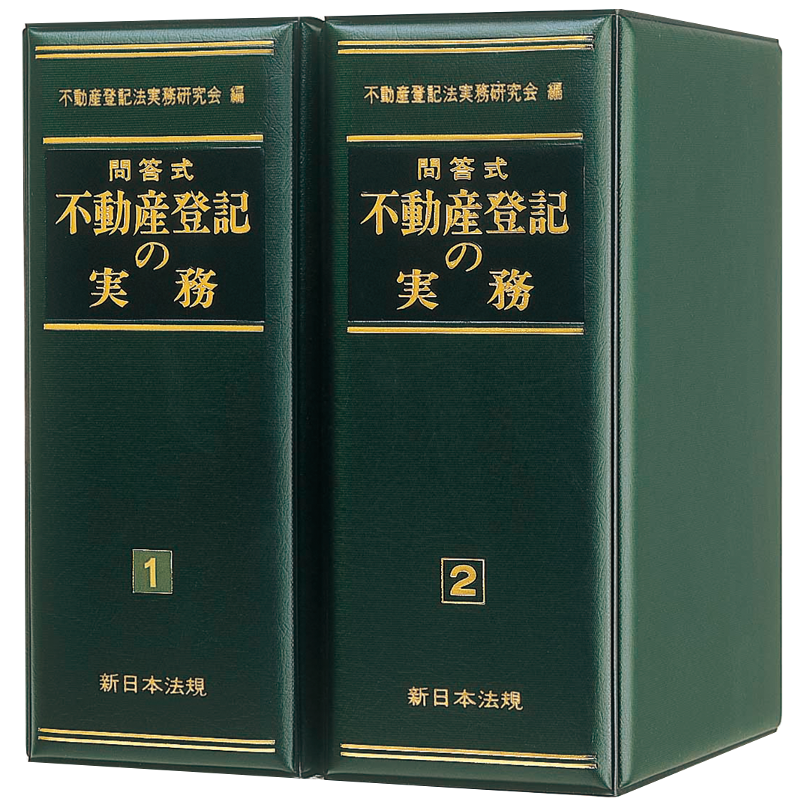行政2025年04月26日 まちの将来は、模索続く 「平成の大合併20年」「地域の明日は」 提供:共同通信社

政府が推し進めた「平成の大合併」。多くの市町村が今年、合併から20年を迎える。人口が減る中、再編で規模が拡大した自治体も、合併しない道を選んだ自治体も将来のまちづくりに向け模索が続く。合併論議が再燃した地域もある。各地の動きを追った。
行政は効率化、弊害も 政府主導、市町村数半減
「平成の大合併」は1999年から国が主導した。少子高齢化で財政が悪化する中、地方分権の受け皿となる自治体の行財政基盤を強化する目的だ。市町村数は3232から、2010年には半分近くの1727へ減少。人件費削減や行政の効率化に効果があった半面、周辺部衰退など弊害もある。
各地で難航する合併協議を後押ししたのが国の誘導策だ。借金返済額の7割を国が負担する「合併特例債」などが「アメ」、小規模な自治体に対する交付税割り増しの縮小が「ムチ」として機能した。
特に、人口1万人未満の自治体の多くが姿を消した。99年には全体の約半数に当たる1537あったが、10年には3分の1以下の457に。99年から20年にかけた変化を都道府県別に見ると、19県で80%以上減少。兵庫は35から0、長崎は55から2になった。
国が成果とするのは、公共施設の統廃合、市町村長や議員らの削減といった歳出改革だ。国の財政優遇策を活用した施設、インフラ整備が進み、広域的まちづくりもしやすくなった。
ただ「合併して良かったという話はほぼ聞かない」(全国町村会幹部)との声も。中心部から離れた旧市町村の衰退、行政サービスの利便性低下が指摘される。
公共施設の集約が進まず維持費が膨らみ、財政優遇策の打ち切りや大型事業の借金返済で財政が苦しくなった例もある。
合併派も単独派も過疎進む 徳島・美波町、牟岐町
太平洋に面した徳島県美波町は2006年に旧由岐、旧日和佐の2町合併で誕生し、今年20年目を迎える。これに加わり「美海町(みうみちょう)」となる予定だった隣接の牟岐町は、直前の破談により、単独で存続。自治体の在り方の選択は分かれたが、ともに過疎化に直面している。
「今もまだ旧町それぞれのことを考えながら行政を進めている」。09年に就任した美波町の影治信良(かげじ・のぶよし)町長(69)は打ち明ける。当初掲げた一体感の醸成には「まだ至っていない」という。
病院再編が最初の課題だった。東日本大震災で病院が被災した宮城県南三陸町を訪れ、旧由岐にある高台への移転を決断。反発の中、旧日和佐には診療所を整備し、理解を得た。
合併のメリットの一つは公共施設集約だ。診療所の整備が財政効果を打ち消したとの批判もあるが「効率性だけではうまくいかない」(影治氏)。インフラ整備からソフト事業まで旧町どちらかの住民にしわ寄せがいかないよう常に心がける。
人口は合併当時から3千人近く減り、5700人弱に。南海トラフ巨大地震に備え、まちづくりを続けており、影治氏は「住民が安心感を持った中で暮らしていけるようにする。エリアが広がってもその使命は変わらない」と誓う。
一方、合併しなかった牟岐町。5千人超いた人口は3500人を割った。ただ町出身で今年、東京から拠点を移した会社役員田中美有(たなか・みゆ)さん(28)は「山も海もあって、観光開発もされていない。輪郭が変わらないが故に町を大事に思う人が多い」と魅力を語る。
町議会議員7期目の藤元雅文(ふじもと・まさふみ)さん(74)は「合併しないと国の交付税は減り、財政破綻すると言われたがそうはならんかった」と振り返る。財政的厳しさは変わらないが、状況は悪くなってないという。「行政と住民の距離が近く、地方自治の本旨の理想にかなった形になっている」
「令和の合併」活路探る 大阪・南河内2町1村
少子高齢化と大都市への人口集中により「近い将来、住民サービスが維持できなくなる」と危機感を抱く地方の自治体は多い。そうした中「令和の合併」に活路を見いだそうとする地域もある。
3月下旬、大阪府南東部に位置する千早赤阪村で同村、河南町、太子町の3町村長が一堂に会する「未来協議会」が開かれた。「近隣市を巻き込んだ形で合併議論をするのが若い世代への責務だ」(田中祐二(たなか・ゆうじ)太子町長)。3人は、3町村に限らない広域合併を模索することで一致した。
協議会による推計では、2町1村の人口は、2020年時点の3万3615人から50年時点で2万175人と、約4割も減少する。
財政は苦しくなり、公共施設やバス路線など住民サービスの維持は難しくなる。23年に設置した協議会は町村事務の共通化、公共施設の共同利用などを進めてきたが、効率化には限界がある。
この日の会合では、合併による効果を検証。3町村の合併では、収支がさほど改善しないとの結果が示された。近隣市を巻き込み、10万人規模以上の合併を目指すしかないというのが結論だ。
ただ「平成の大合併」で早急な協議に住民が反発するなどし、近隣市との合併が頓挫した経緯もある。
合併特例債など国の優遇措置もない中で「複数の市と話はしているが、参加自治体を増やすのは容易ではない」(協議会関係者)。
会合参加者は「小さな自治体はいよいよ厳しくなっている。自治体間の連携だけでは効果が薄く、令和でも合併が選択肢になるよう国に制度設計を求めたい」と訴えた。
総務相「将来300市」 地方自治の将来に一石
「1700以上ある自治体数は300~400市で済む」「県庁もいらない」。2月、村上誠一郎総務相の唐突な発言が自治体関係者らの反響を呼んだ。今世紀末に日本の人口が半減するという推計を踏まえると、現在の自治体規模は維持できないとの趣旨だ。「個人的見解」と断ったが、共感する声もあり、地方自治の将来を巡って一石を投じる形となった。
発言があったのは2月13日の衆院総務委員会。村上氏は、人口半減が予測される将来に「国、県、市町村のシステムが本当に構成できるのか、危惧を持っている」と指摘した。
その上で「全国を30~40万人規模の市で区切れば300~400市で済む。その市が国と直接交渉できるシステムが一番いいんじゃないか」と持論を展開した。
現実になれば「平成の大合併」を上回る大再編で、さまざまな反応があった。一見勝之三重県知事は「都道府県の役割は大きい」と反論。江崎禎英岐阜県知事は「国ではきめ細かい(住民)対応が難しく、経済単位として市町村は小さすぎる」と疑問視した。
一方、吉村洋文大阪府知事は「今のままで日本は本当に持つのか、という点は共感する」、大村秀章愛知県知事は「市町村を集約し、ある程度の固まりにするのは合理性がある」と理解を示す。
総務省幹部は「このままでは自治体が立ちゆかなくなるというのは共通認識だ。ただ、そこに至るまでに知恵を出して何をなし得るかが重要」と指摘。まずは自治体間の広域連携などで行政の効率化を進める方針だ。
(2025/04/26)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
関連商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.