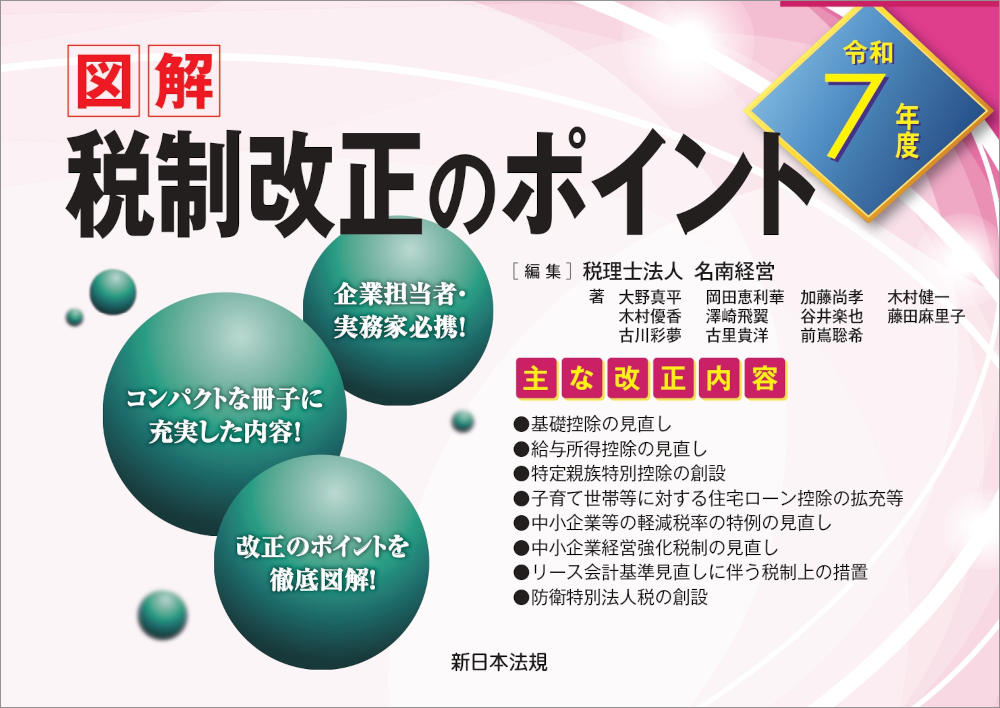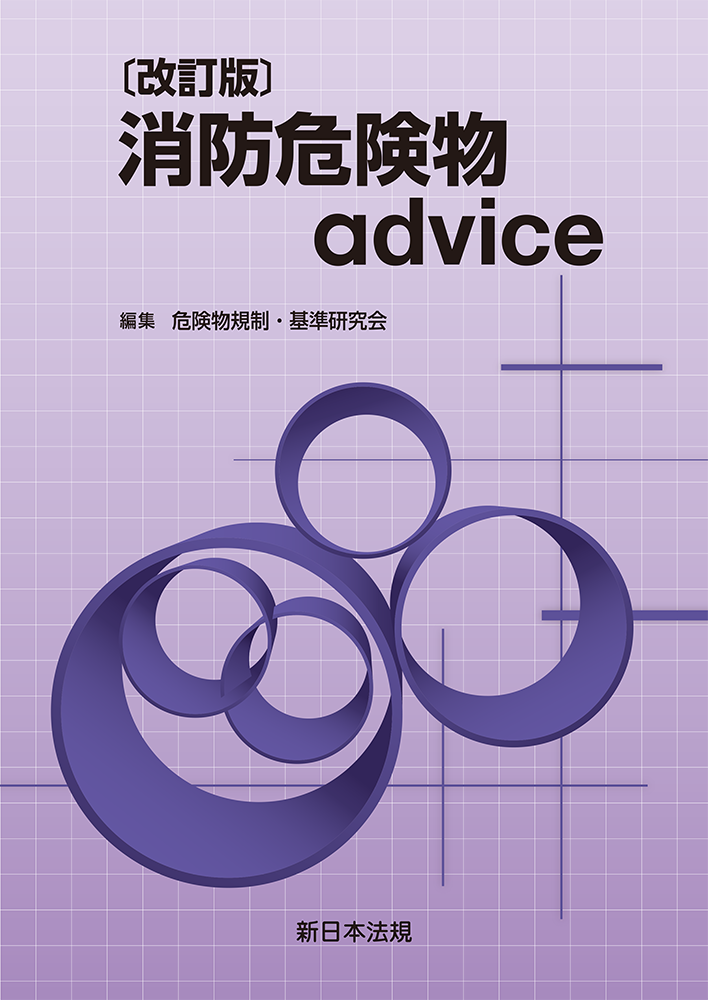解説記事2012年05月21日 【第2特集】 組織再編成税制を巡る否認が相次ぐ中、今明かされる「行為計算否認規定(法人税法132条の2)の創設の経緯・目的と解釈」(2012年5月21日号・№451)
座談会(3・了)
組織再編成税制の立案担当者 × トップ法律事務所タックスロイヤー
組織再編成税制を巡る否認が相次ぐ中、今明かされる「行為計算否認規定(法人税法132条の2)の創設の経緯・目的と解釈」

大きな反響を呼んだ本座談会も、今回が最終回となる。第3回目となる今回は、繰越欠損金の活用を狙いとする組織再編成の問題や、法人税法132条の2に関する税務訴訟の意義、同条の適用の課題のほか、同条の適用を巡り税務執行当局と対峙することになる企業の対応などについて語ってもらった。
追徴課税負担の取り決めと「第三者間取引」
藤田 この裁判(編注:前号24ページで取り上げた組織再編成に関する税務訴訟)でも問題になっていると聞いていますが、追徴課税負担の取決め(編注:組織再編成の当事者が組織再編成に関して追徴課税を受けた場合、その組織再編成の他方当事者やその他の関連者が追徴税額相当額に対応する追加の支払い義務を負うもの)を組織再編成の契約に盛り込むことは問題なのでしょうか。税務当局はそれを問題視しているようですが。
朝長 確かに、組織再編成における当事者のいずれかが税金を減らすメリットを享受するということであれば、そのような契約は何ら不自然ではないという主張もあり得ると思います。
しかし、法人税制においては、取引の妥当性は、お互いに利害関係のない者同士で取引を行うときのその取引―「第三者間取引」や「独立当事者間取引」と言ってもよいのかもしれません―が自然で妥当性のある取引であるという考え方に立っていることに留意する必要があります。
追徴課税負担の取決めの問題に関しても、支配関係も特別な利害関係もない上場会社同士が組織再編成を行う場合にそのような取引をするのか、ということを考えてみればよいわけで、「そのような取引はしない」ということであれば、現にそのような取引をしたケースには「そのような取引をする特別な理由がある」ということになります。

―「そのような取引」とは、例えばどのような取引でしょうか。
朝長 例えば、税金の減少のメリットを本来の享受者でない者が享受したり、そのスキーム取引やセット取引を提案した者が享受したりするケースです。そのようなケースにおいては、現実に税務否認が行われて追徴課税を受ける場合には、税金の減少のメリットを受けることになっていた者や、そのスキーム取引やセット取引の提案者も追徴税額を負担する、ということでなければおかしいわけです。
仲谷 税金減少のメリットを当事者間で分け合い、それを経済的に調整―精算―するというのは不自然でしょうか。
藤田 誰が税務メリットを受けるのかによって変わってくるでしょうね。不自然な税額減少メリットの分配を意図したような取引でない場合であれば、追徴税額負担条項が入っているというだけで、取引が不自然だという結論になるわけではありません。グループ外の組織再編成を行う場合には、合理的な企業であれば、当然その組織再編成による税務効果を考慮に入れて相手方との条件交渉をしますので、想定した税務効果と異なる結果になった場合に備えた条項を入れること自体は、必ずしも不自然とは思いません。しかし、朝長先生がご指摘のように、税制上税務メリットを受けることが想定されていない当事者やスキームのアレンジャーが税務メリットの相当の部分を持っていくような取引は、「不自然」な取引ではないかという疑いを呼ぶ理由にはなり得るでしょうね。
朝長 自分の税金は自分で負担し自分の税金の減少のメリットは自分が享受するというのが通常の姿であるわけですが、他人の税金を自分が負担したり他人の税金の減少のメリットを自分が享受するという通常ではない取引を行うということになれば、通常ではない契約をせざるを得ない、ということになるものと考えられます。
先般、話題になりましたパチンコ業の租税回避においては、スキームの提案者が税金の減少額の一定割合を報酬としてもらい、「スキームが否認された場合にはそのスキームの提案者がもらった報酬の半分を返す」という内容の契約が交わされていたようです。
繰越欠損金の取引は組織再編成の本体取引そのものではない
仲谷 欠損金の繰越額を有する会社で、事業を行っていないに等しいものを買い取って、その欠損金の繰越額を使って税金を減らすという“節税策”があると思います。これについては、もちろん個別の否認規定(法人税法57条の2)がありますが、それが適用されないのであれば、欠損会社を買収した会社は、欠損金の利用というメリットをフルに受けられるとも考えられますが。
朝長 欠損金の繰越額がある会社の買取りに際しては、その税の減少効果額が取引金額を左右することがあります。そのようなケースでは、その税の減少効果額の一定額が取引金額とされるわけですが、その金額はケースによってかなり異なると言われています。
欠損金の繰越額を有する会社の価値をどのように考えるべきかということに関して、参考となるものがあります。日本公認会計士協会の会計制度委員会研究報告第11号「継続企業の前提が成立していない会社等における資産及び負債の評価について」(平成17年4月12日)では、被合併会社の資産及び負債の評価と繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、次のように述べています。
仲谷 なるほど。欠損金の繰越額のある被合併法人がその欠損金の繰越額を損金の額とすることによって減少する税額の回収可能性を判断して繰延税金資産を計上する場合には、その欠損金の繰越額が合併法人において使用できるという前提で考えるのではなく、被合併法人が単独で事業活動を続けると仮定して考える必要がある、ということですね。
朝長 そうです。これは会計上の考え方を示したものではありますが、被合併法人の事業価値や株価を適正に捉えるという観点からしても、妥当性があると考えられるところです。
藤田 このような観点から被合併法人の資産及び負債の価値を評価するということになると、被合併法人から承継する事業からの利益では被合併法人が有していた繰越欠損金やその他の繰延税金資産をとても回収する見込みがないというような場合であれば、合併の結果として被合併法人の欠損金の繰越額によって合併法人の固有の所得が相殺されて納税額が減少するというその減少額については、被合併法人ではなく、合併法人が得るべきもの、ということになりますね。
朝長 はい。仮に、その減少額に相当する金銭等が被合併法人の株主に交付されるということになると、合併による被合併法人の資産及び負債の移転の取引とは別に、欠損金の繰越額の取引が行われた、と見ることもできます。被合併法人に欠損金の繰越額が無かった場合にどのような取引となるのかということを考えてみると分りやすいのですが、税務執行当局も、当然、そのように見るのではないかと思われます。
藤田 そのように整理して捉えると、収益力が乏しくて繰延税金資産の回収可能性に疑問があるような被合併法人による組織再編成において、組織再編成に関連して合併法人に対して追徴課税が行われた場合に、「被合併法人の株主はその追徴課税の額に相当する金額を返還する」という内容の契約を締結したとしたら、その取引は実質的には欠損金による節税効果の取引であった可能性があることが分るということですね。
朝長 そうですね。追徴税額相当額の返還契約取引の部分だけを見るのではなく、通常は合併法人が享受することとなる税の減少のメリットを被合併法人の株主が享受するという取引と追徴税額相当額の返還契約取引の全体を見て、「通常」であるのか「自然」であるのかといった議論をする必要があるわけです。
外国税額控除事件の判決文(編注:大阪高裁判決(平成14年6月14日))においては、「外国税額控除の余裕枠を他人に利用させ、その対価を得ること自体を正当な事業目的ということはできない」と述べられていたと記憶しています。例えば、繰越欠損金を有する法人の株主がその株式を譲渡する場合、その法人が自社で使い切れる分の繰越欠損金によって減少することとなる税額は株式の譲渡対価に反映されるはずですが、それを超える税額の減少額、つまり、使い切れない繰越欠損金によって減少することとなる税額が譲渡対価に反映されることはないはずです。仮に、その株主が、その株式を譲渡して、その法人が使い切れない繰越欠損金によって減少することとなる税額を反映した金額までも譲渡対価として得るとすれば、その部分に関しては「正当な事業目的」とは言えない目的の取引―税金を減少させる「権利」の取引―が行われているということにならざるを得ないでしょうし、これを「通常」とか「自然」「合理的」とか言うことはできない、ということになる可能性が高いのではないでしょうか。
パートⅣ 企業に求められる対応
132条の2を巡る税務訴訟の意義 ―長時間に及ぶこの座談会も、そろそろまとめに入りたいと思います。近年、132条の2を巡る税務否認事例が出始め、そのうちの一部は、大型訴訟へと発展しています。こうした税務訴訟の意義やあり方についてお考えをお聞かせください。
朝長 仲谷先生の方から、この法人税法132条の2を巡る争いは過去の税務訴訟の中でもとりわけ大きな影響を与えるものになるのではないかというお話がありましたが(編注:第2回26ページ参照)、私もそのように感じております。組織再編成において問題となる金額は非常に大きい場合があり、また、先ほども触れたように(編注:第2回26ページ参照)、法人の7割以上が赤字という状態が長く続く我が国においては繰越欠損金が期限切れになりそうな法人が非常にたくさんあるわけで、現在訴訟中の案件ほど大きな影響を与えることとなる税務訴訟は、今後、当分の間は出てこないのではないかとさえ思っています。
仲谷 どのような事実がどの要件に該当するから……というように、検証可能な理由で結論を出していただきたいと思います。そのためには、今日、お話に出てきたような132条の2を巡る解釈論が必須です。
朝長 ただ、税金を減らそうとして度を過ぎた“節税”を行っている一部のケースは別として、組織再編成を行うに当たって節税を考えながらやるということは、別におかしなことではありませんので、そのような大多数の真っ当な組織再編成が行い難くなるというようなことでは困るわけです。
藤田 それはおっしゃるとおりですね。真っ当なものは認められなければなりません。
仮装隠ぺいよりも租税回避を問題にする時代に ―132条の2による否認事例は今後も増加することが予想されますが、否認を行う側である税務執行当局についてはどのような感想をお持ちでしょうか。
朝長 現実には、仮装・隠ぺいによって税金を少なくしようという人は僅かで、しかも、数百億円や数十億円という多額の税を減らすために仮装したり隠ぺいしたりするという人はまずほとんどいない、と言ってもよいと思います。大きな金額の節税をしようとする人は、「体」を使うのではなく「頭」を使うわけですから、税務上の問題があるとすれば、それは、仮装・隠ぺいではなく、租税回避ということになります。このため、税務執行当局は、今後ますます「租税回避」に目を向けることにならざるを得ないでしょう。
藤田 最近は、海外で組織再編成を行うという例が急速に増えていますので、今後、国内の組織再編成だけでなく、海外の組織再編成に関して132条の2が適用されるというケースが生じてくることも考えられると思いますが、海外で組織再編成を行った場合の取扱いは、必ずしも明確ではありません。国税当局においては、海外で組織再編成を行った場合の取扱いを公表するという話もあるようですが、そうであれば早めに公表してもらいたいですね。
海外の組織再編成は、我が国の会社法とは関係のないところで行われますので、いわゆる「借用概念」、つまり、会社法や民法における法律用語の解釈に依拠して税法を解釈するという手法は、説得力に欠けます。正に、我が国の法人税法が組織再編成をどのようなものと考えているのかということが問われるわけで、そこのところをはっきりさせないと、海外の組織再編成への132条の2の適用の有無も正しく判断できないのではないかと思います。

朝長 おっしゃるとおりです。そのうちに、海外の組織再編成に132条の2が適用されるというケースが発生すると思いますね。外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)、移転価格税制や外国税額控除制度などとの関係が論点になることもあるはずです。
本誌(編注:本誌439号18頁「税務マエストロ」参照)でも書きましたが、「合併」や「分割」などの法人税法で用いている用語は全て法人税法における「合併」であり法人税法における「分割」であるという当たり前のことが十分に理解されていない向きがあるようです。しかし、そのような状況はさておき、税務調査では、132条の2の適用の有無が問題とされる可能性があるわけですから、むしろ国内の組織再編成以上にしっかりとした対応が必要になると思われます。
―132条の2の適用についてはどのような課題があると思われますか?
仲谷 何が良くて何が良くないのかということを、網羅的・具体的に法律に書ければ良いのでしょうが、現実にはそれは無理でしょう。とすると、現在問題になっている事案において、裁判所が整合性と説得力のある判断をしてくれることを望みます。そのためには、代理人となる弁護士が、条文のきちんとした解釈に基づき主張と立証を行わなければなりません。
そういう意味では、我々の責任は重大だと感じております。

朝長 企業活動は昔のように単純ではありませんし、企業を取り巻く環境も非常に複雑かつ多様になっていますので、それに合わせて「良いもの」と「良くないもの」が具体的に示されていく必要があると思いますが、企業が行う行為や計算の全てを予め知るといったことは不可能です。このため、包括的な租税回避防止規定を設けた上で、そこには必ず「不当」というような抽象的な不確定概念を用いざるを得ないという点は、承知しておく必要があります。世の中の租税回避の全てを知悉して具体的に書けるということであれば、それらの防止規定を個々に定めればよいわけであり、そもそも包括的な租税回避防止規定は必要ないわけですが、現実はそうは行きません。このような租税回避防止規定の宿命は、よく承知しておかなければなりません。「具体的に書け」と言えばそれで済む、ということではないわけです。
石橋を叩いても渡らないくらいの備えをせざるを得ない ―最後に、まさに132条の2を巡って実際に税務執行当局と対峙することになる納税者側の対応はどうあるべきか、という点についてお聞かせください。
朝長 「税務調査においてどのような指摘を受けるか分らない」、「税務調査において否認されるかもしれない」というような不安定な状態は、納税者にとっては大きなリスクを抱えた状態であるわけで、特に税務処理の誤りが許されない案件を抱える納税者にとっては大きな問題となります。このため、税務処理の誤りが許されない案件や失敗が許されない案件に関しては、どのように優秀で粘り強い調査官が来ても大丈夫というくらいに、すなわち、石橋を叩いても渡らないというくらいに十分な備えをせざるを得ません。
また、組織再編成や資本等取引に関しては、それらによって移転した資産の売却等の処理が終わるまで、ずっと、それらの組織再編成や資本等取引の処理の適否が問題とされることになる点にも、留意する必要があります。5年の更正期限が過ぎてから、5年前の組織再編成や資本等取引における減額更正を行う必要がなくなり、5年以内の売却等に関する原価過大等の増額更正のみが行い得るようになって、更正期限を過ぎてから初めて否認リスクが生ずる、ということになるものも珍しくありません。実際、ご相談を頂いたケースの中には、税務調査で「10年前の組織再編成の処理が誤っている」という指摘を受けたものや「7年前の資本等取引の処理が誤っている」という指摘を受けたものもあります。
藤田 もちろん、税務訴訟に対しては万全な対応を図り、納税者に貢献していきたいと考えております。しかし、税務訴訟はあくまでも事後的に問題が生じてしまった場合の話です。それよりも、事前に、つまり取引を実行する前に計画する段階でご相談いただけると、将来の課税リスクを低くすることができます。
税務訴訟で勝った負けたという事実は派手に報道されますが、事前に相談を受けて、そもそも問題にならなかった取引、あるいは調査段階で税務当局に問題なしと納得してもらえた事案は、報道されることもなく、粛々と成功を収めているだけのことです。
仲谷 実は、私ども税金の案件を専門に扱う弁護士の腕の見せ所は、このような事前のプラニングであり、実際に私どもの仕事のうち相当の比重を占めています。
また、事後に問題が生じた場合も、税務調査への対応からご相談いただいた方がうまくいくと思います。特に組織再編成、金融取引や国際取引などの専門的な分野では、初期の段階から我々のような弁護士が関与すると、十分に税務署と議論することができ、実際に、処分なしという結果になったこともしばしばです。
朝長 これまでご相談を受けたものを思い起こしてみますと、法令の解釈能力の不足のために、ポイントを的確に把握することが出来ていないものがたくさんありました。
税に関する争いは相手のある話ですので、相手をよく知らなければ良い結果を得ることはできないわけですが、そもそも、法制度における争いにおいては、相手以上の法令解釈を示すことができなければ、勝てないわけです。いくら威勢よくウケのよい話をしてみても、中身がなければ、結果は期待できません。
その点、アメリカなどと比べると、我が国の税務に関する争訟は、まだまだレベルアップの余地がある、と感じています。 (了)
朝長英樹 ともなが ひでき
九州大学法学部卒業。税理士。東京国税局・税務署において、主に法人税調査・審理に従事(昭和57年~平成7年)。財務省主税局において、金融取引に係る法人税制改正(平成12年)、組織再編成税制の創設・資本等取引税制の抜本改正(平成13年)、連結納税制度の創設(平成14年)などを主導。税務大学校研究部において、事業体税制等を研究。平成18年7月に税務大学校教授を最後に退官。日本税制研究所 代表理事(平成19年3月~)、参議院客員調査員(平成19年9月~20年2月)、登録政治資金監査人(平成20年9月~)、朝長英樹税理士事務所(平成21年3月~)。
『企業組織再編成に係る税制についての講演録集』(日本租税研究協会)、『日本型連結納税制度の基本的な考え方と法令等の概要』(日本租税研究協会)、『国際的二重課税排除の制度と実務―外国税額控除制度・外国子会社配当等益金不算入制度―』(法令出版、共監・共著)、『会社合併実務必携』(法令出版、共著)、『詳解 グループ法人税制』(法令出版、編著)ほか、著書・論文多数。
藤田耕司 ふじた こうじ
東京大学法学部卒業。米国University of Michigan(LL.M.)卒業。弁護士(日本およびニューヨーク州)・税理士。米国ニューヨークのCravath, Swaine & Moore法律事務所、ドイツ・フランクフルトのBruckhaus Westrick Stegemann(現事務所名Freshfields Bruckhaus Deringer)法律事務所勤務勤務を経て、1995年、アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー就任。日弁連税制委員会委員(2007年)、経済産業省国際課税研究会委員(2009年)。ビジネス・タックス―企業税制の理論と実務―(共著・有斐閣 2005年10月)、適格合併の判定に際して、合併交付金が配当代り金に当たるか否かの判定基準(JTRI税研 No.123 2005年9月号)、海外事業体の課税上の扱い(「租税法の発展」(有斐閣)2010年12月)(共著)ほか、著書・論文多数。
仲谷栄一郎 なかたに えいいちろう
東京大学法学部卒業。弁護士。英国ロンドンのAllen & Overy法律事務所勤務を経て、2002年、アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー就任。2007-08年、早稲田大学法学部非常勤講師(担当科目:国際租税法)。『租税条約と国内税法の交錯』(第36回日本公認会計士協会学術賞受賞 共著・商事法務)、『外国企業との取引と税務』(共著・商事法務)ほか、著書・論文多数。
組織再編成税制の立案担当者 × トップ法律事務所タックスロイヤー
組織再編成税制を巡る否認が相次ぐ中、今明かされる「行為計算否認規定(法人税法132条の2)の創設の経緯・目的と解釈」

大きな反響を呼んだ本座談会も、今回が最終回となる。第3回目となる今回は、繰越欠損金の活用を狙いとする組織再編成の問題や、法人税法132条の2に関する税務訴訟の意義、同条の適用の課題のほか、同条の適用を巡り税務執行当局と対峙することになる企業の対応などについて語ってもらった。
追徴課税負担の取り決めと「第三者間取引」
藤田 この裁判(編注:前号24ページで取り上げた組織再編成に関する税務訴訟)でも問題になっていると聞いていますが、追徴課税負担の取決め(編注:組織再編成の当事者が組織再編成に関して追徴課税を受けた場合、その組織再編成の他方当事者やその他の関連者が追徴税額相当額に対応する追加の支払い義務を負うもの)を組織再編成の契約に盛り込むことは問題なのでしょうか。税務当局はそれを問題視しているようですが。
朝長 確かに、組織再編成における当事者のいずれかが税金を減らすメリットを享受するということであれば、そのような契約は何ら不自然ではないという主張もあり得ると思います。
しかし、法人税制においては、取引の妥当性は、お互いに利害関係のない者同士で取引を行うときのその取引―「第三者間取引」や「独立当事者間取引」と言ってもよいのかもしれません―が自然で妥当性のある取引であるという考え方に立っていることに留意する必要があります。
追徴課税負担の取決めの問題に関しても、支配関係も特別な利害関係もない上場会社同士が組織再編成を行う場合にそのような取引をするのか、ということを考えてみればよいわけで、「そのような取引はしない」ということであれば、現にそのような取引をしたケースには「そのような取引をする特別な理由がある」ということになります。

―「そのような取引」とは、例えばどのような取引でしょうか。
朝長 例えば、税金の減少のメリットを本来の享受者でない者が享受したり、そのスキーム取引やセット取引を提案した者が享受したりするケースです。そのようなケースにおいては、現実に税務否認が行われて追徴課税を受ける場合には、税金の減少のメリットを受けることになっていた者や、そのスキーム取引やセット取引の提案者も追徴税額を負担する、ということでなければおかしいわけです。
仲谷 税金減少のメリットを当事者間で分け合い、それを経済的に調整―精算―するというのは不自然でしょうか。
藤田 誰が税務メリットを受けるのかによって変わってくるでしょうね。不自然な税額減少メリットの分配を意図したような取引でない場合であれば、追徴税額負担条項が入っているというだけで、取引が不自然だという結論になるわけではありません。グループ外の組織再編成を行う場合には、合理的な企業であれば、当然その組織再編成による税務効果を考慮に入れて相手方との条件交渉をしますので、想定した税務効果と異なる結果になった場合に備えた条項を入れること自体は、必ずしも不自然とは思いません。しかし、朝長先生がご指摘のように、税制上税務メリットを受けることが想定されていない当事者やスキームのアレンジャーが税務メリットの相当の部分を持っていくような取引は、「不自然」な取引ではないかという疑いを呼ぶ理由にはなり得るでしょうね。
朝長 自分の税金は自分で負担し自分の税金の減少のメリットは自分が享受するというのが通常の姿であるわけですが、他人の税金を自分が負担したり他人の税金の減少のメリットを自分が享受するという通常ではない取引を行うということになれば、通常ではない契約をせざるを得ない、ということになるものと考えられます。
先般、話題になりましたパチンコ業の租税回避においては、スキームの提案者が税金の減少額の一定割合を報酬としてもらい、「スキームが否認された場合にはそのスキームの提案者がもらった報酬の半分を返す」という内容の契約が交わされていたようです。
繰越欠損金の取引は組織再編成の本体取引そのものではない
仲谷 欠損金の繰越額を有する会社で、事業を行っていないに等しいものを買い取って、その欠損金の繰越額を使って税金を減らすという“節税策”があると思います。これについては、もちろん個別の否認規定(法人税法57条の2)がありますが、それが適用されないのであれば、欠損会社を買収した会社は、欠損金の利用というメリットをフルに受けられるとも考えられますが。
朝長 欠損金の繰越額がある会社の買取りに際しては、その税の減少効果額が取引金額を左右することがあります。そのようなケースでは、その税の減少効果額の一定額が取引金額とされるわけですが、その金額はケースによってかなり異なると言われています。
欠損金の繰越額を有する会社の価値をどのように考えるべきかということに関して、参考となるものがあります。日本公認会計士協会の会計制度委員会研究報告第11号「継続企業の前提が成立していない会社等における資産及び負債の評価について」(平成17年4月12日)では、被合併会社の資産及び負債の評価と繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、次のように述べています。
| 合併前の会社である被合併会社の資産及び負債は、合併後の合併会社における事業活動ではなく、合併を前提としない被合併会社単独の事業活動の実施を仮定して評価せざるを得ないことになると考えられる。このことは、被合併会社が計上する繰延税金資産についていえば、その回収可能性は、合併を前提として判断してはならないことを意味することとなる。 |
朝長 そうです。これは会計上の考え方を示したものではありますが、被合併法人の事業価値や株価を適正に捉えるという観点からしても、妥当性があると考えられるところです。
藤田 このような観点から被合併法人の資産及び負債の価値を評価するということになると、被合併法人から承継する事業からの利益では被合併法人が有していた繰越欠損金やその他の繰延税金資産をとても回収する見込みがないというような場合であれば、合併の結果として被合併法人の欠損金の繰越額によって合併法人の固有の所得が相殺されて納税額が減少するというその減少額については、被合併法人ではなく、合併法人が得るべきもの、ということになりますね。
朝長 はい。仮に、その減少額に相当する金銭等が被合併法人の株主に交付されるということになると、合併による被合併法人の資産及び負債の移転の取引とは別に、欠損金の繰越額の取引が行われた、と見ることもできます。被合併法人に欠損金の繰越額が無かった場合にどのような取引となるのかということを考えてみると分りやすいのですが、税務執行当局も、当然、そのように見るのではないかと思われます。
藤田 そのように整理して捉えると、収益力が乏しくて繰延税金資産の回収可能性に疑問があるような被合併法人による組織再編成において、組織再編成に関連して合併法人に対して追徴課税が行われた場合に、「被合併法人の株主はその追徴課税の額に相当する金額を返還する」という内容の契約を締結したとしたら、その取引は実質的には欠損金による節税効果の取引であった可能性があることが分るということですね。
朝長 そうですね。追徴税額相当額の返還契約取引の部分だけを見るのではなく、通常は合併法人が享受することとなる税の減少のメリットを被合併法人の株主が享受するという取引と追徴税額相当額の返還契約取引の全体を見て、「通常」であるのか「自然」であるのかといった議論をする必要があるわけです。
外国税額控除事件の判決文(編注:大阪高裁判決(平成14年6月14日))においては、「外国税額控除の余裕枠を他人に利用させ、その対価を得ること自体を正当な事業目的ということはできない」と述べられていたと記憶しています。例えば、繰越欠損金を有する法人の株主がその株式を譲渡する場合、その法人が自社で使い切れる分の繰越欠損金によって減少することとなる税額は株式の譲渡対価に反映されるはずですが、それを超える税額の減少額、つまり、使い切れない繰越欠損金によって減少することとなる税額が譲渡対価に反映されることはないはずです。仮に、その株主が、その株式を譲渡して、その法人が使い切れない繰越欠損金によって減少することとなる税額を反映した金額までも譲渡対価として得るとすれば、その部分に関しては「正当な事業目的」とは言えない目的の取引―税金を減少させる「権利」の取引―が行われているということにならざるを得ないでしょうし、これを「通常」とか「自然」「合理的」とか言うことはできない、ということになる可能性が高いのではないでしょうか。
パートⅣ 企業に求められる対応
132条の2を巡る税務訴訟の意義 ―長時間に及ぶこの座談会も、そろそろまとめに入りたいと思います。近年、132条の2を巡る税務否認事例が出始め、そのうちの一部は、大型訴訟へと発展しています。こうした税務訴訟の意義やあり方についてお考えをお聞かせください。
朝長 仲谷先生の方から、この法人税法132条の2を巡る争いは過去の税務訴訟の中でもとりわけ大きな影響を与えるものになるのではないかというお話がありましたが(編注:第2回26ページ参照)、私もそのように感じております。組織再編成において問題となる金額は非常に大きい場合があり、また、先ほども触れたように(編注:第2回26ページ参照)、法人の7割以上が赤字という状態が長く続く我が国においては繰越欠損金が期限切れになりそうな法人が非常にたくさんあるわけで、現在訴訟中の案件ほど大きな影響を与えることとなる税務訴訟は、今後、当分の間は出てこないのではないかとさえ思っています。
仲谷 どのような事実がどの要件に該当するから……というように、検証可能な理由で結論を出していただきたいと思います。そのためには、今日、お話に出てきたような132条の2を巡る解釈論が必須です。
朝長 ただ、税金を減らそうとして度を過ぎた“節税”を行っている一部のケースは別として、組織再編成を行うに当たって節税を考えながらやるということは、別におかしなことではありませんので、そのような大多数の真っ当な組織再編成が行い難くなるというようなことでは困るわけです。
藤田 それはおっしゃるとおりですね。真っ当なものは認められなければなりません。
仮装隠ぺいよりも租税回避を問題にする時代に ―132条の2による否認事例は今後も増加することが予想されますが、否認を行う側である税務執行当局についてはどのような感想をお持ちでしょうか。
朝長 現実には、仮装・隠ぺいによって税金を少なくしようという人は僅かで、しかも、数百億円や数十億円という多額の税を減らすために仮装したり隠ぺいしたりするという人はまずほとんどいない、と言ってもよいと思います。大きな金額の節税をしようとする人は、「体」を使うのではなく「頭」を使うわけですから、税務上の問題があるとすれば、それは、仮装・隠ぺいではなく、租税回避ということになります。このため、税務執行当局は、今後ますます「租税回避」に目を向けることにならざるを得ないでしょう。
藤田 最近は、海外で組織再編成を行うという例が急速に増えていますので、今後、国内の組織再編成だけでなく、海外の組織再編成に関して132条の2が適用されるというケースが生じてくることも考えられると思いますが、海外で組織再編成を行った場合の取扱いは、必ずしも明確ではありません。国税当局においては、海外で組織再編成を行った場合の取扱いを公表するという話もあるようですが、そうであれば早めに公表してもらいたいですね。
海外の組織再編成は、我が国の会社法とは関係のないところで行われますので、いわゆる「借用概念」、つまり、会社法や民法における法律用語の解釈に依拠して税法を解釈するという手法は、説得力に欠けます。正に、我が国の法人税法が組織再編成をどのようなものと考えているのかということが問われるわけで、そこのところをはっきりさせないと、海外の組織再編成への132条の2の適用の有無も正しく判断できないのではないかと思います。

朝長 おっしゃるとおりです。そのうちに、海外の組織再編成に132条の2が適用されるというケースが発生すると思いますね。外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)、移転価格税制や外国税額控除制度などとの関係が論点になることもあるはずです。
本誌(編注:本誌439号18頁「税務マエストロ」参照)でも書きましたが、「合併」や「分割」などの法人税法で用いている用語は全て法人税法における「合併」であり法人税法における「分割」であるという当たり前のことが十分に理解されていない向きがあるようです。しかし、そのような状況はさておき、税務調査では、132条の2の適用の有無が問題とされる可能性があるわけですから、むしろ国内の組織再編成以上にしっかりとした対応が必要になると思われます。
―132条の2の適用についてはどのような課題があると思われますか?
仲谷 何が良くて何が良くないのかということを、網羅的・具体的に法律に書ければ良いのでしょうが、現実にはそれは無理でしょう。とすると、現在問題になっている事案において、裁判所が整合性と説得力のある判断をしてくれることを望みます。そのためには、代理人となる弁護士が、条文のきちんとした解釈に基づき主張と立証を行わなければなりません。
そういう意味では、我々の責任は重大だと感じております。

朝長 企業活動は昔のように単純ではありませんし、企業を取り巻く環境も非常に複雑かつ多様になっていますので、それに合わせて「良いもの」と「良くないもの」が具体的に示されていく必要があると思いますが、企業が行う行為や計算の全てを予め知るといったことは不可能です。このため、包括的な租税回避防止規定を設けた上で、そこには必ず「不当」というような抽象的な不確定概念を用いざるを得ないという点は、承知しておく必要があります。世の中の租税回避の全てを知悉して具体的に書けるということであれば、それらの防止規定を個々に定めればよいわけであり、そもそも包括的な租税回避防止規定は必要ないわけですが、現実はそうは行きません。このような租税回避防止規定の宿命は、よく承知しておかなければなりません。「具体的に書け」と言えばそれで済む、ということではないわけです。
石橋を叩いても渡らないくらいの備えをせざるを得ない ―最後に、まさに132条の2を巡って実際に税務執行当局と対峙することになる納税者側の対応はどうあるべきか、という点についてお聞かせください。
朝長 「税務調査においてどのような指摘を受けるか分らない」、「税務調査において否認されるかもしれない」というような不安定な状態は、納税者にとっては大きなリスクを抱えた状態であるわけで、特に税務処理の誤りが許されない案件を抱える納税者にとっては大きな問題となります。このため、税務処理の誤りが許されない案件や失敗が許されない案件に関しては、どのように優秀で粘り強い調査官が来ても大丈夫というくらいに、すなわち、石橋を叩いても渡らないというくらいに十分な備えをせざるを得ません。
また、組織再編成や資本等取引に関しては、それらによって移転した資産の売却等の処理が終わるまで、ずっと、それらの組織再編成や資本等取引の処理の適否が問題とされることになる点にも、留意する必要があります。5年の更正期限が過ぎてから、5年前の組織再編成や資本等取引における減額更正を行う必要がなくなり、5年以内の売却等に関する原価過大等の増額更正のみが行い得るようになって、更正期限を過ぎてから初めて否認リスクが生ずる、ということになるものも珍しくありません。実際、ご相談を頂いたケースの中には、税務調査で「10年前の組織再編成の処理が誤っている」という指摘を受けたものや「7年前の資本等取引の処理が誤っている」という指摘を受けたものもあります。
藤田 もちろん、税務訴訟に対しては万全な対応を図り、納税者に貢献していきたいと考えております。しかし、税務訴訟はあくまでも事後的に問題が生じてしまった場合の話です。それよりも、事前に、つまり取引を実行する前に計画する段階でご相談いただけると、将来の課税リスクを低くすることができます。
税務訴訟で勝った負けたという事実は派手に報道されますが、事前に相談を受けて、そもそも問題にならなかった取引、あるいは調査段階で税務当局に問題なしと納得してもらえた事案は、報道されることもなく、粛々と成功を収めているだけのことです。
仲谷 実は、私ども税金の案件を専門に扱う弁護士の腕の見せ所は、このような事前のプラニングであり、実際に私どもの仕事のうち相当の比重を占めています。
また、事後に問題が生じた場合も、税務調査への対応からご相談いただいた方がうまくいくと思います。特に組織再編成、金融取引や国際取引などの専門的な分野では、初期の段階から我々のような弁護士が関与すると、十分に税務署と議論することができ、実際に、処分なしという結果になったこともしばしばです。
朝長 これまでご相談を受けたものを思い起こしてみますと、法令の解釈能力の不足のために、ポイントを的確に把握することが出来ていないものがたくさんありました。
税に関する争いは相手のある話ですので、相手をよく知らなければ良い結果を得ることはできないわけですが、そもそも、法制度における争いにおいては、相手以上の法令解釈を示すことができなければ、勝てないわけです。いくら威勢よくウケのよい話をしてみても、中身がなければ、結果は期待できません。
その点、アメリカなどと比べると、我が国の税務に関する争訟は、まだまだレベルアップの余地がある、と感じています。 (了)
朝長英樹 ともなが ひでき
九州大学法学部卒業。税理士。東京国税局・税務署において、主に法人税調査・審理に従事(昭和57年~平成7年)。財務省主税局において、金融取引に係る法人税制改正(平成12年)、組織再編成税制の創設・資本等取引税制の抜本改正(平成13年)、連結納税制度の創設(平成14年)などを主導。税務大学校研究部において、事業体税制等を研究。平成18年7月に税務大学校教授を最後に退官。日本税制研究所 代表理事(平成19年3月~)、参議院客員調査員(平成19年9月~20年2月)、登録政治資金監査人(平成20年9月~)、朝長英樹税理士事務所(平成21年3月~)。
『企業組織再編成に係る税制についての講演録集』(日本租税研究協会)、『日本型連結納税制度の基本的な考え方と法令等の概要』(日本租税研究協会)、『国際的二重課税排除の制度と実務―外国税額控除制度・外国子会社配当等益金不算入制度―』(法令出版、共監・共著)、『会社合併実務必携』(法令出版、共著)、『詳解 グループ法人税制』(法令出版、編著)ほか、著書・論文多数。
藤田耕司 ふじた こうじ
東京大学法学部卒業。米国University of Michigan(LL.M.)卒業。弁護士(日本およびニューヨーク州)・税理士。米国ニューヨークのCravath, Swaine & Moore法律事務所、ドイツ・フランクフルトのBruckhaus Westrick Stegemann(現事務所名Freshfields Bruckhaus Deringer)法律事務所勤務勤務を経て、1995年、アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー就任。日弁連税制委員会委員(2007年)、経済産業省国際課税研究会委員(2009年)。ビジネス・タックス―企業税制の理論と実務―(共著・有斐閣 2005年10月)、適格合併の判定に際して、合併交付金が配当代り金に当たるか否かの判定基準(JTRI税研 No.123 2005年9月号)、海外事業体の課税上の扱い(「租税法の発展」(有斐閣)2010年12月)(共著)ほか、著書・論文多数。
仲谷栄一郎 なかたに えいいちろう
東京大学法学部卒業。弁護士。英国ロンドンのAllen & Overy法律事務所勤務を経て、2002年、アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー就任。2007-08年、早稲田大学法学部非常勤講師(担当科目:国際租税法)。『租税条約と国内税法の交錯』(第36回日本公認会計士協会学術賞受賞 共著・商事法務)、『外国企業との取引と税務』(共著・商事法務)ほか、著書・論文多数。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.