解説記事2016年10月31日 【ニュース特集】 CFC税制改正の行方(2016年10月31日号・№665)
ニュース特集
ペーパーカンパニーや資本関係ないSPC活用の租税回避スキーム封じ込めも
CFC税制改正の行方
外国子会社合算税制(CFC税制)は“実質”に着目して思い切った組み替えが行われることになりそうだ。
平成29年度税制改正ではCFC税制の大幅改正が実施される見込みとなっているが、“実質”に着目した結果、規制強化となる改正事項もあれば、逆に納税者有利となる改正事項も出てくることになろう。
具体的には、ペーパーカンパニーや資本関係のないSPCを使った租税回避スキームを封じ込める改正が実施される可能性が高い一方、企業から税制改正要望が上がっていた航空機リース事業はついに合算対象から外れることになりそうだ。
外国子会社配当益金不算入制度を利用し、ほぼ無税で資金を還流
現行CFC税制は、租税負担率が20%以上である場合には適用対象外となるが、この点を逆手にとった租税回避行為が横行している。その一つがペーパーカンパニーを使ったスキームだ。
本来、日本企業が海外企業に投資をした結果得たリターンや知的財産の使用権の付与により得た使用料については、日本で法人税を支払う必要がある。しかし、ペーパーカンパニーを介在させることで、日本企業は海外で得た投資リターンや知財の使用料収入の税負担を軽減させつつ、ほぼ無税で(ペーパーカンパニーから)日本企業に資金を還流させることが可能になる。
具体的なスキームは次頁図表1のとおり。ペーパーカンパニーは、法人税率が20%以上(すなわち、CFC税制の対象にならない)で、受取配当等への課税がなく、また知財使用料に対する優遇税制がある国(A国)に設立する。このペーパーカンパニーを通じて、B国にある会社に投資したり、知財の使用権を提供すれば、A国ではその結果得た配当には課税されず、また知財使用料に対する税負担は軽減された上、「外国子会社配当益金不算入制度」を利用すれば、ペーパーカンパニーから日本企業への配当も益金不算入になるという仕組みだ。
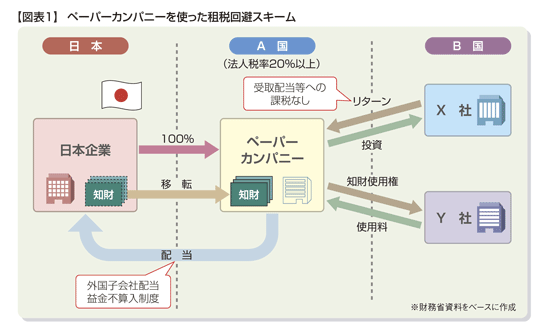
税務当局はこうした租税回避スキームを問題視しており、平成29年度税制改正では、ペーパーカンパニーは、たとえ租税負担率が20%となる場合でも合算対象とするよう、税制改正が行われる可能性が高まっている。
出資持分を保有せずにSPCを実質的支配でCFC税制の適用を回避
もう一つ税務当局が問題視しているのが、資本関係のないSPCを使った租税回避スキームだ。
これは、租税回避地にあるSPCを“実質的に”支配することにより、SPCが投資事業を行って獲得した利益を租税回避地にプールしておくというもの。
次頁図表2のとおり、日本企業はブローカーに依頼し、租税回避地にSPCを設立してもらう。ここでポイントとなるのは、SPCを設立するのはあくまでブローカーであり、日本企業とSPCの間には資本関係がないということだ。
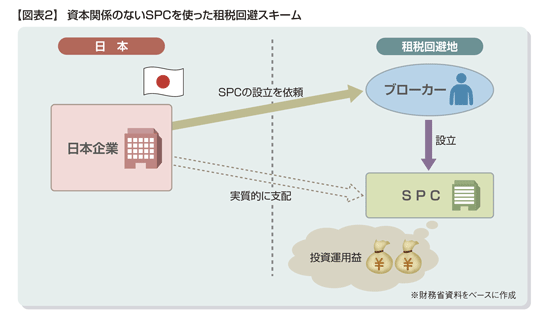
資本関係がない中でSPCを実質的に支配するため、日本企業はSPCの設立を依頼したブローカー(SPCの出資持分を保有)との間で、「SPCの投資事業は日本企業の指示の下でブローカーが管理する」旨の契約を締結する。
こうして、日本企業はSPCが獲得した利益を実質的に享受しつつも、両者の間には資本関係がないことから、当該利益はCFC税制の適用対象外となる。
平成29年度税制改正では、こうした租税回避スキームを封じ込めるため、資本関係がないSPC等も合算対象とするよう、税制改正が行われる可能性が高い。
航空機リースは合算対象から外れる方向
このようにペーパーカンパニーや資本関係のないSPCを使った租税回避スキームを封じ込める改正が実施される方向となる一方で、企業側の税制改正要望を受け入れる形で見直される可能性が高まっているのが、特定外国子会社等を通じて行われる航空機リース事業の取扱いだ。
大手商社や銀行グループがアイルランドの航空機リース子会社を通じて同事業に乗り出しているのは周知のとおりだが、現行CFC税制上、特定外国子会社等を通じた航空機リース事業は、CFC税制の「適用除外基準」のうち「事業基準」をクリアできない。これは、事業基準では、(タックスヘイブン対策税制の適用対象外となるために)特定外国子会社等の「主たる事業」が“該当してはならない事業”として、「船舶もしくは航空機の貸付け」を挙げているからだ。
ただ、日本企業がアイルランドでの事業展開を選択した背景には、税負担の軽減のみならず、主なリース先である欧米の航空会社にアクセスしやすいことや、航空機リース事業に特化した専門家(弁護士、会計士等)が質・量ともにそろっているといったことがある。
現行CFC税制が航空機リース事業を合算対象としているのは「航空機リースなどの事業は国外で行う経済合理性が希薄」であることが理由とされるが、実際、そこでは実体のある航空機リース業が行われている。
こうした中、企業側は航空機リース事業を合算課税の対象から除外するよう平成27年度税制改正議論の時から税制改正を求めて来たが(本誌561号8頁参照)、平成29年度税制改正では、航空機リース事業を合算課税の対象とするか否かは“実質”により判断する方向で法改正が行われる可能性が高まっている。
この改正が実現すれば、大手商社や銀行グループによる航空機リース事業の展開に拍車がかかることになりそうだ。
ペーパーカンパニーや資本関係ないSPC活用の租税回避スキーム封じ込めも
CFC税制改正の行方
外国子会社合算税制(CFC税制)は“実質”に着目して思い切った組み替えが行われることになりそうだ。
平成29年度税制改正ではCFC税制の大幅改正が実施される見込みとなっているが、“実質”に着目した結果、規制強化となる改正事項もあれば、逆に納税者有利となる改正事項も出てくることになろう。
具体的には、ペーパーカンパニーや資本関係のないSPCを使った租税回避スキームを封じ込める改正が実施される可能性が高い一方、企業から税制改正要望が上がっていた航空機リース事業はついに合算対象から外れることになりそうだ。
外国子会社配当益金不算入制度を利用し、ほぼ無税で資金を還流
現行CFC税制は、租税負担率が20%以上である場合には適用対象外となるが、この点を逆手にとった租税回避行為が横行している。その一つがペーパーカンパニーを使ったスキームだ。
本来、日本企業が海外企業に投資をした結果得たリターンや知的財産の使用権の付与により得た使用料については、日本で法人税を支払う必要がある。しかし、ペーパーカンパニーを介在させることで、日本企業は海外で得た投資リターンや知財の使用料収入の税負担を軽減させつつ、ほぼ無税で(ペーパーカンパニーから)日本企業に資金を還流させることが可能になる。
具体的なスキームは次頁図表1のとおり。ペーパーカンパニーは、法人税率が20%以上(すなわち、CFC税制の対象にならない)で、受取配当等への課税がなく、また知財使用料に対する優遇税制がある国(A国)に設立する。このペーパーカンパニーを通じて、B国にある会社に投資したり、知財の使用権を提供すれば、A国ではその結果得た配当には課税されず、また知財使用料に対する税負担は軽減された上、「外国子会社配当益金不算入制度」を利用すれば、ペーパーカンパニーから日本企業への配当も益金不算入になるという仕組みだ。
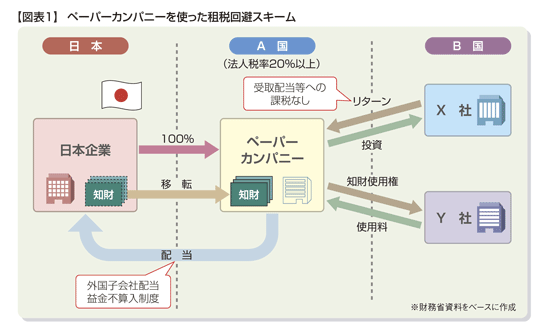
税務当局はこうした租税回避スキームを問題視しており、平成29年度税制改正では、ペーパーカンパニーは、たとえ租税負担率が20%となる場合でも合算対象とするよう、税制改正が行われる可能性が高まっている。
出資持分を保有せずにSPCを実質的支配でCFC税制の適用を回避
もう一つ税務当局が問題視しているのが、資本関係のないSPCを使った租税回避スキームだ。
これは、租税回避地にあるSPCを“実質的に”支配することにより、SPCが投資事業を行って獲得した利益を租税回避地にプールしておくというもの。
次頁図表2のとおり、日本企業はブローカーに依頼し、租税回避地にSPCを設立してもらう。ここでポイントとなるのは、SPCを設立するのはあくまでブローカーであり、日本企業とSPCの間には資本関係がないということだ。
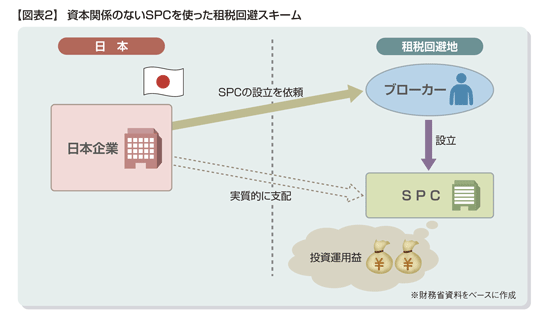
資本関係がない中でSPCを実質的に支配するため、日本企業はSPCの設立を依頼したブローカー(SPCの出資持分を保有)との間で、「SPCの投資事業は日本企業の指示の下でブローカーが管理する」旨の契約を締結する。
こうして、日本企業はSPCが獲得した利益を実質的に享受しつつも、両者の間には資本関係がないことから、当該利益はCFC税制の適用対象外となる。
平成29年度税制改正では、こうした租税回避スキームを封じ込めるため、資本関係がないSPC等も合算対象とするよう、税制改正が行われる可能性が高い。
航空機リースは合算対象から外れる方向
このようにペーパーカンパニーや資本関係のないSPCを使った租税回避スキームを封じ込める改正が実施される方向となる一方で、企業側の税制改正要望を受け入れる形で見直される可能性が高まっているのが、特定外国子会社等を通じて行われる航空機リース事業の取扱いだ。
大手商社や銀行グループがアイルランドの航空機リース子会社を通じて同事業に乗り出しているのは周知のとおりだが、現行CFC税制上、特定外国子会社等を通じた航空機リース事業は、CFC税制の「適用除外基準」のうち「事業基準」をクリアできない。これは、事業基準では、(タックスヘイブン対策税制の適用対象外となるために)特定外国子会社等の「主たる事業」が“該当してはならない事業”として、「船舶もしくは航空機の貸付け」を挙げているからだ。
ただ、日本企業がアイルランドでの事業展開を選択した背景には、税負担の軽減のみならず、主なリース先である欧米の航空会社にアクセスしやすいことや、航空機リース事業に特化した専門家(弁護士、会計士等)が質・量ともにそろっているといったことがある。
現行CFC税制が航空機リース事業を合算対象としているのは「航空機リースなどの事業は国外で行う経済合理性が希薄」であることが理由とされるが、実際、そこでは実体のある航空機リース業が行われている。
こうした中、企業側は航空機リース事業を合算課税の対象から除外するよう平成27年度税制改正議論の時から税制改正を求めて来たが(本誌561号8頁参照)、平成29年度税制改正では、航空機リース事業を合算課税の対象とするか否かは“実質”により判断する方向で法改正が行われる可能性が高まっている。
この改正が実現すれば、大手商社や銀行グループによる航空機リース事業の展開に拍車がかかることになりそうだ。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
情報がありません
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

















