解説記事2022年05月23日 ニュース特集 裁決事例から読む個人のRSUの税務上の取扱い(2022年5月23日号・№931)
ニュース特集
退職後の経済的利益の所得区分で争い
裁決事例から読む個人のRSUの税務上の取扱い
長期インセンティブプランとして外資系企業を中心に導入されているリストリクテッド・ストック・ユニット(RSU)。退職後に支給を受ける経済的利益が給与所得か退職所得のいずれかに該当するかが争われた裁決で国税不服審判所は、経済的利益は在職中に付与されたユニットが付与された時の規定書に定められた条件を満たしたことによって得たものであるため、退職所得には該当せず給与所得であるとの判断を示している。退職という事実によって初めて給付がなされたものではないとの判断だ。リストリクテッド・ストック・ユニットについては、平成29年度税制改正により、事前確定届出給与として損金算入の対象となっており、今後、導入する企業が増える可能性もある。今一度税務上の取扱いを確認しておくべきといえよう。
会社都合により退職、その後のRSUによる経済的利益は?
リストリクテッド・ストック・ユニット(以下「RSU」)とは、事前にユニットとしての権利を付与し、その後、一定の勤務条件を満たした場合に株式を付与するタイプの報酬のこと。業績条件や株価条件はない。今回紹介する裁決事例は、請求人の勤務先であるX社の親会社である外国法人からRSUを付与されたことによる所得区分及び収入の計上時期が争われたものである。
X社では、従業員等を対象に、「成功に対する貢献」などを基礎としてRSUを付与する制度を実施。RSUは、X社の親会社の普通株式1株に等しい価値を持つ譲渡制限付株式ユニットであり、RSUを付与された従業員等は、RSUが所定の時期に権利確定した際に、RSUの数に等しいX社の親会社の普通株式を取得することができる制度であった。
RSUは、従業員の雇用が継続している場合、RSUの付与日の1年後から1年ごとに4分の1ずつ権利確定するものであるため、通常、給与所得に該当するものと想定されるが、本件では請求人がX社を退職したことが争いの原因となっている。
請求人は、勤務先の親会社である外国法人から長期インセンティブプランによって在職中に付与されたRSUに係る経済的利益について、RSUは請求人の退職に際して勤務先の代表者と請求人との間で、在職中に付与されたRSUを没収することなく退職金の一部として付与することを口頭で合意したものであり、退職所得であると主張した(表1参照)。
【表1】当事者の主な主張
(争点1)本件経済的利益は、給与所得又は退職所得のいずれに該当するか
| 原処分庁 | 請求人 |
| 本件RSUは、付与から一定期間後に、従業員とその従業員が勤務する会社との雇用関係が継続している場合に権利が確定し、また、付されていた譲渡制限も解除されるものであるから、経済的利益はX社との雇用契約に基づいて給付された労務の対価と認められる。したがって、本件経済的利益は、給与所得に該当する。 | 本件RSUは、規定上、自己都合による退職をする場合には没収されることとされているところ、請求人は、自己都合による退職を申し出た際、当時の代表者との間で、未確定RSUについて、没収されることなく退職金の一部として付与を受ける旨を口頭で合意した。そうすると、未確定RSUは、退職時の上記合意によって没収されることなく初めて付与されたものといえるから、本件経済的利益は、退職所得に該当する。 |
(争点2)本件経済的利益の収入すべき時期はいつか
| 原処分庁 | 請求人 |
| 本件RSUは、定められた権利確定日に一定の要件を満たすことによって、その権利が確定し、譲渡制限が解除されるものであるから、RSUに基づく経済的利益は、権利確定日に要件の充足を前提としてその権利が確定し、併せて、譲渡制限が解除されることによって初めて現実化するものといえる。本件未確定RSUは、それぞれ所定の権利確定日に権利が確定し、これと同日に譲渡制限が解除されたものであるから、経済的利益の収入すべき時期は、各権利確定年月日となる。 | 本件RSUについては、雇用関係が維持されていること等を前提とする譲渡制限期間が設けられているが、請求人が自己都合による退職を申し出て退職し、これに伴って退職後の未確定RSUを規定どおり供与するとされたことにより、雇用関係の終了を原因として未確定RSUを没収される可能性がなくなったことから、その時点で、未確定RSUの供与を受ける権利が確定した。したがって、経済的利益の収入すべき時期は、未確定RSUの供与を受ける権利が確定した時(退職日)となる。 |
なお、RSUを付与された従業員は、表2に掲げたAからCの条件に基づきRSUに関する制限が失効する時まで、RSUについて売却、移転、譲渡、抵当に入れるといったことができないとされる譲渡制限が付されている。
税制改正による損金算入実現で日本でもRSUを導入する動き
平成29年度税制改正では、役員給与税制が大きく見直されている。これまではインセンティブ報酬の中で、報酬類型によって損金算入の可否が異なっていたが、類型の違いによらず、一定の要件を満たすことで損金算入が可能になっている。事前に届出をした上で事後に株式を交付する事後交付型リストリクテッド・ストックである「リストリクテッド・ストック・ユニット」についても、事前確定届出給与として損金算入の対象となっている。導入企業は多くないものの、税制改正を受け、メルカリ、野村ホールディングス、ソフトバンクグループなどといった上場企業がリストリクテッド・ストック・ユニットを導入している。
【表2】RSUの譲渡制限解除等の条件
| A 従業員の雇用が継続している場合、RSUの付与日の1年後から1年ごとにRSUの4分の1ずつ権利確定し、同時に譲渡制限が解除される。 B RSUの権利確定及び譲渡制限が解除される前に雇用が終了した場合、一定の場合を除き、RSUは没収される。 C 上記Bにかかわらず、雇用終了の理由が、会社側が特別退職金等を支払う場合の退職に該当するとき、RSUは上記Aに基づき引き続き権利確定し、譲渡制限が解除される。ただし、RSU規定書に記載された要件を遵守しない場合は、RSUは没収される。 |
退職後もRSUは没収されず
審判所は、ある金員が所得税法30条1項にいう「退職所得、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与」に当たるというためには、①退職すなわち勤務関係の終了という事実によって初めて給付されること、②従来の継続的な勤務に対する報奨ないしその間の労務の対価の一部の後払いの性質を有すること、③一時金として支払われることの3つの要件を備えることが必要であり、また、同項にいう「これらの性質を有する給与」に当たるというためには、形式的には①から③の各要件の全てを備えていなくても、実質的にみてこれらの要件の要求するところに適合し、課税上、「退職により一時に受ける給与」と同一に取り扱うことを相当とするものであることを必要とすると解すべきであるとした。
その上で審判所は、請求人は、RSUは(表2の)Aの条件を満たして権利確定する前にX社を退職しているが、①RSUはBの条件にかかわらず、請求人の退職によっても没収されていない、②請求人がX社を退職した際に作成された雇用保険被保険者資格喪失確認通知書には資格喪失原因が会社都合による離職である旨が記載されており、実際に退職の際に特別退職金の支給を受けていることからすれば、条件Cの「会社側が特別退職金等を支払う場合の退職」に該当すると認められると指摘。請求人が退職したにもかかわらず未確定のRSUが没収されなかった原因は条件A及びCを満たしたことであり、請求人の退職という事実によって初めて給付されたものではなく、また、一時金として支払われたものでもないとし、審判所は、本件経済的利益は退職所得には該当せず、給与所得に該当するとの判断を示した。
付与日から1年経過ごとの権利確定日に計上
また、審判所は、未確定RSUは各条件を満たすことにより、請求人の退職にかかわらず、各付与日から1年を経過するごとに、それぞれ4分の1ずつ権利確定し、同時に譲渡制限が解除され、普通株式の形で決済されるのであるから(図参照)、RSUから生じる経済的利益の収入計上時期はRSU規定書に定められた権利確定年月日になるとした。
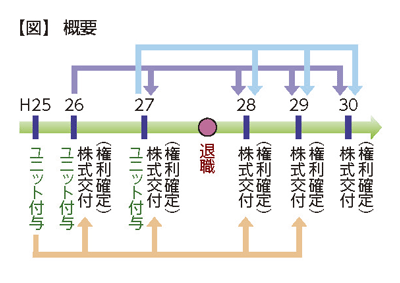
請求人は、経済的利益の収入計上時期を未確定RSUの供与を受ける権利が確定した退職日であると主張するが、審判所は、未確定RSUは退職後も没収されなくなっただけであって、この時点で権利が確定していないことは明らかであるとして請求人の主張を斥けた。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























