解説記事2020年01月27日 実務解説 雑損控除と災害減免法による所得税額の軽減免除(2020年1月27日号・№820)
実務解説
雑損控除と災害減免法による所得税額の軽減免除
税理士 柴原 一
今回のテーマ
近年は地震や風災、水災等による被害があとをたたない。令和元年においても台風19号は広範囲にわたり甚大な被害をもたらした。このような状況に鑑み、災害等によって住宅や家財等に損害を受けた場合の税実務、①雑損控除と②災害減免法による所得税額の軽減免除についてまとめてみた。
雑損控除
1.雑損控除の概要(所法72)
① 雑損控除とは、災害、盗難、横領により、住宅や家財、生活に通常必要な資産(棚卸資産や事業用の固定資産等、生活に通常必要でない資産を除く。)に損害を受けた場合に、一定の金額を所得金額から控除する制度である。本人以外に生計を一にする配偶者や親族などが所有している資産に生じた損失についても、雑損控除を適用することができる。損害の発生原因は限定されており、詐欺や恐喝による損失は対象とならない。
② 雑損控除は他の所得控除に先だって控除することになっている。
③ 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、「雑損失の繰越控除」として、翌年以後3年間にわたり、各年の所得金額から差し引くことができる。雑損失の繰越控除は、その雑損失を生じた年分の所得税につき、確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り適用することができる。(所法71①②)
2.雑損控除の対象になる適用対象者(資産所有者)および対象資産(所法72①、62①、70③)
| 適用対象者 (資産所有者) |
①本人 又は ②同一生計の親族で総所得金額等38万円(令和2年分以降は48万円)以下の者 |
| 対象資産 | 「棚卸資産」もしくは「事業用固定資産」または「生活に通常必要でない資産(注)」 のいずれにも該当しない資産であること |
(注)「生活に通常必要でない資産」とは、趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する別荘などの不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)も含まれる。)や貴金属(製品)、書画、骨董などで1個又は1組の価額が30万円超のものをいう。
3.損害の原因(所法72、2①二十七、所令9)
次のいずれかの場合に限られる。
(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられない。
| 損害の原因 | 災害、盗難、横領 |
4.雑損控除の金額(所法72)
次の二つのうちいずれか多い方の金額。
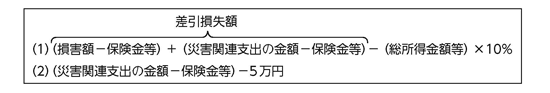
(注1)災害により被害を受けた住宅や家財、車両の損害額の計算が困難な場合には、下記5.「損失額の合理的な計算方法」によることができる。
(注2)「損失額の合理的な計算方法」により求めた損害額と原状回復費用(修繕費)とのいずれか大きい金額をもって損害額とする。
(注3)「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し、または除去するために支出した金額などである。
※災害関連支出には、原状回復費用から住宅や家財の損失額を控除した金額も含まれる。
<例1>
・時価(損害額) 450万円
・原状回復費用 40万円
・土砂等除却費用 110万円
・総所得金額等 700万円
(雑損控除額)
①(450万円*1+110万円)-700万円×10%=490万円
② 110万円-5万円=105万円
③ ①>② ∴490万円
*1 450万円>40万円 ∴450万円
<例2>
・時価(損害額) 450万円
・原状回復費用 500万円
・土砂等除却費用 110万円
・総所得金額等 700万円
(雑損控除額)
①(500万円*2+110万円)-700万円×10%=540万円
②(50万円*3+110万円)-5万円=155万円
③ ①>② ∴155万円
*2 450万円<500万円 ∴500万円
*3 500万円-450万円=50万円
5.雑損控除の適用における「損失額の合理的な計算方法」
災害により被害を受けた住宅や家財、車両の損失額は、その損失の生じた時の直前におけるその資産の価額を基として計算する。
しかし、①住宅の主要構造部に損壊がある場合で、かつ、②損害を受けた資産について個々に損失額を計算することが困難な場合には、次の方法により計算することができる。
(1)住宅に対する損失額の計算
① 住宅の取得価額が明らかな場合
損失額=(住宅の取得価額-減価の額)×被害割合(※3)
(注)保険金、共済金及び損害賠償金などで補てんされる金額がある場合には、上記算式の金額からその補てんされる金額を差し引いた後の金額(マイナスの場合はゼロ)が差引損失額の基となる。ただし、被災者生活再建支援法に基づくものは差し引く必要はない(以下同じ)。
② 住宅の取得価額が明らかでない場合
損失額=〔(1㎡当たりの工事費用(※1)×総床面積)-減価の額〕×被害割合(※3)
(2)家財に対する損失額の計算(生活に通常必要な動産で、車両を除く。)
① 家財の取得価額が明らかな場合
損失額=(家財の取得価額-減価の額)×被害割合(※3)
② 家財の取得価額が明らかでない場合
損失額=家族構成別家庭用財産評価額(※2)×被害割合(※3)
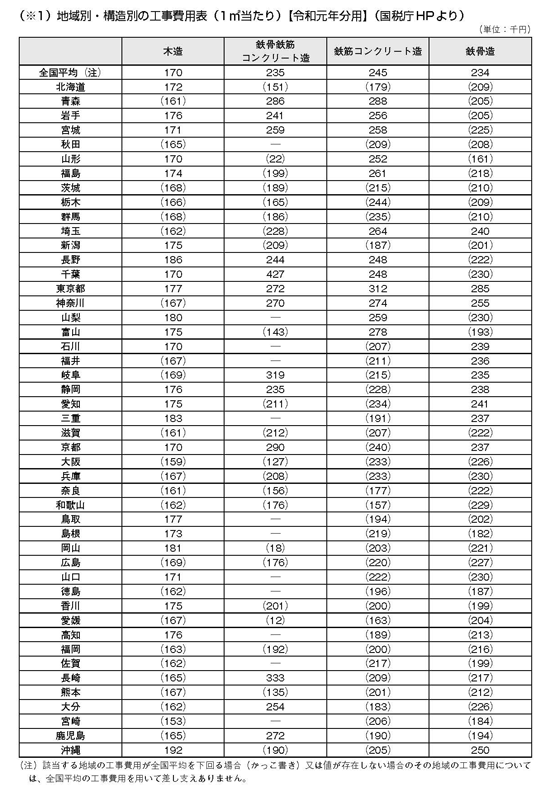
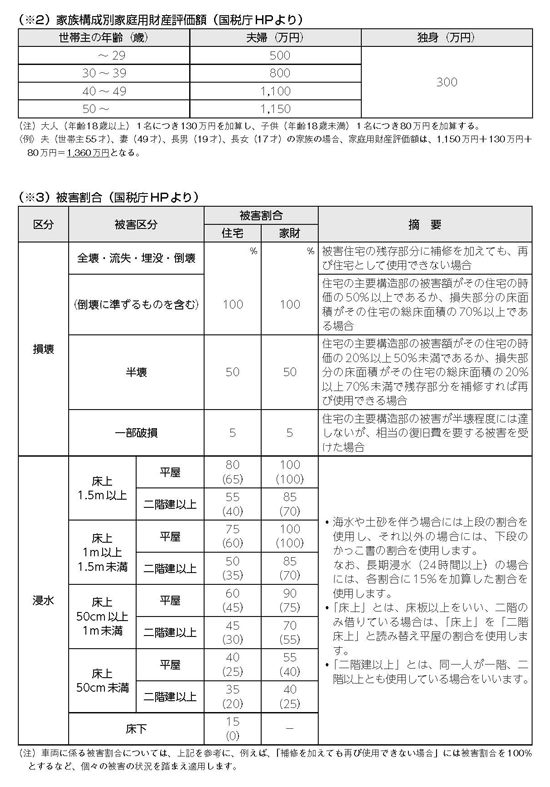
(3)車両に対する損失額の計算
損失額=(車両の取得価額-減価の額)×被害割合(※3)
(注)車両については、生活に通常必要な資産と認められる場合に、雑損控除の対象となる。
なお、生活に通常必要であるかどうかについては、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が、専ら通勤に使用しているなど、車両の保有目的、使用状況等を総合勘案して判断することになる。
6.確定申告のための手続き(所令262①一)
確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害関連支出の領収書の他、災害の場合は(被害割合判定の目安とするため)市役所等の罹災証明書(下記7.参照)、盗難の場合は警察署が発行する被害額届出の証明書などを添付して提出する必要がある。
7.罹災証明書
市区町村は、災害により被災した住民からの申請があったときは、「被害の程度」を証明するものとして罹災証明書を発行する。罹災証明書は、税、保険料、公共料金、義援金等様々な被災者支援を受ける際に必要となるものである。
罹災証明書に記載される「被害の程度」と雑損控除の計算上使用する「被害割合」との対応関係はおおむね次のとおりである。
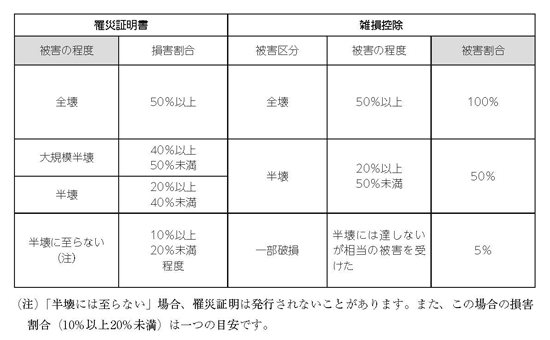
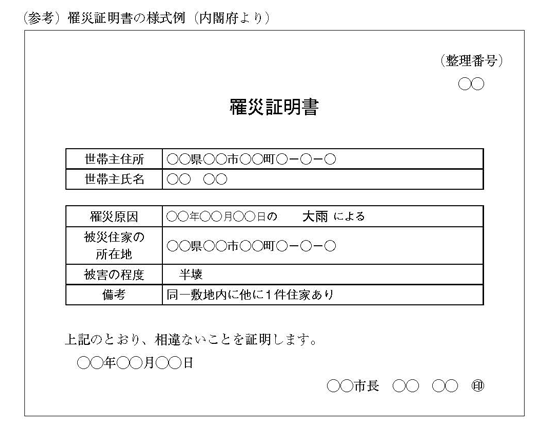
災害減免法
8.災害減免法による所得税額の軽減免除(災法1、2、災令1)
(1)制度の概要
災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除く)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除の適用を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税のうち一定額が軽減されるか又は免除される。本人以外に生計を一にする配偶者や親族などが所有している資産に生じた損失についても災害減免法を適用することができる。
(2)災害減免法の対象になる適用対象者(資産所有者)および対象資産
| 適用対象者 (資産所有者) |
①本人 又は ②同一生計の親族で総所得金額等38万円(令和2年分以降は48万円)以下の者 |
| 対象資産 | 住宅又は家財 |
(注)災害減免法の適用を受けるためには、損害金額(雑損控除における差引損失額と同義)が対象資産の時価の2分の1以上である必要がある。したがって保険金の支払があった場合には、保険金差引後の損失額が時価の2分の1以上であるかどうかで判定することになる。
(3)損失の発生原因
災害による損失に限られる。盗難、横領による損失は災害減免法の対象外である。
| 損害の原因 | 災 害 |
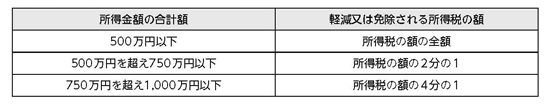
(5)適用を受けるための手続(災令2)
災害減免法の適用を受けるためには、確定申告書等に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載した計算明細書を添付して、納税地の所轄税務署長に確定申告書等を提出する。
(6)雑損控除と災害減免法の比較
災害により、住宅や家財などに被害を受け、一定の要件に該当したときは、①「災害減免法による減免」または②「雑損控除」いずれか有利な方法を選択できる。条件等が異なるため、以下の比較表を参考にされたい。
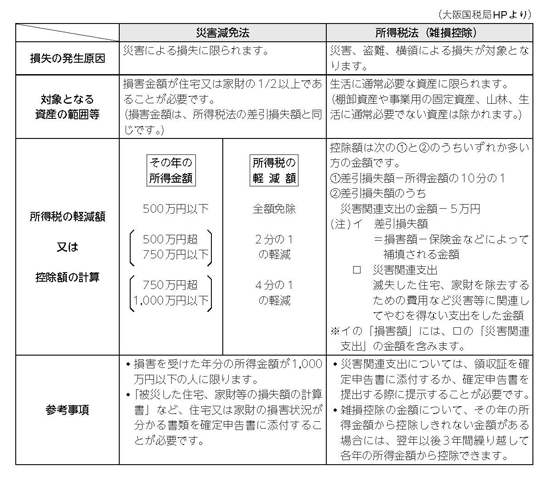
(7)災害を受けた場合の住民税申告等
前述のように一定の要件を充たした場合、所得税では、
① 雑損控除を受けるか
② 災害減免法の規定の適用を受けて所得税の減免を受けるか
のいずれかの有利な方を選択することになる。
一方、翌年度分の住民税には雑損控除の適用はあるが、災害減免法の適用がない。所得税において雑損控除を適用した確定申告書を提出すれば、翌年度分の住民税については自動的に雑損控除が適用される。
しかし、所得税において災害減免法の適用を受けたとしても翌年度分の住民税について自動的には何ら災害に関する特例は適用されない。このような場合は、住民税について別途申告書を提出することにより雑損控除が適用可能であることにも留意されたい。
(注)災害を受けた日の属する年度分の住民税については、市町村条例により、減免を受けられる場合がある。
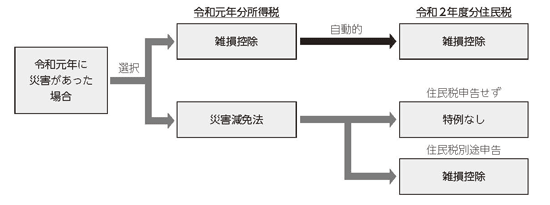
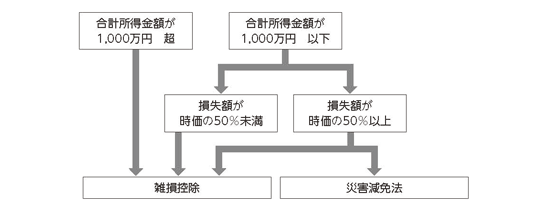
所得税では、所得税法に定める雑損控除又は災害減免法のいずれか有利な方を選択。翌年度分の住民税には災害減免法の規定なし。
所得税で災害減免法の規定を適用し、翌年度分の住民税で雑損控除を適用することもできるが、この場合は所得税の申告書と住民税の申告書の両方を提出する必要がある。
具体例
9.具体例
(設例1)雑損控除額
次の資料に基づき、雑損控除額を計算しなさい。
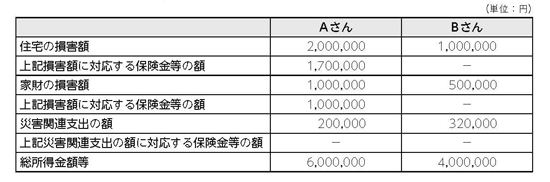
解答(単位:円)
〈Aさんの場合〉
(1)① 差引損失額
(2,000,000-1,700,000)+(1,000,000-1,000,000)+200,000=500,000
② 総所得金額等×10% 6,000,000×10%=600,000
③ ①-② ①-② < 0 ∴0
(2)200,000-50,000=150,000
(3)雑損控除額
(1)③<(2) ∴150,000
〈Bさんの場合〉
(1)① 差引損失額1,000,000+500,000+320,000=1,820,000
② 総所得金額等×10% 4,000,000×10%=400,000
③ ①-② 1,820,000-400,000=1,420,000
(2)320,000-50,000=270,000
(3)雑損控除額
(1)③>(2) ∴1,420,000
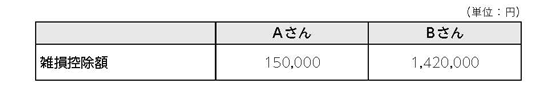
(設例2)災害減免法と雑損控除
次の資料に基づき雑損控除又は災害減免法のどちらか有利な方法を選択して、納付税額を計算しなさい。
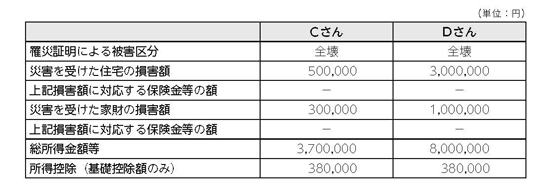
解答(単位:円)
〈Cさんの場合〉
1. 災害減免法
(1)適用判定
① 所得金額 3,700,000≦10,000,000
② 全壊、保険金なし
∴時価の50%以上の損失のため適用有
(2)減免額
① 算出税額(3,700,000-380,000)×20%-427,500=236,500
② 減免額
所得金額(3,700,000)が500万円以下
∴全額免除236,500
(3)納付税額 236,500-236,500=0
2. 雑損控除
(1)雑損控除
① 差引損失額500,000+300,000=800,000
② 総所得金額等×10% 3,700,000×10%=370,000
③ ①-②=430,000
(2)算出税額 {3,700,000-(430,000+380,000)}×10%-97,500=191,500
(3)納付税額 191,500+191,500×2.1%(復興特別所得税)=195,521 ∴195,500
3. 有利判定
Cさんの場合は災害減免法による減免を受ける方が有利
納付税額 0円
〈Dさんの場合〉
1. 災害減免法
(1)適用判定
① 所得金額8,000,000≦10,000,000
② 全壊、保険金なし
∴時価の50%以上の損失のため適用有
(2)減免額
① 算出税額(8,000,000-380,000)×23%-636,000=1,116,600
② 減免額
所得金額(8,000,000)が750万円超
∴25%軽減 279,150(=1,116,600×25%)
(3)納付税額
1,116,600-279,150+(1,116,600-279,150)×2.1%(復興特別所得税)=855,036
∴855,000
2. 雑損控除
(1)雑損控除
① 差引損失額3,000,000+1,000,000=4,000,000
② 総所得金額等×10% 8,000,000×10%=800,000
③ ①-②=3,200,000
(2)算出税額 {8,000,000-(3,200,000+380,000)}×20%-427,500=456,500
(3)納付税額 456,500+456,500×2.1%(復興特別所得税)=466,086 ∴466,000
3. 有利判定
Dさんの場合は、雑損控除の方が有利
納付税額 466,000
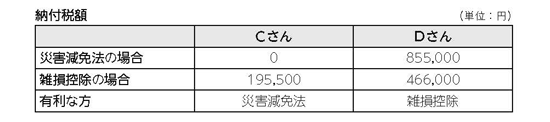
10.雑損控除の記載例
(単位:円)
(1)家族関係 Eさん(昭和34年8月10日生)
Eさんの妻(昭和38年1月15日生)
(注)同居家族はEさんの妻のみ
(2)給与収入 6,000,000 源泉徴収税額 161,000
(3)所得控除 社会保険料 897,900
生命保険料 120,000(旧生命保険料)
Eさんの妻 無職
(4)災害による損失他
① 損害の原因および日付
令和元年9月15日の大雨により罹災(罹災証明による被害の程度:全壊)
② 住宅
住宅の種類・区分 二階建木造
取得年月日 平成6年12月
床面積 89.1㎡
取得価額 不明
※1㎡当たりの工事費用については、全国平均を採用
③ 家財
取得価額 不明
④ 取壊費用(災害関連支出)
1,100,000(令和元年11月11日)
⑤ 損害額に対応する保険金
住宅 6,000,000
家財 4,000,000
※災害関連支出に対する保険金はなし
〈Eさんの場合〉
解答(単位:円)
(1)住宅の損失額
① 取得価額(工事費用×総床面積)
170,000×89.1㎡=15,147,000
② 減価の額
木造22年×1.5=33年 ∴0.031
平成6年12月~令和元年9月 24年10月 ∴25年
15,147,000×0.9×0.031×25年=10,565,032
③ 損害額
(①-②)×100%(被害割合→全壊)=4,581,968
④ 住宅の差引損失額
4,581,968-6,000,000(保険金)=△1,418,032 →0
(2)災害関連支出 1,100,000
(3)家財の損失額
① 家族構成別家財評価額
60才≧50才 夫婦 ∴11,500,000
② 損害額
11,500,000×100%(被害割合→全壊)=11,500,000
③ 家財の差引損失額
11,500,000-4,000,000(保険金)=7,500,000
(4)差引損失額 0+1,100,000+7,500,000=8,600,000
(5)総所得金額等×10%
{6,000,000-(6,000,000×20%+540,000)}×10%=426,000
(6)(4)-(5)=8,174,000
(7)1,100,000(災害関連支出)-50,000=1,050,000
(8)雑損控除額 (6)>(7) ∴8,174,000
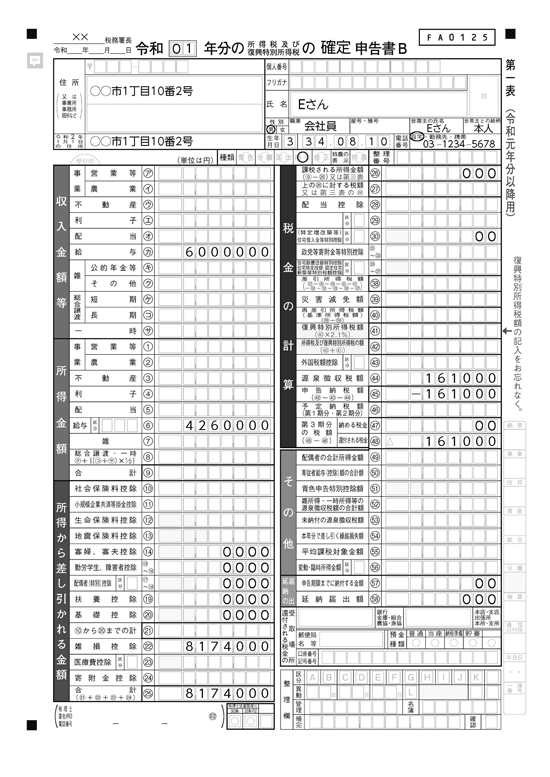
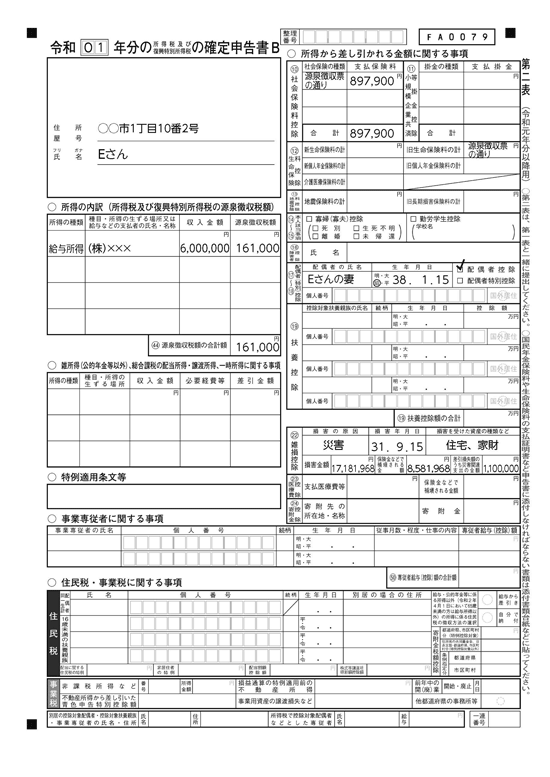
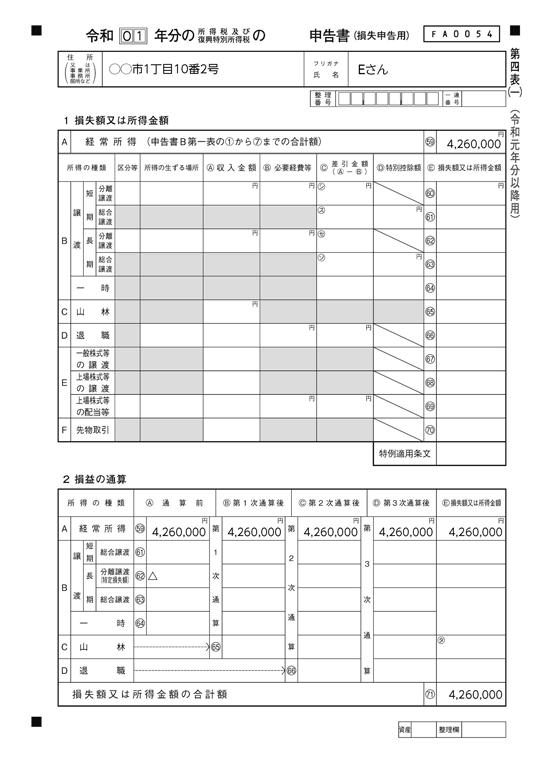
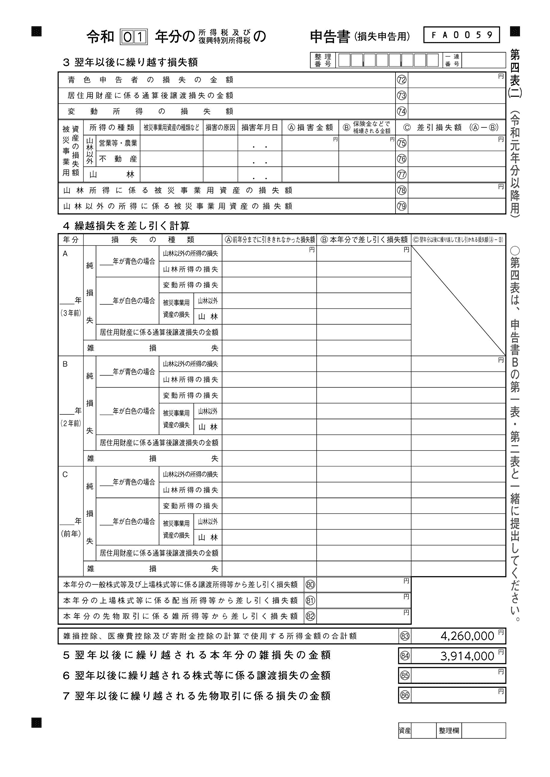
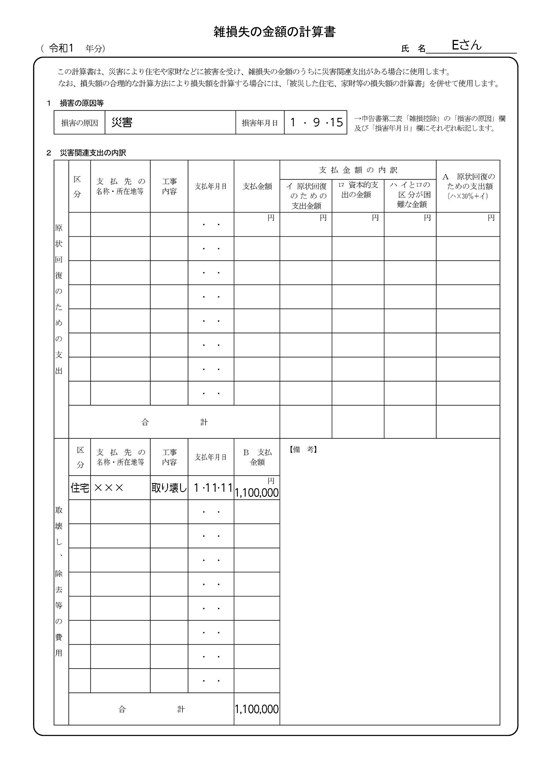
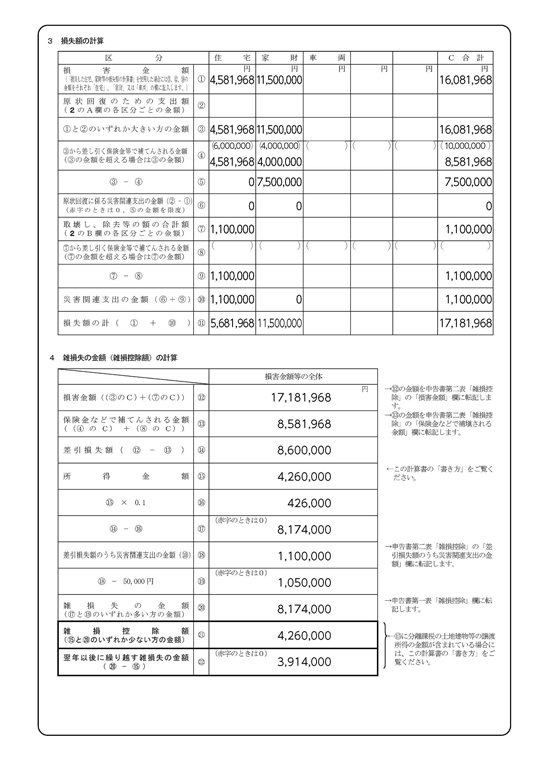
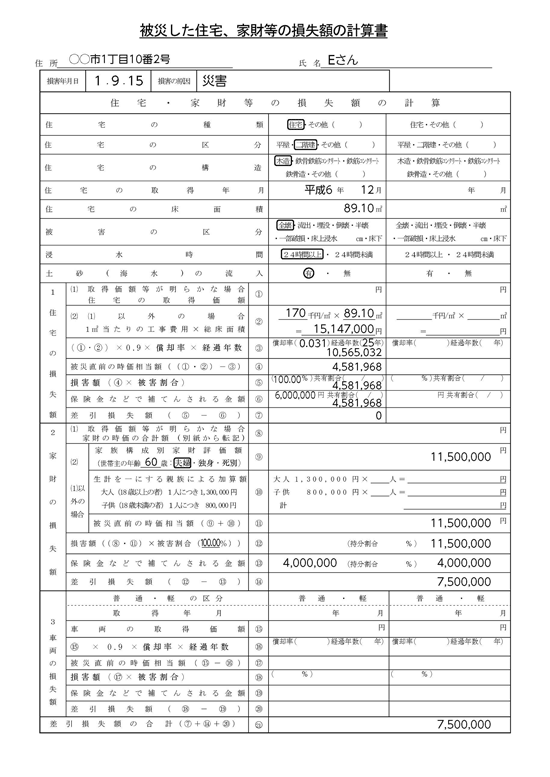
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























