解説記事2023年12月25日 ニュース特集 令和6年度主要法人税制改正の全容(2023年12月25日号・№1008)
ニュース特集
戦略分野国内生産促進税制は税額控除40%、大企業向け賃上げ税制はメリハリ強化
令和6年度主要法人税制改正の全容
令和6年度税制改正における主要な法人税制の改正項目の全容が判明した。
まず、従来の投資減税とは異なるタイプの投資促進税制として注目されるのが、戦略分野国内生産促進税制とイノベーションボックス税制だ。戦略分野国内生産促進税制は、「生産・販売量」に応じて減税を行うもので、事業年度ごとの税額控除の上限は基本的に法人税額の40%(半導体は20%)とかなりの高水準となる。イノベーションボックス税制は、国内で自ら研究開発した知的財産権から生じる一定の所得について、所得控除を行うもの。対象知財は特許権及びAI関連のプログラムの著作権であり、ソフトウェアは対象外となる。また、対象所得は知財の譲渡所得、ライセンス所得とされ、製品組み込み型の知財は対象とならない。所得控除率は30%で、地方法人二税を含む法人実効税率ベースでは約9%の引き下げ効果が生じる。措置期間は異例の7年間となる。
賃上げ税制については、新たに中堅企業(資本金は1億円超だが従業員は2,000人以下である企業)の概念を設け、大企業とは異なる内容の措置を講じることとした上で、賃上げ率要件や控除率が見直されている。大企業向けでは、最大控除率が現行の30%から35%に引き上げられたものの、最大控除率の適用を受けるための賃上げ率も5%から7%に引き上げられている。7%の賃上げは相当に困難である上、賃上げ率3%または4%達成の場合の控除率は引き下げられている。大企業向けの賃上げ税制はかなりメリハリが強化されたと言えよう。さらに、収益が拡大しているにもかかわらず賃上げや国内設備投資に消極的な企業について、研究開発税制等の租特を使わせないとするムチ税制の期限が3年間延長されることとなった点も要注意だ。当初はムチ税制における給与要件を厳格化する案が強く主張されていたが、最終的には給与要件については基本的に手を付けず、設備投資要件の若干の切り上げで対応することとなった。普通の企業であれば抵触することは考えにくいだろう。
本特集では、大綱からのみでは読み切れない本誌独自取材情報を含め、主要法人税制の改正内容をお伝えする。
戦略分野国内生産促進税制
生産段階における「生産・販売量」に着目して税額控除
令和6年度税制改正の目玉の一つと評されているのが、GX・DX・経済安全保障の戦略分野における国内投資を促進するため、「生産・販売量」に応じて減税を行う戦略分野国内生産促進税制の創設だ。これまでの投資減税のように「初期投資額」に対し税額控除等を行うのではなく、「生産段階」において生産量等に着目した税額控除を行うものであり、過去に類例のない税制となる。
戦略分野に該当する物資は、電気自動車等(蓄電池)、グリーンスチール、グリーンケミカル、SAF(持続可能な航空燃料)、半導体とされた。ここでいう「電気自動車等」にはEV(電気自動車)、FCV(燃料(水素)電池自動車)、PHEV(プラグインハイブリッドカー)が該当する。一方、既に補助金で投資促進策を講じている蓄電池に対しては直接的な税制上の措置は講じないこととなった。生産量に応じて電気自動車等を支援することによって、間接的にバリューチェーン上の蓄電池を支援する。
所得要件、賃上げ要件、国内設備投資要件に“全て”抵触なら適用なし
措置期間は産業競争力強化法に基づく事業計画認定時から10年間となる。事業計画認定は令和8年度末までに行うことが求められる。
税額控除額は「物資毎の単位当たりの控除額×販売量」となる。ただし、自ら生産したものに限られることになる。後半年度は米国の税制措置も参考に、控除額が段階的に引き下げられる(8年目:75%、9年目:50%、10年目:25%)。ここでいう8年目等の起算点は、計画認定時ではなく、生産開始時となる。
財源は、GX関連の物資(すなわち半導体以外)については、GX経済移行債から充当する。事業年度ごとの税額控除の上限は基本的に法人税額の40%(半導体は20%)となる。当初の経産省要望の50%と比べれば多少削られたが、それでも高い水準と言える。繰越期間は4年(半導体は3年)となる。
ただし、以下の①~③の要件全てに該当する場合、当該年度については税額控除が適用されないので注意したい(繰越控除は除く)。この点は後述するムチ税制とも若干関連することになる。
①所得金額:前年度比で増加
②継続雇用者給与等支給総額:
対前年度増加率1%未満
③国内設備投資額:
当期の減価償却費の4割以下
イノベーションボックス税制
著作権はAI関連に絞り込み
イノベーションボックス税制とは、研究開発拠点としての立地競争力強化のため、国内で自ら研究開発した知的財産権から生じる一定の所得について所得控除を行うもの。対象知財は特許権及びAI関連のプログラムの著作権であり、令和6年4月1日以降に取得したものに限られる。
当初、著作権で保護されたソフトウェアを広く認めるよう要望する声が企業側から上がっていたが、漫画・アニメ・キャラクターなど個人の創作に基づくものも含まれ得るため不適切との判断から、最終的にはAI関連に絞り込まれた。
知財の取得を令和6年4月1日以降として既存知財を排除したのは、減収額が大きくなることを防ぐため。もっとも、議論の過程では施行日後に取得した知財(令和7年4月1日以降に取得した知財)に限るとの案もあり、この案よりは緩和された形での決着となった。
製品組み込み型の知財は対象外
対象所得は知財の譲渡所得、ライセンス所得となる。電機メーカー等から期待の高かった製品組み込み型の知財については、最後まで調整がもつれたが、議論の時間が足りないことや、執行に難があることなどから、見送られた。
また、税源浸食防止の観点から、海外への譲渡に伴う譲渡所得は対象所得から除かれる。また、関連者(移転価格税制上の関連者をいう)からの所得も除かれる。ライセンスを得る相手が生産・製品販売を行う子会社と仮定すると、事実上、製品組み込み型の知財も対象となり、制度の潜脱となってしまうためだ。
ただし、与党税制改正大綱の「令和6年度税制改正の基本的考え方」には、「イノベーションボックス税制の対象範囲については、制度の執行状況や効果を十分に検証した上で、国際ルールとの整合性、官民の事務負担の検証、立証責任の所在等諸外国との違いや体制面を含めた税務当局の執行可能性等の観点から、財源確保の状況も踏まえ、状況に応じ、見直しを検討する。」との記述があり、今後対象範囲が広がる可能性もある。
所得控除率は30%とされる。法人税率で約7%の引き下げ効果がある(23.2%×0.3=6.96%)。所得控除であるため地方法人二税への影響は遮断されず、法人実効税率ベースでは約9%(30%×0.3=9)の引き下げ効果が生じることになる。措置期間は知財の取得から商業化に至るまでの期間が長いことを踏まえ、異例の7年間とする(令和7年4月1日施行)。
財源に研究開発税制、試験研究費減少なら控除率を段階的に逓減
イノベーションボックス税制の創設を巡る議論の中で大きな課題となったのが財源だ。具体的には、イノベーションボックス税制を創設するのであれば、既存の研究開発税制を削ることが不可避との情勢の中、①海外委託研究費に手をつける案、②モデルチェンジに係る試験研究費を縮減する案、③試験研究費が減少している場合にディスインセンティブを講じる案等が示唆されていた。
しかし、製薬業界や電機業界等からは特に①についてはダメージが大きすぎるとの異論が続出し、結局は③で対応することとなった。具体的には令和8年度、11年度、13年度の3回に分けて、試験研究費が減少している場合に控除率を段階的に逓減させる。第1段階では、増減試験研究費割合がマイナス30%の場合、控除率が現行1%のところゼロ%となる。第2段階では同割合がマイナス27.5%の場合、控除率がゼロとなる。第3段階では、同割合がマイナス25%の場合、控除率がゼロとなる。議論の過程では、「一挙に財源を拠出すべき」との意見もあったが、激変緩和の観点から、徐々に財源を拠出することとなった。概ね税収中立と言えよう。
賃上げ促進税制
女性活躍・子育て支援に積極的な企業には5%控除率を上乗せ
まず、新たに中堅企業(資本金は1億円超だが従業員は2,000人以下である企業)の概念を設け、大企業とは別に税制措置が講じられることとなった。
その上で、本改正後の大企業(資本金1億円超かつ従業員2,000人超)については、賃上げのインセンティブ強化の観点から以下の通り基本部分について賃上げ率要件や控除率の見直しが行われる。
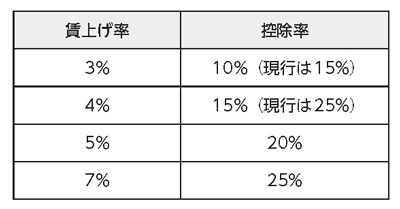
また、教育訓練費が20%以上増加した場合に控除率5%上乗せとの部分は、「10%以上増加した場合」に改め(要件緩和)、引き続き5%の控除率を適用する。なお、1円でも教育訓練費を増加させれば追加の控除率を適用できてしまっている現状を改め、教育訓練費について「当期の給与総額の0.05%以上」との要件を追加する。さらに、女性活躍・子育て支援に積極的な企業については追加的に5%控除率を上乗せする。
中小企業については、賃上げ率の要件(1.5%(控除率15%)、2.5%(控除率30%))および控除率とも現状が維持されるが、赤字の企業にも賃上げを促すため、新たに繰越控除措置を創設する。
当初の議論では、賃上げ率3%及び4%ゾーンの廃止案も
総じてみれば、最大控除率は現行制度では30%「25%(4%の賃上げ率クリア)+5%(教育訓練費要件クリア)=30%」であったところ、改正後は35%「25%(7%の賃上げ率クリア)+5%(教育訓練費要件クリア)+5%(女性活躍等要件クリア)=35%」となり、“拡充”と言えなくもない。
しかし、7%の賃上げは普通に考えれば相当に困難であり、賃上げ率3%または4%達成の場合の控除率は縮減となっている。大企業向け賃上げ税制は、かなりメリハリが強化されたと言えよう。
ただし、当初の議論では、賃上げ率3%及び4%ゾーンの廃止案も出ていたことからすると、企業にとってみれば現実的かつ許容可能な落としどころとも言えよう。
マルチステークホルダー方針に免税事業者との適切な関係構築方針を記載
また、マルチステークホルダー方針の公表を要件とする企業の範囲が拡大される。
具体的には、中堅企業枠の創設も踏まえ、資本金1億円超かつ従業員2,000人超の企業については、「中堅企業ではない=見直し後の大企業」ということで、当該方針の公表がなければ、大企業向けの賃上げ税制は適用できないこととなる。
加えて、インボイス制度の導入を踏まえ、消費税の免税事業者との適切な関係の構築の方針についても記載が行われるよう、マルチステークホルダー方針の記載事項を明確化する。
また、本誌取材によると、マルチステークホルダー方針の公表時期については、現行の事業年度から45日以内との期限が前倒しとなり、事業年度内ということになりそうだ。
ムチ税制
給与要件の水準自体を切り上げる改正は行わず
収益が拡大しているにもかかわらず賃上げや国内設備投資に消極的な企業について、研究開発税制等の租特を使わせないとするムチ税制の期限が3年間、延長される。ムチ税制の発動条件としては、「and条件(すべての要件に抵触した場合に発動)」が維持される。
給与要件については、上乗せ要件(1%の賃上げ。通常では0%)の対象となる企業の範囲が広がる。現行では、「資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上で、前年度が黒字」の企業が上乗せ要件の対象となっているが、今回の改正では、これに加えて、「従業員数2,000人超で、前年度が黒字」の企業についても、新たに上乗せ要件(1%の賃上げ)の対象とする。給与要件の水準自体を切り上げる改正は行われない。
設備投資要件は、大企業(資本金10億円以上かつ常時使用従業員数1,000人以上、または常時使用従業員2,000人超で、前年度が黒字の場合)に対して、上乗せ要件が設けられる。具体的には、当期の減価償却費の「3割以下」との要件が「4割以下」に引き上げられる。
ムチ税制の上乗せ要件を「戦略分野国内生産促進税制」に組み込み
当初の議論では、ムチ税制における給与要件の厳格化を強く主張する意見もあったが、賃上げ促進税制における最低賃上げ率が3%で維持された以上、現行の1%以上賃上げとのムチ税制の要件をあまりにも急激に切り上げると、賃上げ税制との差分がほとんどなくなってしまうため、給与要件については基本的に手を付けず、設備投資要件の若干の切り上げで対応することとなった。普通の企業であれば抵触することのない、まだ余裕のある水準と言えるだろう。
また、適用停止の対象となる租特の追加はないが、戦略分野国内生産促進税制の要件自体に、ムチ税制の上乗せ要件に相当するものが組み込まれることとなった点、留意したい。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























