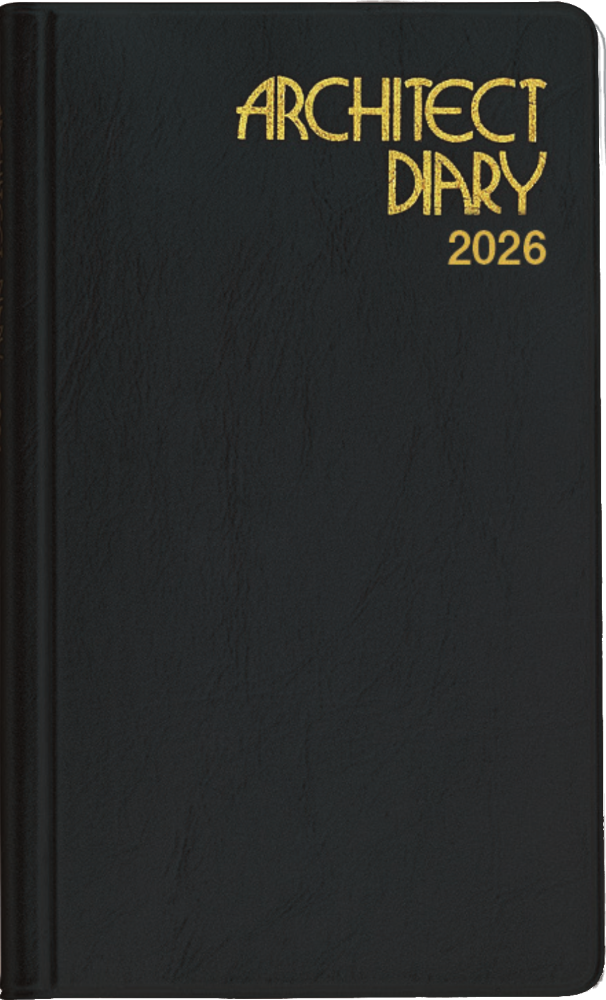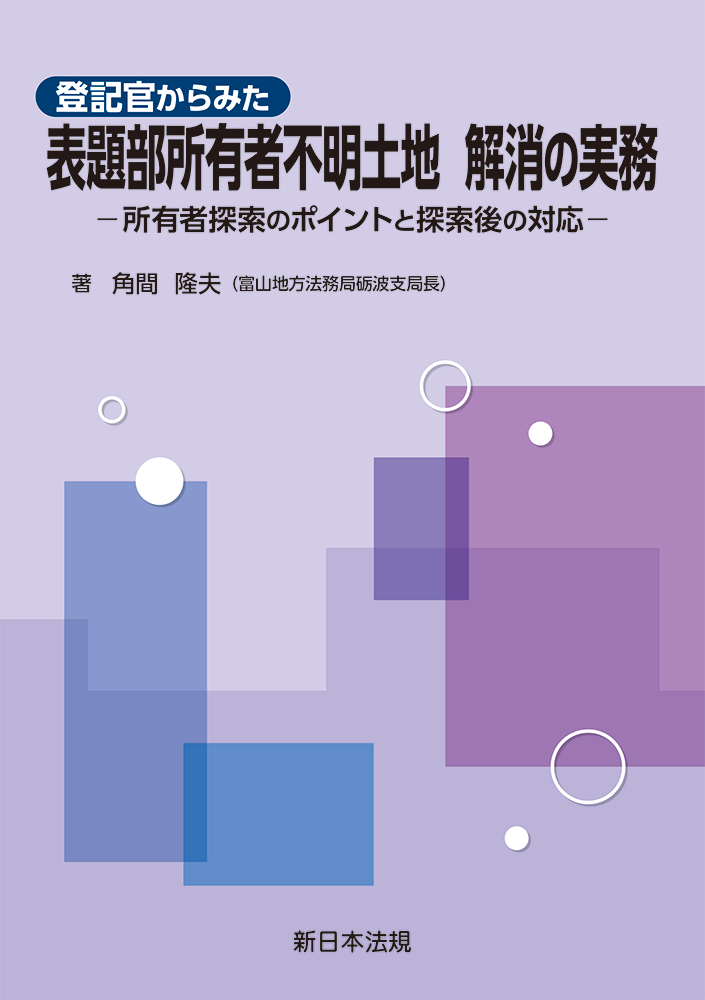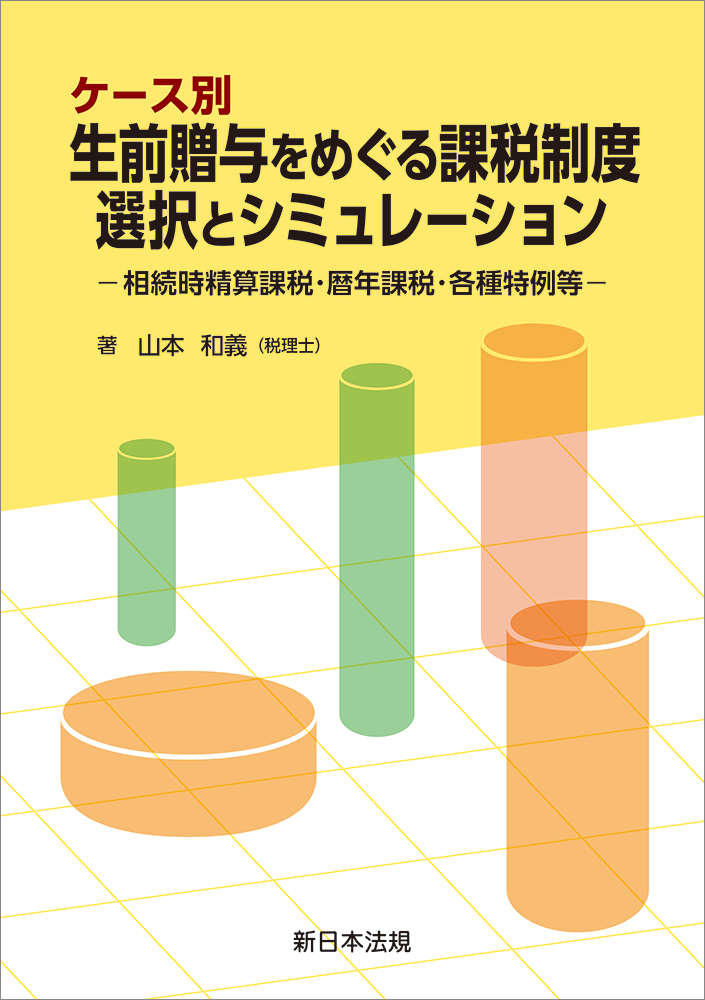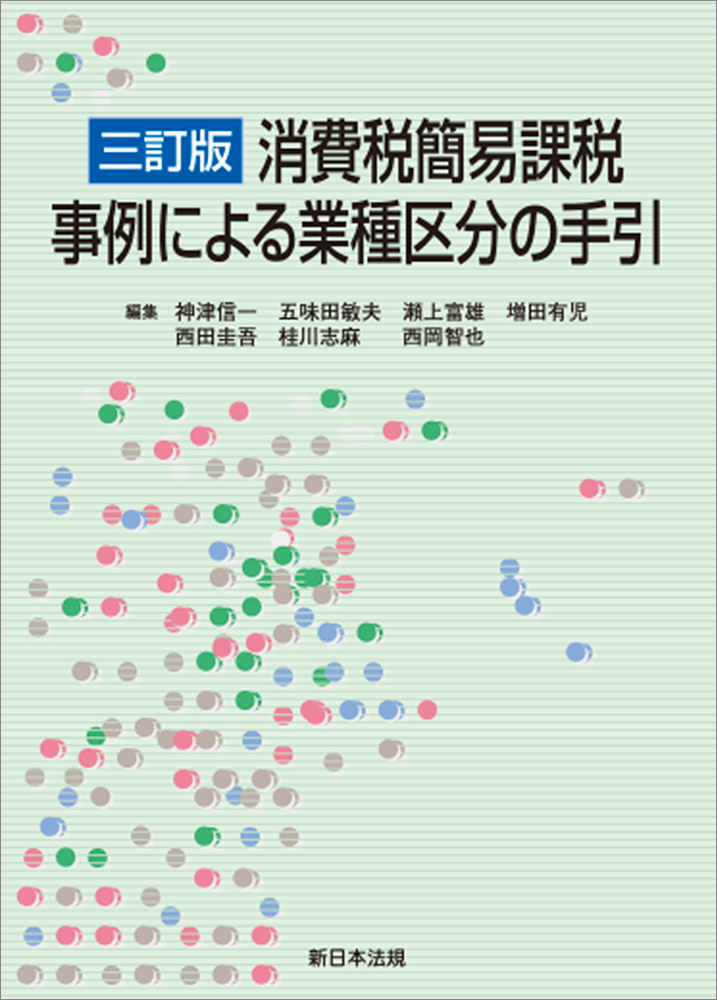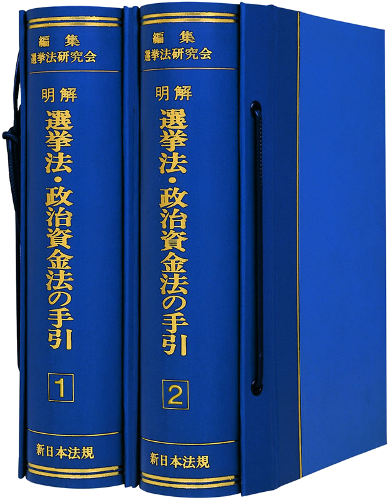民事2025年10月23日 「18歳が立候補したらだめですか?」初めての選挙に絶望した大学生が裁判を起こした理由 若者は本当に「経験不足」なのか、国会では年齢引き下げの動きも 提供:共同通信社

選挙で投票できるのは18歳から。では、選挙に出られるのは何歳から―?公職選挙法は立候補できる年齢について、衆院選と地方議員選などが「25歳以上」、参院選と都道府県知事選は「30歳以上」と定めている。
「同じ有権者なのに年齢で線を引くのはおかしい」。京都市の大学生久保遼さん(22)は、年齢で立候補を制限する公選法の規定は憲法違反だと訴え、仲間5人と東京地裁に裁判を起こした。審理は2年以上にもおよび、社会も自身を取り巻く環境も大きく変化した。「僕らは政治家に話を聞いてもらうだけの存在ではない」。今月24日に言い渡される判決を前に、訴訟の経過と立候補年齢を巡る現状をリポートする。(共同通信=助川尭史)
▽候補者は全員60歳オーバー、消去法で投じた初めての一票
久保さんが初めて一票を投じたのは2021年の衆院選。18歳になったばかりの高校3年生だった。「それまでは自分が抱える将来への不安感や問題意識がないものにされていると感じていた。投票を通して意思を表明することがやっとできる。そんな期待感でいっぱいだった」
だが、選挙区に立候補していたのは2人だけ。どちらも60歳を超え、主張は年金や社会保障など自分には縁遠く感じるテーマばかりだった。関心のあった気候変動や環境問題についてどう取り組むのか知りたいと、両陣営にメールで問い合わせたが返信は無かった。
結局、消去法で票を入れた候補は落選。無力感だけが残った。「自分が持つ問題意識を共有して投票したいと思える同世代の候補者がいたらと思うようになった」
大学進学後は若者の政治参加を支援する団体に所属し、活動を続ける中で法律が年齢で立候補を制限していることを知った。同じ社会に生きる一員のはずなのに、なぜ年齢を理由に政治の担い手になることができないのか。 「誰も明確な答えを教えてくれなかった。それなら裁判を通して対等な立場で国の公式な見解を聞いてみようと思った」。2023年7月、東京地裁に提訴した。
▽「若い世代以外にメリットあるの?」
裁判で国は、立候補の自由は「重要な権利の一つ」との前提の上で、「政治家には一定の知識や経験が必要だ」と説明。複雑で多岐にわたる政治の仕事には、社会経験からくる思慮と分別が必要だとして「年齢は物差しとして客観的要素になる」と制限の正当性を強調した。
「こんなにも曖昧で根拠のない理由で制限しているとは」。久保さんはこうした国側の主張を聞いた時の驚きをそう振り返る。「18歳になれば成人としてさまざまな責任が課されるし、若者にだって知識や社会経験もある。若い候補者が当選したとしても、それは選挙を通して自分の票を託したいと思う人が多かった結果。国は有権者のことをそこまで信用していないのかなって」
裁判を起こしてから、多くの議員と面会し、立候補年齢の引き下げを訴えてきた。だが、返答は「若い世代以外にメリットがあるのか」「世論が追い付いていない」という後ろ向きなものばかりだった。
「僕たちは権利の話をしているのに、なぜか世代間の問題や損得の話にすり替わってしまう」。消極的な声を聞く度に、裁判を通して法に照らして判断してもらう必要があると再確認した。
▽海外では10代の議員が続々誕生、国内でも進む議論
日本では約80年にわたって一度も見直されていない立候補の年齢制限だが、海外では引き下げる動きもある。
フランスは2011年、日本の衆院に相当する議会下院の出馬可能な年齢を23歳以上から18歳以上に引き下げた。韓国も2021年に国会議員などの選挙に出られる年齢を25歳以上から18歳以上とした。その結果、実際に10代や20代前半の政治家が続々と誕生している。
こうした世界的な潮流や、訴訟で正面から立候補年齢の問題が争われたことも踏まえ、日本の政界もようやく重い腰を上げつつある。自民党は3月にプロジェクトチームを設置。当事者の高校生や大学生へのヒアリングを実施するなど、引き下げに向けた検討を始めた。
他党もより具体的に実現に向けた動きを進めている。立憲民主党は6月、衆院議員や地方議会議員の立候補年齢を18歳以上、参院議員と都道府県知事、市町村の首長を23歳以上とする公選法などの改正案を国会に提出。7月の参院選では、日本維新の会や国民民主党などが立候補年齢を18歳以上とする公約を掲げた。
▽「人として大切な当たり前の権利認めて」
久保さんは昨年、18歳から立候補が認められているデンマークに留学。国政選挙の投票率が80%を超え、若者が対等に扱われる社会を肌で感じた。
「10代の政治家が同じテーブルで国の問題を議論する姿を見た時、ものすごいカルチャーショックだった。若者が対等に権利を持って社会とつながっている。そんな社会に生きたいと強く思えた」。自分が求めている方向は間違いない、答え合わせをした気がした。
帰国後、通っていた大学を中退し、10月からはアルバイトをしながら通信制大学の教育課程で学び始めた。「もし18歳から立候補ができるようになったとしても、すぐには変わらないと思うし、ハードルが一個減るだけ。まずは教育の現場から、自分たちも社会の一員だと思える子どもたちを増やして、社会の意識を変えていきたいと思った」
24日の判決では、裁判所が若者の権利について正面から向き合った判断を下すことを願っている。「政治家になる能力を判断するのは法律ではなく有権者。政治の舞台に挑戦することは、人として大切な当たり前の権利だと認めてほしい」
(2025/10/23)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
関連商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -