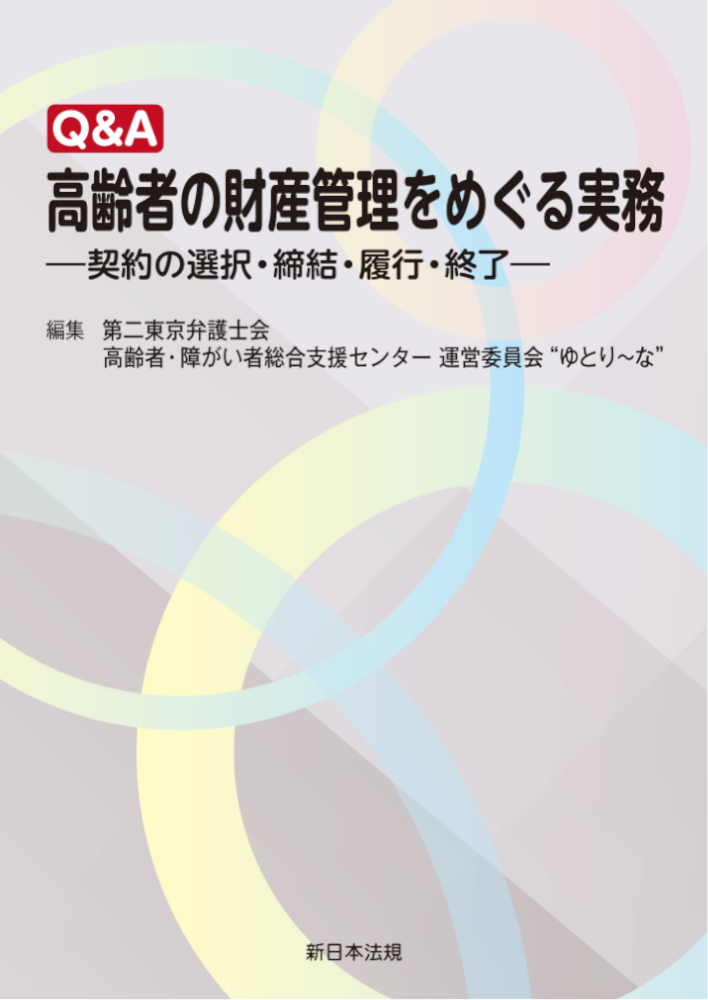民事2025年11月14日 別荘地の管理費問題について 執筆者:石丸文佳

いわゆる別荘地を所有すると、別荘地特有の管理費が発生することが多くあります。別荘地には通常は人が住んでいませんが、人がいないと荒れてしまうため、管理業者が存在することが多いです。
ただ、別荘地を所有するに至る経緯は人によって様々ですし、管理契約も存在したりしなかったりします。そして、一部の所有者しか管理費を支払っていないために管理不全に陥り、管理業者から所有者に対して訴訟を提起されることもまた、しばしば見られます。
令和7年6月30日、この件でひとつの最高裁判例が出ました。結論に戦慄した人も多かったのではないでしょうか。
この判例の概要は、管理契約を結んでいなくても、そこに建物を建てて土地を利用していなくても、管理費を請求できるとしたものでした。契約があってもなくても、業者の管理によって土地の所有者は利益を得ているから、その利得分を請求できるという理屈です。もとより、報酬の定めがなくても報酬を請求できる条文として商法512条がありますし、契約関係が存在しない事務管理であっても、これによって利益を受けていれば費用を請求できるとした民法702条もありますので、不当利得という趣旨に立ち返ればそこまで意外な結論ではないはずですが、当該判例に戦慄した人が多かったのは、この最高裁判例が出るまでは、むしろ契約があって初めて契約に基づく管理費を請求できるという考え方が一般的だったと思われるからです。
実際には、それまでも判例はかなり割れていました。事実、この最高裁令和7年6月30日判決でも一審は管理費の請求を認め、二審が認めず、最高裁にて再度認めたという経緯を辿っています。
一審は、建物がなくとも雨水排水設備、街路灯、消火栓、ごみ集積所の維持管理、道路ゲートの管理、除草等清掃作業、パトロール等は別荘地自体の価値を高めているし、実際固定資産税評価額も管理のあるとなしとでは相当の差が出るから所有者には利得があるという判断でした。
二審は、固定資産税評価額の上昇が管理のあるなしで生じているかは不明である(比較対象となった管理なしの土地は地目が異なっていた)から、所有者に利得が生じているかも不明と言わざるを得ないと判断しました。
そして最高裁は最終的に、固定資産税評価額の上昇云々とは無関係に、管理業務は別荘地の機能や質を確保するために必要なもので、契約を締結していない所有者のみを管理業務による利益の享受から排除することは困難な性質のものであるとして利得を認めました。
しかしそれまでの判例では、そもそも何らかの管理契約が存在することを前提として管理費の請求を認めていたと思われ、そのために管理費の請求がされた場合、まずは管理契約の有無や解除の可否を争っていたのです。というのも、別荘地を取得した初代は大概併せて管理契約を締結しているものですが、その契約は別荘地が別荘地として存続する限り継続することが予定されており、当然に更新されまたは解除できないとされていることが多く、この点が争われることもまた多かったのです。
たとえば、東京地裁平成26年12月18日判決は、管理委託業務は別荘地が存在する限り継続することが予定されており、(民法651条によればいつでも委託者が解除できるはずであっても)所有者からの解除権の行使を制限できるとしました。つまり、あくまで「契約があるから」管理費の請求を認めていたと思われるのです。なお、この事件は控訴されたようですが、控訴審でどう決着したかは不明です。
逆のパターンとして、大阪高裁令和4年9月20日判決は、管理契約中の「所有者が分譲地に土地を所有する間、更新するものとする」という条項を消費者契約法10条違反、つまり消費者(所有者)を一方的に害するもので無効と判断しました。建物を有していない所有者の多くが管理契約を必要としているとは考え難く、管理者側は管理から撤退できるのに所有者側だけができないのは明らかに不均衡で、所有している限り永遠に管理契約に拘束されなければならない理由は見出しがたいと判断したのです。これも上告されているようですが、結論はわかりません。ただ、いずれにせよ、これらは「契約ありきの請求」であったと思われるのです。
勿論、契約がないことが前提となってなお、不当利得を観念することはできますので、偶々これらの判例ではそこまで判断されなかっただけかもしれません。しかし、契約がなくても不当利得によって管理費の請求ができるのであれば、管理の押し売りがまかり通るということになりますし、そもそもこのような契約の有無について争うこと自体、抜本的な解決につながらないということになります。そういう意味ではやはり、今回の最高裁判例は戦慄と言っていい内容でしょう。
一方で、最高裁判例の射程がどこまでなのかという点が今後の課題にもなります。業者の管理によって本当に所有者が恩恵を受けているのかという点が、まずは課題だと思います。たとえば管理によって固定資産税額が上がることは、むしろ相続によって負動産を押し付けられたというようなケースだと却って迷惑でしょう。これは、原野商法で購入させられた不動産があるような場合においても当てはまると思います。更に、建物がないということは、実際には管理されているあらゆる設備を利用することはないということであり、自らそれを承知で不動産価値に惹かれて購入した初代ならともかく、相続の場合でも当てはまるものでしょうか。特に、管理費ばかりかかる別荘地は、資産どころか負債であることも多く、資産価値を高めたから利得があると言い切るには躊躇を覚えます。
また、以前から、管理実態も怪しいような会社がある日突然管理費を請求して所有者に対し提訴してくるという事例は散見されていました。管理実態についても、それが本当に所有者の利得になるような管理が行われているかどうか、きちんと調査の上で反論することが重要になるでしょう。
(2025年10月執筆)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
執筆者

執筆者の記事
執筆者の書籍
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -