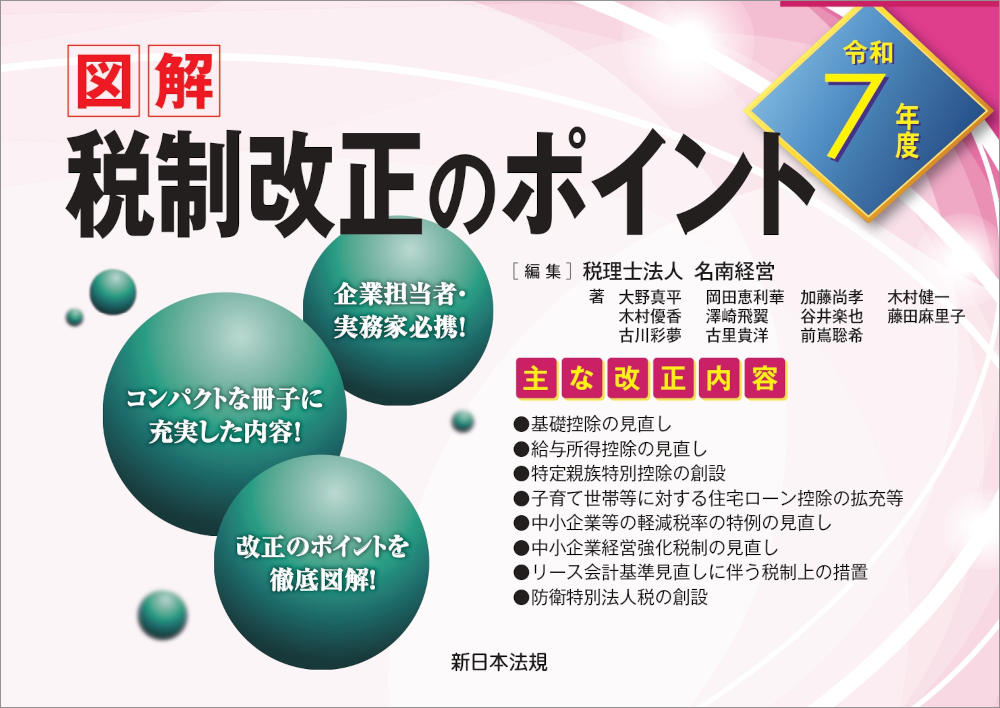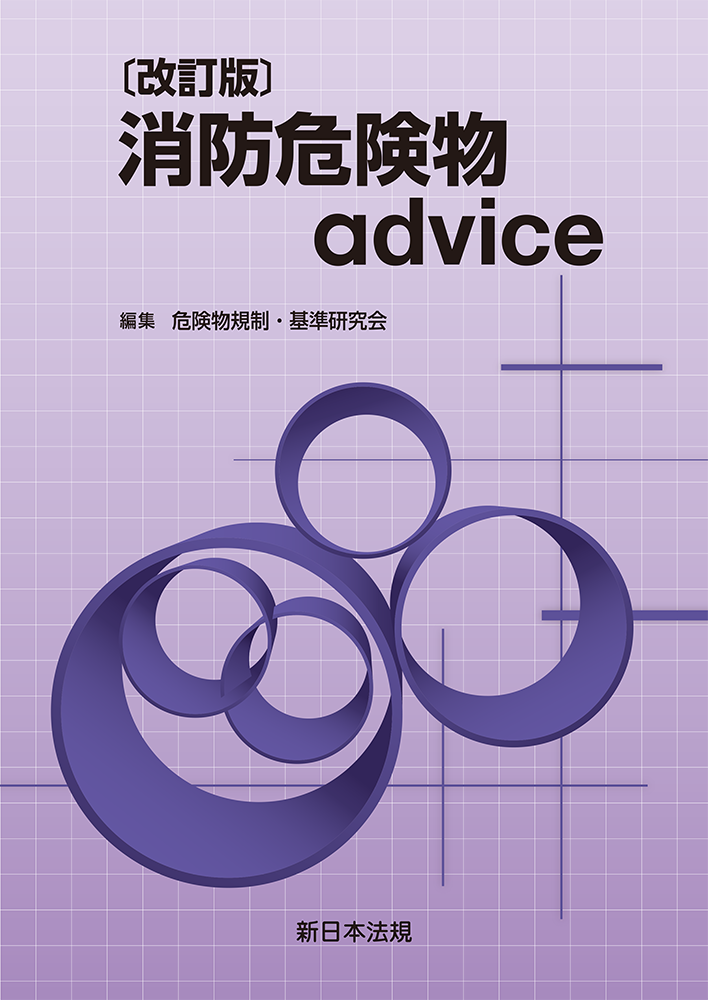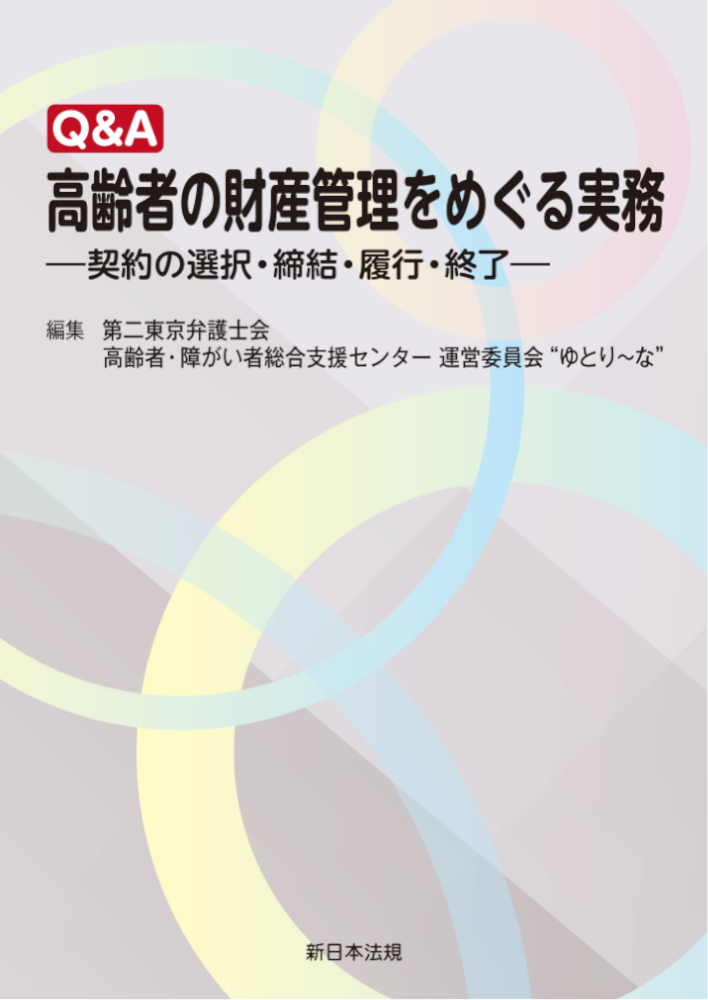一般2023年09月01日 勾留に関する近年の逆風傾向について 執筆者:石丸文佳

先日、令和4年の司法統計が発表されました。今回は、ここから刑事事件における勾留に関する問題を取り上げます。
20年前は、現在よりも勾留請求件数が遥かに多く、一方で勾留却下や勾留決定に対する準抗告認容件数は遥かに少ない時代でした。それが、無罪推定が働く段階での安易な身柄拘束は人権侵害であるという意識が高まり、また法が定める勾留要件(住居不定、逃亡もしくは罪証隠滅・証人威迫を疑うに足りる相当の理由があること)を事案に即して具体的に検討すべきと考えられるようになったことから年々勾留請求件数は減り、同時に被疑者国選対象事件の拡大で勾留直後に弁護人が就く事件が増えたことも相俟って、勾留却下や勾留決定に対する準抗告認容件数は増えてきました。但し、これは20年という長期間を視野に入れ、大まかに判断した傾向です。しかし、令和の時代に入ってから、この傾向が当てはまらなくなってきているようです。
令和4年の司法統計を前年と比較すると、上記の傾向にブレーキがかかっていることがわかります。勾留却下件数、勾留決定に対する準抗告認容件数は、共に前年より減っているのです。ここ20年で勾留却下件数が最多だったのは令和元年の6263件、準抗告認容件数が最多だったのは令和2年の2906件でした。令和4年は、それぞれ4487件、2534件で、最多の年からいずれも年々減少してきています。勿論、そもそも勾留請求された件数が少なければこれらの件数も減少して当然ですし、20年前から勾留請求件数自体は毎年減少しているのですが(勾留請求件数が最多だったのは平成17年です)、それを考慮して勾留却下や準抗告認容件数の割合を出しても、勾留却下率や準抗告認容率はここ数年は減少傾向に転じているのです。
私の弁護士としての肌感覚もこれと一致しており、これは勾留されない、勾留されても準抗告で解放できると思った件が最近立て続けに勾留され、勾留決定に対する準抗告が棄却され、かつ当然のように勾留期間が延長される(そして延長決定に対する準抗告も棄却される)ということが相次いでありました。これは、保釈を認めたら逃亡したという著明な案件が複数件起きたこと等で、裁判所がある程度の身柄の拘束はやむなしという方針に傾いているのではないかという推測ができます。
しかし、身柄の拘束が与える悪影響を、裁判官は軽視し過ぎです。裁判官は、身柄を拘束されている人が勾留中にどれだけ精神的に弱っていくのか、社会的にどれだけ不利益を被って人生を狂わせるのかを直接見る機会がないので理解し辛いのかもしれませんが、今、身柄の拘束が解けるなら、どれだけ後に不利益が生じるとわかっていても被疑者は迎合してしまうのです。否認事件だから、共犯事件だから、逮捕時の罪名が一見重罪だからというだけで身体拘束を是と判断し、事案ごとに異なる具体的な勾留要件をきちんと検討したとは思えないものも多く、嘆かわしいと言わざるを得ません。先に述べたように、勾留には、逃亡や罪証隠滅を疑うに足りるだけの相当な理由が必要なのですが、否認だろうが共犯がいようが逮捕時の罪名が重罪だろうが、到底逃亡や罪証隠滅が考えられない背景を持つ被疑者はいくらでもいます。初犯で実刑になることが想定されておらず、家族のしっかりした監督があり、逃亡すれば家族も身分も職も失って何も残らないというような事案であっても、裁判官は「本件事案の性質及び内容からすれば、弁護人が指摘する事情を踏まえても逃亡すると疑うに足りる事情がある」等と定型文言で身柄の拘束を認めているのが現状です。
一方で、弁護士の準抗告申立件数も令和2年を境に漸減しており、弁護士側にも諦めが見られるように思えます。一般的な感覚で判断すれば勾留の要件を欠くと考えられる事件なら、否認だろうが共犯がいようが罪名が何であろうが、弁護士側も積極的に検事や裁判官に対して勾留しないように、もしくは勾留決定を覆せという働きかけを行う姿勢が大事です。
(2023年8月執筆)
人気記事
人気商品
執筆者

執筆者の記事
執筆者の書籍
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.