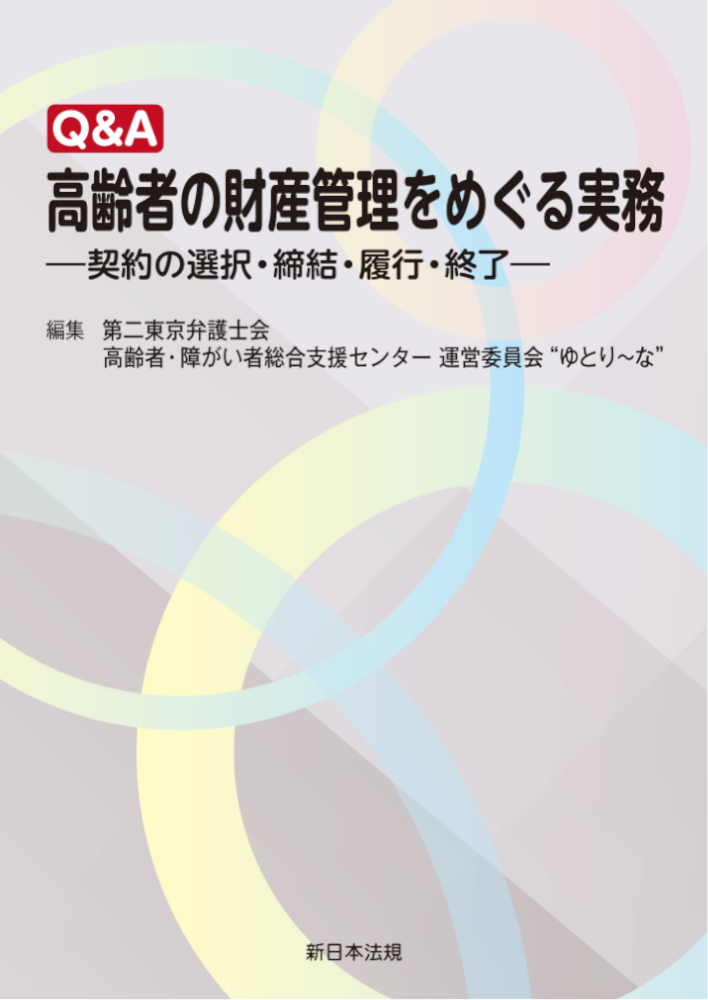訴訟手続2024年11月19日 裁判管轄について思うこと 執筆者:石丸文佳

ここで国際管轄の話までできれば格好いいところですが、私が今からつらつらと書くのはあくまで国内の管轄争いの話です。
土地管轄が複数あるとき、原告は自身に有利な場所を管轄地に選んで提訴できますが、被告はこれに対して移送の申立てを行って管轄を移動させることがあります。
私は以前、長崎県の離島で職務を行っていたこともあり、この頃は管轄争いが一大事でした。自身の管轄地以外で裁判が行われることになると、絶対に船か飛行機に乗らなければ出頭できないので、依頼者の不利益が甚だしかったからです。経済的に苦しい方に、弁護士費用の他に何回分もの飛行機代や宿泊代まで負担させるのは実質的には不可能なので、管轄争いで負ければ現地の弁護士を見つけて共同受任をお願いせざるを得ませんでした(もっとも当時の私は法テラスのスタッフ弁護士だったので、全国各地に仲間がいたのは幸いでした)。
被告側も離島まで来るのは大変だからでしょう、それなりに移送の申立てを起こされていましたが、当時はそれなりの勝率を収めていました。この頃は、基本的に、①原告と被告の立場の差(法人か個人か、経済力の差等)や、②当方管轄で裁判が行われても相手の負担を軽くできる事情の有無、③当方管轄で裁判を行うことのメリット(証人の多くが当方管轄にいる等)で判断が下されていました。一度、これらの条件に当てはめたら移送されてしまうなと思っていたにも拘らず勝利したこともあり、先方の裁判所が自分のところで裁判をしたくなくてこちらの裁判所に事件を押し付けたのかなと思ったこともありましたが、これは例外だったと思ってよいでしょう。
ところが最近、かつてのセオリーはほとんど通じなくなっており、ここのところ移送申立てもしくは移送申立てに対する答弁は連敗中です。例えばですが、
ケース1:千葉と京都の管轄争い。双方法人でしたが、法人の規模に大きな差があり、当方は法人とは名ばかりのほとんど個人、相手は東京にも支店を持つそれなりの規模の法人でした。なお、争いの対象物は千葉でも京都でもなく、管轄争いに影響しなかったケースです。
これは、これまでのセオリー通りであれば千葉に管轄が認められるケースだったと思います。法人としての規模に差がある上、先方は仮に出頭を要請された際、東京支店の社員が裁判に出頭することが可能だった(むしろ当該事件の発端となった勧誘場所は東京であったため、証人になるのであろう社員は京都本店の所属ではなかった可能性も高かった)からです。
ところが、管轄は京都から動きませんでした。理由は、双方に代理人弁護士が就いていたから出頭の不利益の多くはWEBで解消されるというものでした。
ケース2:東京と静岡の管轄争い。双方個人で属性にそれほどの差がなく、どちらの管轄になっても事件の進行にはそれほど差が生じないだろうケースでした。そうであれば、これまでのセオリーでは管轄を移動させなければ著しく訴訟が遅延するというような事情はないと判断されて、移送申立てが却下されてもおかしくない事案だったと思います。
しかし、管轄は静岡に移送されました。理由は、当方は代理人が就いているからWEBで期日をクリアできるが、先方はその時点で弁護士が就いておらず、出廷の不利益が大きいというものでした。
要するに、裁判のIT化によって管轄争いの内容が大きく変わってしまったということです。現状、弁護士が代理人に就いていればWEB期日が可能ですから、「当事者の立場の差」とは法人・個人の差や経済力、出廷のしやすさ如何を問わず、弁護士が就いているかいないかだけがポイントになってしまった感があります。
確かに、WEB期日は慣れれば極めて楽なものです。最近は慣れ過ぎてしまい、事務所で別の仕事をしているうちに気が付いたら期日の時間を過ぎそうになって、慌ててログインすることすらあります。しかし、以前は出廷して裁判官と顔を合わせることで、期日前後の雑談等を通して知れることやそれとなく伝えられるものもありました。WEB期日は電話とは違って一応顔は見えますが、細かい表情までわかるわけではなく、何よりも余談というものがありません。管轄争いはもはや無意味ではないかとすら言われますが、リアルで出廷する余地を残しておくことは、意外と有利に働くことがあるかもしれないと思うのです。
(2024年11月執筆)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
執筆者

執筆者の記事
執筆者の書籍
関連カテゴリから探す
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.