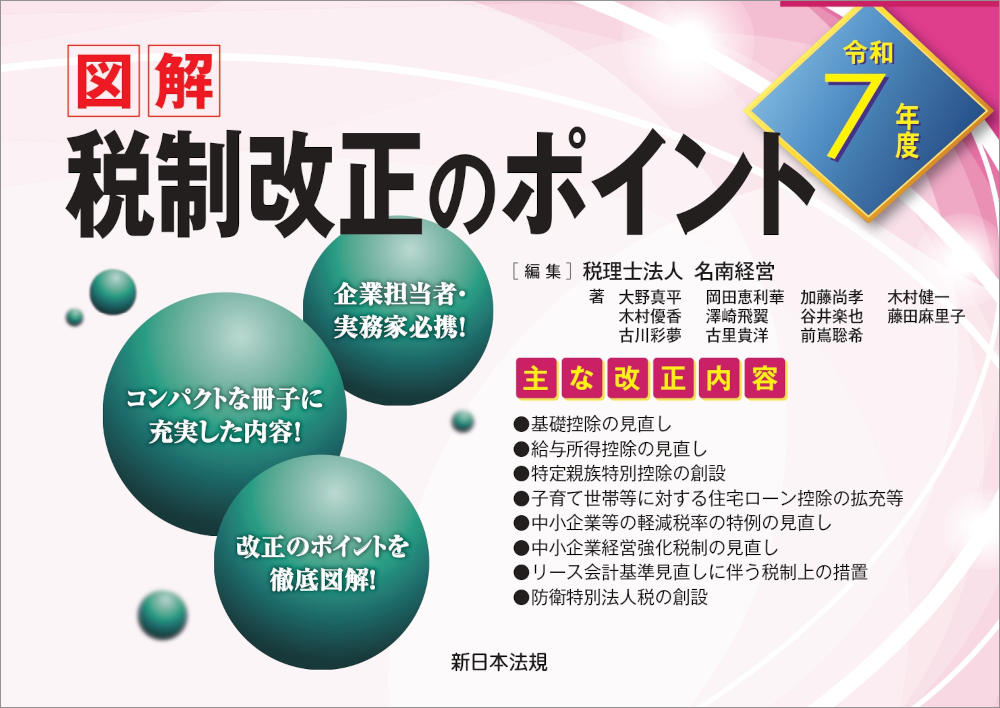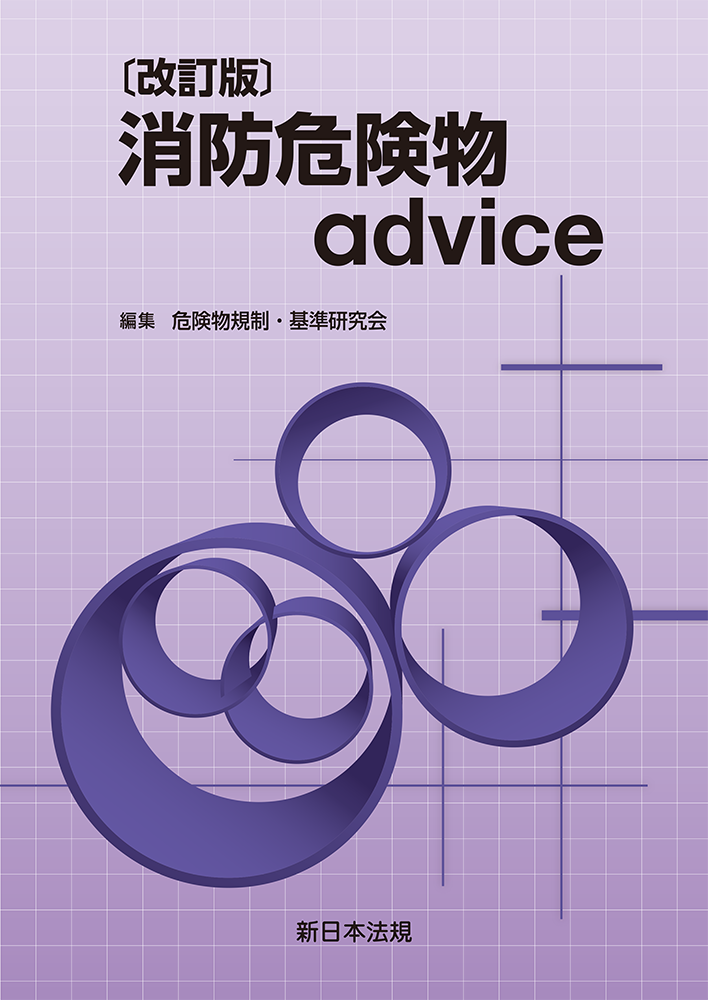解説記事2018年08月13日 【特別解説】 「収益認識に関する会計基準等への対応」として平成30年度に行われた税法・通達改正の検証(3)(2018年8月13日号・№751)
特別解説
「収益認識に関する会計基準等への対応」として平成30年度に行われた税法・通達改正の検証(3)
日本税制研究所 代表理事 税理士 朝長英樹
前回及び前々回は、平成30年度税制改正で改正された法人税法22条4項と新たに創設された22条の2の前提となった22条2項と4項の解釈を確認した。
第3回目となる今回は、平成30年度税制改正後の22条4項と22条の2について、改正の内容を条項ごとに確認しながら、改正の適否や実務対応などについて検証を行う。
Ⅱ 平成30年度税制改正後の法人税法22条4項と22条の2の確認と検証
Ⅱにおいては、まず初めに、平成30年度税制改正後の22条4項の確認と検証を行い、その後に、22条の2の確認と検証を行うこととする。
1 平成30年度税制改正後の法人税法22条4項の確認と検証 平成30年度税制改正後の22条4項は、次のとおりとなっている。
上記の下線部分が平成30年度税制改正において追加された部分である。
上記Ⅰ2(本誌2018.8.6号15頁)において確認したとおり、4項は、2項の「収益の額」及び3項の「原価の額」等の「計算」をする場面において「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」を「尊重」するべきであるという「計算心得を宣言、確認する規定」という性格のものであり、また、2項や3項の「別段の定め」が適用される場面に適用されるものともなっていない。
このため、4項には、2項や3項の「別段の定め」を除く旨の文言を挿入する理由がない。
また、上記Ⅰ2において、「引渡基準」及び「完了基準」と「実現主義」の例、無償による譲渡の例、「債務確定基準(債務確定主義)」の例、賞与引当金などのさまざまな引当金の例を挙げて確認したとおり、4項は、2項と3項において定められたことを変更するものでもない。
このため、2項の取扱いに関して22条の2を設けるとしても、4項に22条の2を除く旨の文言を挿入する必要もない。
このように、平成30年度税制改正において4項に「別段の定めがあるものを除き」という文言を挿入した改正は、誤りと言う他ない(注)。
(注)『平成30年度 税制改正の解説』においては、4項に「別段の定めがあるものを除き」という文言を挿入することによって、同項が収益認識の時期に適用されないようにしたという説明(273頁)や同項と22条の2以下の規定とが抵触しないようにしたという説明(280頁)がなされているが、これらの説明は、上記本文の説明からもうかがわれるとおり、同項の解釈を誤ったものと言わざるを得ない。
これらの詳細に関しては、後にⅢにおいて述べることとする。
しかし、4項に「別段の定めがあるものを除き」という文言を挿入したことによって何か問題が生ずるのかというと、元々、同項が2項や3項の「別段の定め」に適用されず、同項が2項と3項の定めを変更するものでもない中で、「別段の定めがあるものを除き」という文言を挿入するという状態となっているため、いわゆる“空振り”となっているだけで、直接、実務に影響を与えるような問題が生ずることはないはずである。
ただし、4項において、このような改正が行われているということは、法人税法において「所得の金額」の計算に関する規定が企業会計における利益の額の計算を前提として定められていると誤って理解されている可能性が高いということでもあるため、今後、22条2項及び3項並びに23条以下の規定の解釈を行う場合においては、企業会計における利益の額の計算を前提として文言を解釈するという、同じ誤りを起こさないように、十分、注意をすることが必要となる(注)。
(注)これに関しては、法人税法における「所得の金額」の計算が法人税申告書別表4(所得の金額の計算に関する明細書)における「所得金額又は欠損金額」の計算――企業会計上の「当期利益又は当期欠損の額」に必要事項を加減算して「所得金額又は欠損金額」を求めるもの――と同様の構造となっていると勘違いして、22条2項及び3項並びに23条以下の規定を解釈する、ということのないようにしなければならない、と言い換えてもよかろう。
2 法人税法22条の2の確認と検証 平成30年度税制改正によって創設された22条の2は、次のとおりである。
(1)第1項
22条の2第1項は、収益認識の時期の原則を定めるものとされており、資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供(以下、「資産の販売等」という。)に係る「収益の額」について、資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の益金の額に算入するものとされている。
この第1項に関しては、従前の取扱いの「明確化」と説明されている。
このため、基本的には、従前どおりの取扱いとなると考えてよい。
しかし、この第1項に関しては、次のような点に留意する必要がある。
① 第1項は、22条2項と内容が重複しているため、2つの取扱いが異なる場合の判断が難しい 22条の2第1項に定められたことは、既に、22条2項において定められていたことであって、22条の2第1項を定めたことにより、「資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供」に係る「収益の額」の認識時期について、2つの定めが存在するという異例の状態となっている(注)。
(注)Ⅰ1(本誌2018.7.30号5頁)において確認したとおり、22条2項に関しては、収益認識の時期の原則をどのようなものとするのかということが最も重要な論点であった。
そして、これらの規定には、いずれにも「資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供」に係る「収益の額」の認識時期が定められており、しかも、いずれにも「別段の定め」があるものを除く旨の文言が存在することから、文理に即して正しく解釈するとすれば、「資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供」に係る「収益の額」の認識時期の判断には、いずれの規定も適用されない、ということになる。
しかし、そうすると、法人税法に「資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供」に係る「収益の額」の認識時期の原則に関する定めが存在しないということになってしまうため、そのような解釈を採るわけには行かず、いずれの規定も適用されると解する他ないわけであるが、そのように解すると、「資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供」に係る「収益の額」について、認識時期を判断する場合に、いずれの規定を根拠規定とするのかという問題が生ずることとなる(注)。
(注)『平成30年度 税制改正の解説』においては、「資産の販売等に係る収益を益金の額に算入するかどうかについては引き続き法人税法第22条第2項の規定によることとし、その時期及び金額について同法第22条の2で規定されていると整理された」(273頁)と説明されている。
しかし、22条2項が収益認識の時期に関する定めであることについては、既にⅠ1(本誌2018.7.30号5頁)において確認したとおりであり、『昭和40年 改正税法のすべて』においても、22条2項について、「この項の規定は、益金の額の内容を規定するものであると同時に、いわゆる期間損益に関する事項を規定したものであります。」(103頁)と説明されており、同項が「益金の額」の内容とともに収益認識の時期等を定めたものであることは、同項が創設された昭和40年以来、何ら変わるところがないわけであるが、そのような中で、22条の2第1項においては、「別段の定め(前条第4項を除く。)があるものを除き」と定めて、22条2項が22条の2第1項の「別段の定め」としてそのまま残ることを明確に規定している(「別段の定め」には、「前条第4項を除く。」という括弧書きがあるため、「前条第4項」が含まれていることが明らかであり、また、「前条第4項」が含まれているのであれば、当然、22条2項も含まれていると解釈することとなる。)。
つまり、上記の説明のように「その時期及び金額について同法第22条の2で規定されていると整理された」ということにするのであれば、22条の2第1項においては、「別段の定め(前条第4項を除く。)があるものを除き」というように「別段の定め」として22条2項をそのまま残すこととなる定め方としてはならないわけであるが、現実には、改正は、22条2項を22条の2と同じ位置付けにして従前の取扱いをそのまま残すこととする場合の定め方としているため、「その時期及び金額」については従前どおり22条2項でも規定されていると整理された、と解するのが条文の正しい理解となると考えられる。
このように、収益認識の時期を判断する場合に、いずれの規定を根拠規定とするのかという異例の問題が生ずることとなっているのは、上記本文からも分かるとおり、22条2項の「解釈」を通達や解説ではなく22条の2という法律の条文にしたことに原因がある。
この点に関しては、後にⅢにおいて改めて述べることとする。
実務において、22条2項と22条の2第1項のいずれを根拠規定とするのかということが問題となる場面があるとすれば、それは、税務調査で新たな法人税基本通達の定めに基づいて早期に「収益の額」を認識するべきであると指摘される場面となるものと思われるが、そのような指摘を受けたという場合には、従前どおり、22条2項に基づく取扱いも認められる、という主張を行うことも考慮するべきである。平成30年度税制改正後も、22条2項はそのまま残り、「収益認識に関する会計基準」を適用する必要のない中小法人や「収益認識に関する会計基準」を適用する前の法人においては、従前どおりの会計処理が「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従った処理となっており、全く何も変わっていないことから、改正前の法人税基本通達による取扱いが改正後も従前どおりに認められることになるはずである(注)。
(注)国税庁が公表している「「収益認識に関する会計基準」への対応について」においては、「なお、中小企業の会計処理については、従来どおり企業会計原則等による会計処理が認められることとされていますので、今般の通達改正により従来の取扱いが変更されるものではありません。」と説明されているが、「従来の取扱いが変更されるものではありません」という説明がいずれの通達を根拠としたものであるのかということが明らかではない。
「従来の取扱い」を定めていた法人税基本通達は、22条2項とは異なり、「今般の通達改正」によって改正されたものが少なくないため、本来は、「従来の取扱いが変更されるものではありません」という説明の根拠となる通達を明確に示す必要があるものと考えられる。
② 法人税法で定めたことと法人税基本通達で定めたことの関係が不明確になっている 22条の2第1項の「別段の定め(前条第4項を除く。)があるものを除き」という部分(注)には、括弧書きの「前条第4項を除く。」という文言が挿入されているが、これは、22条4項による取扱いを前提に置いて22条の2第1項による取扱いを規定した、ということを示すものである。
(注)「別段の定め(前条第4項を除く。)があるものを除き」という文言が22条の2第1項、第2項及び第4項の3箇所において用いられていることに違和感を覚えるという声が多く聞かれるが、この文言が3箇所で用いられているのは、22条2項の「解釈」として通達に定めるべきことをこれらの規定に書いたために、22条2項と同様に、このような文言を入れることが必要となったことによるものである。
なお、改めて言うまでもないが、この「別段の定め」という文言に関しては、その範囲が限定されているわけではないため、22条2項や3項の例からも分かるとおり、「別段の定め(前条第4項を除く。)があるものを除き」という文言の後に規定されている「その資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する」というところのいずれの部分に関する条項であっても、全て含まれることになる。
このように規定すると、どうなるのかというと、「収益認識に関する会計基準」が22条4項の「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」として適用されている状態のところに、「別段の定め」として22条の2第1項が適用される、ということになる(注)。
(注)22条4項を正しく解釈すれば、同項が22条の2以下の条文に適用されるという解釈が誤りであることは、既に述べたとおりである。
そして、22条4項は同条2項の収益認識の時期を「履行義務充足基準」に変更するものであるため、22条の2第1項において、22条4項を「別段の定め」に含めたままとすると、同項が「別段の定め」として22条の2第1項に優先して適用される、ということになってしまうわけである(注)。
(注)「別段の定め(前条第4項を除く。)があるものを除き」という文言があるということは、22条2項の「解釈」を通達ではなく法律の条文で書いているということを示しており、その文言の中に「前条第4項を除く。」という括弧書きがあるということは、22条4項を「計算心得を宣言、確認する規定」ではなく2項と3項の定めを変更する「創設的、強制的規定」であると勘違いしているということを示しているわけである。
つまり、「前条第4項を除く。」という括弧書きを入れて、22条4項によって収益認識の時期が「収益認識に関する会計基準」における「履行義務充足基準」となるとした上で、その「履行義務充足基準」を否定するために、「引渡基準」と「提供基準」を定める、ということとされているわけである。
そうすると、22条の2第1項の「引渡基準」と「提供基準」による取扱いと、「「収益認識に関する会計基準」における収益の計上単位、計上時期及び計上額について「履行義務」という新たな概念を盛り込んだ形で見直しを行う」(国税庁「「収益認識に関する会計基準」への対応について」)こととして新たに創設されたり改正されたりした法人税基本通達における「履行義務充足基準」による取扱いとの関係がどうなっているのか、という疑問が生じてこざるを得なくなる。
要するに、22条の2第1項においては、「引渡基準」と「提供基準」による取扱いを定めながら、法人税基本通達においては、企業会計における「履行義務充足基準」による取扱いと同様の取扱いを数多く定めることとされているため、両者の関係が不明となっているわけである。
現実には、実務においては、22条の2の定めとは関係なく、法人税基本通達2-1-1以下の定めを見て具体的な事項に関する判断がなされるものと推測されるため、同条にどのような定めが設けられているとしても、あまり影響はないものと考えられるが、法人税基本通達に定められていない事項の取扱いが問題となった場合や法人税基本通達に定められている事項の取扱い自体が問題となった場合には、上記の両者の関係はそもそもどうなっているのか、ということが問題とならざるを得ない。
③ 「役務の提供」に関しては、収益認識の時期の原則が従前の「完了基準」から「提供基準」に変わって益金算入時期が早まっている 22条の2第1項においては、「資産の販売若しくは譲渡〔中略〕に係る収益の額」に関しては従前どおりに「目的物の引渡し〔中略〕の日の属する事業年度」の益金の額に算入するものとされているが、「役務の提供〔中略〕に係る収益の額」に関しては、従前のように役務提供が完了した日の属する事業年度の益金の額に算入するのではなく、「役務の提供の日の属する事業年度」の益金の額に算入するものとされている(注)。
(注)法人税法が昭和40年に制定されて以来、半世紀以上もの間、「原則」とされてきたものを変更するという場合には、本来は、それを変更しなければならない理由があることを明確に説明しなければならないわけであるが、上記の改正の理由は、全く説明されておらず、不明である。
このように、「役務の提供」の収益認識の時期の原則が変わることにより、法人税基本通達に収益認識の時期の取扱いが具体的に定められていないものに関しては、従前の「完了基準」が「提供基準」となり、益金算入時期が早まることとなるため、注意が必要となる(注)。
(注)法人税基本通達2-1-21の2(履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の帰属の時期)においては、「収益認識に関する会計基準」の「適用対象となる取引」である役務の提供のうち、「履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの」について、「履行義務が充足されていくそれぞれの日」が22条の2第1項の「役務の提供の日」となることに留意すべき旨が定められており、同2-1-21の3(履行義務が一時点で充足されるものに係る収益の帰属の時期)においては、「収益認識に関する会計基準」の「適用対象となる取引」である役務の提供のうち、「履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの」以外のものについて、目的物の引渡しの日又は役務の全部を完了した日が22条の2第1項の「役務の提供の日」となることに留意すべき旨が定められている。
実務は、概ね、上記の2つを初めとする法人税基本通達の定めによって収益認識の時期を判断することとなるものと思われる。
ただし、法人税において、何故、「収益認識に関する会計基準」の適用対象となる役務の提供(「収益認識に関する会計基準」においては、「役務」という用語ではなく、「サービス」という用語が用いられている。)に限って上記の通達のような取扱いとしなければならないのか、「収益認識に関する会計基準」の適用対象とならない役務の提供(税法上の「役務の提供」は、非常に範囲が広い。)の取扱いはどうなるのか、22条の2第1項の定め方からすると「収益認識に関する会計基準」の適用対象となるのか否は関係がないのではないかなど、さまざまな疑問が残らざるを得ない。
④ 従前どおりの取扱いと「収益認識に関する会計基準」と同じ取扱いとの選択ができる状態となっている 「収益認識に関する会計基準」が制定されたとしても、それが適用される前の会計処理が認められないということになるわけではなく、大多数の中小法人は、従前どおりの会計処理を行うこととなるはずであり、この会計処理は、従前どおり、22条4項の「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に該当するものということになる。
また、上記①において述べたとおり、第1項は22条2項と内容が重複しているため優先関係等の判断が難しいという問題があったとしても、22条の2第1項は、役務の提供に係る収益認識の時期の原則について上記③で述べたように「完了基準」を「提供基準」に変更している点を除けば、従前の取扱いを変更する内容のものとはなっていない。
そして、上記②においても触れたとおり、法人税基本通達においては、企業会計における「履行義務充足基準」による取扱いと同様の取扱いを数多く定めることとされている。
このため、結果的には、同じ取引について、従前どおりの取扱いと「収益認識に関する会計基準」と同じ取扱いのいずれも認められるという状態となっている(注)。
(注)上記①の最後の注記において述べたとおり、「従来の取扱いが変更されるものではありません」ということがいずれの通達を根拠とした説明であるのかということが明らかではなく、「今般の通達改正」によって従前の通達が無くなっていることから、改正後の通達を根拠として従前の取扱いが否認されるというものが出てこないとも限らないということに留意しておく必要がある。
⑤ 「収益認識に関する会計基準」に合わせた部分も含めて法人税の取扱いが「収益認識に関する会計基準」よりも先に適用される 改正後の法人税基本通達は、「収益認識に関する会計基準」の取扱いに合わせて新たに認められることとなった取扱いも含めて、改正後の法人税法22条4項及び22条の2と同様に、原則として、「平成30年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税」について適用されるため(経過的取扱い(1))、法人税の取扱いが「収益認識に関する会計基準」よりも先に適用されることとなる。「収益認識に関する会計基準」の取扱いに合わせて新たに認められることとなった取扱いは、その多くが「収益の額」の一部の計上を繰り延べることができるものとなっているため、中小法人や「収益認識に関する会計基準」を適用する前の法人も、積極的に活用を検討するべきである。
他方、上記③において述べたとおり、22条の2第1項では、「役務の提供」に関して「完了基準」を「提供基準」として益金算入時期を早めているわけであるが、同項を「施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税」に適用するものとしているため(改正法附則19)、不利益遡及となるものが出てくる可能性がある状態となっている。
このように、平成30年度税制改正が遡及適用される状態となっているのは、その改正の殆どが「明確化」という位置付けとなっているためであると考えられるが、実際には、上記③において述べた「役務の提供」の収益認識の時期の改正だけでなく、22条の2第2項以下の取扱いに関しても、従前の取扱いを変更するものが含まれているため、特に平成30年4月1日以後、最初に終了する事業年度における処理には、注意が必要である。
⑥ 消費税の取扱いが明確ではない 消費税における資産の譲渡等の時期に関しては、次の消費税法基本通達が定められている。
この消費税法基本通達9-6-2に関しては、次のように説明されている。
(濱田正義編『平成30年版 消費税法基本通達逐条解説』(大蔵財務協会)586・587頁)
この消費税法基本通達9-6-2は、平成30年度税制改正後においてもそのまま存置されていることから、基本的には、法人税において益金の額への算入時期が変わったものに関しては、消費税においても、それに合わせて課税資産の譲渡等の時期が変わることになるはずであるが、詳細は、明らかではない。
具体的な取扱い例に関しては、後にⅣ3において国税庁が示している取扱いの例の検証の中で触れることとするが、法人税が各事業年度に帰属する収益の額の合計額から計算される「所得の金額」に課税をするというものであるのに対し、消費税においては、資産の譲渡等という「取引」に課税をするという考え方が採られており、そのような税の性質の違いから、消費税法と消費税法基本通達の改正が行われなくても、従前どおりの取扱いとされるものが出てくることとなっているものと考えられる。
(2)第2項 22条の2第2項は、収益認識の時期の特例を定めるものとされており、資産の販売等に係る「収益の額」について、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従って引渡し等の日に「近接する日」に収益認識を行っている場合には、法人税法上もその「近接する日」に収益認識をするものとされている。
この第2項は、従前の取扱いを確認する内容のものとなっていると解してよいわけであるが、同項には、次のような疑問点と留意点がある。
① 法人税基本通達では、11箇所で「近接する日」に収益認識をすると定めているが、新たな取扱いは1箇所のみである 22条の2第2項に定めが設けられたことを受けて、法人税基本通達において、引渡し等の日に「近接する日」に収益認識をする旨の定めが11箇所にわたって設けられている。
しかし、その11箇所の内、10箇所は、従前、収益認識を行うことを認めていた日を「近接する日」と言い換えただけで、1箇所が新たに「近接する日」に収益認識をすることができることとなっているのみである。
この1箇所とは、法人税基本通達2-1-1の16に定められたもので、次のとおりとなっている。
この法人税基本通達2-1-1の16を見ると、確かに、22条の2第2項が設けられたことで、(1)に「又は同条第2項に規定する近接する日」という文言を置くことが可能となって選択肢が1つ増えていることは事実であるが、わざわざここにこの文言を置かなければならない理由があるとも思われない。
22条の2第2項を設けることで、何箇所かの適切な取扱いが新たに可能となるということであれば、同項を設ける理由があったということにもなろうが、上記の1箇所が増えただけという程度のことであれば、「税制簡素化」が昭和42年当時よりもなお一層必要な中で、わざわざ法律の条項まで創る必要が本当にあったのか、という疑問が残らざるを得ない。
② 「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従って「近接する日」に収益計上を行わなければ、従前どおりの税制上の取扱いが認められなくなる 平成30年度税制改正前に、22条2項の取扱いとして、法人税基本通達において「収益計上を行うこと」等の表現によって会計上で収益に計上する経理をすることを要件に、その経理どおりの益金算入を認めていたものの中には、改正後、22条の2第2項の適用対象とされることにより、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従って収益に計上する経理を行わなければ同様の取扱いが認められなくなるものがあるため、注意が必要である。
例えば、従前は、旧法人税基本通達2-1-2(棚卸資産の引渡しの日の判定)において、ガス、水道、電気等を販売する場合には、いわゆる「検針日基準」によって「収益の額」を認識することが認められていたが、その際には、会計処理上、検針日に「収益計上」を行うことが要件とされていた。しかし、改正後の法人税基本通達2-1-4(検針日による収益の帰属の時期)においては、検針日を「近接する日」として収益認識をすることが認められている点は変わらないものの、検針日を「近接する日」として「法第22条の2第2項《収益の額》の規定を適用する」とされているため、22条の2第2項によって、その収益認識が「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従ったものでない限り、税法上も、その収益認識が認められなくなってしまい、原則どおり、引渡し等の日に収益認識を行わなければならないということになってしまう。
つまり、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従って収益認識を行っていなければ、従前どおりの取扱いが認められないわけであるが、上記①で述べた10箇所には、全てそのような制限が掛かることとなっている。
このような制限を課すことが妥当であるのかということを考えてみると、その妥当性には、疑問がある。
上記①で挙げた10箇所は、上記の「検針日基準」のように、企業会計において「検針日基準」が採られていることを理由として税務上も「検針日基準」を採ることとしていたというものではなく、税務上、「検針日基準」も認めるのが適当であると判断されたために、「検針日基準」を採ることとしていた、という性質のものである(注)。そして、従前、税の観点から「検針日基準」も認めるのが適当であると判断されていたものについて、その判断を変えるべき事情が何か生じたかというと、何も生じていないわけである。
(注)企業会計上は認められるが税法上は認められないというものは、いろいろな場面に数多く存在する。当然のことながら、税法上の取扱いの適否は、税の観点から判断するべきものである。近年、企業会計が多様化する中にあっては、税が自らの観点から取扱いの適否を判断するということがなお一層重要となる、ということを忘れてはならない。
それにもかかわらず、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従うことを要件として追加するということには、合理的な理由がない、と言わざるを得ない(注)。
(注)22条の2第2項において、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従うことを要件として追加したのは、上記Ⅰ2(本誌2018.8.6号17頁掲載)において述べたとおり、法人税法における「所得の金額」の計算と企業会計上の当期利益の額の計算との関係を勘違いしていることに原因があるものと考えられる。
仮に、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従うものではないということを理由に、「検針日基準」等が認められないとして、課税が行われるようなこととなった場合には、22条2項が従前どおりであることも踏まえて、従前どおりの取扱いが認められると解される旨の主張をすることになるものと考えられる。
(3)第3項 22条の2第3項は、申告調整によって2項の「近接する日」に収益認識をすることができるということを定めるものとされている。
この定めにより、柔軟な収益認識が可能となっている。
特に、中小法人や「収益認識に関する会計基準」の適用前の法人は、積極的に活用することを検討するべきである。
ただし、22条の2第3項に関しては、このような法律の条項を創る必要性について、疑問がある。
上記(2)①において述べたとおり、法人税基本通達には11箇所において「近接する日」に収益認識を行うことができる旨の定めが設けられているわけであるが、その中の従前から存在する10箇所に関しては、申告調整で収益認識を認めるということであれば、改正後のように、22条の2第2項で「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従って会計処理を行うことを求めた上で、22条の2第3項で申告調整によって収益認識を認める、という迂遠なことをせずとも、従前、法人税基本通達で「収益計上」を求めていた文言を削除すれば、それだけで足ることとなる。
要するに、わざわざ法律で2つの条項を設け、法人税基本通達で「法第22条の2第2項《収益の額》の規定を適用する」と定めて、22条の2第2項の適用を受けさせることとした上で、22条の2第3項を適用して申告調整によることもできる、というような回りくどい複雑な仕組みを創る必要などなく、従前の法人税基本通達の「収益計上」を求める文言を削除するという、「税制簡素化」に資する簡単な通達改正を行うだけで、同じ結果が得られるわけである。
この22条の2第3項に関しても、わざわざ法律の条項まで創る必要が本当にあったのか、ということを改めて考えてみる必要があると考えられる。
(4)第4項 22条の2第4項は、「収益の額」について、「その販売若しくは譲渡をした資産の引渡し時における価額又はその提供した役務につき通常得べき対価の額」に相当する金額となると定めており、資産の販売等の「収益の額」をどのような金額とするのかということに関する原則を定めたものと説明されている。
この22条の2第4項については、「値引きや割戻しについては、譲渡資産等の時価をより正確に反映させるための調整と位置づけることができる」(国税庁「「収益認識に関する会計基準」への対応について」9頁)とされており、法人税基本通達2-1-1の11(変動対価)が新たに設けられ、「ケース3 割戻を見込む販売(論点:変動対価)」(国税庁「収益認識基準による場合の取扱いの例」3頁)においても販売時に割戻しに対応する金額を後の事業年度で売上に計上する処理例が示されている。
つまり、22条の2第4項により、資産の販売等の後に値引きや割戻しがあるものについては、資産の販売等の時の益金算入額を従前よりも少なくすることができることとなる。
このため、この22条の2第4項に関しても、値引きや割戻しなどがある場合には、積極的に利用することを検討するべきである(注)。
(注)22条の2第4項の条文をどのように読んでも、値引きや割戻しなどがある場合にその値引きや割戻しの部分の「収益の額」を後の事業年度に繰り延べてよいと解釈することは困難であるため、法律の条文の正しい解釈という観点からすれば、上記の法人税基本通達2-1-1の11のような解釈には疑問があると言わざるを得ないわけであるが、国税当局が「収益の額」の一部を後の事業年度に繰り延べてよいと解釈しているのであれば、納税者としては、そのメリットを積極的に享受することでよいものと考えられる。
ただし、この22条の2第4項に関しては、その内容に疑問があるため、注意が必要である。
22条の2第4項においては、役務の提供に係る「収益の額」とすべき資産の「時価」に関しては、「通常得べき対価の額」(注)に相当する金額としており、これが提供した役務の「時価」となることに異論はないはずであるが、資産の販売又は譲渡に係る「収益の額」とすべき資産の「時価」に関して、「資産の引渡し時における価額」としていることについては、誤りと言う他ない。
(注)資産の販売又は譲渡に係る「収益の額」とすべき資産の「時価」に関して、時点を示して「資産の引渡し時における価額」と規定するのであれば、本来は、役務の提供に係る「収益の額」とすべき役務の「時価」に関しても、同様に、時点を示して規定するべきである。
勿論、その反対に、役務の提供に係る「収益の額」とすべき役務の「時価」に合わせて資産の販売又は譲渡に係る「収益の額」とすべき資産の「時価」を定めるという方法もあるわけであるが、いずれにしても、法令作成の常識からすると、「又は」という用語を用いて並べた一方「時価」の規定の仕方と他方の「時価」の規定の仕方とが違っていることに関しては、適当ではない、と言わざるを得ない。
資産の販売又は譲渡の取引は、基本的には、当事者が取引価格を含む取引条件に合意することによって成立し、その成立した取引の実行行為として、「資産の引渡し」が行われることとなるため、通常、当事者が取引価格に合意した時点では、「資産の引渡し」までは行われておらず、「資産の引渡し」は、当事者が取引価格に合意した時点よりも後の時点で行われることとなる。このため、資産の販売又は譲渡の取引における「時価」は、「約定時(取引が成立した時)」の「時価」となっており、「資産の引渡し時」の「時価」とはなっていない。
要するに、資産の販売又は譲渡に係る「収益の額」とすべき資産の「時価」について、「資産の引渡し時における価額」を原則とするということに関しては、誤りと言わざるを得ないわけである。
仮に、資産の販売又は譲渡に係る「収益の額」とすべき資産の「時価」を「資産の引渡し時における価額」としなければならないということになると、ほぼ全ての法人が大量の取引について、膨大な申告調整を行わなければならないという事態となってしまう。
実務においては、従前どおり、「約定時(取引が成立した時)」の「時価」に基づいて「収益の額」を認識することでよいものと考えられるが(注)、当分の間は、国税当局の対応を注視しておく必要があるものと考えられる。
(注)「約定時(取引が成立した時)」の「時価」又は「通常得べき対価の額」によって「収益の額」を認識するということであれば、誰もが既に分かっていることであって、わざわざ法律の条文を創る必要はない。
(5)第5項 22条の2第5項においては、「前項の引渡しの時における価額又は通常得べき対価の額」について、貸倒れや買戻しの可能性がある場合においても、その可能性がないものとした場合における価額とする、とされている。
この22条の2第5項に関しても、前項と同じく、その内容に疑問がある。
「資産の販売等」が金銭の貸付けとなっている場合について考えてみると、その貸付けが第三者間取引であれば、当然、債務者の貸倒れの可能性等を約定金利に反映させることとなるわけであって、貸倒れの可能性がある場合とない場合とで取引価格が異なるのは、当然のことである。仮に、金銭の貸付けにおいて、「その可能性〔1号の「金銭債権の貸倒れ」の可能性〕がないものとした場合における価額」を「時価」として「収益の額」を認識しなければならないということであれば、金銭の貸付けの当事者である法人の殆ど全てに寄附金と受贈益が発生するというような事態になってしまう。
また、この22条の2第5項による取扱いに関しては、次の「ケース4 返品権付き販売(論点:変動対価)」(国税庁「収益認識基準による場合の取扱いの例」4頁)に具体的な処理例が示されているため、この処理例で確認してみよう。
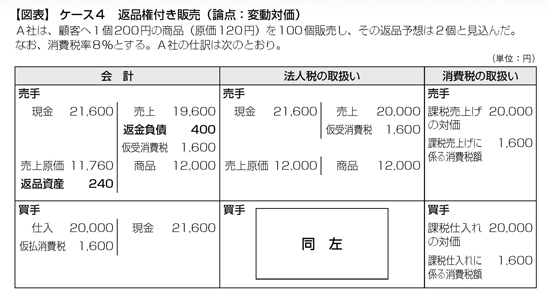
このケースは、22条の2第5項2号に該当するものであり、企業会計上、「売上」が「19,600」とされるとしても、税法上、「売上」は、同項の「その可能性〔2号の「資産の買戻し」の可能性〕がないものとした場合における価額」である「20,000」となる、とされているわけである。
しかし、このケースを雑誌の販売など返品が多いものを例にして考えてみると、「20,000」という金額は、資産の買戻しがないものとした場合における価額ではなく、資産の買戻しがあるものとした場合における価額となっていることが容易に分かるはずである。このケースでは、返品予想が2個のみであるが、それがあるが故に、取引価格が返品のない場合の取引価格よりも少し高い「20,000」とされているわけである。
要するに、22条の2第5項は、「金銭債権の貸倒れ」や「資産の買戻し」があるということであれば、当然、「時価」はそれらの可能性があるものとした場合における価額でなければならないところ、その反対のことを書いているわけである。
22条の2第5項がなければ、誰もが、「金銭債権の貸倒れ」や「資産の買戻し」があるということであれば「時価」はそれらの可能性があるものとした場合における価額であると認識するはずであり、同項は、本来、設けてはならない内容の規定を設けた、という状態になっているわけである。
(6)第6項 22条の2第6項においては、「無償による資産の譲渡に係る収益の額」は「金銭以外の資産による利益又は剰余金の分配及び残余財産の分配又は引渡しその他これらに類する行為としての資産の譲渡に係る収益の額」を「含むものとする」と定められている。
この22条の2第6項に関しては、「明確化」と説明されているわけであるが、後のⅢ6において、『平成30年度 税制改正の解説』における説明を引用しながら、「明確化」をする必要はなく、22条における「取引」の理解を誤ったために同項が設けられることとなったものである、ということを具体的に説明することとする。
(第4回(本誌2018.9.3号掲載予定)に続く)
「収益認識に関する会計基準等への対応」として平成30年度に行われた税法・通達改正の検証(3)
日本税制研究所 代表理事 税理士 朝長英樹
前回及び前々回は、平成30年度税制改正で改正された法人税法22条4項と新たに創設された22条の2の前提となった22条2項と4項の解釈を確認した。
第3回目となる今回は、平成30年度税制改正後の22条4項と22条の2について、改正の内容を条項ごとに確認しながら、改正の適否や実務対応などについて検証を行う。
Ⅱ 平成30年度税制改正後の法人税法22条4項と22条の2の確認と検証
Ⅱにおいては、まず初めに、平成30年度税制改正後の22条4項の確認と検証を行い、その後に、22条の2の確認と検証を行うこととする。
1 平成30年度税制改正後の法人税法22条4項の確認と検証 平成30年度税制改正後の22条4項は、次のとおりとなっている。
| 4 第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。 |
上記Ⅰ2(本誌2018.8.6号15頁)において確認したとおり、4項は、2項の「収益の額」及び3項の「原価の額」等の「計算」をする場面において「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」を「尊重」するべきであるという「計算心得を宣言、確認する規定」という性格のものであり、また、2項や3項の「別段の定め」が適用される場面に適用されるものともなっていない。
このため、4項には、2項や3項の「別段の定め」を除く旨の文言を挿入する理由がない。
また、上記Ⅰ2において、「引渡基準」及び「完了基準」と「実現主義」の例、無償による譲渡の例、「債務確定基準(債務確定主義)」の例、賞与引当金などのさまざまな引当金の例を挙げて確認したとおり、4項は、2項と3項において定められたことを変更するものでもない。
このため、2項の取扱いに関して22条の2を設けるとしても、4項に22条の2を除く旨の文言を挿入する必要もない。
このように、平成30年度税制改正において4項に「別段の定めがあるものを除き」という文言を挿入した改正は、誤りと言う他ない(注)。
(注)『平成30年度 税制改正の解説』においては、4項に「別段の定めがあるものを除き」という文言を挿入することによって、同項が収益認識の時期に適用されないようにしたという説明(273頁)や同項と22条の2以下の規定とが抵触しないようにしたという説明(280頁)がなされているが、これらの説明は、上記本文の説明からもうかがわれるとおり、同項の解釈を誤ったものと言わざるを得ない。
これらの詳細に関しては、後にⅢにおいて述べることとする。
しかし、4項に「別段の定めがあるものを除き」という文言を挿入したことによって何か問題が生ずるのかというと、元々、同項が2項や3項の「別段の定め」に適用されず、同項が2項と3項の定めを変更するものでもない中で、「別段の定めがあるものを除き」という文言を挿入するという状態となっているため、いわゆる“空振り”となっているだけで、直接、実務に影響を与えるような問題が生ずることはないはずである。
ただし、4項において、このような改正が行われているということは、法人税法において「所得の金額」の計算に関する規定が企業会計における利益の額の計算を前提として定められていると誤って理解されている可能性が高いということでもあるため、今後、22条2項及び3項並びに23条以下の規定の解釈を行う場合においては、企業会計における利益の額の計算を前提として文言を解釈するという、同じ誤りを起こさないように、十分、注意をすることが必要となる(注)。
(注)これに関しては、法人税法における「所得の金額」の計算が法人税申告書別表4(所得の金額の計算に関する明細書)における「所得金額又は欠損金額」の計算――企業会計上の「当期利益又は当期欠損の額」に必要事項を加減算して「所得金額又は欠損金額」を求めるもの――と同様の構造となっていると勘違いして、22条2項及び3項並びに23条以下の規定を解釈する、ということのないようにしなければならない、と言い換えてもよかろう。
2 法人税法22条の2の確認と検証 平成30年度税制改正によって創設された22条の2は、次のとおりである。
| 第1目 収益の額 第22条の2 内国法人の資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供(以下この条において「資産の販売等」という。)に係る収益の額は、別段の定め(前条第4項を除く。)があるものを除き、その資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 2 内国法人が、資産の販売等に係る収益の額につき一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて当該資産の販売等に係る契約の効力が生ずる日その他の前項に規定する日に近接する日の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場合には、同項の規定にかかわらず、当該資産の販売等に係る収益の額は、別段の定め(前条第4項を除く。)があるものを除き、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 3 内国法人が資産の販売等を行つた場合(当該資産の販売等に係る収益の額につき一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて第1項に規定する日又は前項に規定する近接する日の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場合を除く。)において、当該資産の販売等に係る同項に規定する近接する日の属する事業年度の確定申告書に当該資産の販売等に係る収益の額の益金算入に関する申告の記載があるときは、その額につき当該事業年度の確定した決算において収益として経理したものとみなして、同項の規定を適用する。 4 内国法人の各事業年度の資産の販売等に係る収益の額として第1項又は第2項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額は、別段の定め(前条第4項を除く。)があるものを除き、その販売若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又はその提供をした役務につき通常得べき対価の額に相当する金額とする。 5 前項の引渡しの時における価額又は通常得べき対価の額は、同項の資産の販売等につき次に掲げる事実が生ずる可能性がある場合においても、その可能性がないものとした場合における価額とする。 一 当該資産の販売等の対価の額に係る金銭債権の貸倒れ 二 当該資産の販売等(資産の販売又は譲渡に限る。)に係る資産の買戻し 6 前各項及び前条第2項の場合には、無償による資産の譲渡に係る収益の額は、金銭以外の資産による利益又は剰余金の分配及び残余財産の分配又は引渡しその他これらに類する行為としての資産の譲渡に係る収益の額を含むものとする。 7 前2項に定めるもののほか、資産の販売等に係る収益の額につき修正の経理をした場合の処理その他第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 |
この第1項に関しては、従前の取扱いの「明確化」と説明されている。
このため、基本的には、従前どおりの取扱いとなると考えてよい。
しかし、この第1項に関しては、次のような点に留意する必要がある。
① 第1項は、22条2項と内容が重複しているため、2つの取扱いが異なる場合の判断が難しい 22条の2第1項に定められたことは、既に、22条2項において定められていたことであって、22条の2第1項を定めたことにより、「資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供」に係る「収益の額」の認識時期について、2つの定めが存在するという異例の状態となっている(注)。
(注)Ⅰ1(本誌2018.7.30号5頁)において確認したとおり、22条2項に関しては、収益認識の時期の原則をどのようなものとするのかということが最も重要な論点であった。
そして、これらの規定には、いずれにも「資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供」に係る「収益の額」の認識時期が定められており、しかも、いずれにも「別段の定め」があるものを除く旨の文言が存在することから、文理に即して正しく解釈するとすれば、「資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供」に係る「収益の額」の認識時期の判断には、いずれの規定も適用されない、ということになる。
しかし、そうすると、法人税法に「資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供」に係る「収益の額」の認識時期の原則に関する定めが存在しないということになってしまうため、そのような解釈を採るわけには行かず、いずれの規定も適用されると解する他ないわけであるが、そのように解すると、「資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供」に係る「収益の額」について、認識時期を判断する場合に、いずれの規定を根拠規定とするのかという問題が生ずることとなる(注)。
(注)『平成30年度 税制改正の解説』においては、「資産の販売等に係る収益を益金の額に算入するかどうかについては引き続き法人税法第22条第2項の規定によることとし、その時期及び金額について同法第22条の2で規定されていると整理された」(273頁)と説明されている。
しかし、22条2項が収益認識の時期に関する定めであることについては、既にⅠ1(本誌2018.7.30号5頁)において確認したとおりであり、『昭和40年 改正税法のすべて』においても、22条2項について、「この項の規定は、益金の額の内容を規定するものであると同時に、いわゆる期間損益に関する事項を規定したものであります。」(103頁)と説明されており、同項が「益金の額」の内容とともに収益認識の時期等を定めたものであることは、同項が創設された昭和40年以来、何ら変わるところがないわけであるが、そのような中で、22条の2第1項においては、「別段の定め(前条第4項を除く。)があるものを除き」と定めて、22条2項が22条の2第1項の「別段の定め」としてそのまま残ることを明確に規定している(「別段の定め」には、「前条第4項を除く。」という括弧書きがあるため、「前条第4項」が含まれていることが明らかであり、また、「前条第4項」が含まれているのであれば、当然、22条2項も含まれていると解釈することとなる。)。
つまり、上記の説明のように「その時期及び金額について同法第22条の2で規定されていると整理された」ということにするのであれば、22条の2第1項においては、「別段の定め(前条第4項を除く。)があるものを除き」というように「別段の定め」として22条2項をそのまま残すこととなる定め方としてはならないわけであるが、現実には、改正は、22条2項を22条の2と同じ位置付けにして従前の取扱いをそのまま残すこととする場合の定め方としているため、「その時期及び金額」については従前どおり22条2項でも規定されていると整理された、と解するのが条文の正しい理解となると考えられる。
このように、収益認識の時期を判断する場合に、いずれの規定を根拠規定とするのかという異例の問題が生ずることとなっているのは、上記本文からも分かるとおり、22条2項の「解釈」を通達や解説ではなく22条の2という法律の条文にしたことに原因がある。
この点に関しては、後にⅢにおいて改めて述べることとする。
実務において、22条2項と22条の2第1項のいずれを根拠規定とするのかということが問題となる場面があるとすれば、それは、税務調査で新たな法人税基本通達の定めに基づいて早期に「収益の額」を認識するべきであると指摘される場面となるものと思われるが、そのような指摘を受けたという場合には、従前どおり、22条2項に基づく取扱いも認められる、という主張を行うことも考慮するべきである。平成30年度税制改正後も、22条2項はそのまま残り、「収益認識に関する会計基準」を適用する必要のない中小法人や「収益認識に関する会計基準」を適用する前の法人においては、従前どおりの会計処理が「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従った処理となっており、全く何も変わっていないことから、改正前の法人税基本通達による取扱いが改正後も従前どおりに認められることになるはずである(注)。
(注)国税庁が公表している「「収益認識に関する会計基準」への対応について」においては、「なお、中小企業の会計処理については、従来どおり企業会計原則等による会計処理が認められることとされていますので、今般の通達改正により従来の取扱いが変更されるものではありません。」と説明されているが、「従来の取扱いが変更されるものではありません」という説明がいずれの通達を根拠としたものであるのかということが明らかではない。
「従来の取扱い」を定めていた法人税基本通達は、22条2項とは異なり、「今般の通達改正」によって改正されたものが少なくないため、本来は、「従来の取扱いが変更されるものではありません」という説明の根拠となる通達を明確に示す必要があるものと考えられる。
② 法人税法で定めたことと法人税基本通達で定めたことの関係が不明確になっている 22条の2第1項の「別段の定め(前条第4項を除く。)があるものを除き」という部分(注)には、括弧書きの「前条第4項を除く。」という文言が挿入されているが、これは、22条4項による取扱いを前提に置いて22条の2第1項による取扱いを規定した、ということを示すものである。
(注)「別段の定め(前条第4項を除く。)があるものを除き」という文言が22条の2第1項、第2項及び第4項の3箇所において用いられていることに違和感を覚えるという声が多く聞かれるが、この文言が3箇所で用いられているのは、22条2項の「解釈」として通達に定めるべきことをこれらの規定に書いたために、22条2項と同様に、このような文言を入れることが必要となったことによるものである。
なお、改めて言うまでもないが、この「別段の定め」という文言に関しては、その範囲が限定されているわけではないため、22条2項や3項の例からも分かるとおり、「別段の定め(前条第4項を除く。)があるものを除き」という文言の後に規定されている「その資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する」というところのいずれの部分に関する条項であっても、全て含まれることになる。
このように規定すると、どうなるのかというと、「収益認識に関する会計基準」が22条4項の「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」として適用されている状態のところに、「別段の定め」として22条の2第1項が適用される、ということになる(注)。
(注)22条4項を正しく解釈すれば、同項が22条の2以下の条文に適用されるという解釈が誤りであることは、既に述べたとおりである。
そして、22条4項は同条2項の収益認識の時期を「履行義務充足基準」に変更するものであるため、22条の2第1項において、22条4項を「別段の定め」に含めたままとすると、同項が「別段の定め」として22条の2第1項に優先して適用される、ということになってしまうわけである(注)。
(注)「別段の定め(前条第4項を除く。)があるものを除き」という文言があるということは、22条2項の「解釈」を通達ではなく法律の条文で書いているということを示しており、その文言の中に「前条第4項を除く。」という括弧書きがあるということは、22条4項を「計算心得を宣言、確認する規定」ではなく2項と3項の定めを変更する「創設的、強制的規定」であると勘違いしているということを示しているわけである。
つまり、「前条第4項を除く。」という括弧書きを入れて、22条4項によって収益認識の時期が「収益認識に関する会計基準」における「履行義務充足基準」となるとした上で、その「履行義務充足基準」を否定するために、「引渡基準」と「提供基準」を定める、ということとされているわけである。
そうすると、22条の2第1項の「引渡基準」と「提供基準」による取扱いと、「「収益認識に関する会計基準」における収益の計上単位、計上時期及び計上額について「履行義務」という新たな概念を盛り込んだ形で見直しを行う」(国税庁「「収益認識に関する会計基準」への対応について」)こととして新たに創設されたり改正されたりした法人税基本通達における「履行義務充足基準」による取扱いとの関係がどうなっているのか、という疑問が生じてこざるを得なくなる。
要するに、22条の2第1項においては、「引渡基準」と「提供基準」による取扱いを定めながら、法人税基本通達においては、企業会計における「履行義務充足基準」による取扱いと同様の取扱いを数多く定めることとされているため、両者の関係が不明となっているわけである。
現実には、実務においては、22条の2の定めとは関係なく、法人税基本通達2-1-1以下の定めを見て具体的な事項に関する判断がなされるものと推測されるため、同条にどのような定めが設けられているとしても、あまり影響はないものと考えられるが、法人税基本通達に定められていない事項の取扱いが問題となった場合や法人税基本通達に定められている事項の取扱い自体が問題となった場合には、上記の両者の関係はそもそもどうなっているのか、ということが問題とならざるを得ない。
③ 「役務の提供」に関しては、収益認識の時期の原則が従前の「完了基準」から「提供基準」に変わって益金算入時期が早まっている 22条の2第1項においては、「資産の販売若しくは譲渡〔中略〕に係る収益の額」に関しては従前どおりに「目的物の引渡し〔中略〕の日の属する事業年度」の益金の額に算入するものとされているが、「役務の提供〔中略〕に係る収益の額」に関しては、従前のように役務提供が完了した日の属する事業年度の益金の額に算入するのではなく、「役務の提供の日の属する事業年度」の益金の額に算入するものとされている(注)。
(注)法人税法が昭和40年に制定されて以来、半世紀以上もの間、「原則」とされてきたものを変更するという場合には、本来は、それを変更しなければならない理由があることを明確に説明しなければならないわけであるが、上記の改正の理由は、全く説明されておらず、不明である。
このように、「役務の提供」の収益認識の時期の原則が変わることにより、法人税基本通達に収益認識の時期の取扱いが具体的に定められていないものに関しては、従前の「完了基準」が「提供基準」となり、益金算入時期が早まることとなるため、注意が必要となる(注)。
(注)法人税基本通達2-1-21の2(履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の帰属の時期)においては、「収益認識に関する会計基準」の「適用対象となる取引」である役務の提供のうち、「履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの」について、「履行義務が充足されていくそれぞれの日」が22条の2第1項の「役務の提供の日」となることに留意すべき旨が定められており、同2-1-21の3(履行義務が一時点で充足されるものに係る収益の帰属の時期)においては、「収益認識に関する会計基準」の「適用対象となる取引」である役務の提供のうち、「履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの」以外のものについて、目的物の引渡しの日又は役務の全部を完了した日が22条の2第1項の「役務の提供の日」となることに留意すべき旨が定められている。
実務は、概ね、上記の2つを初めとする法人税基本通達の定めによって収益認識の時期を判断することとなるものと思われる。
ただし、法人税において、何故、「収益認識に関する会計基準」の適用対象となる役務の提供(「収益認識に関する会計基準」においては、「役務」という用語ではなく、「サービス」という用語が用いられている。)に限って上記の通達のような取扱いとしなければならないのか、「収益認識に関する会計基準」の適用対象とならない役務の提供(税法上の「役務の提供」は、非常に範囲が広い。)の取扱いはどうなるのか、22条の2第1項の定め方からすると「収益認識に関する会計基準」の適用対象となるのか否は関係がないのではないかなど、さまざまな疑問が残らざるを得ない。
④ 従前どおりの取扱いと「収益認識に関する会計基準」と同じ取扱いとの選択ができる状態となっている 「収益認識に関する会計基準」が制定されたとしても、それが適用される前の会計処理が認められないということになるわけではなく、大多数の中小法人は、従前どおりの会計処理を行うこととなるはずであり、この会計処理は、従前どおり、22条4項の「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に該当するものということになる。
また、上記①において述べたとおり、第1項は22条2項と内容が重複しているため優先関係等の判断が難しいという問題があったとしても、22条の2第1項は、役務の提供に係る収益認識の時期の原則について上記③で述べたように「完了基準」を「提供基準」に変更している点を除けば、従前の取扱いを変更する内容のものとはなっていない。
そして、上記②においても触れたとおり、法人税基本通達においては、企業会計における「履行義務充足基準」による取扱いと同様の取扱いを数多く定めることとされている。
このため、結果的には、同じ取引について、従前どおりの取扱いと「収益認識に関する会計基準」と同じ取扱いのいずれも認められるという状態となっている(注)。
(注)上記①の最後の注記において述べたとおり、「従来の取扱いが変更されるものではありません」ということがいずれの通達を根拠とした説明であるのかということが明らかではなく、「今般の通達改正」によって従前の通達が無くなっていることから、改正後の通達を根拠として従前の取扱いが否認されるというものが出てこないとも限らないということに留意しておく必要がある。
⑤ 「収益認識に関する会計基準」に合わせた部分も含めて法人税の取扱いが「収益認識に関する会計基準」よりも先に適用される 改正後の法人税基本通達は、「収益認識に関する会計基準」の取扱いに合わせて新たに認められることとなった取扱いも含めて、改正後の法人税法22条4項及び22条の2と同様に、原則として、「平成30年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税」について適用されるため(経過的取扱い(1))、法人税の取扱いが「収益認識に関する会計基準」よりも先に適用されることとなる。「収益認識に関する会計基準」の取扱いに合わせて新たに認められることとなった取扱いは、その多くが「収益の額」の一部の計上を繰り延べることができるものとなっているため、中小法人や「収益認識に関する会計基準」を適用する前の法人も、積極的に活用を検討するべきである。
他方、上記③において述べたとおり、22条の2第1項では、「役務の提供」に関して「完了基準」を「提供基準」として益金算入時期を早めているわけであるが、同項を「施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税」に適用するものとしているため(改正法附則19)、不利益遡及となるものが出てくる可能性がある状態となっている。
このように、平成30年度税制改正が遡及適用される状態となっているのは、その改正の殆どが「明確化」という位置付けとなっているためであると考えられるが、実際には、上記③において述べた「役務の提供」の収益認識の時期の改正だけでなく、22条の2第2項以下の取扱いに関しても、従前の取扱いを変更するものが含まれているため、特に平成30年4月1日以後、最初に終了する事業年度における処理には、注意が必要である。
⑥ 消費税の取扱いが明確ではない 消費税における資産の譲渡等の時期に関しては、次の消費税法基本通達が定められている。
| (資産の譲渡等の時期の別段の定め) 9-6-2 資産の譲渡等の時期について、所得税又は法人税の課税所得金額の計算における総収入金額又は益金の額に算入すべき時期に関し、別に定めがある場合には、それによることができるものとする。 |
| 資産の譲渡等の時期の取扱いについて、基本通達9-1-1から9-6-1までにおいてその具体的な基準を定めているが、所得税又は法人税の課税所得金額の計算における総収入金額又は益金の額に算入すべき時期に関し、基本通達と別に定めがある場合には、それによることができる旨を本通達で明らかにしたものである。[中略]法人にあっては、法人税の法令、通達等に定める益金の額に算入すべき時期によることができることとなるのであり、例えば、法人税基本通達2-6-1《決算締切日》がこれに該当する。 |
この消費税法基本通達9-6-2は、平成30年度税制改正後においてもそのまま存置されていることから、基本的には、法人税において益金の額への算入時期が変わったものに関しては、消費税においても、それに合わせて課税資産の譲渡等の時期が変わることになるはずであるが、詳細は、明らかではない。
具体的な取扱い例に関しては、後にⅣ3において国税庁が示している取扱いの例の検証の中で触れることとするが、法人税が各事業年度に帰属する収益の額の合計額から計算される「所得の金額」に課税をするというものであるのに対し、消費税においては、資産の譲渡等という「取引」に課税をするという考え方が採られており、そのような税の性質の違いから、消費税法と消費税法基本通達の改正が行われなくても、従前どおりの取扱いとされるものが出てくることとなっているものと考えられる。
(2)第2項 22条の2第2項は、収益認識の時期の特例を定めるものとされており、資産の販売等に係る「収益の額」について、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従って引渡し等の日に「近接する日」に収益認識を行っている場合には、法人税法上もその「近接する日」に収益認識をするものとされている。
この第2項は、従前の取扱いを確認する内容のものとなっていると解してよいわけであるが、同項には、次のような疑問点と留意点がある。
① 法人税基本通達では、11箇所で「近接する日」に収益認識をすると定めているが、新たな取扱いは1箇所のみである 22条の2第2項に定めが設けられたことを受けて、法人税基本通達において、引渡し等の日に「近接する日」に収益認識をする旨の定めが11箇所にわたって設けられている。
しかし、その11箇所の内、10箇所は、従前、収益認識を行うことを認めていた日を「近接する日」と言い換えただけで、1箇所が新たに「近接する日」に収益認識をすることができることとなっているのみである。
この1箇所とは、法人税基本通達2-1-1の16に定められたもので、次のとおりとなっている。
| (相手方に支払われる対価) 2-1-1の16 資産の販売等に係る契約において、いわゆるキャッシュバックのように相手方に対価が支払われることが条件となっている場合(損金不算入費用等に該当しない場合に限る。)には、次に掲げる日のうちいずれか遅い日の属する事業年度においてその対価の額に相当する金額を当該事業年度の収益の額から減額する。 (1)その支払う対価に関連する資産の販売等に係る法第22条の2第1項《収益の額》に規定する日又は同条第2項に規定する近接する日 (2)その対価を支払う日又はその支払を約する日 |
22条の2第2項を設けることで、何箇所かの適切な取扱いが新たに可能となるということであれば、同項を設ける理由があったということにもなろうが、上記の1箇所が増えただけという程度のことであれば、「税制簡素化」が昭和42年当時よりもなお一層必要な中で、わざわざ法律の条項まで創る必要が本当にあったのか、という疑問が残らざるを得ない。
② 「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従って「近接する日」に収益計上を行わなければ、従前どおりの税制上の取扱いが認められなくなる 平成30年度税制改正前に、22条2項の取扱いとして、法人税基本通達において「収益計上を行うこと」等の表現によって会計上で収益に計上する経理をすることを要件に、その経理どおりの益金算入を認めていたものの中には、改正後、22条の2第2項の適用対象とされることにより、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従って収益に計上する経理を行わなければ同様の取扱いが認められなくなるものがあるため、注意が必要である。
例えば、従前は、旧法人税基本通達2-1-2(棚卸資産の引渡しの日の判定)において、ガス、水道、電気等を販売する場合には、いわゆる「検針日基準」によって「収益の額」を認識することが認められていたが、その際には、会計処理上、検針日に「収益計上」を行うことが要件とされていた。しかし、改正後の法人税基本通達2-1-4(検針日による収益の帰属の時期)においては、検針日を「近接する日」として収益認識をすることが認められている点は変わらないものの、検針日を「近接する日」として「法第22条の2第2項《収益の額》の規定を適用する」とされているため、22条の2第2項によって、その収益認識が「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従ったものでない限り、税法上も、その収益認識が認められなくなってしまい、原則どおり、引渡し等の日に収益認識を行わなければならないということになってしまう。
つまり、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従って収益認識を行っていなければ、従前どおりの取扱いが認められないわけであるが、上記①で述べた10箇所には、全てそのような制限が掛かることとなっている。
このような制限を課すことが妥当であるのかということを考えてみると、その妥当性には、疑問がある。
上記①で挙げた10箇所は、上記の「検針日基準」のように、企業会計において「検針日基準」が採られていることを理由として税務上も「検針日基準」を採ることとしていたというものではなく、税務上、「検針日基準」も認めるのが適当であると判断されたために、「検針日基準」を採ることとしていた、という性質のものである(注)。そして、従前、税の観点から「検針日基準」も認めるのが適当であると判断されていたものについて、その判断を変えるべき事情が何か生じたかというと、何も生じていないわけである。
(注)企業会計上は認められるが税法上は認められないというものは、いろいろな場面に数多く存在する。当然のことながら、税法上の取扱いの適否は、税の観点から判断するべきものである。近年、企業会計が多様化する中にあっては、税が自らの観点から取扱いの適否を判断するということがなお一層重要となる、ということを忘れてはならない。
それにもかかわらず、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従うことを要件として追加するということには、合理的な理由がない、と言わざるを得ない(注)。
(注)22条の2第2項において、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従うことを要件として追加したのは、上記Ⅰ2(本誌2018.8.6号17頁掲載)において述べたとおり、法人税法における「所得の金額」の計算と企業会計上の当期利益の額の計算との関係を勘違いしていることに原因があるものと考えられる。
仮に、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従うものではないということを理由に、「検針日基準」等が認められないとして、課税が行われるようなこととなった場合には、22条2項が従前どおりであることも踏まえて、従前どおりの取扱いが認められると解される旨の主張をすることになるものと考えられる。
(3)第3項 22条の2第3項は、申告調整によって2項の「近接する日」に収益認識をすることができるということを定めるものとされている。
この定めにより、柔軟な収益認識が可能となっている。
特に、中小法人や「収益認識に関する会計基準」の適用前の法人は、積極的に活用することを検討するべきである。
ただし、22条の2第3項に関しては、このような法律の条項を創る必要性について、疑問がある。
上記(2)①において述べたとおり、法人税基本通達には11箇所において「近接する日」に収益認識を行うことができる旨の定めが設けられているわけであるが、その中の従前から存在する10箇所に関しては、申告調整で収益認識を認めるということであれば、改正後のように、22条の2第2項で「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従って会計処理を行うことを求めた上で、22条の2第3項で申告調整によって収益認識を認める、という迂遠なことをせずとも、従前、法人税基本通達で「収益計上」を求めていた文言を削除すれば、それだけで足ることとなる。
要するに、わざわざ法律で2つの条項を設け、法人税基本通達で「法第22条の2第2項《収益の額》の規定を適用する」と定めて、22条の2第2項の適用を受けさせることとした上で、22条の2第3項を適用して申告調整によることもできる、というような回りくどい複雑な仕組みを創る必要などなく、従前の法人税基本通達の「収益計上」を求める文言を削除するという、「税制簡素化」に資する簡単な通達改正を行うだけで、同じ結果が得られるわけである。
この22条の2第3項に関しても、わざわざ法律の条項まで創る必要が本当にあったのか、ということを改めて考えてみる必要があると考えられる。
(4)第4項 22条の2第4項は、「収益の額」について、「その販売若しくは譲渡をした資産の引渡し時における価額又はその提供した役務につき通常得べき対価の額」に相当する金額となると定めており、資産の販売等の「収益の額」をどのような金額とするのかということに関する原則を定めたものと説明されている。
この22条の2第4項については、「値引きや割戻しについては、譲渡資産等の時価をより正確に反映させるための調整と位置づけることができる」(国税庁「「収益認識に関する会計基準」への対応について」9頁)とされており、法人税基本通達2-1-1の11(変動対価)が新たに設けられ、「ケース3 割戻を見込む販売(論点:変動対価)」(国税庁「収益認識基準による場合の取扱いの例」3頁)においても販売時に割戻しに対応する金額を後の事業年度で売上に計上する処理例が示されている。
つまり、22条の2第4項により、資産の販売等の後に値引きや割戻しがあるものについては、資産の販売等の時の益金算入額を従前よりも少なくすることができることとなる。
このため、この22条の2第4項に関しても、値引きや割戻しなどがある場合には、積極的に利用することを検討するべきである(注)。
(注)22条の2第4項の条文をどのように読んでも、値引きや割戻しなどがある場合にその値引きや割戻しの部分の「収益の額」を後の事業年度に繰り延べてよいと解釈することは困難であるため、法律の条文の正しい解釈という観点からすれば、上記の法人税基本通達2-1-1の11のような解釈には疑問があると言わざるを得ないわけであるが、国税当局が「収益の額」の一部を後の事業年度に繰り延べてよいと解釈しているのであれば、納税者としては、そのメリットを積極的に享受することでよいものと考えられる。
ただし、この22条の2第4項に関しては、その内容に疑問があるため、注意が必要である。
22条の2第4項においては、役務の提供に係る「収益の額」とすべき資産の「時価」に関しては、「通常得べき対価の額」(注)に相当する金額としており、これが提供した役務の「時価」となることに異論はないはずであるが、資産の販売又は譲渡に係る「収益の額」とすべき資産の「時価」に関して、「資産の引渡し時における価額」としていることについては、誤りと言う他ない。
(注)資産の販売又は譲渡に係る「収益の額」とすべき資産の「時価」に関して、時点を示して「資産の引渡し時における価額」と規定するのであれば、本来は、役務の提供に係る「収益の額」とすべき役務の「時価」に関しても、同様に、時点を示して規定するべきである。
勿論、その反対に、役務の提供に係る「収益の額」とすべき役務の「時価」に合わせて資産の販売又は譲渡に係る「収益の額」とすべき資産の「時価」を定めるという方法もあるわけであるが、いずれにしても、法令作成の常識からすると、「又は」という用語を用いて並べた一方「時価」の規定の仕方と他方の「時価」の規定の仕方とが違っていることに関しては、適当ではない、と言わざるを得ない。
資産の販売又は譲渡の取引は、基本的には、当事者が取引価格を含む取引条件に合意することによって成立し、その成立した取引の実行行為として、「資産の引渡し」が行われることとなるため、通常、当事者が取引価格に合意した時点では、「資産の引渡し」までは行われておらず、「資産の引渡し」は、当事者が取引価格に合意した時点よりも後の時点で行われることとなる。このため、資産の販売又は譲渡の取引における「時価」は、「約定時(取引が成立した時)」の「時価」となっており、「資産の引渡し時」の「時価」とはなっていない。
要するに、資産の販売又は譲渡に係る「収益の額」とすべき資産の「時価」について、「資産の引渡し時における価額」を原則とするということに関しては、誤りと言わざるを得ないわけである。
仮に、資産の販売又は譲渡に係る「収益の額」とすべき資産の「時価」を「資産の引渡し時における価額」としなければならないということになると、ほぼ全ての法人が大量の取引について、膨大な申告調整を行わなければならないという事態となってしまう。
実務においては、従前どおり、「約定時(取引が成立した時)」の「時価」に基づいて「収益の額」を認識することでよいものと考えられるが(注)、当分の間は、国税当局の対応を注視しておく必要があるものと考えられる。
(注)「約定時(取引が成立した時)」の「時価」又は「通常得べき対価の額」によって「収益の額」を認識するということであれば、誰もが既に分かっていることであって、わざわざ法律の条文を創る必要はない。
(5)第5項 22条の2第5項においては、「前項の引渡しの時における価額又は通常得べき対価の額」について、貸倒れや買戻しの可能性がある場合においても、その可能性がないものとした場合における価額とする、とされている。
この22条の2第5項に関しても、前項と同じく、その内容に疑問がある。
「資産の販売等」が金銭の貸付けとなっている場合について考えてみると、その貸付けが第三者間取引であれば、当然、債務者の貸倒れの可能性等を約定金利に反映させることとなるわけであって、貸倒れの可能性がある場合とない場合とで取引価格が異なるのは、当然のことである。仮に、金銭の貸付けにおいて、「その可能性〔1号の「金銭債権の貸倒れ」の可能性〕がないものとした場合における価額」を「時価」として「収益の額」を認識しなければならないということであれば、金銭の貸付けの当事者である法人の殆ど全てに寄附金と受贈益が発生するというような事態になってしまう。
また、この22条の2第5項による取扱いに関しては、次の「ケース4 返品権付き販売(論点:変動対価)」(国税庁「収益認識基準による場合の取扱いの例」4頁)に具体的な処理例が示されているため、この処理例で確認してみよう。
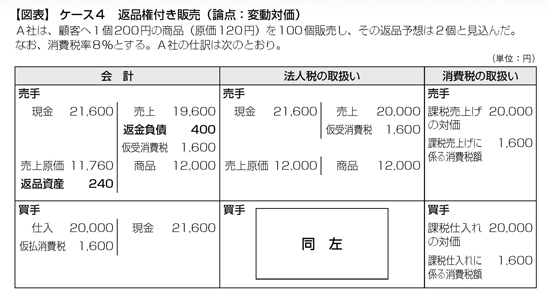
このケースは、22条の2第5項2号に該当するものであり、企業会計上、「売上」が「19,600」とされるとしても、税法上、「売上」は、同項の「その可能性〔2号の「資産の買戻し」の可能性〕がないものとした場合における価額」である「20,000」となる、とされているわけである。
しかし、このケースを雑誌の販売など返品が多いものを例にして考えてみると、「20,000」という金額は、資産の買戻しがないものとした場合における価額ではなく、資産の買戻しがあるものとした場合における価額となっていることが容易に分かるはずである。このケースでは、返品予想が2個のみであるが、それがあるが故に、取引価格が返品のない場合の取引価格よりも少し高い「20,000」とされているわけである。
要するに、22条の2第5項は、「金銭債権の貸倒れ」や「資産の買戻し」があるということであれば、当然、「時価」はそれらの可能性があるものとした場合における価額でなければならないところ、その反対のことを書いているわけである。
22条の2第5項がなければ、誰もが、「金銭債権の貸倒れ」や「資産の買戻し」があるということであれば「時価」はそれらの可能性があるものとした場合における価額であると認識するはずであり、同項は、本来、設けてはならない内容の規定を設けた、という状態になっているわけである。
(6)第6項 22条の2第6項においては、「無償による資産の譲渡に係る収益の額」は「金銭以外の資産による利益又は剰余金の分配及び残余財産の分配又は引渡しその他これらに類する行為としての資産の譲渡に係る収益の額」を「含むものとする」と定められている。
この22条の2第6項に関しては、「明確化」と説明されているわけであるが、後のⅢ6において、『平成30年度 税制改正の解説』における説明を引用しながら、「明確化」をする必要はなく、22条における「取引」の理解を誤ったために同項が設けられることとなったものである、ということを具体的に説明することとする。
(第4回(本誌2018.9.3号掲載予定)に続く)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.