解説記事2024年04月15日 巻頭特集 行為計算否認を中心とした東京国税局における調査の最新トレンド(2024年4月15日号・№1023)
巻頭特集
対談
行為計算否認を中心とした東京国税局における調査の最新トレンド
北海道大学大学院法学研究科 教授 佐藤修二(元弁護士・元国税審判官)
島田法律事務所 弁護士 井村 旭(元東京国税局 国際調査審理官)
令和4事務年度において行われた法人税・消費税に係る実地税務調査の件数は前事務年度比152.3%となっており、追徴税額も近年の最高額を記録している。これは、税務調査への新型コロナウイルス感染症の影響が解消されたことを示しており、納税者や納税者をサポートする専門家は、再び活発化する税務調査に対峙していく必要がある。
本対談では、元国税審判官の北海道大学大学院法学研究科・佐藤修二教授をリード役として、東京国税局で国際調査審理官を務めた経験を持つ島田法律事務所の井村旭弁護士に、質量ともに全国の国税局をリードする東京国税局の調査体制等について解説していただいた上で、東京国税局の調査の最新トレンドや調査において納税者が意識をすべき視点について語っていただいた。
税収の増加に伴い存在感を増している消費税への調査に加え、近年、毎年のように新たな裁決事例が出されるなど、税務当局としての注力事案であることが伺えるのが、行為計算否認規定(法人税法132条~132条の3)を使用した課税事案だ。本対談では、ヤフー・IDCF事件、TPR事件、PGM事件など、これまで注目を集めた裁判例、裁決例を総ざらいしながら、合併の適格性を「事業の継続性」の観点から判断するTPR事件の判断枠組みに対する批判的な見解を述べる専門家が相次ぐ中、東京国税局や国税不服審判所のスタンスの変化を分析していただく。
このほか、ユニバーサルミュージック事件の最高裁判決で注目された法人税法132条、最近初の適用事案が登場した法人税法132条の3についても取り上げる。
1. 東京国税局の最新動向−任期付職員の役割・組織の概要・調査のトレンドなど
はじめに
佐藤:今回は、島田法律事務所の井村旭先生にお話を伺います。井村先生は、2021年7月から2023年の7月まで、いわゆる任期付公務員として、東京国税局で勤務されていました。まずは、東京国税局における任期付職員制度の概要と、井村先生が応募された経緯、所属の部署や役職などをお聞きできますでしょうか。
井村:ご紹介いただきありがとうございます。東京国税局においては、任期付職員として、主に、法務専門家、会計専門家、金融専門家という三つのポジションが募集されており、私が務めていた法務専門家は弁護士資格を有する者が、会計専門家は公認会計士資格を有する者が、金融専門家は金融機関での勤務経験を有する者が、それぞれ募集対象となっています。採用後、法務専門家は、調査第一部調査審理課にて国際調査審理官として、会計専門家及び金融専門家は、調査第一部国際調査課にて国際税務専門官として、それぞれプロパー国税職員の方々とともに仕事をすることになります。
私が応募した経緯については、様々な要因があるのですが、法人・個人問わず、誰しもが必ず関心があると思われる税金について、規制当局である税務当局がどのような考え方をして活動しているのかを知ることは、時に規制当局と対峙する弁護士にとって有益な経験になると考えたからです。
法務専門家の主な業務は、①調査部所管の大規模内国法人及び外国法人の課税事案に関する法務面からの支援、②調査部所管の大規模内国法人及び外国法人の調査、③民法・会社法等に関する職員研修の講師とされています。具体的には、①については、東京国税局の調査第一部から第四部までの各調査部門が行っている税務調査において問題となる企業取引の法律関係の分析、当該分析を前提とした課税要件の充足の検討が主な業務内容になりますが、複雑性・困難性が高いことが見込まれる事案については、税務調査を行う以前に、事案選定や調査のポイントを整理する調査企画が行われることになりますので、当該調査企画についてもアドバイスを行うことになります。また、税務調査の段階から納税者からの不服申立てが見込まれる事案については、納税者と税務当局の主張を対照表の形にした争点整理表をもとに行う調査審理課内の事案検討会に参加して意見を述べたり、税務調査以前に納税者から出された質疑に関する調査審理課内の検討会にも参加して意見を述べたりしていました。②については、調査審理課では、納税者による不服申立て手段としての再調査の請求の対応を行う職員もいるのですが、当該対応の一環として、再調査請求人たる納税者の下への臨場に同行することもありました。また、これに関連して、国税不服審判所における審査請求事案についても、原処分庁側の書面作成に関与しておりました。最後に、③については、税務当局には、法務専門家のように民法、会社法等の私法を専門とする職員の方は、検察庁からの出向者を除いては、基本的にいらっしゃいませんので、東京国税局を含む全国の国税局、沖縄国税事務所、及び税務大学校において、私法の専門家の立場から様々な内容の研修の講師を行うということもありました。これらの研修によって、全国の国税職員の皆様と繋がりが生まれますので、事案に関する相談というのは、東京国税局の所管法人に関するものに限らず、東京国税局管内の税務署や全国の国税局の所管する納税者に関するものにも及ぶことがありました。
なお、会計専門家については、会計基準やバリュエーションに関する専門的知識を生かして、金融専門家については、金融商品に関する実務的知識を生かして、調査部における税務調査を支援しており、事案によっては、各専門家が連携をして支援を行うということもありました。
佐藤:ありがとうございます。私自身は、東京国税不服審判所で任期付職員として審判官をしていました。審判官の仕事は、不服申立事案の調査・審理で、興味深い仕事ですが、東京国税局の任期付職員も、かなり色々な業務を担当すると聞いたことがあり、面白そうだなと思っていました。実際、かなり色々な仕事があることが良く分かりました。
東京国税局の組織の概要等
佐藤:それでは次に、東京国税局の中で、大規模法人の調査を担当する調査部の組織の概要をお伺いできますでしょうか。特に、井村先生が関係されたであろう調査審理課、国際セクション、特官室や各調査部門を中心に、可能な範囲でざっくばらんな実情も含めて、伺えればと思います。
井村:図表1をご覧ください。先ほどお話させていただきましたように、東京国税局の調査部は、調査第一部から第四部までに分かれており、第二部から第四部については、その内部において業種毎の区分に従って約10名程度の単位のグループ(このグループは「調査第〇部門」と呼ばれます。)が作られ、各グループについて担当する法人が割り当てられています。他方で、第一部においては、特別国税調査官と呼ばれるチームが存在し、これが通称「特官室」と呼ばれるわけですが、上場企業を中心とした日本を代表するような企業については、特官室所掌法人として、特官室の中の各グループが、それぞれ担当をすることになっています(こちらのグループは、アルファベットと数字の組み合わせで「A−1班」、「B−2班」等と呼ばれます)。また、第一部には国際調査課を始めとする国際部門と呼ばれる部署が存在し、これらの部署では、移転価格税制に関する事案等を専門的に取り扱っています。私が所属していた調査審理課も、調査第一部に属していますが、調査審理課の仕事の対象となるのは、特官室所掌法人や国際税務には限られず、調査第二部から第四部にて所管している法人についても対象となります。
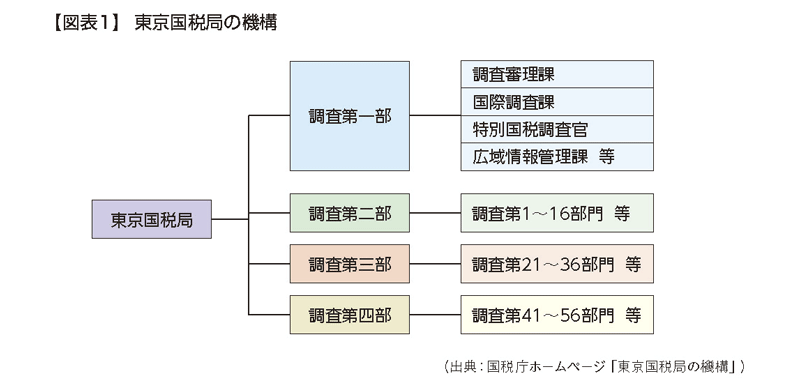
調査審理課は、その名前のとおり、調査を審理する部署でして、例えば、課税処分によって、一定金額以上の増差所得が見込まれる事案や不服申立の見込まれる事案について、証拠に照らし課税要件を充足しているか等について審理を行うことになります。また納税者が東京国税局に対して行う質疑のうち、一定数は各部門の審理担当者において回答がなされるのですが、複雑な事案を前提にするものや統一的な処理が求められるものについては、調査審理課において回答の検討が行われることになります。さらに、繰り返しにはなりますが、調査審理課では、再調査の請求における再調査審理庁、審査請求における原処分庁の役割を果たす機能もありますので、これらの対応も行われており、調査以前から調査、不服段階まで、東京国税局の頭脳というような重要な位置づけにあると感じています。これを、一般企業で例えるならば、調査部は数字目標を持った営業部であり、調査審理課は営業部の業務の適法性を担保する法務部といったイメージになるかと思います。
佐藤:どうもありがとうございます。東京の審判所には、東京国税局の調査審理課から出向でいらっしゃる方があり、また、上記ご説明にあるとおり、審査請求の国税側の当事者でもあり、接する機会が多くありました。正に「税務のプロ」という感じの方々ですね。調査審理課で働かれていた際には、税務調査を税務当局の立場から見ていたということになると思いますが、そのような経験を踏まえ、税務調査において納税者が意識をすべき視点等を伺えればと思います。
井村:東京国税局内の調査審理課の位置付けを踏まえると、東京国税局調査部による税務調査については、調査審理課を意識した対応を行うことが重要かと思われます。先ほどお話したように、調査審理課には、調査の内容を審理し、課税処分を行うか否かの判断を行う権限がありますので、調査審理課をして、課税処分が困難であるという心証を抱かせることができれば、不服申立手続に至ることなく、課税処分を回避するということも期待できます。そうしますと、税務調査においては、目の前にいる調査官を説得することに捉われるのではなく、その背後にいる調査審理課職員に、納税者の見解を伝えることを意識することが重要と考えています。
したがいまして、納税者の見解が調査審理課職員に正確に伝わるよう納税者の見解については、書面の形で伝えることが望ましいですし、当該書面の作成にあたっては、国税局内部で作成される争点整理表の構成を念頭に、法的三段論法を意識することが必要と思われます。
東京国税局の調査のトレンド
佐藤:最近の東京局の調査のトレンドなどをお伺いできればと思います。具体的なテーマとしては、どのようなものが増えているでしょうか。
井村:個別のトレンドのお話に入る前に、直近の税務調査の動向を図表2で確認したいと思います。こちらは、国税庁のホームページにおいて公表されています「令和4事務年度 法人税等の調査事績の概要」(脚注1)から引用したものになりますが、令和4事務年度(令和4年7月から令和5年6月まで)において行われた法人税・消費税に係る実地の税務調査は、6万2千件であり、前事務年度比で152.3%となっています。また、申告漏れ所得金額及び追徴税額についても増加し、特に追徴税額については近年の最高値である3,225億円となっていますので、税務調査への新型コロナウイルス感染症の影響というのは、解消されたと評価して良いでしょう。
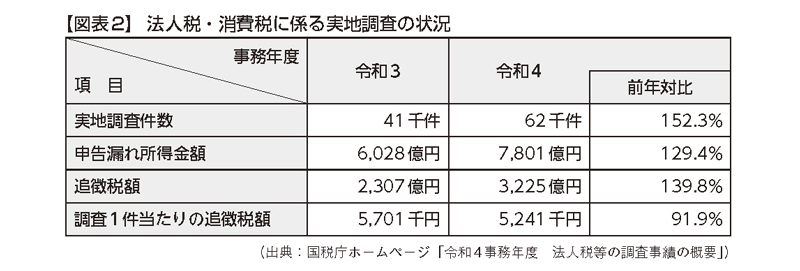
こちらの資料では、「主要な取組」として、税務当局の調査における取組が紹介されておりまして、ここからも調査のトレンドを垣間見ることができます。この「主要な取組」では、冒頭において「消費税還付申告法人に対する取組」が紹介されており、その例として輸出物品販売場制度を悪用した免税売上仮装事案が挙げられていますが、このような悪質事例はもちろんのことながら、一般の納税者に対する税務調査においても、消費税に関する調査の存在感というのは高まっている印象があります。これは、消費税が国の税収で最も収入額が大きい税目となっていることや、令和3事務年度に各税務署に「消費税専門官」を、令和4事務年度には東京国税局に「消費税不正還付対策本部」をそれぞれ設置していること等、消費税調査を専門に担当する部署の体制が強化されていることからも明らかと言えます(脚注2)。最近では、法人税については課税処分を諦めるが、消費税については引き続き課税処分を検討するといった事案の存在を耳にしたこともあり、インボイス制度を含め、今後は消費税に関する対応の重要性がより高まってくると感じています。
また、日々の税務調査というレベルで見ると、期ズレの問題というのは頻出論点であるという印象があります。金額的に軽微なものであれば、さほど問題はないですが、会社の主力ビジネス(例えば、システム開発ビジネス等)に係る益金や損金の計上時期については、当該ビジネス全体への波及効果も踏まえると、金額的な影響が重大なものになる可能性がありますので、注意が必要です。税務調査で指摘される期ズレの問題は、ほぼ例外なく「益は早く損は遅く」の公式に則ることになりますので、時に企業は「企業会計上の保守主義原則」とは反対の要請からの検討を強いられることに留意いただきたいと思います。
そして、これは近時において継続したトレンドであると認識していますが、行為計算否認規定(法人税法132条~132条の3)を用いる課税事案というのは、後に触れますように、近時、毎年のように新たな裁決事例が出されていることからも、税務当局としての注力事案であることが伺えますので、納税者としては引き続き注意すべき論点であると感じております。
2. 行為計算否認の動向−法人税法132条の2を中心に
法人税法132条の2の判断枠組み
佐藤:ここからは、上記ご説明でも最近の重要トピックとして出て来た、行為計算否認について、最近否認事案が増えて関心の高い法人税法132条の2を中心に、東京国税局の状況を伺ってまいります。まずは、リーディングケースであるヤフー事件・IDCF事件(脚注3)について、井村先生にまとめていただきたいと思いますが、事案の概要等を見る前に、まずはヤフー事件・IDCF事件で最高裁が示した法人税法132条の2の判断枠組みについて整理いただきたいと思います。
井村:本件では、法人税法132条の2により否認される法人の行為は、更正又は決定を受ける法人の行為に限定されるのかという、「その法人の行為又は計算」という文言の解釈も争点となっており、この点については、更正又は決定を受ける法人の行為又は計算に限定されないとの判断が示されていますが、今回は、法人税法132条の2の「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」(不当性要件)の解釈に絞って、ご紹介したいと思います。
まず、法人税法132条の2の不当性要件の解釈について、最高裁は、以下のとおり判示しております(下線は話者)。
同条にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは、法人の行為又は計算が組織再編成に関する税制(以下「組織再編税制」という。)に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものであることをいうと解すべきであり、
その濫用の有無の判断に当たっては、①当該法人の行為又は計算が、通常は想定されない組織再編成の手順や方法に基づいたり、実態とは乖離した形式を作出したりするなど、不自然なものであるかどうか、②税負担の減少以外にそのような行為又は計算を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮した上で、
当該行為又は計算が、組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって、組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるもの又は免れるものと認められるか否かという観点から判断するのが相当である。
この判断枠組みは、一読するだけではなかなか理解することが難しいのですが、上記の引用では、あえて3つの段落に分けて記載をしておりまして、このような3つのブロックに分けて読むと理解が進むと感じております。
すなわち、最高裁は、第一段落において、法人税法132条の2の不当性要件は、制度濫用要件であるという法解釈の結論を示しています。そして、その制度濫用要件は、第三段落において示されているように、主観面としての「組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図」(租税回避の意図)と、客観面としての「組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様」という2つの観点から判断されることになりますが、その判断に際しては、第二段落で示された①「当該法人の行為又は計算が……不自然なものであるかどうか」、及び②「そのような行為又は計算を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか」等の事情を考慮する旨が述べられております。
この点、ヤフー事件の調査官解説(脚注4)によれば、これらの考慮事情は、「単なる考慮事情にとどまるものではなく、実質的には、法132条の2の不当性要件該当性を肯定するために必要な要素である」と述べられていますので、不当性要件の該当性判断にあたり、考慮することが必須の事情と位置付けられており、また、これらの考慮事情について、「法人の行為・計算が不自然であり、かつ、そのような行為・計算を行うことの合理的な理由となる事業目的等が存在しない場合には、上記の租税回避の意図の存在を推認し得るのが通常であると解されよう」と述べられていることからすると、上記2つの考慮事情は、制度濫用要件の客観面の判断よりも、その主観面である租税回避の意図の判断において重視されるものであり、租税回避の意図を事実上推定させる事情を、最高裁が示したと考えられます。これらの整理を図式化したものが図表3になります。
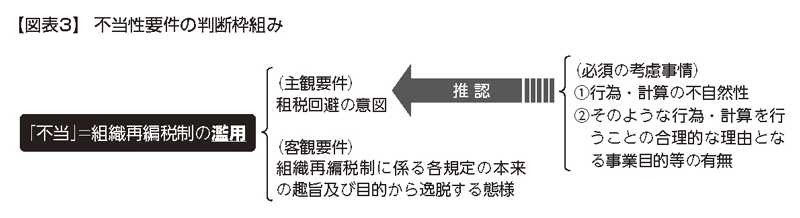
そうしますと、不当性要件の充足の検討に際しては、特に、上記①②の考慮事情の当てはめの重要性が高いと言えますので、過去に法人税法132条の2の適用が問題となった事案において、裁判所や国税不服審判所が、いかなる事実関係を2つの考慮事情の当てはめに用いているのかを理解しておくことが、納税者として法人税法132条の2の適用可能性を検討する際にも役立つ視点になると思われます。
佐藤:ご説明をありがとうございました。重要な点として挙げていただいた①「当該法人の行為又は計算が……不自然なものであるかどうか」、及び②「そのような行為又は計算を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか」が、実質的には要件に近いという点については、私自身、最高裁判決が出た直後に似たようなことを書いており(脚注5)、それが調査官解説にも引用されました。また、余談になりますが、ヤフー事件については、最高裁判決が出る前の段階で、下級審判決の示した基準に批判も多くあったことから、最高裁による明示的な判断を期待するといった会話を、座談会の中で中里実先生と私とでしたことがありました(脚注6)。調査官解説では、その部分が引用されており、嬉しく思ったことを覚えています。
ヤフー事件・IDCF事件
佐藤:では次に、ヤフー事件・IDCF事件について、前提となる事案の概要と、実際の不当性要件の当てはめについてご説明いただけますでしょうか。
【事案の概要】
井村:まず事案の概要についてですが、図表4をご覧ください。①ヤフー株式会社(以下「ヤフー」といいます。)は、平成20年11月21日、その筆頭株主であるソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」といいます。)から、ソフトバンクの完全子会社であるソフトバンクIDCソリューションズ株式会社(以下「IDCS」といいます。なお、IDCSは、当時、多額の未処理欠損金を有していました。)を買収すること等に関する提案(以下「本件提案」といいます。)を書面により受け、当該提案書に記載されたとおりの組織再編成が実行されることになります。
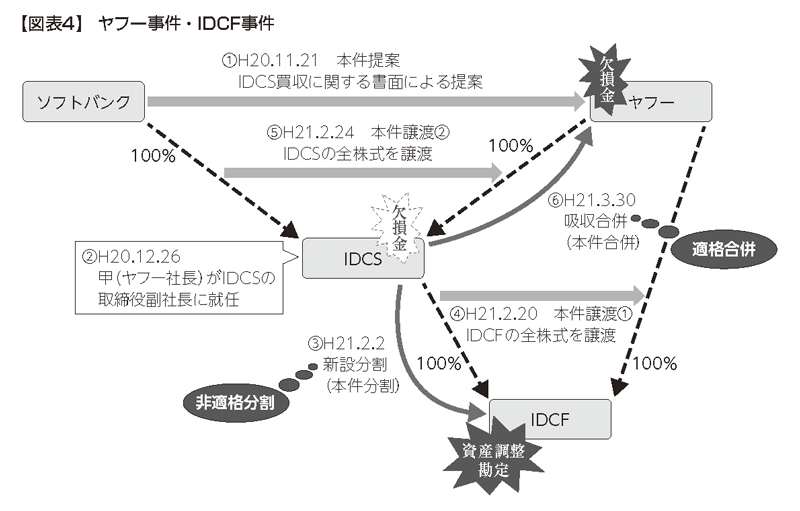
具体的には、②ヤフーの代表取締役社長であった甲が、平成20年12月26日、IDCSの取締役副社長に就任し、③IDCSは、平成21年2月2日、新設分割(本事案との関係において、以下「本件分割」といいます。)により、株式会社IDCフロンティア(以下「IDCF」といいます。)を設立し、④IDCFの全株式は、平成21年2月20日、IDCSからヤフーに譲渡(以下「本件譲渡①」といいます。)されます。
続いて、⑤ソフトバンクは、平成21年2月24日、ヤフーに対してIDCSの全株式を譲渡(以下「本件譲渡②」といいます。)し、最終的には⑥IDCSを被合併法人、ヤフーを合併法人として、平成21年3月30日に、完全支配関係のある当事者間での適格合併(本事案との関係において、以下「本件合併」といいます。)が行われます。
【争点】
井村:以上の事案を前提として、(i)ヤフー事件では、ヤフーが、本件合併につき、甲がIDCSの副社長に就任していたことにより、特定役員引継要件(法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)112条7項5号)が充足されるとして、IDCSの未処理欠損金約543億円をヤフーの損金とみなして損金算入したことに関し、甲の副社長就任行為が不当性要件を充足するか否か、(ii)IDCF事件では、本件分割は、本件譲渡①が計画されていたことにより、適格分割の要件である完全支配継続見込み要件(法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)第4条の2第6項1号)を欠く状態となり、非適格分割とされ、その結果、IDCSに譲渡益約100億円が、IDCFに譲渡損に対応する資産調整勘定約100億円が、それぞれ発生し、IDCFはこの資産調整勘定の一部を償却して損金算入したことに関し、本件譲渡①を予定して行われた本件分割が不当性要件を充足するか否か、がそれぞれ争われました。
【裁判所の判断(ヤフー事件)】
井村:ヤフー事件について、不当性要件における必須の考慮事情に関する当てはめを表の形でまとめると下表のとおりです。
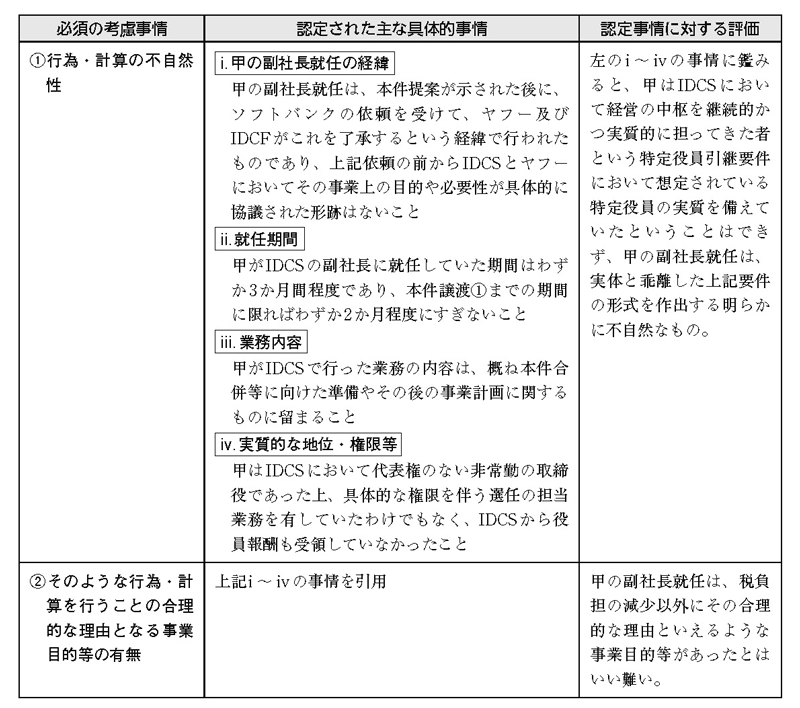
下表のような必須の考慮要素の当てはめを経て、最高裁は、「本件副社長就任は、組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって、適格合併における未処理欠損金額の引継ぎを定める法57条2項、みなし共同事業要件に該当しない適格合併につき同項の例外を定める同条3項及び特定役員引継要件を定める施行令112条7項5号の本来の趣旨及び目的を逸脱する態様でその適用を受けるもの又は免れるものと認められるというべきである」(下線は話者)と、制度濫用要件の主観面と客観面の充足を認め、不当性要件が充足されると結論付けました。
【裁判所の判断(IDCF事件)】
井村:次に、IDCF事件について、不当性要件における必須の考慮事情に関する当てはめを表の形でまとめると次表のとおりです。
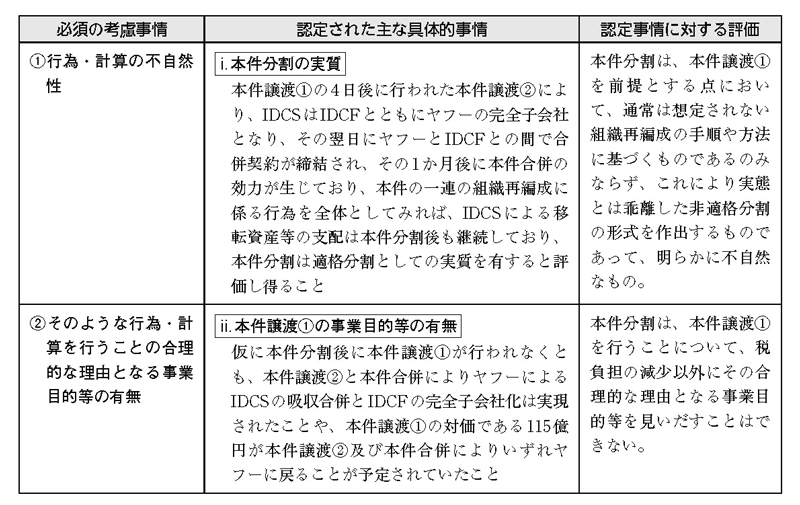
次表のような必須の考慮要素の当てはめを経て、最高裁は、本件譲渡①を行う「計画を前提とする本件分割は、組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって、適格分割の要件を定める法2条12号の11イ及び施行令4条の2第6項1号、適格分社型分割につき譲渡損益の計上の繰延べを定める法62条の3並びに資産調整勘定の金額の損金算入等について定める法62条の8の本来の趣旨及び目的を逸脱する態様でその適用を受けるもの又は免れるものと認められるというべきである」(下線は話者)と、制度濫用要件の主観面と客観面の充足を認め、不当性要件が充足されると結論付けました。
【ヤフー事件・IDCF事件の共通点】
井村:なお、ヤフー事件では、(i)本件の一連の組織再編成に係る行為は、IDCSが有していた未処理欠損金の活用を意図して、ごく短期間のうちに計画的に実行されたものであること、及び、(ii)甲の副社長就任は、特定役員引継要件を満たすことを意図して行われたものであることから、IDCF事件では、上記(i)の事情、及び、(iii)本件譲渡①は、本件分割が適格分割の要件である完全支配継続見込み要件を満たさないことになることを意図して行われたものであることから、いずれの事件についても、必須の2つの考慮事情から強いて推認するまでもなく、本件の一連の組織再編成に係る行為が、組織再編成を利用した租税回避スキームとして計画された行為であり、制度濫用要件の主観面である租税回避の意図が認められることが明らかな事案であると、調査官解説において評価されていますが、それにもかかわらず、最高裁は、先ほど整理をしたように2つの考慮事情について丁寧に認定・評価を行っているのであって、この点からも、2つの考慮事情を最高裁が重視していることが伺えると思います。
佐藤:詳細にわたり、どうもありがとうございました。ヤフー事件・IDCF事件も、かなり昔の事案になりつつありますが、やはり出発点として重要ですね。また、判断基準もさることながら、具体的な事案に判断基準がどのように当てはめられたのかも大事だと思います。その点を、かなり詳しく整理していただきました。
TPR事件
佐藤:ヤフー事件・IDCF事件に続く2件目の否認事例は、TPR事件(脚注7)です。実は、この事件は、私自身が訴訟代理人を務めており、守秘義務もありますので基本的にコメントは控え、井村先生にお考えをお聞きすることにしたいと思います。まずは、TPR事件における裁判所の判断についてご説明いただけますか。
【事案の概要】
井村:まず事案の概要についてですが、図表5をご覧ください。①自動車部品等の製造及び販売を主たる目的とするTPR株式会社(以下「TPR」といいます。)は、平成14年2月9日、自動二輪車用アルミホイール製造事業(以下「本件事業」といいます。)を営むテーピアルテック株式会社(以下「旧TAT」といいます。)の発行済株式総数の3分の2を取得した上で、同月13日付けで、旧TATとの間で取引基本契約(以下「旧取引基本契約」といいます。)を締結し、自動二輪車用アルミホイールの製造を旧TATに委託しました。その後、TPRは、平成15年3月18日に、旧TATの発行済株式を追加取得し、同社を完全子会社化しましたが、旧TATは、平成22年2月28日までの事業年度の時点で未処理欠損金約12億円を有することになります。
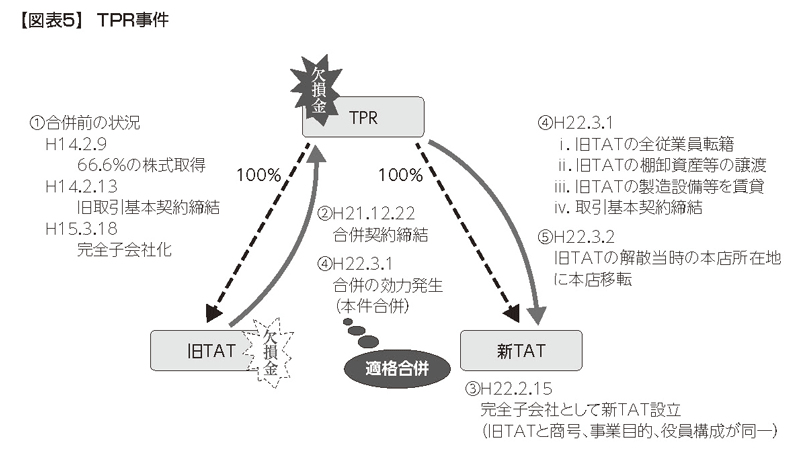
そのような状況下において、TPRは、②平成21年12月22日、旧TATとの間で、平成22年3月1日付けで、旧TATを被合併法人とする合併契約(本事案との関係において、この合併を以下「本件合併」といいます。)を締結するとともに、③平成22年2月15日、旧TATと商号、事業目的及び役員構成を同一とするテーピアルテック株式会社(以下「新TAT」といいます。)を設立しました。その後、④平成22年3月1日に、本件合併の効力が発生し、旧TATの有する欠損金はTPRに引き継がれましたが、同日付けで、TPRは、(i)旧TATの全従業員を新TATに転籍させ、(ii)旧TATの棚卸資産(製品・仕掛品・原材料等)等を新TATに譲渡し、(iii)旧TATの製造設備等を新TATに賃貸し、(iv)新TATとの間で、概ね旧取引基本契約と同内容の取引基本契約を締結しました。そして、⑤新TATは、平成22年3月2日、本店所在地を、旧TATの解散当時の本店所在地に移転しました。
【争点】
井村:以上の事案を前提として、(a)特定資本関係が合併法人の当該合併に係る事業年度開始の日の5年前の日より前に生じている場合に法人税法132条の2を適用することができるか否か、(b)本件合併が不当性要件を充足するか否かが争われました。
【裁判所の判断】
井村:東京高裁は、上記(a)については、法人税法132条の2の適用は排除されないとの判断をした上で、上記(b)について、ヤフー事件・IDCF事件で示された不当性要件の法解釈を前提に判断を行っています。上記(b)の争点について、東京高裁の不当性要件における必須の考慮事情に関する当てはめを、下表にてまとめています。
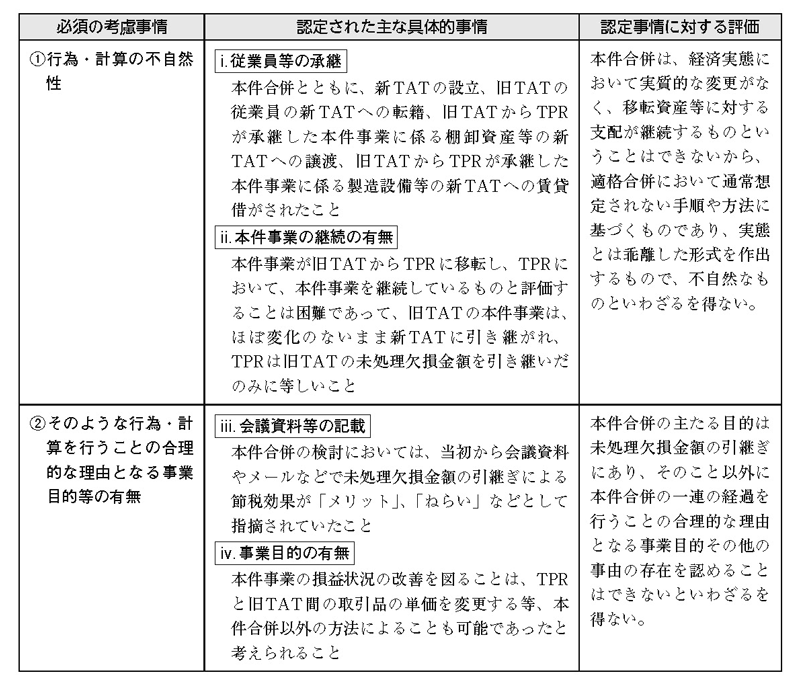
下表のような必須の考慮要素の当てはめを経て、東京高裁は、「本件合併は、租税再編税制に係る法人税法57条2項を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものとして、法人税法132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たる」と、不当性要件が充足されると結論付けました。
佐藤:TPR事件について、租税法学界や実務界からの評価を私も耳にしていますが、井村先生に、客観的にまとめていただけますと幸いです。
井村:TPR事件判決については、東京高裁が、「完全支配関係にある法人間の適格合併……においても、被合併法人から移転した事業が継続することを要するものと解するのが相当である」等と判示したことを巡り、法人税法57条2項が、完全支配関係がある適格合併について、事業の移転や事業の継続を欠損金引継ぎの要件としていないことに反するといった批判をする見解がみられます(脚注8)。
他方で、近時では、東京高裁の判示は、法人税法57条2項に、事業の移転及び事業の継続という明文にない欠損金引継ぎの要件を解釈により上乗せしたと読むべきではなく、「法人税法57条2項の適用について一種の縮小限定解釈を行い、本件の具体的事実関係の下では不自然で正当な事由もないから、本件合併が事業の移転及び継続という実質が備わってない限り、欠損金の引継ぎという恩恵の享受は認められべきではない(原文ママ)、と判断したものと理解すべき」(脚注9)であり、その基本的な構造は、りそな銀行外国税額控除事件最高裁判決(脚注10)と同様と考えられるものとして、東京高裁の上記判示の適用場面を限定しようとする見解も示されているところです。
佐藤:どうも、民間の実務家の評判は良くないようですね。また、学界でも、ニュアンスはいろいろですが、批判的な見解が多いようです(脚注11)。敗軍の将は兵を語らずということもありますので、平川雄士先生が「係属部の裁判長の性向によっても、大幅に判断が左右されるのではないかということも、これまた実務家としての率直な直感としてあります」(脚注12)と述べておられることに触れるにとどめたいと思います。
PGM事件
佐藤:次に、東京国税局が課税処分を行い、現在、東京地裁に係属しているPGM事件(脚注13)について、お伺いできますでしょうか。
【事案の概要】
井村:まず事案の概要(脚注14)についてですが、図表6をご覧ください。①平成21年4月28日、パシフィックゴルフプロパティーズ株式会社(以下「PGP」といいます。)は、大手商社から、ゴルフ場運営会社であるPGPAH6株式会社(以下「PGPAH6」といいます。)の全株式を取得しました。しかし、②PGPAH6では元幹部の横領事件が発生しており、これに基づく債権者からの損害賠償債務等の簿外債務が存在することから、PGPは、PGPAH6からゴルフ場事業(Good事業)だけを分社型分割(物的分割)で切り出し、新設子会社に承継させ、その対価として当該新設子会社の株式(以下「本件株式」といいます。)を取得し、PGPAH6(ゴルフ場事業以外のBad事業)は、簿外債務の管理や債権者対応等のために存続することになりました。その後、③PGPAH6は、グループ会社に、本件株式を全て譲渡し、この株式譲渡によって、PGPAH6には多額の株式譲渡損が生じ、約57億円の欠損金を抱えることになります。
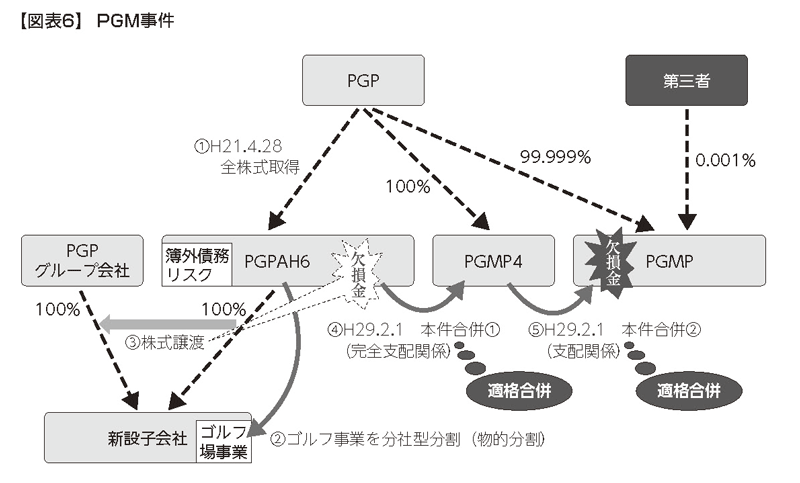
そこから月日は経過し、④平成29年2月1日、PGPAH6は、同じくPGPの完全子会社でゴルフ場を運営するPGMプロパティーズ4株式会社(以下「PGMP4」といいます。)を合併法人、PGPAH6を被合併法人とする適格吸収合併(以下「本件合併①」といいます。)を行い、次いで⑤同日、PGMプロパティーズ株式会社(以下「PGMP」といいます。)を合併法人、PGMP4を被合併法人とする適格吸収合併(以下「本件合併②」といい、本件合併①と総称して、本事案との関係において、以下「本件合併」といいます。)を行い、PGPAH6の有する欠損金はPGMPに引き継がれました。
なお、PGMPの株主には、0.001%の株式を保有する第三者がいたため、PGMPは、PGPの完全子会社ではありませんでした。そのため、本件合併②については、本件合併①とは異なり、完全支配関係のある法人間で行われる合併(法人税法2条12号の8イ)ではなく、支配関係のある法人間で行われる合併(同法2条12号の8ロ)として、従業員引継要件と事業継続要件を充足する形で適格合併とされました。
【争点及び審判所の判断】
井村:以上の事案を前提として、本件合併に係る一連の行為が不当性要件を充足するか否かが争われました。審判所は、この点について、ヤフー事件・IDCF事件で示された不当性要件の法解釈を前提に判断を行い、PGMPの請求を棄却しています。
この裁決については、裁決事例集に登載されておりませんが、裁決要旨が審判所のホームページに掲載されています(脚注15)。そこでは、裁決要旨として、以下のとおりの記載があります(下線は話者)。
事業を営んでいないグループ法人の本件未処理欠損金額を請求人に引き継がせることを目的として合併を2段階に分けた本件合併は、実態とはかい離した形式を作出したものであり、税負担を減少させること以外に合理的な理由となる事業目的その他の事由は認められないことから、本件合併に係る一連の行為は、組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって、組織再編成の本来の趣旨及び目的を逸脱する態様でその適用を受けるものと認められるというべきであり、本件合併により本件未処理欠損金額を、請求人の連結欠損金等の当期控除額として連結所得の金額の計算上、損金の額に算入したことは、組織再編税制に係る規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものとして、法人税法第132条の2に規定する「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たると解するのが相当である。
上記の下線部からも伺えるのですが、審判所は、TPR事件の東京高裁判決の「完全支配関係にある法人間の適格合併……においても、被合併法人から移転した事業が継続することを要するものと解するのが相当である」という判示部分を根拠に、「簿外債務管理や債権者対応のためだけに存続しているPGPAH6のPGMP4による吸収合併の適格性を、「事業の継続性」の観点から否定した」(脚注16)とされ、その判断に際しては、PGPAH6は事業を行っていないとまで判断しているとされています(脚注17)。また、私法上は、本件合併と同じ効果を、PGPAH6とPGMPとの直接の吸収合併でも生じさせることができますが、税務上この場合には、事業継続要件の充足の点で、適格合併として欠損金を引き継げるか疑義が生じるところ、本件合併のように二段階のプロセスを敢えて取ることでこの論点を回避し、欠損金の引継ぎを実現させている点も、「実態とはかい離した形式を作出した」という不当性要件における必須の考慮事情の不自然判断に繋がっていると考えられます。
【審判所の判断に対する評価】
井村:しかしながら、事業の継続性が無いことを根拠に不自然性を肯定するTPR事件東京高裁判決のロジックを他の事案において一般化するのは妥当ではないと思われますし、三社間合併について二段階のプロセスをとることが実務上不自然とも思われません。こういった点を踏まえ、PGM事件裁決についても肯定的な評価は多くないように思われます(脚注18)。
佐藤:どうもありがとうございます。東京国税局も東京の審判所も、国税勝訴事案であるTPR事件の判断枠組みに依拠して判断をしているわけですね。行政の対応としては分からないわけでもありません。その流れを覆せるとすると、やはり裁判所で新しい判断が示されることを期待するしかないのかもしれません。
PGM事件より後の裁決事例
佐藤:ところで、PGM事件以外にも、審判所の裁決事例があるそうですね。それらについても、お伺いできますか。
【令和4年8月19日裁決】
井村:まず、令和4年8月19日裁決(大裁(法・諸)令4第5号)(脚注19)について図表7をご覧ください。本件では、①青果物等の売買等を行う株式会社である請求人の完全子会社であるB社を分割法人、C社を分割承継法人とする新設分割(本事案との関係において、以下「本件分割」といいます。)が行われ、この新設分割によって、B社が保有していたほぼすべての資産、負債、雇用契約その他の権利義務関係が、未処理欠損金額を除き、C社に承継されました。そして、②請求人が、B社を吸収合併(本事案との関係において、以下「本件合併」といいます。)し、同社が有していた未処理欠損金約14億円を引き継ぎました。
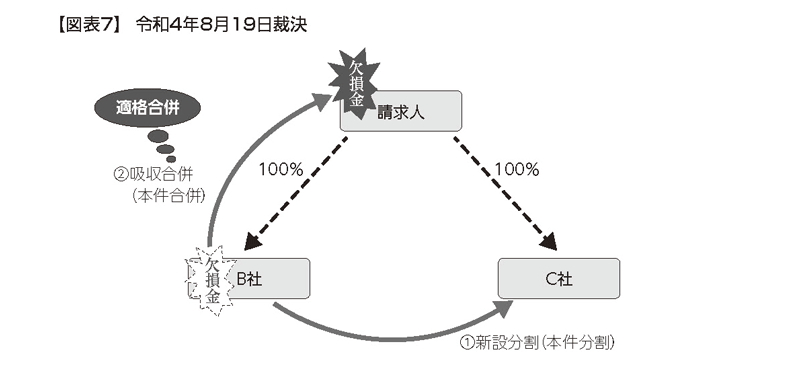
以上の事案を前提として、本件合併及び本件分割(総称して、以下「本件組織再編成」といいます。)が、不当性要件を充足するか否かが争われました。審判所は、この点について、ヤフー事件・IDCF事件で示された不当性要件の法解釈を前提に判断を行い、請求人の請求を棄却しています。
この裁決についても、裁決事例集に登載されておりませんが、審判所のホームページにおいて、裁決要旨として、以下のとおりの記載があります(下線は話者)。
法人税法第57条第2項は、未処理欠損金額の付け替えを主たる目的とする合併が行われた場合においてまで、その引継ぎを認めることを想定したものではないと解されるところ、本件組織再編成によって、旧子会社の未処理欠損金額を旧子会社の事業から分離することは、新旧子会社の事業の収益力が向上するものとは認められず、また、旧子会社の営んでいた事業が、未処理欠損金額等を除いてそのまま新子会社に引き継がれていることなどからすると、本件組織再編成は、未処理欠損金額を旧子会社から請求人に付け替えることを意図したものであり、この意図に基づくものでなければ、これを行う必要のないものであって、通常は想定されない不自然な組織再編成というべきである。したがって、本件組織再編成は、法人税法第57条第2項の本来の趣旨及び目的を逸脱する態様でその適用を受けるものであって、同規定を租税回避の手段として濫用することによって法人税の負担を減少させるものであるから、同法132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当する。
本件についても、TPR事件東京高裁判決の「完全支配関係にある法人間の適格合併……においても、被合併法人から移転した事業が継続することを要するものと解するのが相当である」という判示部分を根拠に、本件合併の適格性を、「事業の継続性」の観点から否定することは可能であったと思われるにもかかわらず、本件の審判所は、このような解釈を取らなかったことが上記の下線部から伺えます。
すなわち、本件において審判所は、「未処理欠損金額の引継ぎの趣旨が、適格合併の場合には、移転資産等に対する支配が継続されていることから、基本的に欠損金額の繰越控除が前提とする各事業年度の間に経理方法に一貫した同一性が継続維持されているとして、合併の前後を通じた事業年度間の所得の金額と欠損金額を平準化することを認めて、従前の課税関係を継続させることにあると解されることからすれば、法人税法57条2項は、例えば、適格合併が企業グループ内の法人の有する未処理欠損金額の企業グループ内の他の法人への付替えと同視できるものである適格合併の場合にまで、未処理欠損金額の引継ぎを認めることを想定した規定ではないと解するのが相当である」(下線は話者)との解釈を前提に、「本件組織再編成は、未処理欠損金額を旧子会社から請求人に付け替えることを意図したもの」と評価したとされ、これが不当性要件の充足の判断に繋がっていると考えられます。
このような審判所の解釈は、TPR事件東京高裁判決の「完全支配関係にある法人間の適格合併……においても、被合併法人から移転した事業が継続することを要するものと解するのが相当である」という判示部分について、各界から否定的な意見が述べられていることを踏まえた可能性があり、現在、本件は大阪地裁に係属しているとのことですので、今後の司法判断が注目されます。
【令和5年3月23日裁決】
井村:もっとも、上記の裁決によって、審判所がTPR事件東京高裁判決の判示と決別をしたかというと、残念ながらそういう状況にはなっておりません。
図表8をご覧ください。令和5年3月23日裁決(東裁(法)令4第101号)(脚注20)は、①酒類、加工食品、農水産食品、冷蔵・冷凍食品、飲料等の製造、販売及び輸出入を業とする法人である請求人が、その完全子会社であるA社を分割法人、同じく請求人の完全子会社であるC社を承継法人として、A社のX事業を吸収分割した上で、②請求人がA社を吸収合併し、また③請求人の完全子会社であるB社についても、B社を分割法人、C社を承継法人として、B社のY事業を吸収分割した上で、④請求人がB社を吸収合併したという事案であり、これらの合併(本事案との関係において、以下「本件合併」といいます。)について、不当性要件を充足するか否かが争われました。審判所は、この点について、ヤフー事件・IDCF事件で示された不当性要件の法解釈を前提に判断を行い、請求人の請求を棄却しています。
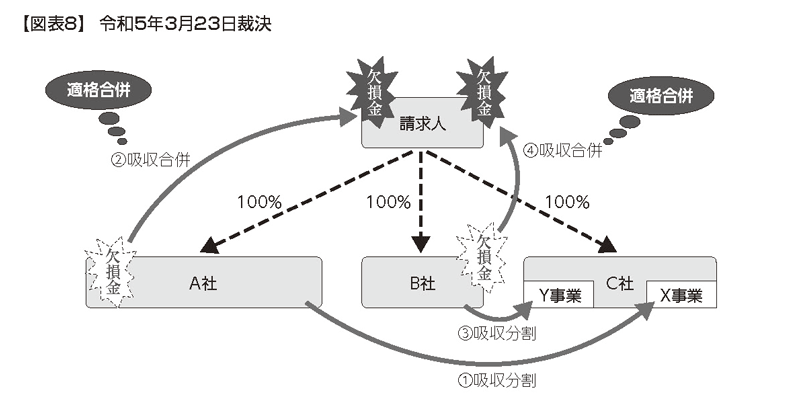
この裁決についても、裁決事例集に登載されておりませんが、審判所のホームページにおいて、裁決要旨として、以下のとおりの記載があります(下線は話者)。
本件合併は、分割により本件子会社が行っていた事業を、請求人以外の法人に移転させ、あえて本件子会社について欠損金額のみを有する法人という形式を作出した上で、本件未処理欠損金額のみを請求人に引き継ぐものであり、①事業の移転先と欠損金の引継先が異なるという適格合併において通常想定されていない組織再編成の手順等に基づく不自然なものであり、②本件未処理欠損金額を引き継ぐことによって請求人の法人税の負担を減少させること以外に本件合併を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由があったとは認められない。したがって、本件合併は、組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって、法人税法第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》第2項の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるものというべきであり、組織再編税制に係る各規定を租税回避の手段として濫用することによって法人税の負担を減少させるものと認められるから、本件未処理欠損金額を請求人の欠損金額とみなして、当該欠損金額に相当する金額を各事業年度の損金の額に算入したことは、法人税法第132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当する。
上記の下線部から、本件の審判所は、合併の適格性を、「事業の継続性」の観点から判断する、TPR事件東京高裁判決が判示する考え方への回帰が伺えるところです。
もっとも、本件の審判所は、「法57条2項の趣旨及び目的から逸脱しているか否かについては、組織再編税制の基本的な考え方……に基づき、事業の移転及び継続を含めて検討することが相当である」(下線は話者)と述べているとされており、事業の移転及び継続は、不当性要件充足の判断における絶対的な要素ではなく、一つの事情に過ぎないかのような表現を取っている点において、TPR事件東京高裁の判示と一定の距離を取っているとの評価もし得るように思われますが、本件も現在は東京地裁に係属しているとのことですので、今後の司法判断が注目されます。
佐藤:PGM事件より後の事例についても紹介いただき、大変勉強になりました。ありがとうございます。
納税者としての留意点
佐藤:それでは、以上の分析を踏まえ、納税者としての留意点についてお伺いできますでしょうか。
井村:税務当局が、法人税法132条の2の適用を積極的に検討している実情を踏まえると、納税者が、組織再編成を用いるスキームを検討する際、法人税法132条の2の適用可能性について検討することは必須であると考えられます。
そして法人税法132条の2の適用において、最も重要な要件となるのが不当性要件ですが、この不当性要件の検討に際しては、①行為・計算の不自然性、及び、②そのような行為・計算を行うことの合理的な理由となる事業目的等の有無という2つの考慮事情が必須の考慮事情とされていることを改めて意識すべきと思われます。すなわち、納税者としては、上記①②の考慮事情のうち、いずれかが充足されないことを、証拠をもって説明することができれば、税務当局から法132条の2を適用されるリスクを回避することができます。
その際に、①行為・計算の不自然性という考慮事情については、「不自然」という概念が曖昧なことに起因して、仮に税務当局から指摘が行われた場合には、その充足の判断についての見解の相違が埋まらない可能性が高いことが予想されるところ、納税者としては、②そのような行為・計算を行うことの合理的な理由となる事業目的等の有無を整理し、記録化することの方がより重要になると考えております。具体的には、同じ目的を達成するためのスキームが複数想定されるような場合においては、当該スキームを選択する理由が、税負担の減少のみではなく、事業上の理由にもあり、主として後者の観点からスキームを選択しているという整理を、外部の専門家等を交えて事前に行い、スキーム選択に際しての意思決定資料として、保存をしておくことが重要と思われます。
また、5年超の完全支配関係が認められる会社間での適格合併による欠損金引継ぎを計画する事案については、TPR事件東京高裁判決が示した「事業の継続」の有無から不当性要件の充足判断を行うという考え方に引き続き注意をする必要があります。実務界及び学界からの評価や近時の裁決例の流れを踏まえると、今後司法の場で、TPR事件東京高裁判決の射程を限定するような解釈が示される可能性はありますが、そのような解釈が司法で確定するまでの間は、税法の執行部隊としての税務当局としては、「事業の継続」が認められない適格合併については、法人税法132条の2の適用が引き続き検討される可能性が高いと思われます。したがって、そのような事例では、事業の継続のない適格合併を行うことの合理的な理由となる事業目的等を、より丁寧に整理しておくことが重要と考えられます。
佐藤:納税者としては、行為計算否認規定で攻めてこられると、なかなか対応しにくいところもありますね。上記のお話は、とても参考になるのではないかと思います。
「引き直し」の問題
佐藤:それから、少しテクニカルな論点ですが、法人税法132条の2における、いわゆる「引き直し」の問題についてお伺いできますでしょうか。
井村:これまでのお話は、法人税法132条の2の適用要件に関するものですが、同条については、その効果面においても、解釈上不明確な点が残されており、それが「引き直し」の問題であると考えております。
この点、ヤフー事件最高裁判決は、「法132条の2は、税負担の公平を維持するため、組織再編成において法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる行為又は計算が行われた場合に、それを正常な行為又は計算に引き直して法人税の更正又は決定を行う権限を税務署長に認めたものと解され」ると述べ(下線は話者)、同条が「引き直し」の規定であることを明言しています。
しかしながら、この「引き直し」が具体的にどのような行為を指すのかについては、未だ不明確であり、税務当局と納税者との間で見解の相違が生じ得るポイントになると感じております。すなわち、納税者としては、「引き直し」とは、問題とされた行為又は計算を、それと同一の結果となるような正常な行為又は計算に引き直すことであると考えるのに対し、税務当局は、これもTPR事件東京高裁判決が判示しているのですが、「引き直し」とは、「当該行為又は計算により不当に減少している税負担の部分を排除するために必要な限度で課税標準等の計算を行えば足りる」のであって、それ以上のことは必要がないとの主張をすることが想定されます。
この点、TPR事件東京高裁判決の上記判示を前提とすると、不当性要件の検討においては合併行為そのものを問題にしていたにもかかわらず、その効果としての引き直しは、欠損金の引継ぎという計算のみを無かったことにすることで足りるということになりますが、要件面の検討において、行為の不当性を検討したのであれば、その効果面においても、行為を含めて引き直しを行うのが、本来の法人税法132条の2の適用のあり方ではないかと思われます。
法人税法132条について
佐藤:最後に、法人税法132条の2以外の条文についても伺いたいと思います。まず、ユニバーサルミュージック事件の最高裁判決(脚注21)で注目された法人税法132条についてはいかがでしょうか。
井村:法人税法132条1項については、ご指摘のユニバーサルミュージック事件において、最高裁が、同項の不当性要件については、「同族会社等の行為又は計算のうち、経済的かつ実質的な見地において不自然、不合理なもの、すなわち経済的合理性を欠くものであって、法人税の負担を減少させる結果となるものをいうと解するのが相当」(下線は話者)として、経済合理性説を採用することを明らかにし、経済的合理性を欠くか否かの判断については「(借入れの目的や融資条件等の)諸事情を総合的に考慮して判断すべき」としました。また、本判決は、「本件借入れには独立かつ対等で相互に特殊関係のない当事者間で通常行われる取引とは異なる点もある」との認定を前提としながらも、「本件借入れが不自然、不合理なものとまではいい難い」と結論付けている点からもわかるように、同族会社等の行為又は計算が独立当事者間の通常の取引と異なっている場合であっても、経済的合理性が否定されない場合があることを明らかにしています。
加えて、本件では、問題とされた借入行為が、「企業グループにおける組織再編成に係る一連の取引の一環として、当該企業グループに属する同族会社等が当該企業グループに属する他の会社等から金銭の借入れを行った場合」に該当することから、当該組織再編成に係る一連の取引が経済的合理性を欠くか否かが、借入目的の合理性の有無を判断するに際して問題となり、組織再編成に係る一連の取引の経済的合理性の判断に際しては、ヤフー事件判決における必須の考慮事情を用いて検討することが合理的かつ有用と考えられたとされています(脚注22)。
この点、納税者としては、問題とされた行為が、ある一連の取引の一環である場合には、当該一連の取引の経済的合理性を主張することで、問題とされた行為の経済的合理性を基礎づけさせる余地が示されたと考えられ、この視点は行為計算否認規定全てに共通し得るものと思われますので、実務上参考になると考えられます。
佐藤:ありがとうございます。ユニバーサルミュージック事件は、132条の2が適用されたヤフー事件とは異なり、132条が適用された事案ですが、東京高裁判決はヤフー事件と同様の判断枠組みを導入し、最高裁も同様の判断を示したことが興味深いですね。これは余談ですが、ヤフー事件の調査官解説を書かれている林史高裁判官がユニバーサルミュージック事件の東京高裁判決に名を連ねておられますので、その影響があったのかもしれません。先ほど、ヤフー事件の調査官解説で中里先生と私の発言に触れていただいたことも述べましたが、実務・学界を通じた人の動きの中で法理が発展していくという面も面白いなと思っています。
法人税法132条の3について
佐藤:次に、132条の3についてはいかがでしょうか。
井村:法人税法132条の3は、令和4年4月1日より前は、連結法人に係る行為又は計算の否認規定であり、同日以後は、通算法人に係る行為又は計算の否認規定となりましたが、改正前から現在まで同条の解釈が問題となった裁判例は存在しません。しかしながら、近時の報道(脚注23)によりますと、連結納税制度を巡り、法人税法132条の3が初めて適用された事案が登場し、当該事案については、現在、国税不服審判所において審査請求が行われているとのことですので、同条に関する議論というのも、今後進展していくことが予想されます。
同条の不当性要件については、法人税法132条の2の不当性要件の解釈を参考に、制度濫用基準を採用するとの立場が有力と思われますが(脚注24)、同法132条の3に固有の問題として、通算法人の単体法人時代の行為については「通算法人」の行為に該当しないため、同条の適用は認められないのではないかという論点があるとされます(脚注25)。
法人税法の条文の建付け上も、単体法人時代の行為については、通算承認の申請却下に係る法人税法64条の9第3項3号ニに規定された不当性要件によって、租税回避行為を防止することが予定されていると考えられ、通算承認がされたにもかかわらず、単体法人時代の行為を不当であるとして法人税法132条の3を適用することは認められないように思われます。
3. まとめ
佐藤:東京国税局の組織・任期付職員の状況、そして注目トピックの行為計算否認と、盛りだくさんのことをお伺いできました。特に、132条の2については、今後、裁判所の判断が相次ぐことになると見込まれ、その前段階である裁決等の動向を知ることができ、私自身も大変勉強になりました。最後に、井村先生からまとめの言葉をお願いできればと思います。
井村:東京国税局は、日本全国の全11の国税局の中でも中心的な役割を果たす組織であるからこそ、税務当局の「伝家の宝刀」と呼ばれる行為計算否認規定についても積極的に用いることが国税組織の内部においても期待されているように感じます。ヤフー事件・IDCF事件以降、行為計算否認規定に関する解釈が少しずつ明確になってきているとは感じるものの、本日ご紹介したように、行為計算否認規定の適用を巡っては、まだまだ解釈が十分に固まっていない点も多くあるように感じ、その議論は複数の税務訴訟において現在進行形で動いているといえます。納税者としては、そのような予測可能性が十分でない中で取引を進めていくことが求められますが、常に最新の議論動向を注視し、時に専門家と連携しながら、歩んでいくことが重要と思われます。
佐藤:どうもありがとうございました。
脚注
1 https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2023/hojin_chosa/pdf/01.pdf
2 この点を含め、近時の消費税争訟に関する動向等については、佐藤修二=安田雄飛「消費税争訟事案の現状と展望」本誌第1010号を参照。
3 本稿では、最判平成28年2月29日民集70巻2号242頁に係る事案を「ヤフー事件」、最判平成28年2月29日民集70巻2号470頁に係る事案を「IDCF事件」という。
4 徳地淳=林史高「判解」最判解民事篇平成28年度84頁。
5 佐藤修二「ヤフー事件・IBM事件の終結を迎えて」NBL1071号68頁。
6 中里実=吉村政穂=長谷川芳孝=佐藤修二「租税訴訟における法務と税務のギャップ(上)」NBL1053号16頁。
7 本稿では、東京高判令和元年12月11日金融・商事判例1595号8頁に係る事案を「TPR事件」という。
8 例えば、片平享介「判批」本誌811号。
9 伊藤剛志「適格合併による未処理欠損金の引継ぎと法人税法132条の2~TPR事件東京高裁判決の合理的解釈の試み~」租税研究2023年12月号132頁。
10 最判平成17年12月19日民集59巻10号2964頁。
11 例えば、渡辺徹也『スタンダード法人税法〔第3版〕』(弘文堂、2023)307~308頁、谷口勢津夫『税法基本判例Ⅰ』(清文社、2023)239頁、吉村政穂「繰越欠損金の引継ぎと組織再編成に係る行為計算否認規定の適用」税務事例研究177号1頁。
12 平川雄士「立法趣旨論再考−最判令3.3.11から近時の法132条の2による否認事例を考える−」租税研究2021年10月号109頁。
13 本稿では、令2年11月2日裁決(東裁(法)令2第30号)に係る事案を「PGM事件」という。
14 PGM事件については裁決事例集に登載されていないため、以下で述べる事案の概要は、伊藤・前掲(注9)135頁~136頁やインターネット上の公表情報等をもとにしている。
15 https://www.kfs.go.jp/cgi-bin/sysrch/prj/web/index.php
16 「新たな132条の2適用事例の全容」本誌第883号。
17 「TPR事件後重要性増す事業継続の当否」本誌第898号。
18 例えば、伊藤・前掲(注9)137頁~138頁。
19 本裁決は、裁決事例集に登載されていないため、以下で述べる事案の概要や裁決の内容については、「法人税法132条の2の適用で一連の組織再編成を否認」本誌第985号の内容等をもとにしている。
20 本裁決は、裁決事例集に登載されていないため、以下で述べる事案の概要や裁決の内容については、「東京局管内でも法人税法132条の2を適用した組織再編成否認事案」本誌第1004号の内容等をもとにしている。
21 最判令和4年4月21日民集76巻4号480頁。
22 大竹敬人「判解」法曹時報2024年1月号308頁。
23 「光通信系、70億円申告漏れ 親子会社で通算 連結納税巡り追徴 国税指摘」日本経済新聞朝刊第14版2024年3月21日、38面。
24 太田洋=伊藤剛志『企業取引と税務否認の実務~税務否認を巡る重要裁判例の分析~〔第2版〕』(大蔵財務協会、2022)52~55頁。
25 太田=伊藤・前掲(注24)48~51頁。
佐藤修二 (さとう しゅうじ)
1997年 東京大学法学部卒業。2000年 弁護士登録。2005年 ハーバード・ロースクール卒業(LL.M.)。2011年~14年 東京国税不服審判所(国税審判官)。2019年~22年 東京大学法科大学院客員教授。2022年 弁護士登録取消し。現在 北海道大学大学院法学研究科教授。
著書に、『対話でわかる租税「法律家」入門』(編著、中央経済社、2024)、『対話でわかる国際租税判例』(共著、中央経済社、2022)、『租税と法の接点』(大蔵財務協会、2020)『事例解説 租税弁護士が教える事業承継の法務と税務』(監修、日本加除出版、2020)など。
井村 旭 (いむら あきら)
2012年 慶應義塾大学法学部法律学科中退(飛び級)、2015年 同大学大学院法務研究科(法科大学院)修了、2016年 弁護士登録。2021年から23年まで東京国税局(調査第一部調査審理課 国際調査審理官)にて勤務し、現在、島田法律事務所に所属。
税務当局対応を含む税務案件、税賠案件、M&A、一般企業法務、争訟等に従事。
近時の著作・講演として、『「益は遅く損は早く」はなぜ見解の相違を生むのか?』(税務弘報2024年2月号)、「顧問先への税務調査、重加算税が問題になった時どうする?」(東京税理士会、2024年)など。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























