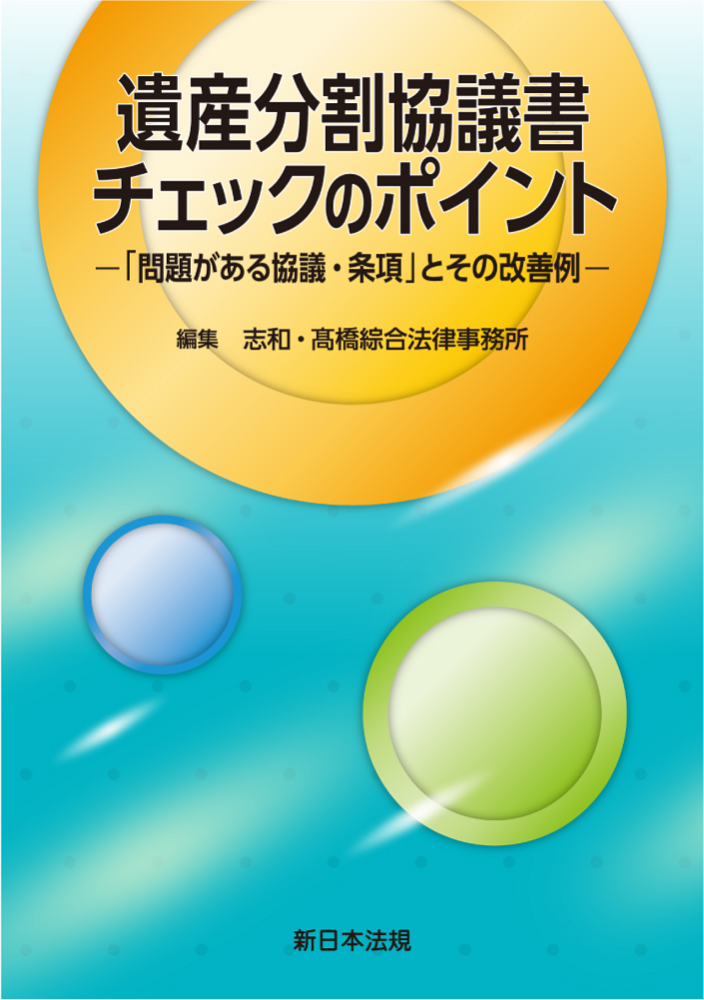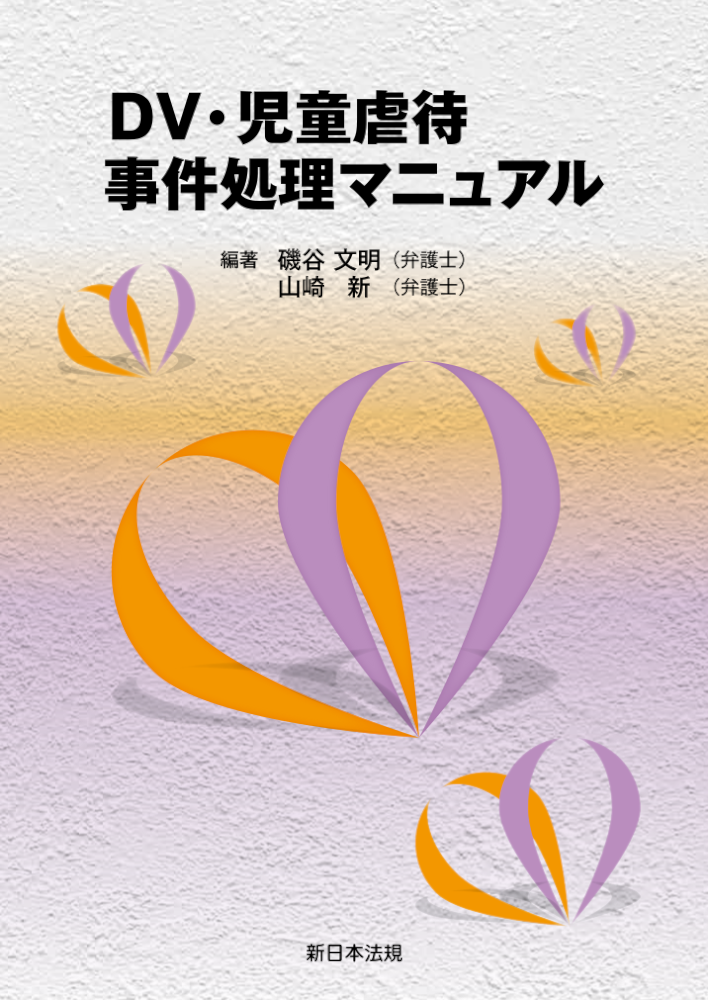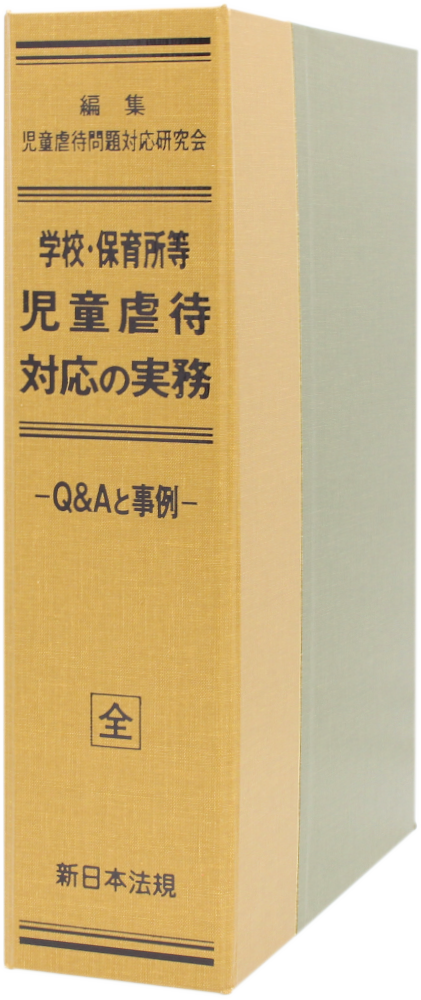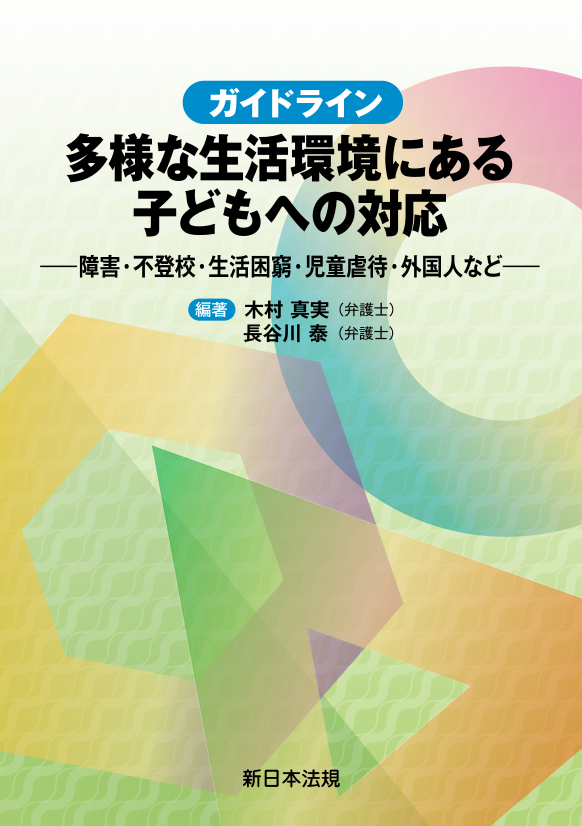行政2025年04月24日 「虐待の連鎖止める」制度の網からこぼれる妊産婦や親子のSOS かつての当事者も寄り添う「コアラのポケット」 【地域再生大賞・受賞団体の今】 提供:共同通信社

虐待されて育った子が親になって不適切な養育を繰り返す―。そんな負の連鎖を止めようと、出産や育児に困窮する親や妊産婦に寄り添うNPO法人が栃木県にある。携わるのは、小児科医や保育士といった専門家、学生や地域の住民、そしてかつて当事者だった人たちだ。
赤ちゃんを守るコアラのポケットのような居場所を運営し、LINE(ライン)での相談、食事や日用物資提供など幅広い事業を展開。行政や医療機関が捉えきれない「SOS」をキャッチし、自治体とも連携している。多くの地域で取り組みが可能なモデルとして、関係者は全国への波及を期待する。(共同通信=市川太雅)
▽実家みたいな場所
栃木県真岡市。住宅や畑地が混じり合うのどかな地域に、その居場所「そらいろポケット」はある。NPO法人「そらいろコアラ」が拠点とする平屋建ての一軒家だ。キッチンや洗面所、こたつの食卓があり、普通の家と変わらない。畳の部屋には玩具や絵本が所狭しと並んでいる。
ここを訪れるのは、幼い子連れの親や、妊娠中の女性たちだ。真岡市に住むパート従業員の伊達理沙さん(36)は定期的に利用する1人。1歳の息子と生後間もない娘を連れ、2時間ほど滞在する。
用意された食事を食べる間、スタッフが2人の子どもを世話する。伊達さんは「ここは実家のような感じ」と安心した表情を見せる。
▽少し助けてもらう
伊達さんは上にもう1人男の子もおり、3人の子育てに追われる。台所で立ったままカップ麺をかき込むこともしばしばだ。自身は幼少期にネグレクト(育児放棄)を受けたという。「ここでゆっくりする時間に本当に助けられている。それがあるから、自分も心に余裕をもって子どもに接することができる」
そらいろコアラのスタッフは利用者の子どもと遊んだり、出産や子育ての相談を受けたりする。スタッフの伊藤美南子さん(39)は「ちょっと助けてもらえる場所、と思ってくれればいい」と説明する。
保育士や社会福祉士などのスタッフもいる。大学生ボランティアや、頼まれたらすぐに駆け付けるという近隣住民が手助けする。
▽かつての自分重ね
スタッフの伊藤さんも、ひとり親家庭で経済的に不自由な子ども時代を過ごした経験を持つ。自身がシングルマザーだった時期もある。
当事者だったからこそ、相談者と同じ目線に立ちやすい。「当時の私と同じ環境にいる子どもや親に、直接手を差し伸べられるのなら」。その思いで、利用者に日々接している。
居場所は1~2組ごとの完全予約制で、毎週10組以上が利用しているという。持ち帰りの食事や日用品を受け取るだけの利用も歓迎。管理栄養士のスタッフが献立を考えている。
▽家でも病院でもなく
そらいろコアラは2020年、共同代表で医療コンサルタントの鳥飼蓬子さん(34)と小児科医の増田卓哉さん(35)の2人が中心となって設立した。
増田さんは勤務医をしながら、団体活動に携わっている。ある時、診察した男子中学生の患者が、家庭に問題を抱えていた。
「家に帰りたくない」と訴えるその子を長期入院させたが、最終的には親元に帰すしかなかった。医療機関が居場所の役割を果たすことは難しい。「診察室の中では不十分。子どもが安心して過ごせる場所が地域の中に必要だ」
▽親には言えない
居場所運営と並んで、そらいろコアラの活動の柱となっているのが、チャットで妊娠・出産や子育ての悩み相談を受ける「コアLINE」だ。毎月50件を超える新規相談があり、半数以上は10~20代からという。
「妊娠したかもしれない」「親には言えない」
24時間・365日送受信できるチャットには、日々SOSが届く。スタッフの伊藤さんをはじめ約20人の相談員でシフトを組んで対応し「妊娠検査薬は数百円で買えるよ」「薬局に行ってみて」などと声をかける。
相談員には助産師や精神保健福祉士、自身も若年出産を経験した看護師もいる。当事者と専門家の知見を踏まえ、最適な寄り添い方を考えるようにしている。
▽出産前から関わる
共同代表の増田さんによると、虐待死のうち多いのは「0日死」、つまり出産してそのまま死なせてしまうケースだという。望まない妊娠や、母親の精神疾患などが背景にあることが多い。
増田さんは定期的に診察していた子の母親から「私、虐待しているんです」と打ち明けられたことがあった。
「信頼関係があれば、問題をキャッチできる」。LINEをきっかけにして、リスクのある母親と出産前から関係を築くことで、虐待を予防できると感じている。
コアLINEの連絡先カードは現在、栃木県庁や多くの自治体の窓口に置かれ、一部の市町では母子手帳の発行と同時に全妊婦に渡している。産婦人科で直接手渡しをするところもある。
▽NPOだからこそ
行政の支援制度を知らない人や、支援に頼ることに抵抗を感じる人も多い。そらいろコアラは相談で寄り添いながら、必要な時には行政支援の申請や医療機関の受診を促している。
反対に、真岡市では支援制度や医療の対象ではないものの困難を抱える人を、市役所やクリニックからそらいろコアラに紹介する場合もある。増田さんは「NPOだからこそ、制度や医療の網の目からこぼれる人を助けられる」と意義を語る。
▽声を拾い上げる工夫
本当に助けを必要とする人は、自分から声を上げられない、という考え方がそらいろコアラの活動の前提になっている。
申し出がなくとも、食事やミルク、おむつなどの物資を配達したり、不定期開催の親子参加型イベントに誘ったりして、さりげなく様子をうかがう。そうしたコミュニケーションは、利用者の「頼る」ことへの心理的ハードルを下げる工夫でもある。
チャットの相談は県内外の各地から届き、件数も年々増えている。そらいろコアラの態勢では限界がある一方、真岡市での取り組みに注目する他の自治体もある。増田さんは「将来的に他の地域でも同様のモデルを広げていければ」と期待する。
× ×
47の地方紙とNHK、共同通信が各地の地域づくりを応援する「地域再生大賞」は2024年度に第15回の節目を迎えた。そらいろコアラは最高賞である大賞に輝き、2月に表彰された。
(2025/04/24)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
関連商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.