解説記事2010年12月20日 【実務解説】 グループ内法人間での寄附についての会社法上の留意点(2010年12月20日号・№383)
実務解説
グループ内法人間での寄附についての会社法上の留意点
西村あさひ法律事務所 弁護士 中山龍太郎
Ⅰ.はじめに
平成22年度税制改正によって導入されたグループ法人税制、とりわけ単体課税制度の改正によって、完全支配関係のある内国法人間での取引にかかる損益の調整が認められた。中でも注目されるのが、100%グループ内法人間での寄附金・受贈益の損金・益金不算入である。
持株会社解禁直後より、グループ経営の自由度を損なうものとして税務上の寄附金・受贈益の課税問題があげられることは多かった。例えば、会社法(商法)の世界では、株式移転によって設立された親会社の初年度の配当財源の捻出が問題となり、株式移転の効力発生日を中間配当の基準日の前に設定するといったテクニカルな手法などが採用されていたが、これらは子会社から親会社への寄附(贈与)が可能であれば何ら必要のない対策であった。
また、持株会社と事業子会社との間で経営指導契約等を締結して、経営指導料を徴収する場合にも、その金額の定め方の適正性や一貫性について、常に税務上の観点を考慮する必要があった。
今回のグループ法人税制によって100%グループ内法人間において、このような考慮が不要となったという点では、今後、グループ法人税制を有効に利用することで経営の自由度が飛躍的に高まることが期待されるところである。
もっとも、このことは、グループ内法人間での寄附等を通じた利益移転について、およそ会社法上の制約原理が働かないことを意味するものではない。むしろ、税務上の制約が撤廃されたことで、今まで余り論じる必要のなかった会社法上の制約原理が今後クローズアップされることとなる可能性がある。
そこで、本稿ではグループ法人税制導入後の寄附にかかる会社法上の留意点について、子会社から親会社、親会社から子会社、兄弟会社間のそれぞれに場合を分けて検討を行うこととする。
Ⅱ.子会社から親会社への寄附について
グループ法人税制導入によって、寄附の活用がもっとも進むこととなるのが子会社から親会社への寄附であろう。特に純粋持株会社形態の企業グループにおいては、持株会社自身は収益事業を営んでいないことから、事業会社で稼得した収益を持株会社に移転しなければ持株会社にいる外部株主への配当を行うことができない。
従来は、子会社から親会社に対する剰余金の配当や経営指導料の支払いをもって親会社への収益とすることが多かった。しかしながら、剰余金の配当については会社法上の配当財源が必要となり、経営指導料については親会社から子会社に提供する経営指導の具体的な内容やサービスが支払われる対価と見合ったものであるかが税務上厳しく見られることもあり、柔軟性に欠けるきらいがあった。これに対して、今後は100%グループ内法人間での子会社から親会社に対する寄附が選択肢として加わることとなり、その意味で親子会社間での収益分配の柔軟性は高まると考えられる。
もっとも、会社法上の財源規制や対価の相当性という制約がない寄附が行われる場合、それだけ子会社側の会社財産が毀損される危険性は高まる。
この観点で留意すべきなのが、役員等の第三者に対する責任である(会社法429条1項)。「役員等」、すなわち、取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人は(会社法423条1項参照)、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこととされている。
ここでいう「第三者」には債権者が含まれ、従来から会社が倒産に瀕した時期に取締役が返済見込みのない金銭借入れを行った事案などで、債権者による取締役の責任追及訴訟がしばしば提起されてきた。
例えば、子会社の取締役は、善管注意義務の一内容として、事業の継続可能性を真摯に検討する義務があると考えられるところ、子会社の取締役が親会社からの指示に漫然と従って寄附を行った結果として、子会社の財務状況が悪化し、債権者に対する約定通りの弁済ができなかったような場合には、子会社の取締役として悪意・重過失による任務懈怠を問われる可能性がある。また、監査役も、このような取締役の任務懈怠を適切に監視する義務を怠ったとして任務懈怠責任を追及される可能性がある。会社に対する義務違反については、全株主の同意で免除が可能であるが(会社法424条)、第三者に対する責任については株主の同意で免除することはできない。
また、このような場合は、子会社の役員等のみならず、子会社に指示をしていた親会社に対しても直接に責任追及が行われる可能性を否定できない。これは、「事実上の取締役」理論として知られるものであるが、会社法上、取締役としての地位を有していない場合であっても、事実上、会社の業務執行を行っていたことを理由に取締役と同様に第三者に対する責任を認めようとする理論である(東京地裁平成2年9月3日判決判例時報1376号110頁、大阪地裁平成4年1月27日判決労働判例611号82頁等参照)。
今までのところ、親子会社関係において、この理論が直接に適用された事例はないが、剰余金の配当のような会社法上の株主の権利や契約に基づかない寄附を親会社が子会社に指示することそのものが、事実上、子会社の業務執行を行う権限を親会社ないしその取締役等が有していたということを裏付ける事実として援用される可能性は否定できない。
さらに、より一般的には、親会社が子会社の意思決定を実質的に支配しているような場合、法人格否認の法理によって、子会社の法人格が否認され、直接的に親会社が子会社債権者に対して債務の弁済の責任を負う可能性も否定できない(解散した子会社の従業員から親会社への未払賃金の請求が法人格否認の法理によって認められたものとして、例えば、大阪地裁岸和田支部平成15年9月10日決定労働判例861号11頁、大阪高裁平成17年3月30日決定労働判例896号64頁)。とりわけ、学説上は、親会社による子会社の搾取が法人格否認の法理の重要な根拠とされており(江頭憲治郎編『会社法コンメンタール1』114-115頁等)、寄附によって子会社の財産基盤が危うくなるような場合には、法人格否認の法理が認められる可能性が高まることが考えられよう。
このような民事的な責任追及に加えて、役員等が親会社のために会社に損害を加えることは、文言上は特別背任罪(会社法960条1項)にも該当する。刑事事件として立件されるのは、よほど悪質な事案に限られるであろうが、親会社の利益のために子会社の利益を疎かにすることを会社法が是認しているわけではないことの一つのあらわれと見ることができよう。
これらの点は別の観点からすれば、以下のようにまとめられよう。
グループ法人税制の導入によって100%親子会社間での寄附の柔軟性が増したとはいえ、子会社の役員等は、第一義的には子会社自身の会社運営を適切に行う義務を負っている。したがって、会社法上の株主の権利(剰余金の配当)や独立当事者条件での取引(経営指導料等)に基づかない純然たる寄附を行う場合には、子会社の財務基盤を危うくしないように配慮しなければならず、これを怠れば子会社の債権者からの責任追及リスクを抱えることとなる。
また、親会社側から見ても、子会社に対して株主権や契約関係に基づかない親会社の都合のみを優先した指示を行うことは、法人としての独立性を危うくする可能性をはらんでいる。とりわけ、子会社側にとって経済的合理性を見いだすことの困難な一方的な寄附は、子会社の法人としての独立性が不十分であることの徴表として、「事実上の取締役」理論や法人格否認の法理を通じて、株主有限責任の利用が制限される可能性を持っているとも考えられる。
このような点からすれば、子会社から親会社への寄附を行う場合には、子会社としての利害得失を個別に検討したり、親会社からの寄附要請に応じる場合の一定のルール等を定めるなど、恣意性を極力排除することが実務上求められていくことになるのかも知れない。
なお、以上のような会社法上の責任とは別に子会社の責任財産を減少することを認識して寄附が行われた場合には、当該寄附は民法上の詐害行為取消権(民法424条)や、法的倒産手続に入った場合には否認権(破産法160条1項等)の対象となる可能性があることにも留意が必要である。
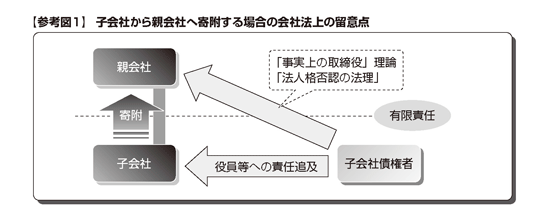
Ⅲ.親会社から子会社への寄附について
親会社から子会社への寄附については、従前から、例えば子会社救済の文脈での債権放棄や増資等の文脈で行われており、実務でのニーズは高い。税務上も、親会社側では法人税基本通達9-4-1や9-4-2にいう「やむを得ない」ものであることが認められれば、これまでも寄附金ではなく全額損金として取り扱うことが認められてきたが、グループ法人税制の導入で、子会社側の受贈益課税の問題がなくなったことで、一層用いられることになろう。また、100%子会社を簡易合併で合併しようとするときに、子会社の簿価純資産が親会社において付している子会社株式の帳簿価額を下回ることで合併差損が発生してしまうことを防ぐような場面で利用することも考えられる。
もっとも、完全支配関係のある子会社とはいえ、あくまで別法人である以上、親会社の役員等としては、親会社の財産を親会社自身の最善の利益のために用いることが善管注意義務の一内容として求められる。
親会社による子会社救済において役員等が負う責任については、既に一定の裁判例の蓄積がある。基本的にはいわゆる経営判断原則の考え方の下で、判断の前提となった事実の調査・検討に特に不注意な点がなく、当該業界の通常の経営者の判断として特に不合理・不適切な点がなかった場合には、取締役に与えられた経営の裁量の範囲の逸脱はないとされる(経営判断原則の考え方を採用したと考えられる近時の最高裁判決(アパマンショップ株主代表訴訟事件判決)と、それを踏まえた現時点でのわが国における経営判断原則については、落合誠一「アパマンショップ株主代表訴訟最高裁判決の意義」商事法務1913号4頁を参照のこと)。
したがって、子会社への寄附にあたって、その効用とリスクをきちんと把握した上で、慎重な分析の下にこれを行っている限りにおいては、実際に役員等の責任が認められる可能性は低いと考えてよい。
しかしながら、従来は、そもそもこの種の寄附にあたっては、税務上、法人税基本通達9-4-1又は9-4-2の要件を充足する形で行われることが多く、その時点で寄附の合理性・妥当性については一定のスクリーニングが働いていたと考えられる。グループ法人税制の導入によって、税務上の要件を考慮する必要はなくなったが、それに代わって、会社が独自に寄附の合理性・妥当性について検討する必要が生じていることには留意が必要であろう。
また、他に子会社への増資や貸付けといった親会社単体の分配可能額を減少しない形での資金移動の選択肢がある中で、あえて(親会社に反対給付が入らない)寄附という形態を選択したのかについては親会社株主の利益の観点からの合理的な説明が必要となると思われる。
Ⅳ.兄弟会社間での寄附について
グループ内法人間での資金配分の最適化はグループ経営における重要な課題の一つであり、既に多くの企業グループにおいてCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)が導入され、グループ内での資金融通によって外部資金への依存度を減らす試みが積極的になされている。
従前、このようなグループ内での資金融通にあたっては、その条件が独立当事者間取引条件であることを確保することが税務上は重要であったが、グループ法人税制の導入によって、少なくとも完全支配関係のある法人間であれば、この点を過度に気にする必要はなくなった。
もっとも、子会社から親会社への寄附で述べたのと同様に、子会社の役員等はあくまで第一義的には当該子会社自身の運営を適切に行う義務を負っている。したがって、親会社からの指示に従って、漫然と会社財産を毀損するような寄附を行えば、当該子会社の債権者からの責任追及にさらされる可能性がある。
また、そのような兄弟会社間での寄附を指示した親会社についても、そのような指示を含めて当該寄附を行った子会社の業務執行を事実上行っているものと見られたり、当該子会社を他のグループ子会社のために搾取していると見られれば、株主有限責任の原則を否定され、「事実上の取締役」理論や法人格否認の法理を介して、当該寄附を行った子会社の債権者に対して直接責任を負う可能性も否定できない。この場合は、寄附による受益は他の子会社であるが、責任は親会社に問われる点には留意が必要である。
なお、このような責任関係とは別に、寄附行為自体についても詐害行為取消権や否認権の対象となり得ることは子会社から親会社への寄附と同様である。
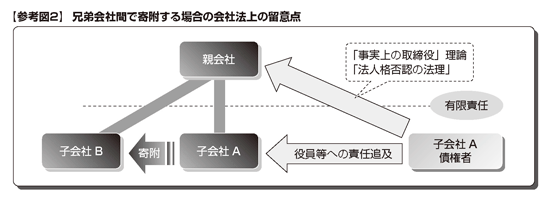
Ⅴ.まとめ
以上述べてきたように、グループ法人税制の導入によって100%グループ内法人間での寄附については、従前より柔軟な取扱いが可能となったものの、会社法上の役員等の責任に照らすと、何ら制約が働かないということではない。
各会社の財務の健全性が維持され、債権者がおよそ害されるようなおそれがない状況であれば、子会社から親会社、あるいは、兄弟会社間での寄附については、比較的柔軟に考えることは可能であろう。しかしながら、経営環境は動的なものであり、寄附の意思決定を行った時点では問題がなかったとしても、それからさほど間を置かず何らかの状況変化によって寄附を行った会社の財務状況が悪化した場合には、以前行った寄附の合理性・妥当性について役員等の責任が問われる可能性は否定できない。
あるいは、親会社から子会社への寄附についていえば、従前、税務上の観点から寄附の合理性・妥当性について第三者的な検討の必要性があったものについて、企業が自らの内部的な判断のみで合理性・妥当性を担保しなければならないこととなったとも言える。とりわけ、親会社に反対給付を生じない形態での子会社への利益移転をあえて行うことの合理性については、親会社株主に対して説明可能な形で検証しておくことが求められる。
したがって、会社法上の責任追及リスクを管理するという観点からすれば、対債権者あるいは親会社株主への説明責任を果たす上では、個別の寄附について、(安易にグループ全体の最適化ということではなく)当該会社にとっての効用とリスクを整理した上で、その合理性・妥当性を検討することが重要になるものと考えられる。もっとも、個別の寄附について、常にそうした詳細な検討を行うことはグループの機動的な経営という観点からは負担ともなり得る。そこで、こうした個別検討の負担を軽減するという意味では、グループ内での寄附についても、予め判断要素や限界をある程度ルール化して、恣意的な形ではなく一貫した説明を外部に行うことができるような備えをしておくことも考慮に値しよう。
このようなグループ内での寄附についての考え方の整理は、また、完全支配関係にないグループ内企業との取引や、これまで完全支配関係にあった会社が完全支配関係から離脱するような場合の離脱前後での取引のあり方に関する整合性をとる上でも有用なものと考えられる。例えば、グループ内法人税制を利用する余地のないグループ会社にも適用される経営指導料として取り扱われるべき部分と、それ以外の完全支配関係にある会社間で行われる寄附のメルクマールや限界を明確にしておくことは、完全支配関係にない会社との取引に付随する税務リスクを軽減する上でも有効足り得よう。
このような考え方の整理を行っていくと、実は、グループ内における経営資源の分配については、既に従来の実務慣行の中で相当程度達成されており、あえてグループ内法人税制を用いる必要がある場面は思ったよりも多くないのかも知れない。
何れにせよ、会社法上は、株主有限責任の恩恵を受けるためには、まずは、それぞれの会社単体として株主以外の債権者への責任を果たさなければならない。グループ内法人税制の導入によって達成されるグループ経営の効率化も、あくまで、このような会社法上の原則を踏まえた上でのものであることは、(当然のことではあるが)改めて留意されるべきであろう。
グループ内法人間での寄附についての会社法上の留意点
西村あさひ法律事務所 弁護士 中山龍太郎
Ⅰ.はじめに
平成22年度税制改正によって導入されたグループ法人税制、とりわけ単体課税制度の改正によって、完全支配関係のある内国法人間での取引にかかる損益の調整が認められた。中でも注目されるのが、100%グループ内法人間での寄附金・受贈益の損金・益金不算入である。
持株会社解禁直後より、グループ経営の自由度を損なうものとして税務上の寄附金・受贈益の課税問題があげられることは多かった。例えば、会社法(商法)の世界では、株式移転によって設立された親会社の初年度の配当財源の捻出が問題となり、株式移転の効力発生日を中間配当の基準日の前に設定するといったテクニカルな手法などが採用されていたが、これらは子会社から親会社への寄附(贈与)が可能であれば何ら必要のない対策であった。
また、持株会社と事業子会社との間で経営指導契約等を締結して、経営指導料を徴収する場合にも、その金額の定め方の適正性や一貫性について、常に税務上の観点を考慮する必要があった。
今回のグループ法人税制によって100%グループ内法人間において、このような考慮が不要となったという点では、今後、グループ法人税制を有効に利用することで経営の自由度が飛躍的に高まることが期待されるところである。
もっとも、このことは、グループ内法人間での寄附等を通じた利益移転について、およそ会社法上の制約原理が働かないことを意味するものではない。むしろ、税務上の制約が撤廃されたことで、今まで余り論じる必要のなかった会社法上の制約原理が今後クローズアップされることとなる可能性がある。
そこで、本稿ではグループ法人税制導入後の寄附にかかる会社法上の留意点について、子会社から親会社、親会社から子会社、兄弟会社間のそれぞれに場合を分けて検討を行うこととする。
Ⅱ.子会社から親会社への寄附について
グループ法人税制導入によって、寄附の活用がもっとも進むこととなるのが子会社から親会社への寄附であろう。特に純粋持株会社形態の企業グループにおいては、持株会社自身は収益事業を営んでいないことから、事業会社で稼得した収益を持株会社に移転しなければ持株会社にいる外部株主への配当を行うことができない。
従来は、子会社から親会社に対する剰余金の配当や経営指導料の支払いをもって親会社への収益とすることが多かった。しかしながら、剰余金の配当については会社法上の配当財源が必要となり、経営指導料については親会社から子会社に提供する経営指導の具体的な内容やサービスが支払われる対価と見合ったものであるかが税務上厳しく見られることもあり、柔軟性に欠けるきらいがあった。これに対して、今後は100%グループ内法人間での子会社から親会社に対する寄附が選択肢として加わることとなり、その意味で親子会社間での収益分配の柔軟性は高まると考えられる。
もっとも、会社法上の財源規制や対価の相当性という制約がない寄附が行われる場合、それだけ子会社側の会社財産が毀損される危険性は高まる。
この観点で留意すべきなのが、役員等の第三者に対する責任である(会社法429条1項)。「役員等」、すなわち、取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人は(会社法423条1項参照)、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこととされている。
ここでいう「第三者」には債権者が含まれ、従来から会社が倒産に瀕した時期に取締役が返済見込みのない金銭借入れを行った事案などで、債権者による取締役の責任追及訴訟がしばしば提起されてきた。
例えば、子会社の取締役は、善管注意義務の一内容として、事業の継続可能性を真摯に検討する義務があると考えられるところ、子会社の取締役が親会社からの指示に漫然と従って寄附を行った結果として、子会社の財務状況が悪化し、債権者に対する約定通りの弁済ができなかったような場合には、子会社の取締役として悪意・重過失による任務懈怠を問われる可能性がある。また、監査役も、このような取締役の任務懈怠を適切に監視する義務を怠ったとして任務懈怠責任を追及される可能性がある。会社に対する義務違反については、全株主の同意で免除が可能であるが(会社法424条)、第三者に対する責任については株主の同意で免除することはできない。
また、このような場合は、子会社の役員等のみならず、子会社に指示をしていた親会社に対しても直接に責任追及が行われる可能性を否定できない。これは、「事実上の取締役」理論として知られるものであるが、会社法上、取締役としての地位を有していない場合であっても、事実上、会社の業務執行を行っていたことを理由に取締役と同様に第三者に対する責任を認めようとする理論である(東京地裁平成2年9月3日判決判例時報1376号110頁、大阪地裁平成4年1月27日判決労働判例611号82頁等参照)。
今までのところ、親子会社関係において、この理論が直接に適用された事例はないが、剰余金の配当のような会社法上の株主の権利や契約に基づかない寄附を親会社が子会社に指示することそのものが、事実上、子会社の業務執行を行う権限を親会社ないしその取締役等が有していたということを裏付ける事実として援用される可能性は否定できない。
さらに、より一般的には、親会社が子会社の意思決定を実質的に支配しているような場合、法人格否認の法理によって、子会社の法人格が否認され、直接的に親会社が子会社債権者に対して債務の弁済の責任を負う可能性も否定できない(解散した子会社の従業員から親会社への未払賃金の請求が法人格否認の法理によって認められたものとして、例えば、大阪地裁岸和田支部平成15年9月10日決定労働判例861号11頁、大阪高裁平成17年3月30日決定労働判例896号64頁)。とりわけ、学説上は、親会社による子会社の搾取が法人格否認の法理の重要な根拠とされており(江頭憲治郎編『会社法コンメンタール1』114-115頁等)、寄附によって子会社の財産基盤が危うくなるような場合には、法人格否認の法理が認められる可能性が高まることが考えられよう。
このような民事的な責任追及に加えて、役員等が親会社のために会社に損害を加えることは、文言上は特別背任罪(会社法960条1項)にも該当する。刑事事件として立件されるのは、よほど悪質な事案に限られるであろうが、親会社の利益のために子会社の利益を疎かにすることを会社法が是認しているわけではないことの一つのあらわれと見ることができよう。
これらの点は別の観点からすれば、以下のようにまとめられよう。
グループ法人税制の導入によって100%親子会社間での寄附の柔軟性が増したとはいえ、子会社の役員等は、第一義的には子会社自身の会社運営を適切に行う義務を負っている。したがって、会社法上の株主の権利(剰余金の配当)や独立当事者条件での取引(経営指導料等)に基づかない純然たる寄附を行う場合には、子会社の財務基盤を危うくしないように配慮しなければならず、これを怠れば子会社の債権者からの責任追及リスクを抱えることとなる。
また、親会社側から見ても、子会社に対して株主権や契約関係に基づかない親会社の都合のみを優先した指示を行うことは、法人としての独立性を危うくする可能性をはらんでいる。とりわけ、子会社側にとって経済的合理性を見いだすことの困難な一方的な寄附は、子会社の法人としての独立性が不十分であることの徴表として、「事実上の取締役」理論や法人格否認の法理を通じて、株主有限責任の利用が制限される可能性を持っているとも考えられる。
このような点からすれば、子会社から親会社への寄附を行う場合には、子会社としての利害得失を個別に検討したり、親会社からの寄附要請に応じる場合の一定のルール等を定めるなど、恣意性を極力排除することが実務上求められていくことになるのかも知れない。
なお、以上のような会社法上の責任とは別に子会社の責任財産を減少することを認識して寄附が行われた場合には、当該寄附は民法上の詐害行為取消権(民法424条)や、法的倒産手続に入った場合には否認権(破産法160条1項等)の対象となる可能性があることにも留意が必要である。
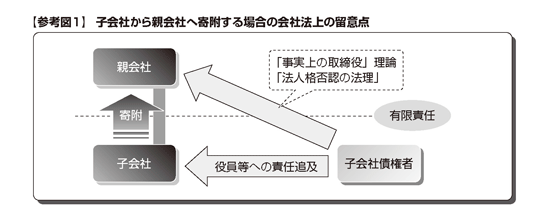
Ⅲ.親会社から子会社への寄附について
親会社から子会社への寄附については、従前から、例えば子会社救済の文脈での債権放棄や増資等の文脈で行われており、実務でのニーズは高い。税務上も、親会社側では法人税基本通達9-4-1や9-4-2にいう「やむを得ない」ものであることが認められれば、これまでも寄附金ではなく全額損金として取り扱うことが認められてきたが、グループ法人税制の導入で、子会社側の受贈益課税の問題がなくなったことで、一層用いられることになろう。また、100%子会社を簡易合併で合併しようとするときに、子会社の簿価純資産が親会社において付している子会社株式の帳簿価額を下回ることで合併差損が発生してしまうことを防ぐような場面で利用することも考えられる。
もっとも、完全支配関係のある子会社とはいえ、あくまで別法人である以上、親会社の役員等としては、親会社の財産を親会社自身の最善の利益のために用いることが善管注意義務の一内容として求められる。
親会社による子会社救済において役員等が負う責任については、既に一定の裁判例の蓄積がある。基本的にはいわゆる経営判断原則の考え方の下で、判断の前提となった事実の調査・検討に特に不注意な点がなく、当該業界の通常の経営者の判断として特に不合理・不適切な点がなかった場合には、取締役に与えられた経営の裁量の範囲の逸脱はないとされる(経営判断原則の考え方を採用したと考えられる近時の最高裁判決(アパマンショップ株主代表訴訟事件判決)と、それを踏まえた現時点でのわが国における経営判断原則については、落合誠一「アパマンショップ株主代表訴訟最高裁判決の意義」商事法務1913号4頁を参照のこと)。
したがって、子会社への寄附にあたって、その効用とリスクをきちんと把握した上で、慎重な分析の下にこれを行っている限りにおいては、実際に役員等の責任が認められる可能性は低いと考えてよい。
しかしながら、従来は、そもそもこの種の寄附にあたっては、税務上、法人税基本通達9-4-1又は9-4-2の要件を充足する形で行われることが多く、その時点で寄附の合理性・妥当性については一定のスクリーニングが働いていたと考えられる。グループ法人税制の導入によって、税務上の要件を考慮する必要はなくなったが、それに代わって、会社が独自に寄附の合理性・妥当性について検討する必要が生じていることには留意が必要であろう。
また、他に子会社への増資や貸付けといった親会社単体の分配可能額を減少しない形での資金移動の選択肢がある中で、あえて(親会社に反対給付が入らない)寄附という形態を選択したのかについては親会社株主の利益の観点からの合理的な説明が必要となると思われる。
Ⅳ.兄弟会社間での寄附について
グループ内法人間での資金配分の最適化はグループ経営における重要な課題の一つであり、既に多くの企業グループにおいてCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)が導入され、グループ内での資金融通によって外部資金への依存度を減らす試みが積極的になされている。
従前、このようなグループ内での資金融通にあたっては、その条件が独立当事者間取引条件であることを確保することが税務上は重要であったが、グループ法人税制の導入によって、少なくとも完全支配関係のある法人間であれば、この点を過度に気にする必要はなくなった。
もっとも、子会社から親会社への寄附で述べたのと同様に、子会社の役員等はあくまで第一義的には当該子会社自身の運営を適切に行う義務を負っている。したがって、親会社からの指示に従って、漫然と会社財産を毀損するような寄附を行えば、当該子会社の債権者からの責任追及にさらされる可能性がある。
また、そのような兄弟会社間での寄附を指示した親会社についても、そのような指示を含めて当該寄附を行った子会社の業務執行を事実上行っているものと見られたり、当該子会社を他のグループ子会社のために搾取していると見られれば、株主有限責任の原則を否定され、「事実上の取締役」理論や法人格否認の法理を介して、当該寄附を行った子会社の債権者に対して直接責任を負う可能性も否定できない。この場合は、寄附による受益は他の子会社であるが、責任は親会社に問われる点には留意が必要である。
なお、このような責任関係とは別に、寄附行為自体についても詐害行為取消権や否認権の対象となり得ることは子会社から親会社への寄附と同様である。
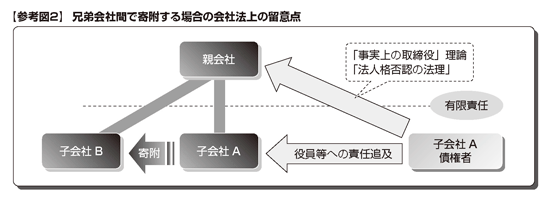
Ⅴ.まとめ
以上述べてきたように、グループ法人税制の導入によって100%グループ内法人間での寄附については、従前より柔軟な取扱いが可能となったものの、会社法上の役員等の責任に照らすと、何ら制約が働かないということではない。
各会社の財務の健全性が維持され、債権者がおよそ害されるようなおそれがない状況であれば、子会社から親会社、あるいは、兄弟会社間での寄附については、比較的柔軟に考えることは可能であろう。しかしながら、経営環境は動的なものであり、寄附の意思決定を行った時点では問題がなかったとしても、それからさほど間を置かず何らかの状況変化によって寄附を行った会社の財務状況が悪化した場合には、以前行った寄附の合理性・妥当性について役員等の責任が問われる可能性は否定できない。
あるいは、親会社から子会社への寄附についていえば、従前、税務上の観点から寄附の合理性・妥当性について第三者的な検討の必要性があったものについて、企業が自らの内部的な判断のみで合理性・妥当性を担保しなければならないこととなったとも言える。とりわけ、親会社に反対給付を生じない形態での子会社への利益移転をあえて行うことの合理性については、親会社株主に対して説明可能な形で検証しておくことが求められる。
したがって、会社法上の責任追及リスクを管理するという観点からすれば、対債権者あるいは親会社株主への説明責任を果たす上では、個別の寄附について、(安易にグループ全体の最適化ということではなく)当該会社にとっての効用とリスクを整理した上で、その合理性・妥当性を検討することが重要になるものと考えられる。もっとも、個別の寄附について、常にそうした詳細な検討を行うことはグループの機動的な経営という観点からは負担ともなり得る。そこで、こうした個別検討の負担を軽減するという意味では、グループ内での寄附についても、予め判断要素や限界をある程度ルール化して、恣意的な形ではなく一貫した説明を外部に行うことができるような備えをしておくことも考慮に値しよう。
このようなグループ内での寄附についての考え方の整理は、また、完全支配関係にないグループ内企業との取引や、これまで完全支配関係にあった会社が完全支配関係から離脱するような場合の離脱前後での取引のあり方に関する整合性をとる上でも有用なものと考えられる。例えば、グループ内法人税制を利用する余地のないグループ会社にも適用される経営指導料として取り扱われるべき部分と、それ以外の完全支配関係にある会社間で行われる寄附のメルクマールや限界を明確にしておくことは、完全支配関係にない会社との取引に付随する税務リスクを軽減する上でも有効足り得よう。
このような考え方の整理を行っていくと、実は、グループ内における経営資源の分配については、既に従来の実務慣行の中で相当程度達成されており、あえてグループ内法人税制を用いる必要がある場面は思ったよりも多くないのかも知れない。
何れにせよ、会社法上は、株主有限責任の恩恵を受けるためには、まずは、それぞれの会社単体として株主以外の債権者への責任を果たさなければならない。グループ内法人税制の導入によって達成されるグループ経営の効率化も、あくまで、このような会社法上の原則を踏まえた上でのものであることは、(当然のことではあるが)改めて留意されるべきであろう。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























