解説記事2016年04月18日 【SCOPE】 第二次納税義務で非上場株式のDCF法による時価評価を容認(2016年4月18日号・№639)
増資により取得した新株式の評価額が問題に
第二次納税義務で非上場株式のDCF法による時価評価を容認
請求人に対する第二次納税義務の納付告知処分をめぐり、滞納法人の子会社が実施した新株発行により請求人が取得した非上場株式の評価額が問題となった事案で国税不服審判所は平成27年10月28日、原処分庁が採用したDCF法および時価純資産法の併用方式による株式評価を認める裁決を下した(仙裁(諸)平27-7)。審判所は、徴収法の規定上、第二次納税義務の限度額を算定するための財産評価に関し財産評価基本通達を適用または準用すべきとした規定はないと指摘。審判所は、DCF法や時価純資産法は実務上、企業の株式評価に広く活用されるなど株式評価の方法として広く認められたものであるため、原処分庁がこれらの方法を選択していることをもって不合理な点があるとは認められないと判断した。
請求人、一般的に税務上の時価評価の基準は相続税評価であると主張
本件は、滞納法人から新設分割された本件子会社が実施した第三者割当増資(以下「本件増資」)をめぐり、本件増資を単独で引き受けることにより本件子会社の新株式を取得した請求人(滞納法人および本件子会社の代表者)に対する第二次納税義務の適法性が争われたもの(事案の概要は図参照)。
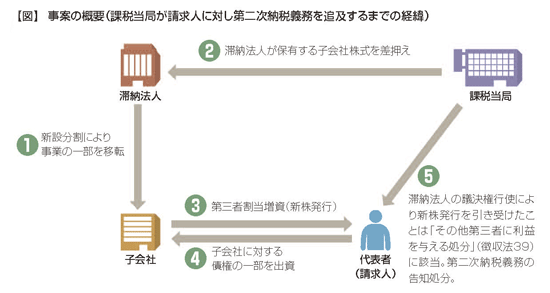
具体的には、本件増資により請求人が受けた利益の額(第二次納税義務の限度額)をめぐり、原処分庁がDCF法と時価純資産法の併用方式により総合評価した新株式(非上場株式)の評価額が合理的なものであるか否かという点などが問題となった。
事実関係をみると、本件子会社は、唯一の株主である滞納法人の議決権行使により、新株割当先を請求人のみとする本件増資を実施することを決議。請求人は、請求人が本件子会社に対して有する債権のうちの一部を出資財産とし、本件増資により本件子会社の新株式を取得した。
これに対し原処分庁は、滞納法人の議決権行使により、請求人が本件増資に関する新株発行を引き受けたことは徴収法39条規定の「その他第三者に利益を与える処分」に該当すると判断し、請求人に対し第二次納税義務の納付告知処分を行った。なお、この処分の際に原処分庁は、企業価値評価業務を営む法人(代表者は公認会計士)がDCF法(企業が将来獲得すると期待されるキャッシュ・フローの現在価値をもとに企業価値を算定する方法)と時価純資産法(資産の時価から負債の時価を控除して純資産の時価総額を求める方法)を併用する方法により算定した本件子会社の新株式の評価額をもとに、請求人が受けた利益の額を算定していた。
この処分を不服とする請求人は、審査請求のなかで、一般的に税務上の時価評価の基準とされる相続税評価によれば「受けた利益の額」は生じない旨を主張。また、請求人は、DCF法によりFCF(本来の事業活動から生じるキャッシュ・フロー)を基礎として株式価値を算定する場合は評価対象者の事業計画に基づき予想することが原則であると指摘し、この原則に反して過去の貸借対照表や損益計算書などの数値をもとに算定された評価額は評価における適正手続きに欠けたものであると主張した。
審判所、徴収法の規定上評価通達を適用すべきとした規定なし
国税不服審判所は、まず、第二次納税義務の限度額を算定するための財産評価に関し徴収法の規定上、財産評価基本通達を適用または準用すべきとした規定はないことから、財産評価基本通達に従って算定しなければならないものではないと指摘。そして、日本公認会計士協会が作成した「企業価値評価ガイドライン」で挙げられている時価純資産法やDCF法は実務上、企業の株式評価に広く活用され、判例でも採用されている現状から株式評価の方法として広く認められたものといえると指摘したうえで、原処分庁が財産評価基本通達によらずDCF法などの評価方法を選択していることをもって、不合理な点があるとは認められないと判断した。
次に、原処分庁が依拠したDCF法が将来の事業計画の数値によらず、過去の決算書等の数値を使用して将来の営業利益等を見積もり算定している点について審判所は、滞納法人が本件子会社の事業計画等の資料を提出しなかったためであり、継続企業の評価時点で大きな状況の変化がない場合は将来においても現状の損益を維持するものとして算定したとしても一概に不合理であるとはいえないと指摘。また、審判所は、評価に大きな影響を与えるような事実が認められない本件状況下においては、過去の数値により将来の数値等を見積もって算定したとしても、不合理な数値を採用したとまでは認められないと指摘したうえで、請求人の主張を斥けた。
第二次納税義務で非上場株式のDCF法による時価評価を容認
請求人に対する第二次納税義務の納付告知処分をめぐり、滞納法人の子会社が実施した新株発行により請求人が取得した非上場株式の評価額が問題となった事案で国税不服審判所は平成27年10月28日、原処分庁が採用したDCF法および時価純資産法の併用方式による株式評価を認める裁決を下した(仙裁(諸)平27-7)。審判所は、徴収法の規定上、第二次納税義務の限度額を算定するための財産評価に関し財産評価基本通達を適用または準用すべきとした規定はないと指摘。審判所は、DCF法や時価純資産法は実務上、企業の株式評価に広く活用されるなど株式評価の方法として広く認められたものであるため、原処分庁がこれらの方法を選択していることをもって不合理な点があるとは認められないと判断した。
請求人、一般的に税務上の時価評価の基準は相続税評価であると主張
本件は、滞納法人から新設分割された本件子会社が実施した第三者割当増資(以下「本件増資」)をめぐり、本件増資を単独で引き受けることにより本件子会社の新株式を取得した請求人(滞納法人および本件子会社の代表者)に対する第二次納税義務の適法性が争われたもの(事案の概要は図参照)。
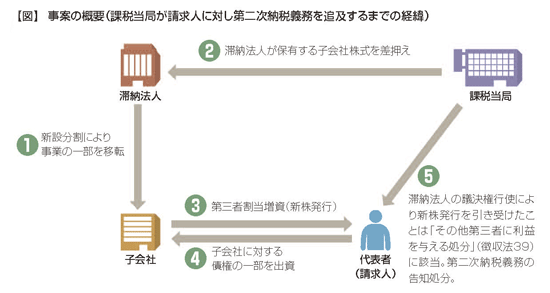
具体的には、本件増資により請求人が受けた利益の額(第二次納税義務の限度額)をめぐり、原処分庁がDCF法と時価純資産法の併用方式により総合評価した新株式(非上場株式)の評価額が合理的なものであるか否かという点などが問題となった。
事実関係をみると、本件子会社は、唯一の株主である滞納法人の議決権行使により、新株割当先を請求人のみとする本件増資を実施することを決議。請求人は、請求人が本件子会社に対して有する債権のうちの一部を出資財産とし、本件増資により本件子会社の新株式を取得した。
これに対し原処分庁は、滞納法人の議決権行使により、請求人が本件増資に関する新株発行を引き受けたことは徴収法39条規定の「その他第三者に利益を与える処分」に該当すると判断し、請求人に対し第二次納税義務の納付告知処分を行った。なお、この処分の際に原処分庁は、企業価値評価業務を営む法人(代表者は公認会計士)がDCF法(企業が将来獲得すると期待されるキャッシュ・フローの現在価値をもとに企業価値を算定する方法)と時価純資産法(資産の時価から負債の時価を控除して純資産の時価総額を求める方法)を併用する方法により算定した本件子会社の新株式の評価額をもとに、請求人が受けた利益の額を算定していた。
この処分を不服とする請求人は、審査請求のなかで、一般的に税務上の時価評価の基準とされる相続税評価によれば「受けた利益の額」は生じない旨を主張。また、請求人は、DCF法によりFCF(本来の事業活動から生じるキャッシュ・フロー)を基礎として株式価値を算定する場合は評価対象者の事業計画に基づき予想することが原則であると指摘し、この原則に反して過去の貸借対照表や損益計算書などの数値をもとに算定された評価額は評価における適正手続きに欠けたものであると主張した。
審判所、徴収法の規定上評価通達を適用すべきとした規定なし
国税不服審判所は、まず、第二次納税義務の限度額を算定するための財産評価に関し徴収法の規定上、財産評価基本通達を適用または準用すべきとした規定はないことから、財産評価基本通達に従って算定しなければならないものではないと指摘。そして、日本公認会計士協会が作成した「企業価値評価ガイドライン」で挙げられている時価純資産法やDCF法は実務上、企業の株式評価に広く活用され、判例でも採用されている現状から株式評価の方法として広く認められたものといえると指摘したうえで、原処分庁が財産評価基本通達によらずDCF法などの評価方法を選択していることをもって、不合理な点があるとは認められないと判断した。
次に、原処分庁が依拠したDCF法が将来の事業計画の数値によらず、過去の決算書等の数値を使用して将来の営業利益等を見積もり算定している点について審判所は、滞納法人が本件子会社の事業計画等の資料を提出しなかったためであり、継続企業の評価時点で大きな状況の変化がない場合は将来においても現状の損益を維持するものとして算定したとしても一概に不合理であるとはいえないと指摘。また、審判所は、評価に大きな影響を与えるような事実が認められない本件状況下においては、過去の数値により将来の数値等を見積もって算定したとしても、不合理な数値を採用したとまでは認められないと指摘したうえで、請求人の主張を斥けた。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























