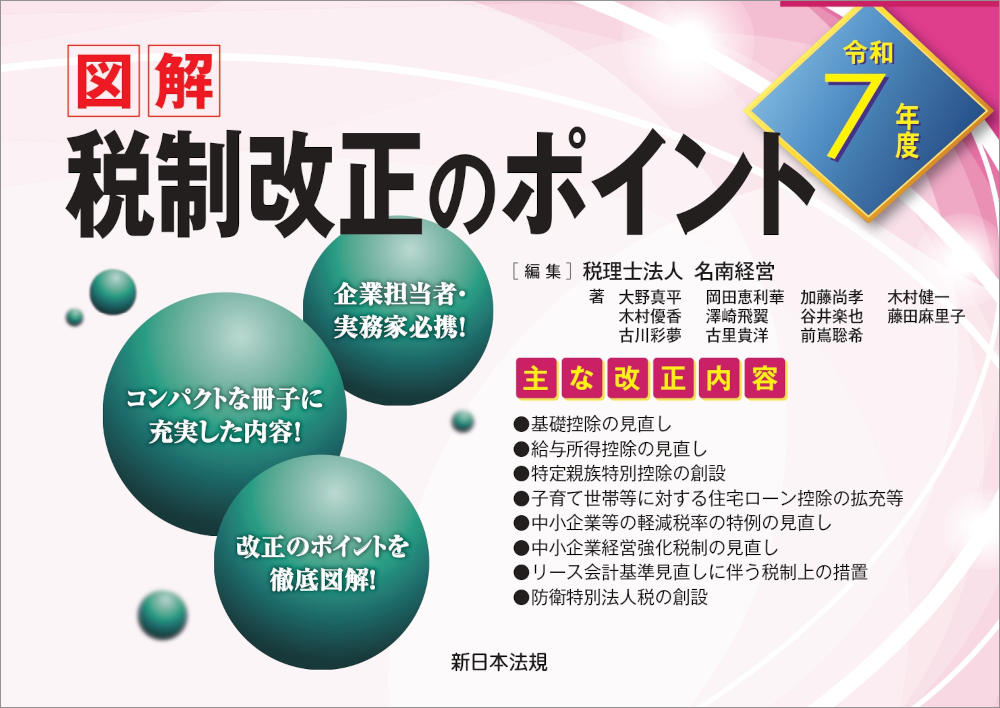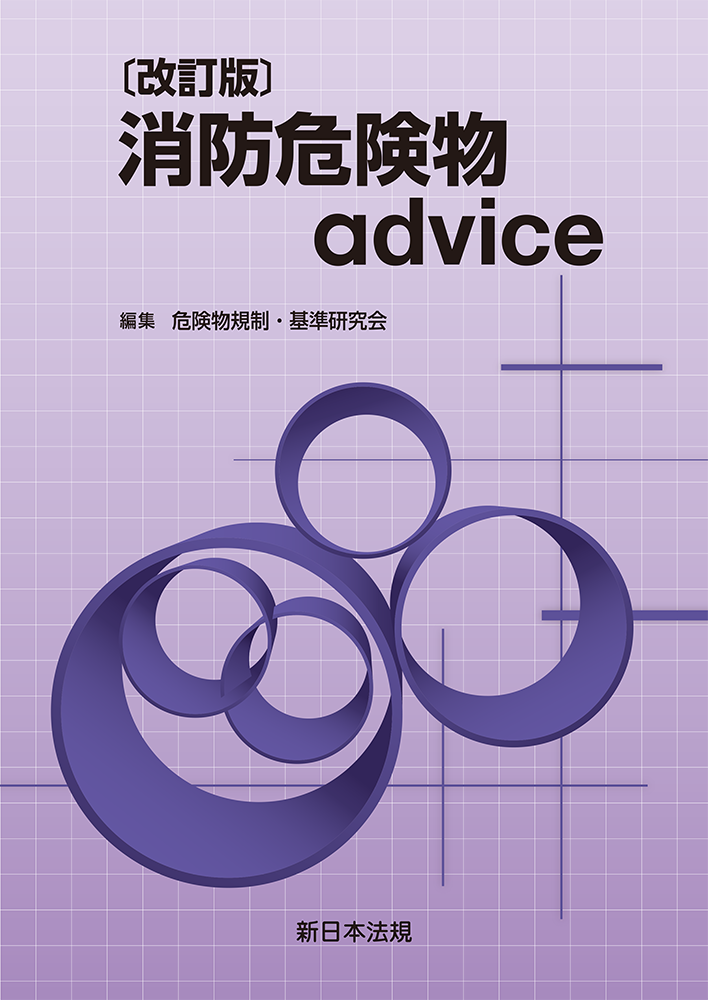解説記事2022年06月27日 最新判決研究 総則6項適用に対する最高裁初の判決(2022年6月27日号・№936)
最新判決研究
総則6項適用に対する最高裁初の判決
最高裁令和4年4月19日第三小法廷判決(令和2年(行ヒ)第283号)
東京高裁令和2年6月24日判決(令和元年(行コ)第239号)
東京地裁令和元年8月27日判決(平成29年(行ウ)第539号)
筑波大学名誉教授・弁護士 品川芳宣
一、事実
(1)被相続人Aは、平成24年6月17日に94才で死亡した。Aの死亡により、Aの妻K(訴外)、長女X1(原告、控訴人、上告人)、長男X2(原告、控訴人、上告人)、二男T(訴外)及び養子X3(Tの長男、原告、控訴人、上告人)(以下「本件共同相続人」といい、原告等3名を「Xら」という。)は、Aを相続(以下「本件相続」という。)し、本件相続に係る財産を取得した。
本件相続に係る相続財産には、杉並区所在の土地(以下「本件甲土地」という。)及び同土地上に存する建物(以下「本件甲建物」といい、本件甲土地と併せて「本件甲不動産」という。)並びに川崎市所在の土地(以下「本件乙土地」という。)及び同土地上に存する建物(以下「本件乙建物」といい、本件乙土地と併せて「本件乙不動産」といい、本件甲不動産と本件乙不動産を併せて「本件各不動産」という。)が含まれていた。本件各不動産は、Aの遺言により、X3が取得した。
(2)Aは、平成21年1月30日、本件甲不動産をC社から総額8億3700万円(以下「本件甲不動産購入額」という。)で購入し、同日、М銀行から6億3000万円を借り入れた。また、Aは、平成21年12月25日、本件乙不動産をG社から総額5億5000万円(以下「本件乙不動産購入額」といい、本件甲不動産購入額と総称して「本件各取引額」という。)で購入し、同日、М銀行から3億7800万円借り入れ、同月21日、Kから4700万円を借り入れた。
なお、X3は、平成25年3月7日、Sに対し、本件乙不動産を総額5億1500万円(以下「本件乙不動産売却額」という。)で売却した。
(3)Xらは、平成25年3月11日、本件相続税の申告(以下「本件申告」という。)をしたが、本件各不動産の価額を財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)の定めに従い、本件甲不動産の価額を2億4万円余及び本件乙不動産の価額を1億3366万円余と評価し(以下「本件各通達評価額」という。)、相続財産の総額10億156万円余、債務等の額9億9706万円余、相続税の総額0円とした。
これに対し、処分行政庁は、平成28年4月27日、本件各不動産の価額を評価通達6項に基づいて評価することとし、不動産鑑定士の鑑定評価額に基づき、本件甲不動産の価額を7億5400万円及び本件乙不動産の価額を5億1900万円(以下「本件各鑑定評価額」という。)と評価し、相続財産の総額18億8581万円、相続税の総額2億4049万円余とする各更正(以下「本件各更正」という。)等をした。Xらは、本件各更正等を不服として、前審手続を経て、平成29年11月22日、国(被告、被控訴人、被上告人)に対し、当該各処分の取消しを求めて、本訴を提起した。
二、争点及び当事者の主張
1 争 点
(1)本件相続開始時における本件各不動産の時価(評価通達の定める評価方法によらない評価が許されるための特別の事情の内容及びその有無(争点①)
(2)評価通達6の定める国税庁長官の指示に関する手続上の違法の有無(争点②)
(3)本件各更正等の理由の提示に関する違法の有無(争点③)
2 国の主張
(1)相続税法22条に規定する時価は、当該財産の取得時の客観的交換価値をいうが、実務上の要請から評価通達の定めによって評価することにしている。しかし、租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかな場合には、別の評価方法によることが許されるものと解すべきであり、このことは、評価通達6が定めている。
(2)本件の事実関係に照らすと、本件各通達評価額と本件各不動産の時価との間には著しいかい離が認められるというべきであり、評価通達の定める評価方法を画一的に適用するという形式的な平等を貫くことによって、かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかである。
(3)本件各鑑定評価額は、不動産鑑定士により不動産鑑定評価基準に準拠した方法で算定されたものであって、いずれも原価法による積算価格と収益還元法(DCF法及び直接還元法)による収益価格がそれぞれ試算され、両者が比較検討された上で、最終的には収益還元法による収益価格が重視され算定されたものであって、これらの鑑定評価の手法はいずれも合理性がある。
(4)本件においては、本件各通達評価額が適当であるか否かを確認するために、評価通達の定める評価方法以外の方法により客観的交換価値を調べる必要があったことから、その調査の一環として、国税庁長官に対する上申(以下「本件上申」という。)の前に鑑定評価が行われたものである。その後、S国税局長は、本件上申を行い、国税庁長官からの指示(以下「本件指示」という。)を受けたものであるから、本件各更正等について、評価通達6の定める国税庁長官の指示に係る手続上の瑕疵は存在しない。
(5)本件各更正等の理由の提示は、行政手続法14条1項に反する点はない。
3 Xらの主張
(1)評価通達の定める評価方法による相続財産の評価は、合理性が担保されているものとして久しく実務界において実施されており、評価通達は、行政先例法としての地位を築いているといえる。そして、例外的に上記方法による評価額を否定し、これによらない評価を認める評価通達6の制定趣旨は、対象財産につき想定外の時価の下落事情が事後的に生じた場合に、評価通達が形式的に適用され、納税者の担税力が過大に測定されることが、担税力に応じた課税(租税公平主義)に反することに鑑み、このような場合に関する救済措置を設けた点にある。
(2)本件各鑑定評価は、いずれも収益還元法を用いて土地及び建物を一括評価しているから、本件各通達評価額との間にかい離が生じることは、評価手法が異なる以上、当然である。評価通達の定める評価方法、とりわけ路線価方式は、合理性があるものとして広く社会に受け入れられているから、本件のようにその評価額と鑑定評価額に数倍ものかい離がある場合、鑑定評価額の適正さに疑問が呈されるべきである。
(3)評価通達6は、その要件を「国税庁長官の指示を受けて評価する」と定めているが、処分行政庁は、国税庁長官の指示を待たず、本件指示の約1年前に不動産鑑定会社2社に鑑定評価を依頼し、本件各鑑定評価を得た。つまり、処分行政庁は、評価通達6の定める国税庁長官の指示の要件を充足することなく、評価通達の定める評価方法による評価を否定する評価を先行して行っていた。したがって、本件各更正等には、評価通達6の定める要件を満たさなかった点で手続上の瑕疵がある。
(4)本件各更正等の理由の提示においては、本件各通達評価額と本件各鑑定評価額の開差が4倍に上ることが記載されているのみであり、評価通達6の適用が肯定される特別の事情があることの理由が記載されていないから、行政手続法14条1項が要求する理由の提示として不十分であり、違法がある。
三、一審判決要旨
請求棄却。
1 本件相続開始時における本件不動産の時価(争点①)
(1)相続税法22条は、相続等により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価による旨を定めているところ、ここにいう時価とは、当該財産の客観的な交換価値をいうものと解される。課税実務においては、評価通達において財産の価額の評価に関する一般的な基準を定めて、画一的な評価方法によって相続等により取得した財産の価額を評価することとされている。このような課税実務は、評価通達の定める評価方法が相続等により取得した財産の取得の時における適正な時価を算定する方法として合理的なものであると認められる限り、相続税法22条の規定の許容するところであると解される。
しかし、他方、評価通達の定める評価方法によっては適正な時価を適切に算定することができないなど、評価通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者に係る全ての財産の価額の評価において用いるという形式的な平等を貫くことによって、かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかである特別の事情(評価通達6参照)がある場合には、他の合理的な方法によって評価することが許されるものと解すべきである。
(2)本件の事実関係の下では、本件相続における本件各不動産については、評価通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者に係る全ての財産の価額の評価において用いるという形式的な平等を貫くと、本件各不動産の購入及び本件各借入れに相当する行為を行わなかった他の納税者との間で、かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかというべきである。
2 評価通達6の定める国税庁長官の指示に関する手続上の違法性(争点②)
評価通達は税務官庁内部における通達にすぎないから、評価通達6の定める「国税庁長官の指示を受けて評価する」旨の定めが、税務官庁内部における手続という性格を超えて対外的な効果を有し、その違反が、更正等の違法を招来するものとは解し難い。
3 本件各更正等の理由の提示に関する違法性(争点③)
本件各更正の各通知書の記載によれば、本件各通知書は、Xらの納付すべき相続税及び過少申告加算税の額を計算過程とともに、本件各不動産につき評価通達6に規定する「評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる」との判断に至った基礎となる事実関係を記載し、その判断過程を根拠をもって具体的に明らかにしているといえる。よって、行政手続法14条に違反しない。
四、控訴審判決要旨
控訴棄却(請求棄却)
(1)当裁判所は、本件更正について、本件各不動産に係る相続税法22条に規定する時価を、評価通達の定めによって評価した本件各通達評価額とせず、本件各鑑定評価に基づく本件各鑑定評価額としたことは適法であり、また、Xらの主張する国税庁長官の指示の有無は、本件各更正処分の効力を左右するものではなく、さらに、本件各更正等については、行政手続法14条1項本文の趣旨が求める程度に理由が提示されているものと認められるから、本件各更正等は適法であり、これらの取消しを求める旨のXらの請求はいずれも棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり補正し、当審における判断を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」に記載のとおりであるから、これを引用する。
(2)相続によって取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価によるということは、相続税法22条によって定められており、評価通達でも、評価通達1(2)において、時価とは課税時期において、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、評価通達の定めによって評価した価額によるとした上で、評価通達6において、評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産については、評価通達の定めによって評価されない場合があることを定めている。このことからすると、相続により取得した財産について、原判決で説示するような場合に、評価通達の定める評価方法以外の方法によって評価した価額を当該財産の時価とすることについて、それがどのような場合であるかについて通達等によってあらかじめ示されていなかったからといって、租税法律主義に違反するものとは解されない。
(3)Xらは、本件各不動産に係る本件各鑑定評価額と本件各通達評価額との3ないし4倍の開差について、特に異常なものではない等と主張する。
しかしながら、上記の開差は、それ自体が大きなものと認められるし、それによって生ずる税額の差や、A及びXらが、あえて、本件各不動産の購入及びAの本件相続開始時の残債務に係る各借入れ(本件各借入れ)が近い将来発生することが予想されるAの相続においてXらの相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ、それを期待して、本件各不動産の購入及び本件各借入れを企画して実行し、その結果、本件各借入れ及び本件不動産の購入がなければ、本件相続に係る課税価格は6億円を超えるものであったにもかかわらず、本件各通達評価額を前提とする本件各申告による課税価格は2826万円余にとどまり、基礎控除により本件相続に係る相続税は課税されないことになることなどからすると、原判決で説示するとおり、本件各不動産については、評価通達の定める評価方法によっては適正な時価を適切に算定することができないものと認められ、評価通達の定める評価方法によって評価した価額を時価とすることは、かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかであると認められる。
(4)Xらは、本件相続開始前後の本件各不動産に係る一連の取引は、租税回避を目的としたものではなかったと主張する。
しかし、先にも判示したとおり、処分行政庁は、飽くまで、本件各通達評価額と本件各鑑定評価額との間の著しいかい離から、本件各不動産を評価通達の定めによって評価することが著しく不適当であるなどとして、本件各不動産を評価通達の定めによって評価しないものとしたのであって、単に税負担の軽減を結果としてもたらす行為を阻止するために評価通達6を適用したものとは認められないから、Xらのこの点についての主張は先の判断を左右できない。この点を措くとしても、A及びXらは、本件各不動産の購入及び本件各借入れを、A及び関係会社の事業承継の過程の一つと位置付けつつも、それらが近い将来発生することが予想されるAの相続においてXらの相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ、それを期待して、あえてそれらを企画して実行したと認められ、これを覆すに足りる証拠は見当たらないことは、原判決で説示するとおりである。
五、上告審判決要旨
上告棄却(請求棄却)
(1)相続税法22条は、相続等により取得した財産の価額を当該財産の取得の時における時価によるとするが、ここにいう時価とは当該財産の客観的な交換価値をいうものと解される。そして、評価通達は、上記の意味における時価の評価方法を定めたものであるが、上級行政機関が下級行政機関の職務権限の行使を指揮するために発した通達にすぎず、これが国民に対し直接の法的効力を有するというべき根拠は見当たらない。そうすると、相続税の課税価格に算入される財産の価額は、当該財産の取得の時における客観的な交換価値としての時価を上回らない限り、同条に違反するものではなく、このことは、当該価額が評価通達の定める方法により評価した価額を上回るか否かによって左右されないというべきである。
そうであるところ、本件各更正に係る課税価格に算入された本件各鑑定評価額は、本件各不動産の客観的な交換価値としての時価であると認められるというのであるから、これが本件各通達評価額を上回るからといって、相続税法22条に違反するものということはできない。
(2)他方、租税法上の一般原則としての平等原則は、租税法の適用に関し、同様の状況にあるものは同様に取り扱われることを要求するものと解される。そして、評価通達は相続財産の価額の評価の一般的な方法を定めたものであり、課税庁がこれに従って画一的に評価を行っていることは公知の事実であるから、課税庁が、特定の者の相続財産の価額についてのみ評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることは、たとえ当該価額が客観的な交換価値としての時価を上回らないとしても、合理的な理由がない限り、上記の平等原則に違反するものとして違法というべきである。もっとも、上記に述べたところに照らせば、相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があると認められるから、当該財産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するものではないと解するのが相当である。
これを本件各不動産についてみると、本件各通達評価額と本件各鑑定評価額との間には大きなかい離があるということができるものの、このことをもって上記事情があるということはできない。
もっとも、本件購入・借入れが行われなければ本件相続に係る課税価格の合計額は6億円を超えるものであったにもかかわらず、これが行われたことにより、本件各不動産の価額を評価通達の定める方法により評価すると、課税価格の合計額は2826万円余にとどまり、基礎控除の結果、相続税の総額が0円になるというのであるから、Xらの相続税の負担は著しく軽減されることになるというべきである。そして、A及びXらは、本件購入・借入れが近い将来発生することが予想されるAからの相続においてXらの相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・借入れを企画して実行したというのであるから、租税負担の軽減をも意図してこれを行ったものといえる。そうすると、本件各不動産の価額について評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことは、本件購入・借入れのような行為をせず、又はすることのできない他の納税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべきであるから、上記事情があるものということができる。
したがって、本件各不動産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するということはできない。
(3)以上によれば、本件各更正において、S税務署長が本件相続に係る相続税の課税価格に算入される本件各不動産の価額を本件各鑑定評価額に基づき評価したということは、適法というべきである。所論の点に関する原審の判断は、以上の趣旨をいうものとして是認することができる。
六、解説
はじめに
相続税法22条にいう「時価」は、「自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額」すなわち「客観的交換価値」を意味することについては学説、判例とも容認している。しかし、「時価」といえ「客観的交換価値」といえ、それらが一律に算定(評価)し得るものでないから、課税の実務では、本件各判決を含む多くの判決が容認しているように、評価通達が定める評価額(評価方法)に合理性が認められる限り、同通達に定める評価額(以下「通達評価額」という。)によっている。
しかしながら、通達評価額については、特に、土地に関しては、路線価方式(評基通13)に代表されるように、いわゆる標準価額によって評価されることになる。このような標準価額については、特に、地価の変動が激しい時等には、「客観的交換価値」又は当該土地の取引価額と乖離することとなり、その乖離を狙った節税策が横行することにもなる。また、家屋の評価額が固定資産税評価額によっていることから、同様な問題が生じることもある(注1)。そのため、そのような節税策等を封じるために、後述するように、かつては、立法上の措置がとられたこともあるが、現在では、主として、評価通達6で代表される評価通達上の否認規定(限定条項)の適用が問題となる。
そして、評価通達6を適用した課税処分については、多くの下級審判決において適法と認められて来たのであるが、本件においては、控訴審において当該課税処分を適法と認めたものの、上告審において弁論が再開されたため、納税者が逆転勝訴するのではないかと注目されていた。結局、納税者が勝訴することはなかったが、最高裁判所が初めて評価通達6の適用の是非について判断を示したということで、意義ある判決となった。以下、関連する問題を含めて、検討することとする。
1 通達評価額と取引価額の乖離の原因
(1)前述したように、通達評価額は、標準価額によっているため、当該財産の取引価額と乖離し易い傾向はある。しかし、通達評価額がある程度の評価の安全性に配慮しているといっても、例えば、土地の価額の評価が公示価格水準の8割で評価されているが如く、それ程大きな乖離を生じさせているわけではない。然るに、本件においては、本件甲不動産については約4倍、本件乙不動産については約5倍の乖離が生じている。この原因は、当該各不動産の各敷地(土地)に係る路線価(公示価格水準の8割で評価)が当該各敷地が取引価額と乖離しているだけではなく、むしろ、当該各不動産の各建物に係る通達評価額と取引価額との間に乖離が生じていることにあるものと考えられる。そして、当該各敷地と当該各建物のそれぞれの乖離が相乗して、4〜5倍という乖離を生じさせているものと考えられる。
(2)ところで、土地についての通達評価額と取引価額との乖離については、地価の変動、標準宅地と取引対象宅地との地形上の差異等と説明されることが多いが、建物(家屋)については、それ程注目されているわけではない。しかし、最近、節税用資産として注目されているタワーマンションや本件各不動産のような賃貸マンションについては、建物(家屋)に係る通達評価額と取引価額との乖離が影響していることが多い(注2)。
すなわち、評価通達は、家屋の価額を固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算した金額によって評価することとし(評基88)、その倍率を1.0と定めている(同別表1)。そして、固定資産税評価額は、一般的には、再建築費の6割程度で評価されていると言われているが、実際には、当該家屋の取引価額の2〜3割に止まる場合が多い。もっとも、この評価額は、固定資産税等の保有税率が1.7%(固定資産税1.4%、都市計画税0.3%)であることを考えると、税負担のあり方からみて低いとは言えないであろう。問題は、評価通達が評価方法を固定資産税評価額に安易に依存していることにあるものと考えられる。
2 不動産の取得と課税(評価)上の規制
(1)前述したように、評価通達における土地及び家屋の価額の評価において構造上の問題があるが故に、相続税又は贈与税の節税対策として、課税時期前における不動産の取得が持て囃され、それらに対する課税(評価)上の規制が行われて来た。
まず、昭和末期の土地バブルの最盛期において、土地等の不動産の取引価額と通達評価額の乖離を狙った節税策(税逃れ)が横行した。もちろん、当時も評価通達6は存在していたが、課税(立法)当局は、立法上の措置でそれらに対処することとした。すなわち、昭和63年12月末に成立した租税特別措置法69条の4(以下「旧措置法69条の4」という。)は、被相続人が、相続開始3年以内に土地等又は建物等(居住用を除く。)を取得している場合には、相続税の課税価格に算入すべき当該土地等又は当該建物等の価額をそれらの取得価額とする旨定めた。このように、相続税の課税価格を「取得価額」に固定すること(すなわち、「時価の法定化」)は、当該財産の取引価額が上昇すれば納税者にとって有利に働くし、下落すれば不利に働くことになる。このことは、「時価」を法定(固定)することの矛盾を惹起することになる。
かくして、平成に入ってバブル経済の崩壊により地価等が暴落したため、大阪地裁平成7年10月17日判決(行裁例集46巻10・11号942頁)の事案では、約23億円で取得した土地が相続開始時に約9億円に暴落したにもかかわらず、約13億円の相続税額を課税する課税処分が行われ、当該処分の合憲性が争われ、同判決は、旧措置法69条の4の規定は合憲であるが、同規定を適用した課税処分は違憲状態になる旨判示し、当該課税処分を取り消した。そして、上訴審の大阪高裁平成10年4月14日判決(訟務月報45巻6号1112頁)及び最高裁平成11年6月11日第二小法廷判決(税資243号270頁)も、前掲大阪地裁判決を支持している(注3)。なお、旧措置法69条の4は、平成8年度税制改正において、廃止された。
(2)旧措置法69条の4の制定によって相続税における不動産取得の節税策が封じられたため、不動産取得による節税策は、贈与税において一層活発化することになった。例えば、親が1億円で取得した土地を子に通達評価額2000万円で譲渡(又は負担付贈与)した場合に、同通達が「時価」を定めている(評基通1(2))が故に、みなし贈与課税(相法7)は適用されないと解されていた。そこで、国税庁は、「負担付贈与又は対価を伴う取引により取得した土地等及び家屋等に係る評価並びに相続税法第7条及び第9条の規定の適用について」(平成元年3月29日直評5ほか、以下「負担付贈与通達」という。)を発遣した。負担付贈与通達は、土地等及び家屋等のうち、負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得したものの価額は、評価通達の規定にかかわらず、当該取得時における通常の取引価額(譲渡者の取得価額がそれに相当するときには、当該取得価額)によって評価することとした。
また、不動産の取得による節税策は、個人間の取引にとどまらず、法人においても行われていた。例えば、純資産価額(相続税評価額)100億円の会社が150億円借金して土地を取得すると、当該土地の相続税評価額が50億円であれば、当該会社の純資産価額方式による株式評価額が零となるので、その取得後全株式を子に贈与しても贈与税は課税されないことになる、という事例もあった。そのため、国税庁は、平成2年8月3日付で評価通達を改正し、評価会社が課税時期前3年以内に取得等した土地等及び家屋等の価額を課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価することとし、当該土地等又は当該家屋等に係る帳簿価額(取得価額)が課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合には、当該帳簿価額に相当する金額によって評価することができる(評基通185かっこ書)こととした。
(3)前記(1)及び(2)で述べた不動産取得の節税策を封じる措置は、評価通達6の考え方を法律又は他の通達の取扱いによって個別に定めたものであるが、なお次のような問題を残している。一つは、類似する封じ策について、法律の定めと通達の定めが混乱しているという批判であり、その批判は、租税法律主義の建前上、全てを法律によって律すべきである旨の主張につながる。また、この批判は、旧措置法69条の4に定める「3年しばり」と評価通達185に定める「3年しばり」は同じであるから、前者が平成8年に廃止された以上後者も廃止すべきである旨の主張を惹起することになった(注4)。しかし、「時価」の取扱いは、本来、「時価」の動向によって対処できる通達によって行われるべきものであって、法律で「時価」を固定することが間違いであることは、旧措置法69条の4が廃止されたことが証明している。よって、評価通達185の「3年しばり」を廃止すべきとする批判も、的を得ていないことになる(注5)。
二つは、旧措置法69条の4及び評価通達185に定める「3年しばり」において、何故「3年」かということである。この「3年」については、課税時期前3年以内の取得価額が「時価」に近似していることと、当時の節税策が銀行から借金して不動産を購入するという手法であったから、当時の借入金の利息5〜10%という金利負担を考慮すると、課税時期3年以上前に不動産を取得しても、当該節税策が成立しなくなるということを考慮したものである。しかし、この「3年しばり」は、本件にも関わることであるが、納税者に対して、不動産を取得して「3年」を越えたら不問にされるという予測を与えていることと、最近の超低金利に対処できないということの問題を惹起している。そのため、「3年しばり」の妥当性が問題となる。もっとも、節税等のための不動産取得と課税時期との間の期間の長さを全く無視すると、評価通達において標準価額制度を設けた趣旨が没却する。
3 評価通達6の運用上の問題点
(1)評価通達6の考え方を初めて容認したのは、東京高裁昭和56年1月28日判決(税資116号51頁)である(注6)。同判決の事案では、被相続人が、市街化農地を4539万円余で譲渡し、手付金及び内金合計1600万円を受領し、当該農地の引渡予定日の15日前に死亡した場合に、所轄税務署長が、当該農地は売却済であるとして、相続財産の価額を当該売買代金残金請求権等とした課税処分の違法性が争われた。一審の東京地裁昭和53年9月27日判決(訟務月報25巻2号513頁)は、当該相続財産は農地であるから当該価額は評価通達に基づく評価額2018万円余(申告額)であるとして、当該課税処分を取り消したのに対し、前掲東京高裁判決は、当該相続財産は当該農地であるが、当該事案のように「特別な事情」がある場合には、当該農地の「時価」を当該売買代金で評価するのが相当であるとし、それが評価通達6が定めていることの所為である旨判示した。
ところが、この東京高裁判決については、当時、本件でXらが主張するように、評価通達6は納税者を救済するための規定であるとか、評価通達の適用上評価額が複数になって納税者に不利に作用するのは租税平等主義に反する旨等の批判もあった。そのこともあってか、上告審の最高裁昭和61年12月5日第二小法廷判決(訟務月報33巻8号2149頁)は、原判決を維持したものの、当該相続財産の種類を当該農地ではなく、手付金等の額と売買残代金債権の合計額(当該売買代金)である旨判示した。もっとも、前掲東京高裁判決は、前記2(2)で述べた負担付贈与通達の発遣や、評価通達185の改正に論拠を与えることとなり、当該各通達発遣後の類似の事案において、評価通達6を適用した課税処分が増加することとなった(注7)。
(2)ところで、評価通達6は、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と定めているところ、この通達6の適用においては、「著しく不適当」と認められるか否かという実体要件と「国税庁長官の指示」があったか否かという手続要件が問題となる。
この「著しく不適当」については、評価通達が相続税法22条に規定する「時価」を解釈・適用するために存在しているのであるから、当該財産の通達上の評価額と客観的交換価額との開差が客観的にみて「著しく不適当」と認められる場合に限定すべきであって、原則的には、租税回避を企画したか否かというような主観的要素は本来当該判断の要件にすべきではないと考えられる(注8)。もっとも、租税回避の企画等については、当該財産の取得当事者が評価通達上の評価額と取引価額に代表される客観的交換価値に相当の開差があることを認識していたことの証左にはなるであろう。なお、租税回避の否認については、別途、相続税法64条を適用すれば足りるものと考えられるが、実務的には、評価通達6の適用と相続税法64条の適用が混乱している場合も見受けられる(注9)。
次に、「国税庁長官の指示」の要否については、①税務通達は法源ではなくても税務官庁の職員を法的に拘束するものであること、②税務通達に反する課税処分が信義則違反、平等原則違反等に問われることがあること、③評価通達6の適用には「国税庁長官の指示」が必要であるから余程のことがない限り同項の適用はないであろうと予測する納税者側の予測可能性を保障する必要があること等を考えると、この手続要件を欠く処分には違法性を惹起するものと考えられる(注10)。しかし、従前の多くの裁判例(注11)が、「国税庁長官の指示」の有無は課税処分の効力に影響を及ぼさず、当該指示の存否を明らかにする必要がない旨判示している。しかし、国税庁側がこのような裁判所の考え方に安易に同調することは、ミスミス納税者側との信頼関係を失うことにもなるので、円滑な税務行政の遂行に腐心されている当局にとっても得策であるとも考えられない。
(3)以上のように、評価通達6は、評価通達が多くの財産について評価基準制度(標準価額)を採用していることから生じる問題を解決するために設けられた規定ではあるが、それを運用するに当たっても種々の問題がある。それらの問題については、前述したように、下級審段階では、概ね評価通達6の適用を適法とする判断が下されてきたところではあるが、最高裁判決が明確な判断を下したことはなかった。その点でも、本件の上告審判決は、非常に意義のあるものと言える。
しかも、本件においては、一審判決及び控訴審判決がいずれも評価通達6を適用した課税処分を適法と認めたことに対し、最高裁判所が納税者側の上告を受理し、弁論を再開したため、納税者側が逆転勝訴し、評価通達6の適用等について大きな影響を及ぼすのではないかという憶測を呼んでいた。
4 本件における評価通達6の適用と最高裁判決
(1)本件においては、札幌に居住していた被相続人Aが、90才を過ぎてから相続税対策のために比較的取引価額と通達評価額の格差が大きい首都圏に所在する本件各不動産を総額13億8700万円で取得し、その購入代金の大部分をM銀行から借り入れたものである。そして、本件各不動産の評価通達上の評価額が3億3370万円余であったというのであるから、Aは、本件各不動産の取得によって、10億5330万円余の相続財産を圧縮することができることになる。その結果、本件相続によって本件共同相続人は、本件申告の段階では相続税の負担を要しなかったというものである。
これに対し、処分行政庁は、評価通達6を適用し、不動産鑑定士の鑑定評価によって本件各不動産を総額12億7300万円(本件各鑑定評価額)と評価し、本件各更正等を行ったため、Xらが、これを不服として、本訴を提起したものである。
そのほか、本件各更正等の違法性の判断において考慮されるべき事情として、本件各不動産の取得と本件相続開始時のタイムラグが、本件甲不動産については3年5月、本件乙不動産については2年7月あり、本件乙不動産を取得したX3が本件相続開始後9月後に5億1500万円で譲渡しており、本件各不動産の取得に係るM銀行の融資の際の貸出稟議書に相続税対策が明確にされていたこと等がある。
そして、一審判決及び控訴審判決とも、前述したように、評価通達6を適用した本件各更正を適法と認め、かつ、「評価通達は税務官庁内部における通達にすぎない」ことを理由に、評価通達6に定める手続に不備(違法性)があったとしても、当該更正の違法を招来するものではない旨判示した。
(2)かくして、Xらが上告したところ、最高裁判所はこれを受理し、かつ、弁論を再開したため、前述したように、Xらが逆転勝訴するのではないかという情報も流された。しかしながら、上告審判決は、前述したように、まず、「評価通達は、上記の意味における時価の評価方法を定めたものであるが、上級行政機関が下級行政機関の職務権限の行使を指揮するために発した通達にすぎず、これが国民に対し直接の法的効力を有するというべき根拠は見当たらない。そうすると、相続税の課税価格に算入される財産の価額は、当該財産の取得の時における客観的な交換価値としての時価を上回らない限り、同条に違反するものではなく、このことは、当該価額が評価通達の定める方法により評価した価額を上回るか否かによって左右されないというべきである。」と判示した。
次いで、上告審判決は、「たとえ当該価額(編注=評価通達6適用後の価額)が客観的な交換価値としての時価を上回らないとしても、合理的な理由がない限り、上記の平等原則に違反するものとして違法というべきである。もっとも、上記に述べたところに照らせば、相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があると認められるから、当該財産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するものではないと解するのが相当である。」と判示した。
そして、上告審判決は、本件各不動産の購入がなければ、本件相続に係る課税価格が6億円を超えるものであったにもかかわらず、当該購入によって当該課税価格が2826万円余にとどまり、相続税額が0円になったのであり、Xらがこれを期待して行ったといえるから、「租税負担の軽減をも意図してこれを行ったものといえる。」とし、「本件各不動産の価額について評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことは、本件購入・借入れのような行為をせず、又はすることのできない他の納税者とXらとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべきである。」と判示し、本件における評価通達6の適用が「平等原則に違反するということはできない。」と判示した。
(3)以上のように、上告審判決は、まず、相続税法における財産の価額の評価の原則論と評価通達の限界を述べた上で、評価通達6の適用と平等原則違反の関係につき、「実質的な租税負担の公平に反するという事情」の有無により判断すべきとして、本件においては、本件各不動産の取得が「租税負担の軽減をも意図してこれを行った」といえ、当該「事情」が認められるから、平等原則に違反しない旨判示している。このような判示については、従来の下級審判決の考え方を概ねオーソライズしたものと考えられる。もっとも、折角、最高裁判所が判決を下すのであるから、評価通達6の適用要件を明確にしてほしかった等の要望・批判も見受けられる。
しかしながら、評価通達6が定める「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる」とは、同通達の下での評価基準制度に基づく標準価額が当該財産の客観的交換価値(時価)と乖離することがあることを想定し、当該乖離が評価上「著しく不適当と認められる」ことを意味しているはずである。また、裁判上における「特別の事情」の存否についても、評価通達における標準価額による評価額によることが実質的な平等原則(税負担の公平性)に反するか否かによって判断されるものと考えられる。そうすると、それぞれの処分行政庁又は裁判官が、それぞれの個別事案に応じて個別に判断せざるを得ないものと考えられる。そのため、「著しく不適当」又は「特別の事情」の判断基準を予め定めておくことは無理であるように考えられる。もっとも、不動産の取得は、節税目的等のために一般的に行われていることであるから、それらの取得について、当該不動産の取得価額と通達評価額との間に相当な乖離があるだけで評価通達6が適用されることになると、納税者側の予測可能性を著しく害することになるし、そもそも、評価基準制度を設けた趣旨を没却することになる。そうすると、当該不動産の取得と課税時期との間に一定の期間(例えば、3年等)を予め定めておくことも必要であるように考えられる。
なお、本件の一審判決及び控訴審判決は、評価通達6の手続要件の不備を当該更正の違法事由には当たらないとし、上告審判決もこれにふれていない(容認している)ことが注目される。しかし、このような手続要件を軽視することは、評価通達6の適用を適正にする見地から望ましいことではないと考えられる。
(注1)評価通達上の評価額と客観的交換価額の乖離がもたらす問題等については、品川芳宣「財産(資産)評価の実務研究 第3回」資産承継2018年春号192頁、同「租税法律主義と税務通達」(ぎょうせい 平成16年)119頁等参照。
(注2)評価通達における家屋の価額の評価方法とその問題点については、品川芳宣「財産(資産)評価の実務研究 第23回」資産承継2022年4月号140頁等参照。
(注3)品川芳宣「重要租税判決の実務研究 第三版」(大蔵財務協会 平成26年)906頁参照。
(注4)品川芳宣「措置法69条の4の廃止と評価通達の関係」税理1996年5月号18頁参照。
(注5)前出(注4)参照。
(注6)前出(注3)806頁参照。
(注7)東京地裁平成4年3月11日判決(判例時報1416号73頁)、東京高裁平成5年1月26日判決(税資194号75頁)、東京地裁平成5年2月16日判決(同194号375頁)、東京高裁平成5年12月21日判決(同199号1302頁)、大阪地裁平成12年5月12日判決(同247号607頁)等参照。
(注8)前出(注1)各書参照。
(注9)大阪地裁平成12年5月12日判決(税資247号607頁)、大津地裁平成9年6月23日判決(税資223号1046頁)、大阪高裁平成12年7月13日判決(同248号319頁)、最高裁平成14年10月29日第三小法廷判決(同252号順号9225)等参照。
(注10)前出(注1)各書参照。
(注11)東京高裁平成5年7月26日判決(税資194号75頁)、東京地裁平成9年9月30日判決(同228号829頁)、東京地裁平成11年3月25日判決(同241号345頁)等参照。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.