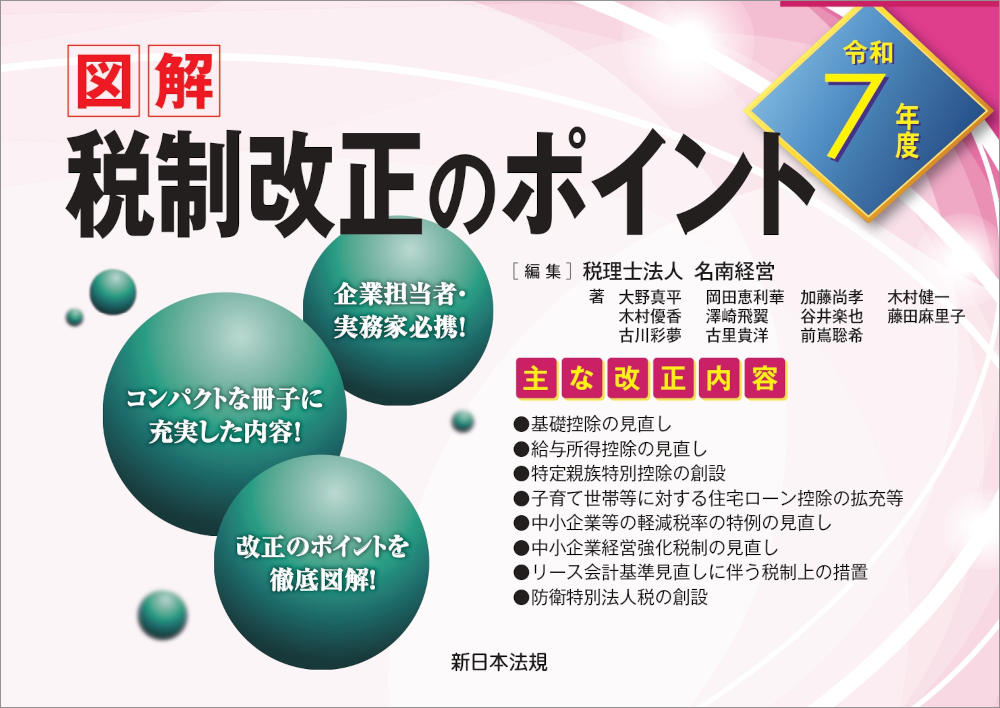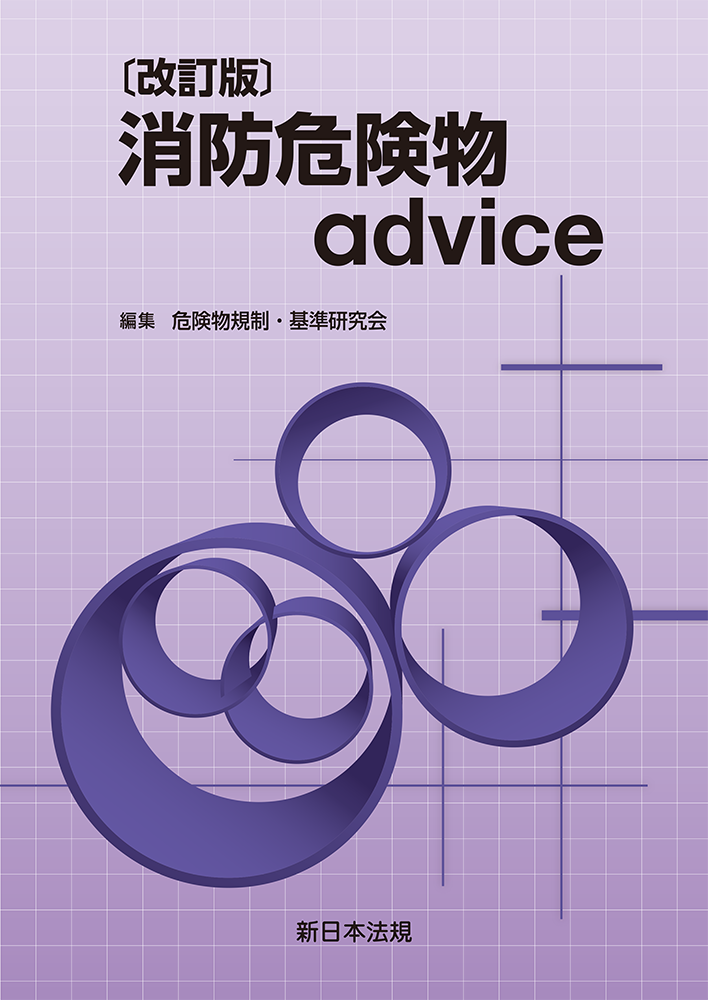解説記事2020年09月14日 最新判決研究 外国パートナーシップ持分を外国法人に現物出資した場合の適格現物出資該当性(2020年9月14日号・№849)
最新判決研究
外国パートナーシップ持分を外国法人に現物出資した場合の適格現物出資該当性
東京地裁令和2年3月11日判決(平成28年(行ウ)第395号)
筑波大学名誉教授・弁護士 品川芳宣
一、事実
(1)内国法人であるXは、平成13年9月、米国法人GSKとの間で、医薬品用化合物の共同開発等を行うジョイントベンチャー(以下「本件JV」という。)を形成する契約を締結し、同契約に基づき、英国領ケイマン諸島(以下「ケイマン」という。)において、特例有限責任パートナーシップであるCILP(以下「本件CILP」という。)を設立し、そのパートナーシップ持分(以下「本件CILP持分」という。)を保有していたが、その後の本件JVの枠組みの変更に際し、平成24年10月31日、本件CILP持分の全部をXの英国所在の完全子会社(以下「SL」という。)に対し、現物出資(以下「本件現物出資」という。)により移転した。
Xは、本件現物出資が法人税法2条12号の14に規定する適格現物出資に該当し、同法62条の4第1項の規定によりその譲渡益の計上が繰り延べられるとして、平成25年3月期分法人税等の確定申告をし、同確定申告に係る繰越欠損金の額を前提として、平成26年3月期分法人税等につき確定申告をしたところ、所轄税務署長から本件現物出資が適格現物出資に該当しないことなどを理由に平成25年3月期分法人税等につき更正処分(以下「本件更正」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定」という。)を受けたため、平成26年3月期分法人税等について、本件更正等による繰越欠損金の額の減少等を前提に修正申告をした上で更正の請求をしたが、同税務署長から更正をすべき理由がない旨の通知(以下「本件通知」といい、本件更正等と併せて「本件各処分」という。)を受けた。
Xは、本件各処分を不服として、前審手続を経て、本訴を提起した。
(2)CILPは、ケイマンの特例有限責任パートナーシップ法(以下「ELPS法」という。)によれば、その債務に対して無限責任を負う1人以上の無限責任パートナー(GP)とその債務に対して原則として出資を限度とする有限責任しか負わない1人以上の有限責任パートナー(LP)とで構成される、我が国の組合に類似した法人格のない事業体である。そして、Xは、平成13年、Xの米国所在の完全子会社であるSGHと共に、ケイマンにおいて、CILPを設立し、そのパートナーシップ持分の割合をLPであるXが99.98%、GPであるSGHが0.02%と定めた。
(3)また、本件現物出資の実行等は、次のとおりである。まず、Xが、平成24年2月に設立していたSLとの間で、本件現物出資に係る契約(以下「本件現物出資契約」という。)を締結し、同契約に基づいて、Xの保有するCILPのパートナーシップ持分(49.99%。以下「本件CILP持分」という。)をSLに給付し、その対価としてSLの新株の割当及び発行を受け(本件現物出資)、SGHも、その保有するCILPのパートナーシップ持分(0.01%)をSLに有償譲渡した。
次いで、SLが、上記のとおり取得した本件CILP持分の全てを、ViiV親会社に対して現物出資し、ViiV親会社の発行済株式の10%を取得するとともに、ViiV親会社の取締役1名の指名権を得た。本件現物出資契約では、本件CILP持分を「本件リミテッドパートナーシップ持分」と定義した上で、Xは一切の負担を伴わない「本件リミテッドパートナーシップ持分」をこれに付随する全ての権利と共に出資し又は出資させ、SLはこの出資を受け入れるものとし、その出資の対価は、SLからXへの普通新株の割当及び発行とする旨が定められていた。
(4)なお、Xは、平成24年10月15日、大阪国税局調査第一部調査総括課長宛ての同日付け「ケイマンパートナーシップ再編に関する税務上の取扱いについて」と題する書面(以下「本件照会文書」という。)を提出し、本件現物出資が適格現物出資に該当するか否かについての照会(以下「本件照会」という。)をした。同調査総括課長及び同課課長補佐(以下「本件照会担当者ら」という。)は、同年11月19日、Xに対し、本件照会に対する回答として、本件現物出資は適格現物出資に該当する旨を口頭で伝えた(以下「本件回答」という。)。
二、争点及び当事者の主張
1 争 点
本件各処分の適法性に関する争点は、次のとおりである。
(1)本件現物出資が適格現物出資に該当するか否か(争点(1))
(2)本件各処分が信義則に反するか否か(争点(2))
(3)国税通則法65条の4項の「正当な理由」があるか否か(争点(3))
2 国の主張
(1)法人税法2条12号の14の規定のうち適格現物出資の範囲から「外国法人に国内にある資産として政令で定める資産の移転を行うもの」を除外する旨を定めた部分及びこれを受けた法人税法施行令(以下「施行令」という。)4条の3第9項(現行10項)の規定は、国内にある資産を現物出資した際の含み益に対する課税が行われなくなることを規制し、我が国の課税権を確保しようとする趣旨で規定されたものである。
内国法人が国内にある事業所において経常的に管理している特定の資産は国内にある資産であるといえ、当該資産の譲渡益には我が国の課税権を確保する必要性が高いから、施行令4条の3第9項にいう「国内にある事業所に属する資産」とは、国内にある事業所において経常的な管理が行われている資産と解するのが相当である。
本件において、Xは、本件CILP持分の持分割合に基づき、CILPに出資する義務やその収益及び費用等の配賦を受ける地位を有していたところ、本件CILP持分は、国内にあるXの本社経理財務部が管理する有価証券台帳に投資有価証券として記帳されており、かつ、同台帳にはXが各出資を行ったことやCILPに係る費用等の配賦の結果等が適宜記帳されていたことからすれば、本件CILP持分は「国内にある事業所に属する資産」に該当すると推認される。
(2)信義則の法理の適用対象となる公的見解とは、少なくともその内容に沿った取扱いを確実に受けられると信頼してしかるべきものに限られる。本件面談時見解は、本件照会文書の提出を受けた当日に、本件照会担当者らが最終的な回答を行うことはできないと明示的に判断を留保した上で、本件照会担当者らがその場で一応の感触を示したにすぎないから、公式の見解の表示に当たるものではない。
(3)本件においては、納税者の過少申告において、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえない。よって、Xに国税通則法65条4項の「正当な理由」があるとは認められない。
3 Xの主張
(1)施行令4条の3第9項にいう「国内にある事業所に属する資産」の「属する」とは、我が国が国際的な源泉地管轄に基づく第一次課税権を有することを意味する。そして、資産を経常的に管理している事業所は、その経常的な管理を通じて、その資産の価値を創造又は増大させていると考えられるから、本件でも、資産が「属する」事業所は、CILPの事業用財産の経常的な管理を通じて、その資産の価値を創造又は増大させている事業所と解すべきである。
CILPの事業用財産は、上記米国事業所において作成・保管されていたCILPとUSOpCoの帳簿に記帳され、Xの本社の帳簿には、本件JVに対する出資持分の記帳がされていたものの、CILPの事業用財産に関する記帳はされていなかった。
以上によれば、CILPの事業用財産全体により構成される新薬開発事業はXの国外にある事業所に属し、国外にある事業所で経常的な管理が行われていたことが明らかであるから、本件現物出資は適格現物出資に該当する。
(2)本件照会担当者らは、平成24年10月15日の面談において、本件照会に対し、適格現物出資に該当するとの回答になる可能性が高い旨の見解(以下「本件面談時見解」という。)を口頭で回答し、その後、本件回答をしたものであるから、本件面談時見解及び本件回答は公的見解の表示に該当する。
(3)本件においては、前述のように、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるから、国税通則法65条4項の「正当な理由」があり、本件各更正処分等のうち過少申告加算税の賦課決定処分は違法である。
三、本判決の要旨
請求認容。
1 本件の事実関係
前提事実(前記一参照)に加え、各証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
(1)新薬の研究・開発の過程は、大要、①新薬の元となる新規化合物を合成し、その性状や化学構造を解析してスクリーニングを行い、新薬候補となる化合物を取捨選択するプロセス、②新薬候補化合物を対象に、動物や培養細胞を用いて、主に体内動態を検証し、有効性及び動物での安全性を評価する非臨床試験を行うプロセス、③非臨床試験において一定の有効性及び安全性を確認することができた新薬候補化合物を健康な人や患者に投与して有効性及び安全性を更に検証する治験(臨床試験)を行うプロセスを経る。通常、①のプロセスに2〜5年、②のプロセスに1〜3年、③のプロセスに3〜7年を要する。
(2)本件JVの設立当時、Xは、欧米先進国で需要が高い脳梗塞薬、抗アルツハイマー薬及び抗HIV薬のそれぞれについて新薬の開発を進めていたが、海外における新薬の開発を行うための人材・ノウハウを有しておらず、海外における医薬品販売事業を行う拠点もなく、海外において新薬承認申請を行ったことがなかったため、これらの新薬の開発を進めるために、欧米の製薬会社と組む必要があった。そこで、Xは、これらの新薬の早期発見と海外における医薬品の販売事業を行うことを視野に入れた拠点の設立を主な目的として、GSKとの間で本件JVを設立した。
(3)本件運営契約では、USOpCoは最高統治機関である執行委員会(後のJSC。)を置き、執行委員会はUSOpCoの事業を運営・管理すること、執行委員会は、6名で構成され、各パートナーが3名を指定し、そのうち1名を共同議長とすること、執行委員会は、四半期に1回の頻度で定例委員会を開催し、USOpCoの開発及び商品化に関する業務全般の決定及び監督等について最終的に責任を負うこと、CILPは、JVテリトリー内での特定化合物の開発をUSOpCoに委託し、受託したUSOpCoは、執行委員会の事前同意を得て、X、GSK又は他の第三者である開発業務受託機関との間で特定化合物に係る実際の開発活動に関する契約を締結することができること、CILPは、X及びGSKの知的財産権に対する開発、製造及び商品化についての2次ライセンスの権利を有し、この権利をUSOpCoに付与することなどが定められていた。
(4)平成13年9月頃、CILPの設立に当たり、Xは、知的財産の使用許諾を出資してLPのパートナーシップ持分99.98%を取得し、SGHは、9002米ドルを出資してGPのパートナーシップ持分0.02%を取得した。
平成13年10月19日、Xは、CILPのLPのパートナーシップ持分の半分(49.99%)をGSKに2250万米ドルで、SGHは、CILPのGPのパートナーシップ持分の半分(0.01%)をGSK子会社に4501米ドルで、それぞれ譲渡し、同日、Xは2250万米ドルを、GSKは知的財産の使用許諾と2250万米ドルを、SGH及びGSK子会社は4501米ドルずつを、それぞれCILPに出資した。
XのCILPに対する出資は、その後の追加出資等により、本件現物出資によるSLへの移転処理が行われる直前(平成25年3月31日時点)の帳簿残高は72億7794万円余となっていた。
これらのXのCILPに対する出資やその増減は、Xの本社の経理財務部において管理されている帳簿に勘定科目を「投資有価証券」として記帳されていた。
(5)Xは、平成24年2月、英国にSLを設立し、SLの事業として、本件JVにおいて開発活動が進められてきた化合物の製品上市の準備をしていたが、抗HIV薬については合剤での治療が主流であり、合剤を含めた経営ができる会社に販売を任せた方がよいこと、別の外国会社を買収したことから本件JVを足がかりとした米国の拠点獲得も不要になったことなどから、ViiVとの間で、本件JVの枠組みの変更を協議した。
また、Xにおいて、本件JVの枠組みを維持した場合と、本件JVの枠組みを変更してCILPのパートナーシップ持分をViiV親会社に移転し、その株式の10%を取得した場合の収益性を比較したところ、変更後の価値の合計の方が大きくなるとの試算結果を得た。そこで、Xは、平成24年10月1日開催の取締役会において承認を得た上で、本件現物出資を実施し、さらにSLにおいてViiV親会社への再現物出資を実施した。
2 本件現物出資の適格現物出資該当性
(1)適格現物出資制度は、平成13年度税制改正で導入された組織再編税制の一部であり、譲渡損益を繰り延べることによって、法人税の負担が現物出資による企業再編の阻害要因となることを防止し、企業再編を容易にするために定められたものであると解される。
ただし、法人税法2条12号の14の括弧書きにおいて「外国法人に国内にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債の移転を行うもの」が適格現物出資から除かれており、この規定を受けた施行令4条の3第9項は、国内にある資産又は負債として「国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法の規定による鉱業権及び採石法の規定による採石権その他国内にある事業所に属する資産又は負債」を定めている。これらの定めは、国内にある含み益のある資産を外国法人に移転することでその含み益に対する課税が行われなくなることを規制し、我が国の課税権を確保しようとする趣旨で規定されたものであると解される。
(2)本件では、本件現物出資の対象資産が施行令4条の3第9項にいう「国内にある事業所に属する資産」に該当するか否かが争点であるところ、この点の判断基準に関し、法人税基本通達1ー4ー12は、「国内にある事業所に属する資産」に該当するか否かは、原則として、当該資産が国内にある事業所又は国外にある事業所のいずれの事業所の帳簿に記帳されているかにより判定するが、実質的に国内にある事業所において経常的な管理が行われていたと認められる資産については、国内にある事業所に属する資産に該当することになる旨を定めている。この法人税基本通達が示す判断基準は、まず、その資産の経常的な管理がどの事業所において行われていたかを判定し、その判定に当たっては当該資産が当該事業所の帳簿に記帳されていたか否かを重要な考慮要素とし、次いで、その判定の結果当該資産の経常的な管理が行われていたと認められる事業所が国内にある事業所に当たるか否かを判定し、それが肯定された場合に「国内にある事業所に属する資産」に該当すると認める旨をいう趣旨に理解することが可能である。このように理解される判断基準は、前記法令の趣旨に鑑みて、合理性を有するものということができ、本件においても、基本的にこの基準に沿って検討するのが相当である。
(3)本件の現物出資の対象資産についての検討の前提問題として、本件現物出資の対象資産の捉え方について争いがあるので、まず、この点を検討する。
① ELPS法上、パートナーシップ持分とは、特例有限責任パートナーシップのパートナーが、パートナーシップ契約又は同法に基づき保有し又は服する、利益、資本及び議決その他の権利、恩恵又は義務に関する持分をいうとされ、同法上、LPのパートナーシップ持分を譲渡した場合の権利義務の承継に関する規定や、LPのパートナーシップ持分を譲渡抵当に入れることができる旨の規定があり、本件パートナーシップ契約においても、他のパートナーの同意があれば、GP及びLPのパートナーシップ持分につき売却、質入れ、担保権の設定その他の移転が可能であるとされ、これらの定めを通じて、CILPのパートナーシップ持分は譲渡可能な資産として位置付けられている。そして、本件現物出資契約においては、本件CILP持分が「本件リミテッドパートナーシップ持分」と定義され、当該「本件リミテッドパートナーシップ持分」が現物出資の対象資産とされていたのであるから、本件現物出資の対象資産は本件CILP持分であったと解するのが相当である。
② もっとも、CILPは、我が国の組合に類似した事業体であり、ELPS法及び本件パートナーシップ契約においても、CILPの事業用財産の共有持分(準共有持分を含む。)と切り離されたパートナーとしての契約上の地位のみが他に移転することは想定されていないものと解される。この点が、法人における株式の移転とは根本的に異なる点である。そうすると、本件現物出資の対象資産となった本件CILP持分についても、その内実は、CILPの事業用財産の共有持分とLPとしての契約上の地位とが不可欠に結合されたものと捉えなければならない。
(4)そこで、このような本件CILP持分の経常的な管理がどの事業所において行われていたかについて、検討する。
① 本件CILP持分は、上記のとおり、CILPの事業用財産の共有持分とLPとしての契約上の地位とが不可分に結合された資産であるから、これを経常的な管理の対象として捉える場合においても、これを個々の事業用財産の持分やパートナーシップ契約上の個々の権利等に分解してそれぞれを管理する事業所を個別に検討するのは相当ではなく、これらが全て結合された1個の資産とみてその管理が行われていた事業所を特定するのが相当である。
そして、パートナーがCILPの事業に参加する目的は、その出資に由来する事業用財産の運用により利益を得ることであり、パートナーとしての契約上の地位は、その運用のための手段と位置付けられるものであるから、CILPのパートナーシップ持分の価値の源泉はCILPの事業用財産の共有持分にあるということができ、また、CILPの事業用財産の共有持分とパートナーとしての契約上の地位との関係は、前者を主とする主物と従たる権利義務との関係に類似する関係にあるものと捉えることが可能である。したがって、本件CILP持分を1個の資産とみた場合のその経常的な管理が行われていた事業所は、CILPの事業用財産、中でもその主要なものの経常的な管理が行われていた事業所とみるのが相当である。
② 前記認定のとおり、CILPの事業用財産は、①現金、②知的財産のライセンス、③治験データ等の無形資産、④USOpCoへの出資等で構成されている。そして、このうち、現金は、米国で開設されたCILP又はUSOpCo名義の預金口座に入金され、また、CILPの事業に係る記帳、会計処理、税務申告等の経理業務は、GSK/ViiV側が有する米国フィラデルフィアの事業所において行われ、知的財産のライセンスも、CILP及びUSOpCoの連結財務諸表に記録されていたというのである。さらに治験データは、GSK/ViiV側のデータベースに保管され、Xには同データベースへのアクセス権が付与されていなかったというのであり、GSK/ViiV側が同データベースを管理する事業所を我が国内に有していたとは認められない。
そうすると、CILPの事業用財産のうち主要なものの経常的な管理は、いずれにしてもGSK/ViiV側が米国その他の我が国以外の地域に有する事業所において行われていたということができる。
(5)CILPの事業用財産の経常的な管理は、CILPの事業活動の一部であり、それを行う事業所がCILPの事業所に当たることは明らかであるから、CILPのパートナーであったXにとっても、当該事業所はCILPの事業活動を行うXの事業所であったということができる。しかし、CILPの事業用財産のうち主要なものの経常的な管理が行われていた事業所は、前記のとおり、米国その他の我が国以外の地域に所在していたから、当該事業所がXの国内にある事業所に当たるとはいえない。
(6)以上のとおり、本件現物出資の対象財産であった本件CILP持分は、その主たる構成要素であるCILPの事業用財産のうち主要なものの経常的な管理が国内にある事業所ではない事業所において行われていたということができるから、「国内にある事業所に属する資産」には該当しないというべきである。したがって、本件現物出資は、適格現物出資に該当するものと認められる。
四、解説
はじめに
現物出資は、法人税法22条2項にいう「資産の譲渡」に該当するので、当該現物に含み益(キャピタルゲイン)があれば、その段階で収益が認識されることになる。しかし、現物出資は、名のとおり、金銭以外の資産を株式又は出資に変えるものであって、いわば現物の資産間の交換である。そのため、現物出資によって当該現物資産の譲渡益が実現したものと観念し得るにしても、当該譲渡益に係る法人税等を納付できる金銭が留保されたわけではない。
そのため、法人税法では、かねてより、所定の要件の充足している現物出資について圧縮記帳の対象として課税の繰延べを図ってきた。しかし、経済取引がグローバル化したことに伴い、特に国際間の取引の中で、当該圧縮記帳制度を利用(悪用)した課税逃れが生じるようになって、それを封じる制度が採用され、平成13年以降、現行の適格現物出資制度へと引き継がれてきた。
本件においては、適格現物出資規定の適用に関し、本件現物出資の対象資産であるパートナーシップ持分が「国内にある事業所に属する資産」に該当するか否かが争われたものであるが、上記のような現物出資に係る法人税制の沿革を理解しておく必要がある。
1 現物出資に対する課税制度の沿革
(1)法人税法は、従前から、特定の取引によって取得した資産の帳簿価額の一部を減額して損金の額に算入するという圧縮記帳(注1)の制度によって、特定の譲渡益又は受贈益の課税の繰延べ制度を採用してきた。本件に関わる現物出資についても、「特定の現物出資により取得した有価証券の圧縮額の損金算入」(平成13年改正前の法人税法(以下「旧法法」という。)51条)の名の下に、次の要件を充足する特定の現物出資により取得した株式(出資を含む。)につき、当該現物出資により生じた差益金の額(圧縮限度額)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額した金額に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することにしていた。
① その出資により取得する株式の数又は出資の金額が、その新設法人の発行済株式の総数又は出資の金額の95%以上であること。
② 他の出資者がその新設法人の設立の際に払い込んだ1株当たりの金額が、特定現物出資をする法人の1株当たりの払込金額に比して著しく低くないこと。
③ 新設法人が特定現物出資をする法人から設立の際に現物出資を受けたそれぞれの資産について、その出資法人の出資の直前におけるその資産の帳簿価額以下の金額をその受入価額としたこと。
上記の要件を満たした圧縮限度額の計算は、次のとおりとなる。
圧縮限度額=特定現物出資により取得した株式等の取得時の価額ー(特定現物出資の出資直前の帳簿価額+特定現物出資に要した経費)
(2)このような圧縮記帳制度は、特定現物出資により取得した株式等を処分(譲渡)した時には、当該圧縮額が譲渡益と実現し、法人税の課税対象になるので、当該処分時までの課税の繰り延べをしているに過ぎない。しかし、現物出資によって外国法人を設立したような場合であって、当該外国法人の所在国が有価証券等の特定の資産の譲渡益を非課税としているときには、上記のような課税の繰延べのみでは済まないことになる。そして、そのような課税逃れを意図したタックスプランニングも行われることになる。
例えば、東京地裁平成13年11月9日判決(税資251号順号9020)、東京高裁平成16年1月28日判決(判例時報1913号51頁)、最高裁平成18年1月24日第三小法廷判決(訟務月報53巻10号2946頁)及び差し戻し審の東京高裁平成19年1月30日判決(判例時報1974号138頁)(注2)の事案では、原告会社(被控訴人、上告人)が、平成3年9月、多額な含み益を有するテレビA株式を現物出資してオランダ所在のAT社を設立(旧法法51条に定める圧縮記帳制度を適用)し、平成7年7月、AT社が、多額な増資を行ってオランダ国内に所在する関連会社AF社に引き受けさせ、AT社株式に係る多額な含み益をAF社に移転させた場合(当該移転については、オランダでは非課税)に、当該増資がX会社の法人税法22条2項にいう「無償による資産の譲渡」に当たるか否かが争われた。かくして、前掲東京地裁判決は、当該増資はX会社の取引に有らずと認定し、X会社に課税関係は生じない旨判示した(注3)。かくして、圧縮記帳制度による現物出資によって外国法人を設立した場合には、単なる課税の繰延べにとどまらない事態が顕在化することになった。
(3)このようなオーブンシャホールディング事件もあったこともあり、平成10年度税制改正では、出資資産が国内にある資産として政令で定める資産である場合に、当該資産の出資により海外子会社を設立するものについては、圧縮記帳制度を適用しないことにした。政令で定める資産は、「国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法の規定による鉱業権及び採石法の規定による採石権その他国内にある事務所に属する資産(その発行済株式の総数又は出資金額の25%以上を有する外国法人の株式又は出資を除く。)」とされた(旧法令93①)。
この税制改正の趣旨につき、国税担当者は、「ここでいう国内にある事業所の資産として管理・記帳されているものをいいますので、はじめから海外にある事業所の資産として管理・記帳されていたものは除かれますが、海外子会社を設立するために国内の事業所から海外の事業所に移管された資産は、国内にある事業所に属する資産に該当することに留意する必要があります。ただし、海外子会社の株式を現物出資して海外に統括子会社を設立するような場合については、従来どおり本措置の適用が受けられるようにされています。」(注4)と説明している。
かくして、現物出資の圧縮記帳に係る上記の改正事項と改正理由は、平成13年度税制改正による組織再編成税制における適格現物出資の適用要件に受け継がれている。
2 適格現物出資の要件
(1)前述したように、平成13年度税制改正によって組織再編成税制が導入され、その一つとして現物出資に係る譲渡益繰延べ制度が、圧縮記帳制度から組織再編成税制へ移管された。組織再編成税制については、我が国法人税制において画期的なことであると評価する向きもあるが、企業組織の変更(再編成=資産・負債の譲渡)に当たって、譲渡益を繰り延べる点では、我が国において伝統的に採用されてきた圧縮記帳制度と変ることはない(その点では、圧縮記帳制度の範囲を拡大すれば足りたものとも解される。)。
ただ、圧縮記帳制度が譲渡益又は受贈益に着目して帳簿価額を減額することに対し、組織再編成税制が帳簿価額を引き継ぐことにあるところ、後者が重視されたのは、当時のデフレ経済の下で多くの企業が欠損金を抱えているところ(注5)、譲渡損の繰延べが容易であったこととアメリカ税制を真似ることに利点があると考えたからであろう。譲渡損を繰延べるという点のみでは、現物出資についても、圧縮記帳制度のままで良かったとも言える。
(2)それらの問題はともかくとして、組織再編成税制では、まず、法人税法62条1項が、「内国法人が合併又は分割により合併法人又は分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときは、当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該合併又は分割の時に価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。」と定めている(注6)。そして、その例外として、適格合併等について資産等の帳簿価額による引継ぎを認めている(法法62の2〜62の6)。
その中に、適格現物出資については、法人税法62条の4が、「内国法人が適格現物出資により被現物出資法人にその有する資産を移転し、又はこれと併せてその有する負債の移転をしたときは、当該被現物出資法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格現物出資の直前の帳簿価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。」と定めている。
そして、その適格現物出資については、法人税法2条12号の14が、「外国法人に国内にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債の移転を行うもの及び外国法人が内国法人に国外にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債の移転を行うもの等を除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る」旨定めている。
この規定を受けて、法人税法施行令4条の3第10項は、「法第2条第12号の14に規定する国内にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債は、国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法(〈略〉)の規定による鉱業権及び採石法(〈略〉)の規定による採石権その他国内にある事業所に属する資産(外国法人の発行済株式等の総数の百分の二十五以上の数の株式を有する場合におけるその外国法人の株式を除く。)又は負債とし」と定めている。
(3)この規定の課税当局の解釈については、法人税基本通達1ー4ー12が、「令第4条の3第10項(〈略〉)に規定する「国内にある事業所に属する資産又は負債」に該当するかどうかは、原則として、当該資産又は負債が国内にある事業所又は国外にある事業所のいずれの事業所の帳簿に記載されているかにより判定するものとする。ただし、国外にある事業所の帳簿に記載されている資産又は負債であっても、実質的に国内にある事業所において経常的な管理が行われていたと認められる資産又は負債については、国内にある事業所に属する資産又は負債に該当することになるのであるから留意する。」と定めている。
また、上記通達の取扱いについて、国税庁の担当者は、「これは、一般に法人が有する資産又は負債については、その資産又は負債を経常的に管理している事業所の帳簿において記帳されていることが通常であろうから、原則として、国内、国外いずれの事業所の帳簿に記帳されているかにより国内の事業所に属している資産又は負債がどうかの判定をするというものである。ところで、国内の事業所に属する資産又は負債を現物出資をすることにより外国法人を設立するような場合、いったん一時的に国外の事業所に移管・記帳した上で、国外でその資産又は負債を現物出資して外国子会社を設立することがある。この場合、その出資資産は、出資直前に国外事業所の帳簿に記帳されていたことから国外の事業所に属する資産又は負債ではないかとの疑問が生ずる。しかし国外の事業所の帳簿に記帳されていたのは、国外で子会社を設立するための準備としてであり、そのように一時的に国外の事業所の帳簿に記帳されていたからといって国外の事業所に属する資産又は負債と判定するのではなく、あくまでも経常的に管理が行われていた場所で判定すべきである。」(注7)と説明している。
3 本件現物出資の「適格」該当性
(1)本件においては、内国法人であるXが、平成13年9月、米国法人GSKとの間で、医薬品用化合物の共同開発等を行うジョイントベンチャー(本件JV)を形成する契約を締結し、同契約に基づき、ケイマンにおいて、特例有限責任パートナーシップであるCILP(本件CILP)を設立し、そのパートナーシップ持分を保有していたが、その後の本件JVの枠組みの変更に際し、平成24年10月、本件CILP持分全部をXの英国所在の完全子会社SLに対し、現物出資、すなわち本件現物出資により移転したというものである。そして、Xは、本件CILP持分の持分割合に基づき、CILPに出資する義務やその収益及び費用等の配賦を受ける地位を有していたところ、本件CILP持分の管理については、「本件CILP持分は、国内にあるXの本社経理財務部が管理する有価証券台帳に投資有価証券として記帳されており、かつ、同台帳にはXが各出資を行ったことやCILPに係る費用等の配賦の結果等が適宜記帳されていた」(国の主張)というものである。そのため、上記取扱いに基づき、本件各処分が行われ、本訴において、当該処分の適法性が争われたというものである。
(2)本判決は、前述のように、本件における事実関係、就中、製薬事業において重要である外国企業との協力関係を詳細に認定し、「本件現物出資の対象資産は本件CILP持分であったと解するのが相当である。」と判示したものの、「その内実は、CILPの事業用資産の共有持分とLPとしての契約上の地位とが不可欠に結合されたものと捉えられなければならない。」と判示し、次いで、「CILPのパートナーシップ持分の価値の源泉はCILPの事業用財産の共有持分のパートナーとしての契約上の地位との関係は、前者を主とする主物と従たる権利義務との関係に類似する関係にあるものと捉えることが可能である。したがって、本件CILP持分を1個の資産とみた場合のその経常的な管理が行われていた事業所は、CILPの事業用財産、中でもその主要なものの経常的な管理が行われていた事業所とみるのが相当である。」と判示し、更に、「CILPの事業用財産は、①現金、②知的財産のライセンス、③治験データ等の無形資産、④USOpCoへの出資等で構成されている。」と判示した上で、これらの①から④までの事業用財産が米国の関係事業所で管理されていることを認定し、「CILPの事業用財産のうち主要なものの経常的な管理は、いずれにしてもGSK/ViiV側が米国その他の我が国以外の地域に有する事業所において行われていたということができる。」と認定し、「本件CILP持分は、その主たる構成要素であるCILPの事業用財産(の共有持分)のうち主要なものの経常的な管理が国内にある事業所ではない事業所において行われていたということができるから、「国内にある事業所に属する資産」には該当しない」と結論付けている。
(3)本判決については、「組合の持分の実体について、組合財産を中心として捉えた本判決の判断は、組合の私法的な性質に照らしても妥当なものと思われる。」(注8)と賛意を表する向きもあるが、前記1で述べたところの「国内にある資産その他国内にある事務所に属する資産」を圧縮記帳制度又は適格現物出資から除外した趣旨に照らすと、首肯し難い問題も残している。
けだし、「国内にある資産その他国内にある事務所に属する資産」を外国法人に現物出資することにつき、圧縮記帳制度なり適格現物出資の特例を認めないとした趣旨は、当該資産に係る含み益(キャピタルゲイン)相当額が我が国で課税できなくなることを防止しようとしたことにほかならない。ところが、本件においては、Xは、平成13年に本件JVを形成する契約を締結して本件CILPを設立し、平成24年に本件現物出資を行い、適格現物出資を適用して約400億円に相当する含み益に係る課税の繰延べを図ることができたというものである。このことは、Xは、平成13年に国内資金によって取得し、国内で管理していた本件CILP持分につき、約11年後に約400億円の含み益が持たらされたことを意味している。そして、当該含み益相当額につき、本件現物出資について適格現物出資の特例を認めると、将来、当該含み益相当額に対して我が国の課税権が及ばないことになる。
また、本判決は、「CILPの事業用財産の共有持分とパートナーとしての契約上の地位との関係は、前者を主とする主物と従たる権利義務との関係に類似する関係にある」として、当該主物の管理状況を殊更重視しているが、このような考え方は、本件CILPの独立した財産価値を無視したもので、「木を見て森(適格現物出資の課税制度の趣旨)を見ない」論法であるようにも考えられる。そのことは、本件CILP持分が、独立して本件現物出資の対象財産となっていることからも裏付けられる。
4 本判決の意義と問題点
(1)以上のように、本件は、我が国の大手製薬会社であるXが、ケイマンにおいて設立した本件CILPの持分全部を英国に所在する完全子会社SLに対し現物出資(本件現物出資)したことに関し、本件現物出資が法人税法上の適格現物出資の要件を充足しているか否かが争われたものである。国は、Xが本件CILP持分を国内にあるX社内で管理していること等を理由に、本件CILP持分が「国内にある事業所に属する資産」に該当するから、本件現物出資が適格現物出資に当たらない旨主張した。これに対し、本判決は、本件CILP持分を組成する事業用財産が米国法人において管理されているから、同持分は「国内にある事業所に属する資産」に該当しないとして、国の主張を排斥した。この判決については、本件CILPを我が国の「組合」に類似する事業体であることを強調してのことであるが、前述のような適格要件を制限した制度の趣旨に照らし疑問が残る。いずれにせよ、適格現物出資の要件が争われた数少ない事例として、本判決の意義がある。
(2)本件においては、Xが、法人税の確定申告をするにあたって、大阪国税局担当課長らから、本件現物出資は適格現物出資に該当する旨の口頭での回答(本件回答)を得ている。そのことが、本件各処分に信義則の適用があるか、過少申告加算税の賦課決定を免れる「正当な理由」(通法65④一)があるかも争われた。これらの争点については、本訴では、本件更正が取り消されたことにより審理されることはなかったが、仮に、本件更正が適法とされた場合に問題となる。
まず、租税法における信義則の適用については、合法性の原則の下厳しく制限されているが、次の各要件を充足したときにその適用があるものと解されている(注9)。
① 税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したこと
② 納税者がその表示を信頼し、その信頼過程において責められるべき事由を有しないこと
③ 納税者がその信頼に基づき何らかの行いをしたこと
④ 税務官庁がその公的見解の表示に反する行政処分をしたこと
⑤ 納税者が行政処分により救済に価する経済的不利益を被ったこと
本件に即して、結論のみ指摘すると、本件回答が口頭であるにせよ、国税局の担当課長からのものとすると、①の要件は充足するものと解されるが(注10)、本件現物出資(平成24年10月31日)が本件回答(平成24年11月19日)を待たずして実施されていることからすると、③の要件は充足しないものと解される(注11)。
また、国税通則法65条4項1号に定める「正当な理由」の存否については、本件回答が本件各処分が行われたことにより結果的には税務職員による誤指導にあったものと考えられるから、当該「正当な理由」があるものと解される(注12)。
(注1)現行法において圧縮記帳制度が認められるものとして、国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金不算入(法法42)、工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入(法法45)、非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入(法法46)、保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入(法法47)及び交換により取得した資産の圧縮額の損金算入(法法50)の5項目がある。
(注2)この事件は、オーブンシャホールディング事件と称されるが、詳細は、品川芳宣「重要租税判決の実務研究 第三版」(大蔵財務協会 平成26年)375頁等参照。
(注3)前掲の控訴審判決及び上告審判決は、X会社の課税関係を認めたが、主として、法人税法における非上場株式の評価方法が争われることになった。
(注4)国税庁「平成10年 改正税法のすべて」311頁参照。
(注5)圧縮記帳制度の下でも、帳簿価額の増額方法を採用すれば、譲渡損の繰り延べも可能である。
(注6)この規定自体は、法人税法22条2項の規定と重複しているものと解される(その必要性に疑問がある。)。
(注7)森文人編著「法人税基本通達逐条解説 六訂版」(税務研究会 平成23年)71頁参照。
(注8)佐藤修二・浜崎祐紀・野口大資「外国籍パートナーシップ持分のクロス・ボーダー現物出資と課税」本誌2020年6月8日号19頁参照。
(注9)最高裁昭和62年10月30日第三小法廷判決(訟務月報34巻4号853頁)、品川芳宣「税法における信義則の適用についてーその法的根拠と適用要件ー」税務大学校論叢8号1頁等参照。
(注10)前出(注9)「税法における信義則の適用について」23頁参照。
(注11)前出(注10)25頁参照。
(注12)申告所得税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)(平成12年7月3日付 課所4ー16ほか)、品川芳宣「附帯税の事例研究 第四版」(財経詳報社 平成24年)113頁以下、札幌地裁昭和50年6月24日判決(税資82号238頁)、那覇地裁平成8年4月2日判決(税資216号1頁)等参照。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.