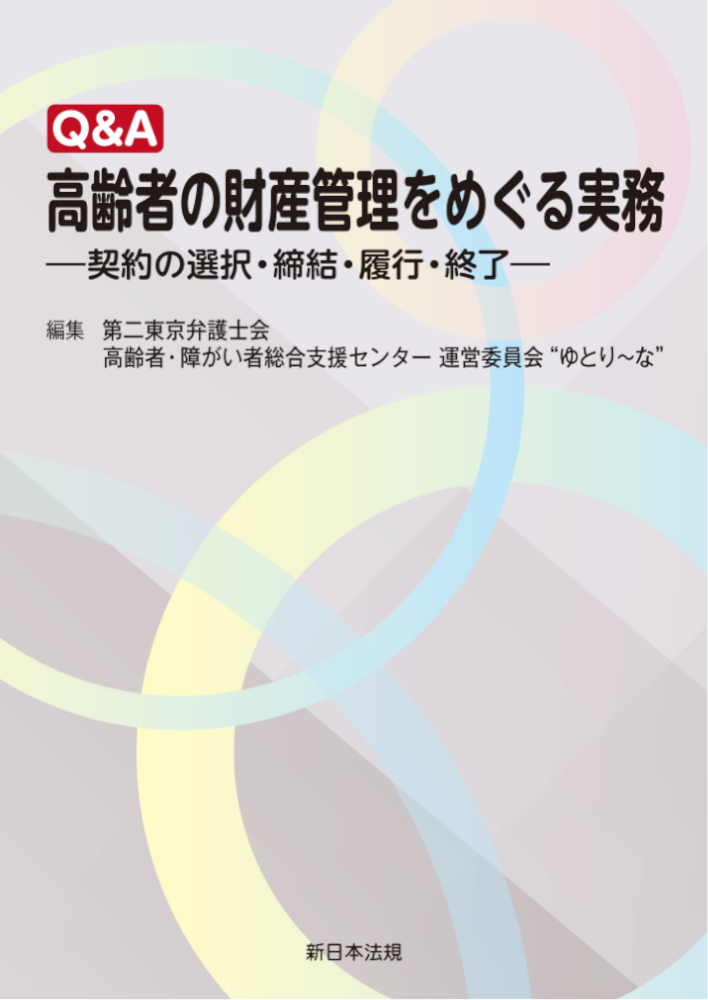一般2025年09月19日 利益相反の話 執筆者:石丸文佳
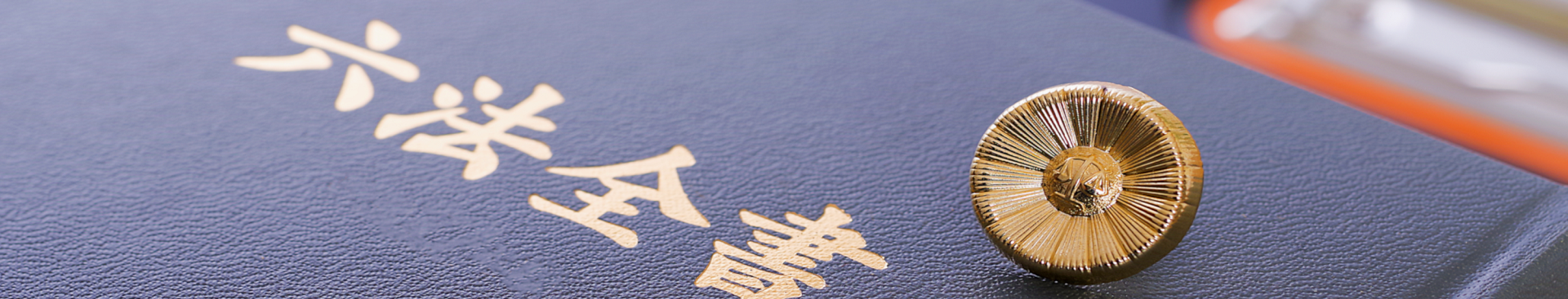
弁護士に禁じられているルールに、「利益相反」というものがあります。利益が相反する立場にある者から委任を受けてはいけないというものです。よくある例を挙げると、離婚相談を既に夫から受けていたら、利益が相反する妻からの委任を受けることはできません。
利益相反が禁じられているのは、一方から得た情報等を利用することで、他方に不利益をもたらす可能性が高いからです。
しかし、このルールはなかなか納得しがたい結論をもたらすことがあります。
私は以前、離島に派遣された法テラスの弁護士でした。法テラスの弁護士の使命として、全国にあまねく法の光を、というものがありますが、当時真っ先に思ったのは、自分が派遣された島以外の島にもリーガルサービスを届けたいということでした。
自分が派遣された島以外の島、とはまるでことば遊びのようですが、要するに日本の島は、単体で存在することはあまりなく、周囲にも島がたくさんあることが多いです。弁護士が派遣される島は、その中でも比較的大きく人口も多い島であることがほとんどですが、その周囲には全く弁護士がいない島もあるのです。要は、そういう弁護士がいない島にもリーガルアクセスを届けたいという野望?でした。
そこで始めたのが、出張相談です。法テラスは半ば公的な機関なので、弁護士がいない島にある役場に協力を求めて、何箇所か出張相談所を設けてもらい、毎月相談に出かけるというシステムを作りました。役場の協力を得たため、出張相談所の大半は町役場関連の施設でした。
とはいえ、そこで受ける相談は、必ずしも私人間のトラブルに留まるものではありません。法律相談には、行政トラブルも多く存在します。手すりのない橋から落ちてけがをした、これは危険な橋をそのままにしておいた行政の責任でないか、というような相談もあったのです。最終的に、このような争いは行政を相手取った国賠請求になるわけですが、行政の協力を得て行っている法律相談で、行政に対する訴えを引き受けるわけですから、協力したのに仇で返されたと思われる可能性もありました。
しかし、あくまで町は場所を提供するに留まり、法律相談内容については一切を関知していないこと、またそもそも、そのようなトラブルも解決することが住民の安心安全につながり、大所高所で言えば町の利益になることから、利益相反にはならないと解釈していました。そうでなければ、法テラスは行政の手先、行政の顧問に成り果てます。あまねく法の光をと言いながら、最も弱い住民の側に立てず、行政に有利になるようにしか動けないのでは存在意義がありません。とはいえ、法テラスの弁護士は街弁としての活動を行う反面、どうしても公的な色合いを持つものですから、こういうことが起こり得るのは想定の範囲内だったとも言えます。
ところが、法テラスの弁護士を辞し、純粋な街弁となった今でも、この手の問題には直面するのです。
私は消費者被害対策に取り組む弁護士ですが、消費者被害は判断能力に乏しい高齢者が遭うことが多く、しかも本人は被害に遭っていることに気づかないので、被害をまず覚知するのは周囲の人間、たとえばヘルパーやケアマネージャー等です。そうすると、このような人たちの消費者被害は、介護保険制度を提供している行政がもっとも把握している可能性が高く、行政との連携で被害が防げる可能性が高いです。消費者被害を解決し、判断能力が落ちている人が以後二度とそのような被害に遭わないように見守り、あるいは後見等の制度に繋げていくというわけです。
行政に信頼してもらい、安心して弁護士と連携してもらうために、最近は「顔の見える関係づくり」が推奨されています。積極的にアウトリーチ、つまり弁護士側から足を運んで関係性を作る活動なのですが、行政が信頼するのはその顔の見える関係性のある弁護士個人なので、場合によっては区との個人的な契約になります。しかし、このような関係になってしまうと、区に不満を持っていると思われる個人の相談には、その弁護士は利益相反で介入できなくなってしまいます。地域住民の安心安全のために行っているはずの連携活動が、どうしてか区のために行っているかのような色合いを帯びてしまうのです。
街弁として、以前法テラスの弁護士だったときと同じように、公的な弁護士ではなくなった分なお一層、自由に住民のための活動を行っていたはずなのに、何故か行政のための活動であるかのような状態になっているのは大変悩ましいことです。利益相反というルールは、ときに不思議な結論をもたらすものだと感じています。
(2025年9月執筆)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
執筆者

執筆者の記事
執筆者の書籍
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -