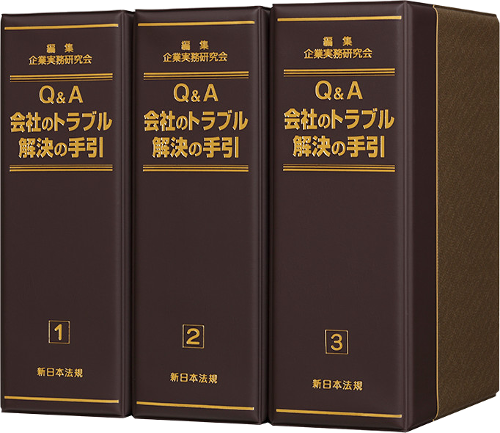労働基準2025年09月25日
公益性の高い専門職の働き方改革
裁判官・検察官・弁護士・医師・教員を比較する 執筆者:大川恒星

| 区分 | 公立学校教員 | 国・私立学校教員 |
|---|---|---|
| 適用法令 | 給特法(公立学校の教職員の給与等 に関する特別措置法) | 労働基準法 |
| 時間外労働命令 | 原則不可。 例外は「超勤4項目」 (①生徒の実習、②学校行事、③職員会議、 ④非常災害かつ「臨時又は緊急のやむを得ない 必要のある場合」) | 就業規則等の労働契約上の根拠と 36協定があれば可能 |
| 割増賃金 | 不要。代わりに「教職調整額」 | 必要(労働基準法37条)。 ただし、多くの国・私立学校で、 公立学校と同様、「教職調整額」で 処理され、未払いが生じることもある |
| 実態 | 部活動等で残業が常態化し、法制度と 実態が乖離 | 割増賃金不払いの例もあり、 制度との乖離が見られる |
(2025年9月執筆)
人気記事
人気商品
執筆者

大川 恒星おおかわ こうじ
弁護士・ニューヨーク州弁護士(弁護士法人淀屋橋・山上合同)
略歴・経歴
大阪府出身
私立灘高校、京都大学法学部・法科大学院卒業
2014年12月 司法修習修了(第67期)、弁護士登録(大阪弁護士会)
2015年1月 弁護士法人淀屋橋・山上合同にて執務開始
2020年5月 UCLA School of Law LL.M.卒業
2020年11月~ AKHH法律事務所(ジャカルタ)にて研修(~同年7月)
2021年7月 ニューヨーク州弁護士登録
2022年4月 龍谷大学法学部 非常勤講師(裁判と人権)
2024年4月 アジア・太平洋労働法制研究会委員
(法務省法務総合研究所・公益財団法人国際民商事法センター)
<主な著作>
「Q&A 感染症リスクと企業労務対応」(共編著)ぎょうせい(2020年)
「インドネシア雇用創出オムニバス法の概要と日本企業への影響」旬刊経理情報(2021年4月)
「中小事業者もこれだけは押さえたい!! ハラスメント対策のポイント解説」税理士のための税務特化情報誌「旬刊速報税理」ぎょうせい(2022年7月1日号)
「若手弁護士のための弁護実務入門2」(共著)成文堂(2023年)
「中小事業者のためのフリーランス新法対応ハンドブック」税理士のための税務特化情報誌「旬刊速報税理」ぎょうせい(2024年10月21日号)
「インバウンドビジネス法務Q&A」(共編著)中央経済社(2024年)
「テーマ別『インバウンド法務』の勘どころ 第5回 人事・労務」(共著)「ビジネス法務」中央経済社(2025年10月号)
<主な講演>
・2025年10月 法務省法務総合研究所・公益財団法人国際民商事法センター 主催 「アジア・太平洋法制研究会 第12回国際民商事法シンポジウム 東南アジア4か国の労働法制と実務対応」
・2022年10月 株式会社ぎょうせい 主催 「あなたの会社は大丈夫?!事例で学ぶハラスメント防止~ハラスメントをしない・させないために」
・2021年7月 在大阪インドネシア共和国総領事館主催・ジェトロ大阪本部共催 ウェビナー「インドネシアへの関西企業投資誘致フォーラム ―コロナ禍におけるインドネシアの現状と投資の可能性について」
・2019年2月 全国社会保険労務士会連合会近畿地域協議会・2018年度労務管理研修会「働き方改革関連法の実務的対応」
執筆者の記事
執筆者の書籍
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -