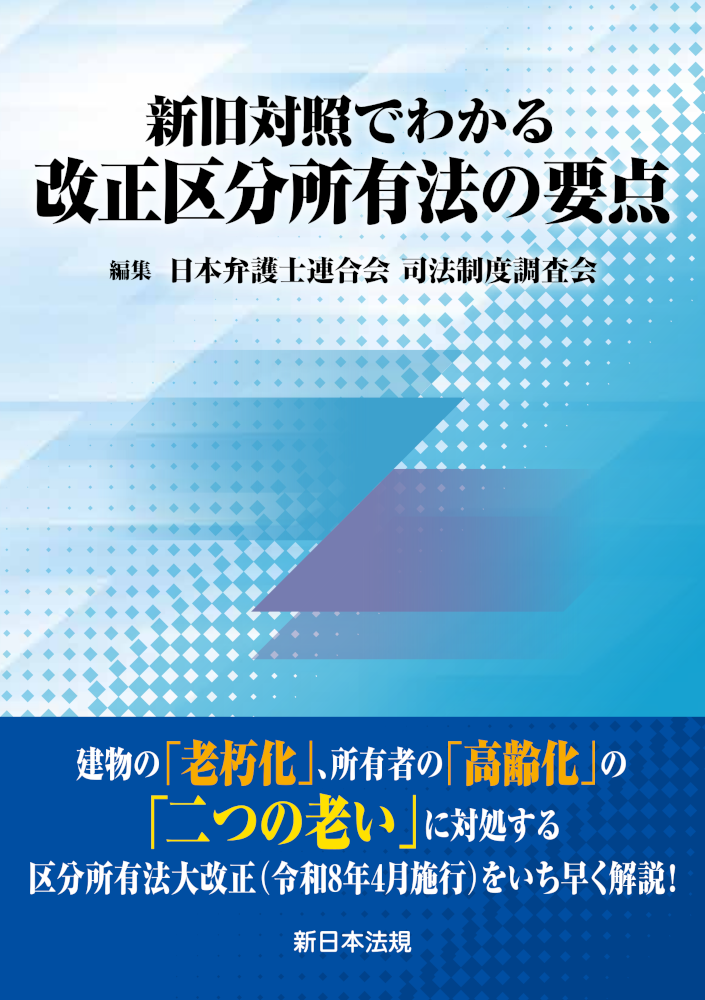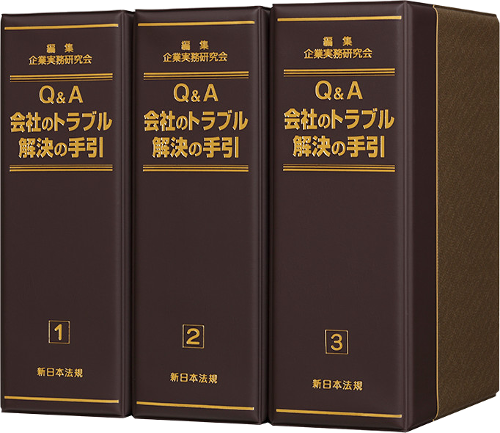労働基準2023年05月22日
今だからこそ、駐在員の労務管理について考えるべき(4)
~駐在員の安全管理-Part1 執筆者:大川恒星

今回から、2回に分けて、海外駐在(海外派遣)における駐在員の安全管理について取り上げます。
これまでと同様、駐在員1年目のAさんが、海外派遣先でメンタルヘルス不調になってしまった例をもとに考えることにしましょう。
なお、この事例については、前々回の拙稿「今だからこそ、駐在員の労務管理について考えるべき(3)~海外駐在において、「日本の労働法令が適用されるのか」-Part1」をご確認ください。
また、前々回の拙稿と前回の拙稿「今だからこそ、駐在員の労務管理について考えるべき(3)~海外駐在において、「日本の労働法令が適用されるのか」-Part2」では、この事例をもとに、「準拠法」と「国際裁判管轄」の2つの問題について整理しました。
企業の安全配慮義務違反を理由に、慰謝料等の損害賠償請求をしたいと考えたAさんにとっては、主たる事務所又は営業所が日本国内にある、所属元の日本国内の企業に対して、日本の裁判所で裁判を起こすことが比較的容易です(民事訴訟法第3条の2第3項)。
日本の裁判所に管轄権が認められると、この事例では、労働契約法上の安全配慮義務(同法第5条)が問題となることから、準拠法の問題として、日本の「国際私法による準拠法決定ルール」である「法の適用に関する通則法」(以下、「通則法」といいます。)が適用されます。通則法のもと、駐在員や所属元の日本国内の企業等は、彼らにとって予測可能性の高い日本法、すなわち、日本の労働法令の適用を求めていくことになるのだろう、というのが前回の拙稿のまとめでした。詳しくは、前回の拙稿をご確認ください。
そこで、以下では、Aさんが、企業の安全配慮義務違反を理由に、慰謝料等の損害賠償を求めるため、所属元の日本国内の企業に対して、日本の裁判所で裁判を起こし、準拠法については、日本法であることを前提に話を進めていくことにしましょう。
1 安全配慮義務とは
労働契約法第5条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と規定し、企業の従業員に対する安全配慮義務を明記しています。
2 所属元の日本国内の企業の安全配慮義務
それでは、所属元の日本国内の企業は、安全配慮義務を負うのでしょうか。
この際、「(在籍)出向」、「転籍」、「海外支店への配置転換」の海外駐在のパターンごとに、または、海外駐在とは異なる「海外出張」と比較して分析することは有用です。3つの海外駐在のパターン及び海外出張の詳細については、過去の拙稿「今だからこそ、駐在員の労務管理について考えるべき(2)~駐在員の海外派遣を命じることはできるのか」をご確認ください。
(1) 海外支店への配置転換・海外出張の場合
まず、海外支店への配置転換、また、海外出張であれば、所属元の日本国内の企業に籍を残したままで、かつ、海外派遣先・海外出張先との間で別途労働契約が存在するわけでもありませんので、当然ながら、所属元の日本国内の企業(のみ)が、労働契約に従い、安全配慮義務を負うことになります
(2) 出向の場合
また、出向では、海外の子会社や関連会社に所属して、現地の使用者の指揮に従って勤務することになるものの、出向元の日本国内の企業に籍を残したままではありますので、やはり、出向元の日本国内の企業も、労働契約に従い、安全配慮義務を負うことになります。
もっとも、駐在員は、出向先である海外の子会社や関連会社との間でも労働契約関係があり、また、出向先の指揮のもと、出向先に対して労務の提供を行っているわけですから、第一次的には出向先が安全配慮義務を負うことになります。
では、出向元のいわば第二次的な安全配慮義務違反の責任は、どのような場合に生じるのでしょうか。
大成建設事件(福島地判昭和49・3・25判時744号105頁)、協成建設工業ほか事件(札幌地判平成10・7・16労判744号29頁)、A鉄道(B工業C工場)事件(広島地判平成16・3・9労判875号50頁)、デンソー(トヨタ自動車)事件(名古屋地判平20・10・30労判978号16頁)、JFEスチール(JFEシステムズ)事件(東京地判平成20・12・8労判981号76頁)等の過去の裁判例(左記の事件はいずれも国内の出向事案ですが、同じ出向である以上、海外出向であってもその考え方は当てはまります。)に照らせば、実態に即して、出向元が、駐在員の出向先での就労状況や健康状態を認識していたのか、あるいは、それらを認識し得たのか、また、かかる認識や認識可能性をもとに、安全配慮義務の一環として何をすべきであったのかが個別具体的に判断されるものと考えられます。
例えば、出向元が海外駐在の途中、駐在員から出向先での就労の悩み(海外勤務のストレスで体調が優れないなど)について相談を受けたのであれば、それをもって、その問題を認識した以上、安全配慮義務の一環として然るべき対応が求められます。また、出向元が出向先での就労について、主体的に労働時間管理等の労務管理を行っているのであれば、第一次的な安全配慮義務を負うこともあり得ます。さらに、出向元が、就労環境が国内とは大きく異なる海外に駐在員を出向させるとの判断を下すわけですから、出向の開始時に、出向先の状況に応じて、駐在員の生命・身体の安全を確保するための人的・物的な体制の整備が求められることもあるでしょう。
このように、出向元の安全配慮義務違反の成否は、ケースバイケースで事後的に判断されますので、出向元としては、出向先に丸投げするのではなく、駐在員の生命・身体の安全を確保すべく、できる限りの配慮をすることが基本的な対応スタンスとなるでしょう。
(3) 転籍の場合
一方で、転籍の場合、転籍元は安全配慮義務を負うことはあるのでしょうか。
転籍では、自身が所属する日本国内の企業から籍を抜いたうえ、海外の子会社や関連会社に所属して、現地の使用者の指揮に従って勤務することになります。つまり、出向とは異なり、転籍元との労働契約関係は終了する一方で、新たに転籍先との労働契約関係が始まるわけです。
すると、素直に考えれば、転籍元との労働契約関係が終了する以上、転籍元には、労働契約法第5条に基づく安全配慮義務は発生しないことになりそうです。
しかし、国内の転籍事案ではあるものの、オタフクソース事件(広島地判平成12・5・18労判783号15頁)では、転籍元の安全配慮義務違反の責任が認められました。
そして、安全配慮義務は、労働者と労働契約関係ないし特別な社会的接触関係(労働契約に準ずる関係)に基づき発生するものとされており、必ずしも直接の労働契約関係がなくとも発生するものです。
転籍とはいえ、駐在員の場合、多くは数年以内の復帰が予定されており、転籍元との関係性は残るわけですから、転籍という法形式を選択したからといって、直ちに転籍元が安全配慮義務を免れるとは言えないと考えます。
したがって、出向と同様、転籍元の安全配慮義務違反の成否は、ケースバイケースで事後的に判断されますので、転籍元としては、転籍先に丸投げするのではなく、駐在員の生命・身体の安全を確保すべく、できる限りの配慮をすることが基本的な対応スタンスとなるでしょう。
3 最後に
次回は、派遣元である日本国内の企業が安全配慮義務の一環として何をすべきかについて具体的に掘り下げたいと思います。
(2023年5月執筆)
人気記事
人気商品
執筆者

大川 恒星おおかわ こうじ
弁護士・ニューヨーク州弁護士(弁護士法人淀屋橋・山上合同)
略歴・経歴
大阪府出身
私立灘高校、京都大学法学部・法科大学院卒業
2014年12月 司法修習修了(第67期)、弁護士登録(大阪弁護士会)
2015年1月 弁護士法人淀屋橋・山上合同にて執務開始
2020年5月 UCLA School of Law LL.M.卒業
2020年11月~ AKHH法律事務所(ジャカルタ)にて研修(~同年7月)
2021年7月 ニューヨーク州弁護士登録
2022年4月 龍谷大学法学部 非常勤講師(裁判と人権)
<主な著作>
「Q&A 感染症リスクと企業労務対応」(共編著)ぎょうせい(2020年)
「インドネシア雇用創出オムニバス法の概要と日本企業への影響」旬刊経理情報(2021年4月)
<主な講演>
・2021年7月 在大阪インドネシア共和国総領事館主催・ジェトロ大阪本部共催 ウェビナー「インドネシアへの関西企業投資誘致フォーラム ―コロナ禍におけるインドネシアの現状と投資の可能性について」
・2019年2月 全国社会保険労務士会連合会近畿地域協議会・2018年度労務管理研修会「働き方改革関連法の実務的対応」
執筆者の記事
執筆者の書籍
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.