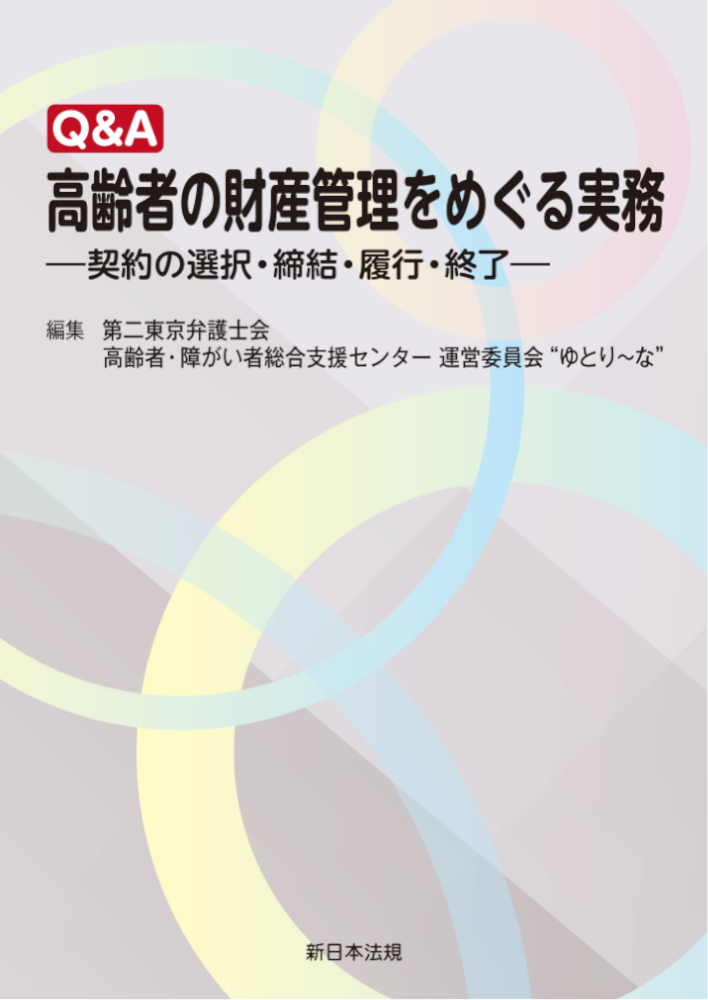一般2025年06月30日 身元「保証」「引受」って何ですか? 執筆者:亀井真紀

ここ数年ずっともやもやしている言葉があります。後見業務の中で、また時には当事者として病院や施設の申込書、契約書に出てくるあれです。長々と契約条項や重要事項説明書などの最後に出てきてサインを求められる「身元保証人」「身元引受人」という言葉です。
ちなみに「身元保証に関する法律 」というものがありますが、この法律で定めているのは雇用関係等において被用者の行為によって使用者が被った損害を身元保証人が保証することなどです。病院や施設に入る局面において雇用関係を結ぶわけではないことは明らかなので適用されるものではありません。
そうだとすれば私がもやもやしている「身元保証人」「身元引受人」とは?ということで、一応検索サイトで調べてみたら、人工知能のAIさんがご丁寧に以下のように教えてくれました。
「身元保証人とは、ある人物(被保証人)の身元(素性、経歴、信用)を保証する人、またはその人が何か問題を起こした際に、本人の代わりに責任を負う人のことです。主に就職や賃貸、病院の入院、老人ホームの入所などの際に必要とされます。」
ほう、就職時や賃貸借契約時と同じですか・・ええ!?と思いませんか。前述の通り「身元保証に関する法律」は雇用関係を結ぶ場面で使われる法律であり、身元保証人の義務は被保証人である労働者の不正やミスで損害が生じた場合の損害賠償責任を負うこととされています。おそらく病院や施設も「身元保証人」に求めている役割はそこではないですよね。入居者が仮に何か問題を起こしたとしても、労働者の不正やミスと同様に考えられるものでもありません。AIさん何かちょっと違うんじゃないですか。
ということで、今度は「身元引受人」で調べてみました。ご指名したわけでもないのにまたまたAIさんが以下のように教えてくれました。
「身元引受人とは、逮捕された被疑者や被告人の身柄を引き受け、釈放・保釈後の生活を監督する人を指します。具体的には、被疑者や被告人が逃亡したり、罪証隠滅したりするリスクを軽減するために、身元引受人が監督を約束することで、釈放や保釈が認められやすくなります。」
なるほどなるほど。確かに私も刑事弁護人として勾留阻止を求める時にご家族に「身元引受書」を頂いて裁判所や検察庁に提出します。釈放や保釈が認められやすくなるという点はそんな単純ではないよと言いたいところですが、それはさておき、私がここで聞きたいのは病院や施設に入る際に求められる「身元引受人」ですよ!それじゃないんですけど!もはやAIさんとの意思疎通には限界を感じました。
さて、思うに、このような言葉の混迷ぶりこそが、私がこの言葉にもつもやもや感を引き起こしているのではないでしょうか。法律用語でもないのに契約書にあたかも指定席のように置かれ、実は明確な定義もない、場面によって異なる意味を持つ・・だけどここにサインをと求められてしまう、法律家としては納得がいきません。実際は「?」と思っている人はそれなりにいるのではないでしょうか。そして、本当の問題は「?」と感じながらも、サインをしなければ入院や入所をさせてもらえないと思い、よく分からないままにサインすることを余儀なくされているという現状です。
私の経験では、実際は契約書や約款をよくよく読むと「身元保証人」「身元引受人」の義務や役割について明記されていることもあります。それは時に民法で言うところの連帯保証人であったり、亡くなった時のご遺体の引受人であったり、救急時の連絡先だったりと様々です。弁護士が職務として連帯保証人となるわけにはいかないので私の方であくまでも後見人としての責務は負う前提で「身元保証人」「身元引受人」という記載は二重線で消させてもらい、代わりに「後見人」とだけ書くことで了解を得る場合もしばしばあります。実際は、そのように柔軟に対応して頂いている病院や施設も多くあるのは分かっています(なので責めているわけではないのですよ)。
ただ、弁護士ならば契約条項を確認し、また疑問点を指摘し、時には修正を求めることができても、これが一般の方であればどうなのでしょうか。特に、病院への入院や施設の入居時というのは、いつも以上に、ご本人含めご家族なども心身ともに疲弊し、弱っていることが容易に推測されます。そのような中で、定型の契約書書式を示され、サインを求められれば、よく分からなくても「とりあえず」サインをしてしまうのが常ではないでしょうか。
そもそも厚生労働省(医政局)は、身元保証人等がいないことのみを理由に、医師が患者の入院を拒否することは、医師法第19条第1項にいう「正当な事由」にならないことを示し、各都道府県に対し、このような事例に関する情報に接したときは適切な指導を求める通知を各都道府県の衛生主管部(局)長宛に発出しています(医政医発0427第2号 /平成30年4月27日)。
また、厚生労働省(老健局)が各都道府県の介護保険主管部(局)長宛に発出した通知(老高発0830第1号、第2号 )で は、「介護保険施設に関する法令上は身元保証人等を求める規定はなく、各施設の基準省令においても、正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできないこととされており、入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当しない。」ことが示されてもいます。
しかし、これらの通知によっても「身元保証人等」を求めることを禁じているわけでもなく、現実にはまだまだ多くの契約や申込場面で「身元保証人」や「身元引受人」が求められています。病院や施設の立場で費用を何らかの方法で 担保しておきたい、緊急連絡先を確保しておきたい、亡くなった場合の対応をしてくれる人を明確にしておきたい等々のニーズがあることは理解します。「おひとりさま」社会と言われるように身寄りのない方が増えている情勢からすれば受け入れる側にとって重要なことであり、そういった役割を担う人を求めること自体が悪いとは思いません。
ただそうであるならば、求めている意味内容を個別に説明し、役割や責務を具体的に分かりやすく明記する、身元保証人を用意できない人には別の選択方法を最初から提案するなどの工夫はあってしかるべきです。抽象的に「身元保証人」「身元引受人」を求めて記載させるだけでは、その意味内容に認識齟齬が生じてかえってトラブルの元でもあります。そういった人を用意できないと入院や入居はできないと誤解させ結果的にサービスの提供を受けることを躊躇させるようなことがあってはなりません。
病院への入院、施設の入居などは人生において誰しもが当事者として遭遇する場面です。多くの人のもやもやが少しでもなくなるよう小さなことから改善していきたいものです。
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
(2025年6月執筆)
人気記事
人気商品
執筆者

亀井 真紀かめい まき
弁護士
略歴・経歴
第二東京弁護士会所属。
平成13年弁護士登録。北海道の紋別ひまわり基金法律事務所(公設事務所)に赴任。
その後、渋谷の桜丘法律事務所(現事務所)に戻り現在に至る。
第二東京弁護士会高齢者・障がい者総合支援センター委員会、日弁連高齢者・障害者権利支援センター委員会等所属。
一般民事・家事、刑事事件のほか、成年後見、ホームロイヤー契約等高齢者、障がい者の事件を多く担当する。
執筆者の記事
執筆者の書籍
関連カテゴリから探す
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -