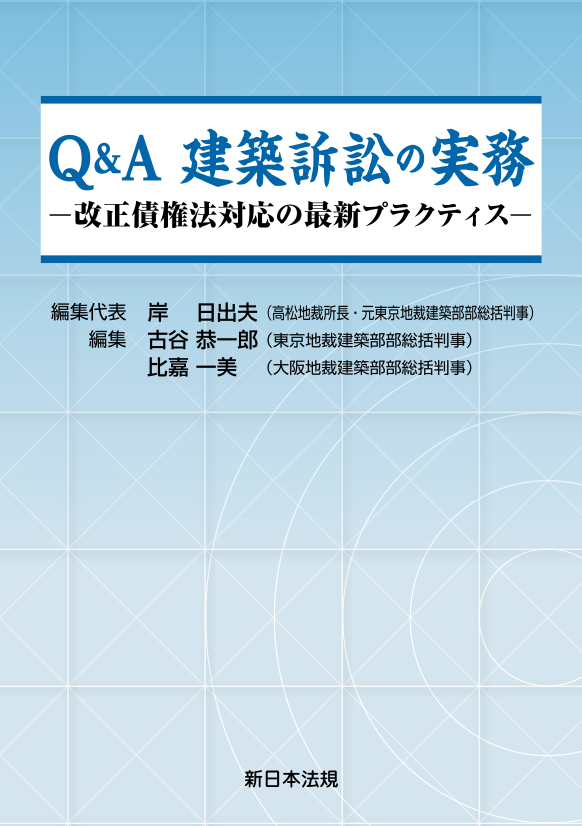民事2021年07月20日 瑕疵ある建築物の施工会社に対する第三者の責任追及 執筆者:政岡史郎

1. 先日、東京都八王子市で、賃貸アパートの外階段が腐食により崩れ、住民の方が階段から転落死されるという痛ましい事故がありました。また、私が相談を受けている事案の中には、投資用の中古賃貸マンションを一棟購入した相談者が、更に第三者にそのマンションを売却した後で、マンションの壁のタイルに剥離(「浮き」)が見つかり、マンション居住者に危険を及ぼしかねないというものがあります。
2. このような建物の危険性は、経年劣化で生じる場合もあれば、欠陥・瑕疵によって生じる場合もあると思います。
では、そのような建物で被害を被った場合、誰にどのように責任追及をすることが出来るのでしょうか。
法律家としては、「誰かが誰かに何かを請求する」場合の法律的な根拠としては、まず「当事者間に何かしらの契約関係(合意)が存在していないか」を考えます。
例えば最初の事例(八王子の賃貸アパート)では、転落死された方の遺族は、まずは契約関係(賃貸借)にあった大家さんに対して、賃貸人が負う「建物を適切に修繕して安全な状態に維持しておく義務」の違反を主張していくのがセオリ―だと思います。
また、次の事例(タイルに剥離のあるマンションの転売事例)では、壁のタイルの剥離があることを発見した買主(現所有者)は、売主に対し、売買契約上の瑕疵担保責任(契約不適合責任)に基づく修補請求や損害賠償請求をすることが考えられます。
3. では、居住者や買主に損害賠償をした後で、その損失を補填することが出来るでしょうか。
最初の事例(八王子の賃貸アパート)は、所有者が施工業者に注文して当該アパートを建築したようなので、直接の契約関係(ここでは請負契約)のある施工業者に対して、請負契約上の債務不履行等を理由に損害賠償請求出来る可能性があります。
次の事例(タイルに剥離のあるマンションの転売事例)の場合はどうでしょうか。
この件は、当初の所有者Aが施工会社にマンションを建ててもらい、数年してから相談者Bに売却し、相談者Bが更に数年後に買主Cに売却したというものでした。
相談者Bは、買主Cから、築年数に比して多すぎる剥離の分について、瑕疵担保責任として修補費用相当額の損害賠償金を支払いました。
そこで、相談者Bも、当初の所有者Aに対して瑕疵担保を理由に損害賠償請求しようと考えましたが、不動産売買によくある瑕疵担保責任の期間制限(中古の建物の場合、たいてい、引渡しから3か月程度)に阻まれ、当初の所有者Aには損害賠償請求できませんでした。
相談者Bは、単に当初の所有者Aからマンションを買っただけなので、施工会社とは何も契約関係は無く、請負契約上の責任追及は出来ません。
しかし、この様な場合、法律上は、「不法行為」制度を用いて、契約関係に無い施工会社に責任追及できる場合があります。
例えば、タイルの貼り方に施工上の不良があるのであれば、民法709条の不法行為を用いて、買主Cに支払ったのと同等の金額を「損害」として賠償請求することが可能となります。相談者Bは既にマンションの所有者ではないので、マンションのタイルの剥離等を理由に施工会社に請求できるというのが何となく不思議な感じもありますが、施工不良が無ければ、売った後に買主Cに損害賠償する必要も無かったわけで、施工不良の存在、その不良と相談者Bの損害との因果関係等を立証できれば、損失を埋めることが可能となります。
4. マンションの壁に貼られているタイルの剥離(「浮き」)や落下事故が実際に生じるのは、建築から数年、場合によって10年以上経過してからで、その時には、施工会社と直接の契約関係にない第三者に転々と所有権が移っている場合も良くあります。
そのため、過去の設計関係資料は散逸し、施工当時の技術的水準(や守るべき施工手順)などを明らかにすることや、施工手順が守られていなかったことを主張立証することは実務的に極めて困難が予想されますが、築年数に応じた一定の剥離率を超えた場合には施工不良が推認されるとの考えもあり、被害者の救済が不可能なわけではありません。
昨今、建築関係の紛争において、タイル剥離等を原因とした不法行為の損害賠償請求訴訟が多くみられているとも言われており、今後、社会的に耳目を集めていくかもしれません。
(2021年7月執筆)
関連商品
執筆者

政岡 史郎まさおか しろう
弁護士
略歴・経歴
H7 早稲田大学卒業、小田急不動産(株)入社
H13 同社退社
H17 司法試験合格
H19 弁護士登録・虎ノ門総合法律事務所入所
H25 エータ法律事務所パートナー弁護士就任
著書
「ある日、突然詐欺にあったら、どうする・どうなる」(明日香出版社 共著)
「内容証明の文例全集」(自由国民社 共著)
「労働審判・示談・あっせん・調停・訴訟の手続きがわかる」(自由国民社 共著)
「自己破産・個人再生のことならこの一冊」(自由国民社 校閲協力)
執筆者の記事
この記事に関連するキーワード
関連カテゴリから探す
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -