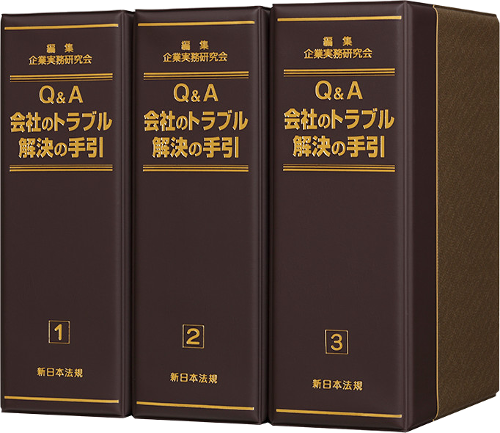労働基準2025年01月23日 外国人や外国企業からの人事労務相談はニッチな分野ではない?! 執筆者:大川恒星

1 前述の本国に滞在したままの越境リモートワークであれば、通則法における最密接関係地法に関する労務提供地を特定することができるのかという複雑な問題も生じる。この場合、労務提供地は日本とも本国とも解釈し得ることから労務提供地を特定することができない場合として、通則法12条2項かっこ書きに基づき当該労働者を雇い入れた事業所の所在地の法を最密接関係地法とする解釈もあり得よう。この点に関連して、国際線の客室乗務員としての業務であるから、労務提供地は、航空機の飛行する複数の法域にまたがっているとして労務提供地を特定することができない場合に当たると判断したケイ・エル・エム・ローヤルダッチエアーラインズ事件・東京地判令和5年3月27日労判1287号17頁がある。
2 外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れや離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークに届け出ることが義務づけられている(28条) 。ただし、外交・公用の在留資格者および特別永住者は除かれる。届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となる(40条1項2号)。
(2025年1月執筆)
人気記事
人気商品
執筆者

大川 恒星おおかわ こうじ
弁護士・ニューヨーク州弁護士(弁護士法人淀屋橋・山上合同)
略歴・経歴
大阪府出身
私立灘高校、京都大学法学部・法科大学院卒業
2014年12月 司法修習修了(第67期)、弁護士登録(大阪弁護士会)
2015年1月 弁護士法人淀屋橋・山上合同にて執務開始
2020年5月 UCLA School of Law LL.M.卒業
2020年11月~ AKHH法律事務所(ジャカルタ)にて研修(~同年7月)
2021年7月 ニューヨーク州弁護士登録
2022年4月 龍谷大学法学部 非常勤講師(裁判と人権)
2024年4月 アジア・太平洋労働法制研究会委員
(法務省法務総合研究所・公益財団法人国際民商事法センター)
<主な著作>
「Q&A 感染症リスクと企業労務対応」(共編著)ぎょうせい(2020年)
「インドネシア雇用創出オムニバス法の概要と日本企業への影響」旬刊経理情報(2021年4月)
「中小事業者もこれだけは押さえたい!! ハラスメント対策のポイント解説」税理士のための税務特化情報誌「旬刊速報税理」ぎょうせい(2022年7月1日号)
「若手弁護士のための弁護実務入門2」(共著)成文堂(2023年)
「中小事業者のためのフリーランス新法対応ハンドブック」税理士のための税務特化情報誌「旬刊速報税理」ぎょうせい(2024年10月21日号)
「インバウンドビジネス法務Q&A」(共編著)中央経済社(2024年)
「テーマ別『インバウンド法務』の勘どころ 第5回 人事・労務」(共著)「ビジネス法務」中央経済社(2025年10月号)
<主な講演>
・2025年10月 法務省法務総合研究所・公益財団法人国際民商事法センター 主催 「アジア・太平洋法制研究会 第12回国際民商事法シンポジウム 東南アジア4か国の労働法制と実務対応」
・2022年10月 株式会社ぎょうせい 主催 「あなたの会社は大丈夫?!事例で学ぶハラスメント防止~ハラスメントをしない・させないために」
・2021年7月 在大阪インドネシア共和国総領事館主催・ジェトロ大阪本部共催 ウェビナー「インドネシアへの関西企業投資誘致フォーラム ―コロナ禍におけるインドネシアの現状と投資の可能性について」
・2019年2月 全国社会保険労務士会連合会近畿地域協議会・2018年度労務管理研修会「働き方改革関連法の実務的対応」
執筆者の記事
執筆者の書籍
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -