契約2025年08月22日 ライセンス契約①(英文契約書(7)) 執筆者:矢吹遼子
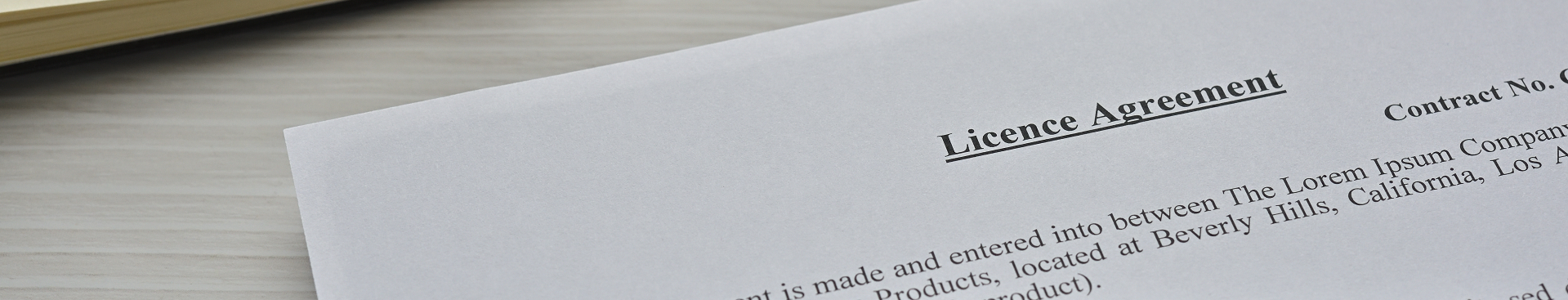
ライセンス契約とは、知的財産権の権利者(ライセンサー)が、契約の相手方(ライセンシー)に対し、その権利の使用を許諾する契約をいいます。知財の利用を通じてビジネス展開を加速させる手段として有効ですが、契約内容次第で将来的な権利関係や事業運営に大きな影響を与えるため、慎重な検討が欠かせません。
1. ライセンス契約のメリット・デメリット
ライセンサー側のメリットは、第一にライセンス料収入が得られることです。特に海外市場へ進出する場合、自社で支店や工場を設立するには莫大な費用がかかりますが、現地のライセンシーを通せば低コストで市場開拓が可能です。一方でデメリットとしては、品質管理をライセンシーに委ねる場合、品質低下がブランドの信用力を損なうリスク、不正使用の危険性があります。契約違反を常時把握することは容易ではありません。
ライセンシー側のメリットは、開発リスクやコストを削減でき、既に市場で信頼のあるブランドを活用して収益化できることです。反面、デメリットとしてロイヤルティや最低支払額(ミニマムロイヤルティ)が経費負担となるほか、契約解除・更新拒絶で事業継続が困難になるおそれがあります。
2. クロスボーダーにおける知財リスク
知的財産権は国ごとに独立しており、日本での特許・商標登録は自動的に海外でも有効になるわけではありません(著作権は例外的に国境を越えた効力が認められます)。海外で製品を製造・販売する場合、その国での権利登録を怠ると、模倣を止められず、ロイヤルティ請求や損害賠償もできません。逆に登録しない間に現地企業に先に登録され、侵害の主張を受けることもあり得ます。一方で、外国で出願をするとなると、現地代理人に現地の用語で行っていただく必要があり、費用も相当かかりますので、事業活動を行いうるあらゆる地域で出願をするというのは現実的ではありません。このため、外国での出願にあたっては、事業計画に沿って費用対効果を踏まえた検討が必要です。国際的な出願制度としては、
があります。
また、進出先で第三者権利を侵害しないよう事前調査が必須です。WIPO(WIPO - World Intellectual Property Organization)や米国特許商標庁(USPTO、United States Patent and Trademark Office)の公開データベースで現地の商標登録状況を確認することができます。
3. 契約書冒頭と定義条項の重要性
英文契約では、契約冒頭に大文字で始まる定義語が多数登場します。大文字で始まる用語は必ずDefinitions条項を確認する習慣が重要です。長い契約では定義条項が10ページ以上に及ぶこともあり、面倒に感じても読み飛ばすべきではありません。定義が不明確だと契約解釈の齟齬を招きかねないため、ライセンス契約においては技術担当者とも確認しつつ漏れや曖昧さのない定義付けを行うことが重要です。
例えば、Net Selling Priceの定義はロイヤルティ算定の基礎となりますので、非常に重要です。典型的には、製品の総販売価格(gross selling price)から、特定の税金、関税、輸送費、リベート・ディスカウント等を控除できる旨記載されます。リベートやディスカウント等の控除については、“customarily and actually allowed”といった曖昧な表現にされることもありますが、例えば“not exceeding 5 percent”などと明記して紛争を防ぐ工夫が求められます。
4. 実施許諾(Grant of License)の基本
ライセンス契約の中核条項であるGrant of Licenseでは、 “Licensor hereby grants to Licensee an exclusive, non-sublicensable, non-transferable right and license to manufacture, use and sell the Product..”というような記載がなされています。
・独占的か非独占的か(Exclusive / Non-Exclusive)
日本の特許法には、専用実施権と通常実施権があります。通常実施権には独占的なものと非独占的なものがあります。“Exclusive”というのは、日本の特許法上の「専用実施権」とは異なる概念であり、通常は、「独占的通常実施権」を指すことが多い点に注意が必要です。専用実施権を意味する場合は、ローマ字で記載したり、特許法条文を明示したりするなどの対策が望まれます。独占的通常実施権(Exclusive)の場合に、ライセンサー自身が実施できるかは契約で定める事項ですので、ライセンサー自身が実施したい場合は、契約書にその旨明記しておくことが必要です。
・サブライセンスの可否(Sublicensable / Non-Sublicensable)
ライセンサーは拒否する場合が多く、認める場合であっても、サブライセンシーの信用調査や範囲制限が必要です。子会社へのサブライセンスでも緩い取り決めはリスクとなります。
・譲渡可能性(Transferrable / Non-Transferrable)
権利義務の譲渡は通常制限されます。
その上で、許諾期間、許諾地域、用途制限などを設けますが、ライセンサーとしては、許諾する権利の種類・範囲、用途や地域を必要最小限に慎重に定義することが肝要です。
5.技術支援条項(Technical Assistance)
ライセンス契約には、技術支援(Technical Assistance)条項が含まれることもあります。これはライセンサーがライセンシーに対し、ライセンス対象技術の実施に必要な技術指導やトレーニングを提供する義務を定めるものです。例えば、ライセンサーの技術者を一定期間ライセンシーの施設に派遣し、製品の設計・製造・設置に関する支援を行う、といった内容です。実務上の注意点としては、支援期間(例えば通算○○人日までなど)や費用負担(旅費・滞在費等をどちらが負担するか)を明確に定めておくことです。航空券やホテルのクラスも指定されている方が望ましいです。技術支援条項はライセンシーにとって技術移転を円滑にするメリットがありますが、ライセンサーにとっては負担にもなるため、提供内容や期間を限定し、追加支援は別途有償契約とするなどの調整が行われます。また、契約締結の前提として、提供する技術を使いこなすことができるライセンシーかどうかをきちんと調査する必要があります。
(2025年8月執筆)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
執筆者

矢吹 遼子やぶき りょうこ
弁護士(弁護士法人 本町国際綜合法律事務所)
略歴・経歴
平成21年弁護士登録(大阪弁護士会)。
弁護士法人 本町国際綜合法律事務所所属。
CEDR(Centre for Effective Dispute Resolution)の認可調停人。
契約書(和文・英文)のリーガルチェックや作成等の国際案件、一般民事、家事事件を多く担当する。
薬害肝炎訴訟、全国B型肝炎訴訟、HPVワクチン(子宮頸がんワクチン)薬害訴訟にも参加。
執筆者の記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























