相続・遺言2025年10月20日 故人の遺志と遺留分侵害額請求 執筆者:政岡史郎
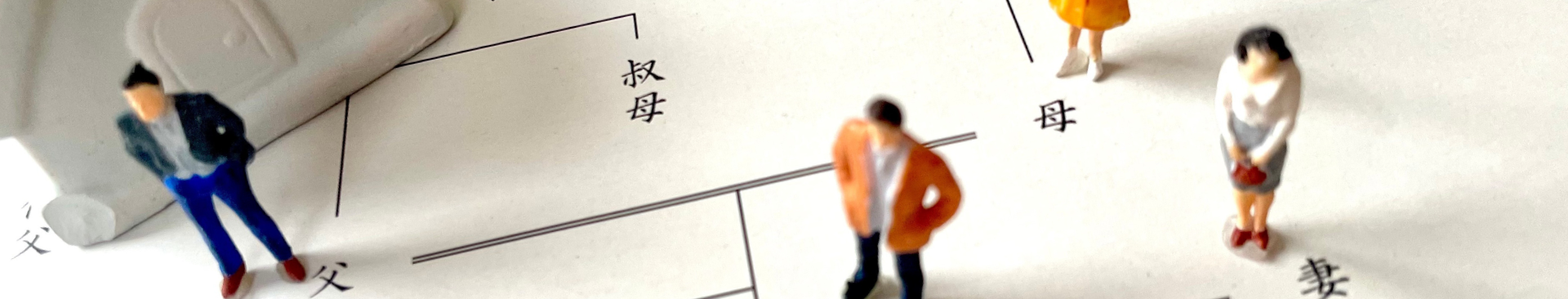
ここ数年、遺言公正証書の作成件数が増えているようです。
日本公証人連合会によれば、以下の通り、対前年比数%の増加傾向で、コロナ禍前(2019年)と2024年を比べると13%も増えています。恐らく、直筆で作成する「自筆証書遺言」も同様に増えていると思います。ちなみに、遺言書作成のボリュームゾーンと思われる65歳以上人口はこの期間で1%しか増えていないので、単純に分母が増えたからという訳ではなさそうです。

誰でも、生きている間は自分の財産を自由に使ったり貯めたり、寄付や贈与をすることができます。その「生きている間は財産を自由に処分できる」ことの延長というか表裏一体の問題として、死後の財産についても自由に決めておきたい方が増えているのだと思います。
遺言書がある場合のトラブルで良く挙げられるのが、法定相続人の「遺留分」(民法1042条)です。
「遺留分」というのは、大まかにいえば「法定相続分の1/2や1/3にあたる財産を獲得できる権利」であり、2018年の改正後は、「遺留分」を主張する相続人(親子や孫に限る)は、シンプルに、他の相続人等にお金(遺留分侵害額)を請求できるようになりました(それまでは、各遺産に対する持分を主張するという、やや複雑な仕組みでした)。
ちなみに、ご相談者の中には、遺産分割協議(相続人間の話し合い)の場面でも「遺留分が私にはあるのだから」という発言をする方がおられるのですが、「遺留分」は遺言書で分け前を少なくされた相続人が主張できるもので、遺言書が無い場合は、「遺留分」ではなく「法定相続分」を前提に相続人が話し合いをすることになります。
このように、「遺留分」は遺言書がある場合にだけ問題となるのですが、気になるのが、上記の「生きている間と同じように、死後も、自分の財産については自分の意思(遺志)で自由に決めておきたい」という故人の遺志(憲法29条の財産権)と衝突することです。
核家族化・都市化が進んでいる現代社会で、例えば大都市圏の市街地に住んで親子が別々に暮らし、別々の生計(仕事)で生活している人たちにとっては、亡くなった父親の財産形成に子供は何も貢献していないことが多くあります。
私は東京都内で仕事をしているためか、「サラリーマンだった父親。疎遠だった長男は仲違いした父親から遺言書で何も遺されなかった。他方、父親は老後の面倒を看てくれていた長女に全てを相続させる遺言書を書いた。父親の死後、長男は長女に対して「遺留分」を主張し、金銭(遺留分侵害額)を要求。」という場面によく出合うことがあります。
父親の生前であれば、長男は、仲違いした父親に「俺に金をくれ」と要求する権利はありません。それにも関わらず、父親が死んだ途端にその財産の一部を要求できてしまうのは、どことなく釈然としないことがあります。
他方で、家族経営で農業や水産業、牧畜、小売店を営んでいる場合などには、親子全員で作り上げた財産や売り上げが便宜的に代表の父親名義になっているという場面も多くあります。この場合、父親名義の財産の中に子の潜在的な共有持分が入っていると考えることもできますので、「遺留分」制度が無かったとしたら、遺言で何も遺されなかった子は、その共有持分に相当する財産すら獲得できないこととなり、気の毒なことになります。
「遺留分」制度は、明治政府が諸外国の法制度を参考にして導入したものです。
諸外国の考え方としては、例えば「子供の経済的な貢献が父親名義の財産の中に含まれているので、それを子供に分けてあげなくてはならない」という考え、「父親による自由な遺産分配で経済的に困窮してしまう子供の生活保障をしてあげる必要がある」という考えです。前者は家族で生計を立てる近現代の「家内工業」が念頭にある感じですし、後者は互いに扶養等の義務がある夫婦や親子においては、死後もその延長線上の生活保障義務があり、何かしら残してあげるべきだ、という感じです。
日本でも、古来より家族が一つの単位となって家業を営んだり、多世代同居で助け合ったりしながら生活をしてきました。そのため、上記の考え方(たまたま家長名義になっているが理屈的には家族全員の財産である。家族がみな支えあって生きていく必要があるのだから、財産についても最低限の分け前が必要。)がすんなり受け入れられたのだと思います。
「遺留分」は別に主張しなければならない義務ではありません。
しかし、遺言で何も遺されなかった相続人の大半は「遺留分があるのだから請求する」と言って金銭を要求してきます。このご時世、当たり前と言えば当たり前かもしれません。
極めて私的な感想を言えば、親の遺産形成に何も貢献していないのであれば、親の遺志を尊重して「遺留分」の請求は控えてもらった方が、道理や義理人情という「法律以外のルール」に適って格好良いのにな、と思うことが実はあるのですが、自分だったら果たして潔い態度を取ることはできるのか、考え込むこともあります。
皆さんはどうでしょうか。
(2025年10月執筆)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
執筆者

政岡 史郎まさおか しろう
弁護士
略歴・経歴
H7 早稲田大学卒業、小田急不動産(株)入社
H13 同社退社
H17 司法試験合格
H19 弁護士登録・虎ノ門総合法律事務所入所
H25 エータ法律事務所パートナー弁護士就任
著書
「ある日、突然詐欺にあったら、どうする・どうなる」(明日香出版社 共著)
「内容証明の文例全集」(自由国民社 共著)
「労働審判・示談・あっせん・調停・訴訟の手続きがわかる」(自由国民社 共著)
「自己破産・個人再生のことならこの一冊」(自由国民社 校閲協力)
執筆者の記事
関連カテゴリから探す
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























