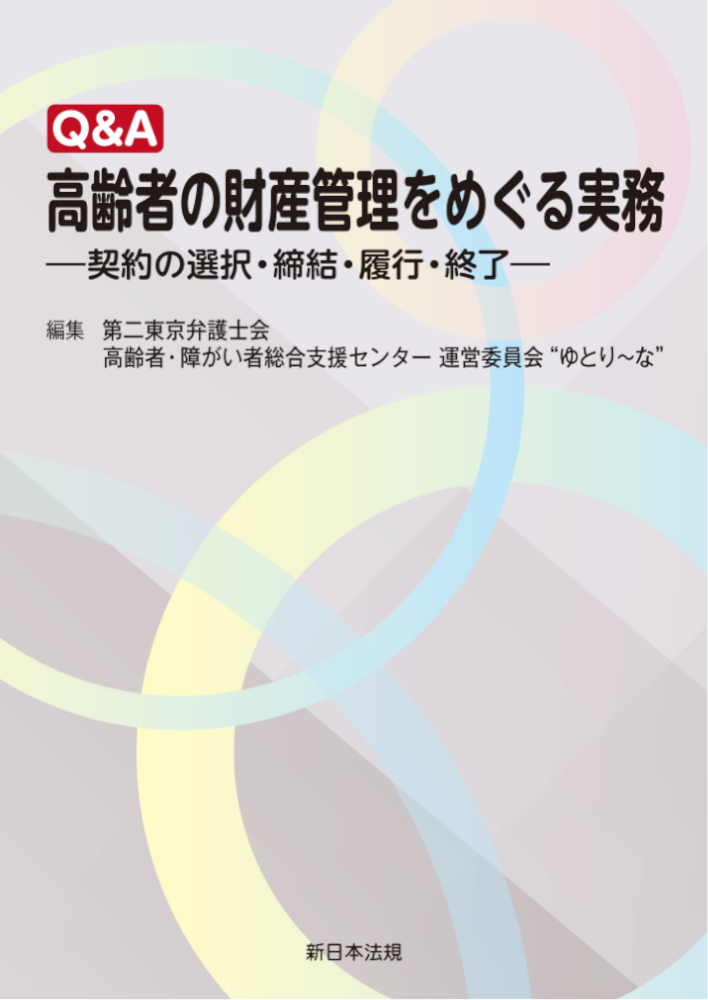相続・遺言2025年10月28日 高齢者とデジタル財産 執筆者:亀井真紀

デジタル財産(デジタル資産と呼ぶこともあるようです)という言葉が司法の分野でも相当頻度利用されるようになりました。よく問題提起されるのは、デジタル財産の相続手続きです。故人がどんなデジタル財産を有していたのか、有していたとしてどれくらいの価値でそもそも相続の対象になるのか、対象になるとしてどうやって手続きをすればよいのか等々です。この点は、デジタル財産が暗号資産なのか、電子マネーなのか、電子マネーやクレジットカード利用で付与されるポイントなのか等々で異なるものの、概ねとにかく手続きが大変だ!という論調をよく目にします。大変な理由はこういった資産が目に見える形になっておらず、全てがスマホやパソコンなどのデジタル機器で管理されていることです。家族といえども「ログインできないよ!」となるわけです。対策として言われるのは、家族などが後でわかるように、エンディングノートにIDやパスワードを記載しておく、パスワード共有カードを作成し財布や冷蔵庫など分かりやすいところに置いておく、修正テープでスクラッチ化しておくなどなど・・なるほどと思いつつ、最後は結局アナログ作業が求められるのだなとそのアンバランスさに何となく微笑ましくもなったりします。
それはさておき、後見人を務めることが多い私としては、ご本人の財産がデジタルだったら・・と気になるところです。高齢者はデジタルに弱い、などと言われることもありますが、70代のスマホ保有率が80%を超えたという統計もあり、周囲を見回しても、LINEをはじめ様々なアプリを利用し、勿論電子マネーだって活用する方はたくさんいます。最近は、地域限定の商品券アプリなどもあり、キャンペーン中は加盟店利用でポイント20%還元!などもあり商店街で使わなきゃ損ですよね、と考えるのは私ばかりではないはずです。そんな中、後見人として財産を管理する場合、本人のデジタル財産を的確に把握できるのかという壁にまず直面しそうです。勿論、ご本人が意思表示でき教えて頂くことができればよいのですが、必ずしもそうでないことも多くあります。昨今は明細書の郵便送付も省略されていることが多く、スマホやパソコンのログインができないとなるとヒントすら得られないのです。何となくあたりをつけて照会をするとしても限界があります。こういった資産は、ご本人が今生きていくための財産ですから、把握できるか否かは、相続手続き以上に実は深刻です。個人情報の厚い壁があるのは承知ですが、特定の権限を付与された人は包括的に照会ができるようにするシステムや制度の構築が検討されるべきではないでしょうか。財産管理をする上で悩ましい時代に突入したものです。
一方で、電子マネーは利用の仕方によっては、日常金銭管理の有用な手段にもなり得るのではとも考えています。現在、後見制度の見直しのための法改正の議論が行われていますが、制度利用は必要な場合に限られ、制度利用を開始したとしても、必要性がなくなったという理由で終了し得ることが想定されています。そして、終了した場合、本人の金銭管理をどのようにするかという課題があります。社会で様々な詐欺行為が横行している中、本人にお金の管理を委ねて大丈夫なのかという心配は福祉や金融機関の関係者の間でも尽きません。思うに、確かに大口の預金口座などはがっちりガードをする必要はあり、何らかの方策(代理人を設定するとか、本人の手続きだけではできないようにするとか)が検討されるべきです。一方でもしご本人がスマホやICカードなどを従前から利用していて、操作にも慣れていたということであれば、第三者が本人と相談して設定をサポートし、電子マネーを利用して日々の買い物ができるようにしてもよいのではと思います。電子マネーはその種類や設定の仕方によっては、残高が一定額以下になると自動的にチャージがなされたり、またそのチャージ額や回数自体を予め制限したりすることができます。現金であればなくなった場合、果たして使ったのか、単なる紛失なのか追跡をすることは困難ですが、電子マネーであれば履歴も残り、本人の同意を得れば、第三者がその履歴をチェックすることもできます。その中で、仮に、本人にとって明らかに不要なものを何度も購入しているとか、すぐに残高が尽きてしまうなどの異変が生じていれば、次の対策を検討することができます。仮に不要なものを購入していたとしても設定した限度額の範囲内であれば大きな損失にはなりません。
どんな人にとっても、自分で買い物をするというのは日々の暮らしのハリにもつながることです。商店街でお得にポイントをゲットするというような些細な喜びはできる限り奪いたくありません。
デジタル財産は悩ましいところがあるのも事実ですが便利な面も多々あり、上手に付き合っていきたいものです。
(2025年10月執筆)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
執筆者

亀井 真紀かめい まき
弁護士
略歴・経歴
第二東京弁護士会所属。
平成13年弁護士登録。北海道の紋別ひまわり基金法律事務所(公設事務所)に赴任。
その後、渋谷の桜丘法律事務所(現事務所)に戻り現在に至る。
第二東京弁護士会高齢者・障がい者総合支援センター委員会、日弁連高齢者・障害者権利支援センター委員会等所属。
一般民事・家事、刑事事件のほか、成年後見、ホームロイヤー契約等高齢者、障がい者の事件を多く担当する。
執筆者の記事
執筆者の書籍
関連カテゴリから探す
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -