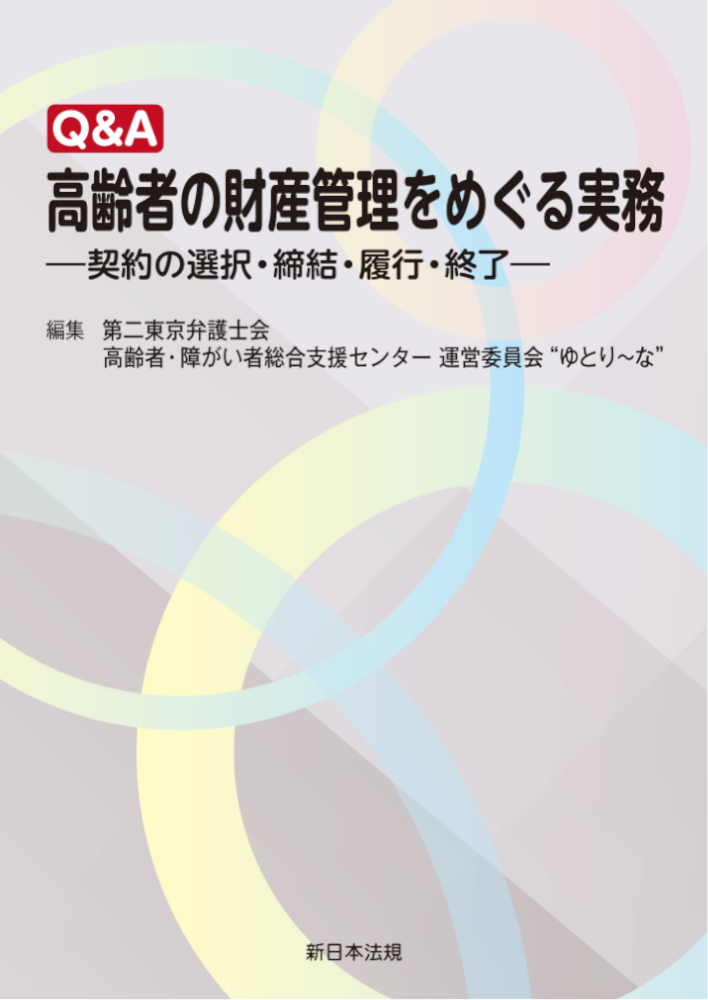一般2025年03月21日 映画と安楽死 執筆者:亀井真紀

「ザ・ルーム・ネクスト・ドア」という映画を観ました。
ネタバレをしない程度で紹介をさせて頂くと、末期がんに冒された主人公が自分らしく人生を終えるため、友人に自分は治療をやめて安楽死を選択すること、最期のその日まで隣の部屋にいてほしいと頼むというストーリーです。
これだけの案内だと暗く重いテーマを扱う作品のように思えますが(実際その覚悟でした)、主人公の人生観が丁寧に描写され、不思議と否定的な気持ちにはなりませんでした。また、二人の女優が本当に美しく、加えて衣装や美術のセンスが素晴らしいので、上質で高級な食事をした後のように満足した気分になりました。これは映画監督の力量によるものですね。
内容面については、色々と思うことはあったのですが、法律家としてやはり気になるのは「安楽死」の合法性です。映画の中でも主人公は法的な問題を意識し、残された友人が処罰されることのないよう様々策を講じることなどが描かれています。
安楽死については、ヨーロッパの一部の国(オランダ、ベルギー、スイスなど)やアメリカの一部の州では認められていますが、映画の舞台となっているニューヨーク州では認められていないようです。
さて、日本ではどうかというと、やはり同様に安楽死は合法化されていません。そもそも法律で「安楽死」という言葉が出てくることもありません。仮に患者本人が自分の死期を悟り、積極的に死ぬことに同意したとしても、関与した者は、刑法202条の嘱託(同意)殺人罪や自殺関与罪に該当し、処罰される可能性があります。ここで可能性と述べていること自体にこのテーマの悩ましさがあるのですが、理論的には罰せられる(有罪)場合と罰せられない(無罪)場合があり得ます。殺人の構成要件に該当しても一定の要件を充たせば、その行為が正当化され、違法性がないとされることもあるからです。
これまで安楽死として刑事裁判で無罪になったケースは私の知る限りありませんが、合法とされる例外的な要件を裁判で示したのが、安楽死裁判のリーディングケースにもなっている有名な東海大学安楽死事件判決(横浜地裁平成7年3月28日判決)です。この判決は、医師による安楽死が許容されるためには、①患者が耐えがたい激しい肉体的苦痛に苦しんでいること、②患者は死が避けられず、その死期が迫っていること、③患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くしほかに代替手段がないこと、④生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示があることという要件を示しました。
結論としては、この裁判で問題となった医師の行為(家族に迫られてワソランとKCLという塩化カリウム製剤の注射をしたというもの)は治療行為の中止という消極的な安楽死ではなく、積極的な安楽死であり、事実認定・評価として①③④の要件を充たさないとし、有罪判決(懲役2年、執行猶予2年)を下しています。
このまま確定しているので、下級審ではありますが、安楽死裁判としては今も代表的な位置づけにあります。積極的安楽死、間接的安楽死、消極的安楽死、尊厳死という言葉を用いて、様々な局面と限界事例を想定して判示しているのも特徴的です。判決は約30年も前のものですが、読み応えのあるものであり、司法の世界では勿論、医療関係者の間でも有名な事件だと思います。個人的には、患者の無念を想像する一方で、被告人とされた医師の追い詰められた極限的な状況は気の毒でなりません。
翻って考えるに、この判決を前提にするとすれば、冒頭で紹介した映画の主人公のような希望はおよそ日本の病院では叶えることはできないことになります。おそらくニューヨークでもそうなのでしょう。だからこそ、死ぬ時は病院ではなく、自分の望む場所にしたい、その隣の部屋には誰かいてほしいという思いと発想が出てくるのかもしれません。少なくとも監督はそういう主人公を描きたかったのでしょう。そうだとすれば、日本でも同様の悩ましい事例は出てきてもおかしくないのかもしれません。また、自分がこの映画の友人の立場だったらどうするか、弁護人の立場だったらどういう主張をするか、いややはりフィクションの世界だからその状況はあり得ないかな等々あれこれ思案しています。
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
(2025年2月執筆)
人気記事
人気商品
執筆者

亀井 真紀かめい まき
弁護士
略歴・経歴
第二東京弁護士会所属。
平成13年弁護士登録。北海道の紋別ひまわり基金法律事務所(公設事務所)に赴任。
その後、渋谷の桜丘法律事務所(現事務所)に戻り現在に至る。
第二東京弁護士会高齢者・障がい者総合支援センター委員会、日弁連高齢者・障害者権利支援センター委員会等所属。
一般民事・家事、刑事事件のほか、成年後見、ホームロイヤー契約等高齢者、障がい者の事件を多く担当する。
執筆者の記事
執筆者の書籍
関連カテゴリから探す
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -