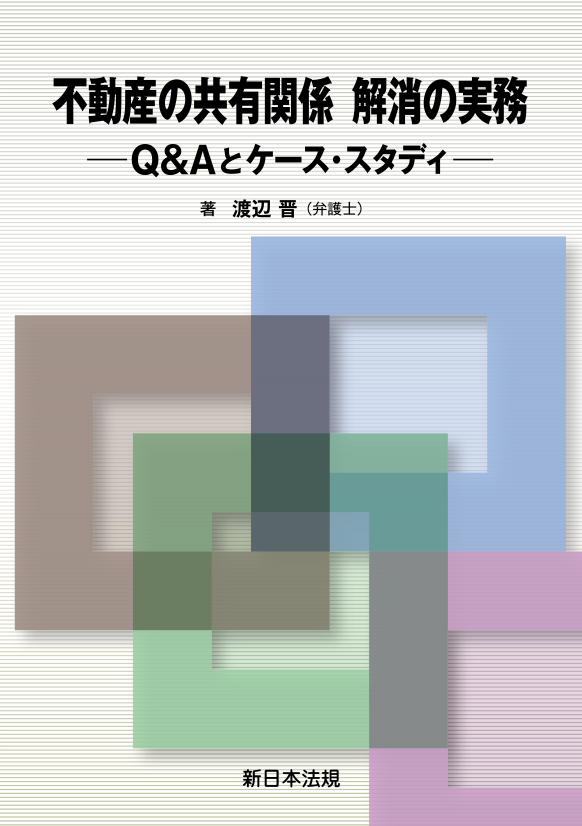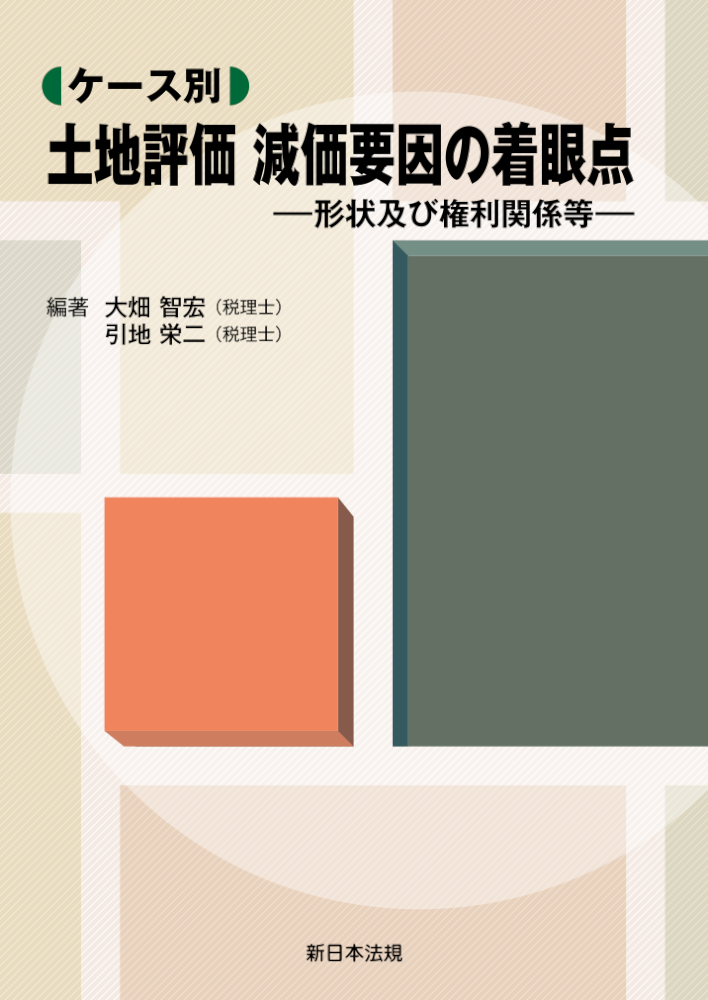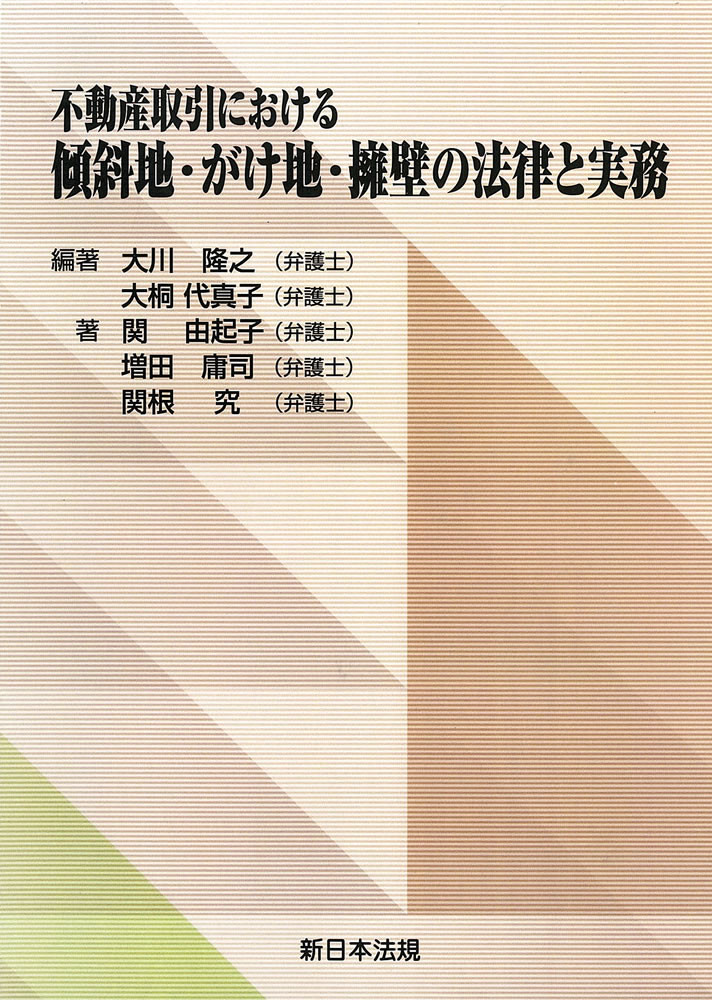民事2021年12月06日 不要な土地(負の遺産)からの解放 執筆者:政岡史郎

先日、法律相談の際に、「土地を売ろうと思っているが、そこは平たんな土地と斜面地が混ざっており、買主が『土地の一部(斜面地)は使い勝手が悪いので要らない』と言っている。売れそうなところだけ売って、残りの土地は所有権を放棄できないか。」というご相談がありました。
実は、2016年11月8日付公開のコラムで「要らない不動産の廃棄処分」という記事を書かせていただきましたが、それから5年が経つ間に、社会問題化していた「不要な不動産の処分」「所有者不明土地の処理」について議論が進み、令和3年4月に、いくつかの法制度が出来ました。そこで、今回は「不要な土地の処分」について改めてご紹介したいと思います。
もともと、法務省の通達では「不動産の所有権放棄は出来ない、そのような登記も認めない」とされていましたし、これが原則論で、今も活きている通達と考えられます。
したがって、「自己所有地を売却しようとしたが、一部は引き受け手がおらず残ってしまう(または、土地全体で売ろうとすると買い手が居なくなってしまう)ので、その一部分だけ所有権を放棄したい。」という上記のご相談のケースでは、残念ながら、自己責任で維持管理していかなければなりません。
ただ、「先祖伝来の土地が地方にあるが、都市部に居る相続人は誰も引き継ぐことを望んでおらず、また自己の子孫にも引き継がせたくないので、それは放棄したい。」というようなケースの場合には、新しい法制度の創設で活路が見出されました。
なお、今までも、土地を手放すには、有償で売却するとか(交換もこれに含みます)、無償で譲渡する手法(寄付や贈与)がありますが、利用価値がない土地には引き取り手がありません(役所が引き取ってくれるのでは、と気楽に考える方がいるのですが、役所は、道路用地などで利用価値=税金を掛けてまで維持する価値がある土地しか引き取ってくれません)。
相続が発生した際、「相続放棄」を家庭裁判所に申し立てることで土地を引き継がなくて済むことがありますが、原則的に、「相続放棄」は「全ての財産について放棄する」手続きなので、「預貯金は相続するけれど山林などの不要な土地は要らない」という「良いとこ取り」は出来ません。
また、仮に「相続放棄」をしたとしても、他に相続する人が出てくる(実際に管理を始める)までは、その山林などの「管理責任」が残るのです。民法上では、自分の他の財産と同様の責任で管理をしなければならない、とされていますので(第940条1項)、例えば台風等で土砂崩れを起こすとか、老朽化した建物の屋根が飛んで隣人に被害を与えた、などの場合には、管理者としての不法行為責任などが生じかねません。
そこで、これらの負担から解放されるために、新しく制定された「相続土地国庫帰属法」という法律を利用することが出来ます。
この制度を利用する場合には、①相続(遺贈)で取得した土地であること(自分の意志で取得した場合はダメ)、②10年分の標準的な管理費をあらかじめ納めること(原野等は10年分で20万円、市街地の宅地は80万円程度が想定されています)、③他人の権利(通行権や抵当権等)の目的となっていない、境界に争いがない、建物等の工作物が存在しない、埋設物や崖・土壌汚染等のリスク要因が無いこと、という条件が色々とあります。
これは、度重なる相続で所有者不明の土地が生じていくという社会問題を国が解消・予防するために作られた法制度なので、個々の国民側からすると使い勝手は悪いのですが、条件を満たしさえすれば、今までは叶わなかった不要な土地からの解放が可能となります。施行後は、この制度を利用することで不要な土地から解放される方が一定数出てくると思いますので、その動向を注視し、今後の業務に活かしたいと思っています(令和5年4月末までの施行予定です)。
人気記事
人気商品
関連商品
執筆者

政岡 史郎まさおか しろう
弁護士
略歴・経歴
H7 早稲田大学卒業、小田急不動産(株)入社
H13 同社退社
H17 司法試験合格
H19 弁護士登録・虎ノ門総合法律事務所入所
H25 エータ法律事務所パートナー弁護士就任
著書
「ある日、突然詐欺にあったら、どうする・どうなる」(明日香出版社 共著)
「内容証明の文例全集」(自由国民社 共著)
「労働審判・示談・あっせん・調停・訴訟の手続きがわかる」(自由国民社 共著)
「自己破産・個人再生のことならこの一冊」(自由国民社 校閲協力)
執筆者の記事
この記事に関連するキーワード
関連カテゴリから探す
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -