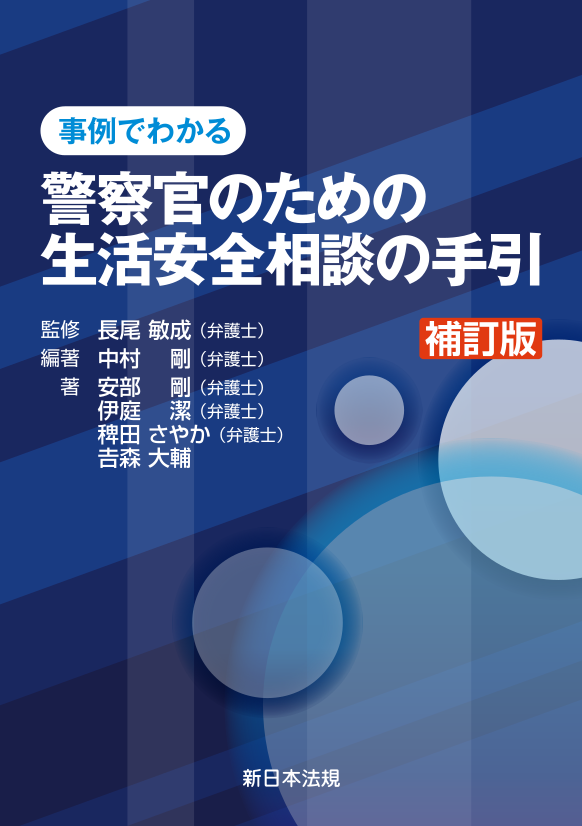企業法務2025年01月08日 コンダクト・リスクの考え方~他律から自律への転換点~(法苑WEB連載第13回)執筆者:吉森大輔 法苑WEB

1.はじめに(本稿の趣旨)
「コンダクト・リスク」とは何か。シンプルに整理すると、企業の役職員による、ステークホルダー・社会の期待・信頼に反する行動(コンダクト)により、企業価値を毀損されるリスクを指す。
この「コンダクト・リスク」は、主に金融庁が金融機関に対して管理を求めているものであることから、金融機関以外の企業や、企業を支援する専門家にとっては、あまり馴染みがないかもしれない。
しかし、「コンダクト・リスク」の考え方は、金融機関以外の企業においても、不祥事を防止し、コンプライアンス・リスク管理を充実させる観点から、有意義なものである。
そこで、本稿では、「コンダクト・リスク」の考え方と、その視点を取り入れることの重要性について解説していきたい。
2.「コンダクト・リスク」の登場とその意義
「コンダクト・リスク」は、主に2008年のサブプライムローン問題を発端とする世界的な金融危機以降、議論が始まったものである。この全世界を揺るがした金融危機は、金融機関の役職員の行為(コンダクト)、特に、直ちに法令違反・不正とはいい難いが、不適切といえる行為が多数介在したことが原因の1つであると考えられている。そこで、「直ちに法令違反・不正とは言い難いが、ステークホルダー・社会の信頼・期待に反するような不適切な行為」もリスク管理の対象に含める必要があるという考え方のもと、「コンダクト・リスク」という概念が登場するに至ったのである。
日本では、2018年10月、金融庁が公表した「コンプライアンス・リスク管理基本方針」において、「コンダクト・リスク」の考え方が紹介されているが、その中には、「リスク管理の枠組みの中で捕捉及び把握されておらず、いわば盲点となっているリスクがないかを意識させることに意義がある」と説明されている。
3.近年の不祥事の傾向からみる、「コンダクト・リスク」の重要性
実際に、日本においても、「盲点」となっていた「コンダクト・リスク」が顕在化した事例、すなわち、「直ちに法令違反・不正とは言い難いが、ステークホルダー・社会の信頼・期待に反するような不適切な行為」による大規模な企業不祥事が続いている。
これらの不祥事の特徴としては、大きく①コンプライアンスを狭く形式的に捉えることによって、安易に管理の対象外と整理し、問題を矮小化した対応に終始していたほか、②企業内において、リスク情報の目詰まりが発生し、経営陣に伝達されず、その結果、不祥事の発見が遅れ、対応が後手に回り、組織における対応より、SNS等による社会の反応が先行し、炎上するという傾向が見受けられる。
こうした傾向を有する近年の不祥事の発生を防ぐためには、①広くステークホルダー・社会の期待・信頼の観点から、コンプライアンス・不祥事を捉えること、そして、②広くリスク情報を把握・発見し、経営陣に伝達される態勢を整備する必要がある。
これは、まさに「盲点」をなくすために、ステークホルダー・社会の期待・信頼に反する行動(コンダクト)をリスク管理の対象に含める「コンダクト・リスク」の発想に他ならないものといえる。
4.「コンダクト・リスク」は金融機関特有のものか
「コンダクト・リスク」が不祥事防止に資するというイメージはさほど難しいものではないと思われるが、「金融庁が、金融機関に対して管理を求めているものであって、それ以外の企業には関係がないのではないか」という疑問を持つ方も多いと思う。
ここで、日本取引所自主規制法人が公表している「不祥事予防のプリンシプル」の内容をみていきたい。このプリンシプルは、上場企業向けに、コンプライアンス・リスク管理の観点から、不祥事を予防・発見するためのポイントを整理したものであるが、この原則1の中に「身を伴った実態把握」がある。
「自社のコンプライアンスの状況を制度・実態の両面にわたり正確に把握する。明文の法令・ルールの遵守にとどまらず、取引先・顧客・従業員などステークホルダーへの誠実な対応や、広く社会規範を踏まえた業務運営の在り方にも着眼する。その際、社内慣習や業界慣行を無反省に所与のものとせず、また規範に対する社会的意識の変化にも鋭敏な感覚を持つ」。
この内容を見ると、「コンダクト・リスク」の考え方と共通していることがわかる。すなわち、コンプライアンスについて、「法令に捉われるべきではない」、「ステークホルダーの視点を考慮すべき」、「社会規範に対応すべき」というものである。
このプリンシプルが伝えたいメッセージというのは、「コンプライアンスについて、法令・ルールさえ守っていればいいという考え方は許されない」というものと考えられる。
要するに、「コンダクト・リスク」の考え方、法令・ルール以外の、社会規範、ステークホルダーの期待・信頼の観点を考慮する必要性は、金融機関以外の企業においても共通しているものといえるであろう。
なお、金融機関も含めて、特にそれ以外の企業の場合、「コンダクト・リスク」というリスク項目を設けることが必須であるというわけではない。ここで強調したいのは、この「コンダクト・リスク」の「考え方」を、既に管理しているもの(コンプライアンス・リスク管理等)の中に取り入れる必要性である。
重要なのは、名目ではなく、内容である。
5.「コンダクト・リスク」の枠組み
では、企業は、どのように「コンダクト・リスク」の考え方を取り入れていけばよいか。ここでは、基本的な枠組みをご紹介したい。
「コンダクト・リスク」の基本的な枠組みとしては、従来のリスク管理の手法・ステップと大きく異なるものではなく、リスクベース・アプローチ(RBA)に基づく対応が求められる。
リスクベース・アプローチとは、幅広い情報収集を行った上で、自らが直面するリスクを包括的かつ具体的に特定・評価し、重大なリスクの所在や、態勢整備が急務である領域を洗い出した上で、当該リスクを低減・制御するための具体的な行動計画を策定し、実行するプロセスのことを指す。
ただ、「コンダクト・リスク」の管理においては、これまで指摘しているとおり、ステークホルダー・社会の信頼・期待の観点から検討することが必要である。
すなわち、RBAの前提として、「自らがステークホルダー・社会から何を期待・信頼されているか」について洗い出すことが求められる。具体的には、自社の企業理念・行動規範等を踏まえつつ、顧客の声、職員アンケートの結果、内部通報で寄せられている職員の声、SNS等で発信されている自社に係る情報、他社の不祥事の事例等を踏まえて、幅広く情報収集を行い、社内で議論・検討することが求められる。
この議論・検討過程こそが、役職員の主体的な関わりを促進し、リスクの感度を高め、充実したコンプライアンス・リスク管理の実践につながってくるものと思慮する。
6.「コンダクト・リスク」の視点を踏まえたこれからのコンプライアンス
従来のコンプライアンスは、「法令等遵守」と呼ばれるように、法令やガイドラインや社内規則等の「ルール」を守ることを指すものと考えられていた。既にある「ルール」があり、それを守る、「comply」するというのが、従来のコンプライアンスの考え方だった。この考え方は、「ルール」への対応=「他律」を前提としたものであり、いわば受動的な対応が求められていた。
ただ、それでは、リスク管理に漏れが生じる、いわば「盲点」となって、社会から非難を受ける大規模な不祥事の事案が発生していることは上記のとおりである。
それは当然の問題であって、社会は、「この企業はルールを守っているのかどうか」をみているわけではない。「この企業は全うであるか」、「ステークホルダーである我々と真摯に向き合っているか」といった観点で企業を見ているのである。
「この企業が全うであるか」の判断基準は、社会のルール、すなわち、ステークホルダーの信頼・期待に反していないかという点で判断されることになり、この点が、これまで「盲点」となっていたのである。
繰り返しになるが、この「盲点」をなくすためにできた概念が「コンダクト・リスク」である。「コンダクト・リスク」は、「他律」ではなく、自らその必要性や内容を考え、主体的にリスクを管理すること=「自律」が求められる。
今後は、コンプライアンスを「法令遵守」と狭く捉えるのではなく、広くステークホルダー・社会の信頼・期待という観点から捉え、主体的にリスク管理を実施していくことが重要である。
(弁護士)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
法苑WEB 全16記事
- 契約に関わる文豪書簡(1)―法律の条文のような諭吉・らいてふの書簡―(法苑WEB連載第16回)執筆者:中川越
- 子どもの意見表明の支援は難しい(法苑WEB連載第15回)執筆者:角南和子
- 「始皇帝モノ」は面白い。連載コラムその3 ─応用編⑴『大秦帝国』シリーズ全4作の紹介─(法苑WEB連載第14回)執筆者:坂和章平
- コンダクト・リスクの考え方~他律から自律への転換点~(法苑WEB連載第13回)執筆者:吉森大輔
- 消防法の遡及制度(法苑WEB連載第12回)執筆者:鈴木和男
- 「始皇帝モノ」は面白い。連載コラムその2 ─入門編は『キングダム~戦国の七雄』から─(法苑WEB連載第11回)執筆者:坂和章平
- 株分けもの(法苑WEB連載第10回)執筆者:村上晴彦
- 「始皇帝モノ」は面白い。連載コラムその1 ─『キングダム』シリーズ全4作を楽しもう!─(法苑WEB連載第9回)執筆者:坂和章平
- 小文字の世界(法苑WEB連載第8回)執筆者:田中義幸
- 20年ぶりに「学問のすすめ」を再読して思うこと(法苑WEB連載第7回)執筆者:杉山直
- 今年の賃上げで、実質賃金マイナスを脱却できるか(令和6年の春季労使交渉を振り返る)(法苑WEB連載第6回)執筆者:佐藤純
- ESG法務(法苑WEB連載第5回)執筆者:枝吉経
- これからの交通事故訴訟(法苑WEB連載第4回)執筆者:大島眞一
- 第三の沈黙(法苑WEB連載第3回)執筆者:相場中行
- 憧れのハカランダ(法苑WEB連載第2回)執筆者:佐藤孝史
- 家庭裁判所とデジタル化(法苑WEB連載第1回)執筆者:永井尚子
執筆者

吉森 大輔よしもり だいすけ
弁護士(霽月法律事務所)
略歴・経歴
2013年 弁護士登録
2013-2019年 長尾敏成法律事務所
2019-2020年 財務省関東財務局理財部 任期付公務員(金融証券検査官)
2020-2022年 金融庁総合政策局リスク分析総括課 任期付公務員(専門検査官及び同局マネロン・テロ資金供与対策企画室室長補佐等を併任)
2022-2024年 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 勤務(2023年2月~パートナー)
2023-2024年 日本郵政株式会社 出向(2023年4月~グループコンダクト統括室長)
2024年 霽月法律事務所入所
<主要著書等>
『地域金融の活用術』(共著、一般社団法人金融財政事情研究会、令和4年)
『〔補訂版〕事例でわかる 警察官のための生活安全相談の手引』(共著、新日本法規出版、令和3年)
執筆者の記事
執筆者の書籍
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.