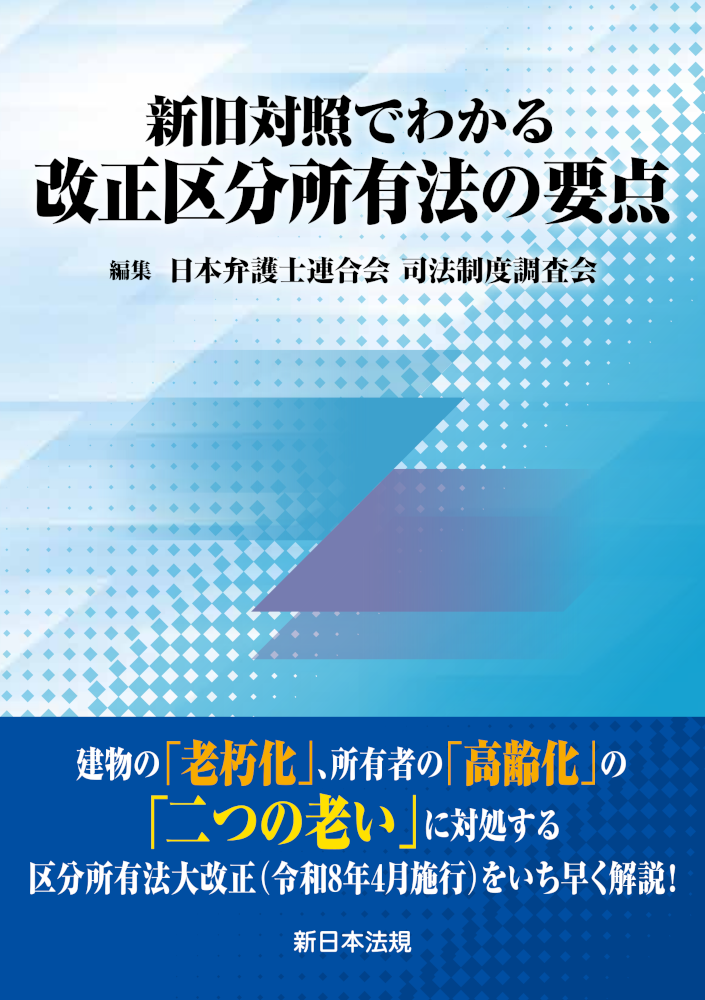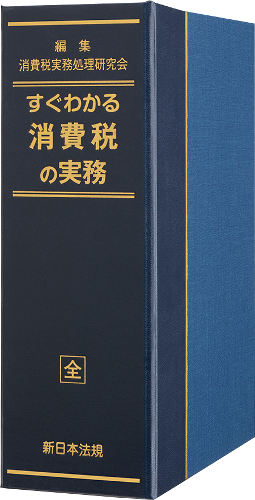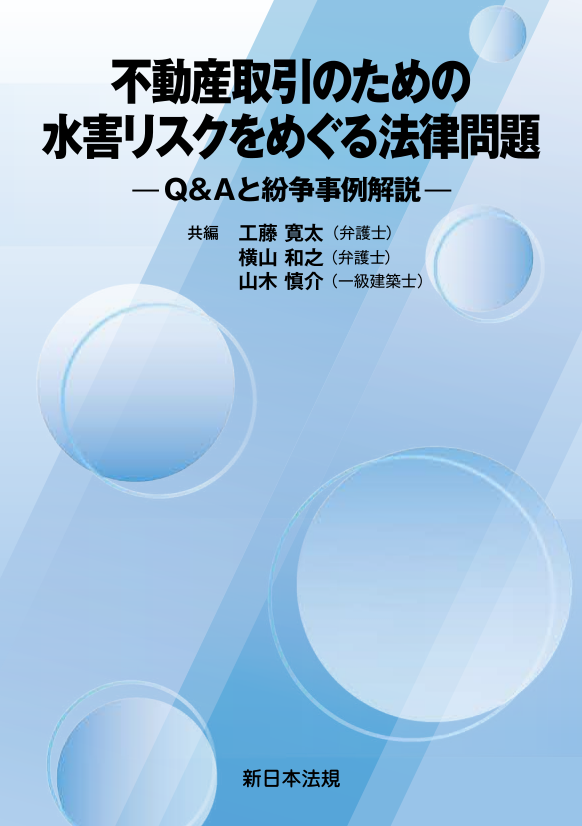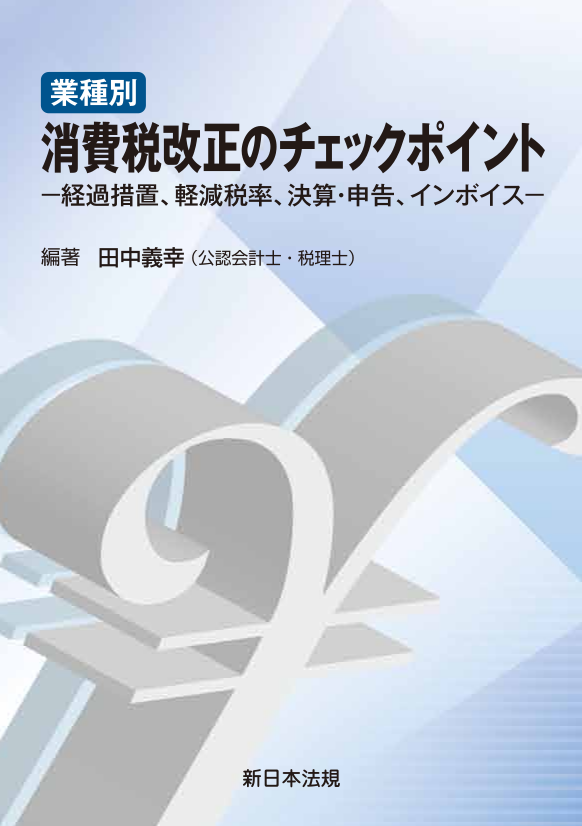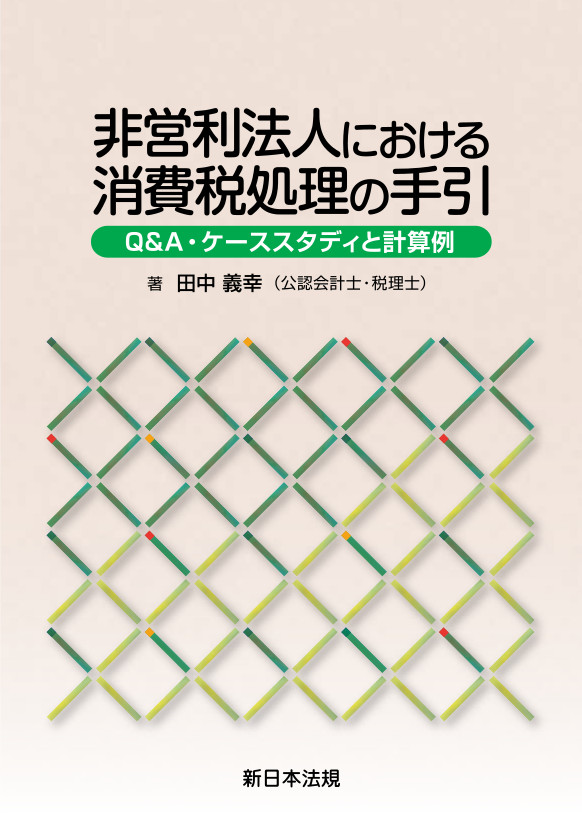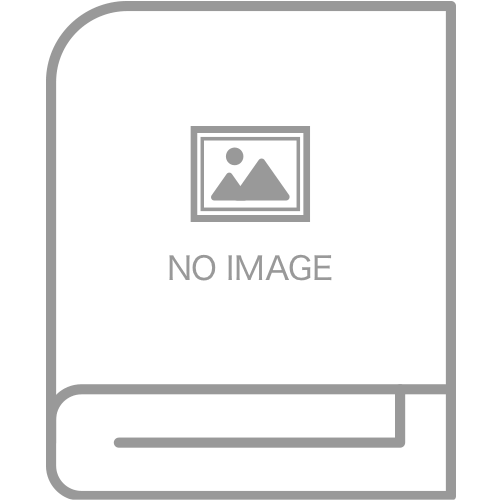一般2024年09月11日 小文字の世界(法苑WEB連載第8回)執筆者:田中義幸 法苑WEB

このところの円安は、我が国の凋落のしるしだと誰もがいう。聞いている側もそれを疑わなくなった。
しかし、日本中どこへいっても、道路は過剰なまでに舗装され、走っている車もそこそこに新しく、周囲にはモデルハウス然とした瀟洒な住宅が立ち並んでいる。市街地の街並みはきれいに整えられ、新しく建替えられたビルの外観も洗練されており、一見するとどこにも凋落のしるしなどは見えない。ただ、ちょっと脇道へ入ると、シャッターの下りた古い商店街がゴーストタウンのように静まり返っていたり、住宅も住人がいなくなったまま放置されて空き家になっているものも少なくないのがわかる。昼日中の街なかは閑散として、子どもの姿はまるでハメルーンの笛吹きにでも連れていかれたように消えてしまい、手押し車などを押した年寄りがたどたどしく歩いていて、かつての街の活気が失われているのを目にすると、我が国の社会から勢いがなくなって、沈みつつあるのを感じざるを得ない。
それで思い返すのは、我が国が上り調子で輝いていたときはいったいいつだったのだろうということである。昭和の終わりから平成の初期にかけてのバブルのときが引き合いに出されることが多いが、あの頃は爛熟というか、頽廃というか、時代の空気が淀んでいて、輝きとは違っていたような気がする。
昭和六十三年の秋、人々は今と同じように自分なりの幸福と不幸を隣り合わせに暮らしていた。私はまだ三十代で公認会計士にはなっていたが法律事務所に勤めていた。昭和が終わりかけていると漠然とは感じていたが、それが昭和最後の秋になるとは思っていなかった。
当時勤務していた渉外法律事務所の代表だった西村利郎先生に呼ばれて霞が関ビルの四階の部屋に行くと、そこから見える東京の高層ビル群を眺めながら、西村先生から「この東京の地価でアメリカ全土が買えるというんだが、君はどう思うかね」と聞かれたことがあった。そのことが、まともに答えられなかった悔恨と共に、いつまでも脳裏に残っている。
それでは、再び、我が国が上り調子で一番輝いていたときはいつだったか。一九六〇年代後半の我が国の経済が高度成長のただなかにあったころはどうだろうか。七〇年安保を控えて各地で大学紛争が燎原の火のように拡がっていたころだが、当時の我が身の日常を振り返ると、輝いていたとはやはり思えない。
鹿児島の田舎で反戦デモに行こうとしていた高校生の私に父がつかみかかってきたことがあった。「皆が東大に入ろうと懸命に勉強しているときに、お前は東大解体なんてほざいて、勉強もしないで何をしているんだ」。傍らにおろおろしている母と、またかという顔で傍観している中学生の弟がいた。我が家では、もう何度も蒸し返された光景だったが、父の絞り出すような声が耳の奥に残って、なかなか慣れっこにはなれなかった。私は何かに反抗しながら、自分の将来に明るい希望があったわけではなく、むしろ絶望が通奏低音のように漂っていたが、ただ十代の生命力だけが絶望に打ち勝って蠢いていたのだと思う。
結局、我が身にとって、我が国が上り調子で一番輝いていたときなどはなく、繰り返すようだがその時々の幸福と不幸を隣り合わせに生きていただけで、それは誰にとっても同じではなかったかと思い返すだけである。
ところで、本は二度も三度も読んで初めて本当に読んだということになるんだという気持ちにさせられたのは、森鷗外の『渋江抽斎』を何度も読んでからである。読み終えてしばらく経つとまた読み返してみたくなり、いつの間にか頁をめくっていて、他の本に気持ちを切り替えることがなかなかできない。渋江抽斎は、江戸時代末期、弘前の津軽藩につかえる医官であるが、鷗外は抽斎が五十四歳で亡くなるまでの生涯のみならず、その祖先から親戚、友垣、子々孫々に至るまでを克明に描いている。
本に登場する江戸時代の人々だが、今からするとひどく短命なのに驚かされる。生まれたばかりの子もそうだが、長じても、あっけないほど簡単に亡くなっている。そのせいか、その頃の人々は他者との距離の取り方がとても近く、それを嫌がっていないように感じられる。要するに現代人のように長生きのせいで人間のダメなところをいやというほど見せつけられて人間嫌いになる前に、江戸時代の人々は亡くなっているのだ。
それから、江戸時代は今のように人が多くなかったことも、人々が人間嫌いに陥らずに済んだ一因だと思う。人っ子一人いない山中で誰か人と出くわしたときの懐かしい、嬉しい気持ちをいつも持っていられたら、人間嫌いになどなれるはずがないからだ。
渋江抽斎の家には、いつも数名から十名を超えるぐらいの食客、つまり居候がいた。これは現代人にはとうてい真似ができない。渋江抽斎が亡くなり、生計が縮小して家を移るときも、未亡人五百(いお)が抽斎の六人の遺児と全部の食客を引き連れていくのだが、この頃の人々は他者に対して現代人とは全く異なる感覚を持っていたのだろう。
『渋江抽斎』は、抽斎の四人目の妻であった山内五百の物語でもある。大名家に奉公して通常なら二十四、五歳で務める中臈頭を十五歳で務め、文武両道に秀でていた五百は、抽斎が集めた八百両の金を奪いに来た三人の賊を、沐浴中の湯殿から口に懐剣をくわえて腰巻一つで駆け付け、賊に熱湯を浴びせて撃退する。かと思うと、抽斎があるとき天井に止まっている蠅の話をしていたら、五百が「人間も蠅が天井に止まったようになっているのだと申しますね」といったので、抽斎は五百が地動説を地理の本などで読んで知っているのに驚いたという。
森鴎外は六十歳で没しているが、晩年の五十代に書いた三つの伝記文学『渋江抽斎』、『伊沢蘭軒』、『北条霞亭』は史伝三部作といわれている。このうち、『渋江抽斎』、『伊沢蘭軒』を近代日本文学の最高峰だと評したのは作家の丸谷才一である。史伝のもう一つの『北条霞亭』を最高峰だとしたのは作家の石川淳である。石川の説によると、鴎外は北条霞亭について書いているうち、この人物が俗物だと分かったが、これが人間だと、そこが素晴らしいのだと思って書き続けた。しかしそのうち、鴎外は自分も俗物だと気づいて困った様子が表れているところに、この作品の文学的価値があるというのだから、石川淳もすごい。
森鴎外は、その人物を俗物の野心家と見て好まなかったようだが、この史伝三部作の中にもう一人見え隠れする人物がいる。一八世紀後半から一九世紀前半にかけてのこの時代に、『日本外史』を書いて多くの人々を魅了し、後世に多大な影響を与えただけでなく、膨大な数の漢詩を詠んで、不世出の文人として天下に名を馳せた頼山陽である。
頼山陽は、広島藩の儒学者の子として幼少のころから詩文の才に恵まれた境遇であったが、若い時から名声を天下に轟かせたいという野心を抑えることができず、脱藩して京都へ出奔し、連れ戻されて自宅に幽閉された。このときに著述を始めたのが『日本外史』である。
頼山陽が十八歳で江戸に遊学したとき世話になった一人が伊沢蘭軒だった。二十四歳の伊沢蘭軒は、父親に命じられて中国の隋の時代の医学書を筆写していたが、それを居候の身の頼山陽にも手伝わせた。鴎外は、そのとき山陽がどんな顔をして医学書を筆写していたのか、「わたくしは、当時の山陽の顔が見たくてならない」と書いている。天下に名声を轟かせたかった山陽が、医学書の筆写など面白かろうはずがない。すぐに、井沢の家を出て狩谷棭斎のところに移った。鴎外の『渋江抽斎』には、抽斎が井沢蘭軒に医学を学び、狩谷棭斎に儒学を学んだことが記してある。そして、井沢蘭軒の親しかった漢詩人に有名な菅茶山がいたが、この菅茶山の同門であったのが頼山陽と北条霞亭である。それで、霞亭の墓碑銘は、山陽が書いている。
頼山陽のことは中村真一郎の『頼山陽とその時代』に詳しいが、この本はとにかく漢詩でつづられているので、漢和辞典が手離せない。
漢和辞典は、昔から使っている学研の『漢和大字典』の他は、だいぶ前に買った角川の『新字源』を改訂新版が出ても買い替えずに手元に置いていたが、私のように買い換えない者が多いせいで、どうも売れ行きが悪く、「漢和辞典は絶滅するかもしれない」といわれるような事態になっているらしい。これはいけないと書店に走ったが、書店の書棚を見る限り、漢和辞典のたたずまいは堂々として、他の辞書を睥睨し、特に弱った顔つきはしていない。
少しでもピンチの足しになればと、角川の『新字源』の改訂版の他に、三省堂の『漢辞海』、学研の『漢字源』、大修館の『漢語林』の三冊を買い求めた。漢和辞典の相場はどれもだいたい三千円ぐらいだが、収録されている内容にくらべたら値段は驚くほど安価で、中身はどう見ても三千万円は優に超えるものが詰まっている。だから、漢和辞典の編纂に当たった人の味わえた豊かさには、どんな億万長者もかなわないだろう。
辞書は何よりも、書店でこれはという辞書を見つける楽しみがある。それから、じっくり引いてみる楽しみがあり、また気に入ったものをいつも座右においておく楽しみがある。辞書は一冊で、三度おいしい。
このところ使っている英語の辞書はよく壊れる。二年前に並装と革装の同じものを二冊そろえた。並装の方は酷使したので、背表紙が剥がれ、中の寒冷紗が裂けて、折り丁の糸かがりの糸がちぎれそうになっている。そして前小口がだいぶ黒ずんでいる。寒冷紗とは、本の中身と表紙をつなぐ芯材となる粗い平織りの布をいう。折り丁は、冊子の大きさに折り畳まれた刷り紙で、真ん中を糸で綴じてある。前小口は、辞書をパラパラめくるときに使う面である。それで、辞書は酷使すると一、二年で前小口が黒くなることと、背表紙から剝がれて装丁が壊れることを知った。若い時から、辞書を酷使することを知っていれば、もう少しましな人間になれたろうにと思う。
なにかで、永井荷風が「鴎外全集と辞書の言海さえ読んでいればいい」と書いていたのを目にして、そういえば手持ちの辞書の中に『大言海』があったのを思い出し、本棚の奥から引っ張り出してきた。『言海』は大槻文彦が明治三十年代に編纂した辞書だが、『大言海』は昭和五十七年に冨山房から記念出版されたものだ。『大言海』を開いてみると、ほとんど引いた形跡がない。引いた記憶もないから当然だが、これも前小口が黒ずみ、糸かがりの糸がちぎれるまで酷使しなければならなかったのだ。試合終了のゴングはまだ鳴っていないけれど。
辞書を引くのが楽しいのはどうしてだろう。辞書を引くときには、自分がいたらないことを認めて、降参して頼っているという感じが、思わず知らず絶対者に帰依しているような充足感を引き出されているからだろうか。それとも、辞書を引くことは、「自分は何も知らないことを知る」という境地に通じて、虚心坦懐であることの楽しさをもたらしてくれるのだろうか。そういえば分厚い法規集を引く楽しさも、辞書に勝るとも劣らないところがある。法規集もそこにあるのは一種の絶対者であり、我々にできるのは絶対者の言葉を解釈することだけだからだろうか。
若い頃は、世界は政治や経済や文化や芸術の大舞台にあると思い込んでいた。いうなれば、大状況の世界、大文字の世界が本当の世界で、私たちの手元、足元にあるような卑小な小状況、いわば小文字の世界は取るに足りない世界だと思い違いをしていた。
年を取って、わかったのは、私たちの手元、足元にある小文字の世界が本当の世界で、政治や経済や文化や芸術といった大文字の世界は、本当の世界の上澄みに過ぎないということである。
世界のことがわかったのは、年を取ったことの効用である。若い頃は夭折することを願ったが、夭折などしていたら、世界の本当のことは知り得なかった。
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
法苑WEB 全16記事
- 契約に関わる文豪書簡(1)―法律の条文のような諭吉・らいてふの書簡―(法苑WEB連載第16回)執筆者:中川越
- 子どもの意見表明の支援は難しい(法苑WEB連載第15回)執筆者:角南和子
- 「始皇帝モノ」は面白い。連載コラムその3 ─応用編⑴『大秦帝国』シリーズ全4作の紹介─(法苑WEB連載第14回)執筆者:坂和章平
- コンダクト・リスクの考え方~他律から自律への転換点~(法苑WEB連載第13回)執筆者:吉森大輔
- 消防法の遡及制度(法苑WEB連載第12回)執筆者:鈴木和男
- 「始皇帝モノ」は面白い。連載コラムその2 ─入門編は『キングダム~戦国の七雄』から─(法苑WEB連載第11回)執筆者:坂和章平
- 株分けもの(法苑WEB連載第10回)執筆者:村上晴彦
- 「始皇帝モノ」は面白い。連載コラムその1 ─『キングダム』シリーズ全4作を楽しもう!─(法苑WEB連載第9回)執筆者:坂和章平
- 小文字の世界(法苑WEB連載第8回)執筆者:田中義幸
- 20年ぶりに「学問のすすめ」を再読して思うこと(法苑WEB連載第7回)執筆者:杉山直
- 今年の賃上げで、実質賃金マイナスを脱却できるか(令和6年の春季労使交渉を振り返る)(法苑WEB連載第6回)執筆者:佐藤純
- ESG法務(法苑WEB連載第5回)執筆者:枝吉経
- これからの交通事故訴訟(法苑WEB連載第4回)執筆者:大島眞一
- 第三の沈黙(法苑WEB連載第3回)執筆者:相場中行
- 憧れのハカランダ(法苑WEB連載第2回)執筆者:佐藤孝史
- 家庭裁判所とデジタル化(法苑WEB連載第1回)執筆者:永井尚子
執筆者

田中 義幸たなか よしゆき
公認会計士・税理士(田中義幸公認会計士事務所)
略歴・経歴
監査法人(現、あずさ監査法人)、法律事務所(現、西村あさひ法律事務所)勤務を経て、平成元年 田中義幸公認会計士・税理士事務所開設
著書
『非営利法人における消費税処理の手引』
『新・事業承継税制まるごとひとつかみ』 他
執筆者の記事
執筆者の書籍
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.