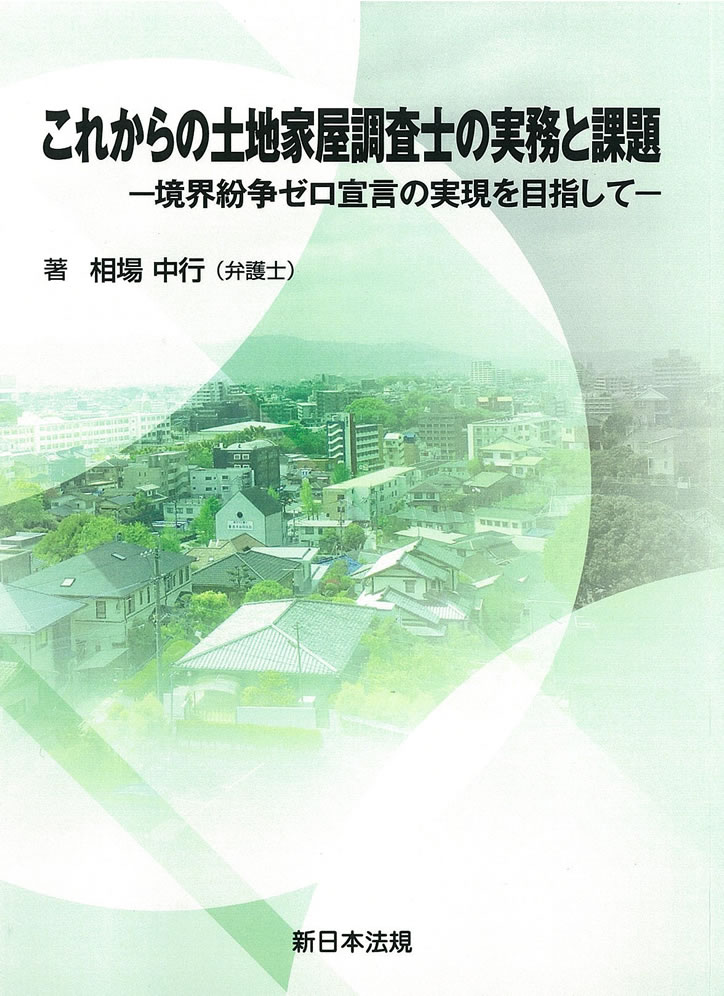一般2024年01月10日 第三の沈黙(法苑WEB連載第3回)執筆者:相場中行 法苑WEB

1 神の沈黙
若いころに読んだ本の中で、その隠されたコードが読み解けなくても、妙に心に残るものがある。例えば、遠藤周作の「沈黙」である。この作品は、踏み絵のイエスがロドリーゴ神父に、「踏め!」と語りかけるイメージが強烈である。こういった、作品のテキストと共にイメージを通じて、読者の意識の深層に直接訴えかける作品を名著というのかも知れない。「沈黙」については、後に、ドナルド・キーン氏が、単に日本の隠れキリシタンの問題に止まらず、すべてのキリスト者に通じる命題を提示していると高く評価していることを知った。
沈黙という小説の舞台は鎖国されて切支丹禁令下の江戸時代であり、その前提となっているのはイエズス会による布教である。
こういう布教の原動力となっているのは一種の浄化思想で、この当時は、主イエスの恩寵を世界に遍く行き渡らせることこそ聖職者の使命であり、王権を神授された王侯は、神から与えられた臣民を異教徒から守り、場合によっては異教徒を排除することこそ神聖な使命である、という思想である。だからこそロドリーゴ神父も、迫害を知りながら鎖国下の日本に密航して布教を試みたのである。これに対して、沈黙の主題とするところは、弱者と寄り添う同伴者イエス、ということらしいが、発表当初はカソリック教会から猛烈な反発があった。しかし、「沈黙」は、グレアム・グリーンにも評価され(「遠藤は20世紀のキリスト教文学で最も重要な作家である。」と言っている。)、2016年には、巨匠マーチン・スコセッシの手によって映画化されている。おそらく、こういった高評価は、日本という全く異質な文化的環境において変質したキリスト教に、最も信仰の核心をついている部分があるからだと思われる。
2 十字軍と浄化思想
こういう浄化思想というのは源流をたどると十字軍に行き着く。
この十字軍という存在は、例えば「草刈り十字軍」(吉田一夫監督、加藤剛主演の同名の映画がある。)という言葉が示すように、西欧世界からは、なにか神聖な責務の遂行のように肯定的な文脈で使われている。しかし、イスラム世界から見ると、十字軍はとんでもない蛮行以外の何物でもない。10世紀まではイスラムと西欧は貿易相手で、良きパートナーであった。イスラム側もエルサレムの「聖墳墓教会」へのキリスト教徒の巡礼の自由を認めていた。ところが、1096年に至り、突如武装したキリスト教徒が大挙して攻め寄せてきて、不浄なムスリムを皆殺しにして聖地を「浄化」せよ、というのである。その一因としては、キリストの昇天後1000年が経過して、いつ最後の審判が下されるかも知れないという終末思想があったらしい(アミン・マルーフ「イスラムが見た十字軍」リプロポート社参照。)。そして、それが十字軍への従軍による免罪、さらには金銭による免罪符(贖宥状)の交付(実は販売?)につながっていく。
我々は、十字軍というと、世界史で第1回から第8回(9回目をカウントするかどうかはともかく。)まであったと習うが、実は、教皇が呼びかけた「十字軍」は多数に及ぶ。例えば、ドイツ騎士団(チュートン騎士団)は、聖地の防衛を目的として11世紀末に創設されたが、主たる活動はバルト三国、ポーランド、ハンガリーなどの異教徒との武力抗争であり、多数回にわたって「十字軍」が布告され、司教も軍事力の一旦を担っていた。
他方、こういった免罪符販売による教会の堕落を「ローマ教皇は反キリストである。」として痛烈に批判したのが、マルティン・ルターであり、「95箇条の論題」が宗教改革の発端であることは周知の通りである。本稿において、宗教改革について意見を述べるつもりは全くないが、西洋法制史の大家である山内進氏によると、こういった「十字軍の思想」は、むしろ、プロテスタントに色濃く受け継がれたらしい(山内進「十字軍の思想」ちくま新書)。マルティン・ルターは実は反ユダヤ主義者だったし、ジャン・カルヴァンの神権政治などは、カソリックも含めた他の信仰の存在を許さないものである。
プロテスタントの中でも最も原理主義的なグループがピューリタンである。この言葉は、「清教徒」と和訳されているが、正に自らプロテスタンティズムに従った清廉な生活を実践し、さらには清潔な社会を目指すセクトであって、山内前掲の指摘するとおり、十字軍の浄化の思想を受け継ぐものと言わざるを得ない。実際に、イングランドで神権政治というか、政教一致を実現したのがチャールズ一世を処刑したオリバー・クロムウェルである。悪名高いアイルランド征服などは、教皇による呼びかけはないものの(プロテスタントだから当たり前だが・・・)、その実態においては十字軍と変わるところはない。ただ、他方で清教徒革命による市民軍の成立がヨーマンリー以下の社会層の台頭をもたらし、結果的に100年後の産業革命の一因となったとの見解もあり(今井宏「クロムウェルとピューリタン革命」清水書院)、ウェーバーの「プロ倫」に馴染んできた身からすると、ちょっと納得する部分もある。今井前掲によれば、「鉄騎兵」を率いたクロムウェルは度々神のご加護により勝利を得たと述べており、こういった信仰の在り方は、遠藤周作の提示する弱者に寄り添う神としてのイエスとは一見して全く異なるように思われる。
こういった広義の「十字軍」による暴力から逃れる方法は一つだけある。それはキリスト教(ないしピューリタン)に改宗することである。つまり、改宗した瞬間異教徒は浄化されるのである。
3 ピューリタンの国アメリカ
そのピューリタンが建国したのがアメリカ合衆国である。
後にピルグリム・ファーザーズと呼ばれる人々を乗せたメイフラワー号が、ジェームス一世による弾圧を逃れてイングランドのサウザンプトンを出港したのが1620年。イングランドでは、その後、清教徒革命が起きて、ジェームス一世は1649年に処刑されている。他方、船中で調印された「メイフラワー誓約」には、冒頭で「神の影響とキリスト教信仰の振興・・・のために・・・誓約をかわす」と記載されている。さらに、いわゆるニュー・ヴァージニア植民地のうち、セイラム市に植民した一団は、もっとあからさまに「新エルサレム」の建設を目的としていた。だから、17世紀前半の時点では、イングランドにおいても、アメリカ(植民地)においても、政教一致の統治体制が指向されていて、1660年にはマサチューセッツ植民地で(オートミールで有名な)クエーカー教徒が絞首刑にされているし、1692年にはセイラムで魔女狩りが行われて、なんと、19人が処刑されている。だから、1620年にイングランドから逃亡したピルグリム・ファーザーズも、当時21歳だったクロムウェルも、目指すところは同じ政体だったということになりそうである。
こんな息苦しい社会を描いたものとして、ホーソンの「緋文字」が有名であるが、ホーソン自身がセイラムの出身であることを考えると、魔女裁判が行われた当時のセイラムの社会を描いたのかもしれない。「ヒトラーのモデルはアメリカだった」(ジェームス・ウィットマン著、みすず書房)という書籍があるが、緋文字に描かれた「A」のマークを付けた女性を社会全体で敵視する有様は、つい、ユダヤ人に六芒星を付けさせて迫害したイメージと重なってしまう。
その後、イングランドでは王政復古に伴って宗教的寛容が実現し、アメリカにおいても、クエーカー教徒やアーミッシュの入植に伴って、独立前から信教の自由を認めるようになった(例えば、1776年のトマス・ペインの「コモンセンス」)。そして、最終的にヴァージニア権利章典において、信仰の自由が高らかに宣言された、ということになっている。
そう考えてみると、ワスプ(WASP)という条件を満たさないJ・F・ケネディが大統領となったことが驚きをもって迎えられたこともなんとなく首肯できるし、アメリカ大統領の就任式では、未だに聖書に手をあてて宣誓することについて宗教差別だといったクレームがついたという話をとんと聞かない。
山内前掲は、アメリカ建国以来の歴史の中に十字軍の思想=浄化思想の影響を指摘して、マカッシー上院議員らによる「赤狩り」も、さらにはイスラエルの独立戦争もその延長線上にあると指摘する。しかし、あくまで個人的な見解であるが、アメリカにおける政教分離以降、「十字軍の思想」は大きく変質しているように思えてならない。すなわち、近代以降のアメリカにとっては、「民主主義」が原理的絶対性を獲得して一種の「神」(又は「正典」?)となったのではないか?もちろん、政治的意思決定システムとしても責任原理としても、民主制は極めて優れた制度である。しかし、民主制には、単に選挙制度による主権者の意思決定システムだけでなく、情報の偏在を除去し、思想の自由を保障するなど様々な制度的基盤が不可欠である。
そういう文脈では、民主主義は勝ち取るものであり、国民の不断の努力によって維持されなければならない制度である。ところが、アメリカにおける「民主主義」はそれ以上の価値を持っているように見える。第二次世界大戦にアメリカが参戦したのは、全体主義・独裁主義に対する民主主義の戦いであると、通常、認識されている。ヨーロッパ戦線で連合国の総司令官の地位にあったのがドワイト・アイゼンハワーであり、アイゼンハワーが大統領選立候補前にヨーロッパ戦線の手記を出版した。その題名は、「ヨーロッパ十字軍」(朝日新聞社)である。そして、アイゼンハワーは大統領に当選したのちに、「デモクラシーは深く感じられた宗教の表現である。」と語っている。実際、戦後一定の期間、民主主義に「改宗」した国は、世界秩序の維持者であるアメリカの恩寵(パクス・アメリカーナ)を受けることができた。
他方、今や、アメリカを典型とする民主制にも限界があって、その新しいかたちが模索されていることも事実である。特に、ベトナム戦争以降のアメリカにおいては、アイゼンハワー的価値観に基づいて「世界の警察官」として民主主義を「輸出」することの限界が明らかになった。独裁体制を転覆して民主的体制を設立するために行使される暴力は違法なものではない、との思想は、山内進氏が指摘するように、キリスト教と十字軍の関係とパラレルであるように思われてならない。デモクラシーの基盤の一つである思想の自由が信教の自由に根源を有することを考えると、上述のアイゼンハワーの表明には違和感を覚えざるを得ない。
4 憲法制定権力の不在
我が国も、昭和20年以降、突如民主的な体制となり、間接民主制を堅持してもう80年近くなる。そして、法律学の世界では、そういった法体系の最上位規範が憲法であり、当該最高規範の源泉となっているのが「憲法制定権力」であると言われている(やっと法律関連エッセイらしくなってきた。)。
ところが、憲法の基盤となる憲法制定権力が果たして我が国に存在するのか、個人的には疑問を感じている。現行の日本国憲法の制定は、形式的には欽定憲法である明治憲法の改正によっている。この点については、宮沢俊義教授の「八月革命説」が有名である。すなわち、明治憲法の日本国憲法への「改正」によって、主権の変更があるのだから日本国憲法への改正の時点で革命があったというのである。調べてみると、昭和60年、中曽根内閣において、憲法改正が志向された際の衆議院での答弁では「日本国憲法は・・・連合国最高司令官の権限においてその有効性が保障されているものではない。・・・ 日本国憲法の前文における『日本国民は…この憲法を確定する。』との文言は、日本国憲法が正当に選挙された国民の代表者によつて構成されていた衆議院の議決を経たものであることを表したものと解される。」とされている。
しかし、そもそも憲法制定権力という概念は、立法機関が自らの権限を定める根拠となる規範(憲法)を制定することは自己矛盾であり法の支配にも反するとの批判に対して、立法機関(日本国憲法においては明治憲法下の衆議院)に正当性を付与する上位概念として想定されている概念である。そして、日本国憲法は、周知のとおり、GHQで起草した原案を帝國議会で審議したのちに、昭和21年10月29日に、昭和天皇の裁可によって成立している。実質的に見れば、同年4月に初めての普通選挙が実施され、新たに国民を代表する国会議員が選任されており、これらの議員が憲法制定権力である国民の意思を体現していた、ということであろう。しかし、(明治憲法下の)国会で審議され、議決されたから日本国憲法は国民を憲法制定権力として定められたものである、という答弁は、論理的には明らかに間違っている。前述のとおり、憲法制定権力という概念は、当該立法機関に正当性を付与するための道具概念だからである。宮沢俊義教授の八月革命説は、実践的意義としては、戦時中の宮沢教授の「沈黙」の(延長線上での)裏返しなのではないかという気がしてならない。
5 弱き者の沈黙
ここで、遠藤周作の「沈黙」に戻りたい。さきに、沈黙が発表当初(1966年)カソリック教会からの反発を受けたことを指摘したが、あるカソリック神父によれば、信仰者は日々踏み絵に直面しているのであり、「キリストの国とキリストの愛」を選ぶのか、自らの「傲慢と利益と邪欲」のいずれを選ぶか試されている。そして、弱い人間として選びやすい方を選んでもよいなら、キリストは人間の弱さ、卑劣さの使徒となり、裏切者となってしまうのであって、キリストが「人類の気高いものの旗印」となったのは、キリストが生命をかけて正義と愛と真理を守り通したからだ、というのである。キリスト教の教義としては正論というほかない。イエスの「踏め!」という心の声を聴いて、イエスを踏んだロドリーゴ神父は、本来のキリスト教徒としては不行状であり、イエスの否定につながるということであろう。ロドリーゴ神父の聞いたイエスの声は、自分の内なる神の声にすぎないからである。ロドリーゴ神父の祈りに対する神の沈黙を、神の与えた試練と考えるのか、沈黙と捉えるのかも、彼の内面における相克でしかない。
これに対して、遠藤周作は、「・・・こうして弱者たちは政治家からも歴史家からも黙殺された。沈黙の灰のなかに埋められた。だが弱者たちもまた我々と同じ人間なのだ。・・・その悲しみや苦しみにたいして小説家である私は無関心ではいられなかった。彼等が転んだあとも、ひたすら歪んだ指をあわせ、言葉にならぬ祈りを唱えたとすれば、私の頬にも泪が流れるのである。」と応答している(遠藤周作「切支丹の里」中公文庫)。
遠藤周作は、キリスト教が徹底的に弾圧された江戸時代の我が国において、信仰が棄教者の内面において変容し、弱者と共にあるイエスが、内心の信仰の核を形成しつつ存続していたことを発見した。そこに描かれているのは、神イエスの沈黙とともに棄教者という弱き者の沈黙である。この視座が読者の心を打ち、声なき者の共感を呼ぶ。ドナルド・キーン氏も、マーチン・スコセッシも、実は「弱き者」として、その内面において、イエスとの対話を通じて自我との葛藤に直面し、日々、悩んでいたのかも知れない。ときとして、作品は作家の意図するところを超えた普遍性を持つのである。
こういった変容と弱き者の沈黙は、我が国の民主主義についても言えないだろうか、というのが、実は本稿の主題である。
6 第三の沈黙
ところで、戦後輸入された我が国の民主主義には責任原理としての側面が希薄である。弱き者に寄り添うイエスが、本来の人類の救済のために犠牲となったイエスとは異なるように、イギリスやアメリカにおいて実現された民主主義と、日本に戦後導入された民主主義は質的に異なっているように思えてならない。
近くて遠い隣国、韓国において、国民の猛烈なデモによって朴政権が辞任に追い込まれたことは記憶に新しい。しかし、我が国においては、どんなに内閣支持率が低迷しようと、実力(暴力ではない。)の行使によって政権交代を実現しようという動きは、少なくともここ60年は全くない。議会制民主主義の母国、イギリスでは、マグナ・カルタ、権利の請願、権利章典などが国王との実力的対峙の中で獲得されてきたことを考えると、韓国の在り方の方がむしろ本来の民主主義の在り方に近いようにも思えてしまう。
考えてみると、我が国においては、海外から輸入された文化が独自の変容を遂げて根付いてゆくという例は枚挙にいとまがない(疑う者はカツカレーを見よ!)。民主主義についても、我が国においては、本来の在り方からすれば変容しつつ受容されているのではないか。そもそも、我が国には、アメリカやイギリスのような二大政党制も根付いていないし、政権交代そのものが稀有な出来事である。外圧を受けても大規模なデモが起きることもないし、外圧も改革も唯々諾々と沈黙のうちに受け入れる。国民が積極的に意思表示し「主権」を行使することもない。選挙の度にマスコミは「主権者の意思表示」と言い立てるが、我が国の総選挙の結果がどのようであろうと、アメリカ大統領選挙のようにドラスティックな変革が起きたことはいまだかつていない。我が国の「民主主義」の在り方は、少なくとも、GHQが憲法草案を起草した時点で予定していた民主主義とは大分様相が異なっているように思われる。こういった我が国固有の民主主義の在り方は、遠藤周作の沈黙に対するカトリック教会の批判のように、一種の「異端」なのかも知れない。
しかし、森本あんり氏の「異端の時代」(岩波新書)によれば、「異端」と「正統」は、教義によって区別されるものでもないし、正典によって定義されるものでもない。名もなき人々の間に普遍している「信仰」によってのみ正統と異端が区別されるのである。したがって、歴史的に見れば、信仰の在り方(の変容)によっては、容易に異端が正統となりうるのである(このあたりの宗教社会学上の議論は、どこか「憲法の変遷」の議論に似ている。)。だからこそ、遠藤周作の「弱者に寄り添うイエス」の発見は、小説家の意図を超えて数多くの人々に共感と感銘を与えたのであり、そのことは、信仰に命を捧げることのできない弱きキリスト者が、日々絶対的規範と自我の対立に悩みつつも、帰依していることの証左であるように思えてならない。
そう考えると、我が国の戦後民主主義は、遠藤周作の提示した隠れキリシタンの声なき民の信仰に本質的な部分で共通するものがあるのではないか?隠れキリシタンの「沈黙」を第一の沈黙とすれば、明治維新を経て、戦後突如顕現した日本の民主主義は、「第三の沈黙」と言えるのではないだろうか?我が国の民主主義は、その本質において変容しつつも、確固として維持し、核心において受容され、声なき祈りを黙示しているのではないだろうか。わが身を振り返ると、私も弱い人間であり、選びやすい方を選んで日々を送る「卑劣さの使徒」であると痛感せざるをえない。しかし、隠れキリシタンが「歪んだ指をあわせ、言葉にならぬ祈りを唱え」るように、声なき民の一員として、現在の我が国の民主主義を少しでも支えたいと願うのである。
人気記事
人気商品
法苑WEB 全16記事
- 契約に関わる文豪書簡(1)―法律の条文のような諭吉・らいてふの書簡―(法苑WEB連載第16回)執筆者:中川越
- 子どもの意見表明の支援は難しい(法苑WEB連載第15回)執筆者:角南和子
- 「始皇帝モノ」は面白い。連載コラムその3 ─応用編⑴『大秦帝国』シリーズ全4作の紹介─(法苑WEB連載第14回)執筆者:坂和章平
- コンダクト・リスクの考え方~他律から自律への転換点~(法苑WEB連載第13回)執筆者:吉森大輔
- 消防法の遡及制度(法苑WEB連載第12回)執筆者:鈴木和男
- 「始皇帝モノ」は面白い。連載コラムその2 ─入門編は『キングダム~戦国の七雄』から─(法苑WEB連載第11回)執筆者:坂和章平
- 株分けもの(法苑WEB連載第10回)執筆者:村上晴彦
- 「始皇帝モノ」は面白い。連載コラムその1 ─『キングダム』シリーズ全4作を楽しもう!─(法苑WEB連載第9回)執筆者:坂和章平
- 小文字の世界(法苑WEB連載第8回)執筆者:田中義幸
- 20年ぶりに「学問のすすめ」を再読して思うこと(法苑WEB連載第7回)執筆者:杉山直
- 今年の賃上げで、実質賃金マイナスを脱却できるか(令和6年の春季労使交渉を振り返る)(法苑WEB連載第6回)執筆者:佐藤純
- ESG法務(法苑WEB連載第5回)執筆者:枝吉経
- これからの交通事故訴訟(法苑WEB連載第4回)執筆者:大島眞一
- 第三の沈黙(法苑WEB連載第3回)執筆者:相場中行
- 憧れのハカランダ(法苑WEB連載第2回)執筆者:佐藤孝史
- 家庭裁判所とデジタル化(法苑WEB連載第1回)執筆者:永井尚子
執筆者

相場 中行
弁護士(弁護士法人 アクトワン法律事務所)
略歴・経歴
・東北大学法学部卒,弁護士(第一東京弁護士会42期),弁護士法人アクトワン法律事務所(代表社員弁護士)
松嶋総合法律事務所にて都市銀行・ノンバンク・ リース会社・クレジット会社・カード会社等を担当し,金融法・担保法・不動産取引を主として執務。司法研修所民事弁護所付,法務研究財団研修委員,司法書士簡裁代理関係業務認定考査委員等を歴任。
・上場企業の監査役,独立委員会委員, ファンドの投資委員会委員などの経験を通じて,企業法務を得意分野とする。
・公益社団法人全日本不動産協会の全日住宅ローンアドバイザーの有識者委員,公益財団法人日弁連法務研究財団研修委員, 日本土地家屋調査士会連合会の法務委員などを務めている。
弁護士法人 アクトワン法律事務所
http://act1-legal.jp/greeting.html
<主要著書等>
『区分所有とマンションの法律相談』 (共著,学陽書房, 1987), 『借地借家の法律』 (共著, ビジネス教育出版社。 1994), 『不動産紛争・管理の法律相談』 (共著,青林耆院, 1994), 『問答式マンションの法律実務』 (共著,新日本法規出版1991), 『簡裁民事実務NAVI第2巻・第3巻(紛争類型別要件事実の基本1 ・2)j (共著,第一法規2011), 『境界紛争事件処理マニユアル』 (共編新日本法規出版, 2015)他多数
執筆者の記事
執筆者の書籍
関連カテゴリから探す
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.