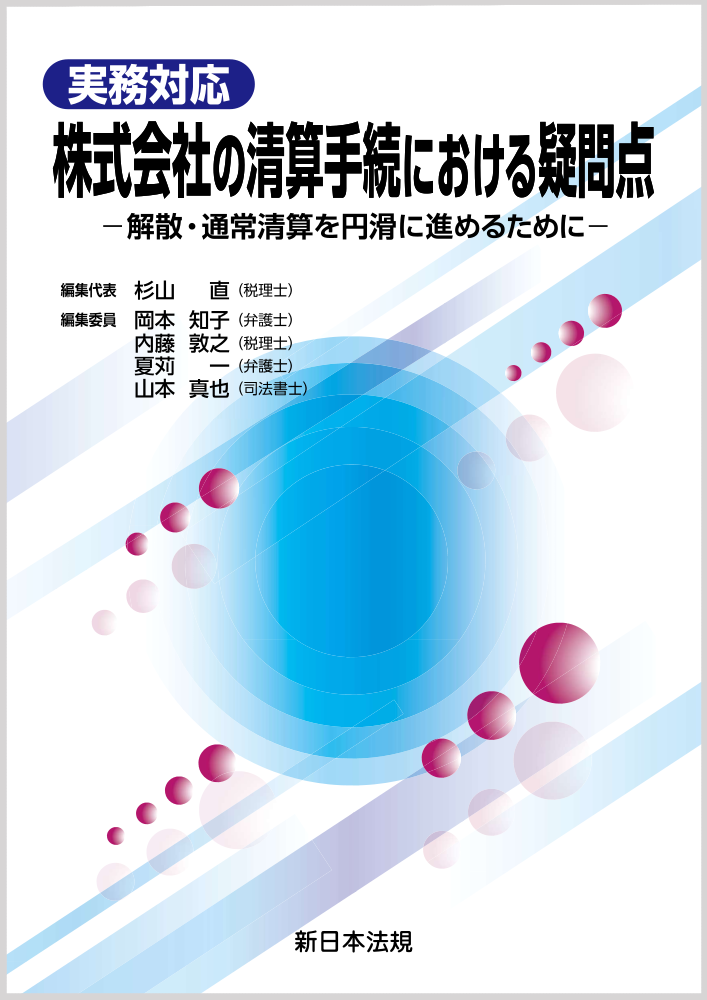一般2021年10月06日 スポーツ・コンプライアンス研修の実践 執筆者:多賀啓

もっとも、「事後対応」は、制度を構築していた、不祥事や有事に適切な対処がなされた、といったように、到達点が目に見えやすい部分であるように思います(その反面、マイナスの評価も受けやすい部分ではあるのですが)。他方、「事前予防」は、先に述べたとおりステークホルダーに対する教育・啓発活動ですから、その効果や到達点がなかなか目に見えにくいところもあり、スポーツ競技団体の運営において、これをどのように実践していくのが良いか悩ましい部分です。実際に、どのように研修活動を進めていくべきか、という相談を受ける機会も多くあります。
スポーツ競技団体にはたくさんのステークホルダーがいます。役員や職員等の組織運営を担う人たち、選手や指導者のようにその競技の現場で活躍する人たち、審判員等競技自体を運営する人たち。スポーツにおいて果たす役割が異なるステークホルダーたちにどのような研修を実施していくかに関しては、スポーツ団体ガバナンスコードにおいても、スポーツ・コンプライアンスに関する他のガイドライン等においても2、大きく「組織マネジメント」に関する研修(役員や職員等の組織運営を担う人たち向けの研修)と、「フォールドマネジメント」に関する研修(選手や指導者、審判員等その競技の現場でスポーツに関わる人たち)の2つを大別して研修を実施するという方向性が示されています。この点は抑えておくべき前提の一つでしょう。
これまでは、集合型の研修の実施が一般的でしたが、コロナ禍の影響もあり、Web会議システムの利用が広く浸透しつつあります。その他、eラーニング、オンデマンド型のコンテンツの配信、ハンドブックの作成といった方法もありますから、研修計画を策定する上で盛り込んでいくことも考えられます(ただし、先立つものとの兼ね合いもあります)。
冒頭にも述べたように、スポーツ・コンプライアンス教育・啓発活動自体、自ずから効果が目に見えにくいものです。到達目標や計画を立てる作業も骨が折れるものです。しかし、コンプライアンス意識の浸透・醸成を目指す上では、この骨の折れる作業が重要であると考えています。
1 スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>原則5
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop10/list/detail/1420887.htm
スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>原則3
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop10/list/detail/1420888.htm 参照
2 例えば、平成29年度スポーツ庁委託事業 スポーツ界におけるコンプライアンス強化ガイドライン
https://www.jsaa.jp/ws/complianceindex.html
(2021年9月執筆)
人気記事
人気商品
執筆者

多賀 啓たが ひろむ
弁護士(パークス法律事務所)
略歴・経歴
パークス法律事務所・弁護士
公益財団法人日本スポーツ仲裁機構 スポーツ仲裁人・調停人等候補者
第一東京弁護士会総合法律研究所 スポーツ法研究部会 部会長
学歴
2010年 首都大学東京都市教養学部法学系(現 東京都立大学法学部)卒業
2012年 首都大学東京法科大学院(現 東京都立大学法科大学院)修了
取扱分野
スポーツ法務、企業・団体法務、訴訟・仲裁その他紛争解決
著書
『スポーツの法律相談』(共著)青林書院(2017年3月)
『スポーツ事故対策マニュアル』(共著)体育施設出版(2017年7月)
『Q&Aでわかる アンチ・ドーピングの基本』(編著)同文館出版(2018年11月)
『法務担当者のための契約実務ハンドブック』(共著)商事法務(2019年3月)
『スポーツ事故の法的責任と予防 ~競技者間事故の判例分析と補償の在り方~』(編著)道和書院(2022年3月)
『これで防げる!学校体育・スポーツ事故 科学的視点で考える実践へのヒント』(編著)中央法規出版(2023年9月)
『実務対応 株式会社の清算手続における疑問点-解散・通常清算を円滑に進めるために』(共著)新日本法規出版(2024年1月)
執筆者の記事
執筆者の書籍
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -